チーズ【cheese】
チーズ
|
チーズには、ナチュラルチーズとプロセスチーズがあります。ナチュラルチーズは、乳等省令では、一 「乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)若しくはクリームを乳酸菌で醗酵させ、又は乳、バターミルク若しくはクリームに酵素を加えてできた凝乳から乳清を除去し、固形状にしたもの又はこれらを熟成したもの」、二 「前号に掲げるもののほか、乳、バターミルク又はクリームを原料として、凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの」とあります。またプロセスチーズは、「ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの」です。 現在、世界中には1,000種類を超えるナチュラルチーズがあり、それぞれの形や味のちがいはもちろん、原材料ひとつをとっても、牛に限らず羊や山羊の乳などさまざまです。個性豊かなナチュラルチーズは、硬さによって大きく4つのタイプに分類することができ、さらに「熟成させるもの」「熟成させないもの」といった細分化が可能です。 |
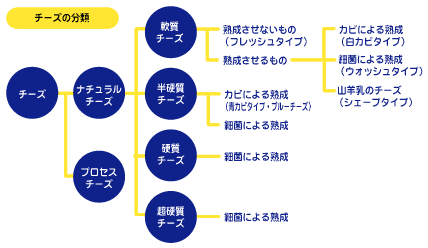 |
チーズ
チーズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/14 22:48 UTC 版)

| 食事 |
|---|
 |
| 総合 |
| 食品 料理 摂食 |
| 習慣食 |
| 朝食 ブランチ イレブンジズ 昼食 アフタヌーンティー 夕食 夜食 |
| 形態 |
| 間食 中食 外食 食べ放題 |
| 要素 |
| 主食 副食 主菜 飲料 デザート オードブル (アミューズブーシュ) アントレ アントルメ |
| 関連項目 |
| 宴会 会食 テーブルマナー 食育 各国の料理 料理の概要 |
| |
| 100 gあたりの栄養価 | |
|---|---|
| エネルギー | 1,553 kJ (371 kcal) |
|
3.7 g
|
|
| 糖分 | 2.26 g |
| 食物繊維 | 0 g |
|
31.79 g
|
|
| 飽和脂肪酸 | 18.057 g |
| 一価不飽和脂肪酸 | 8.236 g |
| 多価不飽和脂肪酸 | 1.286 g |
|
18.13 g
|
|
| トリプトファン | 0.232 g |
| トレオニン | 0.772 g |
| イソロイシン | 0.938 g |
| ロイシン | 1.716 g |
| リシン | 1.516 g |
| メチオニン | 0.475 g |
| シスチン | 0.11 g |
| フェニルアラニン | 0.939 g |
| チロシン | 0.916 g |
| バリン | 1.187 g |
| アルギニン | 0.518 g |
| ヒスチジン | 0.546 g |
| アラニン | 0.613 g |
| アスパラギン酸 | 1.551 g |
| グルタミン酸 | 4.073 g |
| グリシン | 0.359 g |
| プロリン | 1.788 g |
| セリン | 1.093 g |
| ビタミン | |
| ビタミンA相当量 |
(31%)
250 μg
(1%)
80 μg
0 μg
|
| チアミン (B1) |
(1%)
0.015 mg |
| リボフラビン (B2) |
(20%)
0.234 mg |
| ナイアシン (B3) |
(1%)
0.076 mg |
|
(8%)
0.403 mg |
|
| ビタミンB6 |
(4%)
0.054 mg |
| 葉酸 (B9) |
(2%)
8 μg |
| ビタミンB12 |
(63%)
1.5 μg |
| コリン |
(7%)
36.2 mg |
| ビタミンC |
(0%)
0 mg |
| ビタミンD |
(4%)
23 IU |
| ビタミンE |
(5%)
0.8 mg |
| ビタミンK |
(2%)
2.6 μg |
| ミネラル | |
| カルシウム |
(105%)
1045 mg |
| 鉄分 |
(5%)
0.63 mg |
| マグネシウム |
(7%)
26 mg |
| マンガン |
(2%)
0.041 mg |
| セレン |
(29%)
20.2 μg |
| リン |
(92%)
641 mg |
| カリウム |
(3%)
132 mg |
| ナトリウム (塩分の可能性あり) |
(111%)
1671 mg |
| 亜鉛 |
(26%)
2.49 mg |
| 他の成分 | |
| 水分 | 39.61 g |
| コレステロール | 100 mg |
|
成分名「塩分」を「ナトリウム」に修正したことに伴い、各記事のナトリウム量を確認中ですが、当記事のナトリウム量は未確認です。(詳細) |
|
|
|
| %はアメリカ合衆国における 成人栄養摂取目標 (RDI) の割合。 出典: USDA栄養データベース |
|
チーズ(英語: cheese)とは、乳蛋白質であるカゼインの凝固によって、さまざまな風味、食感、形状で製造される乳製品である。 牛・水牛・羊・山羊・ヤクなど鯨偶蹄目の反芻をする家畜から得られる乳からの蛋白質と脂質で構成されている。通常、乳酸発酵で酸乳化し、酵素(レンネットまたは同様の活性を持つ細菌性酵素のいずれか)が添加され、できた凝乳(カード)から液体成分(ホエー)を分離してさらにプレスし脱水して完成したチーズとなる[1]。酸乳化後固形分を濾しとる方法や、加熱(低温殺菌の温度まで)しクエン酸や食酢や柑橘果汁を添加し出来た固形分を濾しとる方法もある。
歴史
チーズは伝統的に乳脂肪を分離したバターと並んで、家畜の乳からつくる保存食として牧畜文化圏で重要な位置を占めてきた。日本語や中国語での漢語表記は、北魏時代に編纂された『斉民要術』に記されているモンゴル高原型の乳製品加工の記述を出典とする乾酪(かんらく)である。
チーズがどのようにして発見されたのかは正確には定かではないが、「アラブの商人が羊の胃袋を干して作った水筒に山羊のミルクを入れて砂漠を旅していた途中に、砂漠の疲れとのどの渇きを癒そうと水筒を開けたところ、中からミルクではなく澄んだ水(乳清)と柔らかい白い塊(カード)がでてきた」というのが最初のチーズの発見であるという説が有力だとされていた[2][3]。
ところが、2012年になって紀元前5000年頃の世界最古のチーズ製造の痕跡(粘土製のチーズを濾すためのザル)がポーランドのクヤヴィで発見された[4][5][6]。このスウィデリアン文化の道具はメソポタミア文明よりも古く、チーズ製造が中東ではなくポーランドあたりの中央ヨーロッパで始まった可能性を示唆している。この人類最古のチーズの原料はヤギの乳であり、また現在のポーランドでも、多くの種類の山羊乳チーズ(いわゆるシェーブルチーズ)が存在する。
いずれにせよ、チーズは近東からヨーロッパにかけての地域に広まり、メソポタミア文明を築いたシュメール人をはじめ、古代ギリシアやローマ帝国においても広く食用とされた。ホメロスの『オデッセイア』にはフェタチーズへの言及があり、プリニウスの『博物誌』やアリストテレスの著作にもチーズについての記述がある。ローマ帝国崩壊後もヨーロッパでのチーズ利用が衰退することはなく、逆に各地で特徴あるチーズが多数生産されるようになっていった。ヨーロッパでは特に、各地の荘園や修道院において特色あるチーズが生産されることが多かった。中世ヨーロッパにおいては、チーズは脂肪分の多いものが珍重されており、そのため15世紀頃にブルターニュやオランダ、フランドル、イギリスなどでバターの生産が盛んとなると、チーズの質では山岳地帯産のチーズのほうが名声を得るようになった[7]。
ただし、チーズの利用はヨーロッパや中近東においては非常に盛んであったが、インドでは古代インドの讃歌集『リグ・ヴェーダ』にチーズを勧める歌があり、パニールなどのフレッシュチーズは盛んに使用製造されたもののレンネット使用の熟成チーズはついに登場しなかった[8]。日本や中国など東アジア地域においては鮮卑系の支配者など北アジアの遊牧民系の勢力によって度々導入されたものの安定して定着することはなかった。こうしたチーズ利用のない地域にチーズが普及するのは、ヨーロッパ勢力が各地に勢力を広げていく19世紀以降のこととなる。
19世紀半ばに入ると、工業的にナチュラルチーズが大量生産できるようになり、ヨーロッパやアメリカ大陸にチーズ工場が建設されるようになった。1874年にはデンマークでレンネットが工業的に量産できるようになり[9]、1904年にはアメリカでプロセスチーズが開発され量産されるようになった[10]。
日本においては東アジア全般の例にもれず、チーズ利用はほとんど存在しなかった。飛鳥時代の645年頃から乳牛の伝来と飼育が始まり、チーズの一種と考えられる
製法
チーズの主な原料は乳の中にあるタンパク質の一種カゼインである。カゼインには分子中に親水性の部分と疎水性の部分があり、これがミセル状となって液体中に浮遊するために乳は白く見える。この乳に乳酸菌を加えてpHを酸性に変え、さらにレンネット(凝乳酵素)を投入してカゼイン分子の親水性の部分を加水分解により切り離すと、カゼイン分子は繊維状に連鎖して集合して沈殿し始める。これを凝乳と言う[14]。凝乳には上記の乳酸発酵とタンパク質分解酵素によるもののほか、酸性化を食酢やレモン汁などといった酸の直接添加、沈殿生成を加熱による変性によっても同じことができ、この乳酸発酵、酸の添加、タンパク質分解酵素添加、加熱の組み合わせが主要な凝乳生成手段となっている。
凝乳したカゼインは繊維状の集合体が熱運動によって収縮することで水及び水溶性成分と分離して沈殿し、乳はホエイ(乳清)という液体部分とカードという沈殿物とに分かれる。このカード部分を取り出したものがチーズの原形(フレッシュチーズ)となる[14]。フレッシュチーズとして販売される場合はここで製造は完了であるが、それ以外のチーズにおいてはこの後、加塩や微生物による熟成工程を経て様々な種類のチーズが作られることとなる[14]。
カード部分は必要に応じて切ってさらにホエイを排出させた後、型や枠に入れて固め、塩をすり込んだり塩水に漬けたりして加塩したのち、冷暗所において熟成させる。チーズの種類はこの熟成工程で決まる。フレッシュチーズ内にある乳酸菌の活動によって、乳糖は乳酸に、タンパク質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸などに分解され、そこからさらに様々な成分が生成される。ここにプロピオン酸菌属などの細菌やカビなどを添加して多様な作用を生じさせる事で各種のチーズがつくられる[14]。この加工時に加温・加圧などの工程を加えて保存性を高めるなどの工夫が凝らされている。
種類
チーズの原料には様々な種類の乳が使用できるが、主な原料となるのはウシ(牛乳)、ヒツジ、ヤギの3種の動物の乳である[15]。なかでも最も広く使用されるのはウシの乳であり、市中に出回っているチーズの原料は特に指定がない限りほとんどの場合は牛乳である。ヒツジの乳は脂肪分が多いため濃厚な味わいが特徴とされる。また、ヤギの乳は特有の臭いがあるものの、これも広く好まれるチーズの一つである。このほかにもスイギュウやヤクなどからチーズが作ることができる。また、ラクダの乳は脂肪の構造がウシなどとは異なるためチーズを作ることは困難ではあるが可能ではあり、その希少性ゆえにラクダチーズは高級品として高く評価されていた[16]。アラブ首長国連邦のドバイでは世界で初めて商業的にラクダチーズを生産販売する会社が現れ、世界各地への売り込みを図っている[17]
チーズの分類
原料や加工法によってチーズは細かく分類され[18]、1000種類以上あるとされる[14]。
チーズは基本的に、ナチュラルチーズとプロセスチーズの二つに区分できる。ナチュラルチーズは牛乳から直接作られる。これに対し、プロセスチーズはいったん生成されたナチュラルチーズを溶かし、それを再び乳化剤を添加して固めて作られる。プロセスチーズは溶解時に加熱殺菌されているため発酵が止まっており、長期保存が可能である[19]。
ナチュラルチーズの分類にはいくつもの方法があるが、一般的なものとしてはフレッシュチーズ、白かびチーズ、ウォッシュチーズ、シェーブルチーズ(山羊乳チーズ)、ブルーチーズ、半硬質チーズ、硬質チーズ(ハードチーズ)、超硬質チーズの8種類に区分できる。これは外観や硬さによる分類である。シェーブルチーズが独立した分類となっているのは、ウシやヒツジの乳とは異なり、ヤギの乳の成分は、レンネットでは凝固できない。よって、シェーブルチーズはあまり大きくすることができず、小さなものが多い。
フレッシュチーズは基本的に熟成させないが、軽く熟成させるタイプも存在する。フレッシュチーズは生鮮食品であり、できたてが最もおいしく、数日以内に食されるものである。味は熟成工程を経ないために原料であるミルクの味が強く、酸味が強いものが多いのが特徴である。白かびチーズ(ホワイトチーズ)は外皮に白カビを植え付けて熟成させたもので、軟らかく、クリーミーな味わいが特徴である。また、チーズの表面に塩水を吹き付けるタイプのチーズがウォッシュチーズである。青カビチーズ(ブルーチーズ)は白カビチーズとは逆に、内部に青かびを植え付けて熟成させるもので、そのため内部にも青かびの菌糸が入り込んでいるのが特徴である。味としては刺激があり、また塩分の強いものが多い。半硬質・硬質・超硬質チーズはいずれもプレスしてホエイをよく抜いた後熟成させるのが特徴であり、そのため大型で保存性もよい[20]。
また、こうしたチーズの分類とは別に、完成したチーズに様々なフレーバーを添加することも広く行われ、フレーバーチーズという一つの区分となっている。フレーバーチーズの中で最もよく知られるものはスモークチーズである。これは生成されたチーズを燻製の製法と同様に燻したものであり、ナチュラルチーズでもプロセスチーズでも作られる。このほかに、素材であるカードそのものにフレーバーを添加して作るもの、生成したチーズの外側にフレーバーをかけたりつけたりするもの、生成したチーズをほぐしてフレーバーを混ぜ込み、再び成形するものがある。フレーバーとして添加されるものは各種ハーブやスパイス、ニンニク、ナッツ類、ドライフルーツなどがある[21]。添加されたフレーバーによって様々な場面で使用され、特にナッツやドライフルーツを添加されたものはデザートとして多用される。
| 分類 | 特徴と主な種類 | |||
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルチーズ (加熱処理されていないもの) |
軟質チーズ | フレッシュチーズ | 熟成させない | モッツァレラチーズ(イタリア)、クリームチーズ(アメリカ)など。 |
| 軽く熟成させる | など。 | |||
| (熟成させるチーズ) | 白かびチーズ (ホワイトチーズ) |
表面に白かびを植えつけて熟成させるもの。 カマンベールチーズ(フランス)など。 |
||
| ウォッシュチーズ | 表面に菌を植え付けて熟成させ、同時にそれをワインや塩水などで洗い流す過程を経たもの。 | |||
| シェーブルチーズ (山羊乳チーズ) |
山羊の乳を原料とするもの。 |
など。いずれもポーランド。 |
||
| 半硬質チーズ(セミハードチーズ) | ブルーチーズ (青かびチーズ) |
内部に青かびを植えつけて熟成させるもの。 | ||
| (その他菌による熟成) | ゴーダチーズ(オランダ)など。 | |||
| 硬質チーズ(ハードチーズ) | チェダーチーズ(イギリス)など。 | |||
| 超硬質チーズ | パルミジャーノ・レッジャーノなど。 | |||
| プロセスチーズ | 加熱・溶解させることで発酵を止め、長期保存に適した状態にしたもの。 | |||
おもなチーズ
以下は比較的よく消費されているチーズの主要産地別一覧である。さらに詳細なリストはチーズの一覧を参照のこと。
- アイルランド
-
- ポーター(ハード)
- アメリカ合衆国(英: cheese)
-
- カッテージチーズ(フレッシュ)
- イギリス(英: cheese)
- イタリア(伊: formaggio)
-
イタリアの市場で撮影 →詳細は「イタリアのチーズ」を参照 - インド(ヒンディー語: पनीर)
-
- パニール/チェーナー(フレッシュ)
- オランダ(蘭: kaas)
- ギリシャ(希: Τυρί)
-
- フェタチーズ(フレッシュ)
- スイス(仏: fromage)
-

スイスのバーゼルのチーズマーケットで撮影 - エメンタールチーズ(セミハード)
- グリュイエールチーズ(セミハード)
- ラクレット(ハード)
- スペイン(西: queso)
- 中華人民共和国(中: 奶酪、乾酪、干酪)
- デンマーク(丁: ost)
-
- ダナブルー(ブルー)
- ドイツ(独: Käse)
-
- クワルク(フレッシュ)
- ブラジル(葡: queijo)
-
- カトゥピリ(ソフト)
- フランス(仏: fromage)
-

フランスの市場での販売風景 →詳細は「フランスのチーズ」を参照 - ルーマニア(ルーマニア語: brânză)
-
- ウルダ(フレッシュ)
- その他
-
トゥファルクチーズ
-
カマンベール
-
ウォッシュチーズ
-
ブリンザチーズ
-
オスツィペックチーズ
-
ゴウカチーズ
-
ポーター
用途
直接食用とする。ヨーロッパのフランス料理やイタリア料理では、レストランのみならず、各家庭の日常の食事においても、チーズは主菜の後とデザートの前の間の口直しとして供される。ワインを共に味わう場合、チーズによってそれまでの主菜と比べてワインの口当たりの変化が楽しめる。前菜として出て来る場合はサラダの素材として供される。ただしイタリア料理の場合、モッツァレラチーズはそのまま前菜(アンチパスト)として供することもある。また居酒屋(仏ブラッスリー、伊トラットリア)などではチーズ盛り合わせ(チーズプラター)といった単品メニューのみをオーダーすることもできる。
イタリア料理(パルミジャーノ・レッジャーノチーズやモッツァレラチーズ)やテクス・メクス料理(チェダーチーズ、モントレー・ジャック)など、チーズが欠かせない料理もある。
インドでは、菜食主義者の割合が多く、菜食主義者は動物の殺生の回避を目的としているため鶏卵も食べない。そのため多くの人が乳製品からタンパク質を補給する。フレッシュチーズのパニールを使った料理が豊富である。インド料理の菜食のメニューの半数程はパニールかダヒ(ヨーグルト)を使っている。
ナチュラルチーズは熱を加えるとカゼインのアミノ酸の鎖が絡まることで溶けた状態になる。溶けたチーズをかけるラクレットはスイスやフランスの、溶かしたチーズを具につけて食べるチーズフォンデュはスイスの名物である。プロセスチーズのように一度溶けたチーズは鎖が切れるためそれ以上溶けなくなる[22]。
中国にも、チベットのヤクのチーズや、料理に用いられるルーシャンや大良牛乳などの特殊なチーズがある。
日本においてはちくわやかまぼこなどにも練り込まれることがある。和菓子とも相性はよく、煎餅などによく使用される。チーズ類を使った煎餅類はメーカーによっては「チーズおかき」と呼ばれる場合もある。
そのほか、パンにそのまま練り込まれたり、サンドイッチの具やピザ、ハンバーグ(チーズトッピングとチーズインがある)に使われたりもされる。パスタにも粉チーズを食前に適量振りかけたり、またカルボナーラパスタ等のようなチーズを利用したりしたパスタ料理が多数存在する。そのほかチーズ使用料理は非常に多数にのぼる。チーズをそのまま使用するだけでなく、スプレー缶に封入されて食品に吹き付けて使うイージーチーズなどもある。菓子としても、チーズケーキをはじめとするケーキや、クッキー、クラッカー等にも使用され(別項参照)、クリームチーズ等を載せて食することもある。
アナログチーズ
厳密にはチーズを名乗れないが、チーズの乳脂肪を植物性脂肪に、乳たんぱくを大豆たんぱくなどに一部もしくは全部を置き換えたコピー食品としてアナログチーズ(代替チーズ)がある。乳製品を一切含まないものもある。原料コストを抑えられ、ドイツでは年間10万トンが生産されている。日本でも2007-2008年の原料乳価格高騰で注目された。本来のチーズと比べてコレステロールが低い、種類によっては牛乳アレルギー患者やヴィーガン(動物性食品を全く摂取しないベジタリアン)でも食べられるなどの利点がある。
世界の生産と消費
| 世界総計 | |
 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |
5,162,730 |
 ドイツ ドイツ |
2,046,250 |
 フランス フランス |
1,941,750 |
 イタリア イタリア |
1,132,010 |
 オランダ オランダ |
745,984 |
 ポーランド ポーランド |
650,055 |
 エジプト エジプト |
644,500 |
 ロシア ロシア |
604,000 |
 アルゼンチン アルゼンチン |
580,300 |
 カナダ カナダ |
408,520 |
| 世界総計 | 25,207,664 |
 ドイツ ドイツ |
3,995,010 |
 フランス フランス |
3,534,620 |
 オランダ オランダ |
3,239,085 |
 イタリア イタリア |
2,201,038 |
 デンマーク デンマーク |
1,350,514 |
 ニュージーランド ニュージーランド |
1,041,534 |
 ベルギー ベルギー |
792,887 |
 アイルランド アイルランド |
743,818 |
 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |
701,854 |
 オーストラリア オーストラリア |
682,834 |
| 世界総計 | 5,442,982 |
 ドイツ ドイツ |
1,008,991 |
 オランダ オランダ |
681,522 |
 フランス フランス |
639,047 |
 ニュージーランド ニュージーランド |
277,758 |
 イタリア イタリア |
272,281 |
 デンマーク デンマーク |
262,989 |
 サウジアラビア サウジアラビア |
237,237 |
 アイルランド アイルランド |
178,095 |
 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |
175,216 |
 ベルギー ベルギー |
162,268 |
| 世界総計 | 24,281,661 |
 ドイツ ドイツ |
3,451,310 |
 イタリア イタリア |
1,997,236 |
 イギリス イギリス |
1,909,123 |
 フランス フランス |
1,399,401 |
 ロシア ロシア |
1,319,892 |
 ベルギー ベルギー |
1,298,907 |
 スペイン スペイン |
1,101,922 |
 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |
1,003,147 |
 日本 日本 |
935,562 |
 オランダ オランダ |
864,789 |
| 世界総計 | 5,084,705 |
 ドイツ ドイツ |
608,220 |
 イタリア イタリア |
472,155 |
 イギリス イギリス |
439,497 |
 ロシア ロシア |
294,183 |
 フランス フランス |
275,464 |
 ベルギー ベルギー |
274,424 |
 スペイン スペイン |
242,652 |
 オランダ オランダ |
216,408 |
 日本 日本 |
199,080 |
 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |
138,326 |
| 国 | kg |
|---|---|
 フランス フランス |
26.3 |
 アイスランド アイスランド |
24.1 |
 ギリシャ ギリシャ |
23.4 |
 ドイツ ドイツ |
22.9 |
 フィンランド フィンランド |
22.5 |
 イタリア イタリア |
21.8 |
 スイス スイス |
20.8[25] |
 オーストリア オーストリア |
19.9 |
 オランダ オランダ |
19.4 |
 トルコ トルコ |
19.2[26] |
 スウェーデン スウェーデン |
19.1 |
 ノルウェー ノルウェー |
17.4 |
 チェコ チェコ |
16.3 |
 イスラエル イスラエル |
16.1 |
 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |
15.1 |
 カナダ カナダ |
12.3 |
 オーストラリア オーストラリア |
11.7 |
 アルゼンチン アルゼンチン |
11.5 |
 ポーランド ポーランド |
11.4 |
 ハンガリー ハンガリー |
11.0 |
 イギリス イギリス |
10.9 |
2011年に世界で最もチーズを生産していた国はアメリカ合衆国であり、次いでドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ポーランド、エジプト、ロシア、アルゼンチン、カナダの順となっている。
一方、チーズの輸出においてはアメリカの順位はかなり後退する。輸出額ベースにおけるチーズ最大輸出国はドイツであり、以下フランス、オランダ、イタリア、デンマーク、ニュージーランド、ベルギー、アイルランド、アメリカ、オーストラリアの順となる。また、輸出量ベースにおいてもドイツが一位となり、以下オランダ、フランス、ニュージーランド、イタリア、デンマーク、サウジアラビア、アイルランド、アメリカ、ベルギーの順となっている。
チーズの輸入においても、ドイツは質量ともに一位を占めている。輸入額ベースにおいてはドイツ、イタリア、イギリス、フランス、ロシア、ベルギー、スペイン、アメリカ、日本、オランダの順となっている。また、輸入量ベースにおいてはドイツ、イタリア、イギリス、ロシア、フランス、ベルギー、スペイン、オランダ、日本、アメリカの順となる。
チーズ貿易においてはドイツは輸出入ともに世界最大であり、イタリアやベルギーも輸出入ともに多い。フランスは輸入も多いが、輸出はそれ以上に多い。オランダはその傾向がさらに顕著で、チーズ生産は輸出にかなり軸足を置いたものとなっている。デンマークやニュージーランド、アイルランドもチーズ輸出がチーズ生産のかなりの割合を示す。こうした国々に対し、チーズのかなりを輸入に頼っているのはイギリスである。ロシアやスペイン、日本もチーズ貿易においては輸入を主とする。
一人あたりのチーズ消費量は、チーズを利用する文化が古くから根付いていたヨーロッパ諸国や地中海諸国、およびそこから分派した新大陸の諸国がランキングの上位を占めている。2011年において最も一人当たり年間チーズ消費量が多かった国はフランスであり、一人当たり1年間に26.3kgのチーズを消費していた。これに次ぐのがアイスランド、次いでギリシャであり、以下ドイツ、フィンランド、イタリア、スイス、オーストリア、オランダ、トルコ、スウェーデン、ノルウェー、チェコ、イスラエル、アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチン、ポーランド、ハンガリー、イギリスの順となっている。
日本
日本においては、1970年代末から、生産過剰となっていた牛乳の需要拡大策として、農林水産省が国産チーズ振興政策に取り組み始めた。よつ葉乳業など大手乳製品メーカーが工場を建設したほか、少量生産の工房が開業するようになった[27]。ナチュラルチーズも39,000トン(2005年)ほど生産されているが、生産量は国内消費量の15%弱に過ぎず、大半は輸入に頼っている[28]。毎年多くのナチュラルチーズが輸入され、国内でプロセスチーズに加工されたり、そのまま消費される。2018年のナチュラルチーズの最大輸入相手国はオーストラリアであり、82,935トンが輸入されている。ついでニュージーランドが62,214トンである。3位はアメリカの32,944トンである。以下はドイツ、イタリア、オランダ、デンマーク、アルゼンチン、フランスの順となっている[29]。2019年2月に発効した日本・EU経済連携協定(日欧EPA)ではソフトチーズの輸入枠拡大と関税引き下げが実施された[30]。
日本のチーズ消費量は第二次世界大戦後から2000年頃までは急増を続け、その後は増減を繰り返しつつ微増傾向となった[29]。2013年の日本のチーズ総消費量は295,000トンだった[29]。かつて1968年には一人当たり年間消費量は130グラムと1 kgにも満たなかったものが[31]、2010年には一人当たり2.0 kgとなり[11]、2012年の一人当たりチーズ消費量も2.4 kgまで増加した[29]。
チーズの消費促進に取り組む業界団体としてはチーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協議会がある[32]。
日本で高品質の国産チーズづくりをめざす動きも広がっている。国内のチーズ工房は2018年で319ヵ所に増え、国際コンテスト「ワールドチーズアワード」で上位入賞するチーズ職人も現れている。国内では中央酪農会議が国産ナチュラルチーズ全国審査会を2年に1回開いており、2019年の第12回は過去最高の86工房200種類超の応募があった[27]。生産者側の団体として、チーズプロフェッショナル協会がある[33]。2019年11月には一般社団法人日本チーズ協会(JCA、「日本チーズ生産者の会」後継団体)が発足した[34]。
健康
チーズは腸と全体的な健康に寄与する可能性のある善玉菌であるプロバイオティクスの健康的な供給源である。通常、プロバイオティクスは、熟成されたがその後加熱されていないチーズに含まれている。これには、スイス、プロヴォローネ、ゴーダ、チェダー、エダム、グリュイエール、カッテージチーズなどのソフトチーズとハードチーズの両方が含まれる。専門家は、善玉菌はアレルギー、気分障害、関節炎などの多くの症状の改善に関連している可能性があると考えている。 チーズなどのプロバイオティクスを含む食品を食べると、この自然なバランスを取り戻すのに役立つ。チーズに関して唯一の注意は、それをやり過ぎないことである。チーズはカロリー、飽和脂肪、ナトリウムが多い傾向がある[35]。
チーズに関連する道具
-
チーズスライサー
-
堅いチーズ用のパルメザンナイフ
-
ジロール(Girolle)
-
Cheese plane
-
チーズグレーター
-
チーズグレーター
表彰
- インターナショナル・チーズ・アワード
脚注
出典
- ^ Fankhauser, David B. (2007年). “Fankhauser's Cheese Page”. 2007年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年9月23日閲覧。
- ^ No,001- チーズの歴史 - 勝沼醸造株式会社
- ^ チーズの歴史って? - オーダーチーズ・ドットコム
- ^ Salque, Mélanie; Bogucki, Peter I.; Pyzel, Joanna; Sobkowiak-Tabaka, Iwona; Grygiel, Ryszard; Szmyt, Marzena; Evershed, Richard P. (2013-01). “Earliest evidence for cheese making in the sixth millennium bc in northern Europe” (英語). Nature 493 (7433): 522–525. doi:10.1038/nature11698. ISSN 0028-0836.
- ^ 「7000年前にチーズ作り、土器に証拠発見 ネイチャーAFPBB(2012年12月13日)2015年12月20日閲覧
- ^ 世界の雑記帳:7500年前にチーズ製造の証拠、土器から発見=研究ロイター/毎日新聞(2012年12月13日)2019年11月11日閲覧
- ^ ブリュノ・ロリウー著『中世ヨーロッパ 食の生活史』pp82-83 吉田春美訳 原書房 2003年10月4日第1刷
- ^ 『チーズと文明』p61 ポール・キンステッド 築地書館 2013年6月10日初版発行
- ^ 林弘通『20世紀乳加工技術史』p12 幸書房 2001年10月30日初版第1刷発行
- ^ 林弘通『20世紀乳加工技術史』p161 幸書房 2001年10月30日初版第1刷発行
- ^ a b c “【業務関連情報】日本人とチーズ”. 独立行政法人農畜産業振興機構. 2015年12月23日閲覧。
- ^ 「日本チーズ物語」一般社団法人Jミルク(2015年12月20日閲覧)
- ^ 林弘通『20世紀乳加工技術史』p156 幸書房 2001年10月30日初版第1刷発行
- ^ a b c d e 「【チーズ】味や香りのちがいとは?どうやってつくられる?」『ニュートン』第33巻第1号、株式会社ニュートンプレス、2013年1月、120-121頁。
- ^ 木村則生『プロフェッショナル・チーズ読本 プロが教えるチーズの基本知識から扱い方まで』p38 誠文堂新光社 2011年11月30日発行
- ^ 「アラブ世界のラクダ乳文化」p74 堀内勝/『乳利用の民族誌』所収 雪印乳業株式会社健康生活研究所編 石毛直道・和仁皓明編著 中央法規出版 1992年3月10日初版発行
- ^ 話題の「ラクダ」食品、世界に売り込みCNN(2014年11月6日)2015年10月30日閲覧
- ^ 牛乳・乳製品の知識 第3章 乳製品のはなし(日本酪農乳業協会)
- ^ プロセスチーズ雪印メグミルク(2015年12月20日閲覧)
- ^ 松成容子編『チーズポケットブック 2007~2008年版』p126 旭屋出版 2006年11月22日初版発行
- ^ ジュリエット・ハーバット監修『世界チーズ大図鑑』p22-23 柴田書店 2011年1月25日初版発行
- ^ “チーズ | 食育レシピ|meiji - Meiji Co., Ltd.”. 明治の食育|株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.. 2020年8月25日閲覧。
- ^ a b c d e UN Food & Agriculture Organisation (FAO)[1]
- ^ “Total and Retail Cheese Consumption – Kilograms per Capita”. Canadian Dairy Information Centre. 2013年5月20日閲覧。
- ^ Switzerland Cheese Marketing AG, Consommation de fromage par habitant en 2012
- ^ USDA, Food and Agricultural Organization, Cheese Statistics
- ^ a b 【論説】国産チーズ新局面 需要創造と所得支援を『日本農業新聞』2019年11月15日(3面)
- ^ 松成容子編『チーズポケットブック 2007~2008年版』p25 旭屋出版 2006年11月22日初版発行
- ^ a b c d “チーズの統計”. 日本輸入チーズ普及協会. 2015年12月23日閲覧。
- ^ 「日欧EPA半年 国内市場に浸透 チーズ、ワイン2割超増」『日本農業新聞』2019年8月1日(2019年11月20日閲覧)
- ^ 林弘通『20世紀乳加工技術史』p31 幸書房 2001年10月30日初版第1刷発行
- ^ 「国産消費もっと 東京でチーズフェスタ」『日本農業新聞』2019年11月12日(7面)
- ^ 「国産チーズ 世界へ飛躍/国際コンテストに初の本格出品◀栃木の工房、ベスト16に◀東京からも参加/全国の作り手、5年で1.3倍」『日経MJ』2019年11月10日(12面)
- ^ 「日本チーズ協会発足へ 認証事業で国産身近に/輸入攻勢 品質で対抗」『日本農業新聞』2019年10月31日(2面)2019年11月11日閲覧
- ^ Publishing, Harvard Health. “Is cheese a healthy source of probiotics?”. Harvard Health. 2021年1月22日閲覧。
- ^ “Oldest cheese” (英語). Guinness World Records. 2023年6月17日閲覧。
- ^ Inc, mediagene (2018年8月28日). “3200年モノのチーズ、危険な細菌まみれだった”. www.gizmodo.jp. 2023年6月17日閲覧。
- ^ “Largest display of cheese varieties” (英語). Guinness World Records (2016年9月23日). 2023年6月17日閲覧。
文献
アンドリュー・ドルビー『チーズの歴史』(ブルース・インターアクションズ、2011年) ISBN 978-4-86020-426-6
関連項目
- 各国のチーズ
- バター
- ヨーグルト
- 食物アレルギー
- ヴィーガンチーズ - 大豆などを使った植物素材から作られたチーズ代用品
- ガバメントチーズ - アメリカ政府が第二次世界大戦後以降に余った牛乳から作り、保管・配布・売却しているチーズ。
- 保護原産地呼称、原産地名称保護制度、伝統特産品保証
外部リンク
- 『チーズ』 - コトバンク
- 婦人雑誌におけるチーズ料理 : 『婦人之友』と『主婦の友』との比較研究橋場浩子 (日本調理科学会, 1997-05-20) 『日本調理科学会誌』30(2)
- 「チーズができるまで」 - 財団法人蔵王酪農センター、六甲バター株式会社に取材し、チーズの製造工程を紹介(全14分) 2009年 サイエンスチャンネル
- 『科学映像館』より
Cheese!
(チーズ から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/05 13:18 UTC 版)
| Cheese! | |
|---|---|
 |
|
| ジャンル | 少女漫画雑誌 |
| 読者対象 | 18歳〜25歳[1] |
| 刊行頻度 | 月刊(毎月24日) |
| 発売国 |  日本 日本 |
| 言語 | 日本語 |
| 定価 | 500円 |
| 出版社 | 小学館 |
| 発行人 | 吉田憲生 |
| 編集長 | 菊池博和[2] |
| 雑誌名コード | 06175 |
| 刊行期間 | 1996年7月[1](1996年10月号) - |
| 発行部数 | 12,333部(2025年4月 - 2025年6月日本雑誌協会調べ) |
| レーベル | フラワーコミックス |
| ウェブサイト | チーズ!ネット |
『Cheese!』(チーズ!)は、小学館が発行する少女向けの日本の月刊漫画雑誌。刊行月の前々月24日に発売されている。
1996年7月に創刊[1]。1996年10月号が創刊号[3]。『少女コミック』(小学館)の派生誌[2]。創刊当初は『少女コミックCheese!(SHO-COMIチーズ!)』の誌名で毎月28日に発売されていた[3]。
18歳から25歳を主なターゲットとしている[1]。版型はB5で、無線とじ[1]。
キャッチコピーは「女の子には、愛される物語が必要だ」[4]。
特徴
映像化作品はアニメよりもテレビドラマや映画など、実写化されることが特徴である[1]。「王道よりも変化球、アダルトな香りを持つ作品」が読者から支持されており、「一般的な恋愛系少女漫画よりも世界観設定が凝っている作品」が多く掲載されている[1]。
歴代編集長
 |
この節の加筆が望まれています。
|
- 武者正昭(20??年 - 2013年[5])
- 菊池博和(2013年 - 2015年[5]、2024年[2] - )
- 畑中雅美(2016年12月時点[6]。2023年1月時点[7]。2015年 - 2019年[8]、2022年[9][10] - )
- 西巻篤秀[11](2019年 - 2022年)
連載作品
※ 2025年6月24日(2025年8月号)現在。
- うちの犬が子ネコ拾いました。(竜山さゆり):2017年6月号[12] -
- 殉国のアルファ(嶋木あこ):2021年5月号[13] -
- 今日もハジメ先輩が好きすぎる(湯町深):2023年6月号[14] - ※休載中[15]
- 今日は何する?(嶋木あこ):2023年11月号[16] - ※シリーズ[16]
- 群青のカルテ(椎名チカ):2023年11月号[16] -
- 鳴川くんは泣かされたくない(遠山あち):2023年11月号[16] -
- ヒロインなのに、イケメンアイドル♂になりました!?(愛染マナ):2024年2月号[17] -
- カノジョは俺にかみつきたい(浅野あや):2024年9月号[18] -
- 蝶は愛執の檻にとらわれる(七海月):2024年12月号[19] -
- 愛でて春 〜呪われた公爵騎士様は溺愛する〜(朱神宝):2025年1月号[20] -
- なきっつらに恋(華谷艶):2025年3月号[21] -
- 僕は魔法少女(♂)に恋をした。(藤田すてふぁにー):2025年4月号[22] - ※電子版限定連載[22]
- 私より可愛いJKがいたら○す(三浦コズミ):2025年6月号[23] -
- 生まれ変わってやり直させて(七尾美緒):2025年7月号[24] -
過去の連載作品
1990年代
- こわしたいほど愛されたい(すもと亜夢):1996年10月号[25] - 1999年5月号
- 月にキスの花束を(北川みゆき):1996年10月号[25] - 1998年1月号
- MYダーリン・ライオン(長谷部百合):1997年 - 2000年
- 永遠かもしれない(赤石路代):1997年10月号 - 2000年6月号
- 罪に濡れたふたり(北川みゆき):1998年12月号 - 2004年12月号
- げっちゅー♥(すぎ恵美子)1999年5月号 -
2000年代
- 私の…メガネ君(すもと亜夢):2001年9月号 -
- 月下の君(嶋木あこ):2002年5月号 - 2004年8月号
- 愛†少女(すぎ恵美子):2003年3月号 - 2004年6月号
- 好きになってもいいの?(太田早紀)2003年11月号 - 2004年12月号
- ヌードな果実たち(北川みゆき)2005年2月号 - 2006年1月号
- 汝、誓いの口づけを…(太田早紀):2005年5月号 - 2005年8月号
- Honey Hunt(相原実貴)2007年2月号 - 2010年1月号[26]
- 僕達は知ってしまった(宮坂香帆):2007年4月号 - 2012年5月号
- キョ→ダイだからなんだよっ!?(棉田のぶ)2007年5月号 - 2007年11月号
- コイイロオモイ(湯町深)2007年7月号 - 2007年9月号
- 裸の王子様〜Love Kingdom〜(山田こもも)2007年8月号 - 2008年5月号
- ウブかわ〜初めての彼〜(堂本奈央)2007年9月号 - 2009年3月号
- 恋したがりのブルー(藤原よしこ):2007年10月号 - 2009年9月号
- トリプルKISS(嶋木あこ)2007年11月号 - 2008年6月号
- 初恋に溺れた(桜田雛)2008年2月号 - 2008年4月号
- 奪ってあげます(西城綾乃)2008年3月号 - 2008年5月号
- 僕はキスで嘘をつく(藤間麗):2008年6月号 - 2008年12月号
- 王子達は依存する(桜田雛):2008年11月号 - 2009年1月号
- 黎明のアルカナ(藤間麗):2009年3月号 - 2013年8月号[27]
- コスプレ刑事(堂本奈央):2009年4月号 - 2011年4月号[28]
- カノジョは嘘を愛しすぎてる(青木琴美):2009年5月号 - 2017年4月号[29]
- ヒミツのアイちゃん(花緒莉):2009年9月号 - 2014年11月号[30]
- 彼氏はドーベルマン(西城綾乃)2009年10月号 - 2009年12月号
- ぴんとこな(嶋木あこ):2009年11月号 - 2015年11月号[31]
- 少女の時間(椎名チカ):2009年12月号 - 2010年2月号
- だから恋とよばないで(藤原よしこ):2009年12月号 - 2011年11月号
2010年代
- 眠れる森の獣たち(山田こもも):2010年1月号[32] -
- 5時から9時まで(相原実貴):2010年3月号[26] - 2020年5月号[33]
- 分別と多感(桜田雛):2010年6月号[34] - 2010年8月号
- お子様ぱーんち!(車谷晴子):2010年7月号[35] -
- 水恋(七尾美緒):2011年1月号[36] -
- 殺されるなら、いっそ桜の木の下で(桜田雛):2011年4月号[28] - 2011年6月号
- 11歳の王様(車谷晴子):2011年5月号[37] -
- ランウェイ・WARS(あらいきよこ):2011年6月号[38] -
- ダメ恋みほん帖(水谷愛):2011年7月号[39] - 2012年6月号
- 青の微熱(椎名チカ):2011年8月号[40] - 2012年8月号
- ブラッディー フォークロア(高宮智):2011年9月号[41] -
- ダンナさんは芸人さん(清水まみ)2011年10月号 - 2012年6月号
- シークレット・シェアハウス(堂本奈央):2011年10月号[42] -
- 初恋はまるで刃のように(わたなべ志穂):2011年12月号[43] -
- ナイショのふたり(浅野あや): 2012年1月号 - 2012年8月号
- 後にも先にもキミだけ(川上ちひろ):2012年1月号[44] -
- ペン先にシロップ(七尾美緒):2012年2月号[45] - 2013年8月号[27]
- カレと私のあんなこと…(湯町深): 2012年3月号 - 2012年9月号
- 金魚の糞(桜田雛):2012年3月号[46] - 2013年7月号
- ピンクのしっぽ(藤原よしこ):2012年3月号[46] -
- 百獣の王に告ぐ!(朱神宝):2012年5月号 - 2012年7月号
- グリーン・ウェンズデー(おおばやしみゆき):2012年7月号[47] - 2012年12月号
- いつか君たちも大人になる(藤緒あい):2012年8月号[48] - 2012年12月号
- 殉血LOVERS(高宮智):2012年9月号 - 2013年4月号
- ノーコントロール(湯川果奈):2012年9月号 - 2012年11月号
- あかいいと(宮坂香帆):2012年10月号[49] - 2015年9月号[50]
- 制服の微熱(湯町深):2012年11月号[51] - 2014年1月号[52]
- 私はまだそれを知らない(椎名チカ):2012年12月号[53] - 2013年3月号
- 不機嫌なロゼット(冬織透真):2013年1月号 -
- スキのかけら、キスの記憶(浅野あや):2013年2月号[54] - 2013年4月号
- はつこい依存症(朱神宝):2013年4月号[55] - 2013年6月号
- 100回泣くこと(原作:中村航、水谷愛):2013年4月号[55] - 2013年6月号
- 今日もウチで待ち合わせ(藤緒あい):2013年7月号[56] - 2013年10月号
- 花街鬼(桜田雛):2013年10月号[57] -
- 夢幻ソワカ〜東京少女陰陽師〜(七尾美緒):2013年10月号[57] - 2014年12月号[58] ※第1部完[58]
- ロッカメルト〜フィアンセは雪男〜(藤間麗):2013年11月号[59] - 2015年1月号[60]
- 37.5℃の涙(椎名チカ):2013年12月号[61] - 2014年11月号[30]、2015年7月号[62] - 2022年7月号[63]
- いつかの君と恋を(佐倉紫露):2014年1月号[64] -
- ケモノスイッチ(湯町深):2014年4月号[65] - 2015年6月号[66]
- はにぃ*ばでぃ(朱神宝):2014年4月号[65] - 2014年6月号[67]
- 隆之介くんは優しくない(浅野あや):2014年5月号 - 2014年7月号[30]、2ndシリーズ:2014年9月号 - 2014年11月号
- 金曜日は初恋(中村ユキチ):2014年6月号[67] - 2014年8月号[68]
- 絶望ベイビー(桜田雛):2014年8月号[68] - 2015年2月号[69]
- 姫とナイトと、となりの私。(朱神宝):2014年8月号[68] - 2014年10月号[70]
- 煩悩パズル(川上ちひろ):2014年10月号[70] - 2017年2月号[71]
- ラブ×ジョイント(中村ユキチ):2014年11月号[30] - 2015年1月号[60]
- 百日紅男子高等学校!!(花緒莉):2014年12月号[58] - 2015年9月号、2016年1月号[72] -
- マンボウちゃんとライオンくん(佐倉紫露):2014年12月号[58] - 2015年2月号[69]
- 上目づかいが効かない理由。(石川ユキ):2015年1月号[60] - 2015年3月号[73]
- 式神男子(七尾美緒):2015年1月号[60] - 2016年1月号[72]
- おひさまにキス(朱神宝):2015年2月号[69] - 2015年4月号[74]
- 鍵のない鳥籠(冬織透真):2015年3月号[73] - 2015年5月号
- てのひらに彗星(中村ユキチ):2015年3月号[73] - 2015年5月号
- 水神の生贄(藤間麗):2015年4月号[74] - 2018年11月号[75]
- モトカレ←リトライ(華谷艶):2015年4月号[74] - 2017年3月号[76]
- コーヒー&バニラ(朱神宝):2015年6月号[66] - 2024年3月号[77]
- 絶対服従アイドル(中村ユキチ):2015年6月号[66] - 2015年8月号[78]
- 花とみるらむ〜恋虜源氏物語〜(桜田雛):2015年6月号[66] - 2016年4月号[79] ※途中で『黒光源氏物語〜花とみるらむ〜』に改題、単行本のタイトルは『黒源氏物語』
- 恋ベタ♀とものぐさ♂が婚活してみた。(朝田とも):2015年7月号 - 2016年1月号[72]
- ラブ×ラブゲーム(湯町深)2015年8月号[78] - 2016年4月号[79]
- 死神たちのレイゾンデイト(冬織透真):2015年9月号[50] - 2015年11月号[31]
- 10万分の1(宮坂香帆):2015年10月号[80] - 2018年10月号[81]
- ぼくの輪廻(嶋木あこ):2016年4月号[79] - 2020年12月号[82]
- 私は天才を飼っている。(七緒美緒):2016年5月号[83] -
- B-PROJECT 妄想*スキャンダル(原作:MAGES.、漫画:杜乃ミズ):2016年7月号[84] - 2016年12月号
- 執事たちの沈黙(桜田雛):2016年8月号[85] - 2020年9月号[86]
- KING OF PRISM Pretty Rhythm〜Over the Rainbow!〜(綾月もか):2016年10月号[87] - 2017年8月号[88]
- なめて、かじって、ときどき愛でて(湯町深):2016年11月号[89] - 2023年2月号[90]
- 本当に良い美容整形 悪い美容整形(朝田とも):2017年1月号[91] -
- 魔法×少女にHが足りないっ(清水まみ):2017年3月号[76] - 2019年12月号[92]
- 捨て犬にハニートースト(華谷艶):2017年5月号[93] - 2018年8月号
- 放課後トキシック(川上ちひろ):2017年6月号[12] - 2019年8月号
- オトナのはじめて(朝田とも):2017年7月号[94] -
- 虹、甘えてよ。(青木琴美):2017年9月号[95] - 2020年10月号[96]
- 発熱リビドー(雨村澪)2018年2月号[97] - 2019年9月号 →『プレミアCheese!』に移籍
- 羊と鋼の森(原作:宮下奈都、漫画:水谷愛):2018年2月号[97] - 2018年6月号
- 宵の嫁入り(七緒美緒):2018年9月号[98] - 2021年8月号[99]
- ハツコイ×アゲイン(華谷艶):2018年9月号[98] -
- 金色ジャパネスク〜横濱華恋譚〜(宮坂香帆)2018年12月号[100] - 2020年6月号[101] →『& Flower』に移籍[101]
- 王の獣(藤間麗):2019年3月号 - 2025年3月号[21]
- 恋と弾丸(箕野希望):2019年6月号[102] - 2022年8月号[103] ※『プレミアCheese!』と平行連載[102]
- 神男子のいいなずけ(川上ちひろ):2019年12月号[92] - 2020年8月号[104]
2020年代
- 狼のシュガーレス(藤原えみ):2020年6月号[101] -
- 黒崎秘書に誉められたい(宮坂香帆):2020年9月号[86] - 2025年6月号[23]
- 社内マリッジハニー(藤原えみ):2020年10月号[96] - 2021年7月号[105] ←『プレミアCheese!』より移籍[96]
- ねぇ先生、知らないの?(浅野あや):2020年11月号[106] - 2022年12月号[107] ←『プレミアCheese!』より移籍[106]
- エレベーター降りて左(相原実貴):2021年1月号[108] - 2023年8月号[109] ※『5時から9時まで』のスピンオフ[108]
- 黒猫に甘噛み(華谷艶):2021年2月号[110] - 2023年5月号[111]
- ラブ・パラサイト(雨村澪):2021年2月号[110] - 2023年1月号
- それは大人の事情です(藤原えみ):2021年9月号[112] - 2022年6月号[113]
- 転生悪役令嬢は見せかけドS王子をお仕置きしたい(清水まみ):2021年10月号[114] - 2023年4月号[115] ※『プレミアCheese!』と平行連載[116]
- 虎に花束(大河きっぷ):2021年11月号[117] - 2022年2月号
- 深愛なるFへ(七尾美緒):2022年1月号[118] - 2025年3月号[21]
- ボクたちの不幸な話をしよう(逆巻詩音):2022年3月号[119] - 2022年6月号[113]
- シンデレラは甘いキスにあらがえない(大葉ノコ):2022年7月号[63] - 2022年10月号[120]
- 君に吹かれて息もできない(大河きっぷ):2022年8月号[103] - 2023年3月号[121]
- 初恋のつづきは男子寮で(七海月):2022年9月号[122] - 2024年9月号[18]→続編を『プレミアCheese!』で連載[123]
- 初恋クラウドハニー(藤原えみ):2022年12月号[107] - 2023年10月号[124]
- 薔薇と殺し屋(箕野希望):2023年2月号[90] - 2023年12月号[125]
- 女神に恋した男たち(浅野あや):2023年4月号[126] - 2024年5月号[127]
- 反抗的なカレシ(川上ちひろ):2023年5月号 - 2024年7月号[128]←『プレミアCheese!』より移籍[129]
- 双子の悪魔とつがいの月(夢月いめ):2023年6月号[14] - 2024年4月号[130]
- この雪原で君が笑っていられるように(ちづはるか):2023年7月号[131] - 2024年11月号[132]
- ショートケーキの苺はいつ食べる?(華谷艶):2023年8月号[133] - 2024年11月号[132]
- 恋は空から降ってくる(花緒莉):2024年6月号[134] - 2025年6月号[23]→『プレミアCheese!』に移籍[135]
連載開始時期不明
- R-18(すぎ恵美子)
- S+M(すもと亜夢)
- キス、絶交、キス〜ボクらの場合〜(藤原よしこ)
- キスは0時を過ぎてから(刑部真芯)
- キミのキスで触れて(花緒莉)
- 君を奪う、君を愛す(刑部真芯)
- 禁色-花筐戀歌-(刑部真芯)
- 禁断シリーズ(刑部真芯)
- 獣は花の夢を見るか(刑部真芯)
- 恋なんかはじまらない(藤原よしこ)
- 今夜、キミが会いにいく(花緒莉)
- しなやかに傷ついて(北川みゆき)
- 囚-愛玩少女-(刑部真芯)
- 素肌に革命(樹本祐季)
- SEX=LOVE2(新條まゆ)
- セツナの楽園(わたなべ志穂)
- 先生のお気に入り!(相原実貴)
- 続・先生のお気に入り!(相原実貴)
- 天使のいいなり(春日あかね)
- 薔薇の鎖(刑部真芯)
- PINKの秘めゴト♥(佐々木柚奈)
- ぼっちゃまはイジワル(長谷部百合)
- 毎日 君に 恋してる(山田こもも)
- モテっ子♥大・作・戦(桜井美也)
- 欲望と恋のめぐり(刑部真芯)
- よっくんといっしょ(水鏡なお)
- 夜まで待てない。(太田早紀)
- ラブ&ノイズ!(本多夏巳)
- ロイヤル☆セブンティーン(香代乃)
 |
この節の加筆が望まれています。
|
映像化作品
| 作品 | 放送年 | 制作 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| ぴんとこな | 2013年 | TBSテレビ 松竹(協力) |
|
| カノジョは嘘を愛しすぎてる | フジテレビ | [136] 番組名:『カノジョは嘘を愛しすぎてる サイドストーリー〜ボクとカノジョが出会う前の物語〜』[136]。 |
|
| 37.5℃の涙 | 2015年 | TBSテレビ テレパック |
[50][137] |
| 5時から9時まで | フジテレビ | [138] 番組名:『5→9〜私に恋したお坊さん〜』[138] |
|
| カノジョは嘘を愛しすぎてる | 2017年 | tvN スタジオドラゴン |
韓国制作のテレビドラマ |
| コーヒー&バニラ | 2019年 | 毎日放送 ソケット |
[139] |
| ねぇ先生、知らないの? | [140] | ||
| 社内マリッジハニー | 2020年 | 毎日放送 ROBOT |
[141] |
| モトカレ←リトライ | 2022年 | [142] | |
| 恋と弾丸 | 毎日放送 ソケット |
[143] |
| 作品 | 配信年 | 配信先 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| ヒミツのアイちゃん | 2021年 | FOD | [144] |
| 作品 | 公開年 | 配給 | 備考・出典 |
|---|---|---|---|
| カノジョは嘘を愛しすぎてる | 2013年 | 東宝 | [145] |
| 10万分の1 | 2020年 | ポニーキャニオン 関西テレビ放送 |
[146] |
増刊誌
Cheese! 増刊
発売日は刊行月(奇数月)の前月10日ごろであった。判型はA5判。[要出典]
プレミアCheese!
2016年5月に発売された6月号より創刊[147]。『Cheese!増刊号』がリニューアルされた形で刊行開始[147]。奇数月5日発売で、祝日により前後することがある[148]。隔月刊で年6回発売の増刊誌[148]。判型は本誌と同じB5判[149]。定価は640円(2022年2月号現在)[149]。略称は「プレチー」[150][116]。
連載作品
※2025年10月号(2025年9月5日)現在。
- 薔薇色ノ約束(宮坂香帆)←『Cheese!』より移籍
- コーヒー&バニラ black(朱神宝):2018年8月号 -
- うさぎは幸せな夢を見る(夢月いめ):2023年8月号[151] -
- 違いすぎる僕たちは、恋しかなかった〜ふたりは真逆でぴったりな〜(朝田とも):2024年2月号[152] - 2025年10月号[153]
- 甘えたがりな彼女について(藤原えみ):2024年4月号[154] - 2025年10月号[153]
- 恋になるとは聞いてない(桃川紗奈):2024年6月号[155] -
- 巫の婿探し(川上ちひろ):2024年12月号[156] -
- 禁断は二十歳になってから(見崎なつみ):2025年2月号[157] -
- ちいさな空にさんかくの太陽(鳩さわこ):2025年2月号[157] -
- 虎くんは今日もお嬢様に試される(菊乃杏):2025年4月号[158] -
- 花妻と宵闇〜没落令嬢は純血を捧ぐ〜(高内藤花):2025年4月号[158] -
- やり直し愛犬は今世も恋する(広中あん):2025年4月号[158] -
- 堕ちた月と太陽(雨宿りぃ):2025年6月号[135] -
- 恋は空から降ってくる(花緒莉):2025年6月号[135] - ←『Cheese!』[135]
- 初恋のつづきは男子寮で(七海月):2025年8月号[123] - ←『Cheese!』連載の続編[123]
- 私と星屑とベース(降旗麦):2025年10月号[159] -
過去の連載作品
- kissだけはヒミツ。(桃川紗奈): - 2016年10月号
- 寝ても覚めても君と(上条あおい): - 2016年10月号
- 故意ですが恋じゃない(浅野あや): - 2016年12月号
- 巧くんは彼女を人に見せたくない(高宮智): - 2017年2月号
- 取り急ぎ、同棲しませんか?(中村ユキチ):2016年6月号 - 2019年2月号
- 王子様はマリッジブルー(わたなべ志穂): - 2017年4月号
- ヒミツのヒロコちゃん(花緒莉):2016年6月号 - 2022年10月号[150]
- 俺に配属されなさい(へんみ奈々恵):2016年10月号 - 2017年6月号
- ゆるふわ水神さま(藤間麗):2016年10月号 - 2018年10月号
- 私はヘンタイを飼っている。(七尾美緒):2016年10月号 - 2018年6月号
- 今日からカノジョになりました。(長谷瑠依):2016年12月号 - 2017年4月号
- デブ漫画家が一番ラクヤセできる方法を探してきましたレポ(桜井美也):2016年12月号 - 2017年8月号
- わがまま男は一途に恋する(箕野希望):2016年12月号 - 2017年4月号[160]
- ラブ→マウント(浅野あや):2017年2月号[161] - 2018年8月号
- 好きやでって言わせたい!!(上条あおい):2017年6月号 - 2017年10月号
- キスより先に、始めます(わたなべ志穂):2017年8月号[162] - 2021年4月号[163]
- LOVE×プレイス.fam(箕野希望:2017年8月号 - 2018年2月号 ※2017年8月号掲載タイトルは『ストレイ×ソウル.fam』
- ムカつきディープクレンジング(桜井美也):2017年10月号 - 2020年12月号
- 会長様のニセヨメ。(桃川紗奈):2018年2月号 - 2020年4月号
- 最愛×マリッジグレー(藤原えみ):2018年2月号 - 2018年12月号
- 社内マリッジハニー(藤原えみ):2019年2月号 - 2020年8月号→『Cheese!』に移籍[96]
- 初恋QUEST〜誰にも聞けない恋の話〜(月森ココ):2018年2月号 - 2018年6月号→『&フラワー』に移籍
- 恋と弾丸(箕野希望):2018年4月号 - 2019年4月号
- ねぇ先生、知らないの?(浅野あや):2018年12月号[164] - 2020年10月号→『Cheese!』に移籍[106]
- その恋は校則違反です(上条あおい):2019年4月号 - 2020年6月号[165]
- 寝ても覚めてもキスしても(中村ユキチ):2019年4月号 - 2019年8月号→『&フラワー』に移籍
- お猫さま…!!(七尾美緒):2019年6月号[166] - 2021年4月号
- 恋と弾丸 Special Bullet(箕野希望):2019年6月号 - 2022年8月号[167] ※『Cheese!』と平行連載[102]
- 発熱リビドー(雨村澪):2019年10月号 - 2020年12月号←『Cheese!』より移籍
- ないものねだりの恋たちは(桃川紗奈):2020年6月号[165] - 2023年6月号
- 宮廷魔女の王子録(上条あおい):2020年8月号[168] - 2021年12月号[169]
- 今日もスーパースターに求婚されてます(七海月):2020年10月号[170] - 2021年8月号[171]
- ラブマリ(たむら紗知):2020年10月号[170] - 2021年4月号[163]
- 恋は〆切のあとで〜書店員。ときどき、ミステリ作家〜(朱音りか):2020年12月号[172] - 2022年10月号[150]
- 反抗期なカレシ(川上ちひろ):2021年2月号[173] - 2023年2月号→『Cheese!』に移籍[174]
- ブラック彼氏(原作:堀井亜生、桜井美也):2021年2月号[175] - 2025年6月号[176]
- 17歳、恋と呼ぶには不十分(逆巻詩音):2021年6月号[177] - 2021年12月号[169]
- パーフェクトスキャンダル(菊乃杏):2021年6月号[177] - 2024年10月号[178]←『めちゃコミック』より移籍[179]
- THE HOUSE〜階下の王子様〜(桃田紗世):2021年8月号[171] - 2022年10月号[150]
- 鬼の千年恋(七海月):2021年10月号 - 2022年10月号[150]←移籍
- 転生悪役令嬢は見せかけドS王子をお仕置きしたい:2021年12月号[116] - 2023年4月号[180] ※『Cheese!』と平行連載[116]
- 早くシて、店長!!(秋ひろな):2021年12月号[116] - 2022年8月号[167]←『&フラワー』より移籍[116]
- 冷酷王子と嫌われ魔女の幸せな人生計画〜罪深き魔女は前世の咎を利用する(上条あおい):2022年2月号[181] - 2023年8月号[151]
- 午前1時過ぎのシンデレラ(秋ひろな):2022年10月号[150] - 2024年12月号[182] ※2023年10月号より新章として『恋を知らずに、愛を売る』にタイトル変更[183]
- 恋獄花嫁道中(朝田とも):2022年10月号[150] - 2023年4月号[180]
- 嘘つきに誓いのキス(朱音りか):2022年12月号[184] - 2023年4月号[180]
- 恋とドリップ 〜Bitter & Sweet〜(松田みさと):2022年12月号[184] - 2023年4月号[180]
- 二度目の恋は最愛(高内藤花):2023年2月号[174] - 2024年2月号[185]
- キミとの夢は世界一(朱音りか):2023年6月号[186] - 2024年6月号[187]
- プライスレスマリッジ(広中あん):2023年6月号[186] - 2024年12月号[182]
- 炎上教師に恋なんて(大島ニコラ):2023年8月号[151] - 2024年8月号[188]
- 年下旦那様がヤンデレすぎてぎゅんぎゅんです(みなとゆみ):2023年8月号[151] - 2024年10月号[178]
- ごめん、ふたりを愛してる(桃川紗奈):2023年10月号[189] - 2024年2月号[185]
- こじらせ王子の恋わずらい(鏡宮ヲリエ):2024年4月号[154] - 2024年8月号[188]
- 今日もごきげん森野さん(お砂糖):2024年6月号[155] - 2025年4月号[158]
- 高澤先輩が怖すぎる(花菜ミツキ):2024年6月号[187] - 2024年10月号[190]
- ふたりぐらし奇譚〜中華的浪漫物語〜(西町セツオ):2024年10月号[191] - 2025年8月号[123]
- 放課後の密かごと(赤月すみれ):2024年12月号[156] - 2025年4月号[158]
発行部数
- 2003年9月1日 - 2004年8月31日、174,833部[192]
- 2004年9月 - 2005年8月、155,833部[192]
- 2005年9月1日 - 2006年8月31日、148,167部[192]
- 2006年9月1日 - 2007年8月31日、144,750部[192]
- 2007年10月1日 - 2008年9月30日、133,000部[192]
- 2008年10月1日 - 2009年9月30日、117,667部[192]
- 2009年10月1日 - 2010年9月30日、103,917部[192]
- 2010年10月1日 - 2011年9月30日、90,417部[192]
- 2011年10月1日 - 2012年9月30日、82,084部[192]
- 2012年10月1日 - 2013年9月30日、76,334部[192]
- 2013年10月1日 - 2014年9月30日、70,750部[192]
- 2014年10月1日 - 2015年9月30日、61,250部[192]
- 2015年10月1日 - 2016年9月30日、59,417部[192]
- 2016年10月1日 - 2017年9月30日、51,750部[192]
- 2017年10月1日 - 2018年9月30日、41,750部[192]
- 2018年10月1日 - 2019年9月30日、30,833部[192]
- 2019年10月1日 - 2020年9月30日、26,917部[192]
- 2020年10月1日 - 2021年9月30日、23,500部[192]
- 2021年10月1日 - 2022年9月30日、20,500部[192]
- 2022年10月1日 - 2023年9月30日、18,750部[192]
- 2023年10月1日 - 2024年9月30日、15,417部[192]
脚注
出典
- ^ a b c d e f g “Cheese!| 小学館AdPocket”. 小学館. 2024年9月24日閲覧。
- ^ a b c “枠にとらわれない発想で、まだ知られていない世界を漫画に。意外性が強みです。『Cheese!』菊池博和編集長インタビュー | 小学館AD POCKET”. 2025年4月6日閲覧。
- ^ a b 「CONTENTS」『少女コミックCheese!』1996年10月号、小学館、1996年。表紙より。
- ^ “祝・Cheese!25周年!「コーヒー&バニラ」朱神宝と「恋と弾丸」箕野希望が大ヒット“溺愛”少女マンガの舞台裏を明かす”. ナターシャ. (2021年7月21日) 2021年10月21日閲覧。
- ^ a b “新文化 - 出版業界紙 - 人事関連ページ”. www.shinbunka.co.jp. 2021年11月19日閲覧。
- ^ “auかんたん決済 presents 女性マンガ誌の編集長24名が選ぶ!今年完結したイチオシマンガ”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年12月20日). 2021年10月21日閲覧。
- ^ “「天まで昇る読後感」「脳バグ体験をぜひ!」くせ者揃いの28タイトル”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年1月30日). 2023年1月30日閲覧。
- ^ “生きづらさを無視したくない。ヒットを連発する少女マンガ編集者、畑中雅美のまなざし | キャリアハック(CAREER HACK)”. キャリアハック. 2021年11月19日閲覧。
- ^ “https://twitter.com/gamikossu/status/1580221306280480768”. Twitter. 2023年2月11日閲覧。
- ^ “商品や企業さんが作品に登場するのが、うちの雑誌ができる一番のタイアップです。『Cheese!』畑中雅美編集長インタビュー”. 小学館AD POCKET. 2023年6月27日閲覧。
- ^ “マンガ誌編集長が選ぶ、2020年のイチオシ作品”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年3月5日). 2021年5月8日閲覧。
- ^ a b “「煩悩パズル」の川上ちひろ、カッコいいけど最低な男子描く新連載をCheese!で”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年4月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “「ぼくの輪廻」の嶋木あこがフランス革命×オメガバース描く新連載、Cheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年3月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ a b “「名探偵コナン」サイン入りクリアカード8枚セットがCheese!に、湯町深の新連載も”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年4月24日). 2023年4月24日閲覧。
- ^ 「CONTENTS」『Cheese!』2025年4月号、小学館、2025年2月21日。目次より。
- ^ a b c d “コヒバニ深見さんの描き下ろしイラストが付録に、「37.5℃の涙」の椎名チカ新連載も”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年9月22日). 2023年9月22日閲覧。
- ^ “「王の獣」描き下ろしブロマイドがCheese!に、次号「コーヒー&バニラ」最終回”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年12月22日). 2023年12月22日閲覧。
- ^ a b 『Cheese!』2024年9月号、小学館、2024年7月24日。表紙より。
- ^ “警察官×キャバ嬢×マフィアの禁断ラブがCheese!で、朱神宝の新連載の試し読みも”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年10月24日). 2024年10月24日閲覧。
- ^ “「コーヒー&バニラ」の朱神宝が描く異世界溺愛ファンタジー、Cheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年11月22日). 2024年11月22日閲覧。
- ^ a b c “藤間麗「王の獣」約6年の連載に幕、つながる表紙の付録も 次号Cheese!には番外編”. コミックナタリー. ナターシャ (2025年1月24日). 2025年1月24日閲覧。
- ^ a b “Cheese!”. 小学館 (2023年9月22日). 2025年3月24日閲覧。
- ^ a b c 「CONTENTS」『Cheese!』2025年6月号、小学館、2025年4月24日。目次より。
- ^ “「深愛なるFへ」の七尾美緒が描く騙し合いラブコメがCheese!で開幕、「王の獣」全サも”. コミックナタリー. ナターシャ (2025年5月23日). 2025年5月23日閲覧。
- ^ a b 「CONTENTS」『少女コミックCheese!』1996年10月号、小学館、1996年。目次より。
- ^ a b “相原実貴「5時から9時まで」の本格連載スタート”. コミックナタリー. ナターシャ (2010年1月23日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ a b “椎名チカ&朱神宝がCheese!に、「黎明のアルカナ」は完結”. コミックナタリー. ナターシャ (2013年6月24日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b “桜田雛チーズで新作、自殺した少女のTwittterに事件の香り”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年2月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “「カノジョは嘘を愛しすぎてる」完結!大原櫻子、佐藤健ら記念コメントも”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年2月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b c d “ヒミツのアイちゃん完結、豪華プレゼントも”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年9月24日). 2024年7月24日閲覧。
- ^ a b “Cheese!の歌舞伎マンガ「ぴんとこな」完結、「5→9」石原さとみインタビューも”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年9月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “Cheese!1月号、宮坂香帆2本立てで「Real Kiss」復活”. コミックナタリー. ナターシャ (2009年11月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “「5時から9時まで」約10年の歴史に幕!柿原徹也演じるアーサー様の甘やかしドラマCDも”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年3月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “Cheese!にあらいきよこ前後編、次号新連載はロリコンもの?”. コミックナタリー. ナターシャ (2010年4月25日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “女子小学生が年上に恋、Cheese!新連載「お子様ぱーんち!」”. コミックナタリー. ナターシャ (2010年5月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “Cheese!15周年イヤー突入、2011年1月号は驚きの3D仕様”. コミックナタリー. ナターシャ (2010年11月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “車谷晴子、11歳少年描くショタコン新連載をCheese!で”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年3月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “あらいきよこ「ランウェイ☆WARS」、Cheese!で連載開始”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年4月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “水谷愛、Cheese!で新連載「ダメ恋みほん帖」開始”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年5月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “Cheese!で椎名チカ新連載、「カノ嘘」踊るMUSHペン付録”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年6月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “高宮智Cheese!で新連載、舞台は連続怪奇殺人が起こる町”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年7月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “音大女子がシェアハウス入居、堂本奈央のCheese!新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年8月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “わたなべ志穂のCheese!新連載、跡継ぎめぐる政略結婚もの”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年10月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “ドラマ「らんま1/2」を青木琴美が取材、Cheese!でレポ”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年11月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “七尾美緒のチーズ新連載、マンガ家と女性編集者の恋愛もの”. コミックナタリー. ナターシャ (2011年12月25日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ a b “藤原よしこのCheese!新連載、田舎娘とイケメンの出会い”. コミックナタリー. ナターシャ (2012年1月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “「さくら前線」のおおばやしみゆき、Cheese!で新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2012年5月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “高校教師が娘の恋愛にハラハラ、Cheese!で藤緒あい連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2012年6月23日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “宮坂香帆のCheese!新連載は、剣道部マネージャーの恋物語”. コミックナタリー. ナターシャ (2012年8月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ a b c “ドラマ「37.5℃の涙」撮影レポマンガがCheese!に、「あかいいと」は完結”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年7月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “「マンゴスチンの恋人」Cheese!別冊でコミカライズ”. コミックナタリー. ナターシャ (2012年9月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ 『Cheese!』2014年1月号、小学館、2013年11月22日。表紙より。
- ^ “花緒莉3年ぶりの読み切り&椎名チカ新連載がCheese!で”. コミックナタリー. ナターシャ (2012年10月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “「黎明のアルカナ」の藤間麗が4年ぶり新作読み切りを執筆”. コミックナタリー. ナターシャ (2012年12月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ a b “小説「100回泣くこと」Cheese!でコミカライズ開始”. コミックナタリー. ナターシャ (2013年2月24日). 2025年6月24日閲覧。
- ^ “「ぴんとこな」一筆箋がCheese!に、美しすぎる24枚綴り”. コミックナタリー. ナターシャ (2013年5月24日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b “七尾美緒&桜田雛のダブル新連載、Cheese!にてスタート”. コミックナタリー. ナターシャ (2013年8月25日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b c d “ヒミツのアイちゃんの花緒莉、男装もの新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年10月24日). 2024年7月24日閲覧。
- ^ “「黎明のアルカナ」の藤間麗、雪男イケメン兄弟描く新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2013年9月24日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b c d “七尾美緒がイケメンを操れる女子描く「式神男子」Cheese!で連載化”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年11月23日). 2024年7月24日閲覧。
- ^ “椎名チカが病児保育士を主役に家族描く新連載、Cheese!で”. コミックナタリー. ナターシャ (2013年10月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “椎名チカ「37.5℃の涙」TVドラマ化決定、新米の病児保育士が奮闘”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年5月23日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ a b “ドラマ化もされた「37.5℃の涙」Cheese!で完結、次号「恋と弾丸」最終回”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年5月24日). 2022年8月24日閲覧。
- ^ “Cheese!で映画「カノ嘘」特集、青木琴美×佐藤健対談など”. コミックナタリー. ナターシャ (2013年11月22日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b “湯町深の豹変男子&朱神宝のヤンキーもの、Cheese!で”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年2月24日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b c d “桜田雛描く超訳「源氏物語」など、Cheese!で新連載3作が同時に開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年4月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b “理系な眼鏡上司との恋描く新連載、Cheese!でスタート”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年4月24日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b c “桜田雛&朱神宝がCheese!でW新連載、「氷点」マンガ版も”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年6月24日). 2024年8月23日閲覧。
- ^ a b c “新境地の近代ロマンスなど、宮坂香帆3本立て&別冊付録がCheese!に”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年12月24日). 2024年7月24日閲覧。
- ^ a b “「後にも先にもキミだけ」の川上ちひろ新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2014年8月24日). 2024年7月24日閲覧。
- ^ “「煩悩パズル」最終回、川上ちひろ描くボス猿ヤンキー×メガネ女子のラブコメ”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年12月25日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b c “「5→9」“渋谷王子”役の長妻怜央がCheese!に登場、朱神宝は2本立て”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年11月27日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b c “「罪ふた」「キス、絶交、キス」などCheese!の名作1話を集めた別冊付録”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年1月25日). 2024年7月24日閲覧。
- ^ a b c “藤間麗がCheese!でファンタジー新連載、付録は「黎明のアルカナ」1巻”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年2月24日). 2024年7月24日閲覧。
- ^ “宮坂香帆「10万分の1」実写映画化!難病と闘う少女と彼女を支える男子描く”. コミックナタリー. ナターシャ (2018年9月22日). 2023年10月24日閲覧。
- ^ a b “やり直しラブ「モトカレ←リトライ」Cheese!で完結、次号「カノ嘘」最終回”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年1月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “「王の獣」描き下ろしブロマイドがCheese!に、次号「コーヒー&バニラ」最終回”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年12月22日). 2024年1月24日閲覧。
- ^ a b “Cheese!に「37.5℃の涙」出演者コメント掲載、「ぴんとこな」は完結間近”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年6月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b c “「ぴんとこな」の嶋木あこ、Cheese!で新連載!マンガから始まる恋物語”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年2月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “Cheese!にて宮坂香帆の新連載、前作「あかいいと」の莉乃&桐谷が主役”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年8月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “宮坂香帆「10万分の1」完結、木村良平演じる「水神の生贄」甘やかしドラマCDも”. コミックナタリー. ナターシャ (2018年8月24日). 2023年10月24日閲覧。
- ^ “「ぴんとこな」の嶋木あこ、Cheese!で新連載!マンガから始まる恋物語”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年2月24日). 2016年2月24日閲覧。
- ^ “七尾美緒がCheese!に“天才”描く新連載、おそ松さんICカードステッカーも”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年3月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “「B-PROJECT」コミカライズがCheese!で開幕!「コヒバニ」深見さん抱き枕も”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年5月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “桜田雛描く新連載は執事×令嬢の裏表&年の差ラブ、Cheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年6月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b “宮坂香帆の新連載、秘書課のドS上司×ポンコツ後輩によるオフィスラブ”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年7月22日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ “「キンプリ」Cheese!でコミカライズ始動、オバレ&エデロ新入生の軌跡を描く”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年8月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “「コーヒー&バニラ」ドラマCDがCheese!に、興津和幸&巽悠衣子が出演”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年6月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “湯町深の新連載がCheese!で始動、間違いから始まる“エロきゅん”ラブコメ”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年9月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b “「恋と弾丸」箕野希望の新連載はキザな殺し屋×追われるJK、Cheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年12月23日). 2022年12月23日閲覧。
- ^ “朱神宝×川上ちひろ×華谷艶の鼎談がCheese!に、浅野直之描き下ろしの付録も”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年11月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b “川上ちひろの新連載は神様に見初められる女子大生のラブ、「コヒバニ」は2本立て”. コミックナタリー. ナターシャ (2019年10月24日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ “「モトカレ←リトライ」の華谷艶、愛が重い男子×押しに弱い女子の新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年3月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “Cheese!に描き下ろし付録やこじらせ女子の新連載、次号コヒバニのドラマCDも”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年5月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “「カノ嘘」青木琴美が男子2人、女子1人の“直球ラブストーリー”描く新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年7月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ a b c d “青木琴美のラブミステリー「虹、甘えてよ。」完結、複製原画など当たる企画も”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年8月24日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b “ピアノ調律師の成長描く「羊と鋼の森」マンガ版がCheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年12月22日). 2023年10月24日閲覧。
- ^ a b “Cheese!で華谷艶&七尾美緒の新連載が開幕、宮坂香帆「10万分の1」は次号完結”. コミックナタリー. ナターシャ (2018年7月24日). 2023年10月24日閲覧。
- ^ “溺愛ラブ「宵の嫁入り」Cheese!で完結、安元洋貴が子猫と戯れるグラビアも”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年6月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “宮坂香帆の新連載は開港ラブロマンス、「10万分の1」映画化記念で無料配信も”. コミックナタリー. ナターシャ (2018年10月26日). 2023年10月24日閲覧。
- ^ a b c “柿原徹也&岡本信彦演じるCheese!男子の“語りかけドラマ”聴ける電話企画”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年4月24日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b c “各電子書店で1位獲得、若頭×女子大生の危険なラブストーリー「恋と弾丸」1巻”. コミックナタリー. ナターシャ (2019年2月26日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b “箕野希望「恋と弾丸」本編がCheese!で完結、実写ドラマ化も決定”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年6月23日). 2022年8月24日閲覧。
- ^ “「コーヒー&バニラ」“プロポーズ回”のドラマCDや披露宴招待状がCheese!に”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年6月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “「恋と弾丸」増田俊樹&伊藤かな恵のドラマCD第2弾、“桜夜の愛”イメージした香水も”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年5月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ a b c “「宵の嫁入り」七尾美緒×「王の獣」藤間麗コラボによる転生読み切りがCheese!に”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年9月24日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b “藤原えみの新連載やドラマ「恋と弾丸」対談、青木琴美新作などがCheese!に”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年10月24日). 2022年10月24日閲覧。
- ^ a b “相原実貴「5時から9時まで」のスピンオフ新連載が開幕、映画「10万分の1」特集も”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年11月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ 『Cheese!』2023年8月号、小学館、2023年6月23日。目次より。
- ^ a b “ピカチュウの便利なマルチケースがCheese!に、華谷艶&雨村澪の新連載も”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年12月23日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ 『Cheese!』2023年5月号、小学館、2023年3月24日。表紙より。
- ^ “Cheese!25周年!9月号に354Pの別冊付録が付属、100作が無料で読める電子フェアも”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年7月21日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ a b “「名探偵コナン」スタンド付きクリアカード3種がCheese!に、立てて飾れる”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年4月22日). 2022年4月22日閲覧。
- ^ “木村良平とKENNがあなたのためにシャンパンコール!Cheese!付録にドラマCD”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年8月23日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ 『Cheese!』2023年4月号、小学館、2023年2月24日。表紙より。
- ^ a b c d e f “恋愛体質JDとバツイチアラフォーの年の差ラブ、プレチーで移籍連載スタート”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年11月5日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ “「名探偵コナン」新一&コナンの100巻ご祝儀袋がCheese!に、新鋭の新連載も”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年9月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “吉野裕行&日野聡がシャンパンコール!Cheese!にドラマCD、七尾美緒の新連載も”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年11月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ “歌舞伎町で身体を売る少年が出会ったのは…現役高校生作家によるCheese!新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年1月24日). 2022年5月24日閲覧。
- ^ 『Cheese!』2022年10月号、小学館、2022年8月24日。目次より。
- ^ 『Cheese!』2023年3月号、小学館、2023年1月24日。目次より。
- ^ “元男子校で展開する七海月の同居ラブ「初恋のつづきは男子寮で」、「コヒバニ」付録も”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年7月23日). 2022年8月24日閲覧。
- ^ a b c d 『プレミアCheese!』2025年8月号、小学館、2025年7月4日。表紙より。
- ^ 『Cheese!』2023年10月号、小学館、2023年8月24日。表紙より。
- ^ 『Cheese!』2023年12月号、小学館、2023年10月24日、ASIN B0CKTT96L4。表紙より。
- ^ “Cheese!に描き下ろしウェディングカレンダー、「ねぇ先生、知らないの?」浅野あや新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年2月24日). 2023年2月24日閲覧。
- ^ 『Cheese!』2024年5月号、小学館、2024年3月23日。表紙より。
- ^ 「CONTENTS」『Cheese!』2024年7月号、小学館、2024年5月24日。目次より。
- ^ Cheese!編集部 2023年3月24日のツイート、2023年3月24日閲覧。
- ^ 「CONTENTS」『Cheese!』2024年4月号、小学館、2024年2月24日。目次より。
- ^ “「コーヒー&バニラ」描き下ろし単行本カバーが付録に、全員に当たるポストカードも”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年5月24日). 2023年5月24日閲覧。
- ^ a b 『Cheese!』2024年11月号、小学館、2024年9月24日。表紙より。
- ^ “「黒崎秘書に褒められたい」「薔薇と殺し屋」の描き下ろし付録と全サがCheese!に”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年6月23日). 2023年6月23日閲覧。
- ^ “「名探偵コナン」付録第2弾がCheese!に、「ヒミツのアイちゃん」花緒莉の新連載も”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年4月24日). 2024年5月24日閲覧。
- ^ a b c d “雨宿りぃの新連載がプレチーで開幕 花緒莉「恋は空から降ってくる」の移籍連載も”. コミックナタリー. ナターシャ (2025年5月2日). 2025年5月2日閲覧。
- ^ a b カノジョは嘘を愛しすぎてる SIDE STORY〜ボクとカノジョが出会う前の物語〜(カノジョは嘘を愛しすぎてる・サイドストーリー〜ボクとカノジョが出会う前の物語〜)テレビドラマデータベース、2023年7月17日閲覧。
- ^ “スタッフ”. 『37.5℃の涙』. TBS. 2024年10月24日閲覧。
- ^ a b “「5→9」収録現場ルポがCheese!に、山下智久インタビュー&ピンナップも”. コミックナタリー. ナターシャ (2015年10月24日). 2024年4月24日閲覧。
- ^ “「コーヒー&バニラ」リサは福原遥、深見に桜田通!黒羽麻璃央、小越勇輝らも出演”. コミックナタリー. ナターシャ (2019年6月14日). 2024年10月24日閲覧。
- ^ “ドラマ「ねぇ先生、知らないの?」馬場ふみかと赤楚衛二が寄り添うポスター解禁”. コミックナタリー. ナターシャ (2019年11月22日). 2024年10月24日閲覧。
- ^ “「社内マリッジハニー」追加キャストにDa-iCE和田颯ら、立石俊樹はオリキャラ演じる”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年10月28日). 2024年10月24日閲覧。
- ^ “「モトカレ←リトライ」に吉田仁人・中村里帆・えなこ・本多力・眞島秀和が出演”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年3月23日). 2024年10月24日閲覧。
- ^ “ドラマ「恋と弾丸」に黒羽麻璃央、中村静香、木村慧人、大澄賢也ら9人”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年9月16日). 2024年10月24日閲覧。
- ^ “ドラマ「ヒミツのアイちゃん」愛子役は平祐奈、玲欧役は佐藤寛太”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年12月19日). 2024年10月24日閲覧。
- ^ “カノジョは嘘を愛しすぎてる”. 映画.com. エイガ・ドット・コム. 2024年10月24日閲覧。
- ^ “10万分の1”. 映画.com. エイガ・ドット・コム. 2024年10月24日閲覧。
- ^ a b “Cheese!増刊号がリニューアル、付録に「5時9時」「カノ嘘」ステッカーも”. コミックナタリー. ナターシャ (2016年5月11日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b チーズ!編集部 2018年7月5日のツイート、2022年1月5日閲覧。
- ^ a b “プレミアCheese!”. 小学館. 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b c d e f g “「ヒミツのヒロコちゃん」がプレチーで完結、12月号には「ヒミアイ」番外編”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年9月5日). 2022年9月5日閲覧。
- ^ a b c d 『プレミアCheese!』2023年8月号、小学館、2023年7月5日。表紙より。
- ^ “ギャル令嬢と老舗御曹司によるハイテンションラブコメ、プレチーで開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年1月5日). 2024年3月5日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2025年10月号、小学館、2025年9月5日。表紙より。
- ^ a b “「恋と弾丸」の箕野希望が描く“史上最強の極道の娘”の物語、プレミアCheese!に”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年3月5日). 2024年3月5日閲覧。
- ^ a b “歯学部男女の少しエッチな新連載がプレチーで、ご機嫌女子との青春ラブコメも始動”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年5月2日). 2024年5月2日閲覧。
- ^ a b “川上ちひろが描く和風ファンタジーラブ「巫の婿探し」がプレミアCheese!で連載化”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年11月5日). 2025年1月4日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2025年2月号、小学館、2025年1月4日。表紙より。
- ^ a b c d e 『プレミアCheese!』2025年4月号、小学館、2025年3月5日。表紙より。
- ^ “泣きながらかき鳴らすベース!天才と鬼才の青春譚、プレミアCheese!で始動”. コミックナタリー. ナターシャ (2025年9月5日). 2025年9月5日閲覧。
- ^ “「煩悩パズル」「モトカレ←リトライ」の特別編がプレミアCheese!に”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年3月5日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ “「故意ですが恋じゃない」の浅野あやが描く危険な恋、プレミアCheese!で開幕”. コミックナタリー (2017年1月5日). 2017年1月6日閲覧。
- ^ “生後6カ月の自分を育てて人生やり直し?わたなべ志穂の新連載がプレチーで”. コミックナタリー. ナターシャ (2017年7月5日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2021年4月号、小学館、2021年3月5日。表紙より。
- ^ “冴えないマンガ家とイケメン美容師のラブストーリー、プレミアCheese!で”. コミックナタリー. ナターシャ (2018年11月5日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b ““普通”じゃない恋のトライアングル、プレチー新連載「ないものねだりの恋たちは」”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年5月1日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ “「宵の嫁入り」の七尾美緒、プレチーで“お猫さま”との日常描くエッセイ”. コミックナタリー. ナターシャ (2019年5月2日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2022年8月号、小学館、2022年7月5日。目次より。
- ^ “「コーヒー&バニラ」の朱神宝、甘えたがりな彼氏とその彼女描く新作読切”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年7月4日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2021年12月号、小学館、2021年11月5日。表紙より。
- ^ a b “年下、憧れの先輩…スターに溺愛される新連載2本、プレミアCheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年9月4日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b “ハイスペマンションオーナー×お家大好きミーハー女子の新連載がプレミアCheese!で”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年7月5日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ “男勝りJKが恋に目覚める「ヒミツのアイちゃん」ドラマ化、来春に配信開始”. コミックナタリー. ナターシャ (2020年11月5日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ “再会した初恋の少年は意外な姿で…川上ちひろの新連載がプレミアCheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2021年1月4日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b “亡くした夫、“わがまま”な義兄…喪失から始まる禁断の恋、プレチーで始動”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年1月5日). 2023年1月5日閲覧。
- ^ 『プレミアCheese!』2021年2月号、小学館、2021年1月4日。表紙より。
- ^ 『プレミアCheese!』2025年6月号、小学館、2025年5月2日。表紙より。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2021年6月号、小学館、2021年5月1日。表紙より。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2024年10月号、小学館、2024年9月5日。表紙より。
- ^ 『プレミアCheese!』2021年6月号、小学館、2021年5月1日。目次より。
- ^ a b c d 『プレミアCheese!』2023年4月号、小学館、2024年3月3日。表紙より。
- ^ “嫌われ魔女が過去の自分に転生し人生やり直し、プレミアCheese!で新鋭の新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年1月5日). 2022年1月5日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2024年12月号、小学館、2024年11月5日。表紙より。
- ^ 「恋を知らずに、愛を売る Night7 特別」『プレミアCheese!』2023年10月号、小学館、2023年9月5日、337頁、ASIN B0CGB4WHSG。
- ^ a b “初恋を10年こじらせたヒロイン&レトロな喫茶店が舞台のラブコメ、プレチーでW新連載”. コミックナタリー. ナターシャ (2022年11月5日). 2022年11月5日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2024年2月号、小学館、2024年1月5日。表紙より。
- ^ a b “2000億円を賭けた後継者レース&夢追う女子の新生活、プレミアCheese!で開幕”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年5月2日). 2023年5月2日閲覧。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2024年6月号、小学館、2024年5月2日。目次より。
- ^ a b 『プレミアCheese!』2024年8月号、小学館、2024年7月5日。目次より。
- ^ “私が愛するのは、幼なじみ2人…純愛が交錯する禁断ラブ「ごめん、ふたりを愛してる」”. コミックナタリー. ナターシャ (2023年9月5日). 2023年9月6日閲覧。
- ^ 花菜ミツキ「高澤先輩が怖すぎる シフトEND」『プレミアCheese!』2024年10月号、小学館、2024年9月5日、411頁。
- ^ “リサと深見さんが高校生に?「コーヒー&バニラ」“もしも”の番外編がプレチーに”. コミックナタリー. ナターシャ (2024年9月5日). 2024年11月5日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 日本雑誌協会JMPAマガジンデータによる1号当たり平均部数。
外部リンク
チーズ(ost)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 09:02 UTC 版)
デンマークは美味しいチーズで知られている。朝食や昼食のサラダの一部として、または夕食後のデザートとしてクラッカーやワインと共にostebord やostetallerken (チーズテーブルまたはチーズプレートの意味)という名前で供される。 デンマークで伝統的な一般に食べられるチーズ(skæreost)は口当たりがよいが、デンマーク料理で使う刺激の強いチーズもある。いくつかは非常に匂いがきつい。ブルーチーズは非常に刺激が強く、デンマークのチーズ製造業者は成形チーズを、非常に口当たりが良くクリーミーなものから、国際的にデンマークと関連する強烈に青い繁殖麺があるものまで作っている。もうひとつの刺激の強いチーズには、長期熟成した刺激のある熟成チーズのブランド、Gamle Ole (「Oleおじいさん」、Oleは男性名)がある。非常に刺激的であり、ラードを塗ったデンマークのライ麦パン、rugbrødの上にタマネギの薄切りと肉の煮凝り(sky)と一緒にのせて供されることが多い。この刺激の強いチーズは、ラム酒に浸して供することもある。 刺激の強いチーズはデンマーク人が習得した味覚でもある。匂いを感じた年配のデンマーク人は、冷蔵庫の中でプラスチック容器に密封されていることから、Gamle Ole の匂いは家中に広がるという冗談を言う。物事が非常に正しいことを語るときに、Gamle Ole の刺激を示し、「それは匂う」と言うことがある。「何か匂う」または「Gamle Ole の匂い」と言うこともある。 デンマークはギリシャとの長い法廷闘争に敗れ、調整乳を使用して製造したデンマーク産チーズは「フェタ」と名乗れなくなった。2002年7月以降、フェタは原産地名称保護制度(PDO)対象となり、欧州連合においてフェタはギリシャ産の羊あるいは山羊の乳で作るものに限定された。欧州連合の判断により、デンマークの乳製品メーカー、アーラ・フーズ(ダンボー (Danbo) も製造)は、フェタ製品をApetina に改称した。 デンマーク産のチーズの幾つかは次の通り: ダナブルー (Danablu) :刺激の強いブルーチーズ ブルー・キャステロ (Castello) エスロム (Esrom) ダンボー (Danbo) ハバティー (Havarti) :セミハードのデンマーク産牛乳チーズで、19世紀中頃に最初に製造した試験農場にちなんで名付けられた。 デンマーク産フェタ スモークチーズ:クミンの風味がするフュン島の特産であり、ラディッシュとライ麦パンと共に供される。
※この「チーズ(ost)」の解説は、「デンマーク料理」の解説の一部です。
「チーズ(ost)」を含む「デンマーク料理」の記事については、「デンマーク料理」の概要を参照ください。
チーズ
出典:『Wiktionary』 (2021/06/20 11:10 UTC 版)
名詞
チーズ
語源
発音(?)
- ち↘ーず
類義語
語義1
関連語
翻訳
- アフリカーンス語: kaas
- アラビア語: جبنة (júbna) 女性
- アゼルバイジャン語: pendir
- ブルガリア語: сирене (sirene) 男性
- ベンガル語: (ponir)
- ブルトン語: keuz 男性, formaj 男性
- ボスニア語: sir 男性
- カタルーニャ語: formatge 男性
- クリミア・タタール語: eremçek, sır
- チェコ語: sýr 男性
- ウェールズ語: caws 男性
- デンマーク語: ost
- ドイツ語: Käse 男性; Kas 男性
- ギリシア語: τυρί (tyrí) 中性, τυρός (tirós) 男性
- 英語: cheese
- エスペラント: fromaĝo
- スペイン語: queso 男性
- エストニア語: juust
- ペルシア語: پنیر (pænīr)
- フィンランド語: juusto
- フランス語: fromage 男性
- 西フリジア語: tsiis
- グアラニ語: kesu
- ヘブライ語: גבינה (gviná) 女性
- ヒンディー語: पनीर (panīr) 男性
- クロアチア語: sir 男性
- ハンガリー語: sajt
- アルメニア語: պանիր (panir)
- インターリングア: caseo
- インドネシア語: keju
- イタリア語: formaggio 男性, cacio 男性
- カザフ語: ірімшік (irimşik)
- 朝鮮語: 치즈,치이즈 (chiijeu)
- クルド語: پهنیر
- ラテン語: caseus 男性, formaticum 中性
- ラトヴィア語: siers 男性
- モンゴル語: бяслаг (byaslag)
- オランダ語: kaas 男性
- ノルウェー語: ost 男性
- オック語: formatge 男性
- ポーランド語: ser 男性
- ポルトガル語: queijo 男性
- ルーマニア語: brânză 女性, caş 中性
- ロシア語: сыр (syr) 男性
- ルワンダ語: ifromaje
- スロヴァキア語: syr 男性
- スロヴェニア語: sir 男性
- アルバニア語: djathë 女性
- セルビア語: сир 男性
- スウェーデン語: ost 通性
- トルクメン語: peýnir
- タガログ語: keso
- トルコ語: peynir
- ウイグル語: pixlak̡, sir, irimqik
- ウクライナ語: сир (syr) 男性
- ウルドゥー語: پنیر (panīr) 男性
- ウズベク語: pishlok, sir
- 中国語: 乾酪/干酪, 奶酪, 乳酪, (台湾)起司, 起士, (広東)芝士
「チーズ」の例文・使い方・用例・文例
- このワインの方がそのチーズには合うよ
- チーズバーガー
- チーズは牛乳から作られる
- チーズ1切れ
- チーズ2個
- チーズは消化するのに時間がかかる
- 持ち帰りでチーズバーガー2個下さい
- チーズを3つに均等に分ける
- このチーズは変な味がする
- チーズ1切れ
- 粉チーズをスパゲッティにふりかける
- 純血種のマルチーズ
- チーズの精選品
- フランスのレストランはオードブル,主コース,チーズ,ワインとパンを含む定食を出します
- チーズの厚切り1枚
- このチーズはいやなにおいがする
- スーはクラッカーにチーズスプレッドをつけたものをパーティーに出した
- 動かないで,ハイ,チーズ
- 私は味の強いチーズは好きではありません
- カマンベールチーズと野菜を好みの大きさに切る
Weblioカテゴリー/辞書と一致するものが見つかりました。
- チーズ一覧 - 日本マイセラ
チーズと同じ種類の言葉
- チーズのページへのリンク







































