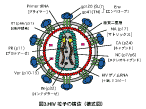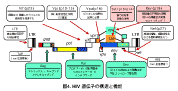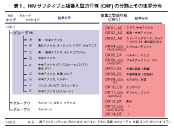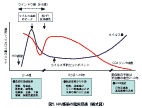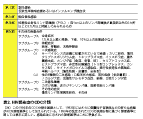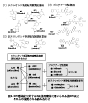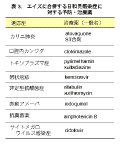|
後天性免疫不全症候群(acquired immunodeficiency syndrome, AIDS, エイズ)はヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus ;HIV)感染によって引き起こされ、重篤な全身性免疫不全によって特徴づけられる疾患であり、高い発症率・死亡率と予防・治療の難しさから、人類が直面する最も深刻な医療問題の一つとなっている。累積感染者数は世界で6,000万人、死者は2,000 万人を超え、中世の黒死病流行に例えられる未曾有の規模の世界流行が進行している。感染症法においては4 類感染症全数把握疾患に定められており、診断した医師は7日以内に保健所を通じて都道府県知事に報告する義務がある(註:その後、2003年11月施行の感染症法一部改正により、5類感染症全数把握疾患に変更)。
はじめに
エイズは1981年に米国で、男性同性愛者にカリニ肺炎やカポジ肉腫など通常まれな日和見感染や腫瘍をもたらす極めて致死性の高い疾患としてはじめて報告された。その後1983 年に、病原体としてレトロウイルスに属するHIV が分離・同定された。HIV はCD4 とよばれる細胞膜蛋白質を受容体として細胞に感染する性質をもつため、細胞性免疫を統御する中枢細胞であるCD4 陽性のヘルパーT細胞やマクロファージに感染し、破壊する。そのため、細胞性免疫の著しい機能低下が起こり、全身性の免疫不全状態が引き起こされ、様々な日和見感染症や日和見腫瘍、中枢神経障害など多彩で重篤な全身症状が起こる。適切な治療が行われなかった場合の予後は2 ~3年である。しかし、ここ1995 年以来の治療薬の進歩には目をみはらせるものがあり、先進国におけるHIV 患者の死亡率や日和見感染の発生率を低下させ、HIV 患者の予後は大きく改善している。
さて、エイズの流行は70年代半ばに中央アフリカ地域に始まったと推定されているが、80年代に入ってカリブ海、欧米、ラテンアメリカ諸国に、ついで80 年代末~90 年始めには南・東南アジア諸国、さらに90年代半ばに入ると東欧、中国などの諸地域において急激なHIV 流行が起っている。2001年末の時点で全世界で6,000万人におよぶ感染者が発生し、すでに2,000万人以上もの人々がエイズが原因で亡くなっているものと推定される。
昨年(2001年)6月は、米国CDC 発行のMMWR 誌上に、エイズの最初の症例(5人の同性愛男性のカリニ肺炎症例)が報告されてからちょうど20年目に当たり、国連ではエイズ特別総会が開催された。この会議で世界エイズ・結核・マラリア基金の創設が決議され、エイズ・結核・マラリアという人類に対する大きな脅威となっている感染症に対する地球規模での取り組みへの強い決意がうたわれた。しかし、その克服にはなお多くの課題が残されている現状にある。
疫 学
国連エイズ合同計画(UNAIDS)による推計によれば、2001 年末の時点で、HIV 感染者(生存者)総数4,000万人(うち15 歳以下が300 万人)、年間感染者発生数は500 万人と推定されている。これらの数値は、世界の総人口(約60億人)の約150人に1人が感染していること、また、一日当たり14,000 人-実に6 秒当たり1人-の新たな感染者が発生していることを意味している。一日当たりの新規感染者数14,000人のうち、95%以上が開発途上国で、2,000 人が15 歳以下の小児である。成人の感染者のほぼ50%が女性、15~49 歳の感染者の約半数が15 ~24 歳の若年層と推定されている。地域別にみると、サハラ以南のアフリカ地域(感染者2,850 万人)と南・東南アジア(560万人)がもっとも深刻で、両地域で世界全体の感染者の85%を占める(図1)。また、昨年度(2001年)1年間のエイズ死亡者は300 万人、流行が開始して以来の累積エイズ死亡数は約2,500万人と推定されている(推計2,480 万人)。アフリカのいくつかの国々では、エイズの流行によって平均余命が60 歳から40 歳にまで減少し、一つの国の存否を左右するほどの深刻な社会・経済問題を引き起こしている。
一方我が国においては、厚生労働省エイズ動向委員会報告によると、2001年12月31日現在、HIV 感染者報告(届出)総数は、4,526 件(男性3,085 件、女性1,441件)、エイズ患者の届出総数は2,248 件(男性1,928件、女性320件)である。2001 年5月31日現在の血液凝固因子製剤による感染者は1,431 名(生存中の患者167名、累積死亡者536 名を含む)である。HIV の年間報告数は1992 年のピーク後一旦減少したが、1996 年以降再び増加傾向が続いている(図2)。2001年は過去最高の新規感染者数621(男534、女87)を記録した。従来凝固因子製剤によるものが感染者の大多数を占めていたが、現在では、異性間(44%)および同性間の性的接触(32%)による感染が主体となっている。また、日本人感染者の大半が国内感染(80%)である。さらに、ここ数年の傾向として10 ~20 歳代の若年層の感染者の増加傾向が指摘されており、近い将来我が国においても若年層を中心にHIV 感染が急増する可能性がある。その一方で保健所における抗体検査の依頼件数はむしろ減少しており、我が国のHIV 感染に対する意識の低さは危機的ですらあると憂慮される。
我が国は諸外国に比べて感染者数は少ないが、HIV 感染の無症候期で検査を受けていない数を考慮すると、実際の感染者はもっと多いことが予想される。HIV 感染者数の実態を正確に把握することは難しいが、厚生省「HIV 感染症の疫学」班(班長 木原正博教授)報告によれば、98年末の時点で約8,000人、2003 年末で16,000人という将来予測がなされている。
[話題1 -HIV とエイズ流行の起源]
HIV の起源に関しては、霊長類を自然宿主とするサル免疫不全ウイルス(simian immunodeficiency virus, SIV)のヒトへの伝播(ズーノーシス=人獣共通感染症、zoonosis)によるとする有力な証拠が集積しつつある。HIV‐2 についてはスーティーマンガベイを自然宿主であるSIV SM に由来することが確証されていた(両ウイルスだけがvpx 遺伝子という特異的な遺伝子を共有し、系統樹上密接な関係がある)が、さらに、最近HIV‐ 1 がチンパンジーのもつSIV CPZ に由来するとする有力な証拠が提出されている。狩猟の際の血液との接触、創傷からの感染、屠殺した霊長類の生肉摂取などがヒトにおける流行発生の契機になったと考えられている。また、HIV 流行の主体となっているHIV‐1グループMが生まれたのは、最近の解析の結果、20世紀初頭の高々100年程度の極く最近の出来事であることが明らかにされている。
エイズ流行のシナリオは次のように考えることができよう。エイズは1960年~70年代より中央アフリカ地域の密林で風土病的に存在したと考えられ、当時「スリム病」と呼ばれた著しい「るいそう(極度の痩せ/栄養不良状態)」によって特徴づけられる疾患群の中に、現在でいうエイズが含まれていたと推測されている。当時は病気は外界とは隔離されていたが、中央アフリカ地域の長年にわたる戦乱による難民化-農村部の疲弊、交通機関・道路網の発達、経済活動の急速な発展に伴う急激な人々の移動、また、売春・不特定多数の性的パートナーと性的接触(promiscuity)といった様々な社会的・経済的要因が絡まりあって、急速に世界に広まったと考えられる。とりわけ1980 年に入って、極めて活発でしかも多数の性的パートナーとの性行動を行う欧米の同性愛者間に急速に拡がり、これがエイズとよばれる疾患単位が認識されるきっかけとなった。またこれに前後して、欧米の薬物乱用者(injecting drug user, IDU)の集団で、同じ注射器を用いての薬物の回し打ち(ニードル・シェアリングneedle‐sharing )によって爆発的に流行が拡大した。1988 年に入ると、これまでエイズ流行の兆候のなかったアジア地域、特にタイ・インドでIDUs の間や売春・不特定多数のパートナーとの性的接触によって爆発的な流行が発生し、現在、これらの地域はアフリカに次ぐ最も深刻な流行地の一つとなっている。さらにごく最近は、薬物乱用者を中心とした東欧・旧ソ連圏や中国などでの新興流行(emerging epidemic, エマージング・エピデミック)が注目されている。
病原体
|
|
|
エイズの病因となる病原体は、レトロウイルス科のレンチウイルスに属するヒト免疫不全ウイルス(human
immunodeficiency virus, HIV)である。このウイルスは、1983 年にフランス・パスツール研究所のルック・モンタニエ(Luc
Montanier)らのグループによって発見された。
|
|
図3.
HIV 粒子の構造(模式図)
HIV 遺伝子とウイルス粒子構成タンパク質との関係を上に示す。ウイルス粒子内部の砲弾型のキャプシド構造内に約9,500
ヌクレオチドからなる(+)鎖ゲノムRNA が2 コピー含まれる。エンベロープ蛋白質は3 量体構造をもつ。
|
図4.
HIV 遺伝子の構造と機能
HIV 遺伝子は、gag, pol, env の3 個の主要な構造遺伝子とvif
, vpr, vpu (HIV‐1 とSIVCPZ だけがもつ)あるいはvpx (HIV‐2 とSIVSM がもつ),
tat , rev, nef の6 個の調節遺伝子から構成され、複雑で精妙な遺伝子発現調節機構によって制御されている。tat,
rev は2 つのエキソンからなる。TAR 及びRRE RNA 領域はそれぞれトランス活性化因子Tat とRev の結合サイト。
|
HIV は直径110nm のRNA 型エンベロープウイルスで、約9,500塩基からなる2 コピーのRNA ゲノム、逆転写酵素などを含む砲弾型のコア(キャプシド)と、それを取り囲む球状エンベロープによって構成される(図3)。ウイルス粒子の外側を構成するエンベロープには、外側に突き出している糖タンパク質gp120と脂質二重膜を貫通する糖タンパク質gp41からなるスパイクがある。エンベロープタンパク質は、ヘルパーT 細胞やマクロファージ表面膜に存在するCD4 分子に対する特異的な結合活性をもち、ウイルスが標的細胞に感染・侵入する過程で重要な役割を果たす。HIV 遺伝子は、両端に存在する転写開始や逆転写・組み込み反応に重要なLTR (long terminal repeat)とよばれる遺伝子領域と、gag, pol, env の3 つの主要な構造遺伝子、tat, rev などの6種の調節/アクセサリー遺伝子からなる極めて複雑な構造と機能をもつ(図4)。
HIV の感染には、CD4 の他にCD4 と協同してウイルスの細胞内侵入を促進する補助因子(コレセプター)が必要である。HIV‐1のコレセプターは長い間謎であったが、1996 年になって、ケモカイン(炎症性サイトカイン)受容体のCXCR4 とCCR5 であることが同定された。HIV は、CD4 およびCXCR4 あるいはCCR5 を受容体として、それらを発現しているヘルパーT 細胞やマクロファージに感染し、その結果として細胞性免疫機構を破綻に至らせる。
また、コレセプター利用能の差異を指標としてHIV の機能的分類がなされている。CXCR4 をコレセプターとして利用するものをX4 ウイルス、CCR5 を利用するものをR5ウイルス、両者を利用する能力をもつものをR5‐ X4 ウイルスと呼ぶ。それらは、ウイルスの細胞指向性に基づく分類によるT細胞株指向性、マクロファージ指向性、二重(T 細胞株とマクロファージの両)指向性ウイルスにほぼ対応する。R5 ウイルスは、ヒトからヒトへの感染と感染個体内での持続感染の成立に関与する最も重要なウイルスと考えられる。一方、X4 ウイルスやR5‐X4 ウイルスは感染後期に出現し、急速なCD4 陽性T 細胞数の低下の原因の一つではないかと考えられている。R5‐X4 ウイルスは細胞障害性の強いウイルスで、CCR5 とCXCR4 以外にもCCR3 やCCR2 など他のケモカイン受容体もコレセプターとして利用する能力をもつ場合があり、発症期の中枢神経症状など多彩で重篤な臨床像と関係している可能性がある。
なお、CXCR4 およびCCR5 を受容体とするケモカインであるSDF‐1(stroma cell derived factor‐1)およびRANTES, MIP‐1 α, MIP‐1 βはそれぞれ、X4 ウイルスおよびR5ウイルスの感染を特異的に阻害する。これらの性質は、CXCR4 やCCR5 がHIV‐1の感染に必須の補助因子であることを裏づける重要な証拠の一つとなった。
[話題2 -HIV 分類の新基準]
HIV は血清学的・遺伝学的性状の異なるHIV-1 とHIV-2 に大別される(表1)。
世界流行の病因となっているHIV-1 は、遺伝学的系統関係からグループM (Major), O(Outlier)およびN (non-M/non-O)の3群に大別される(表1)。このうち、グループM は最も主要な系統で、さらにサブタイプA‐D, F‐H, J, K の9 サブタイプに分類される。これらサブタイプの他に、世界流行を駆動する動因として、これらサブタイプ間の組換えウイルスが重要な役割を果たしていることが明らかにされている。これが組換え型流行株(circulating recombinant form, CRF)と呼ばれるもので、現在までに14 種のCRF が報告されている。CRF は発見の順番を示す番号と、下線の後にそれを構成するサブタイプ名(3 つ以上のサブタイプからなる場合は一律cpx として示す)を組み合わせて表示される(表1)。CRF01_AE はこれまでサブタイプEと呼ばれたウイルス株で、タイを中心とする東南アジア地域に広範に分布する代表的な組換え型流行株である。このような多様なサブタイプの存在やサブタイプ間のモザイク-組換え現象は、HIV-1 が多様性やそのfitness(適応性)を増す戦略の一つとなっていると考えられる。
我が国では、HIV 感染者の約75%がサブタイプB で、約20%がCRF01_AE 、残り数%がサブタイプC, F, A, Dなどである。サブタイプB は欧米に広く拡がっているウイルス株で、我が国では、非加熱血液製剤によるいわゆる「薬害エイズ」患者や男性同性愛患者のほとんどがこのタイプのウイルスの感染者である。一方、異性間の性的接触による感染者の間では、サブタイプBと東南アジアに由来するCRF01_AE が多く見られる。90年代に入るまで、我が国の感染者はほとんど例外なく欧米に広く分布するサブタイプB であったが、91~92 年以降CRF01_AE が主に性感染のルートを介して拡がりつつある。表1にHIV のサブタイプ分類とその世界分布を示す。また図1には、2001 年末の大陸別HIV 感染者(含むAIDS 患者)生存者推計数、および新規の年間感染者数(WHO/UNAIDS 推計)に加え、HIV サブタイプおよびCRF の世界分布を示す。
サブタイプ分類が可能となった結果、世界における流行株の起源、系統関係が整理され、ウイルス流行の様相をより実体的に把握することが可能になってきた。しかし、サブタイプの違いが、病原性や感染効率(性感染や母子感染)の差異などのウイルスの生物学的性質にどのように関連するかは明らかではない。
(国立感染症研究所エイズ研究センター 武部 豊)
|
 全ての辞書から後天性免疫不全症候群
を検索
全ての辞書から後天性免疫不全症候群
を検索