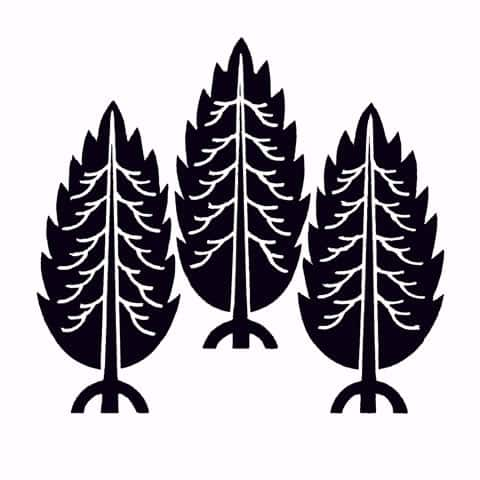さん【▽杉】
すぎ【杉/×椙】
スギ

| 本州、四国、九州に分布する日本の代表的な樹種の一つです。最近では、天然生のものは少くなり、それはほとんどが人工造林されたものです。天然のスギの産地として、現在でも、しばしば話題になる地域に秋田地方(アキタスギ)、屋久島(ヤクスギ)などがあります。古くから造林され、北海道南部以南の日本全土にスギの林が見られ、そのうちでも吉野、尾鷲、天竜、日田、飫肥、智頭などの各地方はスギの産地として有名です。 ■木材 ■用途 |
すぎ 【杉・椙】
スギ
すぎ (杉)
杉
杉
杉
杉
杉
杉
杉
杉
杉
杉
杉
杉
スギ
(杉 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/26 06:47 UTC 版)

| スギ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
||||||||||||||||||||||||
| 保全状況評価[1] | ||||||||||||||||||||||||
| NEAR THREATENED (IUCN Red List Ver.3.1 (2001)) |
||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||||||||
| 属: Cryptomeria D.Don (1839) |
||||||||||||||||||||||||
| シノニム | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||||||||
| スギ(杉[7]、椙[7]、倭木[7][8]、須疑[9])、マキ(真木[10]、槙[11]、槇[12])[注 3] | ||||||||||||||||||||||||
| 英名 | ||||||||||||||||||||||||
| Japanese cedar[7], Japanese redwood[13] | ||||||||||||||||||||||||
| 下位分類 | ||||||||||||||||||||||||
スギ(杉、椙、学名: Cryptomeria japonica)は、裸子植物マツ綱のヒノキ科[注 2]スギ属に分類される常緑高木になる針葉樹の1種である(図1)。スギは、スギ属の唯一の現生種とされることが多い。大きなものは高さ60メートルになり、日本自生の木の中で最も大きくなる種とされる。樹皮は赤褐色で縦に細長く裂ける。葉は鎌状針形、枝にらせん状につく。"花期"は早春、球果はその年の秋に熟す。成長が速く、比較的長命である。本州(青森県鰺ヶ沢町以南)、四国、九州(屋久島以北)に自生し、北海道道南や青森県南部地方など自生地以外を含めて国内外で植栽されている(→#分布)。日本固有種とされることもあるが、中国南部のもの(カワイスギ)も自生とされる。日本の太平洋側と日本海側のスギでは形態的・生態的・遺伝的差異があり、それぞれオモテスギ、ウラスギとよばれる(→#分類)。
「スギ」の名は「すぐ(まっすぐ)」に由来するとされることが多いが、諸説ある(→#名称)。日本では最も広く植林されている樹種であり、その面積は日本の人工林の45%、全森林の18%に達する(→#植林)。日本国内には多数の産地があり、北山杉のように、ふつうその産地名を冠してブランド化されている。材は、建築、家具、樽、土木などに広く利用されている(→#木材)。そのほかにも屋根、線香、杉玉など樹皮や枝葉が利用されることもあり(→#樹皮・枝葉などの利用)、また観賞用に植栽されることもある(→#観賞用)。古くから神社などに植栽され、神木とされているものや天然記念物に指定されているものも多い(→#文化、#天然記念物)。スギは早春に大量の花粉を散布し、日本では花粉症の主な原因となっている(→#スギ花粉症)。
名称
「スギ」の名は、真直ぐに成長する木、「直木(すぐき)」に由来するとされることが多い(貝原益軒『大和本草』、新井白石『東雅』など)[15][14][17]。ただし、古代において「直(すぐ)」の読みはなかったことから、この説は後世の付会ともされる[17]。その他の説として、成長が速い「すくすく育つ木」(「すくすく」という擬態語は古代からあった)に由来するとする説(『大言海』など)、上へ進み上る「進木 (すすき)」に由来するとする説(本居宣長『古事記伝』など)、「ス(細く痩せた)木」に由来するとする説(狩谷掖斎『箋注倭名類聚抄』など)がある[17]。
漢字の「杉」は、日本ではスギのことを指すが、もともと中国ではコウヨウザン(ヒノキ科)のことを指し、中国ではスギは「柳杉」とよばれる[7]。またスギは「椙」とも表記されるが、これは日本の国字である[18]。
スギは、古くは「マキ(真木、槙、槇)」ともよばれた[14]。マキは良い木、立派な木のことであり、スギのほかにコウヤマキ(コウヤマキ科)、イヌマキ(マキ科)、ヒノキ(ヒノキ科)を意味することもある[11][12][10]。
日本ではスギは代表的な針葉樹であるため、系統的にスギに近縁ではない針葉樹が「…スギ」と名付けられた例があり、レバノンスギやヒマラヤスギ(マツ科)、ナンヨウスギ(ナンヨウスギ科)などがある[19]。また、その外形などがスギに似ている植物に「スギ」が付されていることもあり、スギゴケ(スギゴケ科)やスギラン、マンネンスギ(ヒカゲノカズラ科)、スギナ(トクサ科)、クサスギカズラ(キジカクシ科)、ミズスギナ(ミソハギ科)、スギナモ(オオバコ科)などがある[20]。また、アズキナシ(バラ科)をカタスギと呼ぶこともある[21]。スギノリ(杉海苔)は、スギの樹形のような形をした真正紅藻綱に属する海藻である[22]。
特徴
常緑高木となる針葉樹であり、高さは15–40メートル (m)、大きなものは樹高40–60 m、幹の直径 4–5 m になる[23][24][16][7][25]。日本自生の木の中では、最も大きくなる種とされる[19]典型的にはまっすぐ伸びた明瞭な主幹をもつが(図1, 2a, c)、基部付近で分岐して株立ちするものもある[7](下図2b)。樹冠はふつう円錐形であるが、古くなると円形になる[7][19]。樹皮は赤褐色から褐色、縦に細長く裂けて剥がれる[16][7][15][26](下図2c)。若い枝はふつう斜上するが、古くなると垂れ下がる[16][14]。小枝はふつう垂れ下がり、無毛[27][14][28]。
葉は先端が尖った鎌状の針形、長さ4–20ミリメートル (mm)、無毛、枝に対して15–45°の角度でらせん状について密生している[26][7][16][29][27](下図3)。葉の基部は茎に沿下し、関節がないため落葉せず、枯れると小枝ごと落ちる[7][16][14]。個々の葉は4–6年ほど樹に付いていると推定されている[30]。葉の横断面はひし形、4面に2–8列の気孔があり、中心に葉脈の維管束が1個あり、その下側に1個の樹脂道が存在する[7][27]。冬季には短い葉が密生して芽を保護しているため、枝についている葉の大きさが一年ごとに短くなっている[15]。冬には葉が赤褐色になり(下図7b)春に緑色に戻るものが多いが、冬に黄色になるものや冬の間も緑色を保つものもいる[24][14][29][31]。
雌雄同株、"花期"は2月から4月だが[24][16][7][32](下図4a)、雄球花("雄花")と雌球花("雌花")は前年の夏頃から小枝の先端に形成され始める[33]。このころの日照量が多く降水量が少ないと、翌年早春の花粉量が多くなる傾向がある[34]。
雄球花[注 4]は楕円形、長さ 2–8 mm、淡黄色、前年の枝先に6–35個が穂状に密生し、遠くからでもよく目立つ[24][28][16][14][7][27][38](下図4)。小胞子葉("雄しべ")の背軸面に、3–5個の花粉嚢("葯室")がある[16][15]。花粉は前年の秋頃から形成され始める[33]。花粉は直径30–40マイクロメートル (µm)、小突起があるが、付着性はない[15]。
雌球花[注 5]は緑色、球形で直径 4–5 mm、前年の枝先に1個ずつ下向きにつく[28][16][15][7](下図5a)。胚珠は珠孔から受粉滴を分泌し、これに花粉が付着し、この受粉滴が再び胚珠内に吸収されることで花粉は取り込まれ、数日で花粉管を伸長し始める[33]。受粉の頃から胚嚢母細胞が減数分裂を開始し、やがて9–10週間後に十数個の造卵器を含む胚嚢(雌性配偶体)が形成される[33]。受精は受粉から12週間後頃に起こり、やがて胚形成、種子の成熟が起こる[33]。球果はらせん状に配列した17–38個の果鱗(種鱗 + 苞鱗)からなり、種鱗と苞鱗は基部側で合着、種鱗の先端には4–6個の歯牙があり、苞鱗の先端は三角状でやや反曲する[16][14][7][33](下図5b)。球果は10–11月に熟し、球形で長さ1.5–3センチメートル (cm)、褐色で木質、裂開する[24][16][14][7][19](下図5c)。種鱗の基部に2–6個の種子がつく[16][7]。種子は長楕円形から倒披針形、長さ 4–7 mm、両側に狭い翼がある[16][7][27](下図5c)。種子の発芽率は一般的に30%ほどであり、子葉は2–3枚、まれに4枚[16][7][33]。染色体数は基本的に 2n = 22、ときに23、24、33、44[16][7]。
枝葉からは重量比約0.5%ほどの精油が抽出され、蒸留初期にα-ピネン、サビネン、リモネンなどのモノテルペンが多く、蒸留後期にはβ-エレモール、γ-オイデスモール、δ-カジネンなどのセスキテルペン、16-カウレンなどのジテルペンが得られる[39][40]。一方、材では特に心材部に多く、δ-カジネンやエピクベノール、ムウロレン、カジナ-1,4-ジエンなどのセスキテルペン、フェルギノールやサンダラコピマリノールなどのジテルペンが得られる[40][41]。
分布

日本では本州(青森県鰺ヶ沢町以南[42])から四国、九州(屋久島以北[43])までの、主に冷温帯(山地帯、ブナ帯)に自生し[44][28][16][14][29]、本州では標高 0–2,050 m(立山連峰劔岳)、四国では 300–1,400 m、九州では 300–1,850 m(屋久島)に分布する[7][19](図6)。ただし、スギは古くから伐採・利用されてきたためため、野生個体群は小さく(多くは 10 ha 以下)、山地にパッチ状に点在しているのみであり、多くは保護林とされている[45]。
日本固有種とされることもあるが[23]、中国南部(福建省、江西省、四川省、雲南省、浙江省)に分布しているものは、中国自生のものに由来すると考えられている(下記参照)。中国でも古くから伐採・利用されており、広く植栽されているが、野生個体群はほとんど残っていないと考えられている[45][46]。
日本では造林面積が最も広い樹種であり[47][26]、古くから植林されているため、天然林か人工林かの判断が難しいことも多い[16][15][19]。自生地以外では、青森県津軽半島[48]や南部地方[49]、北海道道南を中心に造林されており、最北端は利尻島にある[47]。ほかにも、沖縄本島北部[50]、台湾、朝鮮半島、中国からヒマラヤ地方、レユニオン島、アゾレス諸島などで木材用に植林されている[7][51][52]。
堆積物中の花粉化石の調査から、最終氷期においてもツガ属、トウヒ属、マツ属などが多かった寒冷期(約7万年前、2万年前など)を除いて、日本ではおおむねスギが多く生育していたことが示されている[53]。最終氷期には、スギは若狭湾から隠岐、伊豆半島周辺、紀伊半島南部、四国、屋久島などいくつかの逃避地に残存し、気候が温暖化し始めた1万年前頃から分布拡大して日本海側や東海地方ではスギが優勢となったが、約900年前以降にはマツ属、コナラ亜属が増加しており、人間活動によって二次林化していったと考えられている[39][53][54][45]。中国では、最終氷期には広く分布していたと推定されているが、その後の降水量の減少によって分布域が分断化され、さらに伐採や開墾などの人間活動によって大きく影響を受けたと考えられている[45]。
生態

自生のものは冷温帯(山地帯、ブナ帯)を中心に生育し、モミやヒノキ、アスナロ、クロベ、ヒメコマツ、ブナ、ミズナラなどと混生する[14][29][16][55]。沢沿いに多いが、岩上や湿原周囲に見られることもある[14][29]。人工的なスギ林は、暖温帯(低地帯)にも広く見られる[56]。沢沿いなど比較的水分と栄養分に富む環境を好む傾向があるため、植林の際にも谷間はスギ、中腹はヒノキ、尾根筋はマツと植え分けられる[57][58](図7a)。
スギの人工林は、ヒノキ林と比べて低木や草本などが育ちやすく、落ち葉が堆積しやすいので、土壌が軟らかい[23]。ただし落葉層が発達した場所ではスギの実生の定着が悪く、秋までにほとんど死滅してしまうとされる[59]。特に屋久島や積雪地の個体群では、実生の生存には倒木の存在が重要であることがしばしば指摘され[60][61]、実生で更新する場合にはいわゆる倒木更新や切株更新を行う樹種であると考えられている。
針葉樹のうち、マツ科の植物は外生菌根を形成するが、スギなどヒノキ科の植物はふつうアーバスキュラー菌根を形成する[62]。同一個体における菌根菌への感染率は一定ではなく、季節を通じて変動があることが報告されている[63]。マツ科の針葉樹はしばしばアレロパシー(他感作用)をもち、他の植物の生育を阻害しているとする報告がある[64][65]が、スギではこのようなアレロパシーは特に知られていない。スギ林には他の植物が生育しやすく、しばしばコクサギやウリノキ、バイカウツギなどの低木や、エビネやサイハイラン、ヤマルリソウなどの草本が見られる[14]。ただし、スギが混交するブナ科森林では、外生菌根を形成する菌根菌の種類が減少するという報告がある[66]。また、スギが植えられた場所はカルシウムなどの塩基が蓄積し、土壌は塩基性に傾くという[67]。
日本に自生するスギの中で、太平洋側のものと日本海側のものの間には形態的・生態的差異があることが知られている[15][19]。日本海側のスギは、下部の太枝が多雪でも折れずに垂れ下がり、接地した部分から発根して新たな株を形成(伏条更新)する性質がある[15][19][68][69]。ほかにも発根性がよく、挿し木が容易であり、幹の下部の不定芽がよく発達する[15]。また、日本海側のスギは樹冠がとがり、太枝が下向き、葉が枝に鋭角につくなど耐雪性の特徴も示す[19]。このような特徴をもつ日本海側のスギは、多雪環境に適応したものと考えられている[70]。一方、日本海側のスギは、太平洋側のスギよりも低温と乾燥に弱い傾向がある[71]。このような違いから、太平洋側のものは「オモテスギ」、日本海側のものは「ウラスギ」として分けられる(→#分類参照)。同様な太平洋側と日本海側での種内分化は、イチイとキャラボク、ヤブツバキとユキツバキなど様々な樹木でも知られている[56][72][73]。

スギは、冬季に葉が赤褐色になって春に再び緑色に戻るものが多いが(図7b)、黄白色になるものや、変色せずに緑色を保つものもいる[14][31][74]。緑色のままや黄白色に変化する形質は、赤褐色に変化する形質に対して潜性形質(劣性形質)であるとされる[74]。赤褐色への変色はカロテノイドの1種であるロドキサンチンの蓄積によるものとされ、光合成機能が低下する低温条件下で太陽光による障害(光阻害)を防ぐ効果があると考えられている[75]。このような低温条件下での光阻害とその対応が種の分布を決める一因となっているとして、高山・亜高山帯に分布するマツ科やツツジ科を中心に研究が行われている[76][77]。
耐塩性については品種、及び樹齢によって異なるとされる[78]。
スギの花粉媒介は風媒であり、2–4月頃に大量の花粉が散布される[26][33][7][32]。スギの花粉は比較的遠距離まで散布されるため、産地の異なるスギを天然林付近に植栽すると、遺伝子汚染を引き起こしやすいとされる[79]。
病虫害
菌類
スギの病害は約80種が報告されているが[80]、スギ赤枯病は特に重要な病害である[81]。スギ赤枯病は Passalora sequoiae(= Cercospora sequoiae; 子嚢菌門クロイボタケ綱)によって引き起こされるスギ苗木に対する代表的な病害であり、葉や枝が枯れ、胞子(分生子)で周囲のスギ苗木に感染して被害が拡大する[82][83][84]。また、類似した病害としてスギフォマ葉枯病(病原菌は Discochora sawadae)、スギペスタロチア病(病原菌は Pestalotiopsis spp.)、スギ列イボ病(病原菌は Cercospora cryptomeriaecola)などがある[84][82][80]。赤枯病に罹病して枯死しなかった苗木が成長すると、患部が溝状に残って成長するため、溝腐病とよばれる[82][85]。若い時期に感染した部分が治癒しないため樹幹は著しく変形して材変色が生じ、また林内の他の木に感染することもある[85]。全く別の菌類であるチャアナタケモドキ(Fomitiporia sp. = "Phellinus punctatus"; 担子菌門ハラタケ綱)が類似した病気を引き起こすことがあり、非赤枯性溝腐病とよばれ、特に千葉県の山武杉(サンブスギ)に大きな被害を与えた[86][87]。
スギ黒点枝枯病もスギの重要な病害であり、Stromatinia cryptomeriae(子嚢菌門ズキンタケ綱)によって引き起こされる[81][88]。小枝先端部に褐色病斑が生じてその病斑が拡大、数年で主枝に達し、主枝を一周するとそれより上部が赤褐色になって枯れてしまう[88]。特に東北地方において重要病害であり、樹齢を問わず発生し、ときに著しい成育阻害を起こす[88]。
スギ枝枯菌核病とスギ褐点枝枯病は東北地方の多雪地帯で重要な病害であるが、同一の菌類 Scolecosporium(子嚢菌門クロイボタケ綱)の異なる世代によって引き起こされることが示唆されている[81]。スギ暗色枝枯病は Guignardia cryptomeriae(子嚢菌門クロイボタケ綱)による病気であり、枝枯、樹幹の陥没、材の変色が起こる[82]。スギ褐色葉枯病では Plectosphaera cryptomeriae(子嚢菌門フンタマカビ綱)が葉に寄生してこれを枯らし、症状が重いと樹勢の低下が著しい[82]。スギ苗癌腫病の原因菌は Valsa cryptomeriae(子嚢菌門フンタマカビ綱)とされていたが、直接の関係はないことが明らかとなっており、病因は不明である[80]。
昆虫・ダニ

スギの葉を好んで食べるスギドクガ(Calliteara argentata; 図8a)は、幼虫が時に大発生し被害が大きい場合は成木でも枯死に至ることがある[89]。スギドクガは新葉より旧葉を好んで食べるという[90]。スギの葉を食べる昆虫として、ほかにウスイロサルハムシ(スギハムシ; Basilepta pallidula)、スギハマキ(Homona issikii)などがいる[82][91]。またスギの葉に潜行する昆虫として、スギメムシガ(Argyresthia anthocephala)やスギタマバエ(Contarinia inouyei)がいる[91]。スギマルカイガラムシ(Aspidiotus cryptomeriae)は、スギの葉を黄色く変色させ、ときに苗木を枯死させる[91]。スギノハダニ(Oligonychus hondoensis)やエゾスギツメハダニ(エゾスギハダニ; Oligonychus pustulosus)もスギにつき、葉に白から褐色の斑紋が生じる[91]。

スギの生木に対する穿孔性害虫としては、特にスギカミキリ(Semanotus japonicus)とスギノアカネトラカミキリ(Anaglyptus subfasciatus)の幼虫が著しい材質低下をもたらす[92][93][94]。スギカミキリの幼虫は内樹皮を食害し、その被害は「はちかみ」とよばれる[82]。一方、スギノアカネトラカミキリの幼虫は材を食害し、その部分に菌類が侵入して材が変色する現象は「とびくされ」とよばれる[82]。スギノアカネトラカミキリは、スギでは尾根筋に生える個体に、逆にヒノキでは谷筋に生える個体に被害を与える[95]。生木または伐採後の原木に穿孔する昆虫として、ほかにヒメスギカミキリ(Callidiellum rufipennis; 図8b)、マスダクロホシタマムシ(Ovalisia vivata)、キクイムシ類、ゾウムシ類(オオゾウムシなど)、キバチ類(ニホンキバチ、オナガキバチなど)、コウモリガ(Endoclyta excrescens)、ヒノキカワモグリガ(Callidiellum rufipenne)、スギザイノタマバエ(Reeseliella odai)などが知られている[82][96][91][97]。穿孔性の昆虫の中には(特にキクイムシ類、一部のキバチ類)、産卵時に特定の菌類を共に植え付け、幼虫がこれを直接または間接的に利用することがあり、このような菌類によって材が変色する[82][96]。穿孔性昆虫の中には、樹皮がついている原木を好む種と、樹皮を剥がした原木を好む種がいる[96]。

スギの球果を食害する昆虫として、チャバネアオカメムシ(Plautia stali[98]; 図8c)やスギメムシガ(Argyresthia anthocephala)、マツマダラメイガ(Dioryctria abietella)、スギカサヒメハマキ(Cydia cryptomeriae)などが知られており、スギ種子の生産を行う採種園に大きな被害を与えることがある[91][99][100]。またスギの球果で増殖したチャバネアオカメムシが、近隣のナシやカキなどの果樹に害を与えることもある[101]。
スジコガネ(Anomala testaceipes)、オオスジコガネ(Anomala costata)、ヒメコガネ(Anomala rufocuprea)、ナガチャコガネ(Heptophylla picea)、キンケクチブトゾウムシ(Otiorhynchus sulcatus)、クワヒョウタンゾウムシ(Scepticus insularis)の幼虫は地中に生育し、スギの根を食害する[91]。
その他
ニホンジカはスギの枝葉を食べ、またニホンノウサギは苗木を食害する[82]。ツキノワグマやニホンジカが樹皮をはいでしまうことがある(熊剥ぎ、鹿剥ぎ)[102]。
著名な個体

最も樹高が高い個体は、京都市左京区の大悲山国有林にある「花脊の三本杉」(図9a)の1本(東幹)であり、2017年に高さ62.3メートルであることが報告された[103][25]。三本杉の別の1本(北西幹)も高さ60.7メートルあり、2番目に樹高が高い個体とされる[103][25]。また、屋久島の「縄文杉」は幹周り16メートルあり、最も太い個体とされるが、縄文杉は複数の木が癒合したものともされ、確実に1本のものは高知県長岡郡大豊町の「杉の大杉」南株であり、幹周り15メートルに達する[15]。
スギの巨木はしばしば樹齢1,000年以上とされるが、スギは成長が早く、実際に1,000年以上のものは少ないと考えられている[15]。屋久島の「縄文杉」はときに樹齢7,200年ともされるが確実な証拠はなく、その樹齢は明らかではない[104]。ただし屋久島には実際に高齢樹が多いと考えられており、確実な例としては、地上6メートルの部分で1,776年の年輪を示す標本があり、ほかにも1,400年、1,345年の記録がある[105]。
屋久杉


鹿児島県の屋久島は日本におけるスギの自生地最南端であり、標高700から1,700メートルの山地に生育している[53]。降水量は多いが花崗岩質で栄養分が乏しいため、屋久島のスギは極めて成長が遅く、樹齢1,660年でも幹の直径が180センチメートルほどにしかならない[106]。そのため材質が緻密であり、樹脂分が多く腐食しにくいため、長命であると考えられている[106]。一般的に屋久島のスギは屋久杉とよばれるが、現地では樹齢800–1,000年以上と考えられるものを屋久杉、それより若いものは小杉とよばれる[7][106][19]。小杉は林業が行われ始めた時代以降のものであり、明るい伐採地で育ったため成長が良好であるが、屋久杉はそれ以前からあるもので暗い林内で育ったため成長が遅く木目が詰まっている[106]。現存する大きな屋久杉は幹の凹凸が激しく、利用しにくいため切り残されたと考えられている[106]。著名な屋久杉として、以下のものがある[107][108]。また、下記のように、屋久島のスギ原生林は特別天然記念物に指定されている[109]。
- 縄文杉(図10a):1966年に発見された。樹高25.3メートル、幹周16.4メートル、最大の屋久杉とされるが、複数の個体が癒合したものともされる[107][108][15]。樹齢は2,200年から7,200年まで諸説ある[107][108]。2005年に折れた大枝は約1,000歳であった[108]。
- 大王杉(図10b):急斜面に生えている[108]。縄文杉の発見以前は最大の屋久杉とされていた[107][108]。樹高24.7メートル、幹周11.1メートル[107][108]。樹齢は3,000年ともされる[107][108]。
- 弥生杉:樹高26.1メートル、幹周8.1メートル[107][108]。樹齢は3,000年ともされる[107]。幹の変形が著しいため切り倒されずに残されたとされる[107][108]。
- 紀元杉:樹高19.5メートル、幹周8.1メートル[107][108]。樹齢は3,000年ともされる[107][108]。
- 三代杉:三代のスギからなるとされ、一代目が2,500年前に発芽し樹齢1,200年で倒木、その上で発芽した二代目が樹齢1,000年で伐採され、その切り株から萌芽したのが現在の三代目とされる[107]。三代目は樹高38.4メートル、幹周4.4メートル、樹齢350年とされる[107]。
- 二代大杉:江戸時代に伐採された一代目の切り株の上で成長したもの[107]。樹高32メートル、幹周3.9メートル[107]。
- ウィルソン株:幹周13.8メートルの切り株[107][108]。この名は、屋久杉を世界に紹介した米国の植物学者であるアーネスト・ヘンリー・ウィルソンに由来する[107]。豊臣秀吉による方広寺(または大坂城)建設のために切り出されたと考えられている[107]。
天然記念物
2023年現在、日本において国の特別天然記念物(*で示している)または天然記念物に指定されているスギは、下記のように49件ある[109]。植栽されたものが多いが、スギの原生林も含まれる。また、県や市区町村で指定されているものも多い[110]。
- 桃洞・佐渡のスギ原生林(秋田県北秋田市)
- 木幡の大スギ(福島県二本松市)(図11a)

11a. 木幡の大スギ - 杉沢の大スギ(福島県二本松市)
- 諏訪神社の翁スギ媼スギ(福島県田村郡小野町)
- 熊野神社の大スギ(山形県鶴岡市)
- 羽黒山の爺スギ(山形県鶴岡市)
- *羽黒山のスギ並木(山形県鶴岡市)(図11b)

11b. 羽黒山のスギ並木 - 山五十川の玉スギ(山形県鶴岡市)
- 逆スギ(栃木県那須塩原市)
- *日光杉並木街道(栃木県日光市、鹿沼市)
- 安中原市のスギ並木(群馬県安中市)
- 榛名神社の矢立スギ(群馬県高崎市)
- 安良川の爺スギ(茨城県高萩市)
- 清澄の大スギ(千葉県鴨川市)
- 箒スギ(神奈川県足柄上郡山北町)
- 将軍スギ(新潟県東蒲原郡阿賀町)(図11c)
11c. 将軍スギ - 天神社の大スギ(新潟県妙高市)
- 虫川の大スギ(新潟県上越市)
- 杉沢の沢スギ(富山県下新川郡入善町)
- 御仏供スギ(石川県白山市)
- 栢野の大スギ(石川県加賀市)
- 八幡神社の大スギ(石川県加賀市)
- 精進の大スギ(山梨県南都留郡富士河口湖町[111])(図11d)

11d. 精進の大スギ - 月瀬の大スギ(長野県下伊那郡根羽村)
- 智満寺の十本スギ(静岡県島田市)
- 杉本の貞観スギ(愛知県豊田市)
- *石徹白のスギ(岐阜県郡上市)
- 神ノ御杖スギ(岐阜県郡上市)
- 大山の大スギ(岐阜県加茂郡白川町)
- 神淵神社の大スギ(岐阜県加茂郡七宗町)
- 加子母のスギ(岐阜県中津川市)
- 久津八幡神社の夫婦スギ(岐阜県下呂市)
- 禅昌寺の大スギ(岐阜県下呂市)(図11e)
11e. 禅昌寺の大スギ - 千光寺の五本スギ(岐阜県高山市)
- 八ツ房スギ(奈良県宇陀市)
- 玉若酢命神社の八百スギ(島根県隠岐郡隠岐の島町)
- 大玉スギ(山口県周南市)
- 平川の大スギ(山口県山口市)
- *杉の大スギ(高知県長岡郡大豊町)(図11f)

11f. 杉の大スギ - 天神の大スギ(高知県香南市)
- 英彦山の鬼スギ(福岡県田川郡添田町)
- 女夫木の大スギ(長崎県諫早市)
- 阿弥陀スギ(熊本県阿蘇郡小国町)
- 金比羅スギ(熊本県阿蘇郡南小国町)
- 大杵社の大スギ(大分県由布市)
- 狭野のスギ並木(宮崎県西諸県郡高原町)
- 八村スギ(宮崎県東臼杵郡椎葉村)
- *屋久島スギ原始林(鹿児島県熊毛郡屋久島町)
人間との関わり
スギは、日本人にとって古くから生活に深く関わり、また信仰の対象となることもある馴染み深い樹木である。建築材や土木材、酒樽などに利用され、樹皮は屋根葺きの材料として利用されてきた。日本酒の酒蔵の軒先には、スギの葉を束ねて丸くした杉玉が吊される。線香は乾燥したスギの葉を粉末状にしたものを原料とすることがある。日本では木材用のスギの植林が戦後盛んに行われたため人工林面積の約45%を占め、また防風や風致のために植栽されることもある。スギは極めて有用な植物であるが、春先の晴れた日に花粉が大量に飛散し、これを原因とするスギ花粉症は日本人の国民病ともいわれ、社会問題のひとつとなっている[23]。
木材
スギは成長が速く、その材は割りやすくやわらかく加工しやすいため、古くから利用されている[112]。縄文時代前期(約6,000年前)の鳥浜遺跡(福井県三方上中郡)からは、板材などの大量のスギ材とともに、長さ6メートルもあるスギの丸木舟が出土している[112]。また弥生時代の登呂遺跡(静岡県静岡市)からは、住居や生活具、水田の畦や溝の土留めとされた大量のスギ材が出土している[112]。
材は比較的軽く、気乾比重は0.30–(0.38)–0.45、割裂性がよく、やわらかく加工しやすい[7][19][47][113][114]。辺材と心材の差は明瞭であり、辺材は白色、心材はふつう淡紅から暗赤褐色(赤芯)だが、黒褐色のもの(黒芯)もある[7][19][39][112][113][114]。スギは含水率が高いことがあり(黒芯など)、このような状態は「水食い」(wetwood)とよばれ、しばしば利用に問題が生じる[113][115][116][117]。木目はまっすぐで年輪は明瞭、肌目はやや粗い[112][19][113][114]。特有の匂いがあり、酒樽に用いることで日本酒の香り付けにも関わる[112][113][114]。心材の耐朽性は中程度[113][114]、耐水性にやや劣る[118]。乾燥は速く、平均収縮率は柾目方向で0.1%、板目方向で0.25%、曲げヤング係数は 7.5–10 GPa[7][113][47]。
日本における木材利用の75%を占めるともされる[7]。建築材(柱、桁、垂木、天井板、欄間、長押、戸、障子など)、家具、器具、包装、樽、桶、下駄、指物、経木、曲物、箸、土木(足場丸太、杭丸太など)など様々な用途で用いられる[24][47][7][39][112][113][114](図12)。また、造船、電柱、天秤棒、背負子などにも使われた[119][47]。
古木の材には鶉杢(うずらもく)や笹杢(ささもく)など特異な模様が生じることがあり、指物や和家具などの材料として珍重される[118]。また、水土中に埋没して火山灰などによって青黒褐色に変色した材は神代杉(じんだいすぎ)とよばれ、工芸品などに利用される[118]。
樹皮・枝葉などの利用
スギの樹皮は屋根の材料とされることがあり、このような屋根葺きは「杉皮葺き」とよばれる[112][120]。また、樹皮は垣根などに利用されることもある[19]。
スギの枝葉を集めて球形にしたものは、杉玉(酒林、杉林)とよばれる[7][112][121][119](下図13a)。日本酒の造り酒屋の軒先に吊るされる杉玉は、新酒ができたことを知らせる意味がある[122][123]。最初は緑色だった杉玉はやがて枯れて茶色になり、次の新酒の際に掛け替えられる[122][123]。杉玉の発祥は酒の神とされる奈良県三輪山の大神神社とされ、大神神社では三輪山のスギを神木とし、毎年11月14日によい醸造を祈願して杉玉を飾る[123][121]。また、古くは防腐のために酒樽の中に杉玉を入れていたとする記述もある[119]。
線香は、匂い線香と杉線香に大別される(下図13b)。匂い線香は、タブノキの樹皮粉末に伽羅や沈香、白檀などの香木(ときに漢方薬や香料)を混ぜて作られたものであり、墓参り以外で現在一般に使われる線香である[124]。一方、乾燥させたスギの枝葉の粉末から作られた線香は杉線香とよばれ、煙が多いため主に墓参り用に使われている[39][112][124]。
葉から抽出された精油は、化粧品の香料や医薬品に利用されることがある[39][19]。
山奥では古くは茶に不自由であったため、スギを茶外茶として利用することがあり、「杉茶」とよばれる[39]。
古くは、飢饉時にスギの内樹皮を食用としたことがあった[29]。
スギのおがくずは、ヒラタケ、エリンギ、ブナシメジ、エノキタケなどの食用キノコの菌床として利用されている[125](上図13c)。また、スギの切り株や倒木にしばしば発生するスギヒラタケは食用とされていたが、2000年代以降、本種が急性脳症の原因となることが示唆され、食用としないよう呼び掛けられている[126](上図13d)。
子供のおもちゃとして、スギの雄球花("雄花")を弾にした杉鉄砲がある[127]。細い竹の管と、その穴にちょうど収まるほどの竹ひごに柄をつけたものを用意し、まず管に雄球花を詰め、竹ひごで押し込む。そのあとにもう一つの雄球花を詰め、竹ひごで押し込めば、空気圧によって前の雄球花が破裂音とともに飛び出す。
観賞用
スギは、庭木や生垣、盆栽、いけばなに用いられることもある[19]。ただし、下記のようにスギは神聖視されることもあるため、屋敷や生垣にすると家が滅びたり福が入らなくなるとされ、植栽が避けられることもある[19]。スギの園芸品種は多く作出されており、例として以下のようなものがある[7][29][128]。
- 枝は長く多数出て著しく伸長し、大小の葉を交互に生じる[29]。
- 葉は細長く柔らかい[7]。
- ムレスギ(叢杉)
- 枝が根元から多数出て叢生する[7]。
- イカリスギ(錨杉) Cryptomeria japonica 'Lycopodioides'
- オウゴンスギ(黄金杉)
- 若葉が黄金色を呈する[7]。
- ミドリスギ(緑杉) Cryptomeria japonica 'Viridis'
- 葉が冬でも緑色を呈する[7]。
- チャボスギ(矮鶏杉) Cryptomeria japonica 'Nana'
- 枝葉が短小で密生し、樹冠が半円形となる[7]。
- マンキチスギ(万吉杉)
- 枝が密生し、葉が著しく剛強で開き、鋭くとがる[7]。
- シダレスギ(枝垂杉)
- 枝が細長く、下垂する[7]。
- フイリスギ(斑入杉)
- 葉に黄白色の斑が入る[7]。
- メジロスギ(芽白杉) Cryptomeria japonica 'Albospica'
- 新芽は白色、枝は詰まって短い[29]。
- セッカンスギ(雪冠杉) Cryptomeria japonica 'Sekkan-sugi'
- 新緑の際に葉の先が白色からクリーム色で雪をかぶったようになる[29]。
植林
上記のようにスギは木材として古くから利用されており、当初は天然林から切り出されていたが、室町時代頃から経済的利用のための植林が行われるようになったと考えられている[129]。火事が頻発した江戸において住宅の再建が可能だったのは、造林されたスギ林による材の大量供給があったためであるとされる[129]。特に第二次世界大戦後の日本では、拡大造林政策によってスギやヒノキ、カラマツの人工林が急激に増加した[129][130]。スギは成長が比較的速く、幹が通直で歩留まりが良いこと、材質が柔らかく加工しやすいこと、ある程度耐朽性があること、山地の中腹以下で湿った場所が生育に適しているため、好まれて植林された[19][129][24]。現在ではスギは日本で最も多く植林されている樹種であり、面積として444万ヘクタール、人工林面積の約45%、総森林面積の18%を占めている[17][47][34](下図15a)。日本以外でも台湾、朝鮮半島、中国からヒマラヤ地方、レユニオン島、アゾレス諸島などで植林されている[7][51][52](下図15b, c)。
スギの生育に最適の環境は、年平均気温12–14°C、年降水量3,000ミリメートル以上とされる[7][19]。斜面下部や谷あいでやや湿気があり、肥沃で深い土壌を好む[7][19]。陽樹であるため、光が多く当たる環境が望ましい[7][19]。
植え付けには実生または挿し木を用い、75%ほどは実生苗であるが、地域によっては挿木苗を用いる[7]。挿し木の成功率は品種によって異なり[131][132]、また薬剤処理[133][134]や加温[135][136]によって改善される報告がある。実生苗と挿し木苗では前者の方が成長が良いとされることが多く、このため積雪地では挿し木苗が不利とする報告がある[137]。
植林の場合は、一般には1ヘクタール当り3,000本植えが標準とされている[7]。よい材を育てるために、過密林を避けて成木の間引き(間伐)が行われる[24]。スギ林は、幼時からこのような間伐や枝打ち、林縁の保護、病虫害への対処などの管理を必要とする[7]。
特異な育成を行うこともあり、京都市北山地方では1本の株(台杉)から多数の幹をまっすぐに育て(台杉仕立て)、これを磨き丸太として利用している[138](上図15d)。台杉となる木は、「シロスギ(白杉)」とよばれる木から挿し木で増やしたものが使われている[138]。
生産地ごとに材の特徴や生産・管理方法に違いがあり、床柱の北山杉、酒樽の吉野杉、造船の飫肥杉、仏壇の屋久杉など産地によって用途を使い分けられることもあったが、現在でも地域名を冠して「…杉」とよばれブランド化されている[129][47]。スギの産地名を冠したものとして以下のような例がある[7][112][39][139][107]。
- 道南杉(どうなんすぎ)[107]: 北海道道南(渡島・桧山地方)。
- 鯵が沢杉(あじがさわすぎ)[107]: 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町。
- 鶯宿杉(おうしゅくすぎ)[107]: 岩手県岩手郡雫石町、和賀郡沢内村。
- 気仙杉(けせんすぎ)[39][107]: 岩手県気仙郡、下閉伊郡南部。
- 秋田杉(あきたすぎ)[129][7][39][107]: 秋田県北部、特に米代川流域。天然のものは特に「天然秋田杉」とよばれる。
- 桃洞杉(とうどうすぎ)[107]: 秋田県北秋田郡阿仁町、森吉町(標高800–900メートル)。
- 鳥海群杉(ちょうかいむらすぎ)[107]: 秋田県由利郡矢島町、鳥海村。
- 西山杉(にしやますぎ)[39][107]: 山形県西村山郡。
- 金山杉(かなやますぎ)[39][107]: 山形県最上郡金山町。
- 山の内杉(やまのうちすぎ)[107]: 山形県最上郡戸沢村。
- 栗駒杉(くりこますぎ)[107]: 宮城県北部の栗駒山麓。
- 八溝杉(やみぞすぎ)[39][107]: 栃木県・茨城県・福島県の県境付近にある八溝山系。茨城県のものは茨城杉(いばらきすぎ)ともよばれる。
- 日光杉(にっこうすぎ)[39][107]: 栃木県日光市、今市市、鹿沼市。
- 西川杉(にしかわすぎ)[129][39][107]: 埼玉県飯能市。
- 山武杉(さんぶすぎ)[129][39][107]: 千葉県東部山武地方。
- 青梅杉(おうめすぎ)[39][107]: 東京都青梅市。
- 根羽杉(ねおすぎ)・遠山杉(とおやますぎ)[39][107]: 長野県下伊那郡根羽村・南信濃村。
- 天竜杉(てんりゅうすぎ)[129][39][107]: 静岡県浜松市天竜区、磐田郡(水窪町・佐久間町・龍山村)。
- 三河杉(みかわすぎ)[39][107]: 愛知県南設楽郡・北設楽郡・新城市・東加茂郡・額田郡。
- 鳳来杉(ほうらいすぎ)[7]: 愛知県旧鳳来町。
- 東濃杉(とうのうすぎ)[140]: 岐阜県の裏木曽、東濃地域。
- 長良杉(ながらすぎ)[39][107]: 岐阜県郡上郡・武儀郡長良川流域。
- 飛騨杉(ひだすぎ)[141]: 岐阜県高山市。
- 越後杉(えちごすぎ)[107]: 新潟県。
- 立山杉(たてやますぎ)[129][7][39][107]: 富山県東部。
- 足羽杉(あすわすぎ)・河和田杉(かわだすぎ)[39][107]: 福井県美山町・鯖江市。
- 谷口杉(たにぐちすぎ)[39][107]: 滋賀県長浜市谷口町。田根杉(たねすぎ)ともよばれる。
- 北山杉(きたやますぎ)[129][39][107]: 京都府京都市北山地方。
- 宇治田原杉(うじたわらすぎ)[39][107]: 京都府京都市南部、宇治田原町一帯。
- 春日杉(かすがすぎ)[39][107]: 奈良県奈良市東部の春日山原始林一帯。
- 吉野杉(よしのすぎ)[7][39][107]: 奈良県吉野郡の吉野川上流域。
- 御山杉(みやますぎ)[39][107]: 三重県伊勢市の内宮・外宮および滝原宮の神域。
- 尾鷲杉(おわせすぎ)[142]: 三重県尾鷲市。
- 紀州杉(きしゅうすぎ)[143]: 和歌山県の紀伊山地周辺。
- 河内杉(かわちすぎ)[39][107]: 大阪府河内地方。
- 宍粟杉(しそうすぎ)[129][7]: 兵庫県宍粟市。
- 若桜杉(わかさすぎ)[39][107]: 鳥取県東部の若桜町一帯。
- 智頭杉(ちずすぎ)[129][129][39][107]: 鳥取県東南部の智頭町一帯。
- 八郎杉(はちろうすぎ)[144]: 広島県廿日市吉和。
- 木頭杉(きとうすぎ)[129][39][107]: 徳島県西南部の那賀郡・海部郡。
- 徳島杉(とくしますぎ)[145]: 徳島県の吉野川南岸から剣山周辺。
- 相生杉(あいおいすぎ)[146]: 徳島県南部の那賀町。
- 久万杉(くますぎ)[129][107]: 愛媛県中部久万高原町、小田町。
- 魚梁瀬杉(やなせすぎ)[129][7][39][107]: 高知県東部の馬路村・東洋町を中心とした一帯。土佐杉ともいう。
- 八女杉(やめすぎ)[129][39][107]: 福岡県八女郡一帯。
- 日田杉(ひたすぎ)[129][39][107]: 大分県日田市を中心とした一帯。
- 市房杉(いちふさすぎ)[39][107]: 熊本県水上村の市房神社の神社林および周辺一帯。
- 小国杉(おぐにすぎ)[129][39][107]: 熊本県阿蘇郡小国地方。
- 飫肥杉(おびすぎ)[129][39][107]: 宮崎県日南市を中心とした飲肥地方一帯。
- 霧島杉(きりしますぎ)[39][107]: 鹿児島県霧島町の霧島神宮の神宮林。
- 屋久杉(やくすぎ)[129][39][107]: 鹿児島県屋久島。
スギの人工林は急速に増えたが、輸入材の急増や労働力の高齢化によって林業が衰退し、このような人工林の中には管理されずに放置されるものも増えていった[129][130]。このような放置林は豪雨などによって崩壊して災害を引き起こすこともある[129][130]。拡大造林政策によってつくられた人工林が収穫期(主伐期)を迎えているが、このような状況のもとで利用されずに放置されている[130]。放置された人工林では林床が暗く草本などが育たず、生物多様性が低い環境となってしまい、「緑の砂漠」ともよばれる[147][148]。そのため、スギなど単一樹種からなる人工林に広葉樹などを導入する複層林施業なども進められている[34]。
防災・風致
スギは保安林区域内にもしばしば生育している樹種であり、生態的に沢沿いを好むことから水源かん養保安林や土石流被害軽減のための土砂流出防備保安林、雪崩被害軽減のためのなだれ防止保安林での指定が多い[149][150][151][152](下図16a, b)。保安林に指定されたスギ林では、しばしば砂防ダムや雪崩防止柵などが設置され伐採も制限されている。
スギは深根性であり、根を深くまで伸ばす[153]。スギの根系直径10ミリメートル (mm) の引き抜き抵抗力は 100 kgf 程度でヒノキや広葉樹(ナラ類)と同程度であり、アカマツやカラマツよりも大きいため、土砂災害に強い森林づくりに好ましい樹種とされる[154]。スギなどの人工林は土砂崩れに弱いといわれることもあるが、上記のようにそのようなことはない[57]。ただし、そもそも土砂崩れが起こりやすい水分が多い環境にスギが植林されるため、スギ植林地で災害が多く起こってしまう[57](上図16c)。
スギは防風の効果を期待して屋敷林として植栽されることがあり[155][156]、富山平野(砺波平野を含む)[157]や北関東[158]の屋敷林にはしばしばスギが用いられている(下図17a, b)。アゾレス諸島でも、スギが防風林として利用されている[52]。
スギは並木道の木として用いられることもあり、スギの並木道は各地に見られる[160][161][162](上図17c, d)。
文化
スギは古くから日本人にとって重要な樹種であり、『日本書紀』では、スギは須佐之男命によってつくられた4種の有用木の1つとされている(ほかはヒノキ、コウヤマキ、クスノキ)[163]。
スギは樹形が美しく日本人の心情によく合い、また神を祭る神聖な木とされ、神社などで広く植栽されてきた[19]。『万葉集』でも、下記のように詠まれた歌があり、古くから植栽されていたことを示している[129][164]。
古 の 人の植ゑけむ 杉が枝 に霞 たなびく 春は来ぬらし
『万葉集』では、ほかにもスギに関する歌がいくつか詠まれている[7][164]。下記の歌は「神聖な三輪の杉に触れてしまった罪のため、あなたに会えなくなってしまったのだろうか」としており、三輪のスギが神聖視されていたことを示している(下図18a)。
味酒 を 三輪の祝 が いはふ杉手触 れし罪か 君に逢ひがたき—丹波大女娘子、『万葉集』巻4-712番
『古今和歌集』にもスギに関わる下記の歌があり、三輪明神の神婚説話と結び付いて明神の歌と伝承されるようになった[7]。
我が
庵 は 三輪の山もと 恋しくは訪 らひ来ませ 杉立てる門 —よみ人しらず、『古今和歌集』巻18 雑歌下、982
伏見稲荷神社にある神木とされるスギは「験の杉(しるしのすぎ)」とよばれ、折り取って植えた枝が枯れなければ願いが通じた、または福を得たしるしとされた[7][165]。験の杉の記述は古くからあり、『山城国風土記』、『蜻蛉日記』、『更級日記』などに見られる[7]。このほかにも鹿島神宮(茨城県)の「神木杉」、豊受大神宮(三重県)の「五百枝の杉」、香椎宮(福岡県)の「綾杉」なども、神木として知られている[7](下図18)。また、スギの枝葉は魔除けや安産のお守りとされることがある[19]。
著名な武将が矢を射立てたとする伝承があるスギも、各地に存在する[7]。藤原秀衡が射立てたとするスギが宮城県名取市に、源頼朝が射立てたとするスギが山梨県大月市にある[7]。
日本では、古くは人の死後三十三回忌に弔い上げ(最後の年忌法要)を行い、その後は仏は神になるという考えがあるが、その際に墓地に杉卒塔婆または梢付塔婆としてスギの小枝を立てる風習がある[7][19]。
スギを家紋に用いている例もある。江戸時代には十数の家が杉紋を用いており、特に大和国の大神神社の神官関係者が多く、大神(おおみわ)氏やその一族である緒形氏もこれを用いていた[39]。家紋の種類としては、一本杉、並び杉、三本杉、杉巴、割り杉などがある[39]。
スギをシンボルとする自治体
上記のように日本ではスギは極めて身近な樹木であり、またスギを用いた林業が盛んな地域も多いため、スギをシンボルとしている自治体は多い[166]。
県の木
市区町村の木
- 北海道:木古内町[168]、乙部町[168]、知内町[169]、福島町[168]
- 岩手県:陸前高田市[170]、雫石町[171]、金ケ崎町[172]、平泉町[173]、住田町[174]、山田町[175]
- 宮城県:登米市[176]、丸森町[177]、涌谷町[178]、女川町[179]
- 秋田県:男鹿市[180]、大館市(秋田杉)[181]、にかほ市(むら杉)[182]、五城目町[183]、上小阿仁村(秋田杉)[184]、東成瀬村(秋田杉)[185]
- 山形県:大江町[186]、戸沢村(山ノ内杉)[187]
- 福島県:喜多方市(飯豊杉)[188]、塙町[189]、石川町[190]、古殿町[191]、楢葉町[192]、小野町[193]
- 栃木県:鹿沼市[194]、市貝町[195]
- 群馬県:安中市[196]、下仁田町[197]、南牧村[198]、榛東村[199]
- 埼玉県:飯能市[200]、杉戸町[201]
- 千葉県:山武市[202]
- 東京都:杉並区[203]、青梅市[204]、奥多摩町[205]
- 新潟県:加茂市[206]、阿賀町[207]
- 富山県:砺波市[208]、小矢部市(宮島杉)[209]、立山町(立山杉)[210]
- 石川県:加賀市[211]
- 福井県:勝山市[212]、池田町[213]
- 山梨県:道志村[214]
- 長野県:須坂市(クマスギ)[215]、根羽村[216]
- 静岡県:裾野市[217]
- 愛知県:東栄町[218]
- 岐阜県:関市[219]、関ケ原町[220]
- 三重県:亀山市[221]、熊野市(熊野杉)[222]
- 和歌山県:新宮市(熊野杉)[223]、印南町[224]、古座川町[225]
- 滋賀県:甲賀市[226]、多賀町[227]
- 京都府:和束町[228]
- 奈良県:桜井市[229]、下市町[230]、吉野町(吉野杉)[231]、曽爾村[232]、御杖村[233]、黒滝村[234]、天川村[235]、川上村(吉野杉)[236]、十津川村[237]
- 大阪府:豊能町[238]
- 鳥取県:智頭町[239]、日野町[240]
- 島根県:隠岐の島町[241]
- 岡山県:新庄村[242]、西粟倉村[243]
- 徳島県:神山町(神山杉)[244]
- 愛媛県:久万高原町[245]
- 高知県:大豊町[246]、土佐町[247]、田野町(魚梁瀬杉)[248]、馬路村(やなせすぎ)[249]、香美町[249]、越知町[249]、梼原町[249]
- 福岡県:篠栗町[250]
- 熊本県:大津町[251]、菊陽町[252]、南小国町[253]、小国町[254]、津奈木町[255]、水上村[256]、山江村[257]、球磨村[258]
- 宮崎県:日南市(飫肥杉)[259]、五ヶ瀬町(アオスギ)[260]
- 鹿児島県:屋久島町(屋久杉)[261]
スギ花粉症
花粉が原因となって引き起こされるアレルギー反応は花粉症とよばれ、くしゃみ、鼻水、目の充血、かゆみなどの症状を示す[262]。日本ではスギの花粉を原因とする花粉症(スギ花粉症)が最も多く、日本の全人口の1割以上がスギ花粉症に罹患しているともされる[263][264]。そのため、例年2月から3月にかけて、マスコミなどでもスギ花粉情報が発信されている[38][263]。ただし、花粉症の原因となる花粉はスギだけではなく、ほかにイネ科(カモガヤ、オオアワガエリなど)、キク科(ブタクサ、ヨモギなど)の花粉を原因とすることもあり、ヨーロッパではイネ科の、アメリカではキク科の花粉症が多い[262][265]。また、北欧や北海道(主に道央以東、以北[266])ではシラカンバ(カバノキ科)の花粉症が多い[262][267]。スギ花粉症は典型的なI型アレルギー反応(IgE抗体による即時型の反応)による疾患であり、そのアレルゲン(抗原)は分子量 40 kDa 前後のタンパク質(Cry j 1, Cry j 2)である[264][268][注 6]。また、この抗体はスギ花粉だけではなく、ヒノキなど同じヒノキ科の植物の花粉にも反応することがある[264]。
上記のように第二次世界大戦後の拡大造林政策によってスギは大量に植樹され(面積は戦前の3倍ともされる)、全森林面積の18%にも達するようになったため、スギ花粉はもっとも頻度が高い花粉アレルゲンとなっていると考えられている[262][38][263]。スギ花粉症の急激な増加は、この時期に大量に植栽されたスギが、花粉を大量に散布する樹齢に達したからともされる[38][263]。そのほかにも、大気汚染の増大、食生活の変化、抗生物質の使用など、他の要因も大きく関わっていると考えられている[263]。
現在では、花粉発生源対策としてスギ人工林の伐採・利用、花粉が少ないまたは花粉を産生しない株の育種や植え替えが進められている[34][38]。ただしこれには極めて長い期間がかかると考えられており、あわせて花粉飛散防止剤など花粉飛散抑制技術の開発も進められている[34]。
分類
中国南部の浙江省(天目山)、福建省(南平市)、江西省(廬山)、四川省、雲南省にはカワイスギとよばれるスギ属の植物が分布しており[270]、スギとは別種(Cryptomeria fortunei)とされることもあるが[271]、ふつうスギの変種(Cryptomeria japonica var. sinensis)とされる[16][272][46]。形態的には、葉が細く著しく内曲し、枝に対する角度が浅く、雄球花は基部の葉よりも短く、種鱗先端の歯牙があまり尖らず、果鱗は約20個でそれぞれ2個の種子をつける点で基準変種(Cryptomeria japonica var. japonica)と異なるとされる[16][19][27]。形態的および遺伝的に日本に分布するスギの変異内に含まれ全て植栽に由来するとされたこともあるが[6][273][274][55]、詳細な解析からは、中国と日本のスギは遺伝的に明瞭に区分できることが示されている[45][275]。日本産のスギにくらべて、中国産のスギの遺伝的多様性は低いが、集団間の遺伝的分化は大きい[45][275][46]。また、中国には日本産スギに由来するものも少数存在することが示されている[275][46]。
日本の太平洋側と日本海側のスギでは、形態的・生態的に異なる傾向があり、太平洋側のものはオモテスギ(表杉、omote-sugi)、日本海側のものはウラスギ(裏杉、ura-sugi)とよばれる[15][7][26][45][276][277][278]。ウラスギは、下部の太枝が雪をかぶっても折れずに垂れ下がり、接地した部分から発根して新しい株を形成する[16][7]。またオモテスギにくらべて、切り株などから萌芽しやすい、枝葉が密生して狭い円錐形の樹冠、太枝が下向き、樹皮が赤褐色で縦に細長く剥離、葉が小型で開度が狭い、球果の付属片が短く全体が丸みを帯びる、低温と乾燥に弱いなどの傾向がある[15][7][19][71]。京都大学の芦生研究林で採集された典型的なウラスギの標本を基に、変種として Cryptomeria japonica var. radicans Nakai (1941)[6] が記載され、和名ではアシウスギ(芦生杉)ともよばれる[15][16][279]。2025年現在、ウラスギ(アシウスギ、サワスギ)は変種または品種として基準変種または品種であるオモテスギと分けて扱われることが多い[45][15][16][279]。また、遺伝的な調査からも、日本産のスギがオモテスギ系とウラスギ系に分かれること、さらに前者が屋久島集団とそれ以外からなる集団、後者が最北部の集団とそれ以外からなる集団に分けられることが示されている[54][45]。
上記のように、一般的にスギはスギ属の唯一の現生種とされる。スギ属は、ふつうスギ科に分類されていた[14][15]。しかし分子系統学的研究によりスギ科とヒノキ科は分けられないことが示され、21世紀になるとスギ科はヒノキ科に含められるようになり、スギ属はヒノキ科に分類されるようになった[16][6]。現生のヒノキ科の中では、スギ属はスイショウ属やヌマスギ属に近縁であり、この3属は併せてスギ亜科(Taxodioideae)に分類される[2]。
スギ属の化石記録は始新世に遡り、カムチャッカ半島から Cryptomeria kamtschatica が報告されている[55][280][270]。中新世から鮮新世には、ユーラシアの中緯度から高緯度地域に、多くはないが広く分布していたと考えられている[55][280]。ヨーロッパ中部では、湿地植生を構成していた[32]。やがて分布が縮小し、現在では自生のものは日本と中国南部に生き残っている[32]。
- ヒノキ科 Cupressaceae Gray (1822), nom. cons.
- スギ亜科 Taxodioideae K.Koch
- スギ属 Cryptomeria D.Don (1839)
- †Cryptomeria kamtschatica Cheleb. (1991)
- †Cryptomeria yunnanensis W.N.Ding & Z.K.Zhou (2018)
- †Cryptomeria protojaponica Klimova (1975)
- †Cryptomeria sichotensis Pimenov (1984)
- 漸新世(ロシア沿海地方)
- †Cryptomeria miyataensis Uemura (1973)
- 中新世(日本)
- †Cryptomeria rhenana Kilpper (1972)
- 中新世から鮮新世(ヨーロッパ)
- †Cryptomeria anglica Boulter (1970)
- 中新世から鮮新世(ヨーロッパ)
- スギ Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don (1839)
- 中新世から現世(日本、中国、†中央アジア)
- カワイスギ[282] Cryptomeria japonica var. sinensis Miq. (1870)[6]
- シノニム: Cryptomeria japonica subsp. sinensis (Miq.) P.D.Sell (1990)[6]; Cryptomeria japonica var. fortunei (Hooibr. ex Billain) A.Henry (1906)[6]; Cryptomeria fortunei Hooibr. ex Billain (1853)[6][283]; Cryptomeria kawaii Hayata (1917)[6][284]; Cryptomeria mairei (H.Lév.) Nakai (1937)[6][284]; Cupressus mairei H.Lév. (1916)[6][284]
- 中国南部
- ウラスギ(アシウスギ、サワスギ)[285] Cryptomeria japonica var. radicans Nakai (1941)[6]
- オモテスギ Cryptomeria japonica var. japonica
- 日本(太平洋側)
- スギ属 Cryptomeria D.Don (1839)
- スギ亜科 Taxodioideae K.Koch
脚注
注釈
- ^ イチイ科などとともにヒノキ目に分類されるが[2][3]、マツ科(およびグネツム類)を加えた広義のマツ目(Pinales)に分類することもある[4]。
- ^ a b スギはふつうスギ科に分類されていた[14][15]。しかし21世紀になるとスギ科はヒノキ科に含められるようになり、スギはヒノキ科に分類されるようになった[16][6]。
- ^ 一般的にはコウヤマキやイヌマキを意味するが、スギやヒノキを意味することもある[12]。
- ^ "雄花"ともよばれるが、厳密には花ではなく小胞子嚢穂(雄性胞子嚢穂)とされる[35]。雄球花のほか、雄性球花や雄性球果ともよばれる[36][37]。
- ^ "雌花"ともよばれるが、厳密には花ではなく大胞子嚢穂(雌性胞子嚢穂)とされる[35][36]。送受粉段階の胞子嚢穂は球花とよばれ、成熟し種子をつけた大胞子嚢穂は下記のように球果とよばれる[36]。
- ^ このほかに分子量約 27 kDa のタンパク質が報告されており、Cry j 3 とよばれる[269]。
出典
- ^ Thomas, P., Katsuki, T. & Farjon, A. (2013年). “Cryptomeria japonica”. The IUCN Red List of Threatened Species 2009. IUCN. 2023年12月15日閲覧。
- ^ a b c Stevens, P. F. (2001 onwards エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “Cupressales”. Angiosperm Phylogeny Website. 2023年2月20日閲覧。
- ^ 米倉浩司・邑田仁 (2013). 維管束植物分類表. 北隆館. p. 44. ISBN 978-4832609754
- ^ 大場秀章 (2009). 植物分類表. アボック社. p. 18. ISBN 978-4900358614
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2023年4月29日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw “Cryptomeria japonica”. Plants of the World Online. Kew Botanical Garden. 2023年12月16日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp 「スギ(杉)」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2023年12月16日閲覧。
- ^ 『牧野日本植物圖鑑』北隆館、1940年。
- ^ 「須疑」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2024年2月2日閲覧。
- ^ a b 「真木」。コトバンクより2023年12月16日閲覧。
- ^ a b 「槙」。コトバンクより2023年12月16日閲覧。
- ^ a b c 「槇」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2024年1月20日閲覧。
- ^ “Japanese cedar”. Britanica. 2024年2月3日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 中川重年 (2000). “スギ”. 樹に咲く花 合弁花・単子葉・裸子植物. 山と渓谷社. pp. 612–615. ISBN 978-4635070058
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 鈴木三男 (1997). “スギ”. 週刊朝日百科 植物の世界 11. pp. 204–207. ISBN 9784023800106
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 大橋広好 (2015). “スギ属”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 1. 平凡社. p. 38. ISBN 978-4582535310
- ^ a b c d 綱本逸雄 (2014). “杉の語源”. 月刊 杉 web版 100.
- ^ 「杉」『デジタル大辞泉』。コトバンクより2023年12月16日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 濱谷稔夫・所三男・飯島吉晴 (1989). “スギ”. In 堀田満ほか. 世界有用植物事典. 平凡社. pp. 331–334. ISBN 9784582115055
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003- エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “BG Plants 和名-学名インデックス」(YList)”. 2023年12月16日閲覧。
- ^ アズキナシ (カタスギ) 北海道森林管理局 2021年3月24日閲覧
- ^ 鈴木雅大 (2011年11月18日). “スギノリ Chondracanthus tenellus”. 2023年12月27日閲覧。
- ^ a b c d 宮内泰之 監修、成美堂出版 編『見わけがすぐつく樹木図鑑』成美堂出版、2023年5月20日、57頁。 ISBN 978-4-415-33237-6。
- ^ a b c d e f g h 田中潔 (2011). 知っておきたい100の木:日本の暮らしを支える樹木たち. 主婦の友社〈主婦の友ベストBOOKS〉. pp. 108–109. ISBN 978-4-07-278497-6
- ^ a b c “花脊の三本杉 樹高測定結果”. 林野庁 (2017年11月28日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ a b c d e 平野隆久監修 永岡書店編 (1997). “286”. 樹木ガイドブック. 永岡書店. p. 286. ISBN 4-522-21557-6
- ^ a b c d e f Flora of China Editorial Committee. “Cryptomeria japonica”. Flora of China. Missouri Botanical Garden and Harvard University Herbaria. 2025年5月22日閲覧。
- ^ a b c d 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2014). 樹皮と冬芽:四季を通じて樹木を観察する 431種. 誠文堂新光社〈ネイチャーウォチングガイドブック〉. p. 245. ISBN 978-4-416-61438-9
- ^ a b c d e f g h i j k l 中川重年 (1994). “スギ”. 検索入門 針葉樹. 保育社. pp. 56–57. ISBN 978-4586310395
- ^ “スギヒノキの新葉と葉の寿命(5月)”. 森林総合研究所 多摩森林科学園. 2023年12月27日閲覧。
- ^ a b 菊池秀夫 (1997). “スギ針葉の冬季における色調の遺伝”. 森林総合研究所研究報告 (374): 31-57. CRID 1050001338650822656.
- ^ a b c d “スギ”. 植物図鑑. 筑波実験植物園. 2023年12月27日閲覧。
- ^ a b c d e f g h 横山敏孝 (1975). “スギにおける胚の形成と球果の成長”. 林試研報 (277): 1-20. CRID 1573668923884992128.
- ^ a b c d e “森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するQ&A”. 林野庁. 2023年12月28日閲覧。
- ^ a b 長谷部光泰 (2020). 陸上植物の形態と進化. 裳華房. p. 205. ISBN 978-4785358716
- ^ a b c 清水建美 (2001). 図説 植物用語事典. 八坂書房. p. 260. ISBN 978-4896944792
- ^ アーネスト M. ギフォード、エイドリアンス S. フォスター『維管束植物の形態と進化 原著第3版』長谷部光泰、鈴木武、植田邦彦監訳、文一総合出版、2002年4月10日、332–484頁。 ISBN 4-8299-2160-9。
- ^ a b c d e 辻井達一『続・日本の樹木』中央公論新社〈中公新書〉、2006年2月25日、31–34頁。 ISBN 978-4121018342。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq 高桑進 (2012). “杉と日本人のつながりについて”. 京都女子大学宗教・文化研究所 研究紀要 (25): 19-40. CRID 1050845762507665664.
- ^ a b 森孝博. “スギ精油の採取方法及びその成分”. 岐阜県森林研究所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ 宮越順二, 松原恵理, 成田英二郎, 小山眞, 清水陽子 & 川井秀一 (2018). “スギ抽出物による熱ショックタンパク発現誘導の抑制効果”. 薬学雑誌 138 (1): 97-106.
- ^ “北限の天然杉:東北森林管理局”. www.rinya.maff.go.jp. 2025年3月19日閲覧。
- ^ “ヤクスギ”. www.forest.kyushu-u.ac.jp. 2025年8月26日閲覧。
- ^ 辻井達一『日本の樹木』中央公論社〈中公新書〉、1995年4月25日、43–47頁。 ISBN 4-12-101238-0。
- ^ a b c d e f g h i Tsumura, Y. (2023). “Genetic structure and local adaptation in natural forests of Cryptomeria japonica”. Ecological Research 38 (1): 64-73. doi:10.1111/1440-1703.12320.
- ^ a b c d Cai, M., Wen, Y., Uchiyama, K., Onuma, Y., & Tsumura, Y. (2020). “Population genetic diversity and structure of ancient tree populations of Cryptomeria japonica var. sinensis based on RAD-seq data”. Forests 11 (11): 1192. doi:10.3390/f11111192.
- ^ a b c d e f g h “スギ”. 北海道立総合研究機構 森林研究本部 林産試験場. 2023年12月27日閲覧。
- ^ “スギ若齢人工林のヒバ混交林への誘導について”. 林野庁 (1997年 - 2011年). 2025年5月29日閲覧。
- ^ “森林・ 林業 森を育てる 森を引き継ぐ”. 青森県庁. 2025年5月29日閲覧。
- ^ 沖縄県. “スギ|沖縄県公式ホームページ”. 沖縄県公式ホームページ. 2025年7月25日閲覧。
- ^ a b 田中淳夫 (2016年3月9日). “スギ花粉は世界中に舞っていた!”. Yahoo!JAPANニュース. 2016年3月12日閲覧。
- ^ a b c 田島正啓 (2002年5月1日). “ポルトガル共和国アゾレス諸島のスギ” (PDF). 林木育種センターだより(2000年1月). 林野庁・林木育種センター. p. 3. 2016年3月12日閲覧。
- ^ a b c 高桑進 (2013). “杉から見た日本列島の森林について”. 京都女子大学宗教・文化研究所 研究紀要 (26): 69-92. CRID 1050282812552810496.
- ^ a b 津村義彦 (2012). “シリーズ: 日本の森林樹木の地理的遺伝構造 (1) スギ (ヒノキ科スギ属)”. 森林遺伝育種 1 (1): 17-22. doi:10.32135/fgtb.1.1_17.
- ^ a b c d Yabe, A., Jeong, E., Kim, K. & Uemura, K. (2019). “Oligocene–Neogene fossil history of Asian endemic conifer genera in Japan and Korea”. Journal of Systematics and Evolution 57 (2): 114-128. doi:10.1111/jse.12445.
- ^ a b 中川重年 (1994). “3. 日本の針葉樹”. 検索入門 針葉樹. 保育社. pp. 159–167. ISBN 978-4586310395
- ^ a b c 田中惣一. “土砂災害を防ぐ森づくり”. 一般社団法人TOKYO WOOD普及協会. 2023年12月28日閲覧。
- ^ 鈴木和夫・福田健二 (2012). “スギ属”. 図説日本の樹木. 朝倉書店. pp. 40–41. ISBN 978-4254171495
- ^ 冨沢日出夫・丸山幸平 (1993). “佐渡島のスギ天然林における実生更新の可能性”. 日本林学会誌 75 (5): 460–462. doi:10.11519/jjfs1953.75.5_460.
- ^ Suzuki, E. (1996). “The dynamics of old Cryptomeria japonica forest on Yakushima Island”. Tropics 6 (4): 421–428. doi:10.3759/tropics.6.421.
- ^ 太田敬之・杉田久志・金指達郎・正木隆 (2015). “スギ天然生林におけるスギ実生の分布と生存 ―出現基質間の比較―”. 日本森林学会誌 97 (1): 10–18. doi:10.4005/jjfs.97.10.
- ^ Wang, B. & Qiu, Y. L. (2006). “Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizas in land plants”. Mycorrhiza 16 (5): 299-363. doi:10.1007/s00572-005-0033-6.
- ^ 畑邦彦・木本遼太郎・曽根晃一 (2018). “スギ成木および実生におけるアーバスキュラー菌根菌の感染率の季節変化”. 日本林学会誌 100 (1): 3–7. doi:10.4005/jjfs.100.3.
- ^ Lee, I. K. (1963). “Ecological studies on Pinus densiflora forest 1. Effect of plant substances on the floristic composition of the undergrowth”. Bot. Mag. Tokyo 76 (905): 400-413. doi:10.15281/jplantres1887.76.400.
- ^ 高橋輝昌・鷲辺章宏・浅野義人・小林達明 (1998). “木本類における他感作用”. ランドスケープ研究 62 (5): 525–528. doi:10.5632/jila.62.525.
- ^ 岡部宏秋 (1994). “外生菌根菌の生活様式 (共生土壌菌類と植物の生育)”. 土と微生物 24: 15–24. doi:10.18946/jssm.44.0_15.
- ^ 澤田智志・加藤秀正 (1991). “スギおよびヒノキ林の林齢と土壌中の塩基の蓄積との関係”. 日本土壌肥料学雑誌 62 (1): 49–58. doi:10.20710/dojo.62.1_49.
- ^ 平英彰 (1994). “タテヤマスギの更新形態について”. 日本林学会誌 76 (6): 547–552. doi:10.11519/jjfs1953.76.6_547.
- ^ 川尻秀樹・安江保民・大橋英雄・中川一 (1989). “岐阜県板取村のカブスギ集団の実態”. 日本林学会誌 71 (5): 204–208. doi:10.11519/jjfs1953.71.5_204.
- ^ 酒井昭 (1977). “植物の積雪に対する適応”. 低温科学生物編 34: 47–78. hdl:2115/17828.
- ^ a b 武藤惇・堀内孝雄 (1974). “スギ種子産地と寒害抵抗性”. 日本林学会誌 56 (6): 210–215. doi:10.11519/jjfs1953.56.6_210.
- ^ 石沢進 (1985). “植物の分布と積雪 ―新潟県およびその周辺地域について―”. 芝草研究 14 (1): 10–23. doi:10.11275/turfgrass1972.14.10.
- ^ 中静透 (2003). “冷温帯林の背腹性と中間温帯論”. 植生史研究 11 (2): 39–43. doi:10.34596/hisbot.11.2_39.
- ^ a b 大庭喜八郎 (1972). “メアサ, キリシマメアサおよびアオスギのミドリスギ劣性遺伝子”. 日本林学会誌 54 (1): 1–5. doi:10.11519/jjfs1953.54.1_1.
- ^ 向井譲 (2004). “低温条件下で樹木が受ける光ストレスとその防御機能”. 日本林学会誌 86 (1): 48–53. doi:10.11519/jjfs1953.86.1_48.
- ^ 丸田恵美子・中野隆志 (1999). “中部山岳地域の亜高山帯針葉樹と環境ストレス (<特集>中部山岳地域の高山・亜高山帯における植物群落の現状と将来)”. 日本生態学会誌 49 (3): 293–300. doi:10.18960/seitai.49.3_293.
- ^ 宇梶徳史・原登志彦 (2007). “Expressed sequence tags (EST)から見た樹木の越冬戦略”. 日本生態学会誌 57 (1): 89–99. doi:10.18960/seitai.57.1_89.
- ^ 青木正則・石川春彦 (1971). “スギ品種の耐塩性の差異について”. 日本林学会誌 53 (4): 108–112. doi:10.11519/jjfs1953.53.4_108.
- ^ 津村義彦 (2012). “日本の森林樹木の地理的遺伝構造(1)スギ(ヒノキ科スギ属)”. 森林遺伝育種 1 (1): 17–22. doi:10.32135/fgtb.1.1_17.
- ^ a b c “日本植物病名データベース”. 農業生物資源ジーンバンク. 2023年9月12日閲覧。
- ^ a b c 窪野高徳 & 市原優 (2004). “スギ枝枯菌核病とスギ褐点枝枯病の同根関係”. 日本林學會誌 86 (2): 164-167. doi:10.11519/jjfs1953.86.2_164.
- ^ a b c d e f g h i j k “森林生物情報データ一覧”. 森林総合研究所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ “自然探訪2019年9月 スギの大敵 ―赤枯病―”. 森林総合研究所 (2019年9月2日). 2023年1月3日閲覧。
- ^ a b 安藤裕萌 & 升屋勇人「スギ赤枯病研究の現状と課題」『日本森林学会誌』第102巻第1号、2020年、44-53頁、doi:10.4005/jjfs.102.44。
- ^ a b “スギ溝腐病”. 森林生物情報データ一覧. 森林総合研究所. 2023年12月16日閲覧。
- ^ “非赤枯性溝腐病”. 千葉県. 2023年12月16日閲覧。
- ^ 幸由利香, 寺嶋芳江, 岩澤勝巳, 福島成樹 & 遠藤良太 (2014). “非赤枯性溝腐病と病原菌チャアナタケモドキに関する最近の知見”. 千葉県農林総合研究センター研究報告 6: 125-131. CRID 1050001338752513408.
- ^ a b c “スギ黒点枝枯病”. 森林総合研究所 九州支所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ 古野東洲・中井勇・里見武志 (1993). “スギドクガに食害されたスギの生育”. 日本林学会関西支部論文集 2: 193–196. doi:10.20660/safskansai.2.0_193.
- ^ 柴田叡弌・西口陽康 (1980). “大発生時のスギドクガ幼虫密度と被害葉量について”. 日本林学会誌 60 (2): 398–401. doi:10.11519/jjfs1953.62.10_398.
- ^ a b c d e f g “スギの害虫”. 北海道立総合研究機構 森林研究本部 林業試験場 (2011年8月22日). 2023年12月22日閲覧。
- ^ 柴田叡弌 (2002). “スギカミキリのスギ樹幹利用様式(<特集>穿孔性昆虫の樹幹利用様式)”. 日本生態学会誌 52 (1): 59–62. doi:10.18960/seitai.52.1_59.
- ^ 伊藤賢介 (2002). “スギカミキリに対するスギの抵抗性反応(<特集>穿孔性昆虫の樹幹利用様式)”. 日本生態学会誌 52 (1): 63–68. doi:10.18960/seitai.52.1_63.
- ^ 斎藤諦 (1960). ““とびくされ”に開係のある3種のカミキリムシ”. 日本林学会誌 42 (12): 454–457. doi:10.11519/jjfs1953.42.12_454.
- ^ 長島啓子・土田遼太・岡本宏之・高田研一・田中和博 (2014). “三重県大台町におけるスギノアカネトラカミキリ被害と立地環境および成長との関係 ―立地環境に基づく林業適地の抽出にむけて―”. 日本森林学会誌 96 (6): 308–314. doi:10.4005/jjfs.96.308.
- ^ a b c “「スギ原木を加害する穿孔性昆虫」防除の手引き”. 富山県農林水産総合技術センター 森林研究所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ “スギザイノタマバエ”. 森林総合研究所 九州支所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ 石川忠 & 守屋成一 (2019). “日本産チャバネアオカメムシ類の最新の分類”. 植物防疫 73 (4): 220-224.
- ^ 佐藤平典, 伊藤松男 & 柏実 (1981). “スギ採種園における球果害虫の防除”. 岩手県林業試験場成果報告 (14): 7-13. CRID 1050564288530934912.
- ^ 片桐奈々. “スギ・ヒノキの大害虫カメムシ”. 岐阜県森林研究所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ 大橋章博. “球果と果樹の害虫 チャバネアオカメムシ”. 岐阜県森林研究所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ 岡本卓也. “樹皮剥ぎの見分け方”. 岐阜県森林研究所. 2023年12月21日閲覧。
- ^ a b “京都の杉が高さ日本一 62.3メートルと確認”. 日本経済新聞. (2017年11月28日)
- ^ 大場秀章 (1997). “「縄文杉」は何歳?”. 週刊朝日百科 植物の世界 11. p. 206. ISBN 9784023800106
- ^ “Cryptomeria japonica”. The Gymnosperm Database. 2023年12月22日閲覧。
- ^ a b c d e “屋久杉ってなあに?”. 屋久杉自然館. 2023年12月26日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi “日本全国の杉”. 森林・林業学習館. 2023年12月23日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m “屋久杉巨樹・著名木”. 屋久杉自然館. 2023年12月26日閲覧。
- ^ a b “国指定文化財等データベース”. 文化庁. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “文化遺産データベース”. 文化遺産オンライン. 文化庁. 2024年2月22日閲覧。
- ^ “精進の大杉(しょうじのおおすぎ)”. 公益社団法人やまなし観光推進機構. 2025年5月20日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k 鈴木三男 (1997). “スギ材の利用と文化”. 週刊朝日百科 植物の世界 11. pp. 211–212. ISBN 9784023800106
- ^ a b c d e f g h “スギ 杉、椙”. 木材の種類と特性. 一般財団法人 日本木材総合情報センター. 2023年12月23日閲覧。
- ^ a b c d e f “スギ(杉)”. 東京木材問屋協同組合. 2023年12月23日閲覧。
- ^ 藤原新二・岩神正朗 (1988)スギおよびヒノキ材の生材含水率. 高知大学学術研究報告37, pp. 169 - 178. hdl:10126/1885
- ^ 中田了五 (2014) 樹木のwetwood 現象と定義, 木材学会誌60(2), pp. 63 - 79. doi:10.2488/jwrs.60.63
- ^ 中田了五, 藤沢義武, 平川泰彦, 山下香菜: スギの生材含水率の個体内樹高方向での変化. 木材学会誌 44(6):395–402 (1998)
- ^ a b c “スギ”. 木材図鑑. 府中家具工業協同組合. 2024年2月16日閲覧。
- ^ a b c 中川重年 (1994). “5. 人の生活との関わり”. 検索入門 針葉樹. 保育社. pp. 174–183. ISBN 978-4586310395
- ^ 大脇潔「〈隠岐・山陰沿岸の民俗〉隠岐・出雲甍紀行 : 杉皮葺きと左桟瓦・石州瓦」『民俗文化』第23号、近畿大学民俗学研究所、2011年6月、1-80頁、 CRID 1050001202545583744、 ISSN 09162461。
- ^ a b 「酒林」『デジタル大辞泉』。コトバンクより2023年12月25日閲覧。
- ^ a b “新酒完成で「杉玉」掛け替え 飛騨市の酒造会社”. 岐阜 NEWS WEB. NHK (2023年11月1日). 2023年12月25日閲覧。
- ^ a b c “酒蔵にある杉玉、どんな意味?杉玉の意味や由来について”. 酒みづき. 沢の鶴株式会社 (2022年11月4日). 2023年12月25日閲覧。
- ^ a b “お線香の香り(匂い)は何がある?煙の少ないお線香からおすすめ品まで紹介”. お仏壇のはせがわ (2022年5月11日). 2023年12月23日閲覧。
- ^ 久田善純. “スギのオガ粉を使ったキノコ栽培について”. 岐阜県森林研究所. 2023年12月22日閲覧。
- ^ “スギヒラタケ”. 林野庁. 2023年12月23日閲覧。
- ^ 酒井惇一 (2023年4月20日). “花粉症と杉鉄砲”. 農業共同組合新聞. 農協協会. 2023年12月23日閲覧。
- ^ 中川重年 & 数田敏雄 (1983). “神奈川県林業試験場樹木園目録”. 神奈川県林業試験場研究報告 (9): 59-77. CRID 1520291855754482688.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y 渡邊定元 (1997). “スギの林業史”. 週刊朝日百科 植物の世界 11. pp. 210–211. ISBN 9784023800106
- ^ a b c d “日本の林業の現状”. 森林・林業学習館. 2023年12月28日閲覧。
- ^ 榎本善夫 (1949). “挿スギに見られた根及び癒傷組織発達の林業品種による差異に就いて”. 東京大学農学部演習林報告 37: 11–18. hdl:2261/23336.
- ^ 宮島寛 (1951). “スギの挿木に於ける発根と品種との関係に就て”. 九州大學農學部學藝雜誌 13 (1/4): 277–281. doi:10.15017/21238.
- ^ 石川広隆・田中郁太郎 (1970). “発根困難なスギ精英樹のさし木に及ぼすインドール酪酸の効果”. 日本林学会誌 52 (3): 99–101. doi:10.11519/jjfs1953.52.3_99.
- ^ 大山浪雄・上中久子 (1970). “発根困難なスギ,ヒノキの精英樹のさし木に対するエクベロン(インドール酪酸)の効果”. 日本林学会誌 52 (12): 374–376. doi:10.11519/jjfs1953.52.12_374.
- ^ 阿部正博・今井元政・島田一美 (1957). “電熱温床によるスギ老令樹さし木試験”. 日本林学会誌 39 (6): 245–248. doi:10.11519/jjfs1953.39.6_245.
- ^ 武田英文 (1971). “伝熱温床による秋田スギさし木試験 (会員研究発表講演)”. 日本林學會北海道支部講演集 19: 99–102. doi:10.24494/jfshc.19.0_99.
- ^ 宮下智弘 (2007). “多雪地帯に植栽されたスギ挿し木苗と実生苗の幼齢期における成育特性の比較”. 日本森林学会誌 89 (6): 369–373. doi:10.4005/jjfs.89.369.
- ^ a b “北山杉story”. 京都北山丸太生産協同組合. 2023年12月30日閲覧。
- ^ “国産材総合情報館”. 株式会社エコリフォーム. 2023年12月23日閲覧。
- ^ “東濃杉”. 株式会社エコリフォーム. 2024年1月27日閲覧。
- ^ “飛騨杉”. 株式会社エコリフォーム. 2024年1月27日閲覧。
- ^ 村山忠親、村山元春 (2020). “スギ”. 新版・原色木材大事典200種:日本で手に入る木材の基礎知識を網羅した決定版. 誠文堂新光社. pp. 12–15. ISBN 978-4416620168
- ^ “紀州杉”. 株式会社エコリフォーム. 2024年1月27日閲覧。
- ^ “八郎杉”. 広島県. 2024年1月27日閲覧。
- ^ “徳島杉”. 株式会社エコリフォーム. 2024年1月27日閲覧。
- ^ “相生杉”. 株式会社エコリフォーム. 2024年1月27日閲覧。
- ^ 山岸健三. “美しいスギ・ヒノキ林が「緑の砂漠」って、どういうこと?”. 名城大学. 2023年12月28日閲覧。
- ^ カメ五郎. “のんびり移住生活日誌”. Firlder 69: 9.
- ^ “保安林の種類別の指定目的”. 林野庁. 2023年12月28日閲覧。
- ^ “森林の適切な整備・保全”. 林野庁. 2023年12月28日閲覧。
- ^ 本山芳裕 (1996). “水源地域の森林の整備について”. 水利科学 40 (2): 1-16. doi:10.20820/suirikagaku.40.2_1.
- ^ “水源林造成事業の施業指針”. 森林整備センター. 2023年12月28日閲覧。
- ^ 苅住昇一 (1979). 樹木根系図鑑. 誠文堂新光社
- ^ 信州大学農学部森林科学科教授 北原曜 (2002年5月1日). “土砂災害に強い森林づくりに向けて” (PDF). 長野県. p. 2. 2016年3月12日閲覧。
- ^ 藤山宏『プロが教える住宅の植栽』学芸出版社、2010年、9頁。
- ^ 矢澤大二 (1936). “東京近郊に於ける防風林の分布に關する研究 (1)”. 地理学評論 12 (1): 47–66. doi:10.4157/grj.12.47.}
- ^ 王聞・深町加津枝 (2020). “砺波平野における典型的な屋敷林の植物相および周囲の水系の利用”. 日本緑化工学会誌 46 (1): 154–157. doi:10.7211/jjsrt.46.154.
- ^ 不破正仁・藤川昌樹 (2011). “栃木県都賀地域における北方系屋敷林の原型とその変容実態 ‐明治期銅版画と現状との比較分析に基づいて‐”. 日本建築学会計画系論文集 76 (666): 1407–1414. doi:10.3130/aija.76.1407.
- ^ 「垣入」『デジタル大辞泉』。コトバンクより2024年2月7日閲覧。
- ^ “日光杉並木街道”. 日光市観光協会. 2023年12月30日閲覧。
- ^ “元箱根旧街道杉並木”. 箱根町総合観光案内所. 2023年12月30日閲覧。
- ^ “戸隠神社奥社参道の杉並木”. 長野市. 2023年12月30日閲覧。
- ^ 大澤毅守 (1997). “ヒノキ”. 週刊朝日百科 植物の世界 11. pp. 181–184. ISBN 9784023800106
- ^ a b “万葉百科”. 奈良県立万葉文化館. 2023年12月18日閲覧。
- ^ 「験の杉」『精選版 日本国語大辞典』。コトバンクより2023年12月20日閲覧。
- ^ “市区町村のシンボル”. 都道府県市区町村. 2023年12月31日閲覧。
- ^ a b c d e “各都道府県のシンボル”. 全国知事会. 2023年12月23日閲覧。
- ^ a b c “北海道と道内各市町村の木と花をご紹介します”. 北海道. 2023年12月23日閲覧。
- ^ “知内町のシンボル”. 知内町. 2023年12月23日閲覧。
- ^ “陸前高田市のプロフィール”. 陸前高田市 (2022年6月27日). 2023年12月23日閲覧。
- ^ “町の概要”. 雫石町 (2022年6月27日). 2023年12月23日閲覧。
- ^ “町の概要”. 金ケ崎町 (2022年6月27日). 2023年12月23日閲覧。
- ^ “町の概要”. 平泉町. 2023年12月23日閲覧。
- ^ “住田町の花、鳥、木”. 2023年12月23日閲覧。
- ^ “町の概要”. 山田町 (2021年3月12日). 2023年12月23日閲覧。
- ^ “登米市の花鳥木”. 登米市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の概要”. 丸森町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町章・木・花”. 涌谷町 (2020年1月1日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “女川の魅力”. 女川町観光協会. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “おがしのはな・とり・き・さかな”. 男鹿市 (2021年3月31日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市章・市の花・市の木”. 大館市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市章・市の花・市の木”. にかほ市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の概要”. 五城目町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “村の花、村の木、村の鳥を定める告示”. 上小阿仁村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “東成瀬村の概要”. 東成瀬村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町政概要”. 大江町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “村の概要”. 戸沢村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市の「市章」・「花・木・鳥・魚・昆虫」”. 喜多方市 (2016年1月4日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “まちのシンボル”. 塙町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町のすがた”. 石川町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “古殿町ってどんなところ?”. 古殿町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “シンボル・歴史”. 楢葉町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の概要”. 小野町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市の紹介”. 鹿沼市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市貝町の花・木・鳥”. 市貝町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市章、市民憲章、市の木・花・鳥について”. 安中市 (2023年7月18日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町のシンボル”. 下仁田町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “村の木・花・鳥”. 南牧村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “村のシンボル・憲章”. 榛東村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “飯能市の紹介”. 飯能市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の花・町の木”. 杉戸町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “山武市市章”. 山武市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “杉並区のプロフィール”. 杉並区. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “青梅市の市章・木・花・鳥”. 青梅市 (2019年10月28日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町章・木・花・鳥”. 奥多摩町 (2022年4月1日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “加茂市の市章、木、花”. 加茂市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “阿賀町の概要”. 阿賀町 (2021年6月1日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市の花、木、花木、鳥が決まりました。”. 砺波市 (2018年3月26日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市章・市指定花木”. 小矢部市 (2023年3月6日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “立山町の位置・地形・地理”. 立山町 (2023年3月6日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “加賀市の花・木・鳥”. 加賀市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “勝山市の木、花”. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “福島県池田町 町勢要覧資料編”. 池田町 (2021年1月). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “山梨県道志村議会 議会の概要”. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “シンボルの紹介”. 須坂市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “広報ねば Vol.216”. 根羽村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “ようこそ!『健康文化都市』裾野市へ”. 裾野市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町章・憲章 町の花・木・鳥・歌”. 東栄町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市の木「杉」”. 関市 (2014年2月3日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町章と町民憲章”. 関ケ原町 (2023年2月27日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市章、市の花・木”. 亀山市 (2021年3月23日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市の花、市の木、市の鳥、市の花木の指定”. 熊野市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “新宮市の紹介・市の花・市の木”. 新宮市. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の沿革・概要”. 印南町 (2023年6月27日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “古座川町のシンボル”. 古座川町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “甲賀市の花・木・鳥”. 甲賀町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “まちのおしらせ 広報たが No.912”. 多賀町 (2023年8月). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の花・木・鳥”. 和束町 (2021年4月1日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “市の紹介(市の木・市の花)”. 桜井市 (2022年3月1日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “下市町の概要”. 下市町 (20160-02-23 エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “吉野町の概要”. 吉野町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “曽爾村を知る”. 曽爾村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “御杖村について”. 御杖村 (2023年4月1日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “黒滝村”. 黒滝村 (2023年3月). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “広報 てんかわ No.365”. 天川村 (2007年6月30日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “川上村のプロフィール”. 川上村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “村の概要”. 十津川村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町のシンボル”. 豊能町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “智頭町について”. 智頭町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の「花」「木」「鳥」”. 日野町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町章、町花・町木”. 隠岐の島町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “新庄村の概要”. 新庄村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “村の概要”. 西粟倉村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “位置・地勢、歴史・沿革について”. 神山町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町歌・町章・町花・町木”. 久万高原町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “地勢・概要”. 大豊町 (2015年6月15日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “土佐町 町勢要覧2021”. 土佐町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “田野町のご紹介”. 田野町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ a b c d “高知市町村便覧”. 高知県市町村振興協会. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の概要”. 篠栗町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町章、町の木・花・鳥”. 大津町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “きくようまちってこんなとこ”. 菊陽町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “町の位置と地勢・町章・町の木・花・鳥”. 南小国町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “小国町について”. 小国町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “津奈木町の紹介”. 津奈木町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “水上村の紹介”. 水上村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “山江村の村鳥・村花・村木”. 山江村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “球磨村について”. 球磨村. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “飫肥杉”. 日南市 (2023年12月1日). 2023年12月26日閲覧。
- ^ “五ヶ瀬町について”. 五ヶ瀬町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ “屋久島町の概要”. 屋久島町. 2023年12月26日閲覧。
- ^ a b c d 「花粉症」。コトバンクより2023年12月29日閲覧。
- ^ a b c d e 平英彰, 吉井エリ & 寺西秀豊 (2004). “スギ雄花の花粉飛散特性”. アレルギー 53 (12): 1187-1194. doi:10.15036/arerugi.53.1187.
- ^ a b c 安枝浩 (2000). “スギ花粉症とスギ・ヒノキ科花粉のアレルゲン”. 日本花粉学会会誌 46: 29-38. CRID 1520290885512141184.
- ^ 王青躍, 大塚岳, 董詩洋, 石原数也, 呂森林 & 関口和彦 (2016). “携帯型エアサンプラーを用いた秋季における草本類花粉飛散量調査手法の検討”. 日本花粉学会会誌 61 (2): 49-55.
- ^ “北海道の花粉情報”. www.iph.pref.hokkaido.jp. 2025年5月28日閲覧。
- ^ 尾張敏章, 石井寛 & 間口四郎 (2001). “北欧におけるシラカンバ花粉症対策の現状”. 北海道大学農学部演習林研究報告 58 (1): 7–27. CRID 1050564288938337792.
- ^ “アレルギー総論”. 厚生労働省. 2024年1月4日閲覧。
- ^ Fujimura, T., Futamura, N., Midoro‐Horiuti, T., Togawa, A., Goldblum, R. M., Yasueda, H., ... & Sakaguchi, M. (2007). “Isolation and characterization of native Cry j 3 from Japanese cedar (Cryptomeria japonica) pollen”. Allergy 62 (5): 547-553. doi:10.1111/j.1398-9995.2007.01331.x.
- ^ a b c Ding, W. N., Kunzmann, L., Su, T., Huang, J. & Zhou, Z. K. (2018). “A new fossil species of Cryptomeria (Cupressaceae) from the Rupelian of the Lühe Basin, Yunnan, East Asia: Implications for palaeobiogeography and palaeoecology”. Review of Palaeobotany and Palynology 248: 41-51. doi:10.1016/j.revpalbo.2017.09.003.
- ^ Zhang, Y., Yang, J., Guo, Z., Mo, J., Cui, J., Hu, H. & Xu, J. (2020). “Comparative analyses and phylogenetic relationships between Cryptomeria fortunei and related species based on complete chloroplast genomes”. Phyton (Buenos Aires) 89 (4): 957-986. doi:10.32604/phyton.2020.011211.
- ^ “スギ Cryptomeria japonica ヒノキ科 Cupressaceae スギ属 三河の植物観察”. mikawanoyasou.org. 2022年3月17日閲覧。
- ^ 佐橋紀男、渡辺幹男、三好彰、程雷、殷敏「中国の天目山と日本の屋久島・伊豆大島産のスギの遺伝的特性」『耳鼻と臨床』第45巻6Supplement2、耳鼻と臨床会、1999年、630-634頁、 CRID 1390282680477923456、doi:10.11334/jibi1954.45.6supplement2_630、 ISSN 0447-7227。
- ^ Chen, Y., Yang, S. Z., Zhao, M. S., Ni, B. Y., Liu, L. & Chen, X. Y. (2008). “Demographic genetic structure of Cryptomeria japonica var. sinensis in Tianmushan nature reserve, China”. Journal of Integrative Plant Biology 50 (9): 1171-1177. doi:10.1111/j.1744-7909.2008.00725.x.
- ^ a b c Xu, H., Xie, W., Zhao, Z., Lin, C., Weng, H., Lin, X., ... & Liang, G. (2025). “Genotyping-by-sequencing reveals the genetic diversity of Cryptomeria japonica var. sinensis in southeastern China”. Pak. J. Bot. 57 (2): 677-684. doi:10.30848/PJB2025-2(36).
- ^ 高桑進・米澤信道・綱本逸雄・宮本水文 (2010). “日本列島におけるスギの分布状況と針葉の形態変化について”. 京都女子大学宗教・文化研究所研究紀要 23: 1–33. hdl:11173/1936.
- ^ 四手井綱英 (1957). “大阪営林局管内の天然生スギの系統の分布について”. 日本林学会誌 39 (7): 270–273. doi:10.11519/jjfs1953.39.7_270.
- ^ 齋藤秀樹・竹岡政治 (1987). “裏日本系スギ林の生殖器官生産量および花粉と種子生産の関係”. 日本生態学会誌 37 (3): 183–185. doi:10.18960/seitai.37.3_183.
- ^ a b 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don f. radicans (Nakai) Sugim. et Muroi”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2023年12月16日閲覧。
- ^ a b Manchester, S. R., CHEN, Z. D., LU, A. M. & Uemura, K. (2009). “Eastern Asian endemic seed plant genera and their paleogeographic history throughout the Northern Hemisphere”. Journal of Systematics and Evolution 47 (1): 1-42. doi:10.1111/j.1759-6831.2009.00001.x.
- ^ van Amerom, H. W. J. (1999). “Cryptomeria”. Fossilium Catalogus. II. Plantae. Pars 100. Backhuys Publishers. pp. 126–128. ISBN 90-5782-002-1
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don var. sinensis Siebold”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2025年5月21日閲覧。
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Cryptomeria fortunei”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2022年12月29日閲覧。
- ^ a b c Flora of China Editorial Committee. “Cryptomeria japonica var. sinensis”. Flora of China. Missouri Botanical Garden and Harvard University Herbaria. 2025年5月21日閲覧。
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Cryptomeria japonica (L.f.) D.Don var. radicans Nakai”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2025年5月21日閲覧。
関連項目
- 花粉症、スギ花粉症、無花粉杉
- 杉玉、集成材、間伐材、焼杉
- 赤枯病 - スギ赤枯病
- Category:杉
- 旧スギ科: コウヨウザン属、タイワンスギ属、タスマニアスギ属、メタセコイア属、セコイア属、セコイアデンドロン属、ヌマスギ属、スイショウ属
- ヘリンボーン (模様) - 杉綾・綾杉とも呼ばれる模様。
外部リンク
杉(すぎ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/09 04:31 UTC 版)
浅尾たちの隣のクラス。よく物を忘れる。前は倉田に借りていたが、浅尾と打ち解けてからは浅尾と貸し借りをする。だが、たまに人のものに落書きをする。興味がないものにはとことん興味がない。成績優秀。ハの字。
※この「杉(すぎ)」の解説は、「浅尾さんと倉田くん」の解説の一部です。
「杉(すぎ)」を含む「浅尾さんと倉田くん」の記事については、「浅尾さんと倉田くん」の概要を参照ください。
杉
「杉」の例文・使い方・用例・文例
- 杉の花粉が花粉症の主な元凶だ
- 私は杉並区に住んでいます。
- 学校見学のために杉並区へ行った。
- 杉並区に住んでいます。
- 私はこの光景は杉山でよく見る。
- 私たちは縄文杉を見に行きます。
- 杉本夫人はいつもこぎれいな着物を着ている。
- 小杉さんにお目にかかりたいのですが。
- 私は、上杉憲信が好き。
- 杉村春子を別格とすれば女優経験の豊かさで彼女に及ぶ者はない.
- おや! 杉山君じゃないか.
- 台風のあとたくさんの杉の木が立ち枯れようとしている.
- 天にも届く杉の木があった.
- 杉山君とは東京駅で別れた.
- もし貴方は高杉さんではありませんか
- 宮へ行く路は杉の並木になっている
- 杉村連とは付き合わない
- 長州にその人ありと知られる高杉晋作であった
- 杉林
- 杉森
杉と同じ種類の言葉
- >> 「杉」を含む用語の索引
- 杉のページへのリンク
![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈
〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈すぎ〉「
〈すぎ〉「