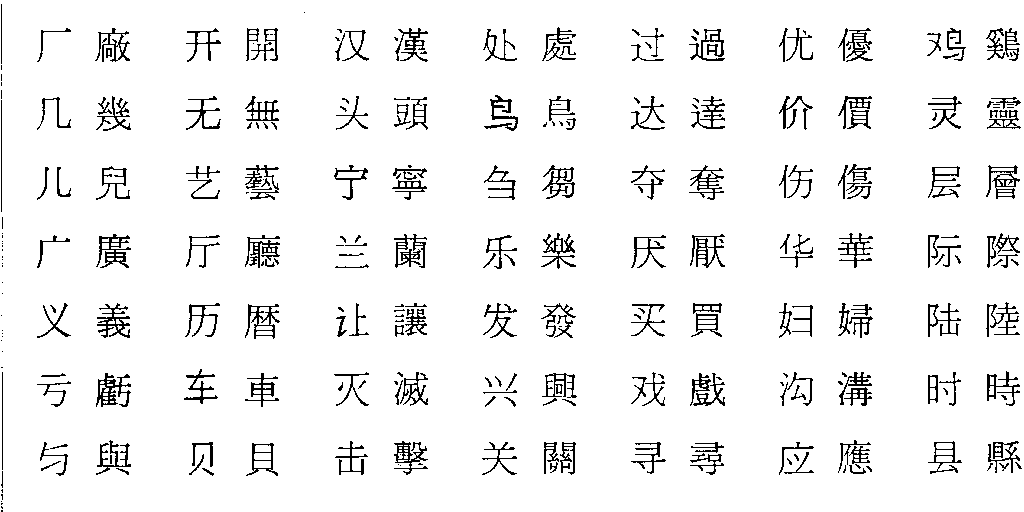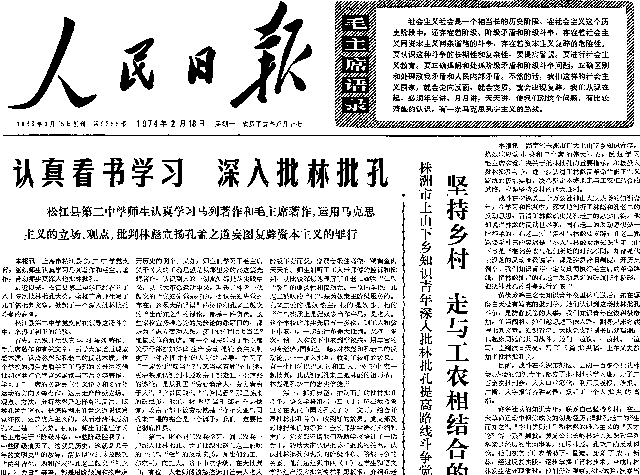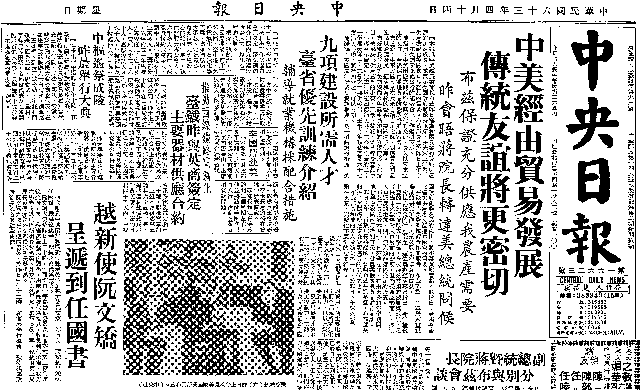かん‐じ【漢字】
漢字 Chinese character
漢字
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/16 02:09 UTC 版)
| 漢字 |
|
|---|---|

|
|
| 類型: | 表語文字 |
| 言語: | 中国語、日本語、朝鮮語、ベトナム語、チワン語 (その他) |
| 時期: | 不明(夏代ないし殷代?) – 現在 |
| 親の文字体系: |
原文字
|
| 子の文字体系: | 仮名、注音、チュノム、女書、契丹文字、契丹小字、西夏文字、女真文字 タイーノム |
| Unicode範囲: | U+4E00 - U+9FFFなど[1](完全なリストはCJK統合漢字を参照) |
| ISO 15924 コード: | Hani |
|
Hans(簡体字) Hant(繁体字)
|
|
| 注意: このページはUnicodeで書かれた国際音声記号 (IPA) を含む場合があります。 | |
漢字(かんじ)は、表語文字のひとつである。中国語および、日本語・朝鮮語といった、中国文化の影響を受けた諸地域(漢字文化圏)の言語の表記に用いられる。漢字はアルファベットなどの表音文字と異なり、多くの場合言語の意味的な最小要素である形態素を表す。中国語と日本語で日常的に用いられる漢字は、2,000文字〜3,000文字に限られるが、Unicodeには2025年現在で100,000文字以上の漢字が登録されている。造字の法則は、共通する形状や音などに基づいて会意・形成・象形などと分類される。
およそ3,000年間以上に及ぶ歴史のなかで、漢字の機能・様式・意味は著しく変化してきた。漢字の起源は不明だが、遅くとも殷代までには成立していた。最初期の漢字は象形・表意的に作られたものであったが、書記文化が中国全土に広まる中で次第に変化していった。書体の改良は複数回繰り返され、たとえば秦代(紀元前221年 - 紀元前206年)には小篆、漢代(紀元前202年 - 220年)には隷書が作られた。隷書は筆記のしやすさを重んじた書体であり、従来象形文字的であった漢字を抽象的な字形に改めた。その後、筆記体である草書の影響を受けながら楷書が成立し、漢字を筆記するに当たっての標準的書体として定着した。字書編纂の歴史を通じて、漢字文化圏ではそれぞれにおいて標準的字体が定まった。中国語圏においては、大陸中国およびシンガポール・マレーシアで簡体字が、台湾・香港・マカオでは繁体字が用いられる。
中国の周辺地域においても、漢字は漢文の筆記のため導入された。さらに、日本・朝鮮・ベトナムなどにおいては、漢字は現地の言語を筆記する言語としても採用された。また、中国内部においてもチワン語といった漢語ではない言語を表記するための文字体系が発達した。これらの地域においては、漢語系語彙に限らず固有語由来の語彙の表記にも漢字が用いられており、独自の文字(国字)が制作されることもあった。朝鮮語・ベトナム語においては漢字はほとんどが廃止されており、現在においても漢字が一般に利用されている書記体系は、中国語を除けば日本語に限られる。
漢字は特定の筆順通りに筆記される筆画を最小要素としており、歴史的には金石・甲骨への彫刻、簡帛・紙への筆記、木版・活版印刷などにより表記された。さらには、19世紀以降には電報のための符号である電碼が作られ、さらにはコンピューターで漢字を扱うための入力方式および文字コードも整備された。
性質と構成
 漢字 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 書体 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 字体 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 漢字文化圏 | ||||||||||||||||||||
| 中・日・朝・越・台・琉・星 | ||||||||||||||||||||
| 派生文字 | ||||||||||||||||||||
| 国字 方言字 則天文字 | ||||||||||||||||||||
| 仮名 古壮字 字喃 女書 | ||||||||||||||||||||
| 契丹文字 女真文字 西夏文字 | ||||||||||||||||||||
| →字音 | ||||||||||||||||||||
漢字は歴史を通じて、さまざまな書記体系のなかで用いられてきた。書記体系は一般に、書記のための文字・数字・句読点といった記号そのもの(書記素)と、それらを用いて言語を筆記するための体系を指す[2]。漢字は表語文字であり、それぞれの書記素は言語の意味要素を指す。漢字は特に、意味の基本単位であるところの形態素を表すことが多い。中国語においてはある形態素は1音節であることがもっぱらであり、それに割り当てられる漢字も1音節である。漢字はしばしば意味を無視した仮借(当て字)をおこなうほか、形声漢字には音のみをあらわす声符がある。こうした特徴から、漢字は形態素-音節文字(morphosyllabic)であるとも論じられる[3]。表語文字は、音の基本単位である音素を表した文字である、アルファベットと対比されうる[4]。漢字は絵文字に起源を遡りうるとはいえ、現在ではもはや観念を直接示す表意文字ではなく、その理解は記されている言語の知識に依存する[5]。
偏旁・部首
多くの漢字はそれを構成する各字符(偏旁)に分解することができ、多くの場合それらの字符も独立に意味を有する。これらの要素は合体字のなかで、特定の位置に収まるように形を調整されている[6]。漢字の字形を左右に分けられる場合、左を偏、右を旁という。また、上下に分けられる場合、上を冠、下を脚という。さらに、上部から左部にまたがるものを垂、左部から下部にまたがるものを繞、上部と左右からかこうものを構という[7]。春秋戦国時代ごろまでは形符の組み合わせは比較的自由に行われ、同じ文書内で偏旁が増減することもしばしばであった。しかし、秦代に小篆が成立し、漢字の構成要素がブロック化されたことにより、現代的な意味の偏旁概念が生じた[8]。
これらの字符は、漢字内部で特定の機能を果たすことがある。たとえば、漢字の音を表す音符、意味を表す意符などがそうである。また、字形や音、意味などが変化したことにより、意符や音符としての機能を失い、記号としての意味しか持たなくなった字符もある[9]。さらに、「八」といった一部の漢字は当初より記号としての機能しか有さなかった[10]。各構成要素(偏旁)に分解できる字を合体字と呼ぶ。また、各構成要素に分析不可能である文字を独体字と呼ぶ。秦漢代以降に作られた漢字はおおむね既存の字から構成されるが、古い漢字には必ずしも独立して字になることのない2つ以上の象形符号を組み合わせたものもある。たとえば、「射(金:  )」などがそうである[11]。
)」などがそうである[11]。
偏旁は、字書においてそれぞれの漢字を整理する際にも用いられる。このとき字書の項目として立てられる字符を部首という。部首の数や種類は字書によってさまざまであったが、清代の『康煕字典』が214部首を立てたため、これが広く用いられている[7]。これらの部首は、たとえば刀部の場合、旁になる場合は「刂」、冠になる場合は「⺈」など、さまざまな形をとる[12]。
筆画・書字

漢字のそれぞれの文字は、方形に収まるように筆記される。篆書から隷書への変化(隷変)のなかで、漢字を構成する線条は筆画として正規化された[13]。筆画はある漢字を筆記するにあたっての最小構成要素となる。隷書・楷書においては、伝統的に「永字八法」、すなわち「永」字にみられる8種の筆画が書法の基本であると論じられている[14]。
筆画の数を画数、書く順番を筆順と呼ぶ[15]。筆順はおおむね上から下、左から右、外側を先に書くように定まっているが[16]、すべての字について画一的な筆順があるというわけではない。漢字文化圏においては教育上の規範として所定の筆順が定められていることもあるが、「必」のように各地域において筆順が如実に異なるものもある。また、「衷」が9画とも10画ともなるように、画数も必ず一定に定まるわけではない[17]。
漢字は伝統的には縦書きで、列は右から左方向に書かれた。また、分かち書きはほとんどなされない。20世紀以降、漢字文化圏においては西洋の影響を受けて左横書きが普及した[18]。中国本土では多くの出版物は左横書きである一方、それ以外の漢字文化圏においてはその限りではない[19]。また、句読点の使用も一般的ではなかったが、19世紀から20世紀にかけて普及した[20]。
文字のおおまかな形のことを字体、そのような文字にほどこされた特徴の体系のことを書体と呼ぶ。伝統的には、漢字の書体として篆書・隷書・楷書・行書・草書の五体がある[21]。また、活字体にはこれらとは別の分類があり、欧文書体におけるセリフに対応する明朝体(宋体)、サンセリフに相当するゴシック体(黒体)、楷書の印刷書体である教科書体(楷体)などに分けられる[22][21]。
異体字

異体字とは、音義を共有する同一字であるものの、字形が異なる文字のことである[23]。異体字は、「貌」と「皃」のように偏旁を加えるか否か、「躰」と「体」のような偏旁の違い、あるいは「蟹」と「蠏」のような偏旁の位置関係の違い、会意の「看」と形声の「𥉏」のような構造性質の違い、「聲」と「声」のような字形の省略、「皐」と「皋」のような書き方の違いなどによって生じる[24]。また、「記」と「紀」のように、おおむね同様である一方、義がまったく同一ではない文字も異体字に加え入れることがある[25]。
もろもろの字体のうち、もっとも標準的に用いられているものを正字と呼ぶこともある[26][27]。また、正字ではない文字のうち、世俗で用いられるものを俗字、かつて用いられたものを古字ともいうが、これらの区分はみな相対的なものであり、ある時代の俗字がある時代の正字であるといったことは珍しいことではない[27]。唐代の『干禄字書』は、それぞれの漢字の正俗を定義したことでよく知られており[27]、その後の中国においても漢字に対する規範意識を背景に多くの字書が編纂された[28]。日本の字書は『康煕字典』の字体を標準としていることが多いが[29]、これは必ずしも現代日本社会で広く用いられる字体ではない[30]。
字音・字義
漢字には特定の音が当てられている[7]。先述した通り、漢語は単音節形態素がほとんどであり、漢字は原則として1音節である。中国語においては、児化の役割を表す「児」と、合字的に作られた「瓩(拼音: qiānwǎ、キロワット)」といった文字が例外となる。また、中国語においても「尼龍(拼音: ní lóng、ナイロン)」といった外来語や、「蝃蝀(虹の異称)」「蜈蚣(ムカデ)」といった連綿語のような一部の語彙は2音節以上となるが、こうした形態素を書き表す場合には専用の漢字が作られるか、仮借が行われた[31][注釈 1]。漢字音の音節構造は音韻学の研究対象となり、頭子音(声)とそれ以下(韻)に分類されて韻書にまとめられた。また、声母と韻母の両者を組み合わせてある漢字の発音を示す反切の技法も生み出された[7][33]。
漢字はある言葉の音声を分析的に表すわけではないため、文字そのものが言語の音韻変化の影響を受けることはほとんどなかった[28]。漢字音には時代・地域によって大きな変遷・差異がある[7]。朝鮮・日本・ベトナムなどに伝来した漢字においても、漢字伝来時の中国語音を反映して、それぞれの地域で固有の読みがなされる[7]。日本語においては漢字の伝来時期と元となった中国語方言に合わせて漢字に複数の音が与えられるほか[34]、中国語においても文語と口語の差によりある漢字が一形多音となることがある[35]。
また、漢字の意味(字義)も時代や地域によって変遷することがある。引申と仮借は、漢字の多義化・多声化にあたって重要な意味をなす[36]。両者はいずれもある字を用いて本義以外の意味を示すことを表す言葉であるが、引申は本字から派生した意味を、仮借は本字の音のみ借りて同音の単語を表す状況を指す[37]。ある文字が仮借と引申の双方を受けることもある[38]。たとえば「強」はもともと「虫」を意符、「𪪺」を音符とする形声文字で、コクゾウムシを指したが[39]、のちに「彊」の仮借文字として「つよい」を表すようになった。さらに、「つよい」の意味の「強」は、引申義である「しいる」の意味も生じさせた[40]。また、複数の異なる起源を有する文字が同形となる場合もある[35]。たとえば、中国語における「鉈」は、矛の義の「鉈(拼音: shé / shī)」、秤のおもりを意味する「秤砣」の「砣」の異体字である「鉈(拼音: tuó)」、タリウムを意味する「鉈(拼音: tā)」の3字が衝突する[41][注釈 2]。
類型
漢字の構成にもとづく分類は、大まかには純粋な意符・音符・記号および、それらの字符の組み合わせというかたちで行うことができる[43]。中国語普通話で一般に用いられる3,500文字のうち、純粋な意符が全体の5%、記号が18%、意符と記号の組み合わせ、音符と記号の組み合わせがそれぞれ19%、残りの58%を意符と音符の組み合わせが占めた[44]。
漢字の分類体系として伝統的によく知られているのは、許慎が『説文解字』にまとめた六書である[45]。この体系は象形・指事・会意・形声・転注・仮借の6分類からなる。六書という概念自体は『周礼』に由来するもので、これに合わせて分類が行われたゆえか、この分類には「転注」なる不明瞭な枠組みがあること、あるいはそれぞれの分類同士の境界も明らかでないといった、いくつかの問題がある[46]。
20世紀中国の古文字学者である裘錫圭は、唐蘭および陳夢家の先行研究をもととして、漢字の機能に関する3分類を提示した[47]。すなわち、単に意味を表す表意文字、音を表す要素を含む表音文字、既存の文字を他の用途に用いる仮借である。なお、裘は、記号といった一部の文字がこの3分類からはみ出ることを認めている[48]。漢字の基本単位として意符・音符を置き、これを踏まえて漢字の性質を整理する裘の論考は、1980年代以降の学者に強い影響を与えたが、六書にもとづく象形・指事・会意・形声はなお漢字の基本的構成と理解される。別のアプローチとして、王寧のように、漢字をその最小単位である「形位」に切り分け、字体構成の歴史について調べる研究者もいる[49]。
本節においては裘錫圭(2022)『中国漢字学講義(原題: 文字学概要)』において説明される「新三書説」にもとづきながら、それぞれの漢字を整理する。なお、本稿においては現代の字形にあわせて古文字を例示することがある。これについても、裘に倣うかたちで、「甲」を甲骨文、「金」を殷ないし周(西周)代金文、「篆」を『説文解字』に記載されるものを含む秦漢の篆書を引用するにあたって用いる[50]。
表意文字
表意文字の構成様式は多様であるが、裘はこれを「抽象字」「象物字」「指事字」「象物字方式の象事字」「変体字」「会意字」の6種類に分類している[50]。なお、この分類は必ずしも相互排反的なものではなく、ある表意文字がどの種類に分類されるかを詳細に論じる意味は薄い[51]。
抽象・象物・象事・変体
抽象字は抽象的記号をもととした漢字であり、「一(金:  )」「回(金:
)」「回(金:  )」「小(金:
)」「小(金:  )」などがそれに当たる。抽象字は秦・漢代にあらわれたものがほとんどであるが、「凹」「凸」「丫」など比較的新しいものもある[52]。象物字は六書における「象形」にあたり、何らかの実際の物体を象ったものを指す。「日(金:
)」などがそれに当たる。抽象字は秦・漢代にあらわれたものがほとんどであるが、「凹」「凸」「丫」など比較的新しいものもある[52]。象物字は六書における「象形」にあたり、何らかの実際の物体を象ったものを指す。「日(金:  )」「月(金:
)」「月(金:  )」「鹿(甲:
)」「鹿(甲:  )」などがそれに当たる[53]。象形は、漢字のなかでももっとも古い造字法のひとつであった[54]。こうした文字は筆記経済をもとめた簡略化の結果として[55]、現代の字形から絵文字的性質を理解することは困難となっている。しかしながら、たとえば「晴」における「日」のように、こうした文字は合体字のなかで絵文字由来の意味を保ちつつ、意符としての機能を担うことがある[56][57]。
)」などがそれに当たる[53]。象形は、漢字のなかでももっとも古い造字法のひとつであった[54]。こうした文字は筆記経済をもとめた簡略化の結果として[55]、現代の字形から絵文字的性質を理解することは困難となっている。しかしながら、たとえば「晴」における「日」のように、こうした文字は合体字のなかで絵文字由来の意味を保ちつつ、意符としての機能を担うことがある[56][57]。
指事字は、象物字や実際の事物を象った形符に、指示符号を加えたものを指す。たとえば「木(篆:  )」に指示符号を加えて「樹木の根」を表した「本(篆:
)」に指示符号を加えて「樹木の根」を表した「本(篆:  )」、などがそれにあたる。指示符号は特殊な象物字の一種とみなすこともでき、「首/𦣻(篆:
)」、などがそれにあたる。指示符号は特殊な象物字の一種とみなすこともでき、「首/𦣻(篆:  )」に曲線を加えた「面(篆:
)」に曲線を加えた「面(篆:  ))」のような象物とも指事ともとれる文字もある[58]。伝統的な分類体系である『説文解字』の六書においては指事の例として「上(金:
))」のような象物とも指事ともとれる文字もある[58]。伝統的な分類体系である『説文解字』の六書においては指事の例として「上(金:  )」「下(金:
)」「下(金:  )」が挙げられる[59]。しかし、裘は「物」の名称を指すか「事」の名称を指すかで象形と指事を分類する伝統的体系は、実物の形を象りつつも抽象的事項を指す「大(金:
)」が挙げられる[59]。しかし、裘は「物」の名称を指すか「事」の名称を指すかで象形と指事を分類する伝統的体系は、実物の形を象りつつも抽象的事項を指す「大(金:  )」などを分類するにあたって不都合であると論じている。なお、『説文解字』を著した許慎自身は「大」を象形にふくめている[60]。また、裘は「上」「下」などを抽象字と分類している[52]。裘の分類によれば、成人男性を表した「
)」などを分類するにあたって不都合であると論じている。なお、『説文解字』を著した許慎自身は「大」を象形にふくめている[60]。また、裘は「上」「下」などを抽象字と分類している[52]。裘の分類によれば、成人男性を表した「 」をはじめとする文字は象物・象事の二重の性質を有しており、これを「夫」の古文字とみるならば象物、「大」の古文字とみるならば象事である。象物字方式の象事字としては、「大」のほかに「左」「右」の本字であり、左手・右手を表した「𠂇(甲:
」をはじめとする文字は象物・象事の二重の性質を有しており、これを「夫」の古文字とみるならば象物、「大」の古文字とみるならば象事である。象物字方式の象事字としては、「大」のほかに「左」「右」の本字であり、左手・右手を表した「𠂇(甲:  )」「又(甲:
)」「又(甲:  )」などがある[61]。変体字は、文字の図形を改変して作った漢字である。変体字には、「
)」などがある[61]。変体字は、文字の図形を改変して作った漢字である。変体字には、「 」の右半分をとって作字した「片(篆:
」の右半分をとって作字した「片(篆:  )」のように、筆画を増減して作ったものと、字形の方向を転換してつくったものがある[62]。
)」のように、筆画を増減して作ったものと、字形の方向を転換してつくったものがある[62]。
会意
会意字は、2つ以上の意符をあわせて、それらの意符そのものの意味とは異なる意味を表す文字を指す。裘の分類では、「射(金:  )」といった文字を会意字に分類するため、分類として「象事字」ではなく「象物字方式の象事字」を置く。たとえば、人が家の中で竹製のむしろの上に寝ている様子を表した図符である「宿(金:
)」といった文字を会意字に分類するため、分類として「象事字」ではなく「象物字方式の象事字」を置く。たとえば、人が家の中で竹製のむしろの上に寝ている様子を表した図符である「宿(金:  )」なども会意字である[63]。また、こうした図形的な会意字のほかに、図画的な意味合いが弱まった、偏旁の位置関係にもとづき造字される文字もある。古文字では人が竪穴から出る様子を表した「出(金:
)」なども会意字である[63]。また、こうした図形的な会意字のほかに、図画的な意味合いが弱まった、偏旁の位置関係にもとづき造字される文字もある。古文字では人が竪穴から出る様子を表した「出(金:  )」などがそれにあたるほか、「嬲」など、比較的新しい時代に同様の手法で作られた文字もある[64]。また、人や動物を表す字や形符に器官の形符を加えた文字として、たとえば「人」に「目」を加えた「視[注釈 3](甲:
)」などがそれにあたるほか、「嬲」など、比較的新しい時代に同様の手法で作られた文字もある[64]。また、人や動物を表す字や形符に器官の形符を加えた文字として、たとえば「人」に「目」を加えた「視[注釈 3](甲:  )」のようなものがある[66]。また、「林(甲:
)」のようなものがある[66]。また、「林(甲:  )」のように同一の偏旁を重複させた字[67]、「少」と「力」からなる「劣」、「更」と「生」からなる「甦」のように2つの漢字を合字のように組み合わせた字などがある[68]。
)」のように同一の偏旁を重複させた字[67]、「少」と「力」からなる「劣」、「更」と「生」からなる「甦」のように2つの漢字を合字のように組み合わせた字などがある[68]。
『説文解字』においては会意の例として「武」「信」がとりあげられ、それぞれ「戈を止める」「人の言」の意味であると論じられるが、実際には上古の会意字において「歪」のように漢字2つの字義を組み合わせて作られた文字はほとんどなく、多くは字符を図画的に組み合わせたものである。また、「信」についてはそもそも「人」を声符とする形声字と考えられている[69]。ウィリアム・G・ボルツのように、伝統的に会意字と理解されてきたおおむねすべての文字は、時代の流れにより声符が不明になってしまった形声字であるとする考えもある[70][71]。ボルツはここで「女」に *ʔ(r)ang の読みがあったとしながら従来会意とみなされてきた「安」「姦」などが「女」を声符とする形声字であるとするが、ジョフリー・サンプソンと陳志群は、同説は音韻的に不正確であり、また、「姦」のような文字を会意としないのは意味的にも不自然であると論じている[72][注釈 4]。
形声文字
形声文字は、意旁と声旁から構成される文字である。最初期の形声文字は、仮借文字への意旁の付加、表意文字への音旁の付加などによって作られたが、後世には意旁と音旁が直接組み合わされるようになった[75]。たとえば、「河」「湖」「流」「滑」「沖」といった漢字は、いずれも水を表す「氵」に声旁を組み合わせたものである[76]。
表意文字への音符の付加によって作られた文字としては、「 」に声旁「止」を加えた「歯」などがある[77]。また、狩猟のために用いられた庭園を指す「囿(甲:
」に声旁「止」を加えた「歯」などがある[77]。また、狩猟のために用いられた庭園を指す「囿(甲:  )」のように、字形の一部を声旁に改めた文字もある[78]。仮借文字への意旁の付加によって作られた文字としては、もともと軍隊を意味したが、漢代にライオンも意味する字としても仮借された「師」がある。同字には犬の旁が加えられ、「師」から分化して「獅」となった。また、引申義(派生的意味)を明確にするために意旁が加えられることも有る。たとえば「取」からは「めとる」の意味が派生し、「女」の旁を加えた「娶」が生じた。このような造字法にもとづき作られた漢字は会意兼形声文字となる。反対に、本義を明瞭にするために意旁が付加されることもある。「它」と「蛇」、「止」と「趾」などがこの関係にある[79]。声旁「𬟏」を省略した「秋(𪛁)」や、「夕」と声旁「亦」から構成されるが、「亦」の一部分が省略された「夜」のように、声旁を省略した造字を省声という[80]。また、星(曐)のように、反対に形旁を省略することを省形という[81]。
)」のように、字形の一部を声旁に改めた文字もある[78]。仮借文字への意旁の付加によって作られた文字としては、もともと軍隊を意味したが、漢代にライオンも意味する字としても仮借された「師」がある。同字には犬の旁が加えられ、「師」から分化して「獅」となった。また、引申義(派生的意味)を明確にするために意旁が加えられることも有る。たとえば「取」からは「めとる」の意味が派生し、「女」の旁を加えた「娶」が生じた。このような造字法にもとづき作られた漢字は会意兼形声文字となる。反対に、本義を明瞭にするために意旁が付加されることもある。「它」と「蛇」、「止」と「趾」などがこの関係にある[79]。声旁「𬟏」を省略した「秋(𪛁)」や、「夕」と声旁「亦」から構成されるが、「亦」の一部分が省略された「夜」のように、声旁を省略した造字を省声という[80]。また、星(曐)のように、反対に形旁を省略することを省形という[81]。
形声文字の字義が形符の意味そのままになることは「船」といった一部の例外を除けば稀であり、多くは字義そのものとは間接的にしか関連しない。また、「妄」「婪」のような、「悪い性質」を意味する形旁としての「女」など、時代の変化により意味が通じなくなったものもある。「粳」と「稉」のように、意味の近い形旁には相互に代替可能なものもある[82]。声旁は多くの場合形声文字そのものと同音であるが、発音の時代・地域による変化、声旁の字形変化、適切な声旁の不在といった様々な理由により、両者が乖離することも少なくない。「灯」と「燈」のように、声旁にも相互に代替可能なものがある[83]。
「娶」、「輌」、あるいは四頭立ての馬車を指す「駟」といった分化字においては、声旁が表意の役割を兼ね備えるため、これらの文字は一般的に形声兼会意文字となる。とはいえ、声旁が意味を持つ形声文字が全体に占める割合は決して多くない。また、著しく特殊な例として、声旁の「丿」「刂」「川」が水素の質量を表す「氕(piē, プロチウム)」「氘(dāo, デューテリウム)」「氚(chuān, トリチウム)」のような文字もある。同源語を表す一連の形声文字は、同一の声旁を共有している場合もあり、ここから漢字を分析しようとする考えのことを右文説と呼ぶ。しかし、同一の声旁に従う漢字が必ずしも意味的関連を有するわけではなく、また、同源語であっても異なる声旁を使っていることは往々にしてあるため、確かな方法ではない[84]。
仮借
既存の漢字を、同音の別の語に対する表記に用いることを仮借と呼ぶ。文字をあてがう必要性がもっとも高い抽象的語彙は図画的に表現しづらく、古漢字に限らずもと表意的であった文字を表音的に用いる例は世界的に見られる[85]。もとから本字のあった語に、仮借文字が与えられる理由は複雑である。文字の役割の分散、あるいは区別する必要のない文字の合併、表意文字の形声文字への代替、複雑ないし紛らわしい字形の回避、避諱、表現を典雅にするためなど、これにはさまざまな理由が挙げられる[86]。
その語を本義ないし引申義とする文字を、仮借文字と区別して本字と呼ぶ[87][注釈 5]。裘の定義によれば、仮借は引申とは区別されるべきものであり、たとえば「めとる」を意味する「娶」を「取」の本字とは呼べない[89]。たとえば「草」は仮借文字であり、本義はクヌギの果実である。「くさ」を意味する「草」の本字としては、「艸」が存在した。また、「いう」の仮借として用いられた「胃」のため造字された「謂」のように、仮借文字に対して本字が新しく生じることもある。古漢語における虚詞(機能語)である「耳(のみ)」「夫(それ)」のように、仮借のみによって表現され、本字にあたる字が存在しない語もある[90]。仮借は、「比丘」といった仏教語や、「阿斯匹林(拼音: ā sī pī lín、アスピリン)」といった現代の非漢語のような、音訳外来語の表記にあたっても用いられる[91]。
その他
先に紹介したいずれの分類にも当てはまらない文字も存在する。たとえば、「五」「六」「七」「八」といった文字は、当初よりその語をあらわす記号として作られた。「叢」の簡化字である「丛」なども、声符「从」に記号の「一」を付け加えて造字されたものである。また、「兵」を変形して、既存の字に由来する別の読み方を与えた「乒乓」のような字(変体変音字)、偏と旁の反切音をあらわす「𡅖」、あるいは「羥」のような字も、三書に分類できない。「午」と「吾」からなる「啎」、「倝」と「干」からなる「幹」のように、音符のみから構成される両声字も同様である。音符のみから構成される字には、チベット文字「ཏ」から派生したとされる「歹[注釈 6]」のように、きわめて特殊な例もある[93]。
歴史
伝承
いくつかの伝世文献によれば、文字発明以前の中国においては結縄が用いられていた[94]。たとえば『易経』繋辞下伝には「上古は縄を結びて治まる。後世の聖人、之れに易うるに書契を以てす」とある[95]。『説文解字』にあるよう、伝統的に漢字の発明者と信じられてきたのは蒼頡である。同書いわく、蒼頡は黄帝の臣下であり、鳥の足跡を見て書契(文字)を発案するに至った。蒼頡はもと古帝王として伝えられる人物であったが、戦国後期(紀元前3世紀)ごろには文字の発明者と論じられるようになり、この伝説は漢代に編纂された『蒼頡篇』を通じて普及した[96]。
先史
甲骨文以前より、中国においてはいくらかの記号的図符が用いられていたようである[97]。「文字」の定義を広く取り、「人々が情報伝達に用いる、一定の意味を表す図画や符号」とするならば、こうした「原文字」は文字と理解可能である。一方、文字を「言語を記録する体系」と狭義に定義するならば、言語を完全に記録することのできない「原文字」と「文字」は区別するべきである[98]。
甲骨文以前の符号は1950年代以降、中国に近代考古学が導入されてからいくらか発見されているが、これらは断片的なものであり、かつ数量的にも十分でないため、漢字の形成を論じるに当たっての論拠とすることはできない。こうした記号としてはまず、仰韶・大渓・馬家窯・良渚・龍山などにおいて土器・亀甲・獣骨などに刻まれた幾何学的符号がある。仰韶文化前期の半坡遺跡から出土する、土器に刻まれた符号(半坡陶符)を、古漢字に紐づける考えがある。一方で、これらの符号はきわめて単純なものであり、文字であるという確証も、漢字と直接的関係を有するという根拠もない。また、こうした幾何学的な「甲類符号」とは別に、象形的な「乙類符号」も見つかっている。たとえば、大汶口遺跡で出土した土器には象形的符号(大汶口陶文)が刻まれており、これを原始的な漢字であると考える研究者もいる。一方で、これに対してもあくまで個人ないし氏族を形象化した図形的標識であり、文字とはいえないとする主張もある[99]。裴李崗文化初期の遺跡である賈湖遺跡からは、亀甲に刻まれた紀元前7000年紀に遡る文字様符号(賈湖契刻文字)が発見されているが、これを文字ないし原文字とする見解には強い反論がある[100]。
黄徳寛によれば、漢字体系の基本がつくられたのは紀元前21世紀頃で、夏代にはおおむねすでに成熟した文字体系としての漢字が成立した[101]。裘錫圭もまた、漢字が形成された時期は早くとも夏代以降(紀元前21世紀 - 紀元前1600年前後)であると論じる一方、この時代においてもやはり文字であると確定できるような符号は確認されていない[102][注釈 7]。李先登は、王城崗遺跡で出土した陶胚に刻まれた符号が殷・周代の「共」に比定可能であると論じ、漢字の発明は夏代初期であると論じている[105]。しかし、これに関しても確定したものではない[102]。陶寺遺跡出土の土器には朱書きが加えられたものがあり、何駑はこれが「文堯」と読解可能であると論じている。やはり、これも定説ではない[106]。
殷代
殷代前期の陶文はまとまったかたちでは見つかっておらず、断片的である。偃師商城においては陶文はほとんど見つかっていないが、黄は殷代初期の文明水準や、殷代後期の文字水準などから鑑みて、この時代にもある程度成熟した文字文化があったと論じている[107]。河南省の鄭州商城(二里岡遺跡)においては大口尊(甕型土器)に数十種の陶文符号が確認されている[108]。しかし、裘はこれをそれ以前の甲類符号と同等のものと考えている。また、二里岡ではほかに、文字の刻まれた骨2片が確認されている[109]。ほかに、河北省の藁城台西遺跡では77点の陶文が発見されており、季雲はこれが殷墟の甲骨文の前段階にあたると論じた[110]。
江西省の呉城遺跡で出土した土器をはじめとする遺物にみられる符号も、台西陶文および殷代晩期甲骨文と比較されている。呉城遺跡1期(二里岡遺跡上層と同年代)層から見つかった陶罐には12の文字ないし符号が記されており、これは唐蘭・李学勤・蕭良瓊などにより解釈され、「帚臣燎豆之宗、仲、七」あるいは「中宗之豆、燎、臣帚七」などと読解されている[111]。同じく江西省の大洋洲程家遺跡でも陶文が見つかっており、これは呉城陶文と比較されている。河南省の小双橋遺跡からは、陶文に加えて朱書文字が確認されている。黄はこれらの文の構造と特徴にはその後の甲骨文・金文と明らかに一致する部分があると論じ[112]、甲骨文字は小双橋陶文から発展したものであるとしている[113]。宮川一夫は小双橋遺跡の符号について、大汶口文化の酒甕の文字記号と、殷墟時代の青銅彝器の族記号(記名金文)を繫ぐものではなかろうかと論じている[114]。
殷代中期の動乱を経て、殷の宮都は現在殷墟として知られる場所(商)に移った[104]。甲骨文字が現れるのは殷墟に都を構えた武丁以降であり[115][注釈 8]、ボルツや徐中舒をはじめとする研究者はこの時代(晚商)をもって漢字が成立したと述べる[119][120]。裘は、殷代後期には漢字は完全に言語を記述できるまでに発達しており、文字体系としてかなり整ったものになっていたとして、漢字の成立はそれよりはるか以前のことであると論じる。一方、資料の制約ゆえ、漢字形成について論じるうえでは殷代後期以降の文字を参考にするしかないことも認めている[120]。甲骨文字はその大半が占いの記録(卜辞)である[121]。殷代の文字資料の大半は甲骨文字であるが、これ以外にも金文・陶文・玉石文字による記録もある[113]。
甲骨文字は、同時期の記名金文[注釈 9]にくらべてかなり簡略化されていた[123]。また、殷代の中でも時代の発展にともない簡略化は進んだ[124]。殷代甲骨文は貞人(占卜儀礼の担当者)のグループである「某組」によって断代(年代の判定)が可能であるが[125]、初期にあたる𠂤組卜辞では写実的に描かれていた文字も、後代の何組・黄組の時代にはかなり記号化されている[124]。また、一部の文字では偏旁の加筆が行われた[126]。
周代・春秋戦国時代
周代にも甲骨文・陶文がみられる[129]。殷代甲骨文においては文字が左右反転することがしばしばあったが、周代甲骨文においてはこれが原則固定された[130]。また、字体は原則として単純なものが継承されたほか[131]、異体字が整理され、形の揺れが少なくなっていった[132]。
しかし、この時代の主な文字資料は青銅器銘文(金文)である。周代青銅器には100字以上の銘文が刻まれることも珍しくなかった[128]。金文の字体は当初、殷代のものと近かったが、その後、筆画の線条化(文字内部での構成要素の太さの統一)・直線化が進んだ。殷代の字体には曲がりくねった線や、方形・円形での塗りつぶしといった、線画が追えない塊が少なからず含まれており、筆記には不便であった[133]。さらに、周代中期以降の金文は、文字の大小・字配りがが均一化した[134]。また、この時代には表意・象形的手法で文字が作られることは少なくなり、形声字が漢字構造の絶対的主流となった[135]。
春秋時代の金文は当初、西周後期の金文の書き方を踏襲するものであった。しかし、この時代に分立した各国では地域ごとに、書体にいくらかの変化が見られた[136]。これらの差異はおおむね書風の違い程度のものであったが[136][137]、各地域の言語差を反映して、声符の置き換えなども行われた。この時代には漢字から実塊(塗りつぶした塊)は消滅し、もともと関連していない筆画が合併されるなどして、漢字のさらなる記号化が進んだ[138]。春秋晩期から戦国早期にかけては美的装飾が施された書体も発展し、越を中心に鳥篆をはじめとする特殊な書体が現れた[139]。
春秋戦国期の社会変化により、それまで経済・政治・文化などで支配的な地位を占めていた貴族階級が衰微するとともに、新興の上流階級が生まれると、民間にも文字が普及しはじめた。特に、戦国時代に入ると、これらの変化により文字の使用される範囲、使用する人は著しく増加した[140]。戦国時代の文字資料は豊富であり、竹簡を代表に、銅器・兵器・貨幣・璽印・木簡・帛書など、その媒体はさまざまである[141]。
この時代には俗体が多く生まれ、字体の様相は周から春秋にかけてのものとは全く異なるものとなった。さらに、各国で文字の差異がうまれ、いくつかの字は国によってまったく異なる書き方をした[142]。戦国文字は一般に秦系(秦)、楚系(楚・曽・呉・越など南方諸国)、斉系(斉・魯など山東諸国)、燕系(燕)、晋系(三晋・周・中山など中原諸国)の5つの種類に分けられる[143]。うち、秦の文字は周代金文の字形を比較的よく継承し[144]、また、その後の小篆・隷書の基礎ともなった。このことから、戦国期の文字を秦国文字とそれ以外の六国文字に区分することもある[145]。
秦漢代以降

紀元前221年、秦の始皇帝によって中国は統一され、中国史上はじめての中央集権的専制王朝が生まれた。始皇帝は度量衡とともに文字の統一事業を行い、小篆として知られる統一書体を整備した[141][注釈 10]。小篆は秦系文字の系譜を引くものであるが、字形は規則的かつ象形性の弱いものとなった[147]。秦系文字と小篆の関係は連続的なものであり、小篆の成立がいつであるかについてはっきりとした論証はない。多くの研究者はこれを戦国中晩期のこととする一方、春秋晩期であるとする考えもある[148]。秦の文字統一事業はきわめて厳格かつ苛烈であり、これを経て文字の地域差はほとんど消滅した[149]。焚書坑儒によって六国の古文の伝承が人為的に断絶せしめられたことも、文字の統一・規範化を推し進めた[150]。
秦系文字は他地域の文字に比べて保守的かつ複雑であり、筆記経済のために簡易な字形も生まれた。このようにして戦国時代後期ごろより生まれた俗体文字が、隷書となった[151][152]。秦系文字の隷変は戦国晩期以降に急速に進んだが[153]、秦代には隷書は補助的書体にすぎないとして、統治者階級からは軽視されていた。とはいえ、隷書は小篆に比べて書きやすかったため、権量銘のような公式の銘文にも隷書の影響を受けた書体が用いられている[154]。

漢代に入ると隷書は小篆にとってかわり、公式な書体となった[155]。前漢前期の簡帛(簡牘・帛書)では、隷書にも篆書に似た字形が見えるが、居延漢簡やロプノール漢簡(楼蘭漢簡)といった武帝後期以降の資料では、こうした字形は大きく減少している。漢代の隷書をそれ以前の秦隷(古隷)と対比して漢隷ないし八分と呼ぶが、これは遅くとも昭帝から宣帝の時代には完全に成立していた[156]。隷書では篆書の曲線が直線に改められ、象形性もおおむね放棄された。また、筆記の簡単のために、筆画の省略・併合が行われた[157]。八分の形成にやや遅れて、隷書を補助する字体であるさらに簡便な字体である草書も生まれた。草書は古隷の俗体から生まれ、遅くとも元帝から成帝の時代には成立していた[158]。八分も後漢の中期・後期には日常的な場面では崩して筆記されるようになり、後漢後期には行書が現れた[159]。

伝統的に楷書を発案したと考えられているのは魏の鍾繇である[160]。これは、東晋の王羲之・王献之によりさらに発展させられた[161]。初期の楷書は、行書の発展型として作られた。既知の楷書史料として最古のものは、鍾繇の『宣示表』といった筆跡の臨模であり、魏晋代の写本・墓誌などには八分およびそれを崩した新隷体が用いられている。こうした理由から、鍾繇や王羲之の筆跡として伝わるものが信頼に足らないとする研究者もいるが、裘は楼蘭遺跡の東晋代資料には行書および楷書様の筆跡が見えることなどから、広く普及こそしていなかったとはいえ当時より確かに楷書は存在していたと考えている。楷書が支配的地位を占めるのは南北朝時代以降である。この時代にも楷書には多少の改良が加えられ、これと並行して草書・行書の字体にも変化が見られた[162]。
南北朝時代には政局の不安定化にともない文字の書き方も統一されなくなったが[163]、隋代に中国が再び統一されると、南北に分裂していた学術も統合が進んだ[28]。隋唐代には科挙もはじまり、受験者は楷書で文言を記述することが求められた。このことは、楷書・文言の安定化に寄与した[164]。楷書の字体改変は唐代初期の欧陽詢の時代に完成し、この時代以降、漢字の字体には目立った変化は見られなくなる[162]。唐代には文字の正俗の乱れを正す目的で正字政策がおこなわれ、顔元孫の『干禄字書』のような書物も著された[28][165]。宋代には印刷業の発展や、科挙の試験における文字の書き方に対する規範が厳格化したことなどにより、文字の字形はさらに固定化していった[162]。また、文字の規範を定めるものとして字書・韻書も刊行されつづけた。宋代の『類篇』『集韻』、元代の『古今韻会挙要』、明代の『洪武正韻』『字彙』、そして清代の『康煕字典』がその代表である[28]。
漢字文化圏における漢字

漢文は、紀元前5世紀から2世紀ごろの中国語を基盤としており[166]、20世紀までの中国において文語として機能し続けた[167]。漢文はその他の中国文化とともに、朝鮮・日本・ベトナムといった周辺地域(漢字文化圏)にも普及した。これらの地域では、公的な記録や史書の編纂、連絡の手段として漢文が用いられた[168]。

中国語・朝鮮語・日本語・ベトナム語は異なる系統に属し[169]、それぞれの性質は異なる。このため、中国語を介さない話者が自国語で漢文を読み下せるよう、訓読が開発された。これはダイグロシアの一形態とも[170]、翻訳の手法とも説明される。アルファベットや音節文字を使って書かれた他の文化圏と比べ、このような状況で発展した文芸文化は、特定の話し言葉と直接的に結びつく度合いが低いものであった。漢字を解する異なる言語の話者同士が、筆談を通してコミュニケーションを取ったことは、こうした状況を論じるうえでの良い例である[171]。漢文・漢字の受容にともない、これらの地域では漢語系語彙(Seno-Xenic vocabulary)が大量に導入された[172]。タイ語のขิม(/kʰim˩˩˦/、琴)やポルトガル語のchá(/ˈʃa/、茶)など、漢語からの借用語自体はさまざまな言語に見られるが、朝鮮・日本・ベトナムにおいては、大量の漢語系語彙の借用が、字音の音韻体系そのものの輸入というかたちで行われたことが特色である[173][34]。
中国の周縁地域においては、固有語を表すための独自の漢字も作られた。日本で作られた漢字を国字といい、飛鳥時代の「鵤(いかるが)」などが初期の例である。「鰯」「躾」「鱈」といった会意的に作られた文字が多いが、「鋲」のような形声文字もある[174]。朝鮮においてはこうした新字(朝鮮の国字)の作成は非常に限定的であったが、国境を意味する「䢘(갓)」、水田を意味する「畓(답)」といった会意文字、「(⿱古乙、kol)」「哛(spun)」といった音符の合成によって作られた文字などがある[175]。
宋代より中国の南方地域では「閂」や、「門から飛び出して驚かす声」を意味する「閄」といった方言字が作られていたが、こうした文化はチワン語における古壮字、あるいはベトナムにおけるチュノムに継承されているかもしれない[176]。中国国内で作られた方言字は、その多くが普通話重視の言語政策によりリテラシー活動から遠ざけられたが、香港においてはその限りではなく、広東語表記のための「冇」や「咗」といった粵語字(香港字)はアイデンティティを束ねる要素のひとつとなった[177]。
新字の作字が特に頻繁に行われたのはベトナムにおいてである。ベトナム語表記に用いられる漢字をチュノム(字喃、𡨸喃)という[175]。チュノムは漢字を仮借したものと、新たに作字したもの(狭義のチュノム)に大別される。鷺澤拓也の分類によれば、狭義のチュノムの造字方法は会音、会意、形声に分類される。会音文字は「吝(lận)」と「寅(dần)」を組み合わせた「𡫫(lần、~回)」のように、音韻ないし声調を部分的に共有する漢字2つを組み合わせてベトナム語の音を表す文字である。全体的な造字方法としては、中国の漢字同様に仮借と形声が大半を占める[178]。
朝鮮

『魏略』によれば、箕子朝鮮・準王代には朝鮮半島に燕・斉・趙といった地域からの移民があったほか、『史記』朝鮮列伝いわく衛氏朝鮮の建国者である衛満は燕人であった。彼らは漢字を用いていた可能性が高い。また、「朝鮮列伝」には衛右渠朝鮮半島における漢字伝来の考古学的証拠として初期のものには、燕の明刀銭をはじめとする貨幣類などがある。前漢・武帝の時代である紀元前108年、朝鮮半島には楽浪郡をはじめとする漢四郡が設置され、以来同地では多くの漢字遺物が確認されるようになる。このなかには、楽浪郡内で書かれたことが確実な簡牘類も含まれている。朝鮮半島南部においても漢代・新代の貨幣が出土するほか、紀元前1世紀の昌原茶戸里古墳群茶戸里1号墓からは、在地産とみられる筆が見つかっている[180]。朝鮮半島の漢諸郡は4世紀初頭、高句麗によって滅ぼされたが、漢字文化にもとづく行政機構は継承された[181]。また、4世紀には百済でも漢字が受容されたようである。新羅においては漢字の受容がやや遅れ、6世紀ごろより漢字利用の豊富な証拠が見つかるようになる。新羅は7世紀に朝鮮を統一し、8世紀には科挙の導入をはじめとする積極的な漢化政策を進めた[182]。
朝鮮においては、漢字の一部を送り仮名として用いる口訣とよばれる技法が漢文訓読に用いられた[183]。また、新羅の歌である郷歌においては、郷札とよばれる漢字を用いた朝鮮語表記が用いられた[184]。郷歌の伝統は高麗期には途絶えたが、その後も吏読とよばれる一種の変体漢文が長く使われた[185]。1443年に、李氏朝鮮4代国王の世宗は訓民正音(ハングル)として知られる表音文字を作成した[186]。しかし、官僚階級である両班はこれを冷眼視し、世宗の没後、公的な場面で再びハングルが広く用いられるのは19世紀から20世紀にかけて以降のこととなる[186][187]。20世紀には多くの刊行物が漢字ハングル混じり文で記されたが、朝鮮民主主義人民共和国においては1949年、大韓民国においてはおおむね1980年代以降、漢字はほとんど用いられなくなった[188]。
朝鮮漢字音は原則として一字一音であり、『慧琳一切経音義』にみられるような唐代長安における中古中国語の音韻体系とよく対応することが知られている。現代朝鮮語の漢字音においては、声母に有声・無声の弁別はない。有気・無気の対立はおおむね保存するが、有気音に偏る傾向もある。疑母・日母は脱落する。語頭の [r] および [ni] はそれぞれ [n]、['i] に変わるが(頭音法則)、北朝鮮標準語ではこのルールがない。前舌母音は後舌化する傾向にある。韻尾はおおむね保存するが、-t は -l となるほか、-j および -w は主母音と融合してそれぞれ前舌母音・後舌母音となる[189]。
韓国においては、漢字教育の場では音(음)にあわせて訓(훈)が教えられる[190]。現といった韓国において訓は漢字の意味を表すラベルとして用いられるのみであるが[191]、歴史的には『三国史記』にみえる新羅の地名例や郷歌などに、漢字に固有語読みを与えた形跡が見られる[192]。
日本

日本列島(倭)において、制作年代がはっきりしている最古の漢字を記した資料は57年の漢委奴国王印である。ほかに、新代の貨幣である貨泉なども見つかっている。在地の資料として最古のものは5世紀前半の稲荷山古墳出土鉄剣であり、115字からなる漢文が記される。5世紀から6世紀にかけてのほかの資料としては、江田船山古墳出土鉄刀および隅田八幡神社人物画像鏡がある。606年造と考えられている東京国立博物館蔵菩薩半跏像には「たかや」を「高屋」と記す銘があり、このときにはすでに訓読みの慣習が生まれていたようである[193]。奈良期まで、日本の文献はすべてが漢字によって記された。『日本書紀』のように正則の漢文で記されたものもある一方、『古事記』のように変体漢文で記された例もあり、記紀歌謡や『万葉集』などにおいては、漢字を一音一音記して日本語の音を表す万葉仮名、あるいは万葉仮名と漢字の和訓を組み合わせた表記などがなされた[7]。
9世紀から12世紀にかけての平安期には、平仮名と片仮名があらわれた[7]。片仮名は9世紀頃、漢文訓読にあたっての万葉仮名の省形としてあらわれた。また、平仮名も同時期、奈良期にはすでにあらわれていた崩した字形の万葉仮名をさらに粗略にした文字としてあらわれた[194]。これらの文字は、最初単独で用いられることがもっぱらであったが、中世には漢字仮名交じり文が生じた。仮名文字の発展のなかでも漢字は引き続き国語を表す文字の中心として扱われ[7]、漢字仮名交じり文が成立した中世に至っても日記・公用文・使用文は変体漢文で記された。中世後期にあたる室町期には候文の利用が活発化し、その代表的教本である『庭訓往来』が記された[195]。候文はその後、江戸幕府による施政のメディアとしても利用され、支配層だけではなく庶民層もこれらを学んだ[196]。近代には教育の体系化と活版印刷の普及により、国民のほぼすべてが漢字を学ぶようになった一方、漢字の廃止や制限も主張されるようになった[197]。太平洋戦争後の1946年には1850字からなる当用漢字が整備されたが、その後文字数およびその拘束力はやや緩和され、2010年の改定時点で常用漢字の数は2136文字となっている[7]。
日本漢字音は大きく呉音・漢音・唐音に区分される。呉音は、7世紀以前に伝来した六朝時代の江南方言、漢音は、7世紀から9世紀初期に伝来した唐代長安方言、唐音は、11世紀から19世紀中葉までに伝来した宋代以降の江南・南部沿海方言に由来すると考えられている。うちもっとも広く用いられるのは漢音であり、7世紀に音博士が任命されたことからもわかるよう、律令体制下において積極的な導入が行われた。それ以前に伝来した漢字音にもとづく呉音は仏教語に多く残り、また、唐音は「行灯(あんどん)」「暖簾(のれん)」「蒲団(ふとん)」などごく一部の言葉を通してしか定着していない[198]。
「大(呉: だい、漢: たい)」のように、呉音においては字母の無声・有声を清音・濁音として弁別するが、漢音ではいずれも清音とする[34]。また、前期中古音から後期中古音への変化を反映して、漢音では「米(呉: まい、漢:べい)」のように、鼻音声母字を濁音で表す[198][34]。介子音 -i- の有無は、かつて「カ」「クワ」の区別として保存されていたが、江戸期に消失した。主母音については、中古音との規則的対応は存在しない。-j, -w といった半母音韻尾は「イ」「ウ」として独立音節化し、-n, -m といった鼻音韻尾は「ン」にまとめられている。-p, -k, -t はそれぞれ「ウ」「ク」「ツ」として独立音節化したか、あるいは消失した[34]。呉音・漢音のあいだには一定程度の規則性があり、何らかの体系的整理が行われた可能性が指摘されている[198]。また、一部の漢字には、慣用音とよばれる呉・漢・唐音のいずれにも当てはまらない読みもある。杏(呉: ぎょう、漢: こう、唐: あん、慣: きょう)などがその一例である[199]。
また、日本語においては、中国語由来の読み(音)に加えて、漢字に与えられた固有語読み(訓)も存在する[7][34]。「氷柱(つらら)」のように、2文字以上の漢語に独立した訓が与えられることもあり[200]、これを熟字訓と呼ぶ[201]。ひとつの熟語の中で音読みと訓読みが織り交ぜて用いられることもあり、これを重箱読み・湯桶読みと呼ぶ[7]。
ベトナム
紀元前3世紀に秦は「百越」とよばれる南方諸民族を平定したが、秦の滅亡後には南越が興った。紀元前111年、南越は漢の版図の一部となった[202]。939年の呉権による政権(呉朝)樹立まで、およそ1000年にわたりベトナムは中華王朝の直接支配を受けており(北属期)、隋唐代には科挙も実施された[202][203]。ベトナムが中華王朝の直接支配を脱した後も、漢字・漢文・儒教の受容および科挙の実施といった、中国的文化は引き続き残された[203]。
ベトナムにおいて、固有語による固有名詞を漢字で書く習慣自体は、はやくも漢代にはあったようである[204]。『大越史記全書』によれば、13世紀・陳代仁宗の時代の阮詮は「又能く国語をもて詩を賦す」とあり、これは当時すでにチュノムが用いられていたことを示す記録として理解されることも多い[205][206]。陳朝後葉の1342年に築かれた護城山碑文においては地名・人名・度量衡・数詞などが漢字の仮借で記されており、こうしたものは初期のチュノムの記録と呼べる[203]。まとまったチュノムの記録として最初期のものとしては、15世紀に阮廌がものした『國音詩集』がある[205][207]。18世紀から19世紀のベトナムでは阮攸、阮廷炤によってチュノムによるベトナム語文学が著されたほか、辞書・字書類にチュノムでの注釈が記されることもあったが、ベトナムの歴史を通じて、漢文・漢字に対するチュノムの地位は従属的なものであった[205]。
19世紀後葉よりベトナムはフランス植民地帝国に吸収されていく。フランス政府は阮朝および従来の知識層の勢力を削ぐため、科挙の廃止、公用文での漢文の廃止とフランス語の公用語化、そして17世紀に宣教師が作ったベトナム語のローマ字表記体系であるクォック・グーの普及政策を進めていく。1906年にはクォック・グーを中心とする学校教育が整備され、1920年代にはクォック・グーによる出版が全国に広まった。植民地下でも温存された阮朝宮廷では1930年代まで漢文による文書作成が続いており、また、ベトナム民主共和国が独立した後も1990年代ごろまではプライベートな手書き文字としてチュノムが書かれる例があったようである[208]。
ベトナム漢字音はおおむね、後期中古音を基盤とするものであるといわれている[209]。しかし、ジョン・ファン(John Phan)のような研究者は、いわゆる後期中古音とベトナム漢字音には対応しない点も多いとして、現代中国語の湘語・平話の祖型に近いであろう、安南中古中国語(Annamese Middle Chinese)の存在を仮定する[210]。中古音と比較したベトナム漢字音は、声母について、一般に清濁(有声・無声)を無声にまとめるが、声調にこれを反映させる。また、幫並母・端定母は有声入破音 [b] [đ] に対応する。また、(音韻学における)歯音が歯破裂音に対応する。唇音について重紐の区別があり、A類は唇音、B類は歯音で表現される。また、中古音における唐代以降の変化である、重唇音・軽唇音の差を反映する。韻母はおおむね唐代中古音のそれと同様であり、入声も -p, -t, -c, -ch として対応する[209][34]。
その他・漢字の派生文字

10世紀から12世紀にかけて勃興した非漢人系王朝である、遼(契丹)・西夏(タングート)・金(女真)は、それぞれ契丹文字・西夏文字・女真文字を作った。契丹文字には、遼を建国した耶律阿保機が920年、耶律突呂不と耶律魯不古に作らせた契丹大字と、阿保機の異母弟にあたる耶律迭剌が925年ごろに作らせた契丹小字の2種類がある。前者はある程度の表語性を有し、漢字からの仮借も行われていた一方、後者は表音性が強く、字符こそ契丹大字と共有するものの音義に関連性はない。女真文字にも、大字と小字の2種類がある。大字は金を建国した完顔阿骨打が1119年、完顔希尹に作らせたもので、小字は熙宗が製字し、1138年に頒行した。女真文字は漢字に加え、契丹文字の影響を受けているようである。西夏文字は1306年に頒行され、漢字と同形の要素こそないものの、漢字に倣って偏旁を組み合わせた作字を行う。ほとんどが形声文字ないし音符の組み合わせからなる[211]。

現在の中国・広西チワン族自治区を中心に居住するチワン人の言語であるチワン語には、多くの中国語からの借用語が含まれる。チワン語のいくつかの方言の漢語系語彙は、平話の語彙と規則的な対応を示す[212]。チワンの文字である古壮字は、漢字からの音義の借用ないし、形声・会意によってつくられる。689年の『六合堅固大宅頌』にあらわれるいくつかの文字が既知の初出の例と言われている。主に聖職者によって用いられるほか、民謡歌集や、伝統劇である壮劇の記述などにも用いられている[213]。
漢字ないし漢字を改造して作った方塊字を用いる民族は、チワン人のほかにも、トン人、ペー人、リス人など多くある[214]。中国南部の少数民族が用いる方塊字としてはほかに、トン人がトン語表記に用いる方塊トン字[214]、プイ人がプイ語表記に用いる方塊プイ字、ヤオ人がミエン語表記に用いる方塊ヤオ字、ミャオ人のうちミャオ語湘西方言話者が用いる方塊ミャオ字などが知られている[213]。
標準化と簡略化
歴史的に、漢字文化圏の諸国家は、漢字の使用を改革・標準化しようと試みてきた。これには、字体・筆順・発音といったものが含まれる。1950年代から1960年代にかけて、中国本土では数千字におよぶ簡体字が標準化・採用された。これらの多くはすでに一般的に使われていた簡化字、あるいは部首や構成要素を体系的に簡略化することによって作られた文字であった[215]。
第二次世界大戦後、日本政府も数百字の漢字を省略した[216]。こうした省略を経ていない漢字は、繁体字と呼ばれる。中国語圏では、中国本土(中華人民共和国)・マレーシア・シンガポールが簡体字を使用し、台湾(中華民国)・香港・マカオが繁体字を使用している[217]。一般的に、中国語話者や日本語話者は、これら三つの標準体系の漢字をおおむね判別することができる[218]。日本・中国・台湾・香港・韓国はそれぞれ標準字体を整備してきたため、文字こそ共有しているものの字体が異なる字もいくつか存在する[219]。
中国
王朝時代
漢字の整理は中国における歴史的課題であり、『周礼』春官には「三皇五帝の書を掌り、書名の四方に達するを掌る」職である「外吏」が定められている。孫詒譲『周礼正義』によれば、「書名」とはすなわち文字のことであり、この職は全国の文字を統一することを目的とするものである。『管子』君臣上にも、「書名を同じくす」という問題が、理想的な政治体系を論じるうえで触れられている[220]。
秦代には従来用いられていた六国文字が廃止され、文字の統一が行われたものの、南北朝時代にはふたたびこれがゆらぎ、唐代にふたたび正字政策に力が入れられた。文字の正俗について論じる『干禄字書』はこのとき編纂されたものである。玄宗帝の時代である735年に公布された『開元文字音義』も、楷書の字形の統一に影響を与えたといわれている[220]。西原一幸は、こうした字書において定められる「俗体」も隷書から楷書への転換の中で人工的に作られたものであり、当時としては社会的に認められた字体であったと論じる。錯誤しやすい字形について論じる字書をまとめて字様書といい、『干禄字書』以前のものとしては敦煌文献にある『正名要録』といったものが挙げられる[221]。
宋代には印刷業の発展や、科挙の試験における文字の書き方に対する規範が厳格化したことなどにより、文字の字形はさらに固定化していった。とはいえ、前近代中国において行われていた文字政策はいずれも保守的なものであり、民間で使われていた簡体字を排除して伝統的なものにとりまとめようとする傾向が強かった[162]。
中華民国
19世紀後半から20世紀初頭にかけて、清代の知識人の間では、中国語の文字体系や口語共通語の欠如が、大衆の識字率向上や全国的な意思疎通を妨げ、国家の近代化の障害となっているとの認識が広まった。そのため、多くの知識人が、書き言葉を口語に近いものに置き換えること、文字形の大規模な簡略化、さらには特定の方言に合わせたローマ字表記体系への転換を提唱するようになった。1909年には教育者・言語学者の陸費逵がはじめて、教育における簡体字の採用を公式に提案した[222]。
1912年には、辛亥革命を通して中華民国が成立する。中華民国は独立当初より国語政策に取り組み、1918年には漢字発音に当たって用いる記号である注音字母が制定された。また、同時期には雑誌『新青年』などを中心に口語中国語による創作が隆盛し、白話運動を盛り上げた[223]。1920年代から1930年代にかけては、銭玄同らにより漢字簡略化が提唱され、宋元明清の略字などの研究が推し進められた[224]。1935年には教育部により、「社会に比較的通行する簡体字」324字をとりまとめた『第一批簡体字表』が公布され、教育現場で採用されることなった。しかし、政府内部での反対により、実際には施行されることはなかった[225]。1937年に盧溝橋事件が起こり、日中戦争がはじまると、抗日戦争と内戦激化により簡体字運動は停滞した[226]。
中華人民共和国

中国共産党は1949年に中華人民共和国を成立させた。同国政府は中華民国時代の文字政策を引き継ぐかたちで文字改革を進め、1955年に『漢字簡化方案』および『第一批異体字整理表』を発表した[227]。『方案』で定まった漢字は1956年から1959年にかけて公布された。1964年には2238文字を収録する『簡化字総表』が発表され、偏旁に対しても同様の規則を当てはめることなどが定まった[228]。こうして定まった簡体字の多くは、以前より用いられていた略字ないし従来正字とされていたものよりも筆画の少ない古字から選ばれた[229]。
また、1958年には漢語拼音方案が批准され、漢字のローマ字表記体系である拼音が定まった[230]。また、1955年から1964年にかけてはこれらと並行して、県級以上にあたる地名に見られる僻字が、同音ないし近い音の字に改められた。1965年には『印刷通用漢字字形表』が発表され、印刷用の漢字に対する標準字形が定められた[231]。1977年には第二次漢字簡化方案が定められたが、一般的にほとんど用いられていなかった略字が多く含まれていたことからほとんど浸透せず、1986年に撤回された[232]。この撤回をもって、中華人民共和国における文字改革はおおむね終了した[233]。1986年には『簡化字総表』が一部改定されたほか、1988年には『印刷通用漢字字形表』を増補・刪定した、7000字からなる『現代漢語通用字表』が発布された[234]。2013年には『現代漢語通用字表』を改めた、8105字からなる『通用規範漢字表』が定められた[235]。
台湾・香港・シンガポール
遷台以降の中華民国(台湾)においても、1953年より教育部により簡略化文字座談会が開かれ、漢字の簡化政策が再び行われようとしていた。しかし、中国共産党が積極的に漢字の簡体化を進めていたことを背景とするイデオロギー的・社会的反発も大きく、こうした政策研究は中止されることとなった[236]。台湾では、1982年に4808字に関して繁体字の標準字形を定める『常用国字標準字体表』が発布された[237]。香港では、イギリス統治下の1986年に『常用字字形表』が発布された。当初同字表は4721字からなったが、その後2007年までに5回の改定を経て4762字となった[238]。
シンガポールでは、漢字の簡体化が行われた。1969年に502文字、1974年には2287文字の簡体化が発表され、後者のうち49文字は中国本土の簡体字と異なっていた。1976年には、これらの文字が削除された。1993年以降、シンガポールでは中国本土の簡体字表がそのまま用いられるようになった[239]。
日本

江戸期の日本において、公的な文書の多くには漢文が用いられていた。しかし、幕末以降、欧米の思想が浸透するようになると、これら漢字・漢文の必要性を疑問視する声が大きくなった[240]。1866年には前島来輔が江戸幕府将軍・徳川慶喜に『漢字御廃止之議』を建白し、明治維新後もさまざまな論者によって漢字廃止論や漢字制限論が唱えられた。福沢諭吉は『文字之教』にて漢字制限を表明・実行したほか、『郵便報知新聞』も紙面で用いる漢字を3000字に限定した[197]。当時の日本における言語の表記法をめぐる論争を国語国字問題というが、こうした動きは同時代の中国にも影響を与えていたことが知られている[241]。
大正期には、国語政策の一環として漢字表が作られるようになる。1919年には、教科書で用いられていたおよそ2600字について字体を整理する『漢字整理案』が発表された。さらに、1923年には1962字からなる『常用漢字表』が制定され、同表に無い漢字は仮名で書くことが定められた。しかし、これは同年に起こった関東大震災の影響でよく普及しなかった。1931年には1856字に改められた常用漢字表が改めて発表されたが、同年に満州事変が起こり、中国の地名・人名が報道に頻出するようになったため、失敗した[197]。1942年には2669字からなる『標準漢字表』が発表され、これは太平洋戦争終戦後である1960年に1850字からなる『当用漢字表』に改められた。当用漢字表にはいわゆる康煕字典体(旧字体)と異なる簡易字体が多数採用され、これを新字体ともいう。当用漢字表は漢字の制限を狙ったものであったが、1981年にはこれを「漢字使用の目安を示すもの」と改めた、1945字からなる『常用漢字表』が発表された。2010年、常用漢字は196字を追加、5字を削除し、2136字となった[242]。
韓国
19世紀後半の李氏朝鮮においては、列強の圧力を背景に民族意識が高まり、ハングルへの注目が集まった[243]。ハングルが「国文」としての公的地位を得たのは高宗の時代である1894年、甲午改革を通してであるが[244][245]、1910年の韓国併合により朝鮮は日本の統治下に置かれる[246]。李承晩政権率いる独立後の韓国では1948年に「ハングル専用に関する法律」が制定され、公文書のハングルでの作成が義務付けられた[247]。1951年には1000字からなる教育漢字が指定されたが[248]、朴正煕政権下ではハングル専用政策がとられ、1970年には教育漢字も廃止された[249]。1972年にはこれに代わり、1800字からなる漢文教育用基礎漢字が制定された[219]。
符号化と入力

電報やタイプライターをはじめとするメディアは漢字のような文字体系を想定しておらず、その導入には困難が生じた。こうした近代的情報技術と漢字の相性の悪さは、しばしば漢字という文字体系の非近代性について論じるうえで引き合いに出された[250]。
中国語を用いた電報のための符号である電碼は、1871年に導入された。これは、およそ6800字を『康煕字典』の掲載順に並べ、4桁の数字を割り振ったものである。中華圏の通信士は、これをコードブックを用いてエンコード・デコードすることで情報を送受信した[251]。はじめての実用的な中文タイプライターは周厚坤により創案され、1918年ごろに商務印書館の舒震東により実用化された。これは数千の文字が並んだ文字盤を金属製の指示棒で指し示し、その位置に対応する活字を選択して印字する仕組みであった[252]。同時期には、杉本京太などにより漢字仮名交じり文を打鍵可能な和文タイプライターも開発された[253]。
1950年代中葉からは、日本において多段シフトキーボードによる入力を主流とする、漢字仮名交じり文の電信伝送がはじまった[254][255]。中国においても特殊なキーボードを用いた漢字入力方法が模索され続けていたが、1970年代から1980年代にかけてはパーソナルコンピューターが普及し始め、いわゆるQWERTYキーボードを用いた漢字の入力法が多数考案された。当時の中国語入力において拼音といった発音に依拠した入力方式はあまり一般的ではなく、むしろ構造に基づいた入力方式が人気を集めた。こうした入力方式の嚆矢となったのは支秉彝による見字識碼であるが、ほかに三角編号法・五筆字型輸入法・倉頡輸入法などが市場で一定程度普及した[256]。日本においては1964年に栗原俊彦が開発した手法を基盤として、1970年代にワードプロセッサーを中心に漢字かな変換システムが搭載されるようになった[257][258]。
入力方式

漢字の入力方式には、大きく分けると文字に割り当てられた符号位置そのものを入力する漢字直接入力(direct methods)と、読みや字形を入力して漢字に変換する間接方式(indirect methods)がある。前者は直感的でないため、一般的には後者が用いられる[259]。音声入力や手書き入力、OCRといったものも入力方式にふくまれる[260]。漢字入力には、インプットメソッドとよばれる変換辞書を備えたソフトウェアが利用される[261]。
かつての日本製ワードプロセッサーでは仮名文字2つを特定の漢字に当てはめた漢字入力方式(2ストローク方式)が少なからず用いられており[254]、これは「ハハ」を「母」に変換するような連想式漢字直接入力がほとんどであった[262]。また、電碼や四角号碼を直接入力する方式も存在する[263]。発音をもとにする入力方式には、拼音・注音符号・仮名文字を用いるものがある。拼音での入力方式には、声母のみを入力する簡拼、すべて入力する全拼、声母と韻母をそれぞれ1キーにまとめた双拼がある。仮名文字を用いた入力方式には、仮名を直接各キーにあてはめたかな入力と、ローマ字で仮名を入力し、それをさらに漢字に変換するローマ字入力の2方式がある[264]。文字構造をもとにする入力方式としては、五筆字型輸入法のように筆画を分割したもの、倉頡輸入法や鄭碼輸入法のように、偏旁・形符を分割したものなどがある。あるいは、認知碼輸入法のように、偏旁と発音を組み合わせた入力方式もある[265]。
符号化文字集合

通信のために用いられる、漢字を符号化したコードの嚆矢は、先述した電碼である[266]。コンピューターにおいては、当初IBM・富士通・日立といった各ベンダーが独自の基準を作っていたほか[267]、日本では新聞社や国会図書館の電算システムなどにも独自の文字コードがあったようである[266]。日本においては、1978年のJIS C 6226においてはじめて国家レベルで標準化された。同規格は1973年制定のISO 2022との整合性を保つべく、94×94を基本単位として作られた[266]。これは漢字文化圏において作られたはじめての国家レベルの文字コードであり、周辺地域にも刺激をもたらした[268]。1980年のGB 2312(中国)、1982年のKS C 5619(韓国)なども94×94を基本単位として作られた[266]。また、台湾では1984年にBig5が発表され、国家規格ではないものの事実上の標準となった[269]。これらのもコードは互換性を有さず、国をまたいだやり取りには不便であった[266]。
1989年に成立したUnicodeは世界の文字を統一的に扱うことを目的とする符号化文字集合であり、1993年より同様の趣旨を持つ国際規格であるISO 10646と事実上統合されている[270]。1992年の Unicode 1.1 においては[271]、これら各地域の文字コードを統合し、異なる字形を包摂することによりつくられたCJK統合漢字20,902字が登録された[272]。当初、Unicodeは16ビット・65,536字から構成されていたが[270]、2000年の Unicode 3.1 において42,711字からなるCJK統合漢字拡張Bが追加されて以降、当初の基本多言語面以外にも割当が行われるようになった[273]。2003年の Unicode 4.0 では異体字セレクタが導入され、従来包摂されていた字形が表示可能となった[274]。2025年の Unicode 17.0 においては、漢字は述べ102,998字登録されている[275]。
漢字をめぐる文化
書道
書ないし書道は、毛筆と墨などを用いて書字をする造形芸術である。中国における書は六芸のひとつであるとともに、科挙の科目とでもあり、官吏や知識人なら必ず学ぶべき教養と位置づけられた。書道を確立したのは戦国時代・東晋の王羲之であるとされ、伝統的には楷・行・草の三書を確立したといわれている[276]。中国を含む漢字文化圏において、書は文学や絵画などと並び、場合によっては融合しながら、文化史上重要な位置を占め続けた[277]。また、書道の理論も研究され、これを書論と呼んだ[278]。
書道においては一般的な書体のほかに、装飾的な書体も広く用いられた。デザイン性の高い書体としては、篆書の装飾体であり、北宋の夢英が集めたという十八体書や、後漢の蔡邕が考案したという飛白といったものがある[221]。また、日本の江戸文字やベトナムの令書のように、地域的な書体もあった[279]。明代には、「寿」の篆書100種類を書いた百寿図や、縁起の良い事物の絵で字を象った花文字といった芸術もあらわれた[221]。
宗教
道教においては、しばしば特殊な漢字様の符号(諱秘字)が記される。これはおおむね、複数の漢字の合字である道教複体字、道教の神名である仙尊聖諱、護符に用いられる符文、呪文に用いられる呪語、真言に分類することができる[280]。また、仏教においても、『釋摩訶衍論』などに呪文の文字として特異な漢字ないし漢字様の符号がみられる。これには則天文字の影響があると考えられており、石井公成や関悠倫らはこれに加え道教の護符の影響も指摘している[281]。
敬惜字紙は、中国における、文字の書かれた紙を尊重し、汚損することを禁じる思想である。清代に科挙の神として知られる文昌帝君信仰の文脈から興ったとされ[282]、台湾などにはこの思想にもとづき、路上に落ちている文字の書かれた紙などを拾い集め、惜字炉とよばれる炉で燃やして供養する風習がある[283]。
脚注
注釈
- ^ なお、上古中国語には「落(*kə.rˤak)」のように、副音節をともなう2音節語も存在したことが指摘されているが、こうした語もやはり1文字で記述された[32]。
- ^ 「鉈」字に「なた」の義を与えるのは国訓[42]。
- ^ 「視」自体は、のちに声符である「示」がついた分化字である[65]。
- ^ 『説文解字』は「安」の字源について「女の宀下に在るに従う」と論じるが[73]、陳剣によれば、「安」は人が跪き座る様子を表した「
 」に意符の「宀」を付加したものである[74]。
」に意符の「宀」を付加したものである[74]。 - ^ 裘の操作的定義からは外れるものの、「本字」という語句は、「舜」に対する「䑞」といったある文字の原初的な書写形式、あるいは「娶」に対する「取」のような、分化字のもととなった文字を呼称するためにも用いられてきた[88]。
- ^ 好歹(こうたい)といった熟語に使われる「歹」を指す。これは、「死」「残」などに含まれる「歹(がつ)」とは同型の別字である[92]。
- ^ 中国の研究者を中心に、夏王朝と二里頭文化の王朝は同一視されることも多い一方、この見解は日本や欧米においても広く認められるものではない。宮川一夫はこの理由を、夏王朝の存在を確証づける同時代の文字資料がないためとまとめる[103]。落合淳思によれば、二里頭文化の王朝は王朝と言える規模であったことこそ疑いないとはいえ、その支配地域は黄河中流域に限られ、伝世文献に記されるような九州を支配するような国家ではなかった。文献に伝わる「夏」は二里頭文化と時期こそ一致するものの、後代に作られた神話としての性質が強い。「夏」という王朝名自体もおそらく周代に定まったものであり、二里頭文化の王朝の自称が何であったかは定かではない[104]。
- ^ 『竹書紀年』および『史記』の記述から、伝統的には殷墟への遷都を行った王は盤庚とされてきたが、この記述には甲骨文字史料をふくむ出土資料との乖離があった[116][117]。宮川は、その後新しく検出された洹北商城こそが盤庚遷殷による宮都であるとの説を紹介している[118]。
- ^ 殷周代の青銅器に記された氏族ないし個人名を表す金文。族徽とも呼ぶ。象形性が高く、これを文字とみなさない考えもある一方、裘はこれを文字とみなした上で、その形質の差異は古体と今体の違いによるものと論じる[122]。
- ^ 『説文解字』には、始皇帝の臣下らの文字の統一作業に当たって「皆な史籀の大篆を取り、或いは頗る省改す」と、小篆が籀文をもとにつくられた文字であるように書かれている。籀文とは伝統的に西周の文字と考えられてきた、『史籀篇』にみえる字体であるが、古文字資料を確認する限り、小篆と秦文字には連続性がある。「大篆」という言葉は小篆以前に現れた古い文字を指して用いられるが、その定義ははっきりとしたものではない[146]。
出典
- ^ “UNICODE U+4E00 - U+9FFF”. 2007年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年11月19日閲覧。
- ^ Qiu 2000, p. 1; Handel 2019, pp. 4–5.
- ^ 裘 2022, pp. 30–33; Norman 1988, p. 74.
- ^ Qiu 2000, pp. 13–15; Coulmas 1991, pp. 104–109.
- ^ Li 2020, pp. 56–57; Boltz 1994, pp. 3–4.
- ^ Boltz 2011, pp. 57, 60.
- ^ a b c d e f g h i j k l 「漢字」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2025年11月8日閲覧。
- ^ 王 2023a, p. 14.
- ^ 裘 2022, pp. 23–25.
- ^ 裘 2022, p. 202.
- ^ 裘 2022, p. 18.
- ^ Handel 2019, pp. 43–44.
- ^ Li 2020, pp. 54, 196–197; 北京大学现代汉语教研室 2004, pp. 148–152; Zhou 2003, p. 88.
- ^ Norman 1988, p. 86; Zhou 2003.
- ^ 「筆画」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月8日閲覧。
- ^ Li 2009, p. 70.
- ^ 王 2023b, pp. 16–17.
- ^ Li 2020, p. 54; Handel 2019, p. 27; Keightley 1978, p. 50.
- ^ Taylor & Taylor 2014, pp. 372–373; Bachner 2014, p. 245.
- ^ Needham & Harbsmeier 1998, pp. 175–176; Taylor & Taylor 2014, pp. 374–375.
- ^ a b 山本 2023.
- ^ Lunde 2008, pp. 23–25.
- ^ 裘 2022, p. 365.
- ^ 裘 2022, pp. 367–371.
- ^ 裘 2022, p. 366.
- ^ 「異体字」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。コトバンクより2025年11月9日閲覧。
- ^ a b c 三村 2023, p. 18.
- ^ a b c d e 「漢字」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月8日閲覧。
- ^ 三村 2023, p. 21.
- ^ “第3章 字体・字形に関するQ&A”. 文化庁 (2016年9月1日). 2025年11月9日閲覧。
- ^ 裘 2022, pp. 34–35.
- ^ Baxter & Sagart 2014, pp. 50–53.
- ^ 河野六郎「音韻学」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月8日閲覧。
- ^ a b c d e f g 豊島正之「字音」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月9日閲覧。
- ^ a b 裘 2022, p. 449.
- ^ 裘 2022, pp. 447–448.
- ^ 裘 2022, pp. 193–194.
- ^ 裘 2022, p. 448.
- ^ 季 2014, p. 894.
- ^ 裘 2022, p. 436.
- ^ 裘 2022, p. 372.
- ^ 「鉈」『普及版 字通』。コトバンクより2025年11月8日閲覧。
- ^ 殷 2007, pp. 97–100; 苏 2014, pp. 102–111.
- ^ 杨 2008, pp. 147–148.
- ^ Norman 1988, pp. 67–69; Handel 2019, p. 48.
- ^ 裘 2022, pp. 184–189.
- ^ Demattè 2022, p. 14.
- ^ 裘 2022, pp. 200–203.
- ^ 黄 2023, pp. 5–7.
- ^ a b 裘 2022, p. 207.
- ^ 裘 2022, p. 252.
- ^ a b 裘 2022, pp. 208–210.
- ^ 裘 2022, p. 210.
- ^ Yong & Peng 2008, p. 19.
- ^ Qiu 2000, pp. 44–45; Zhou 2003, p. 61.
- ^ Qiu 2000, pp. 18–19.
- ^ Qiu 2000, p. 154; Norman 1988, pp. 68.
- ^ 裘 2022, p. 222.
- ^ 裘 2022, p. 184.
- ^ 裘 2022, p. 186.
- ^ 裘 2022, p. 223.
- ^ 裘 2022, pp. 247–251.
- ^ 裘 2022, pp. 224–225.
- ^ 裘 2022, pp. 231–234.
- ^ 裘 2022, p. 419.
- ^ 裘 2022, pp. 235–236.
- ^ 裘 2022, pp. 239.
- ^ 裘 2022, p. 241.
- ^ 裘 2022, pp. 187–188.
- ^ Boltz 1994, pp. 104–110.
- ^ Sampson & Chen 2013, p. 256.
- ^ Sampson & Chen 2013, pp. 265–268.
- ^ “安 - 中國哲學書電子化計劃” (中国語). ctext.org. 2025年11月4日閲覧。
- ^ 徐 2022, pp. 1–2.
- ^ 裘 2022, p. 269.
- ^ Cruttenden 2021, pp. 167–168.
- ^ 裘 2022, p. 270.
- ^ 裘 2022, p. 220, 272.
- ^ 裘 2022, pp. 274–275.
- ^ 裘 2022, pp. 286–289.
- ^ 裘 2022, p. 292.
- ^ 裘 2022, pp. 298–300.
- ^ 裘 2022, pp. 302–212.
- ^ 裘 2022, pp. 312–318.
- ^ 裘 2022, pp. 7–9.
- ^ 裘 2022, pp. 329–335.
- ^ 裘 2022, p. 322.
- ^ 裘 2022, pp. 319–322.
- ^ 裘 2022, pp. 320–321.
- ^ 裘 2022, pp. 323–329.
- ^ 裘 2022, p. 323.
- ^ 裘 2022, p. 204.
- ^ 裘 2022, pp. 202–205.
- ^ Demattè 2022, pp. 79–80.
- ^ 宇野 & 平岡 1974, pp. 386–387.
- ^ 山田 2016, p. 48.
- ^ 裘 2022, p. 39.
- ^ 裘 2022, pp. 1–2.
- ^ 裘 2022, pp. 39–52.
- ^ Pilcher, Helen R. (2003-04-30). “Earliest handwriting found?” (英語). Nature. doi:10.1038/news030428-7. ISSN 1476-4687.
- ^ 黄 2023, pp. 14–15.
- ^ a b 裘 2022, p. 55.
- ^ 宮川 2020, p. 22.
- ^ a b 落合 2015, p. 24.
- ^ 黄 2023, p. 48.
- ^ 宮川 2020, p. 367.
- ^ 裘 2022, pp. 46–47.
- ^ 裘 2022, p. 41.
- ^ 裘 2022, p. 56.
- ^ 裘 2022, pp. 33–34.
- ^ 裘 2022, pp. 34–37.
- ^ 裘 2022, pp. 38–40.
- ^ a b 裘 2022, p. 54.
- ^ 宮川 2020, p. 387.
- ^ 宮川 2020, p. 435.
- ^ 宮川 2020, p. 463.
- ^ 落合 2015, p. 45.
- ^ 宮川 2020, p. 466.
- ^ Boltz 1999, pp. 74, 107–108.
- ^ a b 裘 2022, p. 57, 59.
- ^ 落合 2015, p. 136.
- ^ 裘 2022, pp. 53–54.
- ^ 裘 2022, p. 57.
- ^ a b 黄 2023, p. 60.
- ^ 落合 2015, p. 177.
- ^ 黄 2023, pp. 61–63.
- ^ 「散氏盤」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。コトバンクより2025年11月7日閲覧。
- ^ a b 裘 2022, p. 88.
- ^ 黄 2023, p. 152.
- ^ 裘 2022, pp. 61–63.
- ^ 黄 2023, p. 157.
- ^ 黄 2023, pp. 159–160.
- ^ 裘 2022, pp. 91–92.
- ^ 黄 2023, pp. 311–312.
- ^ 黄 2023, pp. 280–281.
- ^ a b 裘 2022, p. 92.
- ^ 黄 2023, p. 389.
- ^ 黄 2023, p. 393.
- ^ 黄 2023, pp. 381–382.
- ^ 裘 2022, p. 93.
- ^ a b 黄 2023, p. 398.
- ^ 裘 2022, pp. 109–111.
- ^ 福田 2016, p. 177.
- ^ 黄 2023, p. 533.
- ^ 裘 2022, p. 101.
- ^ 裘 2022, pp. 98, 125–126.
- ^ 裘 2022, p. 126.
- ^ 黄 2023, p. 570.
- ^ 裘 2022, pp. 126–129.
- ^ 裘 2022, p. 595.
- ^ 裘 2022, p. 579.
- ^ 裘 2022, p. 131.
- ^ 裘 2022, p. 583.
- ^ 黄 2023, pp. 139–140.
- ^ 黄 2023, p. 140.
- ^ 裘 2022, pp. 152–154.
- ^ 裘 2022, pp. 156–160.
- ^ 裘 2022, pp. 162–165.
- ^ 裘 2022, pp. 169–173.
- ^ Chan 2020, p. 125.
- ^ Qiu 2000, p. 143.
- ^ a b c d 裘 2022, pp. 174–181.
- ^ 裘 2022, pp. 491–492.
- ^ Li 2020, p. 41.
- ^ 裘 2022, p. 492.
- ^ Vogelsang 2021, pp. xvii–xix.
- ^ Handel 2019, p. 34; Norman 1988, p. 83.
- ^ Handel 2019, pp. 11–12; Kornicki 2018, pp. 15–16.
- ^ Handel 2019, pp. 28, 69, 126, 169.
- ^ Kin 2021, p. XII.
- ^ Denecke 2014, pp. 204–216.
- ^ Handel 2019, p. 212.
- ^ Handel 2019, p. 11.
- ^ 笹原 2023, pp. 206–207.
- ^ a b Handel 2019, pp. 103–108.
- ^ 笹原 2013, p. 20.
- ^ 張 2023, pp. 444–445.
- ^ 鷺澤 2023.
- ^ 藤本幸夫「東国正韻」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月10日閲覧。
- ^ 古澤 2023.
- ^ Handel 2019, p. 65.
- ^ Handel 2019, pp. 66–67.
- ^ 張 2023.
- ^ Handel 2019, p. 91.
- ^ Handel 2019, pp. 110–111.
- ^ a b Handel 2019, p. 112.
- ^ 金 1984, pp. 129–152.
- ^ Handel 2019, pp. 112–113.
- ^ 河崎 2023.
- ^ Handel 2019, pp. 79–80.
- ^ Handel 2019, p. 189.
- ^ Handel 2019, pp. 88–94.
- ^ 沖森 2023.
- ^ 「仮名」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月10日閲覧。
- ^ 田中草大 2023.
- ^ 佐藤 2023.
- ^ a b c 山下 2023.
- ^ a b c 田中郁也 2023.
- ^ Handel 2019, pp. 177–178.
- ^ Handel 2019, pp. 198–199.
- ^ 月本雅幸「訓」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2025年11月9日閲覧。
- ^ a b Handel 2019, pp. 124–126.
- ^ a b c 清水 2023.
- ^ Handel 2019, p. 133.
- ^ a b c 巻下 2023, p. 240.
- ^
 (中国語) 大越史記全書/本紀卷之五, ウィキソースより閲覧。
(中国語) 大越史記全書/本紀卷之五, ウィキソースより閲覧。 - ^ Handel 2019, p. 134.
- ^ 岩月 2023.
- ^ a b 清水 2023a.
- ^ Handel 2019, p. 132.
- ^ 荒川 & 大竹 2023.
- ^ 黄 2023.
- ^ a b 蘇 2023.
- ^ a b 兼重 2023.
- ^ Zhou 2003, pp. 60–67.
- ^ Taylor & Taylor 2014, pp. 117–118.
- ^ Li 2020, p. 136.
- ^ Wang 2016, p. 171.
- ^ a b 安岡 & 安岡 2017, p. 70.
- ^ a b 裘 2022, pp. 492–493.
- ^ a b c 西原 2023.
- ^ Zhou 2003, pp. xvii–xix; Li 2020, p. 136.
- ^ 宮西 2014, pp. 48–50.
- ^ 宮西 2014, p. 103.
- ^ 宮西 2014, p. 106.
- ^ 宮西 2014, p. 107.
- ^ 宮西 2014, pp. 107–110.
- ^ 裘 2022, p. 493.
- ^ Chen 1999, pp. 155–156.
- ^ 宮西 2014, p. 89.
- ^ 裘 2022, p. 494.
- ^ Chen 1999, pp. 159–160.
- ^ Chen 1999, pp. 196–197.
- ^ 裘 2022, p. 495.
- ^ Li 2020, pp. 145–146.
- ^ 宮西 2014, pp. 115–116.
- ^ Lunde 2008, p. 81.
- ^ 安岡 & 安岡 2017, p. 61.
- ^ Shang & Zhao 2017, p. 320.
- ^ 増田 2013, p. 315.
- ^ 宮西 2014, p. 16.
- ^ 山下 2023b.
- ^ 金 1984, p. 144.
- ^ イ 2020, p. 19.
- ^ 大江孝男「ハングル」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月12日閲覧。
- ^ イ 2020, p. 20.
- ^ イ 2020, p. 46.
- ^ イ 2020, p. 51.
- ^ イ 2020, p. 65.
- ^ マラニー 2021, pp. 89–91.
- ^ マラニー 2021, pp. 123–126.
- ^ マラニー 2021, pp. 156–178.
- ^ マラニー 2021, pp. 211–212.
- ^ a b “誕生と発展の歴史-コンピュータ博物館”. museum.ipsj.or.jp. 情報処理学会. 2025年11月13日閲覧。
- ^ 浦城 2002, p. 1094.
- ^ Mullaney 2024, pp. 123–143.
- ^ “戦後日本のイノベーション100選 安定成長期 日本語ワードプロセッサ”. koueki.jiii.or.jp. 公益社団法人発明協会. 2025年11月13日閲覧。
- ^ 浦城 2002, p. 1095.
- ^ Lunde 2008, p. 299.
- ^ Lunde 2008, pp. 353–354.
- ^ Lunde 2008, p. 355.
- ^ 浦城 2002, pp. 1094–1095.
- ^ Lunde 2008, p. 320.
- ^ Lunde 2008, pp. 301–309.
- ^ Lunde 2008, pp. 317–319.
- ^ a b c d e 安岡 & 安岡 2017, p. 12.
- ^ Lunde 2008, p. 84.
- ^ Lunde 2008, p. 85.
- ^ 安岡 & 安岡 2017, p. 42.
- ^ a b 安岡 & 安岡 2017, p. 13.
- ^ Lunde 2008, p. 153.
- ^ Lunde 2008, p. 157.
- ^ “PDUTR #27: Unicode 3.1”. www.unicode.org. 2025年11月13日閲覧。
- ^ “Unicode 4.0.0”. www.unicode.org. 2025年11月13日閲覧。
- ^ “Unicode Character Count V17.0”. www.unicode.org. 2025年11月13日閲覧。
- ^ 「書」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2025年11月13日閲覧。
- ^ 「書」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月13日閲覧。
- ^ 杉村邦彦「書論」『改訂新版 世界大百科事典』。コトバンクより2025年11月13日閲覧。
- ^ Nawar 2020.
- ^ TCA , Academician Fong-Mao Lee (李豐楙) and Center for the study of Chinese religions, NCCU(政大華人宗教 研究中心) (2022年10月14日). “Suggestions for Taoism Sacral Character Encoding”. Unicode Consortium. 2025年11月14日閲覧。
- ^ 関 2021, pp. 35–38.
- ^ 李 2010, pp. 144–145.
- ^ 川崎 2015, p. 157.
参考文献
英語
- Bachner, Andrea (2014). Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of Culture. Columbia University Press. ISBN 978-0-231-16452-8
- Baxter, William H.; Sagart, Laurent (2014), Old Chinese: A New Reconstruction, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-994537-5.
- Boltz, William G.『The Origin and Early Development of the Chinese Writing System』American Oriental Society、1994年。 ISBN 978-0-940490-78-9。
- Chan, Sin-Wai, ed (2016). The Routledge Encyclopedia of the Chinese Language. Routledge.
ISBN 978-1-317-38249-2
- Wang, William S.-Y. "Chinese Linguistics". In Chan (2016), pp. 152–184.
-
———, ed. (2020). “The Three Kingdoms Period”. The Routledge Encyclopedia of Traditional Chinese Culture. Routledge. ISBN 978-1-138-21115-5.
{{cite encyclopedia}}: CS1メンテナンス: ref=harv (カテゴリ) - Chen Ping (陳平) (1999). Modern Chinese: History and Sociolinguistics (4th ed.). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-64572-0
- Coulmas, Florian (1991). The Writing Systems of the World. Blackwell. ISBN 978-0-631-18028-9
- Cruttenden, Alan (2021). Writing Systems and Phonetics. Routledge. ISBN 978-1-00-033404-3
- Demattè, Paola (2022). The Origins of Chinese Writing. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-763576-6
- Denecke, Wiebke (2014). “Worlds Without Translation: Premodern East Asia and the Power of Character Scripts”. In Bermann, Sandra. A Companion to Translation Studies. Wiley. pp. 204–216. ISBN 978-0-470-67189-4
- Handel, Zev (2019). Sinography: The Borrowing and Adaptation of the Chinese Script. Language, Writing and Literary Culture in the Sinographic Cosmopolis. 1. Brill. ISBN 978-90-04-35222-3
- Keightley, David (1978). Sources of Shang History: The Oracle-Bone Inscriptions of Bronze-Age China. University of California Press. ISBN 978-0-520-02969-9
- Kin, Bunkyō (2021). King, Ross. ed. Literary Sinitic and East Asia: A Cultural Sphere of Vernacular Reading. Language, Writing and Literary Culture in the Sinographic Cosmopolis. 3. Brill. ISBN 978-90-04-43730-2
- Kornicki, Peter (2018). Languages, Scripts, and Chinese Texts in East Asia. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-251869-9
- Li, Wendan (2009). Chinese Writing and Calligraphy. University of Hawaiʻi Press. ISBN 978-0-8248-3364-0
- Li, Yu (2020). The Chinese Writing System in Asia: An Interdisciplinary Perspective. Routledge. ISBN 978-1-138-90731-7
- Lunde, Ken (2008). CJKV Information Processing (2nd ed.). O'Reilly. ISBN 978-0-596-51447-1
- Mullaney, Thomas S. (2024). The Chinese Computer: A Global History of the Information Age. MIT Press. ISBN 978-0-262-04751-7
- Nawar, Haytham (2020). “Transculturalism and Posthumanism”. Language of Tomorrow: Towards a Transcultural Visual Communication System in a Posthuman Condition. Intellect. pp. 130–155. ISBN 978-1-78938-183-2. JSTOR j.ctv36xvqb7
- Needham, Joseph, ed (1998). Language and Logic. Science and Civilisation in China. VII:1. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-57143-2
- Norman, Jerry (1988). Chinese. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-29653-3
- Qiu, Xigui (2000). Chinese Writing. Early China Special Monograph Series. 4. Society for the Study of Early China and The Institute of East Asian Studies, University of California. ISBN 978-1-55729-071-7
- Sampson, Geoffrey; Chen, Zhiqun (2013). “The Reality of Compound Ideographs”. Journal of Chinese Linguistics 41 (2): 255–272. JSTOR 23754815.
- Shang, Guowen; Zhao, Shouhui (2017). “Standardising the Chinese language in Singapore: Issues of Policy and Practice”. Journal of Multilingual and Multicultural Development 38 (4): 315–329. doi:10.1080/01434632.2016.1201091. ISSN 0143-4632.
- Taylor, Insup; Taylor, M. Martin (2014). Writing and Literacy in Chinese, Korean and Japanese. Studies in Written Language and Literacy. 14 (Revised ed.). John Benjamins. ISBN 978-90-272-1794-3
- Vogelsang, Kai (2021). Introduction to Classical Chinese. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-883497-7
- Yong, Heming; Peng, Jing (2008). Chinese Lexicography: A History from 1046 BC to AD 1911. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-156167-2
中国語
- 北京大学現代漢語教研室『現代漢語』商務印書館、2004年。 ISBN 978-7-100-00940-9。
- 季旭昇『說文新證』(2版)藝文出版社、2014年9月。 ISBN 978-957-520-168-5。
- 蘇培成『現代漢字学綱要』(3版)商務印書館、2014年。 ISBN 978-7-100-10440-1。
- 徐超『古漢字通解500例』中華書局、北京、2022年。 ISBN 978-7-101-15625-6。
- 楊潤陸『現代漢字学』北京师范大学出版社、2008年。 ISBN 978-7-303-09437-0。
- 殷寄明『現代漢語文字学』復旦大学出版社、2007年。 ISBN 978-7-309-05525-2。
日本語
- イ・ソンヨン『言語共同体形成のための朝鮮半島における言語政策展開過程に関する研究 : 1910年から1979年までの言語表記単一化政策を中心に』(博士(国際関係学)論文)2020年3月31日。doi:10.34382/00013407。2025年11月12日閲覧。
- 宇野精一、平岡武夫 編『全釈漢文大系』 10巻、集英社、1974年。
- 浦城恒雄「日本の情報処理技術の足跡 漢字・日本語処理技術の発展 日本語の入出力と処理」『情報処理』第43巻第10号、情報処理学会、2002年10月15日、1093–1098頁、 ISSN 0447-8053。
- 落合淳思『殷 : 中国史最古の王朝』 2303巻、中央公論新社〈中公新書〉、2015年1月。 ISBN 978-4-12-102303-2。
- 川崎ミチコ「敬惜字紙について : 森島中良・瀧澤馬琴の敬惜字紙」『東洋思想文化』第2号、東洋大学文学部、2015年3月、158–140頁、 ISSN 2188-2991。
- 金両基『ハングルの世界』 742巻、中央公論新社〈中公新書〉、1984年。 ISBN 978-4121007421。
- 裘錫圭 著、稲畑耕一郎、崎川隆、荻野友範 訳『中国漢字学講義』東方書店〈東方学術翻訳叢書〉、2022年6月。 ISBN 978-4-497-22207-7。
- 黄徳寛 著、藪敏裕 監訳、 石川泰成、鋤田智彦、名和敏光、宮本徹、劉海宇 訳『古漢字発展論』樹立社〈漢字文化研究叢書〉、2023年6月。 ISBN 978-4-8433-6486-4。
- 笹原宏之『方言漢字』角川学芸出版〈角川選書〉、2013年2月。 ISBN 978-4-04-703520-1。
- 関悠倫「『釈摩訶衍論』の成立と武則天─新羅華厳との関係の再考─」『東洋学研究』第58巻、東洋学研究所、2021年、21–46頁、doi:10.34428/00013367、 ISSN 0288-9560。
- 日本漢字学会 編『漢字文化事典』丸善出版、2023年11月。
ISBN 978-4-621-30835-6。
- 王一凡『偏旁冠脚』、14–15頁。
- 王一凡『筆順と画数』、16–17頁。
- 三村一貴『正字・俗字・古字・別字』、18-20頁。
- 山本宣宏『書体と字体』、24-25頁。
- 田中郁也『呉音・漢音・唐音』、34-35頁。
- 河崎啓剛『朝鮮漢字音の研究方法』、48–51頁。
- 清水政明『ベトナム漢字音の研究方法』、52-55頁。
- 古澤義久『朝鮮半島における文字文化のはじまり』、146-149頁。
- 沖森卓也『記紀万葉以前の漢字』、162-163頁。
- 田中草大『中世の漢文』、180-181頁。
- 佐藤貴浩『近世の漢字』、182-183頁。
- 山下真里『近代の漢字』、188-189頁。
- 山下真里『現代の漢字』、194-195頁。
- 笹原宏之『字種の作製:日本製漢字・国字』、206-207頁。
- 西原一幸『字様』、262–263頁。
- 本田卓『デザイン性豊かな漢字たち』、398-399頁。
- 兼重努『隣接民族の文書と漢字文化受容』、432-433頁。
- 荒川慎太郎; 大竹昌巳『中国北方諸民族の漢字系文字』、434-437頁。
- 蘇柳朱『中国北方諸民族の漢字系文字』、438-441頁。
- 張玥『漢語の方言字と香港字』、444-445頁。
- 清水政明『ベトナムの漢字文化』、486-487頁。
- 趙晟桓『朝鮮における漢文の読み方』、478-479頁。
- 清水政明『ベトナムの漢字文化』、486-487頁。
- 鷺澤拓也『ベトナム漢字音とチューノムの関係』、487-491頁。
- 岩月純一『ベトナムにおける漢字廃止の過程』、500-501頁。
- 黄海萍『ベトナムにおける漢字廃止の過程』、508-509頁。
- 福田哲之「戰國竹簡入門 戰國竹簡文字研究略説」『漢字學硏究』第4号、立命館大學白川靜記念東洋文字文化硏究所、2016年12月、177–191頁、 ISSN 2187-7017。
- 増田周子「明治期日本と〈国語〉概念の確立:文学者の言説をめぐって」『東アジアにおける知的交流:キイ・コンセプトの再検討』第44巻、国際日本文化研究センター、2013年、315-326頁。
- 巻下由紀子「『漢字文化大観』第16章「世界での痕跡-海外における漢字」第3節「ベトナムにおける漢字」翻訳(前半)」『京都外国語大学国際言語平和研究所紀要』、京都外国語大学国際言語平和研究所、2023年、233–248頁。
- トーマス・S・マラニー 著、比護遥 訳『チャイニーズ・タイプライター : 漢字と技術の近代史』中央公論新社、2021年5月。 ISBN 978-4-12-005437-2。
- 宮川一夫『中国の歴史』 1巻、講談社〈講談社学術文庫〉、2020年10月。 ISBN 978-4-06-521261-5。
- 宮西久美子『近現代中国における言語政策 : 文字改革を中心に』(博士(言語文化学)論文)大阪大学、2014年。doi:10.11501/3161839。2025年11月12日閲覧。
- 安岡孝一; 安岡素子『日本・中国・台湾・香港・韓国の常用漢字と漢字コード』(レポート)京都大学未踏科学研究ユニット・学知創生ユニット・人文科学研究所、2017年3月1日、1–146頁。
- 山田崇仁「蒼頡傳説の形成過程について : 『説文解字』敍に至るまでを對象として」『漢字學硏究』第4号、立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所、2016年12月、31–51頁、 ISSN 2187-7017。
- 李季樺「十九世紀台湾における惜字慣習の形成」『中国』第25巻、2010年7月、144–159頁。
漢字(かんじ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 17:24 UTC 版)
識字率は低い方で、商家ならともかく庶民は知らない者が多い。紫劉輝によると常用漢字があるらしい。玖と九がそれぞれ人名に出るなど、新旧字体が混在している。読みは現実の音読みが多いが、櫂瑜の櫂の様に訓読みや、榛蘇芳の蘇芳の様に慣例読みの例もある。
※この「漢字(かんじ)」の解説は、「彩雲国物語の用語」の解説の一部です。
「漢字(かんじ)」を含む「彩雲国物語の用語」の記事については、「彩雲国物語の用語」の概要を参照ください。
漢字
「漢字」の例文・使い方・用例・文例
- 漢字
- 私の妹は最近漢字が読めるようになった
- あなたは漢字が上手に書けるね
- 学生は漢字が派手に描かれたTシャツを着ていた。
- かな漢字変換システムの変換候補
- 漢字の構成素のひとつ
- この漢字をどう読むのか私に教えてください。
- 日本では、たくさんの女性が美しいという意味の漢字を名前に持っています。
- 日本の駅の名前は漢字よりも英語を見た方が読めると思う。
- 漢字の宿題と奮闘中です。
- 彼にその漢字の読み方を教えて下さい。
- あなたはこの漢字を読むことができますか。
- あなたはどのようにその漢字を書きますか?
- 私はその漢字に間違いがあるのを見つけた。
- あなたは上手に漢字を書いていますよ。
- 彼女は難しい漢字が読めます。
- 私は漢字の宿題をする予定です。
- 彼はあまり漢字が読めない。
- あなたは彼よりもよりたくさんの漢字を知っているかもしれない。
Weblioカテゴリー/辞書と一致するものが見つかりました。
- 漢字辞典 - 漢字辞典
漢字と同じ種類の言葉
「漢字」に関係したコラム
-
FX(外国為替証拠金取引)のドテンとは、現在のポジションを決済して同時に逆のポジションを保有することです。ドテンは、漢字では「途転」と書きます。ドテンは、例えば売りポジションを決済して同時に買いポジシ...
- >> 「漢字」を含む用語の索引
- 漢字のページへのリンク