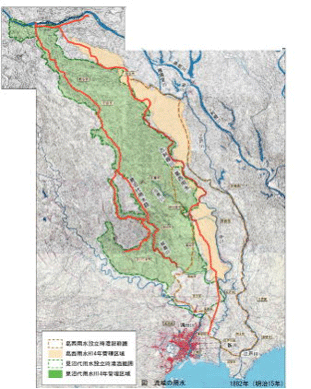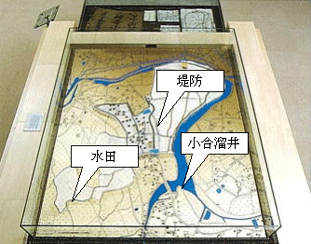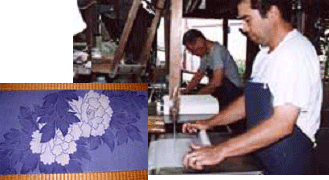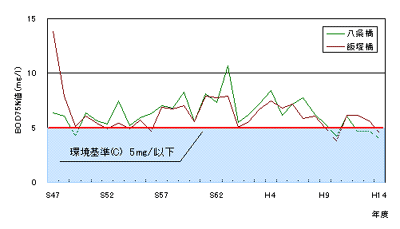なか‐がわ〔‐がは〕【中川】
なかがわ〔なかがは〕【中川】
中川
| 中川は埼玉県羽生市を上流端とし、大落古利根川、新方川、元荒川、大場川など多くの河川をあつめて南下し、東京都葛飾区高砂で新中川を分派します。さらに、中川七曲りと呼ばれる蛇行区間を経て綾瀬川と合流し、上平井で荒川と平行して流れ、江戸川区で東京湾に注ぐ流路延長約81km、流域面積約811km2の一級河川です。 綾瀬川は埼玉県桶川市を上流端とする流路延長約47km、流域面積約176km2の一級河川です。草加市で古綾瀬川、都県境の花畑地先で伝右川と毛長川を合わせ、葛飾区上平井で中川に合流しています。 中川・綾瀬川の流域は、流域一帯の勾配が非常にゆるやかな低平地河川という特徴をもっているため、しばしば洪水に見舞われてきました。さらにその後、急速に首都圏のベッドタウンとしての開発が進んだことにより、その重要性が高まっています。 |
 |
| 東京都葛飾区で中川と綾瀬川は合流する (手前から荒川、綾瀬川、中川) |
| 河川概要 |
|
 ○拡大図 |
| 1.中川・綾瀬川の歴史 |
| "利根川の東遷事業により洪水の危険が軽減された後の中川・綾瀬川流域の低地帯は地形を生かした灌漑排水網が整備され新田開発が行われました。中川沿いの集落の多くは、中川沿いに集中しており、自然堤防を利用することで少しでも洪水の危険性から逃れつつ、舟運を利用し、集落を形成していました。この地域は河川との深い関わりの中で人々の暮らしが営まれてきたことから、現在も「水」や「川」に因む地名が多く見られます。" |
|
灌漑と洪水の歴史 ‐中川‐ |
| 2.地域の中の中川・綾瀬川 |
| "戦後から高度経済成長期にかけて人口が急増し、市街化が急激に進展しました。この市街化に伴い、湿地がひろがっていた一帯は住宅地へとかわっていきました。 古くから人口と産業が集積し、高密度な都市が形成した中川の下流域では広い水面が都市の中で貴重な空間となっています。中川は河川敷がほとんどないことなどから、水面を使った利用が盛んで、沿川自治体が開催するイベントには毎年多くの人で賑わっています。綾瀬川は町の中心を流れ、川沿いには文化施設もあることから町の顔になっています。" |
地域の発展と洪水への対策
この急激な都市化により、綾瀬川には多くの汚濁物質が流れこみ、昭和40年代をピークに汚濁がすすみ、国土交通省管理の一級河川のなかで、全国ワースト1を昭和55年より15年間も継続するという不名誉な記録を持っています。 しかし、問題に地域住民と行政が協力して取り組むことで、年々水質は改善される傾向にあります。 もともと、洪水を受けやすい地域であったことに加え、この急速な市街地によって中川流域は毎年のように浸水被害は増加しました。そのため、中川は支川綾瀬川ともに河川改修、貯水池の活用、土地利用の適正化などを実施し、流域全体で洪水を防ぐ「総合治水対策」が進められています。 |
| 3.中川・綾瀬川の自然環境 |
| "中川はボラ、マハゼ、モツゴ等が生息しています。底生生物は、ゴカイが見られるとともに淡水性のヤゴ、カゲロウ類が多く生息しています。鳥類はユリカモメ、スズメなど水面や水辺及び都市部に生息する種が多く見られます。水際にはヨシ群落オギ群落等の自然植生がわずかに分布し、オオヨシキリ、カヤネズミ、ヒヌマイトトンボ、コムラサキ等も確認されています。上流部では、オオタカ、ハヤブサ等の猛禽類も確認されています。 中川の水質は、環境基準を上回る状況が続き、一級河川の水質調査結果では近年常にワースト上位に位置しています。 綾瀬川の魚類は、下流部でコイ、フナ等の汚濁に強い魚類が確認されています。底生動物は、水質汚濁に強いシマイシビル、ユスリカ等が生息しています。綾瀬川は草地や畑地面積が少なく市街化が進んでいますが、スズメ、ムクドリ等が多く見られます。 綾瀬川の水質は昭和40年代をピークに汚濁が進みワースト1を平成55年から15年間も記録しました。その後流域が一体となった取り組みによりワースト1を脱却し、環境基準を満足する程度まで水質改善が進んでいます。" |
|
中川の自然環境 中川の水源の多くは、利根大堰から取水された農業用水となっているため、中川の流量はかんがい期(5月~9月)において、通常時多く、水質もよくなっています。逆に非かんがい期においては、都市排水が主体となるため、通常時の流量が少なくが少なく、水質も悪化する傾向となっています。
また、中川には、環境省絶滅危惧Ⅰ類に指定されるヒヌマイトトンボをはじめコムラサキなどのチョウやガの仲間、カブトムシなどの甲虫類も見られます。 |
| 4.中川・綾瀬川の主な災害 |
| "中川・綾瀬川流域一帯は、昔から網の目のように多くの川が乱流していた氾濫原で浸水被害が繰り返されてきました。さらに、昭和40年代から始まる急激な流域の都市化は遊水・保水機能をなくし、相対的に治水安全度が低下したことなどが相まって、浸水被害がより大きなものになってきています。近年では、相次ぐ治水施設の整備効果と大きな洪水が発生していないことなどから、大きな浸水被害は発生していません。" |
|
中川・綾瀬川の災害の歴史 中川・綾瀬川流域一帯は、昔から網の目のように多くの川が乱流していた氾濫原で、そのために、低地に降った雨が小水路を通って幹線水路に到達する前に各所で湛水が生じたり、河道に入ってからも流下能力を超えるとすぐ氾濫し、浸水被害が繰り返されてきました。さらに、昭和40年代から始まる急激な流域の都市化は遊水・保水機能をなくし、流出量の増大と氾濫区域のダメージポテンシャルの増大を招き、相対的に治水安全度が低下したことなどが相まって、浸水被害がより大きなものになってきています。近年では、相次ぐ治水施設の整備効果と大きな洪水が発生していないことなどから、大きな浸水被害は発生していません。
|
(注:この情報は2008年2月現在のものです)
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
中川
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/12 09:50 UTC 版)
| 中川 | |
|---|---|

吉川市と越谷市の境
|
|
| 水系 | 一級水系 利根川 |
| 種別 | 一級河川 |
| 延長 | 83.7 km |
| 平均流量 | -- m3/s |
| 流域面積 | 286.2 km2 |
| 水源 | 埼玉県羽生市 |
| 水源の標高 | -- m |
| 河口・合流先 | 東京湾[1](江戸川区) |
| 流域 | 埼玉県、茨城県、東京都 |
|
|
|




中川(なかがわ)は、埼玉県・茨城県および東京都を流れ東京湾に注ぐ一級河川。利根川水系の支流である。上流を天神堀や島川、中流を庄内古川と呼称する場合もある[2][3]。
地理
埼玉県羽生市街地の住宅地の中に、水源を発する。宮田落(農業排水路)が葛西用水を伏せ越しで潜った吐口(羽生市東七丁目7-6地先)に起点を示す石標がある[3]。
源流付近では、その排水路から繋がる河川そのままの細い流れだが、羽生市街地を抜けて周囲は田園地帯が続くようになり、小さな農業用排水路や小川を集めて徐々に幅を広げ、元は渡良瀬川(権現堂川)の流路であった幸手市付近では川幅約70 mにもなるが、幸手市上宇和田で幸手放水路の分岐により一度川幅が3分の1以下になる。
江戸川の西側を平行して南へ流れ、春日部市の国道16号地下を流れる首都圏外郭放水路に接続(この放水路へは増水時に通水する)する。北葛飾郡松伏町大川戸から同町下赤岩まで開削された河道を通り古利根川に合流し、越谷市付近で新方川と元荒川を合わせると再度川幅が広くなり幅約100 m程度になる。このあたりから流域は、農地から次第に住宅地や商業地が目立つようになる。

東京都葛飾区内で新中川を分ける。東京湾から約8 kmのところで綾瀬川を合わせ、以後は荒川と接しながら並流。河口付近の荒川0キロ標の直ぐ川下側で荒川と合流するが[1]、法令上としての中川の河川区域はその先も続き、葛西臨海公園の西なぎさの突端で、東京湾に達している[1]。綾瀬川が合流する地点には水門が設けられている。最下流部の江戸川区東小松川には、全国唯一の河川水面の競艇場である江戸川競艇場がある。
水元公園の小合溜[4]は、中川の水を導水したものが用いられている。
中川は、利根川には合流せず荒川と並走する形で東京湾へと注ぐ[1]。このことから荒川水系と誤解され易いが、1964年の河川法改訂時における建設省河川審議会管理部会の見解によれば、中川は利根川の分流である江戸川の分流・旧江戸川に合流する新中川放水路が分流しているため、水系の定義である「本流より分流し直接海に流入する派川と、その派川に流入する支流の全ては、同一水系に所属する」という建前から、河川法改訂後利根川水系が一級河川に指定される際に、利根川水系に属する決定が下された[5]。このことから、中川とその支流は『利根川水系の河川』であり、荒川水系ではない。そもそも荒川は、人工河川である荒川放水路であり、元々の荒川の自然流路は隅田川である。
歴史
中川の流路は、その上流部は明治時代以前の庄内古川(幸手市高須賀より上流は島川)と、下流部は古利根川(利根川東遷事業以前の利根川本流で東京湾へ注ぐ河口部は旧中川)とを、北葛飾郡松伏町大川戸から松伏町下赤岩まで大正・昭和に開削された河道で接続して造られた。それ以前は古利根川が亀有付近で分流した河道のうち、江戸川区西葛西付近の河口へ向かう河道を中川と呼んだ(西へ向かうもうひとつの河道は古隅田川)。
この水系整備により、島川・庄内古川より東京湾河口までが中川として扱われ、合わせて古利根川、元荒川、綾瀬川なども中川水系とされた。
なお庄内古川は、江戸時代以前の渡良瀬川の権現堂川より下流の流路を流れた。渡良瀬川の下流は古くは太日川と呼ばれた。太日川は江戸時代に整備され野田市関宿・幸手市西関宿から南流する江戸川となり、庄内古川とは吉川市付近で合流した。松伏町金杉と吉川市上内川の境界周辺に庄内古川の流路跡となる旧堤防が残されている[6]。
中川の河口部は旧中川を流れて東京湾へ注いでいたが、荒川放水路の開削に伴い河道は分断され、旧中川が切り離された。
主な出来事
- 1896年(明治29年)9月 - 台風接近に伴う集中豪雨により中川の堤防が決壊。本所区、南葛飾郡、南足立郡で多くの浸水被害者を出した[7]。
- 1936年(昭和11年)5月19日 - 渡船が転覆して乗客ら10人が死亡[8]。
- 1958年(昭和33年)7月23日、昭和33年台風第11号豪雨により江東区で堤防が決壊。多数の人家が浸水した[9]。
環境
人口急増による生活排水の増加、下水道整備の遅れなどの影響により、20世紀後半に水質がきわめて悪化したが、流域の下水道の普及により、1990年代から次第に改善した。もっとも、日本国内の他の河川と比べると未だ悪い方に入る。2004年にBOD値平均の全国比較で、ワースト2位になった(1位は支流の綾瀬川)。2011年の全国比較では、ワースト1位(2位は同じ支流の綾瀬川)になった[10]。
水質が改善されてきたため、中川では23種の魚類と、4種のエビ・カニ・貝類が確認されている[11]。
流域の自治体
支流
|
|
橋梁
上流から
- 261号橋
- 向谷橋
- 名称不明
- 藤北橋
- 北谷橋
- 中谷橋(埼玉県道84号羽生栗橋線)
- 弁天橋
- 天神橋
- 名称不明
- 中荻大橋
- 天神堀川橋(東北自動車道)
- 日本橋(埼玉県道366号三田ヶ谷礼羽線)
- 西道橋
- 十軒橋
- 天神橋(埼玉県道46号加須北川辺線)
- 鷹野橋
- 内野橋
- 板橋
- 鹿沼橋
- 道橋
- 八ツ島橋
- 水門橋(埼玉県道346号砂原北大桑線)
- 令和橋(栗橋大利根バイパス)
- 豊野橋
- 荒井大橋
- 古門樋橋(国道125号)(加須市・久喜市)
- 門樋橋(埼玉県道3号さいたま栗橋線)(久喜市)
- 古利根川橋梁(東北本線)(久喜市)

- 島川橋(久喜市)
- 中川橋(久喜市)
- 東北新幹線(久喜市)
- 昭和橋(埼玉県道316号阿佐間幸手線)(久喜市・幸手市)
- 島川橋梁(東武日光線)(幸手市)
- 行幸橋(国道4号)(幸手市)
- 上船渡橋(埼玉県道・茨城県道267号幸手境線)(幸手市・猿島郡五霞町)
- 令和橋(埼玉県道・茨城県道267号幸手境線バイパス)(幸手市・猿島郡五霞町)
- 首都圏中央連絡自動車道(幸手市・猿島郡五霞町)
- 宇和田公園橋(幸手市)
- 権現堂橋(幸手市)
- 新船渡橋(茨城県道・千葉県道・埼玉県道26号境杉戸線)(幸手市)
- 古川橋(幸手市)
- 吉田橋(幸手市)
- 高平橋(幸手市)
- 天神橋(埼玉県道383号惣新田幸手線)(幸手市)
- 玉子橋(幸手市)
- 船渡橋(千葉県道・埼玉県道183号次木杉戸線)(杉戸町)
- 万年橋(春日部市・杉戸町)
- 大榎橋(春日部市・杉戸町)
- 松富橋(埼玉県道320号西宝珠花春日部線)(春日部市)
- 庄内橋(埼葛広域農道)(春日部市)
- 中川橋(国道16号春日部野田バイパス)(春日部市)
- 新川橋(埼玉県道321号西金野井春日部線)(春日部市)
- 中川人道橋(春日部市)
- 庄内古川橋梁(東武野田線)(春日部市)
- はなみずき橋(都市計画道路藤塚米島線[12])(春日部市)
- 永沼橋(春日部市)
- 庄内古川橋(新4号国道越谷春日部バイパス)(春日部市)
- 倉田橋(春日部市)
- 新開橋(埼玉県道80号野田岩槻線)(北葛飾郡松伏町)
- 松乃木橋(北葛飾郡松伏町)

- 豊橋(埼玉県道19号越谷野田線)(北葛飾郡松伏町・吉川市)
- 田島橋(北葛飾郡松伏町)
- 旭橋(埼玉県道378号中井松伏線)(北葛飾郡松伏町・吉川市)
- 赤岩橋(北葛飾郡松伏町)
- 弥生橋(埼玉県道67号葛飾吉川松伏線)(北葛飾郡松伏町)
- 新川橋(吉川市道1-979号線)(吉川市)
- 吉川橋(埼玉県道52号越谷流山線)(越谷市・吉川市)
- 吉越橋(埼玉県道52号越谷流山線)(越谷市・吉川市)
- 中川橋梁(武蔵野線)(越谷市・吉川市)
- 新中川水管橋(※水道・人道橋)(越谷市・吉川市)
- 八条橋(埼玉県道29号草加流山線)(八潮市・三郷市)
- 潮郷橋(国道298号、東京外環自動車道)(八潮市・三郷市)
- 共和橋(埼玉県道116号八潮三郷線、首都高速6号三郷線)(八潮市・三郷市)
- 中川橋梁(つくばエクスプレス)(八潮市・三郷市)
- 新中川橋(埼玉県道54号松戸草加線)(八潮市・三郷市)
- 潮止橋(埼玉県道54号松戸草加線)(八潮市)
- 飯塚橋(東京都道501号王子金町市川線)(東京都足立区、葛飾区)
- 中川橋梁(常磐線)(東京都足立区、葛飾区)
- 中川橋(東京都道467号千住新宿町線)(旧水戸街道)
- 中川大橋(国道6号)(東京都葛飾区)
- 中川橋梁(京成本線)(東京都葛飾区)
- 高砂橋(旧東京都道468号堀切橋金町浄水場線)
- 青砥橋(東京都道318号環状七号線)



- 奥戸橋
- 本奥戸橋(東京都道60号市川四ツ木線)
- 平和橋(東京都道308号千住小松川葛西沖線)
- 上平井橋
- 平井大橋(東京都道315号御徒町小岩線)(東京都葛飾区、江戸川区)
- 荒川・中川橋梁(総武本線)(東京都葛飾区、江戸川区)
- 小松川大橋、新小松川大橋(国道14号)(東京都江戸川区)
- 荒川大橋(首都高速7号小松川線)(東京都江戸川区)
- 船堀橋(東京都道50号東京市川線)(東京都江戸川区)
- 荒川・中川橋梁(都営新宿線)(東京都江戸川区)
- 葛西橋(東京都道10号東京浦安線、東京都道475号永代葛西橋線)(東京都江東区、江戸川区)
- 荒川中川橋梁(東京メトロ東西線)(東京都江東区、江戸川区)
- 清砂大橋(東京都道10号東京浦安線)(東京都江東区、江戸川区)
- 荒川河口橋(国道357号 東京湾岸道路)、荒川湾岸橋(首都高速湾岸線)(東京都江東区、江戸川区)
- 荒川橋梁(JR東日本京葉線)(東京都江東区、江戸川区)
脚注
- ^ a b c d “荒川の終点、海との合流点”. 国土交通省関東地方整備局 荒川上流河川事務所. 2018年6月24日閲覧。
- ^ 災害教訓の継承に関する専門調査会報告書 1947 カスリーン台風 第5章 利根川氾濫流の流下と中川流域 (PDF) - 内閣府防災部門HP
- ^ a b 中川の起点 - 有限会社フカダソフト、2018年6月27日閲覧。
- ^ 正式名称は「小合溜井」(こあいためい)。かつての古利根川(中川)の一部で1729年に井沢弥惣兵衛が水害防止、及び灌漑用水を調整する遊水池として設けられた。
- ^ 『利根川百年史』p.1601
- ^ 庄内古川の旧堤防 - 有限会社フカダソフト(きまぐれ旅写真館)、2018年6月24日閲覧。
- ^ 北原糸子 編、松浦律子 編、木村玲欧 編『日本歴史災害事典』吉川弘文社、2012年6月11日、387.388頁。ISBN 9784642014687。
- ^ 日外アソシエーツ編集部編 編『日本災害史事典 1868-2009』日外アソシエーツ、2010年、46頁。 ISBN 9784816922749。
- ^ 日外アソシエーツ編集部 編『日本災害史事典 1868-2009』p.129
- ^ 河川水質の現況 - 国土交通省
- ^ 中川 Archived 2012年1月18日, at the Wayback Machine. - 東京都建設局
- ^ “春日部市が藤塚米島線の開通式典を開催”. 日本工業経済新聞社(埼玉建設新聞) (2013年5月14日). 2018年4月24日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 中川・綾瀬川 - 国土交通省 水管理・国土保全局
- 中川 - ウェイバックマシン(2019年3月31日アーカイブ分) - 有限会社フカダソフト(きまぐれ旅写真館)
- 「東鷲宮駅コース」 久喜市観光ウォーキングマップ (PDF) - 久喜市ホームページ
中川(なかがわ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/10 23:33 UTC 版)
※この「中川(なかがわ)」の解説は、「香水心中」の解説の一部です。
「中川(なかがわ)」を含む「香水心中」の記事については、「香水心中」の概要を参照ください。
「中川」の例文・使い方・用例・文例
- 私が不在の際には中川が代理でご用件を伺います。
- 中川君を訪問したとき彼は出かけようとしていた。
- もしそれが本当なら、中川は有罪であるということになる。
- 「中川さんをお願いします」「私ですが」
- 紅組の初出場者には,リア・ディゾンさん,中川翔(しょう)子(こ)さん,人気アイドルグループAKB48などがいる。
- この鐘は日本国際連合協会の幹部であった中川千(ち)代(よ)治(じ)さんの発案によるものだ。
- 5月6日,鐘が戻ったことを記念する式典が行われ,千代治さんの長男である中川鹿(しか)太(た)郎(ろう)さんと,藩(パン)基(ギ)文(ムン)国連事務総長が鐘を鳴らした。
中川と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
「中川」に関係したコラム
-
個人投資家が株式投資を行う場合、証券会社を通じて株式売買を行うのが一般的です。証券会社は、株式などの有価証券の売買をはじめ、店頭デリバティブ取引や有価証券の管理を主な業務としています。日本国内の証券会...
- >> 「中川」を含む用語の索引
- 中川のページへのリンク
![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif)
![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)