わたらせ‐がわ〔‐がは〕【渡良瀬川】
渡良瀬川
| 渡良瀬川は、栃木県足尾町と群馬県利根村の境にある皇海山にその源を発し、幾つもの渓流を合わせながら、大間々町で山峡の地を離れ、以後桐生市、足利市の中心を南東に流下し、藤岡町で渡良瀬遊水地に注いでいます。途中の支川を合流させると流域面積2,621km2、幹川流路延長107kmの利根川水系最大の支川です。 |
 |
| 足利市岩井町地先を流れる渡良瀬川 |
| 河川概要 |
|
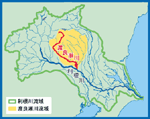 ○拡大図 |
| 1.渡良瀬川の歴史 |
| "1.江戸時代から陸上交通網が整備されるまで物資輸送の動脈として栄えた渡良瀬川。 2.織物の町(桐生・足利)を支える渡良瀬川の水。 3.麺の町(佐野・館林・太田・桐生・足利)を支える渡良瀬川の水。" |
|
特有の歴史、先人の知恵の活用 |
|
1.渡良瀬川における舟運 近代になって陸上交通網が整備されるまで、渡良瀬川は、大切な物資の輸送手段でした。 江戸時代においては、年貢米の輸送などを目的として河川改修工事と合わせて舟運網の整備が進められ、江戸時代中期には、整備された河岸は、16箇所にのぼり流域各地から、米や薪炭・木材、葛生方面から石炭、桐生・足利の織物などを江戸方面へ運搬していました。 明治に入ると、佐野越名河岸と両国との間に蒸気船「通運丸」(全長約63m、幅約12.6m、約65人収容)が就航し、旅客輸送が本格化し、鉄道が整備されるまでの間、両毛地区(桐生・足利・佐野・栃木)から東京へ向かう客の足となり活躍しました。 また、足尾鉱毒の被害を訴えた田中正造も東京に向かうのに利用したという話も残っています。 2.織物の町 桐生・足利 を支えた渡良瀬川の水 桐生は、江戸時代「西の西陣」・「東の桐生」と並び称される織物の町として有名なところです。また、足利の織物は、鎌倉時代にかかれた随筆「徒然草」にも出てくるほどの古くからある地場産業となっています。 織物は、渡良瀬川の豊富な水を用い染めた糸や布を洗い、織物を仕上げるというのが大きな特徴であり、渡良瀬川は、近年まで地域の基幹産業を支えてきました。 なお、近年では、化学染料の発達及び機械化により、観光用としての『友禅流し』を残すのみとなりました。 3.麺の町と共に歩む渡良瀬川 渡良瀬川の流域には、佐野ラーメンをはじめとして、館林・桐生のうどんなど麺づくりがさかんなところです。湿度の低い冬と内陸型の蒸し暑い夏が、良質な原材料である小麦の生産に適すると共に、日本名水百選にも数えられる「出流原弁天池」のわき水始め、渡良瀬川流域の良好な水環境によることが考えられます。 |
| 2.地域の中の渡良瀬川 |
| "足尾鉱毒公害で荒廃した山の緑を取り戻すために渡良瀬川は、河川事業・砂防事業を一つの事務所で行っているため、源流部~下流部まで総合的な学習が比較的容易に可能となっています。また、足利花火大会(北関東最大)のメイン会場でもある渡良瀬川は、貴重なオープンスペースとなっています。" |
|
地域社会とのつながり 1.足尾鉱毒事件と煙害との関わり
こうした中、これまで多く人々が知恵と時間をかけ、下流沿川への被害解消に向けた、砂防えん堤等の砂防事業及び下流域の堤防整備等の河川事業を実施してきています。また、山々への緑の回復に向けて、植樹等の対策を展開し、徐々に緑を取り戻してきています。 2.渡良瀬川周辺の学習施設
上流部には、治水・利水等の多目的に作られた草木ダム(水資源開発機構 管理)の見学も可能となります(事前申込要)。 中流~下流部には、渡良瀬川の歴史や自然をわかりやすく紹介している「わたらせ川のふれあい館せせら」があり、自由に見学できる施設となっています。 3.貴重なオープンスペースの渡良瀬川 足利市街地を2分して流れる渡良瀬川は、貴重なオープンスペースを地域に提供し、公園等に有効利用されていると共に、北関東最大級の「足利花火大会」のメイン会場になり、地域の憩いの場となっております。 |
| 3.渡良瀬川の自然環境 |
| "渡良瀬川の水質は、「水生生物による水質判定」によると、きれいな水~少しきたない水に分類され、上流の渓流域は、ニホンカモシカ等の大型のほ乳類が生息する等の良好な自然環境を形成しています。中~下流域も多種多様な生物環境を形成しています。また、放流したサケも帰ってきています。" |
渡良瀬川は、その昔、鉱毒事件により川は汚れ、一時は生物がすめない川となってしまいましたが、現在では、水質も改善されてきており、たくさんの生物が住める川となってきています。その水質は、「水生生物による水質判定結果」の指標で、上流域では、きれいな水、中~下流域では少し汚れた水に大まかに分類されます。 1.上流域(渓流)にくらす生きものたち
このように上流域(渓流)では、良好な渓流を形成し、多種多様な生物が生息しています。 2.中~下流域にくらす生きものたち
植物は、中流域には、ハリエンジュやハンノキといった高木が群落を形成し、鳥類が休息する環境を提供し、下流域にはヨシやガマ等の草丈の低い、植物が大きな群落を形成しています。 3.サケの帰ってくる川へ 渡良瀬川では、地域の方々や漁協とが協力し、毎年のようにサケを放流しています。平成15年度には、群馬県桐生市にある太田頭首工の魚道を遡上するサケも確認されました。 |
| 4.渡良瀬川の主な災害 |
| "1.昭和22年9月カスリーン台風による被害 2.昭和24年8月キティー台風による被害" |
|
(注:この情報は2008年2月現在のものです)
渡良瀬川
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/15 08:16 UTC 版)
| 渡良瀬川 | |
|---|---|

錦桜橋付近(桐生市)
|
|
| 水系 | 一級水系 利根川 |
| 種別 | 一級河川 |
| 延長 | 107.6[1] km |
| 平均流量 | -- m3/s |
| 流域面積 | 2,621 km2 |
| 水源 | 皇海山(日光市) |
| 水源の標高 | 2,144 m |
| 河口・合流先 | 利根川(古河市/加須市) |
| 流域 | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県 |
渡良瀬川(わたらせがわ)は、北関東を流れる利根川水系利根川支流の一級河川である。流路延長107.6kmは利根川の支流中で、鬼怒川、小貝川に次いで第3位の長さを持つ。流域面積2,621km2は利根川の支流中では最大である。
地理
栃木県日光市と群馬県沼田市との境にある皇海山(すかいさん)に源を発し、足尾山塊の水を集め草木ダムを経て南西に流れる。群馬県みどり市(大間々町)で平野に出て、南東へ急に向きを変え、桐生市から足利市・太田市・佐野市・館林市など、おおむね群馬・栃木の県境付近(両毛地域)を東南東へ流れる。
栃木県栃木市藤岡地域で明治・大正期に開削された洪積台地(藤岡台地)を東へ抜けた後、南に向きを変え、渡良瀬遊水地に入り巴波川(うずまがわ)、思川を併せる。茨城県と埼玉県の県境を南へ流れ、茨城県古河市と埼玉県加須市の境界で利根川に合流する。
一般的に日光市足尾地区渡良瀬にある神子内川との合流部から下流が渡良瀬川であり、これより上流は松木川(まつきがわ)と呼び分けられている。なお国土交通省では、足尾ダムから神子内川までの合流部分も含めて渡良瀬川と定めている。また、足尾ダムよりも上流部の松木川も渡良瀬川と呼ぶことがある。
-
源流の碑
(足尾ダム湖畔) -
河口
(利根川合流点)
名称の由来
上流にある足尾町の渡良瀬という地名に由来する[2]。伝承によれば、この地名は日光を開山した勝道上人による命名である。勝道上人が川を渡ろうとしたところ、渡るのにちょうど良い浅瀬があったのでその場所を渡良瀬と名づけたという。
歴史
およそ5万年前までの流路は、関東平野へ出た大間々町(2006年からみどり市)付近から南向きに深谷市方向へ流れ、利根川へ合流した[3]。大間々町を扇頂とする大間々扇状地を形成した。
その後、渡良瀬川は東向きへ流路を変え、東京湾へ南流する思川の河道へ向かった。すなわち現在の桐生市・足利市・太田市・館林市を通り板倉町へ至り[4]。そこから南下し加須市の旧大利根町域付近で思川と合流した [5][6]。およそ5000年前の縄文海進時はこの渡良瀬川河道には板倉町付近まで東京湾が湾入した。
古代には、渡良瀬川の本流は桐生川との合流点(足利市小俣)より下流は太田市との境を蛇行しながら東流し(現在の矢場川)、上野国・下野国の国境となっていた[7][8]。板倉町の大曲・細谷付近では館林市との境界を東流し、藤岡台地(洪積台地)の縁に当たって向きを変え南下していた。
ただしその後、本流は、只上・市場町付近(上野国太田)で、より北へ流路を変え(桐生川・松田川の河道へ近づき)、次第に下野国内を東流するようになり、現在の矢場川を流れなくなっていった。
板倉町の海老瀬(本郷)地区では藤岡台地の縁に沿った南下から再び東へ向きを変え、洪積台地の幅が狭くなった地点を掘り割る形で旧谷中村方向へ向けて流れていた[9][10]。ここを抜けた後は、海老瀬地区(上野国)と旧谷中村(下野国)の境界を屈曲を繰り返しながら南流し、七曲がりと呼ばれた。加須市小野袋で旧合の川(利根川の支流)と合流し[11]、そこからは下野国・武蔵国の国境を流れ(長さ約1km)、古河市のすぐ西で思川と合流した。
思川との合流以降南流し、武蔵国・下総国の国境を4km流れた後[12]、当時の利根川本流への合流へ向かう分流と別れ、下総国葛飾郡を50km貫流し東京湾へ注いだ。下流部は現在の江戸川の流路に近く[13]、「太日川」(ふといがわ)と呼ばれた。当時の利根川本流とはほぼ平行して南流し、東京湾への河口も異なっていた。
戦国時代後期に、現在の足利市では渡良瀬川の河道を本格的に矢場川から分離させ移す工事が行われ[14][15]、現在の渡良瀬川本流となった。
元和7年(1621年)に新たな利根川本流河道として新川通を開削して、加須市旗井(久喜市栗橋の北1km)で利根川を渡良瀬川へ接続し、以降は、渡良瀬川は利根川の支流となった。
寛文4年(1664年)に、矢場川を館林市木戸から下早川田まで開削し渡良瀬川本流に合流させた。この新たな矢場川河道(および合流点より下流の渡瀬川)に合わせて上野国・下野国の国境も移動された[16]。
大正7年(1918年)に藤岡台地を開削・通水し、藤岡町赤麻[17]・渡良瀬遊水地を経由する河道となった。
支流
河川施設

- 足尾砂防ダム
- 草木ダム
- 高津戸ダム
- 渡良瀬遊水地
- 庚申ダム(庚申川)
- 黒坂石ダム(黒坂石川)
- 桐生川ダム(桐生川)
- 松田川ダム(松田川)
- 南摩ダム(思川左支川南摩川)
- 大間々頭首工
- 太田頭首工
- 邑楽頭首工
橋梁
上流


- 銅橋(あかがねはし)
- 古河橋
- 新古河橋
- 南橋橋
- 名称不明(旧足尾町立足尾本山小学校前)
- 間藤橋
- 第二松木川橋梁(足尾線(貨物線))- 廃橋
- 下間藤橋
- 第一松木川橋梁(わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線)
- 田元橋
- 大黒橋(栃木県道250号中宮祠足尾線)
- 新渡良瀬橋
- 渡良瀬橋(人道橋)
- 足尾橋
- 七滝橋
- 通洞大橋(栃木県道142号通洞停車場線)
- 砂畑橋
- 遠下橋(国道122号足尾バイパス)
- 第二渡良瀬川橋梁(わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線)
- 原橋(栃木県道139号原向停車場線)
- 沢入橋(群馬県道343号沢入桐生線)
- 第一渡良瀬川橋梁(わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線)
- 東宮橋
- 草木橋
- わらべ橋(人道橋)
- 萬年橋(群馬県道343号沢入桐生線)
- 松島橋
- 下松島橋
- 東橋
- 東瀬橋
- 五月橋(群馬県道257号根利八木原大間々線)
- くろほね大橋
- 貴船橋
中流


- 福岡大橋(群馬県道257号根利八木原大間々線)
- 新栄橋
- はねたき橋(人道橋)
- 高津戸橋(群馬県道338号駒形大間々線)
- 相川橋
- 赤岩橋(群馬県道3号前橋大間々桐生線)
- 渡良瀬川橋梁(上毛電気鉄道上毛線)
- 渡良瀬川橋梁(両毛線)
- 桐生大橋(清瀬橋)
- 錦桜橋(群馬県道68号桐生伊勢崎線)
- 中通り大橋
- 昭和橋(群馬県道332号桐生新田木崎線)
- 松原橋(群馬県道316号桐生太田線)
- 葉鹿橋(群馬県道・栃木県道254号毛里田坂西線)
- 鹿島橋(群馬県道・栃木県道256号竜舞足利線)
- 渡良瀬川橋(北関東自動車道)
- 緑橋(栃木県道40号足利環状線)
- 渡良瀬橋(栃木県道・群馬県道5号足利太田線)
- 中橋(栃木県道116号足利市停車場線)
- 田中橋(国道293号)
- 岩井橋
- 福寿大橋
- 福猿橋(栃木県道・群馬県道8号足利館林線)
- 川崎橋(栃木県道・群馬県道128号佐野太田線)
下流

- 渡良瀬川大橋(国道50号)
- 高橋大橋(栃木県道・群馬県道223号寺岡館林線)
- 渡良瀬大橋(栃木県道・群馬県道・埼玉県道7号佐野行田線)
- 渡良瀬川橋梁(東武佐野線)
- 渡良瀬川橋(東北自動車道)
- 渡良瀬川橋梁(東武日光線)
- 新開橋(栃木県道・群馬県道・埼玉県道・茨城県道9号佐野古河線)
- 藤岡大橋(栃木県道11号栃木藤岡線)
- 西赤麻橋(沈下橋)
- 新赤麻橋
赤麻橋(沈下橋)- 廃橋- 野渡橋(沈下橋)- 人道橋
- 三国橋(国道354号・栃木県道・群馬県道・埼玉県道・茨城県道9号佐野古河線)
- 新三国橋(国道354号古河バイパス)
脚注
- ^ 国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所『渡良瀬川を知ろう』 2016年3月3日閲覧
- ^ 渡良瀬川 - こがナビ(古河市観光協会)
- ^ 当時の利根川はその付近から南向きの流れとなり、荒川の流路を通り東京湾へ注いだ。
- ^ その間、桐生川・松田川などが合流、また分流の変遷があった。
- ^ 「先史時代の利根川水系とその変遷」菊地隆男、アーバンクボタ、1981年。
- ^ 利根川もおよそ3000年前に東向きへ河道を変え、分流しながら渡良瀬川の流路地帯(加須から越谷)へ向かって流れるようになり(大落古利根川など)、分流の一部は渡良瀬川に合流した。
- ^ 歴史的農業環境閲覧システム - 農業環境技術研究所、2016年3月23日閲覧。
- ^ この国境はほぼ栃木県足利市、佐野市、栃木市(藤岡町)と群馬県太田市、館林市、板倉町との境に当たる。
- ^ 板倉川の約400m北の地点にあたる。これが自然の開削なのか人工なのかは異論がある。
- ^ この地点の川の断面積は小さく水位が上昇して板倉町側に波及し堤防決壊が起きやすかった。棒出しなどによる下流の水位にも影響を受けた。
- ^ 合流点には谷田川が流れ込んでいる。
- ^ 渡良瀬川は思川との合流以降、加須市旗井を通り加須市琴寄で利根川(浅間川)と合流するまで、武蔵国・下総国の国境の河道(約8km)を西向きに流れていたという考えもある(「越谷市内とその周辺の河川の歴史」2016年9月24日閲覧)。
- ^ 国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所『渡良瀬川のうつりかわり』 2016年3月3日閲覧
- ^ 足利市借宿の北を通る河道や、板倉町除川・西岡の北を通る河道などの開削工事が行われた。
- ^ 「板倉町と水辺」松浦茂樹、国際地域学研究2009年3月
- ^ 群馬県館林市・板倉町と栃木県足利市・佐野市・藤岡町との境界にあたる。
- ^ 旧谷中村の北にあたり、赤麻沼があった。開削された河道は藤岡新川と呼ばれた。
関連項目
- 足尾鉱毒事件 - 上流にあった足尾銅山によって発生した公害問題。下流域の農業被害や堆積による天井川で洪水が発生した。
- 足利事件 - 1990年5月、河川敷で行方不明になっていた女児の遺体が見つかった。
- 古河城 - 渡良瀬川の改修に伴い、城跡が河川敷となった。
- 勧農城(岩井山城) - 河川敷に城跡がある。
- わたらせ渓谷鐵道わたらせ渓谷線 - わたらせ渓谷鐵道が運営する流域の鉄道路線。
- 渡良瀬橋 - 森高千里が発表した楽曲。足利市にかかる渡良瀬橋とそれに隣接する歩道橋をモデルにしている。
- 大間々扇状地 -渡良瀬川が作り上げた扇状地である。
- 栃木県道402号桐生足利藤岡自転車道線 - 渡良瀬川沿いのサイクリングロード(桐生市錦町から栃木県栃木市藤岡町藤岡までの38.3km)。
外部リンク
- 国土交通省 関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所
- 迅速測図(歴史的農業環境閲覧システム)(農業環境技術研究所)
- 渡良瀬川(国立公文書館 デジタルアーカイブ)
渡良瀬川と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 渡良瀬川のページへのリンク







