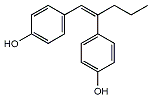PHS
「PHS」とは、personal handy-phone systemの略で日本初の無線通信による移動体通信サービスのひとつを意味する表現。
「PHS」とは・「PHS」の意味
「PHS」とは、「personal handy-phone system(パーソナルハンディフォンシステム)」の略称で、1995年に無線通信を利用した移動体通信サービスのひとつとして登場した。屋内用コードレスホンの技術をもとに開発され、デジタルデータの高速通信に優れるという特徴がある。日本発の通信規格であり、パケット通信やカメラ付端末、スライド式キーボードなどの装備は、携帯電話に先行してPHSの端末で実用化されたものである。読み方は「ピーエイチエス」「ピーエッチエス」、簡略化したものは「ピッチ」。当初は「personal handy phone」を略した「PHP」と呼ばれたが、同じ表記の企業と紛らわしいことから1994年4月22日に呼称を「PHS」に変更し「ピーエイチエス」、簡略化して「フォス」と呼ぶと発表された。しかし「フォス」は定着せず、若者の間で「ピッチ」の呼び方が広がり、1999年以降は、通信事業者のCMやパンフレットなどでも「ピッチ」が用いられるようになった。
「PHS」が誕生する前は、電話などの通信事業は国有事業であったが1985年4月に自由化された。それによって通信事業へ民間事業者が参入を開始したことが「PHS」が登場した背景にある。
日本では、1995年7月1日に東京・北海道地区でサービスが開始され、優れた通話品質と安価なコストで若い世代を中心に普及し、1997年には700万件の契約を獲得するまでに至った。しかし、その後はガラケーと呼ばれる携帯電話の通話品質が向上したことや料金が引き下げられたこと、高機能化などによって競争力を失い契約件数が減少した。
「PHS」は、半径500m程度の距離をカバーするアンテナを設置して有線の電話回線に接続して通話を実現するものである。PHS本体からアンテナまでは無線で、それ以降は有線で通信を行うため、システム登録を行えばコードレス電話を親機、PHSを子機として利用する使い方も可能である。ひとつのアンテナがカバーできる範囲が狭いため、アンテナを多数設置しなければならなかったが、小規模なものでよいため、設置するコストを比較的安く済ませることが可能であった。
携帯電話は、大型の基地局を介し高出力の電波を送受信することで広範囲で無線通信を行うものである。大規模な基地局であれば一つの基地局で数十km程度の広さをカバーすることが可能だ。つまり、「PHS」は狭い地域で通話ができる一般の固定電話の延長で生まれたもの、携帯電話は、広範囲の通話を可能にする自動車電話の延長で生まれたものということができる。通信方式が違うため、携帯電話サービスを提供するためには無線局免許状が必要であるが、PHSは不要であると電気通信事業法では定めている。
当初は、電波のばらつきがある携帯電話よりもPHSの方が安定した通話が可能であり、安価な価格設定だったことや基地局を地下鉄や地下街にも設置することができたため都市部では広範囲で通信できるというメリットもあった。2000年代に入ると、3Gの登場や携帯電話の機能が向上し通信エリアが限られる「PHS」は、徐々にそのシェアを失っていったが、電波が弱く医療機器への影響が少ないという特徴をメリットとして生かすことができる医療施設や介護施設では活用されていた。
2021年には、テレメタリングサービスを除いて「PHS」の個人向けのサービスが終了。PHS回線で自動販売機やコインパーキングなどを遠隔監視するためのテレメタリングサービスは、2019年から新規の契約や変更の受付を停止し、2023年3月末で終了となった。病院などの医療施設や看護や介護の現場で利用されている構内PHSは、当面の間は利用可能であるがスプリアス規格が古いものは利用が規制される。
「PHS」では、「070」から始まる電話番号が割り当てられていた。しかし現在では、PHSのサービスが終了したこともあり、一般の携帯電話の番号にも「070」が割り当てられている。
ピー‐エッチ‐エス【PHS】
PHS(ぴーえっちえす)
簡易型携帯電話といい、携帯電話と同じように使える。サービス料金が安いことや、データ通信が速い、ということがPHSの強みである。かつては移動中には使えないという欠点などのため、加入者数が減ってきていたが、1999年から新技術が相次いで導入され、最近は人気が回復している。2001年4月からの次世代携帯電話開始に伴い、PHS各社も新戦略を始めるところが目立つ。
NTTドコモはPHSの「ドッチーモ」にiモードを導入してPHSの人気挽回を図る。業界最大手のDDIポケットは10月にカラー画面表示の新機種を発売し、デジカメの映像をE-mailで送受信するサービスを始める。TTNetは年末には新機種を発表し、PHS端末だけでインターネット接続ができるようにする。この端末では、ホームページを見たり電子メールを送受信したり、といったことができる見込みである。
全国に15万ヶ所ある基地局を使った、PHSならではの新しい試みもある。たとえばDDIポケットはPHSを自動車に掲載し、盗難にあったときに基地局を通じて車の位置を特定する、というサービスを4月から始める予定である。PHSの位置特定機能を生かし、痴呆性老人にPHSを持たせ、迷子になった時にPHSの基地局を通じて居場所を探す、という試みもある。
(2000.07.11更新)
携帯電話・PHS(けいたいでんわ・ぴーえっちえす)
固定電話に対して、持ち運びができる電話機のことを一般に携帯電話という。
携帯電話サービスは1987年に始まった。ただそのころは加入者が少なく、1989年時点でわずか24万台だった。
これが1994年の規制緩和を受けて、携帯電話が爆発的に広がる。特に、1999年にはNTTドコモ発売のiモードが人気を呼び、普及に拍車がかかった。iモードの契約数は、2001年3月に2000万人を達成した。
2001年5月末には、NTTドコモが世界で初めて、商用の次世代携帯電話サービスを開始した。次世代携帯電話では、動画像の送受信も行うことができる。
一方、携帯電話の普及に反して、一般加入電話の契約数は1996年をピークに減少し続けている。
(2000.01.11更新)
携帯電話、IMT-2000、PHS
携帯電話は、昭和54(1979)年に自動車電話として、800MHz帯でアナログ方式でのサービスが開始されました。平成2(1990)年にはデジタル方式(PDC方式)が決められ、平成3(1991)年には800MHz帯に加え、新たに1.5GHz帯が割当てられました。800MHz帯は平成5(1993)年から、1.5GHz帯は平成6(1994)年4月からこの方式によるサービスが開始されています。既に使用を停止した前述のアナログ方式を第1世代移動通信システムとし、このデジタル方式を第2世代移動通信システムと呼んでいます。また同じくデジタル方式であるCDMA方式は、平成10(1998)年からサービスが開始されています。さらに平成13(2001)年からは、第3世代移動通信システムであるIMT-2000のサービスが開始されています。
IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000)IMT-2000は第3世代のシステムとして、昭和61(1986)年に、国際電気通信連合 (International Telecommunication Union : ITU)で検討が開始され、平成12(2000)年5月に5つの方式が正式勧告されました。
IMT-2000は、動画像伝送や高速インターネットアクセスの実現を目指して開発がなされており、室内等での準静止時には2Mbit/s、自動車等での高速移動時でも毎秒144kbit/sまでの伝送速度を提供可能なシステムです。IMT-2000が目指すサービスの主な特徴は以下のとおりです。
- グローバルサービスの実現(様々な利用形態、地域を超え利用可能)
- マルチメディア通信サービスの提供
- インターネットとの高い親和性
- 固定網と同等な高品質なサービスの提供
- 高い周波数利用効率の実現(既存システムと同等以上の周波数利用効率)
現在我が国で最も普及しているPDCシステムの携帯電話は、日本以外では使用されておらず、端末を海外で使用することはできません。IMT-2000では、世界中に端末を持ちこんで、そのまま利用できるグローバルローミングの実現を目指して開発がなされています。グローバルローミングを可能とするためには、無線周波数と通信方式を世界的に共通化する必要があり、無線周波数については、平成4(1992)年に開催されたITUの無線通信主管庁会議(WRC-92)において、2GHz帯の周波数を2000年から使用することが、世界的に合意されました。その後、平成12(2000)年に開催されたITUの世界無線通信会議(WRC-2000)において、800MHz帯、1.7GHz帯、2.5GHz帯がIMT-2000用の周波数として追加分配されています。また、通信方式については、5つの方式が勧告され、日本ではNTTドコモグループ、ボーダフォングループ(旧J-フォングループ)がW-CDMA方式を、KDDIグループがCDMA-2000方式を採用しています。サービスは平成13(2001)年10月から開始されています。(NTTドコモグループは平成13(2001)年10月サービス開始、ボーダフォングループは平成14(2002)年12月にサービス開始、KDDIグループは平成14(2002)年4月から800MHz帯でのIMT-2000サービスを開始、平成15(2003)年10月より2GHz帯でCDMA2001x EV-DO方式を開始しています。)
携帯電話は、デジタル化によるシステム収容効率の大幅な向上や端末の小型化、パケット方式によるインターネットアクセスなど、サービスの充実により、平成16年4月末で約8200万加入まで普及しており、このうち第3世代携帯電話が約1770万加入(全体の22%)となっています。
今後、IMT-2000のサービスにより、移動体通信はさらに発展すると考えられ、第2世代から第3世代への移行が急速に進むものと考えられます。
携帯電話サービスの地域間格差是正事業等の推進総務省では、携帯電話サービスの地域間格差の是正について、過疎地域等を対象に、平成3(1991)年度から移動通信用鉄塔施設整備事業を実施し、平成11(1999)年度末において全国の市町村役場周辺において通話が可能となっています。平成13(2001)年度からは、一層の地域間格差の是正を図るため、公共事業関係費から支出し、国庫補助率を1/3から1/250音順に引き上げるとともに、鉄塔の基地局から交換局までの回線(無線設備等)を補助対象に追加しています。
また、近年における携帯電話の急速な普及に伴い、高速道路等トンネル及び地下街等において、電波が遮へいされることにより通話が途切れる等の状態を解消することについての要請が高まっていることから、平成5(1993)年度から10(1998)年度まで移動通信用鉄塔施設整備事業により実施していた高速道路等トンネル及び地下街等閉塞地域における整備について、平成11(1999)年度から新たに電波遮へい対策事業として実施するとともに、補助率を従来の1/4から1/250音順に引き上げました。
2.PHS
概要PHS(Personal Handy-phone System)は、平成7年(1995年)のサービス開始以来、音質に優れ、また簡便かつ低廉な移動通信手段として都市部を中心に普及し、携帯電話とともに、国民生活に密着した情報通信手段として定着しています。平成10年(1998年)7月には、電気通信技術審議会答申「PHSの高度利用の促進に資する技術の導入方策」が示され、移動中や屋内における通話品質の改善等、PHSの利便性の向上が図られるとともに、インターネットアクセスを中心としたデータ通信トラヒックが増加している状況にあります。
また、PHSの64kbpsの通信速度を生かしたデータ通信専用のカード型端末の普及も進んでいます。
平成16年4月末現在での加入数は、約511万となっています。
新サービスの導入PHSに導入された新サービスには次のようなものが挙げられます。
・位置情報サービス
PHSの基地局がカバーするエリアが数百メートルと狭い(携帯電話の場合、1.5~数km)ため、端末が存在するエリアを表示するサービスが可能です。GPSと組合せ、複数の基地局からの方向を得ることで端末の位置を確認する方式もあります。
・音楽、映像配信
64kbpsの速度で通信できることを生かしたサービスとして、音楽データのダウンロードサービスが平成12年から実施されています。また、デジタルカメラを接続し、撮影した画像をメールに添付して送信できる端末も登場しています。
・インターネット接続サービス
データ通信に優れ、料金が低廉なPHSならではの特長を活かし、iモードと同様に、PHS端末単独でインターネットのウェブサイトを閲覧可能な端末によるサービスが平成12年より開始されました。また、平成13年6月からは、パケット方式による定額制サービスが導入されるなど、新たなサービスが開始されています。
PHSの高度化に向けてPHSについては、モバイルインターネットアクセスの手段として今後とも利用の拡大が見込まれるほか、データ通信を中心に引き続き通信トラヒックが増加していくものと考えられ、多様化・高度化するユーザニーズに的確に対応していくため、サービスの一層の高度化に向けた新たな技術の導入等についての検討が必要となっています。また、PHSは第3世代移動通信システム(IMT-2000)と周波数が隣接しているため、PHSの高度化に当たっては、干渉軽減方策の検討を行うことも求められています。
このような背景を踏まえ、平成12年7月24日、電気通信技術審議会(現情報通信審議会)に「IMT-2000との共存下におけるPHSの高度化に必要となる無線設備の技術的条件」について諮問し、平成13年6月25日に答申が示され、平成14年に制度化されました。
これにより、高度化方策の組合せによっては、最大1Mbps程度の高速データ伝送速度が可能となり、またIMT-2000との共存については、高度化PHSへの干渉除去フィルタの導入等により可能となります。
PHSの海外展開PHSは、中国で約4500万加入に達するなど、アジアや南米、中近東、アフリカなど、海外においても広く導入されています。PHSには、家庭やオフィスでのコードレス電話としての使い方と、屋外での携帯電話としての使い方の他に、PHSの技術を利用した一般の加入電話網としてのアプリケーションがあります(加入者系無線アクセスシステム)。
加入者系無線アクセスシステムは、各家庭に有線を引き込む場合に比べ低コストで短期間に加入電話網を構築可能であるため、発展途上国等加入電話網の構築が急務となっている国々においては、その有用性が期待されています。
こうしたPHSの海外展開をさらに支援するための機関として、平成8年よりPHS-MoU(MoU:Memorandum of Understanding)が設立され、国内外の電気通信事業者、メーカ、総務省を含め、計35のメンバー(2001年7月現在)から構成されています。
関連リンク先(50音順)PHS
読み方:ピーエイチエス,ピッチ
 PHSとは、移動電話サービスのひとつで、1.9GHz帯の周波数を使用したデジタル方式の移動体通信サービスのことである。高音質と低料金を特徴とする。家庭用コードレス電話機の子機を外に持ち出すという発想で、電波システム開発センター(現、電波産業会)が規格を標準化した。サービス開始は1995年7月。
PHSとは、移動電話サービスのひとつで、1.9GHz帯の周波数を使用したデジタル方式の移動体通信サービスのことである。高音質と低料金を特徴とする。家庭用コードレス電話機の子機を外に持ち出すという発想で、電波システム開発センター(現、電波産業会)が規格を標準化した。サービス開始は1995年7月。
PHSの基地局は、1局あたりのカバー範囲(セル)が半径100~500m程度と小規模なものにとどめられているため、簡易で安価に設置することができる。このため地下街や地下鉄駅などでの基地局設置がいち早く進み、特に都市部では携帯電話よりも接続されやすいという状況にある。また、通信料金や端末価格が廉価であることもPHSの特徴をなしている。
サービス開始当初は、PHSの基地局のカバーするエリアが狭いため、サービスエリアの拡大に時間がかかり、屋内での利用に向かないといった難点があった。さらに基地局間での通話情報の引き渡し(ハンドオーバー)に時間がかかり、最大で2~3秒程度通信が途切れるとされた。しかし1999年頃からは、これらの難点も改善されはじめ、安定した機種が増えている。
PHSはその利用のしやすさから急速に普及し、サービス開始から2年余りで700万人以上の加入者を獲得した。しかし携帯電話の低価格化と普及に伴って、総加入者数は減少の一途を辿っている。NTTドコモなどもPHS事業から撤退してしまった。
1997年4月からはPIAFS方式による32kbpsの高速データ通信サービスを開始、1999年4月に64kbpsのデータ通信サービスが開始された。最近では携帯情報端末(PDA)やノートパソコンに接続して高速データ通信を行う無線モデムのしての機能に特化し、携帯電話との差異化が図られている。現在の主なPHSサービスとしては、ウィルコム(旧DDIポケット)が提供している「AIR-EDGE」(旧AirH")や、ケイ・オプティコムが提供している「eo64エア」などがある。
※画像提供 / 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
参照リンク
WILLCOM
ケイ・オプティコム
α‐プロピル‐4,4′‐スチルベンジオール
PHS
PHS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 03:49 UTC 版)
「64で発見!!たまごっち みんなでたまごっちワールド」の記事における「PHS」の解説
他のプレイヤーを自分と同じマスに呼び寄せられる(そのため、お世話した場合は横取りされる危険もある)。その際、ごきげんが1上がる。
※この「PHS」の解説は、「64で発見!!たまごっち みんなでたまごっちワールド」の解説の一部です。
「PHS」を含む「64で発見!!たまごっち みんなでたまごっちワールド」の記事については、「64で発見!!たまごっち みんなでたまごっちワールド」の概要を参照ください。
PHS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:43 UTC 版)
「携帯電話IP接続サービス」の記事における「PHS」の解説
NTTパーソナルが1998年3月にインターネットメール化したキャリアメール「パルディオEメール」を開始。NTTパーソナルを承継したドコモPHSは2001年2月にドットiと同様のサービスとなる「ブラウザフォン」を開始している。 DDIポケットは独自網内でショートメッセージと文字コンテンツの提供を行っていた「PメールDX」において1998年12月にインターネットメールに対応しキャリアメール化、2000年1月には文字コンテンツにおいても勝手サイトの閲覧が可能となる『オープンコンテンツ化』を実施し、2000年8月に「H"LINK」に改称(現:AIR-EDGE PHONE)。 アステルでは1999年11月にMOZIOeメールサービスでキャリアメールに対応し、2000年12月にCompact HTMLブラウザを搭載し、接続先をISPとする事も可能な「ドットi」を開始した。
※この「PHS」の解説は、「携帯電話IP接続サービス」の解説の一部です。
「PHS」を含む「携帯電話IP接続サービス」の記事については、「携帯電話IP接続サービス」の概要を参照ください。
PHS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 01:03 UTC 版)
ソフトバンクに関しては、一部のメールアドレスのみ携帯電話、およびはメールアドレス持ち運びサービスに移行後も使用できる。 NTTパーソナル (ドコモPHS)キャラめーる(サービス終了)(050ではじまる電話番号)@cmhokkaido.nttpnet.ne.jp(NTT北海道パーソナル通信網), (050ではじまる電話番号)@cmtohoku.nttpnet.ne.jp(NTT東北パーソナル通信網), (050ではじまる電話番号)@cmchuo.nttpnet.ne.jp(NTT中央パーソナル通信網), (050ではじまる電話番号)@cmtokai.nttpnet.ne.jp(NTT東海パーソナル通信網), (050ではじまる電話番号)@cmkansai.nttpnet.ne.jp(NTT関西パーソナル通信網), (050ではじまる電話番号)@cmchugoku.nttpnet.ne.jp(NTT中国パーソナル通信網), (050ではじまる電話番号)@cmshikoku.nttpnet.ne.jp(NTT四国パーソナル通信網), (050ではじまる電話番号)@cmkyusyu.nttpnet.ne.jp(NTT九州パーソナル通信網) パルディオEメール(サービス終了)(070で始まる電話番号)@em.nttpnet.ne.jp, ○○@mb2.em.nttpnet.ne.jp, ○○@△△△.em.nttpnet.ne.jp アステルドットi@phoneメール(サービス終了)○○@phone.ne.jp MOZIOeメール(サービス終了) ○○@mozio.ne.jp, ○○@△△.mozio.ne.jp ソフトバンクY!mobileブランドPHS用Eメール○○@y-mobile.ne.jp(ソフトバンクに移行した継続契約者・メールアドレス持ち運びサービス利用者は引きつづき使用できる) イー・モバイル(廃止)emobileメール ○○@emobile.ne.jp EMモバイルブロードバンド メールサービス ○○@bb.emobile.ne.jp EMnetメール(※EMnet未契約の場合はMMSになる) ○○@emnet.ne.jp EMメール-S ○○@emobile-s.ne.jp ウィルコムEメール(サービス終了)○○@willcom.com(ソフトバンクに移行した継続契約者、およびはメールアドレス持ち運びサービス利用者は引きつづき使用できる) ○○@wcm.ne.jp(PHS向けスマートフォンからの継続契約者) papipo!メール(廃止 キッズケータイpapipo!専用)○○@bandai.jp 旧DDIポケットグループPメールDX(サービス終了 ウィルコムを経てソフトバンクに移行した継続契約者、およびはメールアドレス持ち運びサービス利用者は引きつづき使用できる)○○@pdx.ne.jp H"LINK(廃止)○○@d△.pdx.ne.jp, ○○@wm.pdx.ne.jp
※この「PHS」の解説は、「キャリアメール」の解説の一部です。
「PHS」を含む「キャリアメール」の記事については、「キャリアメール」の概要を参照ください。
「PHS」の例文・使い方・用例・文例
- 携帯電話やPHSからのお問合せは下記番号へおかけ下さい。
- 東京消防庁は,緊急事態の現場へ向かう途中で119番通報者と連絡が取れるように,救急車でのPHSの使用を開始した。
- それと同時に,あなたのPHSに自動的に電話をかける。
- PHSのディスプレイで,あなたは家で何が起こっているか見ることができるのだ。
- 電気通信事業者協会は携帯電話とPHSの契約数が1月末の時点で1億台に達したと発表した。
- 1990年代中頃(ごろ),企業が次々と携帯電話やPHSの事業に参入し,携帯電話とPHSの売り上げが急増した。
- 1999年には,携帯電話向けインターネット接続サービスが始まり,携帯電話とPHSの契約数が5000万台を超えた。
PHSと同じ種類の言葉
- PHSのページへのリンク