mass
「mass」の意味
「mass」は、主に3つの意味を持つ英単語である。1つ目は「大量」や「集まり」を意味し、物体や人々が集まっている様子を表す。例えば、大量の荷物や人々が集まった場所などが該当する。2つ目は「質量」を意味し、物体の重さや大きさを示す物理学用語である。3つ目は宗教的な意味で、「ミサ」と訳されることが多く、キリスト教の礼拝の一種を指す。「mass」の発音・読み方
「mass」の発音は、IPA表記では/mæs/であり、カタカナ表記では「マス」となる。日本人が発音する際のカタカナ英語では「マス」と読むことが一般的である。発音によって意味や品詞が変わる単語ではないため、特別な注意は必要ない。「mass」の語源
「mass」の語源は、ラテン語の「massa」であり、これはギリシャ語の「maza」に由来する。どちらの言葉も「塊」や「固まり」を意味しており、現代英語の「mass」の意味と関連性がある。また、宗教的な意味での「ミサ」は、ラテン語の「missa」から来ており、「送る」や「解散させる」といった意味がある。「mass」の類語
「mass」の類語としては、「bulk」「multitude」「quantity」などが挙げられる。これらの単語も「大量」や「集まり」といった意味を持ち、文脈によっては「mass」と同じように使われることがある。「mass」に関連する用語・表現
「mass」に関連する用語や表現としては、「mass production」(大量生産)、「mass media」(大衆メディア)、「mass transit」(大量輸送)などがある。これらは、それぞれ「大量」や「集まり」といった意味を含んでおり、「mass」の意味を理解する上で参考になる。「mass」の例文
1. A mass of people gathered in the square.(広場に大勢の人々が集まった。)2. The mass of the Earth is approximately 5.97 x 10^24 kg.(地球の質量はおおよそ5.97 x 10^24キログラムである。)
3. They attended the Christmas mass at the church.(彼らは教会でクリスマスのミサに出席した。)
4. The mass of data needs to be analyzed carefully.(大量のデータを慎重に分析する必要がある。)
5. Mass production has made goods more affordable.(大量生産によって商品が手頃な価格になった。)
6. The mass media has a significant influence on public opinion.(大衆メディアは世論に大きな影響を与える。)
7. The mass of the object can be determined by its weight.(物体の質量はその重さによって決定される。)
8. Mass transit systems are essential for reducing traffic congestion.(大量輸送システムは交通渋滞の緩和に不可欠である。)
9. The mass migration of people has caused various social issues.(大量の人々の移動がさまざまな社会問題を引き起こしている。)
10. The mass of the iceberg was too large for the ship to avoid.(氷山の大きさがあまりにも大きく、船が避けることができなかった。)
ます
[助動][ませ・ましょ|まし|ます|ます|(ますれ)|ませ・まし]動詞、助動詞「れる」「られる」「せる」「させる」の連用形に付く。
1 丁寧語として、聞き手に対する敬意を表す。「山登りに行って来ました」「何かお手伝いすることがありますか」「使いの者を伺わせます」→ませ
「其上馬には子細が御ざる、かたってきかせませう」〈虎明狂・牛馬〉
[補説] 室町時代以降の語で、古くは未然形に「まさ」、終止・連体形に「まする」、命令形に「ませい」が用いられることもある。その成立については、「座(ま)す」「申す」「おはす」を起源とする説があるが、「まゐらす→まらする→まるする→まっする→まっす→ます」と変化したものを本流とみる説が有力である。仮定形「ますれ」はほとんど用いられず、代わって「ますなら」が多く使われる。命令形「ませ」「まし」は、「どうぞお入りくださいませ」「お早くお召し上がりくださいまし」のように、敬語動詞にしか付かない。「ます」を含んでいる文体を敬体とよび、常体の「だ・である体(調)」に対し、「です」とともに「です・ます体(調)」とよばれる。
ま・す
マス【Mas】
マス【mass】
マス
「マスターベーション」の略。
ま・す【▽在す/×坐す】
読み方:ます
[動サ四]
1 「ある」「いる」の意の尊敬語。いらっしゃる。おいでになる。
「大君は千歳に—・さむ白雲も三船の山に絶ゆる日あらめや」〈万・二四三〉
2 「行く」「来(く)る」の意の尊敬語。いらっしゃる。おいでになる。
「我が背子が国へ—・しなばほととぎす鳴かむ五月(さつき)はさぶしけむかも」〈万・三九九六〉
ま・す【増す/▽益す】
読み方:ます
[動サ五(四)]
㋒(「…にもまして」の形で)あるものよりも、もっと程度が上であることを表す。「前にも—・して元気になる」
㋐加える。また、加えて大きくする。ふやす。「人員を—・す」「紅葉が渓谷の景観を—・す」
㋑高める。伸ばす。進める。「興味を—・す」「親しみを—・す」
㋒すぐれるようにする。まさらせる。
「待てと言ふに散らでしとまるものならば何を桜に思ひ—・さまし」〈古今・春下〉
[可能] ませる
[用法] ます・ふやす——「権力が増す」「人気が増す」「水かさが増す」のように、「増す」が「が」をともなう場合は、物の量・程度が多くなる意で用いる。◇「速度を増す」「明るさを増す」「人手を増す」と「増す」が「を」をとる場合、物の量・程度を多くする意で用いる。◇「ふやす」は「貯金をふやす」「文庫の本をふやす」のように「を」をとる用法だけで、物の数・量を多くする意に使う。◇類似の語の「ふえる」は、「町の人口がふえた」「体重が五キロふえた」と「が」をともない、具体的な物の数・量が多くなる意に用いる。
ます【×枡/升/×桝/▽斗】
読み方:ます
1 液体や穀物などの分量をはかる容器。木製または金属製で、方形や円筒形のものがある。「—で米をはかる」「一升(しょう)—」「五合—」
ま・す【▽申す】
ます【×鱒】
読み方:ます
サケ科の魚で「マス」とつく名のものの称。特に、サクラマス・カラフトマスをいう。また、釣りではニジマスをさすこともある。《季 春》「—生(あ)れて斑雪(はだれ)ぞ汀(みぎは)なせりける/波郷」
ます【鱒】
マ ス
マス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/09 16:54 UTC 版)

マス(鱒、鮅[1])は、サケ目サケ科に属し日本語名に「マス」がつく魚、または日本で一般にサケ類(サケ(通称でシロザケ、いわゆる鮭)、ベニザケ、キングサーモンなど)と呼ばれる魚を除いたサケ科の魚をまとめた総称。マス、トラウト共にサケ類の陸封型の魚、及び降海する前の型の魚を指すことが多い。主に、イワナ、ヤマメ、アマゴ、ニジマス、ブラウントラウトなどがマス類、トラウト類など呼ばれる。
概要

タイヘイヨウサケ属、タイセイヨウサケ属、イワナ属、コクチマス属、イトウ属などの魚を包括する。一般的に「鱒」がよく使われるが、古い文献では、「鮅」も使われている。
サケとマスの境界が厳密でないため、国により区分方法が異なる。たとえば英語圏でキングサーモンはサケに区分されるが、日本では同じ魚をマスノスケと呼ぶほか、サクラマス、サツキマス、ニジマスをマスとして区分している。英語では、サケがSalmon、マスがTroutに対応している。単にtroutというと淡水産を意味し、海産のものはsalmon troutと呼ばれるが、シートラウト(Sea trout、ブラウントラウトの降海型、Salmo trutta morpha trutta)という例外もある。(⇒ サケ科#サケとマス)
北半球の高緯度地域に自然分布し、最高水温が20℃以下の河川や池沼(淡水)で産卵し稚魚の一部が降海し海洋で生活する生活様式をもつ。南半球では、放流によりオーストラリア、ニュージーランド、チリなどに分布する。ほとんどの種が重要な食用種で、毒性がなく独特のうまみがあるため身や卵を様々に加工調理し利用されている。
サケ目サケ科以外の魚種であるニベ科ナガニベ属には、スポッティドシートラウト(Spotted sea trout)と呼ばれる。
食材
- 焼き物
マスの一覧





- タイセイヨウサケ属 Salmo
- タイヘイヨウサケ属 Oncorhynchus
- カラフトマス O. gorbuscha
- シロマス属 Coregonus
- モトコクチマス C. albula
- エニセイシロマス[2] C.autumnalis
- ダウリアシロマス[3] C. chadary
- シロマス[4] C. clupeaformis
- シナノユキマス C. maraena
- オームリ(バイカルシロマス)[5] C. migratorius
- アイヅユキマス C. peled
- ウスリーシロマス[6] C. ussuriensis
- イワナ属 Salvelinus
- イトウ属 Hucho
- コクチマス属 Brachymystax
- カワヒメマス属 Thymallus
- キタカワヒメマス T. arcticus
- ウオノハナ(カワヒメマス) T. grubii
- ホンカワヒメマス T. thymallus
- チョウセンウオノハナ T. yaluensis
サケマス分類の混乱
サケマス研究が欧州に遅れていた日本では、名前を付ける際に、淡水産はマス・海産はサケ、小さいのはマス・大きいのはサケなどのように単純に区分していた。ところが後に陸封型であるヤマメやイワナなども途中でダムなどのない場所ではサケと同様の生活史を送っていることが判明した。遺伝学の進歩により、アミノ酸解析やDNA解析によって進化系の研究が進められている。また、日本海の地殻移動による閉鎖性なども考慮する必要がある。近年では、岐阜県水産試験場・当時場長であった本荘鉄夫によって「サケに似た変な魚」としてサツキマスと名付けられた長良川の魚が、アマゴの降海型であると確認されたこともある。混乱は現在もなお継続している。
特に、ニジマスにおいて混乱が著しい。かつてあったニジマス属を廃止し、海に降りて河川へ遡上し産卵したら死亡するシロザケなどのタイヘイヨウサケ属にニジマスを組み込む際、ニジマスは産卵しても死なないため、死なないグループであるイワナ属・イトウ属・タイセイヨウサケ属(サルモ属)との境界線をどこに置くかについて学者間で意見が分かれている。そのため、世界中で11属約66種と“約”で表されている。
脚注
- ^ U+9B85「魚+必、ひつ」
- ^ 疋田豊彦、三原健夫 (1968). “バイカル湖のオームリ”. さけ・ます資源管理センター技術情報 127: 2.
- ^ 『原色満洲有用淡水魚類圖説』南満洲鉄道、1939年、7頁。
- ^ 黒田長禮 (1953). “琵琶湖産魚類とその分布”. 魚類学雑誌 2 (6): 273.
- ^ 疋田豊彦、三原健夫 (1968). “バイカル湖のオームリ”. さけ・ます資源管理センター技術情報 127: 3.
- ^ 『原色満洲有用淡水魚類圖説』南満洲鉄道、1939年、6頁。
- ^ 『原色満洲有用淡水魚類圖説』南満洲鉄道、1936年、5頁。
- ^ 『原色満洲有用淡水魚類圖説』南満洲鉄道、1936年、6頁。
外部リンク
- 日本のサケ科魚類、水産総合研究センター
- 世界では11属、約66種に分類 - ウェイバックマシン(2009年4月9日アーカイブ分)
マスを題材にした作品
マス (MAS 1948)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 08:33 UTC 版)
「うぽって!!」の記事における「マス (MAS 1948)」の解説
※この「マス (MAS 1948)」の解説は、「うぽって!!」の解説の一部です。
「マス (MAS 1948)」を含む「うぽって!!」の記事については、「うぽって!!」の概要を参照ください。
マス
「マス」の例文・使い方・用例・文例
- クリスマス後のセール
- マス釣りをする
- 私はトマス・エディソンのような人になりたい
- クリスマスはすぐそこまで来ている
- クリスマスの時になるといつもたくさんのパーティーに出かける
- アメリカでは,クリスマスは大きな行事だ
- クリスマスの1週間前になるといつも帰郷する
- 私はクリスマスの日に生まれました
- クリスマスのだいたい1週間前にはいつも帰郷する
- 間に合わなかったクリスマスカード
- 彼は君にクリスマスのすばらしいごちそうをしてくれるつもりだよ
- クリスマス切手帳
- クリスマス休暇
- トーマス兄弟商会
- クリスマスが来るまでに彼はお金を使い果たした
- クリスマスカード
- クリスマスキャロル
- クリスマスはどんなふうに祝うのですか
- クリスマスに
- クリスマスを祝う
マスと同じ種類の言葉
「マス」に関係したコラム
-
FXやCFDのマスインデックスとは、高値と安値から値動きの幅を調べてトレンドの転換点を見つけるためのテクニカル指標のことです。マスインデックスは、ボラティリティの上昇とともに値が上昇し、ボラティリティ...
- >> 「マス」を含む用語の索引
- マスのページへのリンク
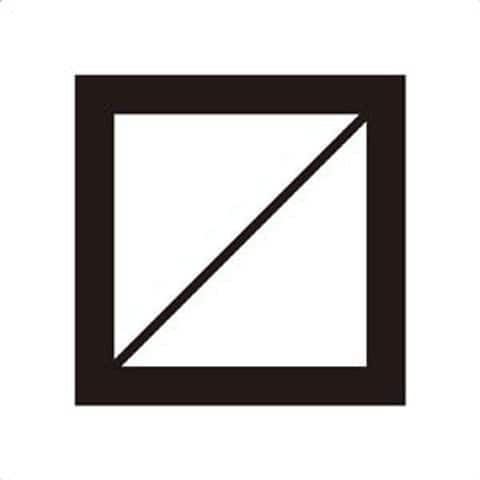
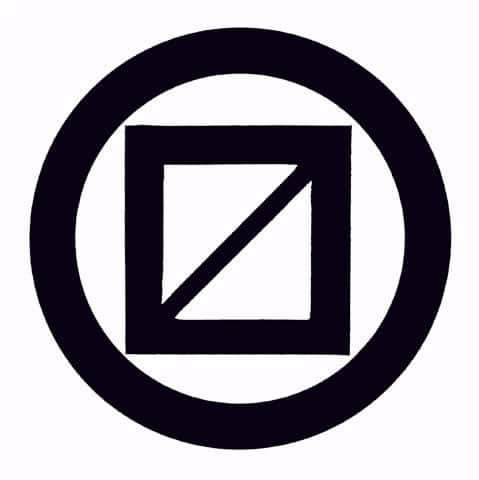
![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif)
![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)







