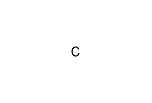たん‐そ【炭素】
炭素(C)
アセチレンブラック
炭素
炭素
炭素
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/09 06:21 UTC 版)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透明(ダイヤモンド)、黒色(グラファイト) |
|||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | 炭素, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 非金属元素 | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 14, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 12.0107 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [He] 2s2 2p2[1] | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 4(画像) | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | 非結晶質[2] 1.8–2.1 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | グラファイト:2.260[1] g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度(室温付近) | ダイヤモンド:3.513[1] g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 昇華点 | 3915 K, 3642 °C, 6588 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 三重点 | 4600 K (4327 °C), 10800[3][4] kPa | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 117(グラファイト) kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 8.517(グラファイト) 6.155(ダイヤモンド) J/(mol·K) |
||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 3, 4[5], 2, 1 [6], 0, −1, −2, −3, −4[7] | ||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.55(ポーリングの値) | ||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1086.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2: 2352.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 第3: 4620.5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 77 (sp3), 73 (sp2), 69 (sp) pm | ||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性[9] | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 119-165(グラファイト) 900-2300(ダイヤモンド) W/(m⋅K) |
||||||||||||||||||||||||
| 熱膨張率 | (25 °C) 0.8(ダイヤモンド)[10] μm/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ (微細ロッド) |
(20 °C) 18350(ダイヤモンド) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| ヤング率 | 1050(ダイヤモンド)[10] GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 剛性率 | 478(ダイヤモンド)[10] GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 442(ダイヤモンド)[10] GPa | ||||||||||||||||||||||||
| ポアソン比 | 0.1(ダイヤモンド)[10] | ||||||||||||||||||||||||
| モース硬度 | 1-2(グラファイト) 10(ダイヤモンド) |
||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-44-0[8] | ||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細は炭素の同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
炭素(たんそ、英: carbon、カーボン、仏: carbone、独: Kohlenstoff)は、原子番号6の元素である[11]。元素記号はC[11]。原子量は12.01。非金属元素、第14族元素、第2周期元素の一つ。
名称
フランス語の「carbone」は、1787年にフランスの化学者ギトン・ド・モルボーが「木炭」を指すラテン語carboから[12]名づけた。英語のcarbonは、これが転じたものである[1]。
ドイツ語の「Kohlenstoff」も「炭の物質」を意味する[1]。
日本語の「炭素」という語は、宇田川榕菴が著作『舎密開宗』にて用いたのがはじめとされる。
特徴
単体・化合物両方においてきわめて多様な形状をとることができる。
非金属の炭素には、4つの外殻電子と4つの空席がある。そのため、価電子数4[13]と元素の中でももっとも多い4組の共有結合を持つことが可能であり、この特徴から多様な分子をつくる骨格となる[14][15]。炭素がほかの元素と結びついて作る化合物の種類は約5,400万種にのぼる[13]。
融点や昇華を起こす温度は全元素の中でもっとも高い。常圧下では融点を持たず、三重点は10.8±0.2MPa、4,600±300Kであり[3][4]、昇華は約3,900Kで起こる[16][17]。
炭素原子同士の共有結合は非常に堅牢であり[13]、それがつくる単体において、自然物としてはもっとも硬いことで知られるダイヤモンドからもっとも柔らかい部類に入るグラファイトまで、幅広い形態や同素体を持つ。
歴史
炭素の単体は有機物を不完全燃焼すれば簡単に取り出せるため、有史以前から知られていた[1][18]。ダイヤモンドの存在も紀元前2500年ごろの古代中国では知られており、古代ローマでは今日と同様に木から木炭を得ていた。古代エジプトでも、粘土で密封したピラミッドの中から空気を抜くために木を熱する方法が用いられた[19][20]。そのため、特定の元素発見者はいない[1]。

1722年、ルネ・レオミュールは鉄が鋼となるには何かしらの物質を吸収することを示したが、現在ではそれは炭素であることが明らかとなった[21]。1772年にはアントワーヌ・ラヴォアジエが燃焼によって水が生じず、重量あたり同じ比率の二酸化炭素を生じることを確かめ、ダイヤモンドが炭素の単体であることを証明した[22]。1779年にカール・ヴィルヘルム・シェーレは、グラファイトが従来考えられていたように鉛の一形態ではないと示し[22]、1786年にクロード・ルイ・ベルトレー、ガスパール・モンジュ、C.A.ヴァンデスモンドが炭素であることを明らかにした[23]。彼らがこれを知らしめた際、この元素にcarboneという名をつけ、ラヴォアジエが1789年にまとめた元素のテキストに採録された[22]。
同素体フラーレンが発見されたのは1985年であり[24]、同じくナノ構造体としてはバッキーボールやカーボンナノチューブも見つかった[25]。これらの発見は1996年ノーベル化学賞の授与対象となった[26][27]。これらに触発された更なる同素体探査の結果、「ガラス状炭素」や、厳密には無定形ではないが名づけられた「無定形炭素」等の発見へつながった[28]。
生成
炭素原子の生成にはヘリウムの原子核であるアルファ粒子の3重衝突が必要となる。これには約1億度の熱が必要となるが、ビッグバンでは宇宙がはじめに大きく膨張してすぐに急速に冷え、炭素は生成されなかったと考えられている[29]。しかし、その後形成された恒星内でトリプルアルファ反応によるヘリウム燃焼過程でエネルギーを放出しながら炭素が生成される[30]。こうして作られた炭素は、主系列星の内部で水素がヘリウムになるCNOサイクルを媒介し、星のエネルギー放射に一役買っている[31]。
分布
宇宙での存在比は水素、ヘリウム、酸素に次いで多い[32]。炭素は太陽や恒星、彗星のなかにも豊富に存在し、さまざまな惑星の大気にも含まれている。まれに隕石の中から微細なダイヤモンドが見つかることがあり、これは太陽系が原始惑星系円盤だったころ、またはそれ以前に超新星爆発時に生成されたものと考えられている[33]。

地球
元素分布
地球上でみると必ずしも割合的に非常にたくさん存在している元素というわけではない[11]。地球の地表及び海洋の元素分布では炭素は重量比0.08%にすぎない[11](これはチタンやマンガンを下回る[34])。ただ炭素は他の元素との結びつき方で、性質の異なる驚異的なほど多彩な化合物を作り出し、地球環境の中に存在している[35](後述)。
地殻中の元素の存在度では15番目に多い炭素[32]の約9割が鉱物として存在し、中でも還元された形、すなわち炭素粒・石油・石炭・天然ガス中が4分の3以上を占める。4分の1が炭酸塩の岩石(石灰岩、苦灰岩 (CaMg(CO3)2)、結晶質石灰岩など)である。海洋など水に溶け込んだ炭酸も多く、その量は炭素量で36兆トン存在する。ついで生物圏に1兆9,000億トン、大気圏の二酸化炭素として8,100億トンがある。
埋蔵石化燃料として石炭が9,000億トン、石油は1,500億トン、天然ガスが1,050億トンに加え、さらにシェールガスのような採掘しにくい形態で別に5,400億トンの存在が見込まれている[36]。これらとは別に、メタンハイドレートとして極地に封じられ、これの炭素量はシベリアの永久凍土層だけでも1兆4,000億トンと見積もられる[37]。
炭素循環
炭素は地球上で多様な状態を示している。炭素は地殻、海洋、生物圏、大気圏を循環しており、年間の移動量は約2,000億トンと見積もられている。
惑星上では、ある元素がほかの元素に転換することは非常に稀である。したがって、地球に含まれる全炭素量はほぼ一定である。そのため、炭素を用いる過程はどこかでそれを獲得し、また放出することが必要となる。このような経路は、二酸化炭素の形で循環する体系を形成する。たとえば、植物は生育地の環境内で、呼吸によって二酸化炭素を放出する一方、光のエネルギーを用いて吸収した二酸化炭素から炭素を固定するカルヴィン回路を働かせ、植物組織を形成する。動物は植物を食べて炭素を吸収し、呼吸によって一部を排出する。このような短期的な循環だけでなく、より複雑な炭素循環も機能する。たとえば海洋は二酸化炭素を溶かし込み、枯れた植物や動物の死体は、バクテリアなどが消化しないと地中で石油や石炭などの形で炭素をとどめることもある。それらが化石燃料として利用されれば、燃焼によって再び炭素は放出される[38]。

炭素化合物
炭素の特性は他の元素と結びついて化合物を作る段階にある[35]。炭素は他の元素を束にしてもまったく歯が立たないほど多様な化合物の世界を作り出している[35]。これまでに天然に発見されたものと化学者が人工的に作り出した化合物の数は7,000万を超えるといわれているが、その約8割は炭素化合物である[35]。
生物
炭素-炭素結合で有機物の基本骨格をつくり、すべての生物の構成材料となる。人体を構成する元素の約18%が炭素といわれている[35]。これは蛋白質、脂質、炭水化物に含まれる原子の過半数が炭素であることによる。光合成や呼吸など生命活動全般で重要な役割を担う。地表での炭素の重量比は0.08%にすぎないため、生命は自然界にあるわずかな炭素をかき集めてかろうじて成立している[35]
鉱物
石炭は商業的にも重要な炭素供給元であり、無煙炭では炭素含有率は92 - 98パーセントにまでなる[39]。これに石油や天然ガスなどを加えた炭素資源は、そのほとんどを燃料として利用している[40]。
天然の黒鉛(石墨[8]、グラファイト)は世界中に分布するが、産出が多い地域は中国、インド、ブラジル、北朝鮮である[41]。天然のダイヤモンドは歴史的に南インド産が有名だが[42]、18世紀にブラジルで発見され[43]、その後南アフリカでも採掘され[44]、現在の主要産出国にはロシア、ボツワナ、オーストラリア、コンゴ民主共和国が名を連ねる[45]。近年ではカナダ、ジンバブエ、アンゴラでも鉱山が開かれ[44]、アメリカ合衆国でも発見されている[46]。
同位体
原子核に6つの陽子を含む炭素原子には、3種類の同位体、12C(存在比98.93パーセント)、13C(1.07パーセント)、14C(微量)が自然界で存在し[47]、それぞれがさまざまな学問分野で重要な位置を占める。
12Cは1961年にIUPACによって原子量の基準とすることが決定され[48]、アボガドロ定数などの基礎的な定数はこれによって算出された。なお、2019年に改訂されたSIではアボガドロ定数を6.02214076×1023 毎モル(mol−1)と定義値とし、12Cは用いなくなった。
13Cは核スピンを持つため、核磁気共鳴分光法において重要な核種である。
14Cは、地球上の存在比が100京分の1[49]、大気中では1兆分の1程度でしかなく[50]、泥土や有機物の中に含まれている[49]。半減期約5,730年の放射性同位体であり[47]、ベータ崩壊を起こして窒素原子に変化する[51]。しかし、成層圏において大気中の窒素と宇宙線(中性子)が反応して常時新たに生成されている[51][52]。そのため古い石や化石などの閉じた系では時間とともに存在比が低くなることが知られ[52]、考古学や標本の分野で4万年スケール、最大6万年の[50]時代判定を行う放射性炭素年代測定法に使用したり[51][53][54]、過去の宇宙線強度が変化した様子を通じて太陽活動[55]や地球磁場の変遷[50]を分析するために使われる。
ほかにも、生物学や医学の分野でも14Cをマーカーにした多くの分析法が開発された。光合成の初期研究には炭素14(14C)が用いられ、その後は効果的な肥料の開発にも同位体が使われる[56]。ただし放射性物質である炭素14は取り扱いが難しいため、現在では放射能を持たない同位体元素である炭素13(13C)を用いた分析法も開発されている。
その他、炭素には半減期が非常に短い15種類の同位体が知られている。8C は半減期 1.98739 × 10-21秒で陽子放出やアルファ崩壊を起こす[57]。19Cは風変わりな中性子ハローの状態で存在する[58]。
単体の性質
同素体

炭素は4本の共有結合ができ、結合の状態によって数種類の同素体を形成する[59]。炭素同士がsp2混成軌道を形成し、正六角形の平面構造を取った膜が重なったものがグラファイトになる[51]。2009年、グラファイトの基本構造である薄いグラフェンは非常に高い硬度を持つことが判明した[60]。しかし、グラファイトから薄いグラフェンを経済的に剥ぎ取る技術は確立されておらず、事業性の確立は今後の開発を待つ必要がある[61]。また、炭素がsp3混成軌道を形成して正四面体の立体結晶構造を取った巨大分子となったものがダイヤモンドとなる[51]。同じ炭素の同素体であるが、前者は電気伝導性が高く軟らかい、後者は絶縁体で硬いなど、まったく異なる性質を示す。ダイヤモンドが炭素の同素体であることを示したのはラヴォアジエである。実験内容は、密閉容器に納めたダイヤモンドを虫眼鏡により燃焼させると二酸化炭素だけが生成されるというものである。
木炭やススなどは結晶構造を持たないアモルファス状態であり「無定形炭素」と呼ばれる。この種類には、工業的に重要な炭素繊維や活性炭、コークスなども含まれる[62]。
以上3種は古くから知られていたが、20世紀後半以降、球状のグラフェンであるフラーレン[25][63]や多分野での開発が進んでいるカーボンナノチューブ[64]、カーボンナノバッド[65]、カーボンナノファイバー[66][67]などや、ロンズデーライト[68]やガラス状炭素[28]、カーボンナノフォーム[69]、カルビン[70]などの複雑な構造を持つ炭素の同素体が多数発見されている。

|
|


生産と用途
炭素の単体は形状によってさまざまな分野で使用されている。アモルファス炭素としてはカーボンブラックや活性炭が大量に生産されており、黒色顔料(インク、コピートナー、墨汁など)やゴム製品への混錬剤、石油の脱硫などの吸着剤をはじめ、きわめて幅広い用途に用いられている。カーボンブラックの平成22年(2010年)度日本国内生産量は72万3,159トンである[71]。
天然のほか、コークスの成形焼結などでも製造される[72]黒鉛は、電池などの電極剤や鉛筆の芯、るつぼ、塗料などに使われる[8]ほか、黒鉛を成形した黒鉛ブロックは黒鉛減速沸騰軽水圧力管型原子炉「RBMK-1000」やコールダーホール型をはじめとした黒鉛炉という原子炉の炉心を構成しており、中性子の速度を下げる減速材として機能している[73][74]。
黒鉛から人工ダイヤモンドを作る技術は1880年ごろから取り組まれ、昭和28年(1953年)ごろには3000℃、13万気圧下で実現し、年間1億カラット以上が生産されている[51]。ダイヤモンドは宝飾用のほかカッターや研磨材また電極としても利用されている[75]。さらには次世代型半導体としても研究されている[76]。
アクリロニトリルを無酸素状態で熱分解し製造する炭素繊維は、軽くて強度や弾力に優れることから、船舶および航空機・宇宙船からスポーツ用具まで幅広い用途において金属を代替する素材として使用されている[62]。活性炭はヤシの殻を蒸し焼きにする方法に加え、廃タイヤから製造する方法も開発された。前者は冷蔵庫などの脱臭剤でよく使われ、後者は吸着力を利用した河川浄化など土木分野での利用が検討されている[62]。
石炭から作られるコークスは構成要素のほとんどが炭素であり、燃料や製鉄に使用されている。平成18年(2006年)度世界生産量は4億7,800万トンであり、その半分以上を中国が占めた[77]。油を燃やして得られるタイヤ着色などに使われる一般的なカーボンブラック[78]は水素を0.3 - 0.8パーセント程度含むが、アセチレンを熱分解または爆発させて製造するアセチレンブラックは水素含有率0.04パーセントと低く鎖状構造を作りやすい。そのため、導電性が要求される素材に用いられる[8]。
化合物

炭素は多様な化合物を作ることができるため、これまで報告されているものは1,000万種をはるかに超える[14]。二酸化炭素や一酸化炭素、炭酸、炭化物等を除き、炭素の化合物は有機化合物(有機物)と呼ばれ、生命活動で生産されるほか、有機化学によって人工的にも多くの物質が生み出されている。
無機化合物として一般的な二酸化炭素(CO2)は大気中にわずかに含まれ、光合成や呼吸など生命活動と密接な関わりを持つ。また、炭酸塩として方解石(石灰岩)などの鉱物中にも分布している。
金属とのあいだでは炭素はアセチリド(C22−)や侵入型固溶体の形で化合物を作る。銑鉄と鋼の関係で見られるように、金属中の炭素量は硬度などの特性に大きな影響を与える。また、炭化ケイ素(SiC)などいくつかの炭素化合物は格子状の結晶構造を持ち、ダイヤモンドと似た性質を持つ。
炭素のオキソ酸
炭素のオキソ酸は慣用名をもつ。次にそれらを挙げる。
| オキソ酸の名称 | 化学式 | 構造式 | オキソ酸塩の名称 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭酸 (carbonic acid) |

ウィキメディア・コモンズには、炭素に関連するメディアがあります。
外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炭素
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/28 07:10 UTC 版)
「国際核融合材料照射施設」の記事における「炭素」の解説
炭素が使用される場合、物理・化学双方のスパッタリングに起因するエロージョンの速度は1年あたり数メートルにも達する。そのため、スパッタされた材料が再蒸着されることに頼らなくてはならない。再蒸着される場所がスパッタされた場所と対応関係にあるわけではないので、炭素の持つ、使用に供し難いほどのエロージョン速度という問題は拭い去れない。更に大きな問題として、炭素の再蒸着の際に三重水素が一緒に蒸着されることがある。炭素の再蒸着層に取り込まれた三重水素と炉内のちりはすぐに数 kg のオーダーの量に達する。これは燃料が再蒸着で失われることと、事故の際にきわめて深刻な放射性物質汚染の問題を引き起こすことを示している。核融合関係者の間では、炭素は核融合実験においては非常に魅力的な材料ではあるが、PFC 材質として第一に選択すべきものとはなり得ないだろう、ということが共通認識となっている。
※この「炭素」の解説は、「国際核融合材料照射施設」の解説の一部です。
「炭素」を含む「国際核融合材料照射施設」の記事については、「国際核融合材料照射施設」の概要を参照ください。
炭素
出典:『Wiktionary』 (2021/07/14 12:14 UTC 版)
名詞
語源
複合語
訳語
- イタリア語: carbonio
- 英語: carbon (en)
- エスペラント: karbono
- オランダ語: koolstof (nl) 男性/女性
- カシューブ語: wãdźel m
- ギリシア語: άνθρακας
- スウェーデン語: kol (sv) 中性
- スペイン語: carbón
- 中国語: 碳(tàn)
- ドイツ語: Kohlenstoff m
- フランス語: carbone
- ポーランド語: węgiel (pl) 男性
- ポルトガル語: carbónio
- モンゴル語: нүүрстөрөгч
- リトアニア語: anglis (lt) 女性
- ルーマニア語: carbon n
- ロシア語: углерод m
参照
「炭素」の例文・使い方・用例・文例
- ドライアイスは炭素と酸素に分解する
- 一酸化炭素中毒
- 石炭は大部分が炭素から成っている
- 二酸化炭素
- 一酸化炭素
- リチウムイオン電池は、負極に黒鉛等の炭素材料を用いています
- 炭素質コンドライト
- この研究は、二酸化炭素が地球温暖化の原因だという仮定を証明するものだ。
- リボースは五炭糖で、5つの炭素原子を含んでいる。
- 炭素の単分子層
- 高炭酸ガス血症は血液中の二酸化炭素の値が高い状態を意味する。
- 月の石の放射性炭素年代測定
- 土壌炭素流出物を削減する
- 森は二酸化炭素を吸収してくれる。
- 2012年と同じ方法で2011年の二酸化炭素排出を計算してください。
- 2011年の二酸化炭素排出の結果を再計算してください。
- 燃焼時に一酸化炭素と二酸化炭素を放出する。
- 私は二酸化炭素を削減するために出来ることをしたい。
- 私は二酸化炭素の削減に貢献することができます。
- 原子力発電は二酸化炭素排出量が少ない。
炭素と同じ種類の言葉
- >> 「炭素」を含む用語の索引
- 炭素のページへのリンク