カバディ
カバディとは「接触」を根幹とするインド発祥のスポーツ(団体競技)である。インドの国技であり、同国およびその周辺の国々で発展した。
【カバディの語源】
カバディ(kabaddi)という言葉そのものの元々の意味・語源・由来は定かでない。競技上、攻撃手は息継ぎせずに「カバディ」と連呼している間のみ攻撃できるというルールがある。
【特徴】
カバディは概ね10メートル四方(12.5m×10m)のコート内で攻守のチームに分かれて行う。ボール等の道具は特に必要なく、コートがあれば競技できる。攻撃側チームはひとり相手陣地に侵入し、守備側チームの誰かにタッチして自陣に帰還すれば得点となる。守備側が攻撃を躱しきれば攻撃失敗である。鬼ごっこやドッジボールの要領に通じるといえる。
カバディは日本では長らく色物的なマイナースポーツとして認識されてきたといえる。2010年代半ば以降、カバディを主題としたマンガ作品が登場し人気を博したこともあり、徐々に認知度や人気を高めてきている。競技人口も増えつつあるという。
カバディ【(ヒンディー)kabaddi】
カバディ
歴史と沿革
 インドを中心にバングラディシュ、パキスタン、スリランカ、ネパールなどの南アジアの国々では、 二千年以上の歴史を持つ伝統のあるスポーツ。特にインドやバングラディシュでは国技として人気が高い。
インドを中心にバングラディシュ、パキスタン、スリランカ、ネパールなどの南アジアの国々では、 二千年以上の歴史を持つ伝統のあるスポーツ。特にインドやバングラディシュでは国技として人気が高い。
約二千年前のインドで、猛獣を数人で取り囲み、武器を持たずに捕らえるという狩りの手法があり、これがカバディの起源といわれている。
競技としてのカバディは、1980年第11回アジア競技大会(北京)から正式競技種目となり、 1994年第12回アジア競技大会(広島)と1998年第13回アジア競技大会(バンコク)に日本人選手を派遣している。 次の2002年第14回アジア競技大会は、釜山での開催が決定している。
日本国内でのカバティ競技は、98年にインドチームと初めて国立代々木第二体育館で対戦が行われた。 以後、毎年、全日本大会を首都圏で開催し、日本代表選手の選考会も兼ねて海外試合に選手を派遣している。
用具を必要としないカバディは、東南アジアで広く普及し、競技人口は1000万人にも及んでいる。ルールや競技方法もシンプルな分、奥が深く、プレーヤーのレベルに応じたプレイができる。体をぶつけあって遊ぶことの少なくなった現代の子供たちには、最適なスポーツといえる。 わが国のカバティ競技人口は5000人ほどで、大学生が多い。近年、女性の愛好者も増えている
競技方法
競技の特徴をひとことでいえば、鬼ごっこと格闘技をかけあわせたようなもの。何も道具を必要とせず、 タテ12.5m×ヨコ10m(女子は10×8m)のコートさえあればプレーできる(下図参照)。
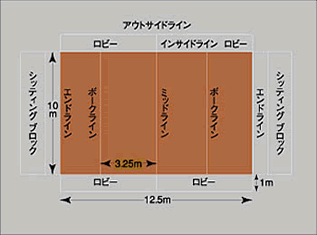
1チーム7人で、試合時間は前後半各20分(女子は15分)。得点はタッチ1人につき1点、攻撃に失敗すると守備チームに1点加算される。競技選手には体重制限があり、85kg未満が条件。試合は攻撃と守備を交互に行う。攻撃側1名(レイダー)が、相手側コートのセンターにあるボークラインを越えた時点でプレーが開始され、守備側(アンティ)のコート内でプレーは展開される。
得点となるプレイとルール
 1. レイダー1人が相手コートに攻め入り、守備側のプレイヤーの体にタッチした後、指先だけでもミッドラインを越えて自陣に戻れば1点の獲得。タッチされた守備側プレイヤーは、その時点でコートアウト(シッティングブロックに一時退場)しなければならない。
1. レイダー1人が相手コートに攻め入り、守備側のプレイヤーの体にタッチした後、指先だけでもミッドラインを越えて自陣に戻れば1点の獲得。タッチされた守備側プレイヤーは、その時点でコートアウト(シッティングブロックに一時退場)しなければならない。
2. レイダーが守備側に捕まって自陣に戻れないときは、守備側の得点となる。ただし、捕まえ損ねて自陣に戻られた場合は、攻撃側の得点となり、同時にレイダーの体に触れた守備側プレイヤーはすべてコートアウトとなる。
3. 得点すると、自陣からコートアウトしている選手が、得点分の人数だけコート内に復帰できる。また、チームの選手が全員が退場になった場合、相手チームに2点を与え、全員がコートに復帰して試合を再開できる(これを「ローナ」といい、英語でいえばリセット)。
4. レイダーは、攻撃中に「カバディ、カバディ」と息継ぎをせずに呼称しなければならず、息継ぎや呼称が途切れればコートアウトとなり、守備側の得点となる。守備側はレイダーに対し、タックルやホールディングなどを試みて、呼吸を途切れさせようと、リスク覚悟の駆け引きをする。
コート
本来、土と堆肥とおが屑で作られた、平坦で柔らかなグラウンド上で競技されるが、日本には柔らかい土のグラウンドが少ないので、体育館でプレーされることが多い。
コートはインサイドラインとエンドラインの内側を使用し、攻撃側も守備側もラインを足が越えた場合はアウトとなる。ただし、攻撃手のタッチが決まった後は、攻撃手は逃げるため、守備側は捕獲のために、両サイドのロビー内も利用できる。したがって、審判員は両サイドラインとエンドラインに4名必要となる。サイドラインの1名の審判員が加点の笛で得点を指示し、得点板に得点を書いて競技者に公開する。最終的に、前後半を終えて得点が勝っているチームが勝者となる。
このように一見単純なスポーツに見えるが、一定レベル以上の試合になると、攻守の緻密な駆け引きと、一転して攻守が入れ替わるので息つく暇がなく、なかなか知恵を必要とするハードで奥深いスポーツといえる。
カバディ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/23 01:30 UTC 版)

カバディ(英: Kabaddi、ヒンディー語: कबड्डी)は、南アジアで主に行われるチームスポーツ。
概要
インドから発祥した国技であり、その源流はマハーバーラタに遡るといわれ、古代に起源すると考えられている。最も大きな特徴として、競技中に攻撃者は「カバディ、カバディ、カバディ……」と発声し続けなければならないというルールがある。 日本では競技人口は少ないながらも、試合中に「カバディ、カバディ、カバディ…」と発声する場面があるスポーツとして知られる[注釈 1]。
ルール
1チーム10 - 12名で、各チーム7名がコートに入り2チームで争う。男子は13m×10m、女性は11m×8mのコートを、長辺の側の中間地点で二分し、両サイドにチームごと分かれて入る。試合時間は、男子は前後半それぞれ20分ハーフで休憩をはさみ5分、女子は15分ハーフで休憩は5分である。守備と攻撃を順番に繰り返し、点数の多い方が勝利となる。
公式試合では基本的に体重制限がある。ただし、体重制限を設けない試合もある。
- 攻撃側
- 攻撃側のチームは、自分たちのチームからレイダーと呼ばれる攻撃者を1名選び、レイダーが守備側のコートに入る。 守備側の7名はアンティと呼ばれる。 レイダーが「カバディ、カバディ……」と発声し続けながら(この発声を「キャント」と呼ぶ)、守備側のチームのアンティにタッチ(「ストラグル」と言い、ポイントを保持している状態)して、素早く自分のコートに戻ってこられればタッチした人数分の点数が入る。 なお、レイダーは一息分でキャントしている間しか攻撃できない。
- 守備側
- 守備側は、点数が入るのを阻止するためにレイダーの四肢・胴体をつかまえたり(「キャッチング」と呼ぶ)して、レイダーが自陣に戻るのを防げれば1点が守備側に入る。守備側のタッチされた選手及びキャッチングされた攻撃側の選手はアウトとなり、味方が得点するまでコート外で待機しなくてはならない。
- 味方の得点によるコート内への復活
- 味方が得点した際、シッティングブロックで待機中の選手はコートに復活できる。復活出来る人数は1得点につき1人となる。但し、ボーナスポイントによる復活は無い。[2]
- ローナ
- 片方のチームの選手が、全てアウトになった状態をローナという。その際は、もう片方のチームに2点を与えて全員がコート内に復活できる。[2]
- Do or Die Raid
- 得点しない攻撃(Empty Raid)が3回続くと、3回目に攻撃に行った選手は強制的にアウトになり、相手の得点になるルール。3回目に攻撃に行く選手は、得点しなければアウトとなるため、やるかやられるかの勝負をしなければならない。終盤に点差が開き、勝っているチームが時間稼ぎで攻撃しないのを防ぐのと、膠着した試合でロースコアの物足りない展開になるのを防ぐため、プロカバディで用いられてきた。
- 近年は国際大会でも使われるようになっており、それに合わせ2017年の第11回東日本カバディ選手権大会以降は国内大会でも使われている。
アジア競技大会

- アジア競技大会において、1990年北京大会より正式種目となっている。日本でカバディが注目され始めたのはこの大会のころである。
- 日本代表は、2010年アジア競技大会にて初のメダルとなる銅メダルを獲得した。
カバディを題材にした作品
漫画
- 灼熱カバディ - 武蔵野創 (マンガワン、小学館)
- カバディ7 ー 小野寺浩二 (コミックフラッパー 、メディアファクトリー)
- ちおちゃんの通学路 - 川崎直孝 カバディを扱った回がある。
- ウワガキ - 八十八良 カバディを扱った回がある。
- ニーチェ先生〜コンビニに、さとり世代の新人が舞い降りた〜 - 松駒×ハシモト 語り部役である著者のバイト仲間がインド留学中に嗜んだと語っている。
- 銀魂 - 空知英秋 登場人物の1人である山崎退はバドミントンとカバディが趣味である。
映画
- カバディーン!!!!!!! 嗚呼・花吹雪高校篇 - 小原剛(ユナイテッドエンタテインメント)
- カバディーン!!!!!!! 激突・怒黒高校篇 - アベユーイチ(ユナイテッドエンタテインメント)
- カバディ!カバディ! - 泊誠也(オフィスエイト)
ゲーム
ヘブンバーンズレッド - 主人公がカバディに興じる交流イベントがある。
歌
脚注
注釈
出典
- ^ “【レビュー】『灼熱カバディ』ネタ扱いスポーツで描く前人未踏の成長物語”. KAI-YOU.net (2021年7月3日). 2022年6月18日閲覧。
- ^ a b https://www.jaka.jp/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%A6%82%E8%A6%81/
関連項目
- 国際カバディ連盟 (International Kabaddi Federation)
- 日本カバディ協会
- ヨガ - 「キャント」はヨガの理論が起源とされている
- カバディ日本代表
- カバディ女子日本代表
- アジアアマチュアカバディ連盟 (Asian Amateur Kabaddi Federation)
- モハメド・ヨネ - 2010年から日本カバディ協会のカバディ親善大使を務めている。
外部リンク
- 国際カバディ連盟
- カバディとは? - ウェイバックマシン(2009年3月2日アーカイブ分)
- カバディのルール - ウェイバックマシン(2019年1月1日アーカイブ分)
- 日本カバディ協会
- アジアアマチュアカバディ連盟
- 大平峻也「FIRE BIRD」MV
カバディ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/08 17:44 UTC 版)
「ラブプリート・サンガ」の記事における「カバディ」の解説
幼少時代よりカバディに打ち込む。2014年、WKL(World Kabaddi League)に参加するユナイテッド・シンズの一員として優勝に貢献。
※この「カバディ」の解説は、「ラブプリート・サンガ」の解説の一部です。
「カバディ」を含む「ラブプリート・サンガ」の記事については、「ラブプリート・サンガ」の概要を参照ください。
カバディ
カバディと同じ種類の言葉
- カバディのページへのリンク



