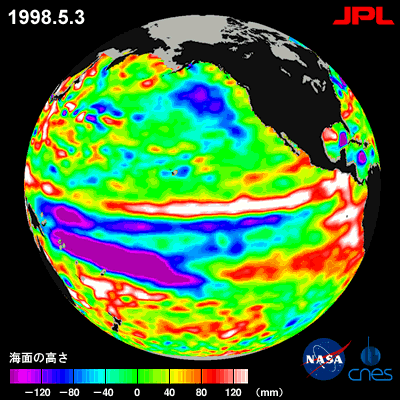エルニーニョ現象
別名:エルニーニョ
英語:El Niño、El Niño event、El Nino
太平洋東部の赤道付近、ペルーとエクアドルの沖合から西へ太平洋のほぼ中心部まで数千キロメートルに及ぶ海域において、海面の水温が局所的に異常上昇する現象。
エルニーニョ現象はおおよそ4~5年に一度の割合で発生し、発生すると数ヶ月から1年ほどの期間にわたり続く。水温は高いところでセ氏5度ほど上昇する。また、エルニーニョ現象は「南方振動」と呼ばれる海面気圧の変動と密接に関連することが知られている。
エルニーニョ現象が発生すると、世界各地の気候も連動して変化する。季節と地域によって異なるが、平年より気温が高くなったり、逆に低くなったり、雨量が増えたり、減ったりする。日本の場合は低温・多雨になりやすいとされるが、過去の観測では暖冬にも寒冬にも、冷夏にも猛暑にも転じており、変化は必ずしも一様でない。
海水温が上昇するエルニーニョ現象に対して、同海水域の海水温が低下する現象が「ラニーニャ現象」(La Niña)と呼ばれる。エルニーニョ現象とラニーニャ現象は、おおむね交互に発生する傾向にある。
関連サイト:
エルニーニョ現象に伴う世界の天候の特徴 - 気象庁
エル‐ニーニョ【(スペイン)El Niño】
エルニーニョ
エルニーニョの語源は、スペイン語の"神の子"
エルニーニョとは南米エクアドルからペルー沿岸にかけて、海水温が4年から5年おきに上昇する現象のことで、水温の高い状態は半年から1年半程度続きます。例年クリスマスのころになると局所的な水温の上昇が起こることが多いのですが、折からバナナなどの収穫期に当たるため、神の恵みに感謝を込めてスペイン語のエルニーニョ(神の子)と名づけられました。これとは反対に、東太平洋赤道域の海面水温が平年より低くなる現象をラニーニャといいます。スペイン語で"女の子"のことで、エルニーニョの"男の子"に呼応して名づけられました。
世界各地に異常気象を引き起こすエルニーニョのすごさ
エルニーニョ現象は、数1,000km以上にわたって水温の異常上昇を引き起こし、大気の流れを変え、世界各地に高温や低温、多雨や小雨など異常気象を引き起こします。1982~83年にかけて発生したときはオーストラリア、インド、アフリカなどにかんばつ、アメリカに熱波、日本に梅雨寒や暖冬をもたらすなど世界的規模で異常気象が発生しました。最近では1990年春に発生し、1992年夏に一時弱まりました。しかし1997年春に約4年ぶりに発生したエルニーニョ現象は、世界各地にもたらした多くの異変によって今世紀最大規模のものとされています。
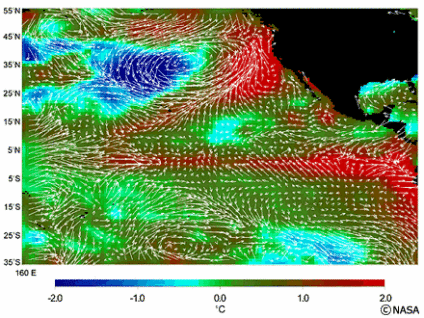
衛星から送られてきた海面温度分布データ。色は海面温度を表し、矢印は風向きを表している。
NASAの報告によると、エルニーニョが1998年1月には最高時の40%に収縮
「1997年春以降続いていたエルニーニョは収縮傾向に入った」。NASAのジェット推進研究所(JPL)は1998年1月16日までの観測で確認しました。エルニーニョは、1997年12月にいったん衰退の兆しをみせましたが、再び増大傾向を示していました。衛星から送られてきた1998年1月の海面温度分布データによると、エルニーニョの勢力は、これまで最高だった1997年11月上旬にくらべ、約40%減少しています。しかし、JPLの海洋学者らは、これまでのエルニーニョも収縮と増大をくりかえしており、異常気象をもたらす海面からの大きなエネルギーが大気中にすでに放出されているなどとして、「今後も異常気象への警戒は怠ってはならない」とよびかけました。
エルニーニョの影響が残る西部太平洋海域
1998年5月、NASAはエルニーニョ現象が東部太平洋では衰えているものの、西部太平洋の赤道海域では冷たい海水が広がっており、依然として影響が続いていることを示す衛星画像を発表しました。画像は、同年5月の海面の高さをとらえた衛星データを基にしており、太平洋のほぼ中央からニューギニア東岸にかけた広い海域で、平年にくらべ水位が約30cmも低いことがわかりました。NASAによると、水位が低いのは海水の温度が低いためで、水温の低い海域が広がっていることを示します。これをNASAは、西部太平洋海域にはまだエルニーニョの影響が残っているためと分析しています。
エルニーニョ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/31 00:02 UTC 版)

|
この項目「エルニーニョ」は翻訳されたばかりのものです。不自然あるいは曖昧な表現などが含まれる可能性があり、このままでは読みづらいかもしれません。(原文:en:El Niño21:32, 23 December 2021)
修正、加筆に協力し、現在の表現をより自然な表現にして下さる方を求めています。ノートページや履歴も参照してください。(2022年1月) |
エルニーニョ(スペイン語:El Niño 語意は「神の子」[注釈 1])またはエルニーニョ現象(エルニーニョげんしょう)とは、エルニーニョ・南方振動(ENSO) での温暖な局面を指す用語で、南米の太平洋岸沖合を含む中央太平洋および東中部太平洋の赤道域(概ね日付変更線と西経120度の間)にて発達する暖かい海流が関与しているもの[注釈 2]。
ENSOとは、中央太平洋および東太平洋の熱帯域で発生する海面水温(SST)が上昇しては下降する振動である。その温暖局面にあたるエルニーニョは西太平洋に高い気圧をもたらし、東太平洋には低い気圧をもたらす。エルニーニョの状態は数年にわたって続くことが知られており、記録ではその周期が2-7年継続することが示されている。エルニーニョの発達時期は、9月から11月にかけて降雨が発生する[要説明][3]。対してENSOの寒冷局面はラニーニャ(スペイン語で「女の子」の意)と呼ばれ、東太平洋の海面温度が平均を下回り、東太平洋で気圧が高くなって西太平洋では低くなる。エルニーニョとラニーニャの双方を含むENSOの周期が、気温と降雨における世界規模の変化を引き起こしている[4][5]。
とりわけ国境を太平洋と接しており農業と漁業に依存する発展途上国が、一般的に最もその影響を受ける。この局面になると、南米付近の太平洋にある暖水域が多くの場合クリスマス頃に最も暖かくなる[6]。元々のフレーズ「El Niño de Navidad」は数世紀前に生まれたもので、ペルーの漁師がキリスト降誕祭にちなんでこの気象現象を命名した[7][8]。
概要
もともと「エルニーニョ」という用語は、クリスマス時期にペルーとエクアドルの沿岸を南に流れる毎年の小規模な暖かい海流を指すものだった[9]。しかし、歳月が経つにつれてこの用語は進化し、現在ではエルニーニョ・南方振動での温暖かつ好ましくない局面および中央太平洋と東太平洋の熱帯域における海面の温暖化や平均を上回る海面水温を指すものとなっている[10][11]。この温暖化が大気循環の遷移を引き起こしており、インドネシア、インド、オーストラリア上空では降雨量が減少し、太平洋熱帯域の上空では降雨量が多くなって熱帯低気圧の形成も増加する[12]。海面辺りを吹く貿易風は、平年だと赤道に沿って東から西に吹いているが、これが弱まったり他の方角から吹くようになる[11]。

エルニーニョは数千年にわたって発生していると考えられている[13]。例えば、エルニーニョは現在のペルーにあったモチェ文化に影響を及ぼしたと思われる。また科学者たちは、エルニーニョによって引き起こされた海面温度の上昇と降雨量の増加による化学的兆候を約13,000年前のサンゴ標本で発見した 。1525年頃、フランシスコ・ピサロはペルーに上陸した際に砂漠での降雨を記述しており、これがエルニーニョの影響を最初に書き留めた記録とされている。現代の調査および再分析技術によって、1900年以降に少なくとも26回のエルニーニョ現象が起こっており、1982-83,1997-98,2014-16年の現象が記録上最も強いものだったことが判明した[14][15][16]。
現在、エルニーニョ現象を構成する要件について各国が異なる閾値を持っており、閾値はその国独特の利害と絡み合ったものである[17]。例えば、オーストラリア気象局はエルニーニョ監視海域3および3.4の貿易風、南方振動指数(SOI)、気象モデル、海面温度を見てからエルニーニョを宣言する[18]。米国気候予測センター(CPC)やコロンビア大学の地球研究所 は、エルニーニョ監視海域3.4の海面温度や太平洋熱帯域の大気を観察してアメリカ海洋大気庁の海洋ニーニョ指数が数シーズン連続で+0.5°Cを超えるとエルニーニョだと予測している[19]。ところが日本の気象庁は、エルニーニョ監視海域3の海面水温基準値との偏差にあたる5か月移動平均値が +0.5℃以上の状態で6か月持続する場合に「エルニーニョ現象が発生」と表現している[20]。ペルー政府は、エルニーニョ監視海域1と2の海面温度偏差が少なくとも3ヶ月間+0.4°C以上となった場合に沿岸のエルニーニョが進行中だと宣言している[21] (エルニーニョ監視海域については後述の海域図を参照)。
エルニーニョ現象には「強くなる、長くなる、短かくなる、弱くなる」のいずれを支持する研究もあるため、気候変動がエルニーニョ現象の発生、強さ、期間に影響をどう及ぼすかに関するコンセンサスが存在しない[22][23]。
発生

エルニーニョ現象は何千年も前から発生していると考えられている[13]。例えば、エルニーニョは雨を降らせまいと人身御供をしたモチェ文化に影響を与えたと考えられている[24]。
1900年以降少なくとも30回のエルニーニョ現象が発生し、1982-83,1997-98,2014-16年の現象が記録上で最も強大だと考えられている[14][15]。2000年以降では2002-03, 2004-05, 2006-07, 2009-10, 2014-16[14], 2018-19年にエルニーニョ現象が観測された[25][26]。
典型的には、この異常が2-7年の不規則な間隔で発生しており、9ケ月-2年ほど継続する[27]。平均的な期間の長さは5年である。この温暖な状態が7-9か月にわたって発生するとエルニーニョ「状態(condition)」に分類され、その継続時期が長い場合にエルニーニョ「期間(episode)」に分類される[28]。
強いエルニーニョ期間の最中に、極東太平洋の赤道域全体で海面温度の二次ピークが最初のピークに続いて起こることが時々ある[29]。
文化史との関連

少なくとも過去300年間でENSO状態が2-7年間隔で発生しているものの、その大半は振れ幅が弱い。1万年前の完新世初期におけるエルニーニョ現象が強かったとする証拠も存在する[30]。
エルニーニョは、モチェ文化をはじめ先コロンブス期のペルー文化を崩壊に至らせた可能性がある[31]。近年の研究では、1789年から1793年にかけての強大なエルニーニョの影響がヨーロッパで作物収穫の不作を引き起こし、これがフランス革命勃発を助長したと示唆されている[32]。1876-77年のエルニーニョで生じた極端な天候は、19世紀の最も致命的な飢饉の原因となったとされ[33]、1876年の飢饉では中国だけで最大1300万人が死亡した[34]。
気候を指す「エルニーニョ」という用語の記録された最初期の言及は1892年、南へ向かう暖流がクリスマスの頃に最も顕著だったためペルー人船員が「エルニーニョ」と名付けた、とカミロ・カリーリョ海軍大尉がリマでの地理学会会議で語った[35]。この現象はグアノ産業や海洋生物の生物圏に依存する他の事業に及ぼす影響から、長年にわたって関心が寄せられていた。早くも1822年には、フランスのフリゲート艦(La Clorinde)で地図製作をしていたジョセフ・ラルティゲがペルー海岸沿いを南に移動するこの「逆流」とその有用性を指摘した記録が残っている[36][37][38]。
1888年にチャールズ・トッドは、インドとオーストラリアの干ばつが同時に起こる傾向があることを示唆した[39]。ノーマン・ロッカーも1904年に同じことを指摘した[40]。1894年にビクトル・エギグレン(1852-1919)、1895年にフェデリコ・アルフォンソ・ペゼット(1859-1929)によって洪水とエルニーニョとの関連が報告された[41][37][42]。1924年にギルバート・ウォーカー (ウォーカー循環の由来となった人物) が「南部振動」を造語し[43]、一般的には彼や気象学者ヤコブ・ビヤークネス などがエルニーニョの影響を特定したと評されている[44]。
1982-83年の強大なエルニーニョが科学界からの関心を高めることになった。1991-95年の時期は、複数のエルニーニョがこれほど急に連続発生することが稀であり異例となった[45]。1998年の特に激しいエルニーニョ現象は、世界のサンゴ礁体系の推定16%が死滅する原因となった。この時は通常のエルニーニョ現象における+0.25°C上昇と比較して、一時的に+1.5°Cの温度上昇が起きていた[46]。それ以来、世界規模で大量のサンゴ白化現象が普遍的となり、あらゆる水域が「重度の白化」被害にさらされている[47]。
多様性

エルニーニョ現象には複数のタイプがあり、正統的な東太平洋型それから「モドキ」な中央太平洋型の2つが最も注目され、受け入れられている[48][49][50]。これら異なるタイプのエルニーニョ現象は、熱帯太平洋の海面温度異常が最大となった場所によって分類される[50]。例えば、正統な東太平洋型での最も強い海面温度異常はその位置が南米沖合となり、モドキな中央太平洋型での最も強い異常位置は日付変更線付近である[50]。ただし、単一のエルニーニョ期間に海面温度異常が最大となる水域は変わってしまう可能性がある[50]。
東太平洋(EP)エルニーニョ[51]とも呼ばれる伝統的なエルニーニョは、東太平洋の温度異常を伴う。しかし、直近20年間で通常とは異なるエルニーニョが複数観察され、通例だと温度異常になる場所(ニーニョ監視海域1と2)は影響を受けないのに、中央太平洋(同3.4)で異常が発生している[52]。この現象は、中央太平洋(CP)エルニーニョ[51]や「日付線」エルニーニョ(国際日付変更線付近で異常が発生するため)またはエルニーニョ「モドキ」[53](「似ているけど異なる」という日本語が由来)とも呼ばれている[54][55][56][57]。
CPエルニーニョの影響は伝統的なEPエルニーニョのものとは異なる。例えば、近年発見されたエルニーニョは頻繁に上陸するより多くのハリケーンを大西洋にもたらしている[58]。
ただし、この新しいENSOの存在に異論を唱える研究も多い。実際には発生が増加していない、統計的に区別するには信頼性の高い記録が足りないとするもの[59][60]、他の統計アプローチを使うと区別や傾向が見つからないとするもの[61][62][63][64][65] 、標準的なENSOと極端なENSOといった他の種類で区別すべきとするものもある[66][67]。
中央太平洋を発端として東方向に移動したエルニーニョの最初の記録は1986年である[68]。近年の中央太平洋エルニーニョは1986-87, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2004-05 ,2009-10年に発生した[69]。さらに1957-59[70],1963-64, 1965-66, 1968-70, 1977-78,1979-80年の現象が「モドキ」だったという[71][72]。一部資料では、2014-16年のエルニーニョも中央太平洋エルニーニョだと述べている[73][74]。
地球規模の気候に及ぼす影響

エルニーニョは、地球規模の気候に影響を与えて通常の気象パターンを混乱させ、その結果ある場所では激しい嵐をもたらしたり、他の場所では干ばつをもたらす可能性がある[75][76]。
熱帯低気圧
大半の熱帯低気圧は赤道に近い亜熱帯高圧帯の側で形成され、そこから高圧軸を越えて極方向に移動したのち偏西風のメインベルトに再帰する[77]。日本の西部および韓国域では、エルニーニョおよび中立な年の9-11月に熱帯低気圧の影響を多く受ける傾向がある。エルニーニョの年には亜熱帯高圧帯の尾根が東経130°付近で居座る傾向があり、日本列島が特に影響を受けることになる[78]。
大西洋域内では、大気中の偏西風が強まることによって鉛直ウインドシアが増加し、これが熱帯低気圧の発生および発達を抑制する[79]。大西洋上空の大気もまたエルニーニョ現象の時期に乾燥かつ安定的になり、これも熱帯低気圧の発生や発達を食い止める[79]。東太平洋海盆では、エルニーニョ現象が東の鉛直ウインドシアを減らす一因となっており、平年以上にハリケーン活動を誘発してしまう[80]。ただし、この海域におけるENSOの影響は多彩であり、背景にある気候パターンに強く影響される[80]。西太平洋海盆ではエルニーニョ現象の最中に熱帯低気圧が形成される場所に変化が生じ、熱帯低気圧の形成が東へ遷移するも、毎年の発現数はさほど変わらない[79]。この変化の結果として、ミクロネシアでは熱帯低気圧の影響を受ける可能性が高まり、中国では熱帯低気圧のリスクが低下する[78]。熱帯低気圧が形成される場所の変化は南太平洋の東経135°-西経120°間でも起こり、熱帯低気圧はオーストラリア地域よりも南太平洋海盆で発生する可能性が高い[12][79]。この変化の結果、熱帯低気圧はクイーンズランド州に上陸する可能性が50%低下し、ニウエ、フランス領ポリネシア、トンガ、ツバル、クック諸島などの島国では熱帯低気圧のリスクが高まる[12][81][82]。
熱帯大西洋での影響
赤道太平洋のエルニーニョ現象が、概ね次の春夏における熱帯北大西洋の温暖と関連していることを示す気候研究がある[83]。エルニーニョ現象の約半分が春季に十分持続すると、夏に西半球の暖水域が異常に大きくなる[84]。時には、エルニーニョが南米上空の大西洋ウォーカー循環に及ぼす影響として西赤道大西洋海域では東の貿易風が強まる。その結果、冬にエルニーニョが頂点に達した後の春夏に東赤道大西洋では異常な寒冷化が起きる場合がある[85]。両方の海洋におけるエルニーニョに似た現象は、モンスーンの雨が長期間降らないことに関連した深刻な飢饉も引き起こしている[86]。
地域別の影響
1950年以降のエルニーニョ現象の観測によると、エルニーニョ現象に関連する影響は時期によって異なる[87]。ただし、エルニーニョ期間に発生する事象や影響は予想されてはいるものの確実ではなく、発生するとの保証はできない[87]。大部分のエルニーニョ現象の最中に概ね発生する影響としては、インドネシアと南米の北部で降雨量が平均を下回り、南米の南東部と東赤道アフリカと米国南部では降雨量が平均を上回る[87]。
アフリカ
アフリカでは、ケニア、タンザニア、白ナイル川の盆地を含む東アフリカで3月から5月にかけて長雨となり、平年よりも多雨になる。南中部アフリカでは、ザンビア、ジンバブエ、モザンビーク、ボツワナを中心に、12月から2月にかけて平年よりも少雨になる。
南極大陸
南極周辺の高南緯にはENSOとの様々な関連が存在する[88]。具体的には、エルニーニョの状態がアムンゼン海とベリングスハウゼン海に異常高気圧をもたらし、これらの海域ならびにロス海では海氷の減少と極に向かう熱流束の増加を引き起こす。逆にウェッデル海は、エルニーニョの最中により多くの海氷ができて寒くなる傾向がある。ラニーニャの期間ではこれと正反対の加熱および大気圧異常が起こる[89] 。この変動パターンは南極の双極子モード[90]と呼ばれるが、ENSOの影響力に対する変化が南極に偏在しているわけではない[89]。
アジア
暖水域が西太平洋やインド洋から東太平洋へと広がるにつれ、そこに雨が降って西太平洋では大規模な干ばつを引き起こし、例年では少雨となる東太平洋に降雨をもたらす。2014年2月にシンガポールは1869年の記録開始以降最も少雨となり、同月の降雨量は僅か6.3mmで気温は2月26日に35°Cにも達した。1968年と2005年もそれに次ぐ乾燥した2月で、降雨量は8.4mmだった。
オーストラリアと南太平洋
エルニーニョ現象の最中に、西太平洋からの降雨量遷移がオーストラリア全土の降雨量を減少させる場合がある[12]。大陸南部の上空では、気象体系がより移動性になって高気圧の遮断域が少なくなるため、平均気温を上回る温度が記録される可能性がある[12]。熱帯オーストラリアではインド-オーストラリアのモンスーン発生が2-6週間遅れ、結果として北部の熱帯地方では降雨量が減少することになる[12]。オーストラリア南東部ではエルニーニョ現象に続いて特にインド洋ダイポールモード現象が組み合わさると、森林火災の季節性リスクが大幅に高まる[12]。エルニーニョ現象中に、ニュージーランドでは夏季に強い偏西風が頻繁に発生する傾向があり、東海岸沿いでは例年状態よりも乾燥するリスクが高くなる[91]。ニュージーランドの西海岸では、北島の山脈と南島のサザンアルプスによるバリア効果のため例年よりも多雨になる[91]。
概ねフィジーはエルニーニョ現象中に例年よりも少雨に見舞われ、島の全土が干ばつになることもある[92]。ただし、この島国への主な影響はエルニーニョ現象が確立してから約1年後に体感するものである[92]。サモア諸島では、平均を下回る降雨量と平年より高い気温がエルニーニョ期間に記録され、島の干ばつや森林火災につながる可能性がある[93]。その他の影響としては、海面の低下、海洋環境におけるサンゴ白化の可能性、サモアに影響を与える熱帯低気圧のリスク増加などがある[93]。
欧州
ヨーロッパにおけるエルニーニョの影響は、同大陸の天候に影響を与える幾つかの要因の1つであり他の要因がこれを圧倒しうるため、議論の余地はあるものの複雑で分析は困難である[94][95]。
北米

北米では、主に気温と降水量へのエルニーニョによる影響が概ね10月から3月にかけて6か月発生する[96][97]。特にカナダの大部分は概ね例年の冬や春よりも穏やかな気候となり、同国東部を除いて重大な影響は起こらない。アメリカ合衆国では、6か月間に以下の影響が概ね観察される。テキサス州からフロリダ州までのメキシコ湾沿いでは雨量が平均を上回り、ハワイ州、オハイオ川渓谷、太平洋北西部、ロッキー山脈では少雨が観察される[96]。
歴史的にエルニーニョは、クリステンセンら(1981)[98]が長期天気予報の科学進展のため情報理論に基づく発見のエントロピーミニマックスパターンを用いるまで、米国の気象パターンに影響を与えるとは理解されていなかった。以前の天候コンピュータモデルは持続性のみに基づいたもので5-7日先にのみ信頼性があり、長期予測は本質的にランダムだった。クリステンセンらは、1年先や数年後でも降水量が平均以下になるか上回かを予測する、些少ながら統計的に有意な技法を実証した。
近年のカリフォルニア州および米国南西部の気象現象研究では、エルニーニョと平均を上回る降水量との間には同現象の強さや別要因に大きく左右される多彩な関係性あることを示している[96]。
テワン風 (Tehuantepecer) の総観状況は、テワンテペク地峡を通って風が加速する寒冷前線の発達をきっかけにメキシコのシエラマドレ・デ・オアハカ山脈で形成される高圧帯と関連がある。テワン風は主に寒冷前線をきっかけに同地域の寒冷期(10月から2月)に発生し、夏季の最大値は7月にアゾレス高気圧の西方進展によって引き起こされる。エルニーニョの冬季は寒冷前線が頻繁にやって来るため、エルニーニョの年における風の強さはラニーニャの年よりも大きい[99]。その影響は数時間から6日ほど継続することがある[100]。一部のエルニーニョ現象は植物の同位体シグネチャに記録されており、このことは科学者達がその影響を研究するのに役立った[101]。
南米
エルニーニョの暖水域は上空で雷雨を育てるため、南米西海岸の一部を含む東中部および東太平洋全体の降雨量を増加させる。南米におけるエルニーニョの影響は、北米よりも直接的かつ強大である。エルニーニョはペルー北部とエクアドルの海岸沿いで4月から10月の温暖かつ非常に多雨な気候と関連があり、同現象が強大で極端になるたび大洪水を引き起こす[102]。2月、3月、4月の影響は南米西海岸沿いで危機的になる場合がある。エルニーニョは、大型魚の個体数を維持する冷たくて栄養豊富な水の湧昇を減らしてしまうが、この魚達が(餌となって)豊富な海鳥を維持しており、その鳥の排泄物が肥料産業を支えている。湧昇の減少は、ペルー海岸沖における魚の死に繋がってしまう[103]。
影響を受ける海岸線沿いの地元の漁業は、長期的なエルニーニョ現象の最中に苦難することがある。世界最大規模の漁業は、1972年のエルニーニョの最中に起きたアンチョベータ減少時に乱獲をしたため崩壊した。1982-83年の現象中には、マアジとアンチョベータの個体数が減少し、ホタテは暖かい水で増加したが、メルルーサは大陸斜面の冷水を追いかけ、エビとイワシは南に移動したため、一部の漁獲高が減少したものの増加したものもあった[104]。エルニーニョ現象の最中にこの海域ではサバが増加する。状況の変化による魚の位置や種類の変化が、漁業の課題となっている。ペルーのイワシは、エルニーニョ現象の最中にチリの海域に移動してしまう。他にも1991年にチリ政府が自営業の漁師や産業艦隊向けの漁場に制限を設けるなど、さらに複雑な状況が生じている。
ENSOの変動性は、ペルー沿岸で成長の速い小型種が大幅に増える一因となる場合があり、これは個体数の少ない時期に同海域の捕食者がいなくなるためである。同じ影響で、捕食者の多い熱帯地域から遠方の巣地へと毎春に移動する渡り鳥には有益となる。
ブラジル南部とアルゼンチン北部もまた例年状況に比べて多雨になるが、これは主に春から初夏にかけての間である。チリ中部では降雨量が多い穏やかな冬を迎え、ペルーとボリビア間のアルティプラーノは異常な冬の降雪現象に見舞われたりもする。乾燥した暑い天候は、アマゾン川流域、コロンビア、中央アメリカの一部で発生する[105]。
チリ北部、中部では、夏場に極端な高温、低湿状態が見られる。こうした状況下で、しばしば山火事が発生し(2023年チリ山火事、2024年チリ山火事)、多くの被害が生じている[106][107]。
人類および自然への社会生態学的影響
経済効果

エルニーニョの状態が何ヶ月も続くと、広範な海洋温暖化と東の貿易風の減少が冷たい栄養豊富な深い水の湧昇を抑制し、国際市場向けの地元漁業における経済的影響が深刻になる恐れがある[103]。
一般的に、エルニーニョは様々な国の商品価格およびマクロ経済に影響を与える可能性がある。エルニーニョは雨が育む農産物の供給を抑制する可能性があり、農業生産、建設、サービス活動を削減したり、食料価格を形成してインフレーションを生じさせたり、主に輸入食品を利用するコモディティ依存の貧困国では社会不安の引き金となる場合もある[108]。ケンブリッジ大学の研究論文では、オーストラリア、チリ、インドネシア、インド、日本、ニュージーランド、南アフリカがエルニーニョ・ショックを受けて経済活動が短命に陥る一方、アルゼンチン、カナダ、メキシコ、米国など他の国々では実際のところエルニーニョ気象ショックの恩恵を(主要貿易相手国からの積極的な波及を通じて直接的または間接的に)受ける場合がある。 さらに、大部分の国々はエルニーニョ・ショック後に短期的なインフレ圧力を受け、世界のエネルギー価格と非燃料コモディティ価格が上昇してしまう[109]。IMFは、1回の大きなエルニーニョが米国のGDPを約0.5%押し上げ(主に暖房費の削減による)、インドネシアのGDPを約1.0%削減しうると推算している[110]。
健康影響や社会的影響
エルニーニョの周期に関連した極端な気象状況は、流行性疾患の発生率の変化と相関がある。例えば、エルニーニョの周期は、マラリア、デング熱、リフトバレー熱など蚊によって伝染する病気のリスク増加と関連がある[111]。インド、ベネズエラ、ブラジル、コロンビアにおけるマラリア周期は、現在エルニーニョと関連がある。別の蚊媒介性疾患であるオーストラリア脳炎(マレーバレー脳炎)のアウトブレイクは、ラニーニャ現象に関連する大雨と洪水の後、オーストラリア南東部の温帯で発生する。 1997 - 98年のエルニーニョの最中にケニア北東部とソマリア南部で極度の降雨が発生し、リフトバレー熱の深刻な突発感染が起こった[112]。
またENSOの状態が、北太平洋を横切る対流圏の風と連携したことで[113]、日本や米国西海岸における川崎病の発生率とも関連性があったとする研究もある[114]。
このほか内戦と関連している可能性もある。コロンビア大学地球研究所の科学者達は1950 - 2004年までのデータを解析し、1950年以降のあらゆる内戦の21%でENSOが何らかの役割を果たした可能性を示唆しており、エルニーニョの影響を受ける国では、ラニーニャ年に比べて内戦発生のリスクが年間3%から6%に倍増するという[115][116]。
生態学的な帰着
陸上生態系では、1972-73年エルニーニョ現象の後チリ北部およびペルー海岸の砂漠沿いでげっ歯類の突発的増殖が観測された[要出典]。一部の夜行性霊長類(ニシメガネザルとスンダスローロリス)とマレーグマ はこれらの消失した森林内で局所的に絶滅したか大幅に数が減少した。鱗翅目の突発的増殖はパナマとコスタリカで文書化された[要出典]。1982-83,1997-98,2015-16年のENSO現象では、熱帯林の大規模拡大が長期間の少雨を経験して広範囲に火災が発生し、アマゾンとボルネオの森林では森林構造と構成樹木種が劇的に変化した。ただし、2015-16年のエルニーニョ期間では極端な干ばつおよび森林火災後に昆虫個体数の減少が観察されたため、その影響は植生だけに留まらない[117]。アマゾンの焼失森林では、特殊な生息地にいたり環境の乱れに敏感な鳥類や大型哺乳類の減少も見られ、ボルネオ島の焼失した森林では100種以上の低地蝶種の一時的な消失が起こった。
最も危機的なものでは、世界規模の大量サンゴ白化現象 が1997-98年と2015-16年に記録され、生体サンゴの約75-99%に及ぶ損失が世界中で記録された。ペルーとチリのカタクチイワシ科個体数崩壊にも相当な注意が払われ、1972-73,1982-83,1997-98年そして近年では2015-16年のENSO現象後に深刻な漁業危機を引き起こした。特に1982-83年の海面温度上昇はパナマで2種のヒドロサンゴが絶滅した可能性があり、チリでは海岸線600kmに沿って昆布床が大量に死亡、これは20年経っても昆布および関連の生物多様性が最も影響を受けた海域となったが徐々に回復した。これら全ての調査結果から、エルニーニョおよびラニーニャを引き起こすENSOは世界中の生態学的変化(特に熱帯林やサンゴ礁における生態学的変化)を後押しする強大な気候力だと捉えられている[118]。
脚注
注釈
出典
- ^ 気象庁「よくある質問(エルニーニョ/ラニーニャ現象)」2021年12月30日閲覧。
- ^ 気象庁「エルニーニョ/ラニーニャ現象とは」2021年12月30日閲覧。
- ^ Changnon, Stanley A (2000). El Nino 1997-98 The Climate Event of The Century. New York: Oxford University Press. pp. 35. ISBN 0-19-513552-0
- ^ Climate Prediction Center (19 December 2005). “Frequently Asked Questions about El Niño and La Niña”. National Centers for Environmental Prediction. 27 August 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。17 July 2009閲覧。
- ^ K.E. Trenberth; P.D. Jones; P. Ambenje; R. Bojariu; D. Easterling; A. Klein Tank; D. Parker; F. Rahimzadeh et al.. “Observations: Surface and Atmospheric Climate Change”. In Solomon, S.; D. Qin; M. Manning et al.. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. The contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press. pp. 235?336
- ^ “El Nino Information”. California Department of Fish and Game, Marine Region. 2021年12月30日閲覧。
- ^ “The Strongest El Nino in Decades Is Going to Mess With Everything”. Bloomberg.com. (21 October 2015) 18 February 2017閲覧。
- ^ “How the Pacific Ocean changes weather around the world” (英語). Popular Science 19 February 2017閲覧。
- ^ Trenberth, Kevin E (December 1997). “The Definition of El Niño”. Bulletin of the American Meteorological Society 78 (12): 2771-2777. Bibcode: 1997BAMS...78.2771T. doi:10.1175/1520-0477(1997)078<2771:TDOENO>2.0.CO;2.
- ^ “Australian Climate Influences: El Nino”. Australian Bureau of Meteorology. 4 April 2016閲覧。
- ^ a b “What is the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) in a nutshell?”. ENSO Blog (5 May 2014). 9 April 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。7 April 2016閲覧。
- ^ a b c d e f g “What is El Niño and what might it mean for Australia?”. Australian Bureau of Meteorology. 18 March 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。10 April 2016閲覧。
- ^ a b “El Nino here to stay”. BBC News. (7 November 1997) 1 May 2010閲覧。
- ^ a b c d “Historical El Niño/La Niña episodes (1950-present)”. United States Climate Prediction Center (1 February 2019). 15 March 2019閲覧。
- ^ a b c “El Nino - Detailed Australian Analysis”. Australian Bureau of Meteorology. 3 April 2016閲覧。
- ^ http://www.bom.gov.au/climate/enso/images/El-Nino-in-Australia.pdf
- ^ “December's ENSO Update: Close, but no cigar”. ENSO Blog (4 December 2014). 22 March 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ “ENSO Tracker: About ENSO and the Tracker”. Australian Bureau of Meteorology. 4 April 2016閲覧。
- ^ “How will we know when an El Nino has arrived?”. ENSO Blog (27 May 2014). 22 March 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ 気象庁「エルニーニョ監視速報の構成」2021年12月30日閲覧。
- ^ “Historical El Niño and La Niña Events”. Japan Meteorological Agency. 4 April 2016閲覧。
- ^ “ENSO + Climate Change = Headache”. ENSO Blog (11 September 2014). 18 April 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ Collins, Mat; An, Soon-Il; Cai, Wenju; Ganachaud, Alexandre; Guilyardi, Eric; Jin, Fei-Fei; Jochum, Markus; Lengaigne, Matthieu et al. (23 May 2010). “The impact of global warming on the tropical Pacific Ocean and El Ni?o”. Nature Geoscience 3 (6): 391?397. Bibcode: 2010NatGe...3..391C. doi:10.1038/ngeo868.
- ^ Bourget, Steve (3 May 2016) (英語). Sacrifice, Violence, and Ideology Among the Moche: The Rise of Social Complexity in Ancient Peru. University of Texas Press. ISBN 9781477308738
- ^ Brian Donegan (14 March 2019). “El Nino Conditions Strengthen, Could Last Through Summer”. The Weather Company. 15 March 2019閲覧。
- ^ “El Nino is over, NOAA says”. Al.com (8 August 2019). 5 September 2019閲覧。
- ^ Climate Prediction Center (19 December 2005). “ENSO FAQ: How often do El Niño and La Niña typically occur?”. National Centers for Environmental Prediction. 27 August 2009時点のオリジナルよりアーカイブ。26 July 2009閲覧。
- ^ National Climatic Data Center (June 2009). “El Nino / Southern Oscillation (ENSO) June 2009”. National Oceanic and Atmospheric Administration. 26 July 2009閲覧。
- ^ Kim, WonMoo; Wenju Cai (2013). “Second peak in the far eastern Pacific sea surface temperature anomaly following strong El Nino events”. Geophys. Res. Lett. 40 (17): 4751-4755. Bibcode: 2013GeoRL..40.4751K. doi:10.1002/grl.50697.
- ^ Carrè, Matthieu et al. (2005). “Strong El Niño events during the early Holocene: stable isotope evidence from Peruvian sea shells”. The Holocene 15 (1): 42–7. Bibcode: 2005Holoc..15...42C. doi:10.1191/0959683605h1782rp.
- ^ Brian Fagan (1999). Floods, Famines and Emperors: El Nino and the Fate of Civilizations. Basic Books. pp. 119-138. ISBN 978-0-465-01120-9
- ^ Grove, Richard H. (1998). “Global Impact of the 1789-93 El Nino”. Nature 393 (6683): 318-9. Bibcode: 1998Natur.393..318G. doi:10.1038/30636.
- ^ Ó Gráda, C. (2009). “Ch. 1: The Third Horseman”. Famine: A Short History. Princeton University Press. ISBN 9780691147970. オリジナルの12 January 2016時点におけるアーカイブ。 3 March 2010閲覧。
- ^ “Dimensions of need - People and populations at risk”. Fao.org. 28 July 2015閲覧。
- ^ Carrillo, Camilo N. (1892) "Disertación sobre las corrientes oceánicas y estudios de la correinte Peruana ó de Humboldt" (Dissertation on the ocean currents and studies of the Peruvian, or Humboldt's, current), Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 2 : 72–110. [in Spanish] From p. 84: "Los marinos paiteños que navegan frecuentemente cerca de la costa y en embarcaciones pequeñas, ya al norte ó al sur de Paita, conocen esta corriente y la denomination Corriente del Niño, sin duda porque ella se hace mas visible y palpable después de la Pascua de Navidad." (The sailors [from the city of] Paita who sail often near the coast and in small boats, to the north or the south of Paita, know this current and call it "the current of the Boy [el Niño]", undoubtedly because it becomes more visible and palpable after the Christmas season.)
- ^ Lartigue (1827) (フランス語). Description de la C?te Du P?rou, Entre 19° et 16° 20' de Latitude Sud, ... [Description of the Coast of Peru, Between 19° and 16° 20' South Latitude, ...]. Paris, France: L'Imprimerie Royale. pp. 22-23 From pp. 22-23: "Il est néanmoins nécessaire, au sujet de cette règle générale, de faire part d'une exception ... dépassé le port de sa destination de plus de 2 ou 3 lieues; ... " (It is nevertheless necessary, with regard to this general rule, to announce an exception which, in some circumstances, might shorten the sailing. One said above that the breeze was sometimes quite fresh [i.e., strong], and that then the counter-current, which bore southward along the land, stretched some miles in length; it is obvious that one will have to tack in this counter-current, whenever the wind's force will permit it and whenever one will not have gone past the port of one's destination by more than 2 or 3 leagues; ...)
- ^ a b Pezet, Federico Alfonso (1896), “The Counter-Current "El Niño," on the Coast of Northern Peru”, Report of the Sixth International Geographical Congress: Held in London, 1895, Volume 6, pp. 603-606
- ^ Findlay, Alexander G. (1851). A Directory for the Navigation of the Pacific Ocean -- Part II. The Islands, Etc., of the Pacific Ocean. London: R. H. Laurie. p. 1233. "M. Lartigue is among the first who noticed a counter or southerly current."
- ^ "Droughts in Australia: Their causes, duration, and effect: The views of three government astronomers [R.L.J. Ellery, H.C. Russell, and C. Todd]," The Australasian (Melbourne, Victoria), 29 December 1888, pp. 1455?1456. From p. 1456: Archived 16 September 2017 at the Wayback Machine. "Australian and Indian Weather" : "Comparing our records with those of India, I find a close correspondence or similarity of seasons with regard to the prevalence of drought, and there can be little or no doubt that severe droughts occur as a rule simultaneously over the two countries."
- ^ Lockyer, N. and Lockyer, W.J.S. (1904) "The behavior of the short-period atmospheric pressure variation over the Earth's surface," Proceedings of the Royal Society of London, 73 : 457-470.
- ^ Eguiguren, D. Victor (1894) "Las lluvias de Piura" (The rains of Piura), Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 4 : 241-258. [in Spanish] From p. 257: "Finalmente, la época en que se presenta la corriente de Niño, es la misma de las lluvias en aquella región." (Finally, the period in which the El Niño current is present is the same as that of the rains in that region [i.e., the city of Piura, Peru].)
- ^ Pezet, Federico Alfonso (1896) "La contra-corriente "El Niño", en la costa norte de Perú" (The counter-current "El Niño", on the northern coast of Peru), Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, 5 : 457-461. [in Spanish]
- ^ Walker, G. T. (1924) "Correlation in seasonal variations of weather. IX. A further study of world weather," Memoirs of the Indian Meteorological Department, 24 : 275-332. From p. 283: "There is also a slight tendency two quarters later towards an increase of pressure in S. America and of Peninsula [i.e., Indian] rainfall, and a decrease of pressure in Australia : this is part of the main oscillation described in the previous paper* which will in future be called the 'southern' oscillation." Available at: Royal Meteorological Society Archived 18 March 2017 at the Wayback Machine.
- ^ “Who Discovered the El Nino-Southern Oscillation?”. Presidential Symposium on the History of the Atmospheric Sciences: People, Discoveries, and Technologies. American Meteorological Society (AMS). 1 December 2015時点のオリジナルよりアーカイブ。18 December 2015閲覧。
- ^ Trenberth, Kevin E.; Hoar, Timothy J. (January 1996). “The 1990-95 El Niño-Southern Oscillation event: Longest on record”. Geophysical Research Letters 23 (1): 57-60. Bibcode: 1996GeoRL..23...57T. doi:10.1029/95GL03602.
- ^ Trenberth, K. E. et al. (2002). “Evolution of El Niño - Southern Oscillation and global atmospheric surface temperatures”. Journal of Geophysical Research 107 (D8): 4065. Bibcode: 2002JGRD..107.4065T. doi:10.1029/2000JD000298.
- ^ Marshall, Paul; Schuttenberg, Heidi (2006). A reef manager's guide to coral bleaching. Townsville, Qld.: Great Barrier Reef Marine Park Authority. ISBN 978-1-876945-40-4
- ^ Trenberth, Kevin E; Stepaniak, David P (April 2001). “Indices of El Nino Evolution”. Journal of Climate 14 (8): 1697-1701. Bibcode: 2001JCli...14.1697T. doi:10.1175/1520-0442(2001)014<1697:LIOENO>2.0.CO;2.
- ^ Johnson, Nathaniel C (July 2013). “How Many ENSO Flavors Can We Distinguish?*”. Journal of Climate 26 (13): 4816-4827. Bibcode: 2013JCli...26.4816J. doi:10.1175/JCLI-D-12-00649.1.
- ^ a b c d “ENSO Flavor of the Month”. ENSO Blog (16 October 2014). 24 April 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ a b Kao, Hsun-Ying; Jin-Yi Yu (2009). “Contrasting Eastern-Pacific and Central-Pacific Types of ENSO”. J. Climate 22 (3): 615-632. Bibcode: 2009JCli...22..615K. doi:10.1175/2008JCLI2309.1.
- ^ Larkin, N. K.; Harrison, D. E. (2005). “On the definition of El Nino and associated seasonal average U.S. Weather anomalies”. Geophysical Research Letters 32 (13): L13705. Bibcode: 2005GeoRL..3213705L. doi:10.1029/2005GL022738.
- ^ 山形俊男「エルニーニョモドキ (新用語解説)」『天気』日本気象学会、2011年3月、48-50頁
- ^ Ashok, K.; S. K. Behera; S. A. Rao; H. Weng & T. Yamagata (2007). “El Nino Modoki and its possible teleconnection”. Journal of Geophysical Research 112 (C11): C11007. Bibcode: 2007JGRC..11211007A. doi:10.1029/2006JC003798.
- ^ Weng, H.; K. Ashok; S. K. Behera; S. A. Rao & T. Yamagata (2007). “Impacts of recent El Nino Modoki on dry/wet condidions in the Pacific rim during boreal summer”. Clim. Dyn. 29 (2?3): 113?129. Bibcode: 2007ClDy...29..113W. doi:10.1007/s00382-007-0234-0.
- ^ Ashok, K.; T. Yamagata (2009). “The El Nino with a difference”. Nature 461 (7263): 481-484. Bibcode: 2009Natur.461..481A. doi:10.1038/461481a. PMID 19779440.
- ^ Michele Marra (1 January 2002). Modern Japanese Aesthetics: A Reader. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-2077-0
- ^ Hye-Mi Kim; Peter J. Webster; Judith A. Curry (2009). “Impact of Shifting Patterns of Pacific Ocean Warming on North Atlantic Tropical Cyclones”. Science 325 (5936): 77-80. Bibcode: 2009Sci...325...77K. doi:10.1126/science.1174062. PMID 19574388.
- ^ Nicholls, N. (2008). “Recent trends in the seasonal and temporal behaviour of the El Nino Southern Oscillation”. Geophys. Res. Lett. 35 (19): L19703. Bibcode: 2008GeoRL..3519703N. doi:10.1029/2008GL034499.
- ^ McPhaden, M.J.; Lee, T.; McClurg, D. (2011). “El Nino and its relationship to changing background conditions in the tropical Pacific Ocean”. Geophys. Res. Lett. 38 (15): L15709. Bibcode: 2011GeoRL..3815709M. doi:10.1029/2011GL048275.
- ^ Giese, B.S.; Ray, S. (2011). “El Nino variability in simple ocean data assimilation (SODA), 1871?2008”. J. Geophys. Res. 116 (C2): C02024. Bibcode: 2011JGRC..116.2024G. doi:10.1029/2010JC006695.
- ^ Newman, M.; Shin, S.-I.; Alexander, M.A. (2011). “Natural variation in ENSO flavors”. Geophys. Res. Lett. 38 (14): L14705. Bibcode: 2011GeoRL..3814705N. doi:10.1029/2011GL047658.
- ^ Yeh, S.-W.; Kirtman, B.P.; Kug, J.-S.; Park, W.; Latif, M. (2011). “Natural variability of the central Pacific El Nino event on multi-centennial timescales”. Geophys. Res. Lett. 38 (2): L02704. Bibcode: 2011GeoRL..38.2704Y. doi:10.1029/2010GL045886.
- ^ Hanna Na; Bong-Geun Jang; Won-Moon Choi; Kwang-Yul Kim (2011). “Statistical simulations of the future 50-year statistics of cold-tongue El Nino and warm-pool El Nino”. Asia-Pacific J. Atmos. Sci. 47 (3): 223-233. Bibcode: 2011APJAS..47..223N. doi:10.1007/s13143-011-0011-1.
- ^ L'Heureux, M.; Collins, D.; Hu, Z.-Z. (2012). “Linear trends in sea surface temperature of the tropical Pacific Ocean and implications for the El Nino-Southern Oscillation”. Climate Dynamics 40 (5-6): 1-14. Bibcode: 2013ClDy...40.1223L. doi:10.1007/s00382-012-1331-2.
- ^ Lengaigne, M.; Vecchi, G. (2010). “Contrasting the termination of moderate and extreme El Niño events in coupled general circulation models”. Climate Dynamics 35 (2-3): 299-313. Bibcode: 2010ClDy...35..299L. doi:10.1007/s00382-009-0562-3.
- ^ Takahashi, K.; Montecinos, A.; Goubanova, K.; Dewitte, B. (2011). “ENSO regimes: Reinterpreting the canonical and Modoki El Niño”. Geophys. Res. Lett. 38 (10): L10704. Bibcode: 2011GeoRL..3810704T. doi:10.1029/2011GL047364. hdl:10533/132105.
- ^ S. George Philander (2004). Our Affair with El Nino: How We Transformed an Enchanting Peruvian Current Into a Global Climate Hazard. ISBN 978-0-691-11335-7
- ^ “Study Finds El Ninos are Growing Stronger”. NASA. 3 August 2014閲覧。
- ^ Takahashi, K.; Montecinos, A.; Goubanova, K.; Dewitte, B. (2011). “Reinterpreting the Canonical and Modoki El Nino”. Geophysical Research Letters 38 (10): n/a. Bibcode: 2011GeoRL..3810704T. doi:10.1029/2011GL047364. hdl:10533/132105.
- ^ Different Impacts of Various El Nino Events (PDF) (Report). NOAA.
- ^ Central Pacific El Nino on US Winters (Report). IOP Science. 2014年8月3日閲覧。.
- ^ Monitoring the Pendulum (Report). IOP Science. doi:10.1088/1748-9326/aac53f。
- ^ “El Nino's Bark is Worse than its Bite”. The Western Producer 11 January 2019閲覧。
- ^ “El Niño and La Niña”. New Zealand's National Institute of Water and Atmospheric Research (27 February 2007). 19 March 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。11 April 2016閲覧。
- ^ Emily Becker (2016). “How Much Do El Niño and La Niña Affect Our Weather? This fickle and influential climate pattern often gets blamed for extreme weather. A closer look at the most recent cycle shows that the truth is more subtle”. Scientific American 315 (4): 68-75. doi:10.1038/scientificamerican1016-68. PMID 27798565.
- ^ Joint Typhoon Warning Center (2006年). “3.3 JTWC Forecasting Philosophies”. 11 February 2007閲覧。
- ^ a b Wu, M. C.; Chang, W. L.; Leung, W. M. (2004). “Impacts of El Nino-Southern Oscillation Events on Tropical Cyclone Landfalling Activity in the Western North Pacific”. Journal of Climate 17 (6): 1419-28. Bibcode: 2004JCli...17.1419W. doi:10.1175/1520-0442(2004)017<1419:ioenoe>2.0.co;2.
- ^ a b c d Landsea, Christopher W; Dorst, Neal M (1 June 2014). “Subject: G2) How does El Nino-Southern Oscillation affect tropical cyclone activity around the globe?”. Tropical Cyclone Frequently Asked Question. United States National Oceanic and Atmospheric Administration's Hurricane Research Division. オリジナルの9 October 2014時点におけるアーカイブ。
- ^ a b “Background Information: East Pacific Hurricane Outlook”. United States Climate Prediction Center (27 May 2015). 7 April 2016閲覧。
- ^ "Southwest Pacific Tropical Cyclone Outlook: El Niño expected to produce severe tropical storms in the Southwest Pacific" (Press release). New Zealand National Institute of Water and Atmospheric Research. 14 October 2015. 2015年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年10月22日閲覧。
- ^ "El Nino is here!" (Press release). Tonga Ministry of Information and Communications. 11 November 2015. 2017年10月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月8日閲覧。
- ^ Enfield, David B.; Mayer, Dennis A. (1997). “Tropical Atlantic sea surface temperature variability and its relation to El Ni?o-Southern Oscillation”. Journal of Geophysical Research 102 (C1): 929?945. Bibcode: 1997JGR...102..929E. doi:10.1029/96JC03296.
- ^ Lee, Sang-Ki; Chunzai Wang (2008). “Why do some El Ni?os have no impact on tropical North Atlantic SST?”. Geophysical Research Letters 35 (L16705): L16705. Bibcode: 2008GeoRL..3516705L. doi:10.1029/2008GL034734.
- ^ Latif, M.; Grötzner, A. (2000). “The equatorial Atlantic oscillation and its response to ENSO”. Climate Dynamics 16 (2-3): 213-218. Bibcode: 2000ClDy...16..213L. doi:10.1007/s003820050014.
- ^ Davis, Mike (2001). Late Victorian Holocausts: El Niño Famines and the Making of the Third World. London: Verso. p. 271. ISBN 978-1-85984-739-8
- ^ a b c “How ENSO leads to a cascade of global impacts”. ENSO Blog (19 May 2014). 26 May 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ Turner, John (2004). “The El Ni?o-Southern Oscillation and Antarctica”. International Journal of Climatology 24 (1): 1-31. Bibcode: 2004IJCli..24....1T. doi:10.1002/joc.965.
- ^ a b Yuan, Xiaojun (2004). “ENSO-related impacts on Antarctic sea ice: a synthesis of phenomenon and mechanisms”. Antarctic Science 16 (4): 415-425. Bibcode: 2004AntSc..16..415Y. doi:10.1017/S0954102004002238.
- ^ 気象庁「気候現象及びそれらの将来の地域的な気候変動との関連性」『IPCC第5次評価報告書』14章、56頁。
- ^ a b “El Niño's impacts on New Zealand's climate”. New Zealand's National Institute of Water and Atmospheric Research (19 October 2015). 19 March 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。11 April 2016閲覧。
- ^ a b “ENSO Update, Weak La Nina Conditions Favoured”. Fiji Meteorological Service. 7 November 2017時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ a b “Climate Summary January 2016”. Samoa Meteorology Division, Ministry of Natural Resources and Environment (January 2016). 2021年5月2日閲覧。
- ^ “What are the prospects for the weather in the coming winter?”. Met Office News Blog. United Kingdom Met Office (29 October 2015). 20 April 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ Ineson, S.; Scaife, A. A. (7 December 2008). “The role of the stratosphere in the European climate response to El Niño”. Nature Geoscience 2 (1): 32-36. Bibcode: 2009NatGe...2...32I. doi:10.1038/ngeo381.
- ^ a b c “United States El Nino Impacts”. ENSO Blog (12 June 2014). 26 May 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ “With El Nino likely, what climate impacts are favored for this summer?”. ENSO Blog (12 June 2014). 30 March 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年12月30日閲覧。
- ^ Ronald A. Christensen and Richard F. Eilbert and Orley H. Lindgren and Laurel L. Rans (1981). “Successful Hydrologic Forecasting for California Using an Information Theoretic Model”. Journal of Applied Meteorology 20 (6): 706-712. Bibcode: 1981JApMe...20.706C. doi:10.1175/1520-0450(1981)020<0706:SHFFCU>2.0.CO;2.
- ^ Rosario Romero-Centeno; Jorge Zavala-Hidalgo; Artemio Gallegos; James J. O'Brien (August 2003). “Isthmus of Tehuantepec wind climatology and ENSO signal”. Journal of Climate 16 (15): 2628-2639. Bibcode: 2003JCli...16.2628R. doi:10.1175/1520-0442(2003)016<2628:IOTWCA>2.0.CO;2.
- ^ Paul A. Arnerich. “Tehuantepecer Winds of the West Coast of Mexico”. Mariners Weather Log 15 (2): 63-67.
- ^ Martínez-Ballesté, Andrea; Ezcurra, Exequiel (2018). “Reconstruction of past climatic events using oxygen isotopes in Washingtonia robusta growing in three anthropic oases in Baja California”. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 70 (1): 79-94. doi:10.18268/BSGM2018v70n1a5.
- ^ “Atmospheric Consequences of El Nino”. University of Illinois. 31 May 2010閲覧。
- ^ a b WW2010 (28 April 1998). “El Nino”. University of Illinois at Urbana-Champaign. 17 July 2009閲覧。
- ^ Pearcy, W. G.; Schoener, A. (1987). “Changes in the marine biota coincident with the 1982-83 El Nino in the northeastern subarctic Pacific Ocean”. Journal of Geophysical Research 92 (C13): 14417-28. Bibcode: 1987JGR....9214417P. doi:10.1029/JC092iC13p14417.
- ^ Sharma, P. D.; P.D, Sharma (2012) (英語). Ecology And Environment. Rastogi Publications. ISBN 978-81-7133-905-1
- ^ “チリで森林火災、56人死亡 気温上昇で消火困難に”. 日本経済新聞 (2024年2月4日). 2024年5月27日閲覧。
- ^ “南米・チリ、大規模森林火災 少なくとも122人死亡 人為的な可能も”. 日テレニュース (2024年2月6日). 2024年5月27日閲覧。
- ^ “Study reveals economic impact of El Nino”. University of Cambridge (11 July 2014). 25 July 2014閲覧。
- ^ Cashin, Paul; Mohaddes, Kamiar & Raissi, Mehdi (2014). “Fair Weather or Foul? The Macroeconomic Effects of El Nino”. Cambridge Working Papers in Economics. オリジナルの28 July 2014時点におけるアーカイブ。.
- ^ “Fair Weather or Foul? The Macroeconomic Effects of El Nino”. 2021年12月30日閲覧。
- ^ “El Nino and its health impact”. allcountries.org. 10 October 2017閲覧。
- ^ “El Nino and its health impact”. Health Topics A to Z. 1 January 2011閲覧。
- ^ Rodó, Xavier; Joan Ballester; Dan Cayan; Marian E. Melish; Yoshikazu Nakamura; Ritei Uehara; Jane C. Burns (10 November 2011). “Association of Kawasaki disease with tropospheric wind patterns”. Scientific Reports 1: 152. Bibcode: 2011NatSR...1E.152R. doi:10.1038/srep00152. ISSN 2045-2322. PMC 3240972. PMID 22355668.
- ^ Ballester, Joan; Jane C. Burns; Dan Cayan; Yosikazu Nakamura; Ritei Uehara; Xavier Rodó (2013). “Kawasaki disease and ENSO-driven wind circulation”. Geophysical Research Letters 40 (10): 2284-2289. Bibcode: 2013GeoRL..40.2284B. doi:10.1002/grl.50388.
- ^ Hsiang, S. M.; Meng, K. C.; Cane, M. A. (2011). “Civil conflicts are associated with the global climate”. Nature 476 (7361): 438?441. Bibcode: 2011Natur.476..438H. doi:10.1038/nature10311. PMID 21866157.
- ^ Quirin Schiermeier (2011). “Climate cycles drive civil war”. Nature 476: 406?407. doi:10.1038/news.2011.501.
- ^ França, Filipe; Ferreira, J; Vaz-de-Mello, FZ; Maia, LF; Berenguer, E; Palmeira, A; Fadini, R; Louzada, J et al. (10 February 2020). “El Niño impacts on human-modified tropical forests: Consequences for dung beetle diversity and associated ecological processes”. Biotropica 52 (1): 252-262. doi:10.1111/btp.12756.
- ^ França, FM; Benkwitt, CE; Peralta, G; Robinson, JPW; Graham, NAJ; Tylianakis, JM; Berenguer, E; Lees, AC et al. (2020). “Climatic and local stressor interactions threaten tropical forests and coral reefs”. Philosophical Transactions of the Royal Society B 375 (1794): 20190116. doi:10.1098/rstb.2019.0116. PMC 7017775. PMID 31983328.
関連項目
- エルニーニョ・南方振動
- エルニーニョ監視速報
- 気候サイクル
- 海洋物理学
外部リンク
- 気象庁「エルニーニョ/ラニーニャ現象」
- “Current map of sea surface temperature anomalies in the Pacific Ocean”. earth.nullschool.net. 2021年12月30日閲覧。
- “Southern Oscillation diagnostic discussion”. United States National Oceanographic and Atmospheric Administration. 2021年12月30日閲覧。
エルニーニョ・南方振動
(エルニーニョ から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/08 08:34 UTC 版)

エルニーニョ・南方振動(エルニーニョ・なんぽうしんどう、英語: El Niño-Southern Oscillation、ENSO、エンソ)とは、大気ではインドネシア付近と南太平洋東部で海面の気圧がシーソーのように連動して変化し(片方の気圧が平年より高いと、もう片方が低くなる傾向にある)、海洋では赤道太平洋の海面水温や海流などが変動する、各々の相が数か月から数十か月の持続期間を持つ地球規模での自然現象の総称である。
大気に着目した場合には「南方振動」、海洋に着目した場合には「エルニーニョ現象」と呼ぶことができる[1]。エルニーニョ現象と南方振動は当初は別々に議論されていたが、研究が進むにつれて両者が強く関係していることが明らかになり、「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」という言葉が生まれた。ENSOは、大気と海洋が密接に連動した現象(大気海洋相互作用)の代表であるとともに、それが世界的な天候変化に波及するテレコネクションの代表でもある。
現在学術的には、この一連の変動現象を「エルニーニョ・南方振動(ENSO)」とし、その振れ幅の両端にあたるのが、太平洋赤道域東部の海水温が上昇する「エルニーニョ現象」、およびその正反対で太平洋赤道域東部の海水温が低下する「ラニーニャ現象」、とする考え方が一般的である。
概要




エルニーニョ
エルニーニョ現象(スペイン語: El Niño event)とは、中部・東部太平洋の赤道付近において海水温が1年以上にわたって上昇する現象のことである[2]。
「エルニーニョ(El Niño)」というのはもともと、南米のペルーとエクアドルの国境付近の海域で毎年12月頃に発生する海水温の上昇現象を指していた[3]。地元の漁業民の間では、この時期がちょうどクリスマスの頃であることから、スペイン語で神の御子イエス・キリストを意味する「エルニーニョ(El Niño)」と呼ばれた[3]。この海域では通常は寒流ペルー海流の影響で海水温が低いものの、クリスマスの時季では暖流赤道反流の南下の影響で海水温が上昇している[4]。
1950年代以降になると、数年に一度、この海水温の上昇現象が3月以降も継続し、かつ太平洋の広範囲に影響を及ぼすことが判明した[3]。これを「エルニーニョ現象(El Niño event)」とよぶ[4]。
太平洋では通常貿易風(東風)が吹いており、これにより赤道上で暖められた海水が太平洋西部に寄せられるが、代わって太平洋東部には冷たい海水が湧き上がり、これを湧昇流という[5]。エルニーニョが発生するとこの暖かい海水を押し流す貿易風が弱まり、暖かい海水が東太平洋に戻るようになり、海水温度が上がる[6]。
エルニーニョ現象が発生した際には、東太平洋赤道域の海水温が平年に比べて1 - 2°C前後上昇する。時に大幅な上昇を示すこともあり、1997年 - 1998年にかけて発生した20世紀最大規模のエルニーニョでは、エルニーニョ監視海域において最大で3.6°C上昇した[7]。
エルニーニョに伴う海水温の変化はまずその海域の大気の温度に影響を及ぼし、それが気圧変化となって現れ大気の流れを変えて、天候を変えてという具合にして世界中に波及する。大気と海洋が密接に関連して発生する現象を大気・海洋相互作用[8]、ある地点の気圧や温度などが遠隔地間で協調しながら変化する現象をテレコネクションという[9]。
具体的には海水温の「西低東高」が気温の「西低東高」、さらには気圧の「西高東低」を引き起こすことでウォーカー循環と呼ばれる従来の赤道付近の大気の循環を変化させてしまう。これがロスビー波の伝播、赤道偏東風ジェット気流や亜熱帯ジェット気流(Js)の流路変化などによってドミノ式に低緯度・中緯度・高緯度へと波及し特有の気圧の変動を起こす。気圧の変化は湿・乾・暖・寒さまざまな性質を持った各地の大気の流れを変化させ、通常とは異なる大気の流れによって異常気象が起こる。
中緯度の日本においても夏は梅雨が長引き冷夏、冬は西高東低の気圧配置が安定せず暖冬となる傾向がある。
エルニーニョ現象の過程
- 何らかの原因(波動伝播、西風バーストなど)で、太平洋を流れる赤道海流が弱まる。
- 海流が弱まったせいで暖水が西太平洋へ集まるスピードが弱まり、西太平洋で暖水域が広がり中部太平洋にまで暖水が広がる。
- 海水温上昇により中部太平洋の気圧が下がり、西風バーストの強化・東進が促される。
- 暖水が東太平洋にまで広がり東部赤道域の海面水温が低下し、それに対応して東太平洋の気圧が下がる。
- 西太平洋に向かう貿易風が弱まるなどして気圧の変化が世界中に波及し、異常気象を発生させる。
- 何らかの原因(赤道波の伝播、暖水の南北移動など)で太平洋を流れる赤道海流が強まり、海水温が平常の状態に戻る。
- 平常状態となった、気圧変化が世界中に波及し、異常気象も収まる。
ラニーニャ
ラニーニャ現象(スペイン語: La Niña)は、エルニーニョ現象と逆に東太平洋の赤道付近で海水温が低下する現象。
ラニーニャはスペイン語で「女の子」の意味である[10]。「エルニーニョ(El Niño)」の反対ということで「アンチエルニーニョ(Anti-El Niño)」と呼ばれていたこともあるが「反キリスト者」の意味にもとれるため、男の子の反対で「女の子(La Niña)」と呼ばれるようになった。
東太平洋赤道域は平年でも、同じ赤道域の西太平洋や大西洋などに比べて海水温は低い。ラニーニャの時は、東太平洋赤道域で冷たい海水の湧昇が強くなって水温が低下するとともに、サーモクライン(水温躍層)の浅い冷水海域が赤道に沿って西に拡大し、東西の温度差がさらに大きくなる。
エルニーニョと同様に、世界中に波及して異常気象の原因となる。その性質上、エルニーニョ時と正反対の異常気象になる場合がある。例えば、エルニーニョで大雨となるアマゾンではラニーニャの時は少雨・干ばつとなる。これは発生域である太平洋赤道域では顕著だが、そのほかの地域では当てはまらない場合も多い。エルニーニョが終息した反動で発生するケースもある。
エルニーニョとラニーニャは表と裏の関係はあるものの、いくつかの違いがある。それは以下の通りである。
- 力学的なメカニズムにより、ラニーニャによる海水温の低下はエルニーニョによる海水温の上昇ほど強くならない。
- エルニーニョの次の年にはラニーニャが現れることが多いのに対し、ラニーニャは長期に渡って(2 - 3年)持続することが多い。
総論
エルニーニョ現象とラニーニャ現象はお互いにコインの表と裏のような密接な関係にあり、切り離して考えることはできない現象である。この海域の海水温や気圧の変動に関する研究が進むにつれ、エルニーニョやラニーニャは海洋と大気の相互作用によって起こることが明らかにされた。相互作用とは、太平洋の赤道付近の大気や海洋にはエルニーニョ・南方振動(ENSO)と呼ばれる一種の連動システムがあるとする考え方で、エルニーニョやラニーニャは常に変動を繰り返しているこのシステムの中で起こる現象とされる。
エルニーニョ・ラニーニャそれぞれの発生例を見ると、近年はそれぞれ約4年ごとに発生し、一度発生すると1年から1年半持続している。エルニーニョとラニーニャは交互に発生することが多い。ただし間隔を置いて発生したり、続けて2度以上発生したりすることもある。交互に発生するメカニズムとして、1980年代後半以降に遅延振動子理論(delayed-action oscillator theory)などの仮説がいくつか提案され観測データ解析などによって検証が行われている。
エルニーニョ・ラニーニャ現象の世界共通の定義はなく、各気象機関などが定めた複数の定義が存在する。その中でも、日本の気象庁と米国海洋大気局の定義が各国の研究者で学術的に広く使われている。
ちなみにエルニーニョやラニーニャが発生していない平常時の状態を「何も無い」という意味のスペイン語、ラナーダ(La Nada)と表現することもある。ただし、これはスペイン語圏においてもほとんど使われておらず、日本でも耳にすることは多くない。
エルニーニョ・ラニーニャは、数週間から数か月先の天候を予測する長期予報において大きな撹乱原因となる。猛暑の予想にもかかわらず一転して冷夏となるといった大きな予想の外れを生む原因であるため、この予測は予報精度の向上に不可欠であるとされる。
発生の根本的な原因
海水温や気圧の異常を引き起こす根本的な原因を突き止めようと研究が行われているが、根本的な原因は未だに詳しく解明されていない。しかし、一部分については解明されてきている。
まずエルニーニョの場合、海水温の異常が発生する数か月前に東から西に流れる赤道海流(北赤道海流と南赤道海流)が弱まったり反転したりする現象が観測されている。これは、何らかの原因によって海流に変化が起きたことによるものと考えられている。また反転の後、西太平洋の低緯度地方(フィリピン付近など)で急激に西風が強まる現象(西風バースト)が観測されたことがあるがこれは赤道海流の変化によって海水温が変化し、これが大気に伝わり気圧の変動を起こしていく過程で発生するものと考えられている。しかし、赤道海流と西風バーストはどちらが原因でどちらが結果であると断定できるものではない。これは両者が海洋大気相互作用現象で密接に関係しているためであり、解明が非常に困難である。
また最近の研究によれば、月の潮汐力の変化と関連があるのではないかとの指摘がなされている[11]。これは月の潮汐力が熱塩循環にも影響を与えるためではないかと言われている[12][13][14]。モデル等においてもENSOやそれに伴う気象変化を高精度で再現して原因を究明する動きがあるが、いずれにしても根本的な原因は確定していないのが現状である。
他方、地球温暖化とエルニーニョ・ラニーニャの関連性については科学的にも社会的にも関心は高い。気候モデルによるIPCCの予測、気象庁[15]をはじめとした各研究機関の予測のいずれにおいても、平均的に太平洋赤道域東部の海水温はわずかに上昇し、エルニーニョのような海水温異常が強まるという予測が多い。また一般的な認識においても、地球温暖化によってエルニーニョが増えたり強まったりするという考えが多い。ただ、気候モデルによる予測では「エルニーニョが強まる・増えるだろう」という大体のことは分かっても「強まる・増える」と断定できるほど確実なレベルには達していない。エルニーニョの原因がはっきりと解明されていないことや(解像度が低いため)モデルが再現できない小規模な気象がまだあるということ、エルニーニョなどの現象に対してモデルの再現性がまだよくないことなどが原因として挙げられている。また研究者の間でも、過去数十年間の太平洋赤道域東部の海水温の変化傾向は地球温暖化が関係しているという意見と自然変動であるという意見に分かれている[16]。結論として、今の段階ではモデルの予測に基づいても「エルニーニョが強まる・増える」とは断定できず地球温暖化との関連については「関連している可能性がある」程度にとどまっている。
なお「エルニーニョは地球温暖化によって起こる」という考えも見受けられるが、推測の域を出ない。
一方、「地球温暖化は(人間の活動ではなく)主にエルニーニョによって起こる」という主張は誤りである[17][18]。
過去のエルニーニョ/ラニーニャ
 |
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年1月)
|
| 期間 | El/La | 天候異常の例 |
|---|---|---|
| 1949年夏 - 1950年夏 | ラニーニャ | |
| 1951年春 - 1951/1952年冬 | エルニーニョ | |
| 1953年春 - 1953/1954年冬 1953年の夏は冷夏であり、1954年の冬は北海道を除き暖冬、南鳥島では真夏日寸前だった。 |
||
| 1954年春 - 1955/1956年冬 | ラニーニャ | 日本で冷夏(1954年の夏は8月を除いて1993年を超える大規模な大冷夏)。ただし、1955年は猛暑で、1950年代では高温な夏、秋は寒秋。1956年は全国的(特に東日本や北日本)に冷夏で秋は北日本を除いて寒秋 |
| 1957年春 - 1958年春 | エルニーニョ | 北・東日本を中心とした暖冬。 |
| 1962年冬 - 1963年春 | ラニーニャ | 北米、欧州、日本を含む東アジアで大寒波(特に日本では記録的な豪雪(昭和38年豪雪)) |
| 1963年夏 - 1963/1964年冬 | エルニーニョ | |
| 1964年春 - 1964/1965年冬 | ラニーニャ | |
| 1965年春 - 1965/1966年冬 | エルニーニョ 1966年の冬全体では並冬だったが、2月のみ暖冬 |
|
| 1967年秋 - 1968年春 | ラニーニャ | |
| 1968年秋 - 1969/1970年冬 | エルニーニョ 1969年は、暖冬冷夏であったが、1970年冬は寒冬だった。 |
|
| 1970年春 - 1971/1972年冬 | ラニーニャ | 夏は冷夏、1972年の冬は暖冬だった。 |
| 1972年春 - 1973年春 | エルニーニョ | 秋は並秋で、冬は前年同様暖冬だった。 |
| 1973年夏 - 1974年春 | ラニーニャ 1973年の夏は奄美沖縄を除いて高温傾向だったが6月は梅雨寒であった。 |
|
| 1975年春 - 1976年春 | ||
| 1976年夏 - 1977年春 | エルニーニョ | 日本で夏は大冷夏だが、冬は大寒冬 1977年2月に沖縄県で霙を観測 |
| 1982年春 - 1983年夏 | 日本で春は暖春・夏は冷夏(1983年の8月〈ただし関東以北は除外〉を除く)、秋は暖秋(11月のみ)、冬は並冬。 | |
| 1983年秋 - 1984年春 | ラニーニャ | 日本で寒冬・寒春(この寒さは1984年の5月上旬まで続いた) |
| 1984年夏 - 1985年秋 | 12月下旬から1月を中心とする寒冬 | |
| 1986年秋 - 1987/1988年冬 | エルニーニョ | 北日本を除く全国で暖冬・少雪 |
| 1988年春 - 1989年春 | ラニーニャ | 夏は冷夏、冬は大暖冬で全国的に記録的な少雪 |
| 1991年春 - 1992年夏 | エルニーニョ | 日本で暖冬・猛暑。ただし、1992年は暖冬・冷夏 |
| 1993年夏 - 1993/1994年冬 | 日本で大冷夏(この時、日本の稲作はほとんどの地域で不作となった(1993年米騒動))・暖冬あるいは並冬 | |
| 1995年夏 - 1996年冬 | ラニーニャ | 日本で1994年に過去最高・観測史上1位の猛暑・暖秋(奄美沖縄除く)。1996年は北海道を除く寒冬・寒春 |
| 1997年春 - 1998年春 | エルニーニョ | 奄美沖縄は超暖冬、東日本、西日本で大暖冬、北海道で寒冬、欧州東部で洪水、北米で豪雨、東南アジアで少雨、全世界で高温 |
| 1998年夏 - 2000年春 | ラニーニャ | 暖冬(北日本のみ並冬)、1999年の東日本 - 北日本で猛暑と暖秋、中国で旱魃、インドネシアで大雨、欧州で寒波 |
| 2002年夏 - 2002/2003年冬 | エルニーニョ | 東・東南アジア・欧州で大雨、インドで低温、インド・豪東部で干ばつ、北日本で寒冬、東・西日本で平冬、南西諸島で暖冬 |
| 2005年秋 - 2006年春 | ラニーニャ | パキスタン・インド・モンゴルで少雨、欧州・東アジアで低温・寒波、北米で多雨、日本で大寒波(2月後半除く)・大豪雪(平成18年豪雪) |
| 2006年夏 - 2007年春 | エルニーニョ | (5か月間NINO.3の基準値を0.5°C以上上回った)豪で干ばつ、ボリビア・ペルー・東アフリカで洪水、日本で1949年と並ぶ大暖冬 |
| 2007年春 - 2008年春 | ラニーニャ | 西日本 - 北日本の日本海側で8月を中心に猛暑・暖秋・寒波、北米で干ばつ、中国で大雪、欧州で寒波、2008年の冬は並冬、2月のみ寒冬 |
| 2009年夏 - 2010年春 | エルニーニョ | アジア全土で多雨、西日本で長期的な豪雨(平成21年7月中国・九州北部豪雨、平成21年台風第8号、平成21年台風第9号)、夏は南西諸島で猛暑の他は平年並みか冷夏。9月は北・東日本で寒秋。欧州・北米・中国・韓国・インドで記録的な大寒波。日本では全国的な平均気温は高く気象庁は暖冬だったと発表したが、西日本 - 北日本で一時的に強い寒波、北日本では寒春など寒暖差が大きかった。一方冬季オリンピックが開催されたバンクーバーではサクラが咲いていた。 |
| 2010年夏 - 2011年春 | ラニーニャ | 21世紀日本で観測史上1位の猛暑、9月を中心とした暖秋。熱中症による死亡多数。 |
| 2011年秋 - 2012年冬 | 秋は全国的に記録的暖秋、冬は奄美沖縄を除けば1984年のような大寒冬 | |
| 2014年夏 - 2016年春 | エルニーニョ | 2014年の夏は西日本を中心に冷夏。8月を中心とした集中豪雨が発生した。秋は西日本 - 北日本で平年並み、および12月 - 翌年(2015年)の1月上旬までを中心とした寒波 スリランカで長期的な大雨 2015年夏は南西諸島を除き6月のみ冷夏、7月後半から8月上旬は記録的猛暑だった。しかし、8月(立秋以降)は冷夏だった(全体的に見ると西日本が冷夏である)。北海道、および東日本 - 西日本で8月 - 9月を中心とした長期的な豪雨(例:平成27年9月関東・東北豪雨(主に栃木県・茨城県・宮城県)など)、北海道を除く北日本で平年より10日 - 14日以上遅い初雪・初冠雪、沖縄では12月に長期的な夏日を観測した |
| 2016年夏 - 2017年春 | ラニーニャ | 北海道を中心とした8月の長期的な大雨・豪雨 1951年に気象庁が統計を取り始めて以来、初めて東北地方の太平洋側に台風が上陸した(平成28年台風第10号) また北日本では平年より7日 - 10日早い初雪・初冠雪を観測し、関東甲信越では2016年11月に初雪・初冠雪を観測した(関東甲信越で11月に初雪・初冠雪が観測されたのは1962年11月以来、54年ぶりとなる) このほか、2017年1月中旬と2月中旬、3月上旬は日本国内(平成29年の大雪)のみならず、国外の多くで10数年に1度の北半球最大規模の大寒波が襲来した。 |
| 2017年秋 - 2018年春 | 日本でこの冬(2017年12月 - 2018年2月)の平均気温は約1°C程度低かった。そして冬の積雪は平年よりかなり多く(平成30年の大雪)、全国規模で寒冬となった。 | |
| 2018年秋 - 2019年夏 | エルニーニョ | 2018年9月4日に近畿地方にかなり台風が接近して危険な暴風となった(平成30年台風第21号)。9月7日 - 9月10日10日は秋雨前線が近づいて西日本では断続的に雨が降り続いた。冬はほぼ全国的に暖冬で、南西諸島は記録的暖冬、西日本や東日本でも顕著な暖冬となり、西日本の日本海側は記録的少雪となった 2019年5月 - 7月は北日本を中心に記録的な長期高温・長期日照・長期少雨となった。7月中旬までは冷夏傾向だったが、2019年8月は平年並みか平年より高い夏だった。6月は南米で大量の雹が局地的に降り、欧州で長期的な異常高温になるなど異常気象が発生した。 |
| 2020年夏 - 2021年春 | ラニーニャ | 2020年初冬より日本国内を中心に、数年に1度の最大規模の大寒波が襲来し(奄美沖縄を除く)、12月14日から21日までの7日間の総降雪量が200センチ(2メートル)を超えた地点が数地点と、主に東日本と北日本の各日本海側、および山陰地方と九州北部の長崎を中心に記録的な大雪を観測した(令和3年の大雪)[21]。特に2021年1月から2月中旬にかけて日本では北日本、および西日本の各日本海側を中心に、2006年1月 - 2月当時を上回る記録的な大厳冬となった(しかし2月後半は暖冬傾向だった)。 2021年1月上旬には日本のみならず、中国や韓国などの東アジアや一部の北米、欧州でも数年に1度の最大規模の大寒波が襲来し、特にスペインの首都マドリードでは半世紀(50年)ぶりの大雪となった[22]。 |
| 2021年秋 - 2022/2023年冬 | 2022年1月上旬には日本(令和4年の大雪)のみならず、パキスタンでも記録的な大雪となった。 また、2022年12月には北米で大寒波が襲来し、記録的な大雪となった。また、日本(令和5年の大雪)でも記録的大雪が多発していた。特に東海地方の津と四国太平洋側の高知では10cmを超える記録的な大雪であった。 |
|
| 2023年春 - 2024年春 | エルニーニョ[23][24] | 九州、および東北北部、北海道を中心とした記録的な大雨・豪雨(2023年6月下旬 - 7月中旬) 沖縄と南西諸島を除く日本列島のほとんどで記録的・長期的な猛暑(2023年7月下旬 - 10月中旬) 日本列島全域で記録的・長期的な暖冬(2023年12月 - 2024年2月)となった一方、北米大陸と(日本を除く)ユーラシア大陸においては数年に1度の最大規模の大寒波(2024年1月 - 2月)が襲来した。 |
※季節は気象庁が定義する「北半球の季節」による区分(春:3 - 5月、夏:6 - 8月、秋:9 - 11月、冬:12 - 2月)。
※発生有無の基準は経緯度1度四方精度の1891年からの表面海水温(SST)月平均値を基礎データとし対象となる月の前年までの30年間の月平均海水温を「基準値」としてNINO.3(後述)海域において基準値と対象月の5か月移動平均値を比較し基準値を0.5°C以上上回った状態が6か月以上続いた場合「エルニーニョ」、基準値を0.5°C以上下回った状態が6か月以上続いた場合「ラニーニャ」としている(期間が太字のもの)。
定義に満たなかった場合でも海水温が上昇・低下し、エルニーニョ・ラニーニャのような異常気象が発生した事例もいくつかある(文字の太さが普通のもの)。
古い時代のエルニーニョ
(オーストラリア国立大学グロウブ博士、Nature、1998年)
- 1396年
- 1685 - 1688年
- 1789 - 1793年
- 1877 - 1879年
エルニーニョ/ラニーニャ発生時の典型的気象
エルニーニョおよびラニーニャの発生時には、世界各地で通常時と比べて異なる傾向の気象が見られる。ただし、先述の通り太平洋熱帯域ではENSOと天候の相関性が高いが、他の地域では他の要因の影響も大きいため一概に下記のようになるとは限らない。日本では後述のインド洋全域昇温・ダイポールモード現象(IOD)等のインド洋の海水温異常や北極振動(AO)の影響を強く受けるほか、ヨーロッパではAOや北大西洋振動(NAO)の影響を強く受けるなどするため、天候の傾向を考える上ではこれらを総合的に判断する必要があるので注意しなければならない。これら複合要因によって変化する天候の変化を予測するため、天候パターンの解明や気候モデルの改良が行われている。
なお、下記の「世界の典型的気象」リストは統計的な傾向を抽出したものに過ぎず、メカニズムが十分に解明されていないなど、ENSOとの因果関係がはっきりしないものが含まれる。
エルニーニョ

エルニーニョによって西太平洋赤道域(フィリピン・インドネシア・ミクロネシア付近)の海水温が低くなると、同海域では対流活動が例年より弱くなる。
例年夏季をはさんだ梅雨から秋雨の頃まで日本に晴天をもたらす太平洋高気圧は、主に西太平洋赤道域からの上昇気流が対流圏上層を経由し下降してくるハドレー循環によって勢力を保っている。また、太平洋・日本パターン(PJ)と呼ばれるテレコネクションパターンによって日本付近の気圧の高低がフィリピン付近の気圧の高低と逆になるという連動性がある。よって、対流活動が不活発化すると同地域のハドレー循環が弱まり、衰えた太平洋高気圧の西への張り出しが弱くなる一方、海水温低下により西太平洋赤道域の気圧は高くなり、日本付近は逆に気圧が低くなる。従って、南西からの熱帯モンスーン気団(暖かく湿った空気)の流入やオホーツク海高気圧の張り出し(冷涼な北東気流の流入)が強くなり、日本では低温でくもりや雨が多い夏となる傾向がある[25][26]。
例年冬季にはシベリア高気圧と周期的に発達しながら日本付近を東進する温帯低気圧の両者が西高東低の気圧配置を作り、日本海側に雪、太平洋側に乾燥した晴れをもたらす。エルニーニョのときには、太平洋・北米パターン(PNA)によってアリューシャン低気圧が勢力を増すため、北極振動による寒気の南下域がアリューシャン列島付近に固定されて日本付近では寒気が入りにくくなる一方で、西太平洋パターン(WP)によって中国大陸からミッドウェー島付近にかけての北西太平洋中緯度で気圧が高くなり、西高東低が弱くなって寒冷な北西季節風が弱まり、日本では全般に暖かく日本海側で晴れが多く太平洋側で曇りや雨雪が多い冬となる傾向がある[25][26]。
- 北半球の春
- 高温
- 低温
- 多雨
- 少雨
- 高温
- 低温
- 多雨
- 少雨
- 高温
- マレーシア - インド、フランス東部付近、アラスカ付近、南アメリカ北西部 - 中部太平洋熱帯域、ブラジル東部
- 低温
- 中央シベリア南部 - 南西諸島周辺 - 西日本、カナダ東部 - 米国中部、南アメリカ南部、ポリネシア南部 - ニュージーランド - オーストラリア北東部
- 多雨
- スペイン - アルジェリア北部周辺、米国南西部付近、南アメリカ南部
- 少雨
- 中央シベリア東部、朝鮮半島 - 中国北部、インド西部 - アラビア半島南部、ブラジル北西部付近、ポリネシア南部 - オーストラリア東部 - インドネシア周辺
- 北半球の冬
- 高温
- 東日本 - 西日本、東南アジア - オーストラリア北部 - インド南部 - アフリカ南部、西アフリカ南部、カナダ西部付近、カナダ南東部、中央アメリカ南部 - 南アメリカ北部 - 中部太平洋熱帯域
- 低温
- 西シベリア、米国南部、ニュージーランド
- 多雨
- 少雨
ラニーニャ

ラニーニャによって西太平洋赤道域(フィリピン・インドネシア・ミクロネシア付近)の海水温が高くなると、同海域では対流活動が例年より強くなる。
夏季には、フィリピン海(フィリピン東方海域)で対流活動が活発化することで気圧が低下する一方、東寄りの太平洋・日本パターン(PJ)によって日本の東にある太平洋高気圧が勢力を強め、北に張り出しやすくなるため、北日本で晴れが多く気温が高い傾向にある一方、対流活動活発化の影響を直接受けて熱帯モンスーン気団(暖かく湿った気流)の流れ込みが強くなり、南西諸島で雨が多い傾向にある[25][26][28]。
冬季には、シベリア高気圧が強まる一方でWPによりアリューシャン低気圧が例年より西寄り(日本東方近海)に発達して西高東低の気圧配置が強まり、寒冷な北西季節風も強まって、西日本を中心に気温が低くなり、更に降雪量が増える傾向にある[25][26]。
- 北半球の春
- 高温
- 低温
- 多雨
- 少雨
- 特に見られない
- 北半球の夏
- 高温
- 低温
- 多雨
- 南西諸島、パキスタン付近、スカンディナビア半島北部、ベネズエラ付近
- 少雨
- 高温
- 東シベリア西部 - 中国北東部、米国中西部・南部周辺、ポリネシア南部 - オーストラリア北東部
- 低温
- フィリピン南部 - インド南部、北アフリカ南部 - 東アフリカ北西部、マダガスカル北部付近、カリフォルニア半島 - カリブ海 - 南米西岸 - ミクロネシア南西部
- 多雨
- メラネシア - オーストラリア北部・東部
- 少雨
- 中央アジア東部、アラビア半島付近、アルゼンチン北部付近、中部太平洋熱帯域
- 北半球の冬
- 高温
- 東シベリア中部、米国南部付近、ポリネシア南部 - ニュージーランド
- 低温
- 西日本 - 中国東部 - オーストラリア北東部 - マダガスカル、北アフリカ西部 - 西アフリカ西部周辺、東アフリカ南部 - 南部アフリカ、カナダ西部 - アラスカ、カリブ海 - 南アメリカ北部 - 中部太平洋熱帯域
- 多雨
- フィリピンの東海上 - マレーシア、南アフリカ - セントヘレナ島、米国北西部、南アメリカ北部付近、メラネシア - オーストラリア北東部
- 少雨
- フロリダ半島 - メキシコ
エルニーニョ・南方振動の監視と予測
現在、海上観測、衛星観測などのデータを基に研究機関や公共気象機関が海水温や気圧などの指標を監視している。一部はウェブ上にも公開されている。
エルニーニョ監視海域
世界の気象機関がエルニーニョ監視のために5つの海域を設定し、その海水温トレンドの統計を取っている。
- NINO.4海域 太平洋西部の海域(5°N-5°S, 160°E-150°W)
- NINO.3海域 太平洋東部の海域(5°N-5°S, 150°W-90°W) - 日本の気象庁がエルニーニョ監視海域に指定している。基準値は上述。
- NINO.1+2海域 ペルー沖(0°-10°S, 90°W-80°W)
- NINO.WEST海域 インドネシア北部の海域(15°N-0°, 130°E-150°E)
南方振動指数
SOI(Southern Oscillation Index)。 南太平洋上のタヒチとオーストラリアの都市ダーウィンとの気圧差を指数化したもの。南方振動のレベルを示す値として使われる。エルニーニョ発生時はマイナスを示す傾向にある。
その他
- 赤道東西風指数 - 太平洋赤道域の貿易風、ウォーカー循環の強さを表す指数。対流圏下層の循環が強いときは上層が弱いという、上下層の相反関係もある。
- 海洋貯熱量 - エルニーニョ・ラニーニャに同期して変化を示す。発生・収束に先行して現れることもあるが、MJOよりは相関性が低い。太平洋・インド洋赤道域0-300 m水温の平年偏差の経度-時間断面図などから変化傾向を割り出す。
- OLR(外向き長波放射)指数 - 対流活動の活発度を示す。エルニーニョ時には太平洋赤道域東部で活発化する一方西部で静穏化する。
- IOBW海域 インド洋熱帯域(20°N-20°S, 40°-100°E)の海面水温 - NINO.3海域の水温に1カ月程度遅れて同様の変化をみせる。エルニーニョの場合、インド洋全域昇温を引き起こす場合があるので重要な監視対象となる。
- マッデン・ジュリアン振動(MJO) - エルニーニョやラニーニャの発生および収束に大きく関連していると考えられている。対流圏上層における速度ポテンシャル平年偏差の経度-時間断面図、対流圏下層における東西風速平年偏差の経度-時間断面図などから変化傾向を割り出す。
エルニーニョ・南方振動(ENSO)の発見
1903年にインド気象局の長官に指名されたイギリスの数理物理学者ギルバート・ウォーカーは、ちょうど整備され始めた世界各国の長期間の気象データと得意の統計学を用いて、「気象要素相互の時空間的な相関関係を使ってインドモンスーンの予兆を探る」という研究に取り組んだ[29]。彼はスタッフを総動員して膨大なデータ同士の相関計算に取り組み、その相関関係から1928年に発表した3つの大気振動の一つが「南方振動(Southern Oscillation: SO)」だった[29]。ちなみに残りの二つは「北太平洋振動」と「北大西洋振動」である。一方で、1925 - 1926年に強いエルニーニョが起こった際に、たまたま研究のためにペルーを訪れていたアメリカの鳥類学者で自然保護主義者だったロバート・マーフィーは、この影響を広く調査するために南米に気候のための観測網を設立して気象観測を始めた[30]。
当初大気の南方振動と海洋のエルニーニョは、それぞれ大気と海洋の独立した現象と思われていた。ところがこの両者が関連していることを明らかにしたのが、インドネシアのジャカルタにあるオランダ東インド王立磁気気象観測所に勤めていた気象学者ヘンドリク・ベルラーヘ[31]である[32]。同観測所では南方振動に関する研究を行っており、ベルラーヘは1926年に東京で開催された第3回太平洋学術会議で発表されたマーフィーの南アメリカ西部での気候観測の結果を手に入れた。彼はこの二つの結果を突き合わせて、大気現象の南方振動と海洋現象のエルニーニョに高い相関があることを発見し、1957年に初めて両者が関連していることを発表した [33]。これがENSOの発見とされている[32]。
なお、このメカニズムを解明したのはアメリカUCLAの教授だったヤコブ・ビヤクネスである。彼は国際地球観測年(IGY)など観測された海洋のデータを解析し、エルニーニョ時のペルー沖の海面の異常昇温は、貿易風が弱まるのにともなってペルー沖の海洋深層からの冷たい赤道湧昇が止まることで起こるというメカニズムを発表した。ヤコブ・ビヤクネスは海面温度の東西傾度による大気の東西循環がウォーカーによって示された南方振動の主要なメカニズムであったことから、1969年にこの熱帯域の東西方向の大気循環を「ウォーカー循環」と名づけた。
類似の現象
エルニーニョもどき
東京大学の山形俊男が命名した現象で、太平洋中央部の海水温が上がることにより上昇気流が発生することにより太平洋高気圧の勢力が強くなる[34][35]。2004年夏に日本で発生した猛暑や集中豪雨の原因とみられている。
大西洋ニーニョ
数年に一度の頻度で発生する現象で、エルニーニョ現象ほど水温偏差は大きくない。しかし、周辺地域の南アメリカやアフリカの気候への影響は大きく、熱帯域で洪水や干魃を発生させる要因となっているほか、エルニーニョにも影響を与えていることも示唆されている。発生のメカニズムはエルニーニョ現象と同様に、「数年に一度、弱まった貿易風の影響で、西側の暖水が東へと張り出す」タイプと「赤道の北側で海洋表層の水温が通常よりも暖められ、暖められた海水が赤道域に輸送される[36]」があると考えられている。
ダイポールモード現象
インド洋で、赤道域東部と赤道域西部の海水温・気圧などが相反して変化する現象[37]。ENSOに連動する場合もあるが、単独で発生する場合もある。アフリカ、モンスーンアジア、オセアニアの天候に影響を与える。
カリフォルニア・ニーニョ/ニーニャ現象
カリフォルニアからバハ・カリフォルニア半島の沿岸に発生する現象で、この海域は海上風と地球の自転の影響により表層の海水が沖合に吹き流され、流された海水を補うために下層から冷水が湧き出す。つまり、この海域の海上風が強くなると海水温は低下し海上風が弱くなると海水温が上昇する。従って、この海域の表層の海水温は低く保たれているが、海上風の強弱の長期的な変動により沿岸域の海面水温の経年変動に偏差が生じる現象。海洋研究開発機構の研究者(袁潮霞、山形俊男)によって命名された。
従来は、エル・ニーニョ/ラ・ニーニャ現象によって引き起こされる現象と考えられていたが、エル・ニーニョ/ラ・ニーニャ現象とは独立した大気海洋結合現象であることが海洋研究開発機構の研究で明らかとなった[38]。
影響
米国のコロンビア大学地球研究所の報告によると3年から7年毎に気温上昇や降雨量減少を招くエルニーニョと戦争の周期的な増加の相関が認められるとされる[39]。報告によれば、1950年から2004年までのエルニーニョ南方振動について、175カ国で1年間に25人以上の死者を出した234の内紛(半数以上が1,000人以上の戦死者を出したもの)の発生との相互関係を調査した結果、ENSOの影響を受けた国における内乱の発生する率はラニーニャ発生期間に約3%、エルニーニョ発生期間にはその倍の6%と倍だったものの、ENSOの影響を受けなかった国では、常に2%のままで、エルニーニョは世界中の21%の内紛でその一因となった可能性があり、エルニーニョの影響を受けた国々ではその割合が30%になるとされる[39]。
より貧困な国の方が悪天候によって混乱に陥りやすく、豊かなオーストラリアはENSOに左右されるものの、これまで内紛はないが、ペルーの高地やスーダン南部ではエルニーニョが発生した年から内紛が激化し、長期化へと発展したとされる[39][40]。
脚注
- ^ 小倉 2016, pp. 284–285.
- ^ 植田 2012, p. 25.
- ^ a b c 小倉 2016, p. 282.
- ^ a b 仁科 2014, p. 121.
- ^ 境田 2008, p. 71.
- ^ 仁科 2014, pp. 122–123.
- ^ 小倉 2016, p. 283.
- ^ 植田・田中 2007, p. 26.
- ^ 小倉 義光、1984、『一般気象学』、東京大学出版会 ISBN 4-13-062084-3 pp. 287-294
- ^ 高薮縁、川辺正樹、中村尚、山形俊男、藤尾伸三『海のすべて』ニュートンプレス、2017年、95頁。 ISBN 978-4-315-52060-6。
- ^ GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 28, NO.1, PAGES 25, 2001[1]
- ^ Nature, 2000, 405(6788)775[2]
- ^ Science, 2002, 298, no.5596, 1179[3]
- ^ Journal of Marine Research, 64, 797, 2006[4]
- ^ 地球温暖化予測情報 第5巻 HTML版、気象庁。
- ^ エルニーニョ現象に関するQ & A エルニーニョ現象と地球温暖化は関係があるのですか、気象庁、2007年7月1日閲覧。
- ^ Vincent, Emmanuel (2016年12月2日). “Daily Mail claim about 2016 global temperature record is misleading”. Science Feedback. Climate Feedback. 2024年10月3日閲覧。
- ^ “Global warming and the El Niño Southern Oscillation”. Skeptical Science. 2024年10月3日閲覧。
- ^ “Historical El Niño/La Niña episodes (1950–present)”. United States Climate Prediction Center (2019年2月1日). 2019年3月15日閲覧。
- ^ “El Niño - Detailed Australian Analysis”. Australian Bureau of Meteorology. 2016年4月3日閲覧。
- ^ 2020年12月 これまでの大雪のまとめ 総降雪量200センチ超えも(tenki.jp) - Yahoo!ニュース 2020年12月21日(2021年1月3日閲覧)
- ^ スペイン首都、50年ぶり大雪 - 時事通信社 2021年1月9日(同日閲覧)
- ^ エルニーニョ監視速報(No.369)2023年5月の実況と2023年6月〜2023年12月の見通し - 気象庁 2023年6月9日(同日閲覧)
- ^ エルニーニョ監視速報(No.380)2024年4月の実況と2024年5月〜2024年11月の見通し - 気象庁 2024年5月10日(2024年6月1日閲覧)
- ^ a b c d 「エルニーニョ/ラニーニャ現象などに伴う天候の特徴」日本1、日本2、日本3 気象庁のまとめ、1979年 - 2008年の観測データに基づく。季節区分は気象庁のもの(春:3 - 5月、夏:6 - 8月、秋:9 - 11月、冬:12 - 2月)。
- ^ a b c d 海洋の健康診断表「総合診断表」2.3 エルニーニョ現象 気象庁。
- ^ a b 「エルニーニョ/ラニーニャ現象などに伴う天候の特徴」 世界1、世界2 気象庁のまとめ、1979年3月 - 2009年2月の観測データに基づく。季節区分は気象庁のもの(春:3 - 5月、夏:6 - 8月、秋:9 - 11月、冬:12 - 2月)。
- ^ 異常気象レポート2005 1.5.3 エルニーニョ/ラニーニャ現象と世界の天候および台風の活動 気象庁
- ^ a b Cox, John D. (2013.12). 嵐の正体にせまった科学者たち. 訳 堤 之智. 東京: 丸善出版. ISBN 978-4-621-08749-7. OCLC 869900922
- ^ Cushman, Gregory T. (2004). “Enclave Vision: Foreign networks in Peru and the internationalization of El Nino research during the 1920s”. Proceedings of the International Commission on History of Meteorology 1.
- ^ Berlage [jr.], Hendrik Petrus(1896-1968)
- ^ a b 堤 2018.
- ^ Enfield, David B. (1989). “El Niño, past and present”. Reviews of Geophysics 27 (1): 159. doi:10.1029/rg027i001p00159. ISSN 8755-1209.
- ^ Low-latitude Climate Prediction Research 海洋研究開発機構 JAMSTEC
- ^ エルニーニョモドキ (PDF)
- ^ 大西洋赤道域の新たな気候変動メカニズム 海洋研究開発機構 JAMSTEC
- ^ インド洋ダイポール 海洋研究開発機構 JAMSTEC
- ^ カリフォルニア・ニーニョ/ニーニャ現象を世界で初めて発見 海洋研究開発機構 JAMSTEC 2014年4月25日
- ^ a b c “研究報告:気候サイクルが戦争を駆り立てる”. 2017年2月6日閲覧。
- ^ “Climate Cycles Are Driving Wars, Says Study”. 2017年2月6日閲覧。
参考文献
- 植田宏昭、田中博 著「海洋」、松岡憲知・田中博・杉田倫明・村山祐司・手塚章・恩田裕一(編) 編『地球環境学―地球環境を調査・分析・診断するための30章―』古今書院、2007年、25-28頁。 ISBN 978-4-7722-5203-4。
- 境田清隆 著「気候の変化・変動」、高橋日出男・小泉武栄(編) 編『自然地理学概論』朝倉書店、2008年、64-74頁。 ISBN 978-4-254-16817-4。
- 植田宏昭『気候システム論』筑波大学出版会、2012年。 ISBN 978-4-904074-21-3。
- 仁科淳司『やさしい気候学』(第3版)古今書院、2014年。 ISBN 978-4-7722-8506-3。
- 小倉義光『一般気象学』(第2版補訂版)東京大学出版会、2016年。 ISBN 978-4-13-062725-2。
- 堤之智『気象学と気象予報の発達史』丸善出版、2018年。 ISBN 978-4-621-30335-1。
関連項目
外部リンク
- エルニーニョ/ラニーニャ現象 - 気象庁
- AMSR-E El Niño Watch - JAXA/EORC
- NOAA El Niño Page - NOAA
- ENSO outlook - BOM
- 世界の週ごとの異常気象 - 気象庁
- 世界の年ごとの異常気象 - 気象庁
- SINTEX-F1 CGCM による予測(ENSOおよびIODの統合予測) - 海洋研究開発機構
- 『エルニーニョ』 - コトバンク
エルニーニョ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:45 UTC 版)
片足をセカンドロープに乗せた状態から膝を当てるムーンサルトプレス。技名の由来は2004年のG1 CLIMAXに向け、「エルニーニョ現象を起こす」とマスコミに向けて発したコメント。この技も今となっては見られなくなった。
※この「エルニーニョ」の解説は、「中邑真輔」の解説の一部です。
「エルニーニョ」を含む「中邑真輔」の記事については、「中邑真輔」の概要を参照ください。
エルニーニョ
出典:『Wiktionary』 (2021/12/11 16:14 UTC 版)
語源
発音
名詞
エルニーニョ
関連語
翻訳
「エルニーニョ」の例文・使い方・用例・文例
「エルニーニョ」に関係したコラム
-
CFDのコモディティの銘柄の1つに大豆があります。大豆は、主に商品先物市場で取引されている銘柄です。CFDでは商品先物市場での価格をベースに取引が行われています。大豆相場を分析する基本情報として、アメ...
-
CFDのトウモロコシ相場は、生産国や消費国の情勢、気候などにより値動きが大きくなります。この値動きは、テクニカル指標では分析できないほど荒い値動きになります。ここでは、過去のトウモロコシ相場を振り返り...
- エルニーニョのページへのリンク