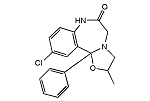オキサゾラム
オムス:トッカータ
トッカータ
バッハ:トッカータ ト短調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バッハ:トッカータ ト短調 | Toccata g-Moll BWV 915 | 作曲年: 1707-13年 出版年: 1843年 初版出版地/出版社: Peters |
作品解説
トッカータ楽章は、華やかな走句で幕を開ける。以下は複縦線で緩やかに区切られ、全体では4セクションから成る。深刻なレチタティーヴォ風のアダージョ、舞曲風の明るいアレグロ、再びレチタティーヴォに戻って終止する。
続くフーガでは、主題の反行形、逆行形をも用いた厳格な対位法が展開される。付点リズムのみで構成される主題は、一時も途切れることがなく、まったく緩みのない重厚なテクスチュアを生む。これは190小節ものあいだ続き、そもそも演奏の易しくないこのフーガをますます近づきがたいものにしている。しかし、フーガ主題はきわめて聞き取りやすく、推進力を持っていて、聴く者を退屈させない。前半の舞曲風セクションやレチタティーヴォとの対比があいまって、演奏効果の高い作品に仕上がっている。
バッハ:トッカータ ト長調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バッハ:トッカータ ト長調 | Toccata G-Dur BWV 916 | 作曲年: 1707-13年 出版年: 1867年 初版出版地/出版社: Peters |
作品解説
急速な冒頭楽章、並行短調によるアダージョ、そしてジーグ風のフーガという3楽章構成は、いっけん《イタリア協奏曲》を思わせる。実際、ある手稿資料では「協奏曲あるいはトッカータ」と題されており、そのばあい冒頭楽章では十六分音符のパッセージをソロ、三和音群をトゥッティとみなすことになるが、どちらもあまりに短く、まるで息切れするように長続きしない。むしろこうしたフレーズは、ドイツの伝統的なトッカータやプレリュードに見出されるものである。また、緩徐楽章とフーガにはトゥッティとソロの交代らしきものがないことから、協奏曲というのはあくまで見かけ、ないし解釈上のちょっとしたヒントとみなすべきだろう。
緩徐楽章冒頭左手の三和音は、前楽章の主題後半部を意識したと思われる。真の主題は5小節目のアルトにようやく現れる。模倣は厳格ではないが、はじめは装飾性の豊かな旋律の核となり、のちには息の長い掛留の対旋律に主題が浮かび上がる。
フーガの主題は付点リズムとトッカータ風の下行走句を組み合わせたもの。最後は3オクターヴを一気に駆け下りて終わる。この楽章、また冒頭のトッカータ楽章でも同様であるが、最終小節で八分音符ひとつのあとを休符で埋め、あまつさえフェルマータが付けられているのには、きわめて重要な意味がある。最後の音は装飾をつけたり、未練がましく引き伸ばしたりしてはならない。作曲家はあくまで、いささか唐突な離別ないし消滅をここで意図しているからである。
プロコフィエフ:トッカータ ニ短調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| プロコフィエフ:トッカータ ニ短調 | Toccata Op.11 | 作曲年: 1912年 出版年: 1913年 初版出版地/出版社: Jurgenson |
作品解説
※調性表記で、「ハ長調」となっている資料が多いとのご指摘をコメント欄にいただきました。事典編集部では本曲はニ短調(少なくとも「ハ調」ではない)であるという見解でしたが、複数資料をあたって「ハ長調」という表記が多い状況を確認しましたので、この件についての調査を行いました。調査報告は下記です。
http://www.piano.or.jp/enc/news/2009/07/30_9112.html
「トッカータ」は、おもにバロック期において、ファンタジーやプレリュードなどと同様に好んで作曲されたジャンルであり、鍵盤楽器用のトッカータは即興的な速いパッセージを特徴とする。バロック期以後、このジャンルは他の楽曲ジャンルの中に取り込まれて次第にその名は影を薄めていった。シューマンは『トッカータ』Op.7、リストは『トッカータ』S.197aをそれぞれ残しているが、これらは19世紀の代表的なピアノ作品においては数少ない例である。
プロコフィエフはシューマンの『トッカータ』に触発されて、1912年にこの『トッカータ』Op.11を作曲したという。プロコフィエフの『トッカータ』は、同音連打によって特徴づけられた楽曲のように思われるが、オクターヴや重音によるパッセージの連続は、たしかにシューマンの『トッカータ』からの影響を想起させる。
左右の手が重なる音域や、跳躍して交差する音域が選ばれ、密集した音響によって特徴づけられた部分から、音域を上下いっぱいに反行しながら拡大した開放的な音響へといたってクライマックスを築き、5オクターヴのグリッサンドによって楽曲が締めくくられる。
バッハ:トッカータ ニ短調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バッハ:トッカータ ニ短調 | Toccata d-Moll BWV 913 | 作曲年: 1707-13年 出版年: 1801年 初版出版地/出版社: Hoffmeister & Kühnel |
作品解説
この曲が「トッカータ第1番」と呼ばれるのは、そのように書き込まれた手稿資料が複数存在するためであり、また7曲のうちではもっとも早く1801年に出版されているからかも知れない。
導入のトッカータ部分、Thema(資料によってはPresto)と題されるフーガ部分、短い動機を連ねた緩やかな推移部、再びフーガ部が始まり、トッカータ風のコーダで終結する。複縦線に従うなら4部構成だが、最後のコーダによって、伝統的な T-F-T-F-T に近い形になっている。
もっとも、最初のトッカータ・セクションでは、第15小節の休符を境にテクスチュアががらりと変化する。さらに言うならばその前の導入部分も、ペダル・バス風に始まり、音階で一気に駆け下り、溜息動機でしばらく進んだのち、ふたたび音階の走句が散りばめられるといった具合で、多様なものが並置されている。
フーガの主題はすでに、トッカータ・セクション後半で準備されている。ただし、Thema とされる最初のフーガ・セクション冒頭は、一般的な主題提示と5度関係での応答ではなく、8度上でなし崩しに模倣されるに留まっており、全体にフーガとしては自由な書法になっている。この印象的な主題は、リズム形を組み替えたり反行や逆行じみた変奏を加えられたりして、いたるところに顔を出したのち、推移部分にも素材を提供する。
2回目のフーガも8度の模倣で始まるが、明確な対主題をもっている。フーガの展開は、最初のThemaに比べれば、より緻密な構成がなされている。
主題は最後の分散和音によるコーダに入っても完全に失われることはない。歯切れの良いリズムがここでは模続進行の流れの中に溶かされて、やがて断片的に浮かび上がり、主題の回帰への期待感を高める。そして最後の3小節でいよいよ主題が再提示されて終結する。
この作品には当時のオルガン音楽の常套句(ペダル・バス、鍵盤の幅をいっぱいに使う音階の走句、分散和音による模続進行等)があふれかえっており、それらの繋ぎ目にややぎこちなさを感じるところもある。しかしこれを統一するのが、Themaにはっきり提示されるリズム形である。動機による統一が見られるのは、7曲中この作品のみである。
バッハ:トッカータ ニ長調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バッハ:トッカータ ニ長調 | Toccata D-Dur BWV 912 | 作曲年: 1707-13年 出版年: 1843年 初版出版地/出版社: Peters |
作品解説
音階の走句による導入、アレグロ、アダージョに続くフーガおよびトッカータ風のコーダ、そしてジーグ風のリズムによるフーガとコーダから成る。複縦線に従うなら4部分だが、書法の上ではより多様なものが並置されている。
アレグロ部分はロンドのように冒頭の主題が回帰する。その間では、右手と左手はそれぞれのパッセージをまるでキャッチボールのように交換する。
アダージョでは、アレグロの明るさが徐々に翳り、急激な下行音階で朗唱が分断され、様々な調を経て短調のフーガを目指す。なお、ここに見られる両手のトレモロは、バッハが初期においてのみ用いた音型で、後年に改訂の機会があればこれを削除した。従って、この作品は作曲も改訂もかなり早い時代に行われたとみられる。
最初のフーガは半音階主題で、2つの対主題をもつ。これら3つが様々な声部に現れ、転回対位法が厳格に実施される。やがて、アダージョで鋭く介入した音階の走句が再び登場して、調の遍歴が始まるが、次第に明るさを増し、一六分の六拍子による軽快なフーガにたどり着く。
このセクションは、三度音程を行きつ戻りつする主題とギャロップする対主題を持つが、対位法よりもむしろ和声の変化によって形成されている。トニカとドミナントの五度関係よりも同主短調関係や三度の関係で進む和声は、きわめて斬新に響く。巧みな転調と絶え間なく続く一六分音符に隠されているが、調は嬰ト短調にまで到達する。
コーダでは三和音が倍速の分散和音にほどけてゆき、速度を増して一気に鍵盤を駆け下りるが、理性的なカデンツで再び上行して終止する。
なお、アダージョ部に見られる両手のトレモロは、バッハが初期においてのみ用いた音型である。後年のバッハはトレモロを好まず、改訂の機会があれば削除していった。従って、この作品は作曲も改訂もかなり早い時代に行われたとみられる。
バッハ:トッカータ ハ短調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バッハ:トッカータ ハ短調 | Toccata c-Moll BWV 911 | 作曲年: 1707-13年 出版年: 1839年 初版出版地/出版社: Peters |
作品解説
複縦線の区切りを持たないが、標語によって以下のように分かれる。トッカータ導入部(第1-12小節)、アダージョ(第12-33小節)、アレグロと題される長大なフーガ(第33-170小節、アダージョのカデンツ(第85小節)を中間に置く)、そしてアダージョとプレストによるコーダ(第171-175小節)である。
全体に模続進行やリズム型の反復がふんだんに用いられ、やや古めかしいスタイルになっている。それでもバッハの生み出したメロディの美しさは格別で、フーガにおいてはテクスチュアと音域の変化が旋律にさまざまな光と陰を投げかけている。
シューマン:トッカータ ハ長調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| シューマン:トッカータ ハ長調 | Tocccata C-Dur Op.7 | 作曲年: 1829-32年 出版年: 1834年 初版出版地/出版社: Hofmeister |
作品解説
シューマンがまだ19歳の時に作曲されたが、後に何度か手を加えて、1832年に完成されている。シューマンには珍しい、技巧を追及した1曲で、はじめはピアニストを志していたというシューマンだけにかなり弾きにくく込み入って書かれている。ピアニストを大いに悩ませる曲だが、ピアニストの自慢の技巧を披露する曲にもなっている。
僅か2小節のシンコペーションのリズムが力強く登場して曲は開始され、このリズムをモチーフに細かい機械的な運動が続いていく。中間部はイ短調に転じて、オクターヴの細かい連打によるメロディーが活躍する。全体にかなり活気溢れた運動性の強い曲だが、叙情的なメロディーや緻密な和声、対位法的書法までもが盛り込まれ、変化に富んだ様々な作曲技法が光る名曲である。
バッハ:トッカータ ホ短調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バッハ:トッカータ ホ短調 | Toccata e-Moll BWV 914 | 作曲年: 1707-13年 出版年: 1839年 初版出版地/出版社: Peters |
作品解説
導入、アレグロ、クロマティックな走句を披露するアダージョの3セクションによる前半楽章と、長大な主題を持つフーガ楽章から成る。
前半は、トッカータに典型的な走句をもたず、比較的ゆるく控えめな始まり方をする。アレグロでは、冒頭で二つの主題が同時に提示され、明澄なテクスチュアながら二重フーガを展開する。これに半音階的な装飾をもつ華やかなアダージョが続く。
フーガは、真作であるには違いないが、ナポリ音楽院に伝わる古い手稿資料にそっくりの主題を持つフーガがあり、バッハはこれを借用したと見られている。跳躍を繰り返す音型は、複数の弦をまたいで演奏するヴァイオリンの典型的な語法である。
バッハ:トッカータ 嬰ヘ短調
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| バッハ:トッカータ 嬰ヘ短調 | Toccata fis-Moll BWV 910 | 作曲年: 1707-13年 出版年: 1837年 初版出版地/出版社: Trautwein |
作品解説
トッカータ風導入部とアリオーゾ風アダージョ、「急速に、切り離して Presto e Staccato」と題されるフーガ、レチタティーヴォ風の推移部、そして半音階主題のフーガの4部分から成る。
最初の推移部であるアダージョは、二分の三という古めかしい書き方がされているが、テンポは決してそれほど遅いわけではない。半音階をふんだんに散りばめ、さまざまな調を渡り歩いてゆく。
続いて、全音階を順次下行するだけのフーガ主題は、バッハのものとしては珍しいほどにシンプルだが、きわめて判りやすくエネルギーに満ちている。二つ目の推移部はほとんど同じリズム形を繰り返し用いており、和声進行も短調なため、やや冗長に聞こえる。
最後のフーガは、シャコンヌ風のリズムと半音階で4度下行する主題を持つ。このテーマはまるでラメント・バスのように響き、フーガに哀愁を与えている。
トッカータ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/02 08:27 UTC 版)
トッカータ(伊 toccata)とは、主に鍵盤楽器による、速い走句(パッセージ)や細かな音形の変化などを伴った即興的な楽曲で、技巧的な表現が特徴。toccataは動詞toccare(触れる)に由来しており、オルガンやチェンバロの調子、調律を見るための試し弾きといった意味が由来である。最初期の鍵盤用トッカータは16世紀中ごろに北イタリアで現れた。
発生〜ルネサンス期
16世紀までの器楽音楽は、声楽アンサンブル用のポリフォニー楽曲の即興的転用あるいは編曲であった。オルガンは教会典礼における声楽ポリフォニーの伴奏楽器として用いられていたが、これは合唱の音程を安定させることも目的のひとつであった。最初期のトッカータ的な特徴を持った楽曲は、教会で宗教曲を演奏するのに際して音を提示する(いわゆる「音取り」)行為を音楽的に発展させ、ある種の和声的進行に音階的走句をともなった簡単な即興曲であった。これらの楽曲は初期の段階ではプレリューディウム (Praeludium)、リチェルカーレ (Ricercare)[1]等と呼ばれていた。
リュートやビウエラ等の撥弦楽器でも声楽ポリフォニーの編曲演奏は盛んであり、これらに対してもその導入部分として即興的な楽曲を演奏することが行われた。これらはRicercareと呼ばれる一方でTastar de Corde(伊)、Tiento(西)などと呼称されることもあった。これらはそれぞれ、「弦に触れる」「感触」の意味で、トッカータ Toccataと同様の意味を持っている。
オルガン用トッカータもこの系譜に属する楽曲である。トッカータの名称をもつオルガン曲を収録した出版譜は1590年代にはじめて現れており、代表的作品としては、アンニーバレ・パドヴァーノやアンドレア・ガブリエリのものをあげることができる。パドヴァーノの曲集 Toccate et ricercari d’organo は1604年出版であるが、パドヴァーノの没年は1575年であるので16世紀中ごろにはすでにオルガン用のトッカータが出現していた事がわかる。
このようなトッカータの発生は、初期バロックまでのトッカータで使用されている、旋法を明記するような曲名表記と関係している。たとえば、「第1旋法のトッカータ」は、そのトッカータがドリア旋法で書かれていることを意味しており、その曲がドリア旋法のポリフォニーの音取り、ないし導入に用いることができることを示唆している。
ルネサンス末期〜初期バロック
パドヴァーノやアンドレア・ガブリエリのトッカータは、単純な和声進行的部分と音階的走句部分の組み合わせで書かれていたが、和声進行的部分は次第に模倣的、対位法的な曲想に置き換えられていった。パドヴァーノやガブリエリとともにヴェネツィアのサンマルコ寺院のオルガニストであった(ヴェネツィア楽派)クラウディオ・メールロは対位法的部分をともなったルネサンス的トッカータ様式の完成者と見なせる。
当時南ドイツでは多くの音楽家がヴェネツィアに留学しその音楽を輸入しようとしていた(ハインリヒ・シュッツなど)。鍵盤楽器の分野ではシュッツよりも1世代上で、同じくヴェネツィアで学んだハンス・レーオ・ハスラーがトッカータをはじめとするイタリア風の鍵盤音楽をドイツにもたらしている。
ちょうど同時期にフランドル・オランダにも優れたオルガニストの一団がいた。その代表としてあげられるのがヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンクである。今日知られているだけでもスウェーリンクの手になるトッカータが十数曲ある。一連のファンタジアとともにスウェーリンクの作品群の主要な一角をなすこれらのトッカータは、形式上は和声部分または模倣部分と音階的楽句部分からなりヴェネツィア楽派をはじめとするイタリア諸派のそれと同様であるが、スウェーリンクのパッセージワークはイタリア風のきらびやかな楽句とは違い、より構造的であると評される。このようなパッセージワークの特徴は、バード、ブル、フィリップス等のイギリスヴァージナル楽派の影響が色濃い。
しかし、音楽史の中でこの時期最も重要な鍵盤音楽の作曲家とされるのがジローラモ・フレスコバルディであり、彼の2巻のトッカータ集(第1巻 1615年/1637年改訂、第2巻 1627年)はこの時期のトッカータという形式における記念碑的作品とされる。トッカータ集第1巻へのフレスコバルディ自身による序文には演奏方法のための注釈が9項目にわたって書き記されており、その1番目には「(このような曲を)演奏するに当たっては、現代のマドリガーレにおけるのと同様、拍を強調すべきではない。演奏が難しいマドリガーレも、あるときはゆっくり、あるときは早く、また停止させるなど表情や言葉の意味に従って拍を変化させることによって演奏がたやすくなる」と書かれている。ここで言う「現代のマドリガーレ」とは、フレスコバルディの同時代人モンテヴェルディなどの作品などを指している。モンテヴェルディはマドリガーレ集第5巻(1605年)の序文で、対位法のルールに固執する第一作法 (prima pratica) を離れて、詩や言葉の持つ感情をより直接的に表現する第二作法 (seconda pratica) を擁護し実践している事を表明している。フレスコバルディの注釈は、鍵盤音楽の分野においてもルネサンス的形式を離れ、第二作法を推し進めていくのだという表明と考える事ができる。その意味で、フレスコバルディは鍵盤音楽において初めて真にバロック的な表現を用いた音楽家のひとりであるといえる。フレスコバルディのトッカータの特徴のひとつはある程度まとまった楽節を次々に繰り出す形式にある。これらの楽節は模倣的であったり走句的であったりするが、必ずカデンツァで終わる。このような楽節構成によるトッカータは後々まで受け継がれていく事になる。
こうして、ルネサンス末期から初期バロック期にかけてはトッカータという形式におけるひとつの最盛期が訪れたといえる。この時期には、オルガン、チェンバロといった鍵盤楽器の他に、リュート(ジョヴァンニ・ジローラモ・カプスペルガーやアレッサンドロ・ピッチニーニなど)やハープ(ジョヴァンニ・マリア・トラバーチなど)のためのトッカータも作られた。これらの作品はそれぞれの使用楽器のテクニックに則した独自の表現を持っているが、構成や走句の作り方などの面でフレスコバルディら鍵盤楽器のトッカータの影響を強く受けている。
中後期バロック
フレスコバルディのトッカータにおける形式や表現法はその弟子たちによって引き継がれ、発展していった。ミケランジェロ・ロッシはフレスコバルディの半音階やエキセントリックなリズム表現法をさらに推し進めた一方で、ベルナルド・パスクィーニはパッセージワークの技法において後期バロックに近い表現を展開した。
フレスコバルディの弟子の中で今日特に有名なのがヨハン・ヤーコプ・フローベルガーである。ウイーンの宮廷礼拝堂付オルガニストであったころ、ローマに滞在しフレスコバルディに学んでいる。フローベルガーのトッカータの楽節的構造はフレスコバルディの影響と見られる一方、個々の楽節は概してフレスコバルディのそれよりも長く、また半音階や奇抜なリズム法はあまり見られない。結果として曲全体としての調和が図られている。フローベルガーはフランスの音楽にも造詣が深く、実際各地を旅し、同時代のフランスの音楽家にも影響を与えたと言われている[2]。
フローベルガーに続いて、南ドイツではヨハン・カスパール・ケルル、ゲオルク・ムッファト、ヨハン・パッヘルベルといった作曲家が活発に優れた鍵盤音楽を作曲し、その中にも多くのトッカータが含まれている。
北方ヨーロッパではスウェーリンク以来のオルガンの伝統があったが、トッカータはそれほど重要視されていなかったようだ。しかし、北方ヨーロッパの伝統を受け継いだ中期バロックの作曲家として、今日ではディートリヒ・ブクステフーデがとくによく知られている。彼のオルガン用トッカータは構成や技法の観点からプレリューディア praeludia とか、プレアンビュルム praeambulum と題名付けられた作品と同種のものである。これらの作品では、即興的楽節と対位法的楽節が交互に組み合わされているが、それぞれの楽節は長く複雑である。対位法的楽節では厳格な模倣を展開する場合が多く、今日フーガと呼ばれるようなものになっている[3]。これらの作品は概して大規模であり、しばしば技巧的なペダル操作を伴っている。これらの特徴はヨハン・ゼバスティアン・バッハの同種の作品群にも受け継がれている。
後期バロックにおいてはイタリアでアレッサンドロ・スカルラッティがチェンバロ用のトッカータを残している。これらは技法の面から見ると息子のドメニコ・スカルラッティのソナタや古典派の鍵盤音楽に見られる常動的パッセージを多く含んでおり上で見てきたトッカータの歴史からは多少乖離した作品である。ナポリ音楽院写本 ms.9478 にあるトッカータの一つは、全曲にわたって指番号が指定されており、これらのトッカータは教育のためにも用いられていた事がわかる。これは、当時の運指法を知る上でも重要な資料の一つである。
後期バロックにおいてトッカータの傑作を残した最後の作曲家がヨハン・ゼバスティアン・バッハである。バッハは彼に直接影響を及ぼしたと思われるブクステフーデなどの作品をよく知っていたばかりではなく、より古い時代の音楽家の作品も詳しく研究していた事が知られており、フレスコバルディの「音楽の花束」(Fiori Musicali)やフローベルガーの作品を写譜していた事がわかっている。オルガン用のトッカータにおいてはブクステフーデの様式を継承するとともに、規模や様式的一貫性、複雑性をより発展させた一方、チェンバロ用のトッカータにはより古い時代のトッカータの影響も見られる。
古典期以降
古典期にはトッカータと名の付く作品はほとんど作られなかったが、後期バロックのトッカータの持っていた常動曲 (moto perpetuo) 的な曲想はピアノ音楽に受け継がれた。数少ない「トッカータ」と名の付く曲でも、即興的楽節と対位法的楽節の組み合わせといった本来のトッカータの性質は失われ、専ら動きの速い反復音形や同音連打といった常動的側面が強調されている。
古典派においてはムツィオ・クレメンティのソナタ作品11に含まれるトッカータが数少ないよく知られた例である。ロマン派におけるトッカータの代表例はロベルト・シューマンのトッカータ作品7である。
近代になるとより注目すべきトッカータの例が現れる。クロード・ドビュッシーの「ピアノのために」(Pour le piano) の第3曲や、モーリス・ラヴェルの「クープランの墓」(Le Tombeau de Couperin) 第6曲はその例である。これらは曲の命名からして懐古的発想が窺えるが、楽想そのものとしてはやはり常動曲としての側面が強い。ラヴェルの「トッカータ」は20世紀のピアノ曲の中でも屈指の難曲といわれる。同音連打が終始一貫して繰り広げられるのが特徴であるが、高速な同音連打は古い時代のピアノでは鍵盤の戻りの悪さから非常に困難であったらしく、近代以降の高性能なアクション(打弦機構)が開発されてから可能になったとされる。プロコフィエフのトッカータ作品11もこの系譜の上に置かれる作品である。
注
- ^ Ricercare(伊)は探す、模索するの意。16世紀後半のかなり早い段階で即興的楽曲の意味では使われなくなり、提示主題とその模倣からなる対位法的楽曲を指すようになる。
- ^ ちなみにフランスではトッカータという曲の形式そのものは定着せず、ほとんど作曲されなかった。
- ^ ただし、ブクステフーデの作品で、「前奏曲とフーガ」、「トッカータとフーガ」といった題名のついた曲はない。
参考文献
- Caldwell, J., Toccata, Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed 2006.09.14), <http://www.grovemusic.com>
- Hammond, F., Silbiger, A., Frescobaldi, Girolamo Alessandro, Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed 2006.09.14), <http://www.grovemusic.com>
- Schott, H., Froberger, Johann Jacob, Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed 2006.09.14), <http://www.grovemusic.com>
- Snyder, K.J., Buxtehude, Dieterich, Grove Music Online, ed. L. Macy (Accessed 2006.09.14), <http://www.grovemusic.com>
- Pierre Pidoux (ed), Girolamo Frescobaldi: Orgel- und Klavierwerke III, Der erste Buch der Toccaten, Partiten usw. 1637, Bärenreiter (1949)
- H.M.ブラウン著/藤江効子,村井範子訳 「ルネサンスの音楽」 東海大学出版会 (1994)
- カーティス・プライス 編/美山良夫 監訳 「オペラの誕生と教会音楽−初期バロック」 音楽之友社 (1996)
関連項目
楽曲記事
- ヨハン・ゼバスティアン・バッハによるもの
- トッカータ (シューマン)
- ピアノのために … 第3曲
- トッカータ (プロコフィエフ)
- クープランの墓 … 第6曲
- ピアノ協奏曲第2番 (メトネル) … 第1楽章
- オーバード (プーランク) … 第1曲
- ピアノ協奏曲・2台のピアノのための協奏曲 (ヴォーン・ウィリアムズ) … 第1楽章
- セヴァーン組曲 … 第2曲『槍試合 (トッカータ)』
- ピアノ協奏曲第5番 (プロコフィエフ) … 第3楽章
- ブラジル風バッハ … 第2番第4曲・第3番第4曲・第7番第3曲・第8番第3曲
- 組曲 (デュリュフレ) … 第3曲
- ピアノ協奏曲 (ブリテン) … 第1楽章
- 管弦楽のための協奏曲 (ルトスワフスキ) … 第3楽章 (パッサカリア、トッカータとコラール)
- 交響曲第8番 (ヴォーン・ウィリアムズ) … 第4楽章
- プラハ1968年のための音楽 … 第4楽章 (トッカータとコラール)
- ドラゴンの年 … 第1楽章
- エレクトリック・ギターとオーケストラのための協奏組曲 変ホ短調『新世紀』 … 第5曲
トッカータ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 15:02 UTC 版)
「トッカータとフーガヘ長調」の記事における「トッカータ」の解説
トッカータは、ヘ長調の主音保続音上の大きな線形カノン(上記の最初の6小節)から始まる。その後カノンの旋律に基づいたペダルソロが続く。カノンは、ハ長調のドミナントでいくつかの変奏を伴って繰り返される。今度は手を入れ替え左手が右に進み、再び長いペダルソロが続く。2つの大きなカノンの展開はこの曲のの108小節を占めている。ペダルソロは60小節。コンチェルトは7つの部分から構造されている。カノンとペダルソロは、主調であるヘ長調から属調のハ長調への転調をもたらし、残りの部分は、コンチェルトの3パートの模倣や印象的な「プロトワルツ」とともに、主調への回帰を構成している。このような形式のパターンは、バッハ作品内でもユニークなものである。 ヘルマン・ケラー(英語版)は、その歓喜を次のように表現している。「冒頭の2声カノンによる直線的な構成、ペダルソロの誇らしげな落ち着き、突き刺すような和音の一撃、3つの短調主題の内面性、有名な七の和音の第三転回形での終わりの素晴らしさ、これに魅了されない人がいるだろうか?」 前奏曲としてのトッカータは、前奏曲とフーガという形式のバッハのすべての作品の中でも割合として最大のものである。それはしばしばフーガを省略した小品としても扱われる。トッカータのリズムはパスピエやミュゼットを思わせるが、その堂々とした音階はこれらの特徴を裏付けていない。 和声的な冒険性もない。2度目のペダルソロの45小節後に、ナポリの六度の第三転回形で一見セカンダリードミナントに解決する属和音がある。特に、主音は半音階で半進行し外側の長九度に移動し、低音は半音下降し予想される五度からかけ離れた動きをしている。バッハはこの強力な偽終止を作品に3度使用しているが、これが慣用的になるのはショパンやチャイコフスキーの頃になってからである。
※この「トッカータ」の解説は、「トッカータとフーガヘ長調」の解説の一部です。
「トッカータ」を含む「トッカータとフーガヘ長調」の記事については、「トッカータとフーガヘ長調」の概要を参照ください。
トッカータと同じ種類の言葉
- トッカータのページへのリンク