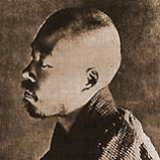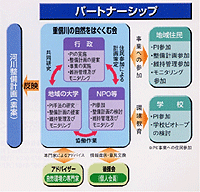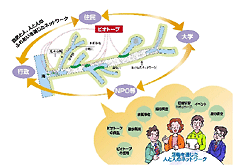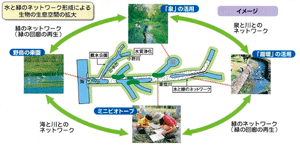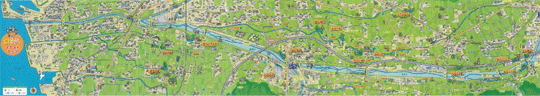しげのぶ‐がわ〔‐がは〕【重信川】
重信川
| 重信川は、愛媛県温泉郡・周桑郡・越智郡の郡境にある東三方ヶ森にその源を発し、南西流して山地を脱し、松山平野(道後平野)をほぼ西流し、石手川など支流を合流し、伊予灘に注いでいる流域面積445km2、幹川流路延長36kmの河川です。 |
 |
| 松山平野(道後平野)中心部を流れる重信川 |
| 河川概要 |
|
 ○拡大図 |
| 1.重信川の歴史 |
| "○松山市繁栄の基礎を築いた「足立重信」 重信川は、昔、伊予川と呼ばれ大雨のたびに氾濫を繰り返していました。そこで、初代松山城主 加藤嘉明が、家臣の足立重信に命じ、重信川の改修にあたらせました。重信は、霞堤や鎌投(水制)などの工法を用い、巧みに氾濫を食い止めたのです。この重信の功績を称え、伊予川を重信川と呼ぶようになったと言われています。" |
|
松山市繁栄の基礎を築いた「足立重信」 |
川に人名が当てられた例は全国でも珍しく、司馬遼太郎の「街道をゆく-南伊予・西土佐の道-」では「日本の河川で人名がついているのはこの川(重信川)だけではないか」などの記述もあります。
また、松山は、俳句の町としても有名です。最近では、全国各地から高校生が参加する俳句甲子園の開催や、町を歩けばいたるところに句碑があり、つられて一句ひねるとすぐに投函できる俳句ポストもあります。 この俳都にゆかりのある俳人としては、正岡子規、内藤鳴雪、高浜虚子らのそうそうたる名が並びます。自由律俳句で知られる漂泊の俳人、種田山頭火は晩年になって松山に定住しました。重信川や石手川にまつわる俳句も多く残されています。 「若鮎の 二手になりて 上りけり」 子規 「石手川 重信川の 青田かな」 虚子
加藤嘉明(かとうよしあきら) 加藤清正、福島正則らと共に豊臣秀吉の子飼いとして諸戦に参陣し、数々の戦功を挙げた。賤ヶ岳の戦いでは、七本槍の一人として活躍。初代松山城城主。 |
| 2.地域の中の重信川 |
| "○重信川の「いも炊き」 涼しくなった秋の河原で、大きな鍋を囲んで、月を楽しみ、酒を酌み交わす「いもたき」は、秋の伊予路の風物詩です。地域の商工会などが開催し、毎年数万人の人手があります。 ○重信川の自然をはぐくむ会 重信川のより良い自然の再生を目指し、民学官のパートナーシップで活動する会が平成14年度に発足しました。基本方針は、緑のネットワークと人のネットワークの形成で、さまざまな活動に積極的に取り組んでいます。" |
重信川の「いも炊き」と「重信川の自然をはぐくむ会」
涼しくなった秋の河原で、大鍋で煮込まれた「いもたき」を囲んで、月を楽しみ、酒を酌み交わす風流な行事は、秋の伊予路の風物詩です。調理法は、下茹でした里芋を大根、鶏肉や油揚げ、椎茸、コンニャクと一緒に大鍋で煮込むだけ。砂糖や薄口醤油、塩、みりんであっさりと上品に仕上げただし汁には、素材のうま味がたっぷりとしみ出しています。とろけるような味わいの里芋が絶品です。 重信川では、出合、森松、砥部、横河原の4箇所で、各地域の商工会などの主催により開催され毎年数万人の人手があります。
重信川では、重信川のより良い自然の再生を目指し、民・学・官のパートナーシップにより、重信川自然再生事業「いきいきネットワーク計画」の取り組みが行われています。 平成14年、15年の2年間で自然再生事業計画を策定。平成16年度より、拠点地区である砥部・高井箇所で事業に着手します。
重信川の自然をはぐくむ会は、愛媛大学工学部教授矢田部龍一会長を中心に、愛媛大学教育学部、理学部、農学部、松山東雲短期大学の教員、愛媛大学の学生が組織する「重信川エコリーダー」、重信川をフィールドに活動するNPOなど7団体などで、総勢1,000人以上の組織となっています。また、砥部・高井地区では、「松原泉と小川の再生」を計画しており、地域部会として「松原泉を再生・保全する会」が発足し、地域とともに自然の再生を目指しています。
松原泉の再生イメージ
|
| 3.重信川の自然環境 |
| "○河口「野鳥の楽園」と河川周辺の「泉」 重信川は、河川水が伏没する瀬切れが発生し、動植物には好ましい環境とはいえませんが、河口は、環境省シギ・チドリ類重要渡来地、重要湿地500に指定され、一年中たくさんの野鳥が訪れます。また、河川周辺の「泉」が、貴重な動植物のオアシスとして存在しています。" |
河口「野鳥の楽園」と河川周辺の「泉」
河口では、広大な干潟やヨシ原が形成され、水量も豊富であることから、カモメ類、冬期に渡来するカモ類や春と秋の渡りの途中に渡来するシギ・チドリ類等にとっての良好な休息地、えさ場となっています。また、この他にもヨシ原ではセッカやオオヨシキリ、水辺のサギ類、カモ類などを狙い上空を飛翔するオオタカやボラなどの魚を狙うミサゴなども見られます。
現在残されている「泉」は、これまで人とともにあり、人の手による管理が行われてきました。そこに残されている自然は人の手によって形づくられてきたと言え、いわゆる里山の自然・風景といえます。重信川周辺の「泉」の多くは、江戸時代にかんがい用水として開発されたもので、人々の暮らしの一部として脈々と引き継がれています。 現在も131箇所の泉が存在し、河川と霞堤や水路でつながり良好なビオトープネットワークを形成しています。
|
| 4.重信川の主な災害 |
|
(注:この情報は2008年2月現在のものです)
重信川
重信川
重信川
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/09 05:01 UTC 版)
| 重信川 | |
|---|---|

出合大橋上から上流側
|
|
| 水系 | 一級水系 重信川 |
| 種別 | 一級河川 |
| 延長 | 36 km |
| 平均流量 | 1.44 m3/s (山之内観測所 2000年) |
| 流域面積 | 445 km2 |
| 水源 | 東三方ヶ森(愛媛県) |
| 水源の標高 | 1,233 m |
| 河口・合流先 | 伊予灘(愛媛県) |
| 流域 |  日本 愛媛県 日本 愛媛県 |
|
|
|
重信川(しげのぶがわ)は、愛媛県中予地方を流れる一級河川重信川水系の本川。東温市付近を扇頂として広大な扇状地(道後平野)を形成している。戦国時代以前は伊予川(上流では久米川、横川)と呼ばれていた。氾濫の多い暴れ川であったと伝えられ、時代により流れを幾度も変えている。急傾斜地を水源とするため、河床に砂礫がたまりやすく、天井川であったと伝えられる。
地理
高縄半島の東三方ヶ森(標高1233m)南麓に発し南流。東温市見奈良からは向きを西に変える。松山平野(道後平野)を潤し、松山市と伊予郡松前町との境界を成しつつ伊予灘に注ぐ。
高低差の割に河川長が短いため、度々洪水に見舞われる一方、河床は砂礫層であり、流域の両岸には伏流水による湧水が多く、灌漑等に用いられてきた。河口は西日本有数の渡り鳥の渡来地となっている。
源流点
2012年12月5日、重信川の自然をはぐくむ会による調査が行われ、東三方ヶ森山頂から東北東約500mの山中にある石積み堰堤箇所を源流点とした[1]。正確な位置は標高1000メートル、北緯33度54分17秒、東経132度57分55秒(西条市丹原町田滝)であった。
歴史
典型的な扇状地河川で伏流しているので、普段は流量も少なく見えるが、降雨が続くと一気に伏流水が地上に溢れ、水害を引き起こす。
- 資料:愛媛大学による
名称の由来
もともと「伊予川」と呼ばれていたこの川は豪雨の度に氾濫していたため、文禄・慶長年間に松山城の城主・加藤嘉明が家臣の足立重信に石手川[2]とともに改修を命じた。重信川については、森松付近から流路を北に寄せ、伊予灘に流れ込む形にした。また、石手川は南西方向に流路を変えて、現在の出合と呼ばれる地点で重信川と合流させた。この重信の一連の工事によって伊予川の氾濫が収まったため、その功績を讃えるために人々は重信川と呼ぶようになった。河川名称に個人の名が付けられるのは、日本では大変珍しいとされる[3][注釈 1]。
流域の自治体
環境
地元地域の小学生(北吉井小学校など)が清掃活動を行った。北吉井小学校は5回の清掃活動を行った。南吉井小学校も積極的である。
伊予灘に流れ込む河口部には干潟が存在し、シギやチドリなどにとっての重要な生息地になっている[4]。
主な支流
- 市町名は流域の自治体。
-
内川
-
悪社川
-
御坂川(左)と砥部川(右)
-
表川
主な橋梁
- (伊予灘)
- 川口大橋(愛媛県道22号伊予松山港線)
- 出合橋(愛媛県道326号松山松前伊予線)
- (伊予鉄道郡中線)
- 出合大橋(国道56号線)
- (予讃線)
- 中川原橋(愛媛県道16号松山伊予線)
- 重信高架橋(松山自動車道)
- 重信大橋(国道33号線)
- 重信橋(愛媛県道194号久谷森松停車場線)
- 久谷大橋(愛媛県道40号松山東部環状線)
- 上村大橋
- 拝志大橋(愛媛県道209号美川松山線)
- 上重信橋
- 重信川橋(松山自動車道)
- 見奈良大橋
- 横河原橋(愛媛県道334号松山川内線)
- 新横河原橋(国道11号線)
- 大畑橋
- 御所橋
- 麓橋
- 藤之内橋(愛媛県道152号寺尾重信線)
- (東三方ヶ森)
-
川口大橋
-
重信川橋梁(予讃線)
-
重信川橋(松山自動車道)
-
拝志大橋
並行する交通
鉄道
道路
流域の観光地
出典
- ^ 西条・丹原の山中に重信川源流点を確定 愛媛新聞ONLINE(2012年12月7日) 2017年10月14日閲覧
- ^ 石手川は足立重信による付け替え前は流路が異なっており、現在のような重信川の支流ではなかった。
- ^ “松山河川国道事務所/重信川とは”. www.skr.mlit.go.jp. 2019年9月7日閲覧。
- ^ 瀬戸内海の環境データベース, 2007年, 湾灘別の環境特性及び課題特性一覧, 国土交通省
注釈
外部リンク
関連項目
固有名詞の分類
- 重信川のページへのリンク