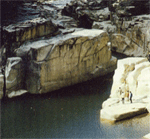いび‐がわ〔‐がは〕【揖斐川】
揖斐川
| 揖斐川は、その源を岐阜県揖斐郡藤橋村の冠山(標高1,257m)に発し、山間峡谷を流下し、岐阜県揖斐川町で濃尾平野に出て、大垣市の東部を南下し、根尾川、牧田川、多度川、肱江川等を加え、長良川と背割堤を挟み併流南下し、三重県桑名市で長良川を合わせ伊勢湾に注いでいる流域面積1,840km2(長良川流域を除く)、幹川流路延長121kmの河川です。 |
 |
| 長良川と合流し伊勢湾に注ぐ揖斐川 |
| 河川概要 |
|
 ○拡大図 |
| 1.木曽三川の歴史 |
| "木曽三川の歴史は、御囲堤、輪中、宝暦治水など洪水との闘いの歴史です。明治になって、オランダ人技師ヨハネス・デレーケらにより近代土木による三川分流工事が完成し、現在の木曽三川の原形がつくられました。" |
|
特有の歴史、先人の知恵の活用 |
| 2.地域の中の木曽三川 |
| "木曽三川は寝覚の床や飛水峡、恵那峡、養老の滝などに代表される景勝地に恵まれている他、鵜飼いや花火大会、また、環境省選定の水浴場88選唯一の河川の水浴場を持つなど、すぐれた自然環境や歴史的文化遺産を活かし、様々な利用がなされています。" |
地域社会とのつながり
【名勝】 木曽川では、飛騨木曽国定公園の中にあり東洋のライン川といわれる日本ライン下りが行われ、その観光船下りのおもしろさは、本場のライン下りを超えると言われています。 また、木曽三川は景勝地にも大変恵まれており、巨大な花崗岩が木曽川の激流に刻まれてできた自然の彫刻であり、浦島太郎が竜宮城から帰った後美しい景色が気に入り、そこに住み、玉手箱を開けたとの伝説のある名勝史跡天然記念物の木曽川の寝覚の床や国の天然記念物に指定されている日本最大級の甌穴群を有する飛水峡、奇岩怪石からなる恵那峡、名水百選にも選ばれ、老を養う若変り水としての不思議な水にまつわる伝説を有する養老の滝などがあります。 【清流】 長良川は、豊富なアユ資源に恵まれ、我が国唯一の宮内庁職員としての鵜匠による鵜飼いが行われています。また、自然景観や水質に優れており、中流域(美濃市、関市、岐阜市)は、環境省選定の名水百選に選ばれ、清流長良川に育まれた美濃和紙づくりは1300年の伝統を持ち、国の無形文化財に指定されています。 岐阜市においては、環境省選定の水浴場88選唯一の河川の水浴場にも選ばれています。岐阜市長良川の花火大会は、2週連続して2回行われ、全国から見物客が集まる程、規模も大きく、風情があります。他にもイベントが数多く行われ、多くの市民や観光客に親しまれています。 揖斐川では、河川の一定水域を竹材などを用いて遮断しそこに落ちる鮎を捕獲する漁法のヤナが観光として盛んに行われ、鮎をつかまえる子どもなど観光客で賑わっています。 |
| 3.木曽三川の自然環境 |
| "木曽三川に生息する魚類の種類数はわが国最大であり、淡水魚の天然記念物であるイタセンパラ、ネコギギ、希少種のハリヨが生息しています。また、下流部から河口域にかけては、ほぼ全域が感潮区間であり、汽水域を好むヤマトシジミの我が国有数の生息地です。" |
【多様な植生】 これらの低平地は、水田、水路、池、湿地、河川など豊かな水環境を有し、生息する魚類の種類数は、わが国最大であり、淡水魚の天然記念物であるイタセンパラ、ネコギギや特別天然記念物のオオサンショウウオ、希少種のハリヨが生息するなど希少な植物と合わせて自然豊かな、我が国を代表する河川です。 木曽川の12~24km付近には明治改修で整備されたケレップ水制によりワンドが形成され、希少な植物であるタコノアシや昆虫ではコフキトンボ、チョウトンボ、コシアキトンボ、二枚貝の大きさとして世界一と思われるイシガイやドブガイが生息するなど、良好な環境が形成されています。また、下流部から河口域にかけては、ほぼ全域が感潮区間であり、汽水域を好むヤマトシジミの我が国有数の生息地となっており、休日には多くの人が干潮狩りを楽しんでいます。 【トンボ天国】 木曽川の三派川地区では、河跡湖であり42種類のトンボや多くの野鳥などが見られる笠松町のトンボ天国に代表される広大で豊かな河川環境が広がり、祖父江地区では、我が国でも珍しい、河川砂丘である祖父江砂丘がみられます。 |
| 4.揖斐川の主な災害 |
|
主要な災害 ■揖斐川
|
(注:この情報は2008年2月現在のものです)
揖斐川
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/10 18:31 UTC 版)
| 揖斐川 | |
|---|---|

福岡大橋東詰から北望(海津市)
|
|
| 水系 | 一級水系 木曽川 |
| 種別 | 一級河川 |
| 延長 | 121 km |
| 平均流量 | 84.28 m3/s (万石観測所1961年~2004年) |
| 流域面積 | 1840 km2 |
| 水源 | 冠山(岐阜県揖斐郡揖斐川町) |
| 水源の標高 | 1257 m |
| 河口・合流先 | 伊勢湾(三重県桑名市) |
| 流域 |  日本 日本岐阜県・三重県 |
|
|
|
揖斐川(いびがわ)は、岐阜県から三重県へと流れる木曽川水系の一級河川である。いわゆる木曽三川の1つに数えられる。
地理

岐阜県揖斐郡揖斐川町の冠山に源を発し、岐阜県内の福井県や滋賀県との県境付近から集水しながら、おおむね南流している。途中、一部で木曽川、長良川と平行して流れ、河口附近の三重県桑名市で長良川と合流し、そのまま伊勢湾に注ぐ。下流部は愛知県との県境に近いものの、愛知県内には入らない。元々は大垣市内を南北に流れる杭瀬川が揖斐川の本流だったが、戦国時代の1530年に発生した大洪水で呂久川と呼ばれていた現在の揖斐川筋に流れが変わり[1][2]、今日に至っている。
大規模改修工事

揖斐川はかつて下流域で木曽川・揖斐川と合流・分流を繰り返していた。江戸時代の宝暦治水で長良川・木曽川との間に大榑川洗堰や油島締切堤が建造されたのに続き、明治の木曽三川分流工事で木曽川本川とは完全に流路が分けられるが、現在でも揖斐川は「木曽川水系の支流」と位置づけられている。また、木曽三川分流工事では岐阜県と三重県の県境付近にあった派川の香取川が廃川となった
木曽三川分流工事後も揖斐川右岸の支川を主として河床上昇が進行しており、水害が絶えなかった。大正から昭和にかけての木曽川上流改修工事では揖斐川本川とともに粕川・牧田川などの右岸支川および根尾川でも改修工事が行われた。

語源
揖斐荘(現揖斐川町)を貫流して流下する河川として名付けられたと考えられている[3]。「揖斐」は大昔、水田へ水を引く「井樋」(イビ)から名付けられたと見られる[4]。
流域の自治体
主な災害
主な支流
主な河川施設
| 揖斐川・概略図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 揖斐川本川
- 根尾川
- 根尾東谷川
- 上大須ダム(ロックフィルダム、中部電力株式会社) 本巣市
- 坂内川
-
西平ダム
-
川上取水堰
文化
揖斐川は方言の境界線
- 下流域では揖斐川を挟んで、三重県の旧桑名市が近畿方言(京阪式アクセント)と岐阜・愛知方言(東京式アクセント)、三重県の旧桑名郡長島町(東京式アクセント)の境界線である。
- 中流域の大垣市内では、1530年の大洪水まで揖斐川の本流であった杭瀬川を挟んで住民の話す言葉のアクセントが異なっており、杭瀬川以東は東京式アクセント、杭瀬川以西の地域は垂井式アクセント及び京阪式アクセントである。
関連作品
- 『ほたるのふる里』
- 2003年にリリースされた石原詢子の楽曲。歌詞に揖斐川が登場する[6]。石原は本作品の表題曲『ふたり傘』で第54回NHK紅白歌合戦に出場した。
関連項目
- 養老の滝 - 支流にある滝
- イビデンの水力発電所 - 揖斐川にあるイビデンの水力発電所について
脚注
外部リンク
揖斐川と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 揖斐川のページへのリンク