ホン
ほん【反/×叛】
読み方:ほん
〈反〉⇒はん
〈叛〉⇒はん
ほん【▽品】
読み方:ほん
⇒ひん
ほん【▽品】
読み方:ほん
 [名]
[名]
2 日本で、親王・内親王に与えられた位階。一品から四品まであり、無位の者は無品(むほん)とよばれた。品位(ほんい)。
 [接尾]上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。
[接尾]上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。
1 仏教で、極楽往生する者の能力や性質などを等級に分ける語。上中下に分け、さらに、それぞれを上中下に分ける。→九品(くほん)
ほん【奔】
ほん【本】
読み方:ほん
[音]ホン(呉)(漢) [訓]もと
![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈ホン〉
〈ホン〉
1 草木の根や茎。植物。「本草(ほんぞう)/草本・藤本(とうほん)・木本・禾本(かほん)科」
2 物事の根源。もと。「本源・本質・本性・本能・本末/元本・基本・根本・資本・大本・張本・抜本」
3 中心となる部分。主となる。「本業・本社・本州・本宅・本店・本部・本論」
4 当の。この。わが。「本案・本官・本件・本日・本書・本人・本邦」
5 正式の。本当の。「本意・本妻・本式・本名・本物(ほんもの)」
7 書物。文書。「異本・絵本・刊本・脚本・原本・古本(こほん・ふるほん)・写本・春本・正本(しょうほん・せいほん)・抄本・新本・製本・謄本・読本・配本・副本・返本・和本・単行本」
[名のり]なり・はじめ
ほん【本】
読み方:ほん
 [名]
[名]
3 模範とすべきもの。手本。「手習いの—とする」「行儀作法の—になる」
4 もととなるもの。主となるもの。根本。また、本分。「学業を—とする」
 [接頭]名詞に付く。
[接頭]名詞に付く。
1 今、現に問題にしているもの、当面のものであることを表す。この。「—議案」「—大会」
2 それがいま話している自分にかかわるものであることを表す。「—大臣としては」
 [接尾]助数詞。漢語の数詞に付く。上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。
[接尾]助数詞。漢語の数詞に付く。上に来る語によっては「ぼん」「ぽん」となる。
1 長い物、細長い棒状のものなどを数えるのに用いる。「鉛筆五—」「二—の道路」
2 剣道や柔道などで、技(わざ)の数を数えるのに用いる。「二—を先取する」
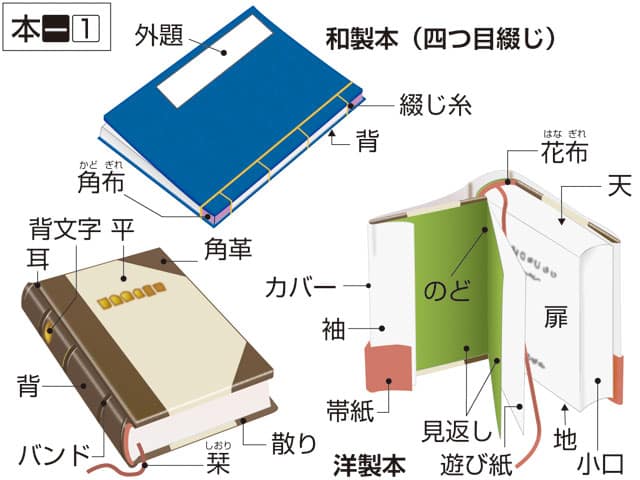
ほん【翻〔飜〕】
ホン
ホン
本
本
本
本
本
ホン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/17 09:52 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2024年6月)
|
ホンは、人が音に感じる大きさを表すための単位であり、日本においては以下の2つの量の単位として用いられた[1]。
- 音の大きさのレベル(ラウドネスレベル)の単位である「フォン」(phon)。騒音レベルの「ホン」とは使い分けられる[2]。(→「#ラウドネスレベル」)
- 音圧レベルを人間の聴覚を考慮した特性曲線により重みづけして求められる騒音レベルの単位としてかつて日本で用いられていた「ホン」。「フォン」(phon)とは異なる[3]。1997年(平成9年)9月30日までは、計量法における法定計量単位であった(計量法に基づく計量単位一覧#廃止された法定計量単位)。それ以降は、非法定計量単位[注釈 1]となっている[4]。(→「#騒音レベル」)
上の2つはいずれも、
という特徴を持ち、時に混同されるが、ラウドネスレベルの「フォン」と騒音レベルの「ホン」は異なる定義を持つ[4]。
ラウドネスレベル

フォン (phon) は、音の大きさ(ラウドネス)のレベル(ラウドネスレベル)の単位。別名ホン、ホーン[5]。
周波数1000ヘルツ[Hz]の純音のフォン[phon]は、その音圧レベル(単位:デシベル[dB])に等しい。これ以外の周波数のフォン値は、同じラウドネスに聞こえる1000ヘルツの純音の音圧レベルに等しい。したがって、同じフォンの音は(個人差等もあるがほぼ)同じ大きさに聞こえる。
音圧レベルのdB値とフォンの関係は等ラウドネス曲線に一致するはずだが、実際には測定条件や個人差などの違いにより、研究者ごとに異なる等ラウドネス曲線が導き出されている。フォンの算出には、ISO 226:2003で規格化された等ラウドネス曲線を使う。
なお、等ラウドネス曲線が等間隔でないため、騒音レベルとは異なり、同じ周波数で音圧レベルが1デシベル増えてもラウドネスレベルが1フォン増えるとは限らない。
ラウドネス「レベル」ではない、ラウドネスの単位にソーン(sone)がある。フォンとソーンには「フォン[phon] ÷ 10 - 4 = log2ソーン[sone]」の関係がある。ラウドネスはISO532で規格化されている。
騒音レベル

平坦特性をZ特性といい、A,C特性は等ラウドネス曲線のそれぞれ60,100phonに近似した重みづけである。その中間のB特性と、航空機騒音評価のために提案されたD特性は音源の改善により用いられなくなった[6]。
ホンは、騒音レベルを表すためにかつて用いられていた日本特有の単位であり、現在は「ホン」ではなくデシベル[dB]が騒音レベルの単位として用いられる[1]。
騒音レベルは、周波数ごとに定められた特性値を音圧レベルの値(単位:dB)に足して得られる。音圧で考えれば、周波数ごとに定められた値を掛けていることになる。 特性には、IEC 61672:2003で規格化されたA特性(または周波数重み付けA)、B特性(ほとんど使わない)、C特性があり、それらを使って得られた騒音レベルは、かつては「ホン(A)」、「ホン(B)」、「ホン(C)」で表された。ただしこの意味でのホンは、計量法により1997年(平成9年)9月30日で廃止され、現在は単にデシベル(dB)を使う。
かつてはA特性であることを明示する場合にdB(A)、dBAなどと書いていたが、現在は単にdBとだけ書く。なぜならば、ISOやJISのJIS Z8203[7]では、単位記号 (dB) に余計な記号を付けることは推奨されないからである。
騒音は多数の周波数の音が混合しているため、実際の測定では、騒音を周波数分解して、それぞれの周波数ごとの音圧に特性のデシベルを比に換算した値を掛け、それらを足し合わせてデシベルに換算する。
なお、騒音レベルは聴覚補正はされているが、一般的に騒音計(サウンドレベルメータ)で測定されることから、電気回路化が容易であるように、特性が実際の等ラウドネス曲線より単純な曲線であることと、デシベルでの単なる加減算であることから、ラウドネスレベルとはあまり一致せず、同じデシベル値を持つ騒音レベルでも、周波数の違いにより同じ大きさに聞こえるとは限らない。また、単なる加減算であるため、同じ周波数なら音圧が1dB増えれば騒音レベルも1dB増える。 また、騒音計での騒音レベル測定においては、通常、レベル化する際には時間的に平滑化するために時間重み特性をかける。(→音圧#実効値の時間変化)
脚注
注釈
出典
参考文献
関連項目
ホン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/04 04:31 UTC 版)
「ディエンビエンフー (漫画)」の記事における「ホン」の解説
プレイメ基地攻略5日前に脱走し、トンの隊に入隊した脱走兵。人を殺すことに恐れを抱いている。ヤーボによって口に手榴弾を詰め込まれ、爆死する。
※この「ホン」の解説は、「ディエンビエンフー (漫画)」の解説の一部です。
「ホン」を含む「ディエンビエンフー (漫画)」の記事については、「ディエンビエンフー (漫画)」の概要を参照ください。
倴
倴 |
|
呠
呠 |
|
奙
奙 |
|
泍
渀
苯
「ホン」の例文・使い方・用例・文例
- プッシュホン
- ヘッドホンでレコードを聴いた
- ホントに頭が良い
- それはホントに体に悪い
- 事務所の出入り口にインターホンが設置された。
- オフィスのセキュリティ強化のためにドアホンを設置した。
- キャッチホンで電話を受けるにはどうすればいい?
- 英語のイヤホンガイドやパンフレットがご利用いただけます。
- 先日はR2 Masterヘッドホンを2 つご注文いただき、ありがとうございました。
- R2 ヘッドホンはオーダーメイドですので、発送されるまでに約3 週間かかります。
- お客様は雑音のないコードをご希望されたので、追加で1つにつき15ドルが、2つのヘッドホンの合計金額に加算されます。
- また、ご注文の際に指定いただいたように、ヘッドホンを2 つの別々の場所に発送する準備もできております。
- 場所の1 つは海外ですので、ヘッドホンの1 つには、国内送料10 ドルに加えて12ドルが必要です。
- 彼はスピーカーホンを通して私たちに話しかけた。
- 男たちはみんなホンブルク帽 をかぶっていた。
- 彼女はその酒場でホンキートンク調の音楽を演奏した。
- 祖母はホンキートンク調の音楽を聴くのが好きだ。
- 彼はホンジュラスの市民権を認められた。
- 私はその時ヘッドホンをつけていた。
- ホンダの創業者本田宗一郎は日本の自動車産業における最も偉大なイノベータの一人だった。
ホンと同じ種類の言葉
- >> 「ホン」を含む用語の索引
- ホンのページへのリンク
![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈もと〉「
〈もと〉「



