ヘラー:3つのノクターン
ヘラー:3つのノクターン
ショパン:3つのノクターン (第1-3番)
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| ショパン:3つのノクターン (第1-3番) | 3 Nocturnes (b:/Es:/H:) Op.9 CT108-110 | 作曲年: 1830-31年 出版年: 1832年 初版出版地/出版社: Leipzig, Paris, London 献呈先: Mme Camille Pleyer |
| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 第1番 変ロ短調 No.1 h-moll op.9-1 | 5分30秒 |
|
| 2 | 第2番 変ホ長調 No.2 Es-dur op.9-2 | 3分30秒 |
|
| 3 | 第3番 ロ長調 No.3 H-dur op.9-3 | 6分30秒 |
|
作品解説
《3つのノクターン》作品9
これら3曲は、ショパンが最初に出版したノクターンである。成立年代は諸説あるが、1830年からショパンがパリに到着する31年にかけて作曲されたとする見解が大勢を占める。楽譜は、パリ(M. Schlesinger, 1833)、ライプツィヒ(Kistner, 1833)、ロンドン(Wessel, 1833)の3都市で初めて出版された。楽器製造社カミーユ・プレイエルの妻で著名なピアニストだったカミーユ・モーク(マリー・モーク, 1811-1875)に献呈。
Nocturne Op.9 No.1
ショパンが折に触れて作曲し続けたノクターンの中で、最初に出版された曲集の第1曲を飾る作品。拡大された中間部を持つ三部形式で書かれている。最初の18小節で、情緒豊かで起伏に富んだ旋律が右手で歌われるが、ここで、ショパンは強弱やニュアンスの指示を事細かに書いている。例えば、3小節目では、右手が速い装飾的パッセージを弾くにも関わらず、スタッカートのある音とない音が書き分けられている(譜例1)。
譜例1 第3~5小節

また、第15、16小節では、左手の伴奏型の中の音を押えたままにして、ペダルを踏み変えても、響きが途切れないようにする、「フィンガー・ペダル」の指示が見られる(ベートーヴェンの《ピアノ・ソナタ》Op.31-2等に先例が見られる)。
譜例2 第15~16小節 各小節の左手4~6拍目のFがフィンガー・ペダル
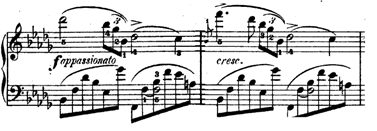
19小節目からは、変ニ長調の中間部に入る。ここに入って32小節間は、延々右手がオクターヴでメロディーを弾くが、そこにはpppやsotto voceといった静けさを求める指示と、オクターヴによる前打音(第30小節)のような御し難いテクニックが同居しているため、美しく歌わせるためには、高度なコントロール能力が必要である。中間部にあたるこの32小節間は、a-a’- a-a’- b-a’- b-a’(リピート記号を使わずに書かれている)の二部形式で書かれている。a’で突然半音上のニ長調に転調したかと思うと直ちに元の変ニ長調に戻り、更にそこで突然音量がfになるという、分裂的な音楽の進行が特に耳を引く。このような遠隔調への転調は、当時の即興実践を反映した幻想曲や即興曲のようなジャンルで見られるものである。譜例3に示すような和声の動きは、理論というよりは、むしろ偶然的な手の動きの産物であろう。概して、このような鍵盤を這うような手の動きがショパンに独自の和声語法の源泉となっている。
譜例3 第23~26小節 第24小節目にニ長調への半音階的転調が見られる
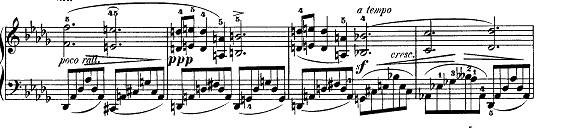
続く8小節では、変ニ長調の主和音にcesの加わった、変ト長調の属七の和音の上で新しいテーマが出てくるが、旋律は第3音のない同じ分散和音の上で奏でられる(この空虚五度の伴奏は同じ和音のまま16小節間も続く)。完全5度の連続による伴奏は、ミュゼット(バグパイプ)を想起させる。さらに、その上で、フルートに似つかわしい旋律が演奏される。
譜例4 第51~54小節
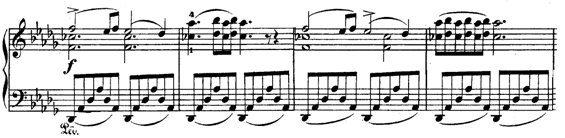
2小節のブリッジを経て、もう1度同じテーマが少し形を変えて現れるが、フルート風の旋律は、今度はホルンの音型を模した二つの声部となって現れる(実際、ここにホルン五度を聴くことができる)。
譜例5 第61~64小節
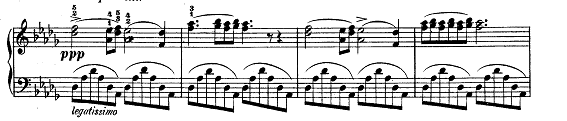
フルート、ホルンは、いずれも田園風景を描く際に象徴的に使用される楽器であり、ミュゼットの和音は田舎の土俗的な雰囲気を出すためによく用いられる。つまり、この16小節は、束の間のパストラールをとみなすことができるのである。
田園風景過ぎ去ると、音楽は変ト長調に向かうように聴こえるが、第67小節から、伴奏型だけが繰り返される中で転調が生じ、主調である変ロ短調に戻り、最初のテーマの短縮された形での再現となる。79小節目後半のモチーフを何度も繰り返し、最後は突然感情が爆発したかのように、高いes-gesから始まる、強烈な不協和音(主音上に置かれた第5音下方変位の属九)による下降音型を経て、変ロ長調の和音連打で静かに終わるが、最後から2番目の音には倚音のgesがあるといった具合に、最後まで、どこか煮え切らないままである。
譜例6 最後の4小節。最初の小節でb・ces・aが衝突し強烈な響きを作っている。

(林川 崇)
Nocturne Op.9 No.2
言うまでもなく、ショパンのノクターンの中で最も知られたもので、ショパンの死後、ヴァイオリン、チェロ、声楽用などの編曲が盛んに作られた。
曲のフレーズは最後の2小節を除けばすべて4小節のフレーズから成っており、以下のように図式化される。

全体を通じて、左手が一貫して同じ伴奏型を続け、その上で右手の旋律が歌われる。変ロ長調のBの部分は2回ともほぼ同じ形で表れるが、AおよびCの部分は出てくるたびに違った装飾が施されている。このような旋律の装飾法は、当時のオペラ・アリアの演奏習慣に由来するもので、声楽を愛したショパンはこれを積極的にピアノ演奏に取り入れた。この装飾は、ショパン自身、毎回違うように弾いたらしく、そうした出版譜と違った変奏が、あるものはショパン自身の演奏を書き取ったものとして、またあるものはショパンが弟子の楽譜に書きこんだものとして、多数残されている(こうした資料が多く残っているケースは、ショパン作品にあっては珍しい。中には、右手が最高音域から3度の半音階で下降するというものもある)。ドラクロワをはじめとするショパンの取り巻きたちは、この即興性や演奏のたびに音色を自在に変化させる能力にショパンの才能を認めている。こうした彼の演奏習慣は、「楽譜通り」の演奏を基本とする演奏美学と大きく異なる点である。
平明なAに対し、Bの部分では、1小節目で、変ロ長調のVの第一転回形に行ったかと思うと、次の小節で、バスが半音下がって変ホ長調のIV-Iと進行(譜例1, 第10小節)し、また、バスが半音上がって変ロ長調に戻り、安定したかと思うとAに戻る直前で唐突に半音階的和声(譜例2)が現れるなど、何か彷徨うような和声がコントラストを成している。ショパン作品全般を特徴づける「彷徨う和声」もやはり、ある程度はショパンの即興的なセンスから導きだされたものであろう。
譜例1 第9小節~第10小節
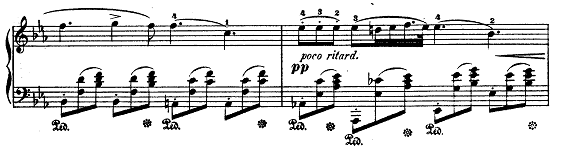
譜例2 第11~12小節
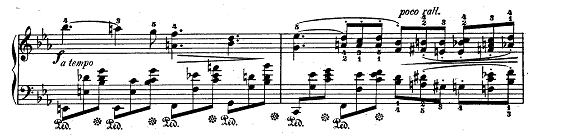
(林川 崇)
Nocturne Op.9 No.3
ショパンのノクターンの中で唯一、Allegrettoという快速なテンポが指示された曲であり、また小節数は彼のノクターンの中で最も多い(158小節)。形式は、他の多くのノクターンと同じくA-B-A’-コーダという三部形式をとるが、Aは更に、a-a-b-bに分けられる。aの出だしは、歌うというよりは飛び跳ねるような軽快な主題であり、「おどけて」Scherzandoという楽想用語が用いられている。aの13小節目で、それまで飛び跳ねていた所に、突如espressivoと指示された嬰ヘ長調の歌が入ってくるが、すぐにロ長調に戻って落ち着く。この主題が装飾を増やした形でもう1度繰り返されると、一貫してなだらかな歌が歌われる嬰へ長調のbに入る(第41~64小節)。このbの最後の8小節は、aのそれがそのまま使われている。bもまた、装飾を増やして繰り返される。第87小節目に現れる最後の上昇音型にはppの指示があり、夢見心地な雰囲気を作るが、その最後の音には、それまで、長調だったdis(譜例1)に代わって、短調の、しかもアクセント記号の付いたdが置かれ(譜例2)、音楽は、突然聴き手を突き放すように、2/2拍子の激情的なロ短調の中間部に入る。
譜例1 第63~64小節

譜例2 第87~88小節 Aの末尾とBの入り
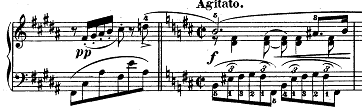
ここでは、強弱記号が頻繁に入れ替わり、行き場のない不安定感を醸し出す。そして、感情が頂点まで高まり、ロ短調のドッペルドミナントに終止すると、我に帰ったかのように、Aの最後の2小節が現れる(譜例3)。
譜例3 第129~133小節 Bの末尾とAの回帰

ここでは、前述の上昇音型の最後の音は、dの異名同音のcisisだが、その時点では音楽はまだ短調のため、暗い展開が続くかの印象が与えられる(譜例3、3小節目)。しかし、そのcisisを経過音として、明るい主部に戻り、aの部分が再現される。
譜例1、譜例2に示した上昇音型のモチーフは、第150小節において11連符に拡大され、1オクターヴ上まで衝動的に駆け上がり(譜例4)、激しさを増したところで、短いコーダに入る。
譜例4 第148~151小節

そしてすぐV度に落ち着くと、第2番同様、右手のカデンツァが登場し、最後は、それまでと全く曲想の異なるAdagio、4/4拍子の両手のゆったりとしたアルペジオで終わる。
ショパン:3つのノクターン (第4-6番)
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| ショパン:3つのノクターン (第4-6番) | 3 Nocturnes (F:/Fis:/g:) Op.15 CT111-113 | 作曲年: 1830-33年 出版年: 1833年 初版出版地/出版社: Leipzig, Paris, London 献呈先: Ferdinand Hiller |
| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 第4番 ヘ長調 No.4 F dur op.15-1 | 3分30秒 |
|
| 2 | 第5番 嬰ヘ長調 No.5 Fis dur op.15-2 | 3分30秒 |
|
| 3 | 第6番 ト短調 No.6 g moll op.15-3 | 4分00秒 |
|
作品解説
《3つのノクターン》作品15
この3曲のノクターンのうち、第1番と第2番は1831年又は32年に、第3番は1833年に作曲された。楽譜は、パリ(M. Schlesinger, 1833)、ライプツィヒ(Breitkopf und Härtel, 1834)、ロンドン(Wessel, 1834)で初めて出版された。この曲を献呈されたドイツ人0005ピアニスト兼作曲家フェルディナント・ヒラー(1811-1885)は、ショパンの信頼する数少ない
音楽家で親友の一人で、演奏会で共演もしている。あまり知られていないが、ショパンの《練習曲》作品10のイギリス初版表紙の献辞には、リストとならんでヒラーの名前が記載されており、1830年代のショパンの取り巻きのなかでは特に重要な人物である。
Nocturne Op.15 No.1
ショパンのノクターンによく見られる三部形式(A-B-B’-A’)で書かれているが、AとA’は、後者において装飾が増え、短い結句が付いている以外はほとんど同じといって良い。BとB’は展開の仕方こそ異なるものの、最初の4小節は全く一緒であり、12小節ずつの構造になっている点、最後の小節が6/8拍子になる点に、シンメトリーを意識した構造が認められる。このような厳格なシンメトリー構造は、ショパンのノクターンでは他に見られない。
Aでは、左手の三連符の伴奏に乗って、起伏の少ない淡白なメロディーが歌われる。速度表示にAndante cantabileとありながら、表情にsemplice e tranquilloとあるのは、恐らく、歌うといっても、本当に歌うような大きな抑揚は付けずに演奏されることを意味するのだと思われる。こうした楽想指示には、マイアベーアのグランド・オペラで歌われるような、大仰な歌い回しを好まなかったショパンの演奏美学を垣間見ることもできよう。22小節目で、フレーズが収束すると思った所でそこから、冒頭の主題が再び出て歌い始めるが、3小節で歌は「消え行くように」smorzandという指示とともに力尽き、中断される(譜例1)。
譜例1 第21~24小節、Aの末尾

「炎を伴って」con fuocoと記された中間部(B, B’)では、右手が重音の伴奏を弾く中で、左手が波打つような旋律を担い、その波は次第に大きくなる(最初の2小節でその幅は2オクターヴ、その次の2小節では2オクターヴと5度になる)。それまで強弱指定はpしか用いられず、淡々と歌が進行していたのに対し、Bはfで開始され、左手の主要モチーフにはクレッシェンド記号とアクセント記号が置かれるなど、主部とは極端な程のコントラストが作られている。ショパンのノクターンにおいて、これほど様式的なコントラストが生み出される曲は他に見当たらない。
譜例2 第25~26小節、Bの冒頭
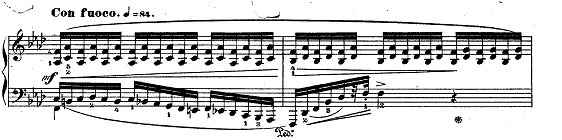
この右手の重音は、ショパンの作品の中にはあまり見られないテクニックであり、むしろ30年代のカルクブレンナーの書法に近付いている。ショパン自身、簡略化した音型を弟子のJ.スターリング(作品55の解説参照)の楽譜に書き込んでいる。A’は、殆どAの再現であり、A同様、70小節目でフレーズが収束すると思わせた所でそこから、冒頭の主題が現れわずか5小節の結句に入る。ここには、1回目にはなかったppが見られるが、それにもかかわらず、diminuendo、rallentando、smorzandoの3つの指示が念を押すように書かれている。曲尾は、テンポ、音量ともに落ちていき、2つの分散和音で、殆ど消え入るように曲は終わる。(林川 崇)
Nocturne Op.15 No.2
この曲もまた三部形式(A-B-A’-コーダ)を取っているが、シンメトリカルな第1曲とは違い、最初のAとBの間に推移部がおかれ、また、再現部のA’は短縮されるといった具合に、実際の構成は著しく対称性を欠いている。Aは、それぞれ8小節からなるa-a’-推移部に分かれている。書法としては、他の多くのノクターン同様、左手の伴奏の上で旋律が歌うという体裁をとるが、aとa’では、それぞれの楽節の最後で、弦楽四重奏を思わせるポリフォニックな動きがみられる(譜例1、第7~8小節)。
譜例1 第5~8小節、 aの後半
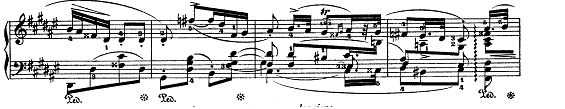
続く8小節の推移部では、溜息のような装飾を伴う半音階的な和声進行を経て、並行調である嬰ニ短調のドミナントに落ち着くが、すぐ主調のドミナントに戻り、Doppio movimento(倍の速さで)と指示された中間部Bが開始される。ここでは、右手の5連符のアラベスクの中に、オクターヴのメロディーの上声・下声、それと装飾の3つの声部がわざわざ書き分けられている。
譜例2 第25~28小節(B冒頭)
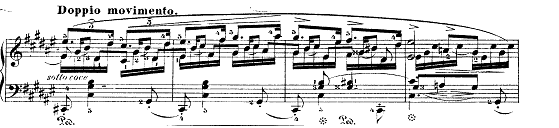
このようなリズムの記譜は、当時としては極めて珍しく、ショパンは音域の異なる音のまとまりを、異なる音色、強弱で引き分けていたということを暗示している。同じことをショパンは《24の前奏曲》作品28の第1番でも試みている。
最初の8小節では低音に、V度の主音であるcisが保持されている。33小節からは、長三度上のイ長調に転調し同じパターンが繰り返されるが、音域が上がるだけでなく、今度はV7の7度音であるDが保持されるため緊張感はいっそう高まる。演奏からは聞き取りにくいが、ここからは右手のリズムパターンが5連符の連続から付点16分音符+32分音符+三連符の連続に変化している(譜例3)。
譜例3 第33小節~36小節
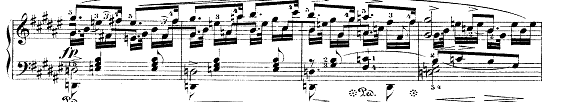
この記譜の変化によって、各拍の後半が切迫し、より緊張感が高まる。こうした記譜の複雑さからは、自身の演奏の微妙なアゴーギグを可能な限り正確に書きとめよとする強い意志が感じ取られる。だが、紙に図形として写すことのできる情報は極めて限られているのであり、実際のショパンの演奏は、単に楽譜を音にする以上に多様なニュアンス、音色に富んでいたであろう。さて、39小節目で、イ長調の並行調であり、かつ主調の嬰ヘ長調の同主調でもある嬰へ短調のV度が響くと、右手は下降を続け、音楽が落ち着きを取り戻し再現部に入る。A’はAの時の半分に短縮されている代わりに、55~57小節目にかけて、華麗な装飾による見せ場が用意される。これが終わると、主和音のみで構成される5小節のコーダで曲は閉じられる。(林川 崇)
Nocturne Op.15 No.3
ショパンのノクターンの中でも異色の1曲で、歌唱的な部分(第1~88小節, 以下A)-コラール風の部分(第89~120小節, 以下B)-マズルカ風の部分(第121~152小節, 以下C)の3セクションからなる。Aでは旋律が常にト短調で提示され冒頭に提示される12小節の旋律が、リズム、伴奏の和声を微妙に変化させながら4回現れる。そのあとに転調域が続くが、ここでは曲冒頭の2小節および第7~第8小節に現れる2種類のリズム動機(譜例1)を利用しながら嬰ヘ長調などの遠隔調に転調する。
譜例1 冒頭8小節
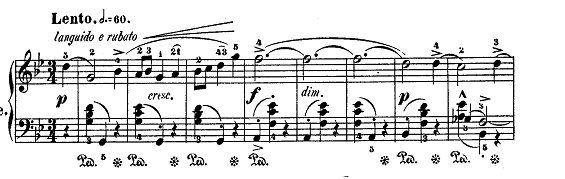
こうした執拗な反復は、どこかショパンと同年生まれのシューマンを想起させる。事実、シューマンは、この曲を気に入り、これに基づく変奏曲を作ろうとした(但し、第3変奏の途中までしか完成されなかった)。
第77小節でクライマックスに達すると半音階的和声の連続と冒頭動機が交替しながら音域を一気に下げ、低音のCisに至り、これが単音で連打される。
譜例2 Cisの反復とコラールの出だし
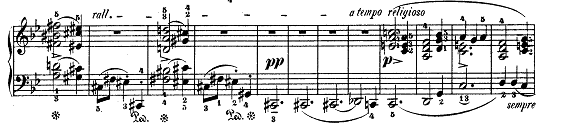
このCisは、主音のGと増4度の関係にある。西洋芸術音楽の文脈において、増4度は古くから悪魔の音程として忌み嫌われてきた。Cis音は、すでに63小節からバスのペダル音として何度も打ち鳴らされ強調されている。Cisに支配された25小節間(第63~87小節)の直後にreligioso(宗教的に)と指示された天上的なヘ長調コラールが来るのは、意味深長である。ここにみる邪悪さと救済をイメージさせる神聖性の対比は、恐らくショパンの周到な計算によるものであり、この解釈によって初めてなぜショパンがト短調から♯系の遠隔調に逸れていったのかが合理的に説明できる。cisを導く転調のセクションは、視覚的にもとげとげしい。♯の多い調に転じるにもかかわらず、調号を用いないのはそのような効果を狙っているからであろう。こうした視覚効果はバッハ、ヘンデルからハイドンに至るまで、ショパン以前の宗教曲などで用いられた一種の音画tone paintingという手法だが、ショパンはこれら「大作曲家」の作品にみられる伝統的な作曲技法を熟知していたのではないだろうか?
譜例3 Bに先立つ転調域の一節(第63小節目よりCisのペダル音が始まる)
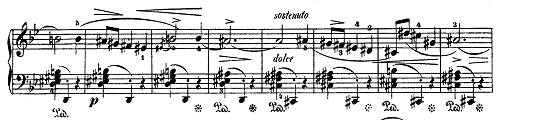
コラールが終わると、突然、世俗の舞踊であるマズルカを想起させる部分に移行する(譜例4)。
譜例4 マズルカ風のセクション
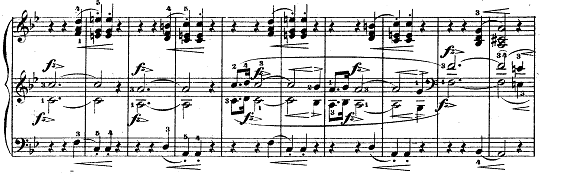
天上から地上へと移行するこのセクションでは、両手のユニゾンとそれを取り巻く刻みの掛け合いが印象的である。テクニック的には、内声を指で押さえたまま(左手は親指だが、右手は中指または薬指で!)、刻みの和音をスタッカートで弾かなければならず、演奏は容易ではない(無論、当時のピアノにソステヌート・ペダルは装備されていなかった)。同じ形を繰り返しながら次第に音に気を下げ、ニ短調に落ち着くかと思わせておいたところで、曲は唐突にト短調のコラールになり、直ちに曲は閉じられる。この短いノクターンには、何か壮大なドラマが秘められているようである。
フォーレ:3つのノクターン
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| フォーレ:3つのノクターン | Nocturne No.1 Op.33 | 作曲年: 1875-1883年 出版年: 1883年 初版出版地/出版社: Hamelle |
| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 変ホ短調 Es dur Op.33-1 | 7分00秒 | No Image |
| 2 | ロ長調 H dur Op.33-2 | 6分00秒 | No Image |
| 3 | 変イ長調 As dur Op.33-3 | 5分00秒 | No Image |
作品解説
第1曲目のレント、変ホ短調の初演は、1885年2月の国民音楽協会にてマリ・ジャエルにより行われている。ジャエル(1846~1925)は、モシェレスらにピアノを、フランクとサン=サーンスに作曲を師事した音楽家。この第1番の夜想曲は、画家のウジューヌ・ボニの妻、マルグリト・ボニ夫人に捧げられている。ボニ夫人(1850~1930)は、1870年から1930年にかけて、パリで音楽を中心としたサロンを催しており、このサロンには、シャブリエ、フォーレ、ドビュッシー、ラヴェル、プーランク等、今日にその名が伝わる音楽家たちが集い、交流する格好の場でもあった。因みに、ボニ夫人は、後年、1892年に彫刻家のサン=マルソーと再婚している。
第1番のこの夜想曲は3部形式で書かれており、瞑想的な雰囲気で開始する。この冒頭部が再現される際には手が加えられ、展開される。これは、その後のフォーレの夜想曲に全般的に見られる手法である。中間部では低音域で第2のモティーフが現れる。これは、葬送行進曲を思わせる。とりわけ、16分音符から成る6連音符が、音楽が進むにつれ、ますます不安を掻き立てるようである。その後、一転して、不安から解き放たれるかのように、ト長調の優美なメロディーが高音域で歌われる。このメロディーは、後に半音高い変イ長調で再現される。やがて1本のラインから派生したかのような経過句が挿入される。素朴なようで憂愁さも帯びたメロディーは巧妙な和声進行によるものだろう。その後冒頭の言わば「ドゥムカ」の部分が再現される際には、前述の通り手が加えられ、経過音や前打音により一層なめらかなものとなっている。殊に、16分休符と半音階の使用が全体の輪郭をぼやかす効果をもつ。終結部分の変へ音は、主音への回帰=休息への願いを想起させる。
第2曲目は、1881年頃に作曲されたと考えられている。このロ長調の夜想曲は、ルイーズ・ギヨン夫人に捧げられている。第1番と同様に、3部形式で書かれており、アンダンティーノ・エスプレッシーヴォの指示がある。冒頭から、メロディーが語りかけるように歌い始める。この部分が12小節続いた後、アレグロ・マ・ノン・トロッポのロ短調の部分へと移る。ここでは一転して、静かにざわつくような雰囲気を醸し出す。ディナーミクの変化が目まぐるしい。コーダでは、中間部で現れたロ短調の動機がロ長調で提示される。
第3曲目は、この3つの夜想曲が出版された1883年に作曲された。初演は、1886年1月の国民音楽協会にてボルド=ペーヌ夫人により行われている。ボルド=ペーヌ夫人(1858~1924)は、音楽研究家であり作曲家であったシャルル・ボルド(1863~1909)の義姉にあたるピアニストである。彼女は、パリ音楽院で1872年にプルミエ・プリを獲得している。変イ長調のこの第3番の夜想曲を捧げられたのは、A. ボオモレツ夫人である。ボオモレツ夫人は、音楽愛好家として知られているカミーユ・クレルク(1828~1882)の2度目の妻の姉にあたる。クレルクは当時、パリのモンソー街に構えた自宅で、頻繁に室内楽の演奏会を催していた。アンダンテ・コン・モートのこの夜想曲も、第1番、第2番と同様に、3部形式で書かれている。しかし、その形としては、3曲中最も簡素に書かれている。
3つのノクターン
| 英語表記/番号 | 出版情報 | |
|---|---|---|
| ヴィエルヌ:3つのノクターン | Trois Nocturnes Op.35 | 作曲年: 1915-16年 出版年: 1923年 初版出版地/出版社: Senart |
| カルクブレンナー:3つのノクターン | Trois Nocturnes Op.187 | |
| ヴォルフ, エドゥアール:3つのノクターン | Trois Nocturnes Op.135 | |
| デーラー:3つのノクターン | 3 Nocturnes Op.52 | |
| クリューガー:3つのノクターン | Trois Nocturnes Op.1 |
- 3つのノクターンのページへのリンク
