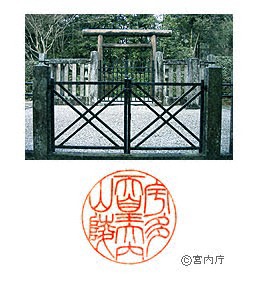うだ‐てんのう〔‐テンワウ〕【宇多天皇】
宇多天皇
母は仲野親王(桓武天皇の皇子)の娘班子女王。
一時臣籍に下り源氏姓を賜ったが、父光孝天皇の発病にともなって親王となりついで皇太子となる。
887年に父光孝天皇の崩御にともなって即位して宇多天皇となった。
藤原基経を関白に迎えようとして「阿衡の紛議」が起き、宇多天皇の藤原基経に対する不信がつのった。
藤原基経の没後に菅原道真を登用し「寛平の治」を実現し、天皇の親政を行った。
899年に仁和寺で出家して初の法皇となる。
931年に没する。
| 第59代天皇 | |
| 天皇名 | 宇多天皇 |
| 読み方 | うだてんのう |
| 名・諱等 | 定省親王 |
| 読み方 | さだみしんのう |
| 時代区分 | 古代 |
| 天皇在位 | 887年から897年 |
| 生年 | 867 |
| 没年 | 931 |
| 父 | 光孝天皇 |
| 母 | 班子女王 |
| 兄弟 | 是忠親王・是貞親王 |
| 配偶者 | 藤原胤子 |
| 皇子女 | 敦仁親王・斉中親王 |
| 即位宮 | 平安京 |
| 天皇陵 | 大内山陵 |
| 所在地 | 京都市右京区鳴滝宇多野谷 |
宇多天皇 大内山陵
(うだてんのう おおうちやまのみささぎ)
宇多天皇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/14 08:34 UTC 版)
| 宇多天皇 | |
|---|---|

|
|
|
|
|
| 即位礼 | 887年12月5日(仁和3年11月17日) |
| 大嘗祭 | 888年12月28日(仁和4年11月22日) |
| 元号 | 仁和、寛平 |
| 時代 | 平安時代 |
| 先代 | 光孝天皇 |
| 次代 | 醍醐天皇 |
|
|
|
| 誕生 | 867年6月10日(貞観9年5月5日) |
| 崩御 | 931年9月3日(承平元年7月19日) 仁和寺 |
| 大喪儀 | 931年9月19日(承平元年8月5日) |
| 陵所 | 大内山陵 |
| 追号 | 宇多院 (宇多天皇) |
| 諱 | 定省 |
| 別称 | 寛平法皇、亭子院、朱雀院太上天皇、満徳法主天、日本金剛覚大王、日本金剛蔵王、日本僧本、空理 |
| 父親 | 光孝天皇 |
| 母親 | 班子女王 |
| 女御 | 藤原温子 藤原胤子 橘義子 橘房子 菅原衍子 |
| 更衣 | 源貞子 徳姫女王 |
| 子女 | 醍醐天皇 敦実親王 斉世親王 ほか(后妃・皇子女節参照) |
| 皇居 | 平安宮 |
宇多天皇(うだてんのう、867年6月10日〈貞観9年5月5日〉- 931年9月3日〈承平元年7月19日〉[2])は、日本の第59代天皇(在位:887年9月17日〈仁和3年8月26日〉- 897年8月4日〈寛平9年7月3日〉)。 諱は定省(さだみ)。
後の佐々木氏などに代表される宇多源氏の祖先にあたる天皇である(詳細は皇子女の欄参照)。
略歴

臣籍から皇位へ
光孝天皇の第七皇子であり、母は皇太后班子女王(桓武天皇の皇子仲野親王の娘)であった。父帝光孝は、先代陽成天皇の大叔父にあたり、陽成が不祥事によって退位させられたために即位に至ったことから、自身の後は陽成の同母弟貞保親王など嫡流に皇位が戻ることを考え、元慶8年(884年)6月に26人の皇子皇女に源姓を賜い臣籍降下させた。定省王もその一人であり、源定省(みなもと の さだみ)と称した。定省が陽成に王侍従として仕えていた時、殿上の間の御椅子の前で在原業平と相撲をとり二人の体が椅子にぶつかって手すりが折れた逸話が残っている[3]。また父に献上された黒猫を下賜され、これを飼育していた[4]。
光孝は立太子を決することのないまま、即位から3年後の仁和3年(887年)に重態に陥った。関白藤原基経は、天皇の内意が貞保親王ではなく源定省にあるとした。貞保は皇統の嫡流に近く、また基経にとっても甥ではあったが、その母藤原高子は基経とは同母兄妹ながら不仲という事情もあったため忌避された。一方、基経自身は特に定省を気に入っていたわけではない[5] ものの、定省は基経の仲の良い異母妹藤原淑子の猶子であり、天皇に近侍する尚侍(ないしのかみ)として後宮に強い影響力を持つ淑子が熱心に推したこともあり、朝議は決した[注釈 2]。同母兄の源是忠を差し置いて弟の定省が皇位を継ぐことには差し障りもあったため、基経以下の群臣の上表による推薦を天皇が受け入れて皇太子に立てる形が取られた[7]。定省は8月25日に皇族に復帰して親王宣下を受け、翌26日に立太子したが、その日のうちに光孝が崩じたため践祚し、11月17日に即位した。
阿衡事件
宇多は経験に乏しく、天皇の勤めを果たすためにも4代に渡って執政の任に当たってきた基経の協力は不可欠であった。宇多は11月17日付で基経に送った手紙の中で「もし基経が執政を辞退してしまうならば、自分には政治を執ることなどできないから、君主の号を抛って山林に逃げ隠れるしかないと思っている」と述べている[8]。
宇多は即位式後間もない11月21日に、基経に引き続き執政の任に当たるよう詔書を発した。この詔書には「関白」の語が含まれており、後の役職としての関白の語源となる。しかし基経が儀礼的に辞退した後に作成した詔書にある「宜しく阿衡の任をもって卿の任とせよ」の文言に基経が立腹し、政務を拒んで自邸に引き籠もってしまう[9]。この詔書は宇多が「朕之博士是鴻儒也(私の師は大学者である)」と信任した参議左大弁橘広相が起草したものであったが、他の朝廷の学者の多くは広相の文言には問題があると一致していた[10]。翌仁和4年(888年)6月、宇多は「阿衡」の詔書を取り消した。しかし、このことは逆に広相が勅を誤ったということを宇多が認めたこととなり、かえって広相は窮地に追い込まれた[11]。基経も「阿衡」の問題が解決しないうちは参内できないと返答した。宇多は基経が光孝天皇から宇多の行く末を託され、宇多も基経を頼ったのにそれが裏切られたとして「(基経が)必ずや能う限りお仕え致します」と言ったではないかと日記に不満を書きつけている[12]。
宇多は基経の娘藤原温子を入内させるなどして和解に務め、10月になってようやく事態を鎮静化させた。寛平3年(891年)1月に基経が死去するに及んで、宇多は親政を開始することができた。なお宇多が勅願寺として仁和寺を建立したのは、この阿衡事件の最中の仁和4年のことである。
寛平の治
宇多天皇は基経の嫡子時平を参議にする一方で、源能有など源氏や菅原道真、藤原保則といった藤原北家嫡流から離れた人物も抜擢した[13]。この期間には遣唐使の停止、諸国への問民苦使の派遣、昇殿制の開始、日本三代実録・類聚国史の編纂、官庁の統廃合などが行われた。また文化面でも寛平御時菊合や寛平御時后宮歌合などを行い、これらが多くの歌人を生み出す契機となった。[要出典]
譲位
宇多は寛平9年7月3日(897年8月4日)に突然皇太子敦仁親王を元服させ、即日譲位し、太上天皇となる。この宇多の突然の譲位は、かつては仏道に専心するためと考えるのが主流だったが、近年では藤原氏からの政治的自由を確保するためこれを行った、あるいは前の皇統に連なる皇族から皇位継承の要求が出る前に実子に譲位して己の皇統の正統性を示したなどとも考られている(後述の『大鏡』にある陽成上皇の言がその暗示と考えられている)。譲位にあたって書かれた『寛平御遺誡』には右大臣源能有の死に強い衝撃を受けたことが書かれており、これを譲位と結びつける見方もある。
新たに即位した醍醐には自らの同母妹為子内親王を正妃に立て、藤原北家嫡流が外戚となることを防ごうとした。また譲位直前の除目で菅原道真を権大納言に任じ、大納言で太政官最上席だった時平の次席としたうえで、時平と道真の双方に内覧を命じ、朝政を二人で牽引するよう命じた[14]。しかしこの人事は権門の公家には不評で、公卿が職務を拒むという事件に発展した。道真は宇多に願ってかかる公卿らに出仕を命じてもらい、ようやく新政がスタートした。
昌泰の変
宇多は譲位後も道真の後ろ盾となり、時平の独走を防ごうとしていたが、一方で仏道に熱中し始めた。昌泰2年(899年)10月24日には出家し、東寺で受戒した後、仁和寺に入って法皇となった。権大僧都の益信を御戒師として、落飾し、法名を金剛覺と称した(初めは空理という名前で、後に灌頂の際に金剛覺と改めたとも伝えられている)。さらに高野山、比叡山、熊野三山にしばしば参詣し、道真の援助を十分に行えなくなった。
昌泰4年(901年)正月、道真は宇多の子で自らの婿でもある斉世親王を皇位に即けようとしていたという嫌疑で、大宰府へ左遷された。この知らせを受けた宇多は急遽内裏に向かったが、宮門は固く閉ざされ、その中で道真の処分は決定してしまった。日本史学者の河内祥輔は、宇多は自己の皇統の安定のために醍醐の皇太子決定を急ぎ、結果的に当時男子のいなかった醍醐の後継をその弟から出すことを考えるようになった。加えて醍醐が許した基経の娘・藤原穏子の入内にも反対したために、これに反発した醍醐が時平と図って法皇の代弁者とみなされた道真を失脚させたという説を提示している。
延喜元年(昌泰4年を改元)12月13日、宇多は受戒の師を益信として東寺で伝法灌頂を受けて、真言宗の阿闍梨となった。これによって宇多は弟子の僧侶を取って灌頂を授ける資格を得た。宇多の弟子になった僧侶は彼の推挙によって朝廷の法会に参加し、天台宗に比べて希薄であった真言宗と朝廷との関係強化や地位の向上に資した。そして真言宗の発言力の高まりは宇多の朝廷への影響力を回復させる足がかりになったとされる。延喜21年(921年)10月27日に醍醐から真言宗を開いた空海に「弘法大師」の諡号が贈られているが、この件に関する宇多の直接関与の証拠はないものの、醍醐の勅には太上法皇(宇多)が空海を追憶している事を理由にあげている[15]。
晩年
宇多の動きを牽制し続けていた藤原時平が延喜9年(909年)に没し、宇多に近い弟の忠平が実権を握ると、宇多の朝廷への影響力を回復させることになる。延喜15年(915年)、忠平の嫡男実頼(後の関白)が元服した際に醍醐に対して実頼への叙爵を指示している[16]。その後も忠平を介する形で天皇への働きかけを行っている[17]。
延喜13年3月13日(913年4月22日)には後院の亭子院で大掛かりな歌合「亭子院歌合」を開いた。これは国風文化の盛行の流れを後押しするものとなった。 延喜11年(911年)6月15日、亭子院の水閣を開いた時、臣から酒豪を選んで宴に招き、酒を賜り酒量を競わせた。(亭子院酒合戦)[18]。
醍醐の健康状態が悪化していくと、宇多がその代理として政務を代行する場面が登場するようになる。そして、延長8年(930年)に醍醐が崩御すると、「天皇の遺詔」があったとして新帝朱雀天皇の摂政となった藤原忠平の要請を受ける形でその後見となっている[19]。
承平元年7月19日(931年9月3日)に崩御。宝算65。日記に『宇多天皇御記』がある。
陽成との関係
陽成上皇との関係は微妙だった。宇多は皇位に即く前に侍従として陽成の側に仕えており、神社行幸の際には舞を命じられたこともあった[20]。『大鏡』には、陽成が宇多のことを、「あれはかつて私に仕えていた者ではないか」と言ったという逸話[21] が残っているが、陽成が復位を画策しているという風説は宇多を悩ませた。
保延年間に書かれた『長秋記』(保延元年6月7日条)によれば、陽成上皇が宇多天皇の内裏に勝手に押し入ろうとしたために、上皇といえども勅許なく内裏に入る事は罷りならないとこれを退けたが、後に昌泰の変が起きた際には醍醐天皇に菅原道真の左遷を止めさせようとして内裏に入ろうとした宇多上皇自身がこの先例を盾にそれを阻まれたという記載がある。
ただし、宇多上皇が内裏に入るのを拒まれたのは、薬子の変の教訓から成立した原則によるもので、陽成・宇多両上皇のケースはこの原則に基づいたものとする考えもある[22]。
系譜
| 宇多天皇の系譜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系図
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 仁明天皇 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 55 文徳天皇 |
|
|
|
|
|
58 光孝天皇 |
|
人康親王 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 清和天皇 |
|
惟喬親王 |
|
59 宇多天皇 |
|
藤原基経妻 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 57 陽成天皇 |
|
貞純親王 |
|
|
|
|
|
|
真寂法親王 (斉世親王) |
|
敦実親王 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| 源清蔭 〔陽成源氏〕 |
|
源経基 〔清和源氏〕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
源雅信 〔宇多源氏〕 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 醍醐天皇 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后妃・皇子女
- 女御(皇太夫人):藤原温子(872年 - 907年) - 藤原基経女 醍醐天皇養母
- 女御(贈皇太后):藤原胤子(? - 896年) - 藤原高藤女
- 女御:橘義子 - 橘広相女
- 女御:菅原衍子 - 菅原道真女
- 女御:橘房子(? - 893年)
- 更衣:源貞子 - 源昇女
- 依子内親王(895 - 936年)
- 更衣:徳姫女王 - 十世王女
- 孚子内親王(? - 958年)
- 更衣:藤原保子 - 藤原有実女
- 誨子内親王(? - 952年) - 元良親王妃
- 季子内親王(? - 979年)
- 更衣:源久子
- 更衣:藤原静子
- 尚侍:藤原褒子 - 藤原時平女
- 宮人:伊勢 - 藤原継蔭女、藤原温子女房
- 生母不明
- 行中親王(? - 909年)
- 成子内親王(? - 979年)
- 源臣子
宇多天皇から見て光仁天皇は男系(父方・光孝天皇)では5世祖であるが、女系(母方・班子女王)では高祖父にあたる。
宇多天皇の若年時からの妻は藤原胤子・橘義子などで、宇多天皇が臣籍降下し源氏となっていた頃に生まれた第一皇子敦仁親王(後の醍醐天皇)・第二皇子斉中親王・第三皇子斉世親王は生誕時は源氏であった。
女御藤原温子は関白藤原基経の娘で、宇多天皇即位後に入内した。女御藤原胤子が病没後、皇太子敦仁親王の養母となり、醍醐天皇即位に伴い、皇太夫人となる。晩年は東七条宮(亭子院)に住んだため、東七条后、七条后とも呼ばれた。
橘義子所生の斉世親王は、菅原道真の女を妻としたことから、後年菅原道真の誣告に際してその名が取り沙汰された。また女御菅原衍子は道真の女である。
宇多天皇の孫は、ほとんどが源氏の姓を賜り、臣籍降下した。 宇多天皇から出た源氏を宇多源氏といい、敦実親王から出た系列が最も栄えた。敦実親王の子源雅信は左大臣を務め、その娘倫子は藤原道長の正室となり、上東門院(一条天皇の中宮藤原彰子)や関白藤原頼通の母となった。朝廷貴族としての地位を維持した子孫としては、公家の庭田家や綾小路家(ともに羽林家)などがあり、また雅信から近江に土着した武家の佐々木氏が出ている。
『大和物語』において、宇多天皇は亭子院、敦慶親王は故式部卿の宮、依子内親王は「女五のみこ」、孚子内親王は「桂のみこ」として、それぞれ登場する。
諡号・追号・異名
通説では譲位後の在所の名称より宇多天皇と追号されたと言われているが、実際の居宅は仁和寺・亭子院・六条院を主としていたという(宇多院[注釈 3]は元は父の光孝天皇の親王時代の邸宅で、宇多天皇はここで成長したからだという説もある)。 また、寛平法皇、亭子院(ていじのいん)、朱雀院太上天皇などの名称でも呼ばれた。
満徳法主天
天神縁起『日蔵夢記』では、満徳法主天という神になったという。別称 日本金剛覚大王、日本金剛蔵王、日本僧本。日本太政威徳天となった菅原道真を慰撫し、その眷属が暴れまわるのを、蔵王菩薩、八幡大菩薩と共に食い止めているという。
在位中の元号
陵・霊廟

陵(みささぎ)は、宮内庁により京都府京都市右京区鳴滝宇多野谷にある大内山陵(おおうちやまのみささぎ)に治定されている。宮内庁上の形式は方丘。
火葬後、拾骨のことがないまま土を覆って陵とされた。所在は早く失われ、江戸時代末になって現在の大内山陵に治定された。
また皇居では、皇霊殿(宮中三殿の1つ)において他の歴代天皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている。
関連作品
その他
- 京都市バスで、宇多天皇が創建した仁和寺(御室御所)の門前を通るバスの系統番号は第59代宇多天皇と同じ番号、59号系統である。
- 京都市北区と右京区との境にある衣笠山の名は、宇多天皇が水無月の御室において「雪の眺めを見たい」と告げると、臣下の者が峰に白絹をかけ、玄冬のけしきをうつしたという故事に由来すると言われる。
脚注
注釈
- ^ 図様は、袈裟に横被を着け、右手に倶利伽羅龍剣・左手に数珠を持ち、法被を掛けた椅子に座す姿で、前に沓を載せた踏台と水瓶が置かれている。画面上部の左右にある色紙形には、『後拾遺和歌集』に収められた天皇の和歌「みやのたき むへもなにおひて きこえけり おつるしらあはの たまとひゝけは」が記されている[1]。
- ^ 光孝天皇即位時に嵯峨天皇の子である左大臣源融が皇位を窺って基経に退けられた(『大鏡』)時と異なり、定省を臣籍に下した父・天皇が健在であったこと、血筋の観点から言えば母親も皇孫であった定省が臣籍降下していること自体が異常という認識が宮廷にあったこと(反対に母親が五位貴族の娘であった源融は母親の出自故に臣籍降下の対象とされたと考えられる)から、定省が皇籍復帰して即位することは大きな問題にはならなかったと考えられている。もっとも、既に源氏を賜っている定省の即位に全く異論がなかったとも考えにくく、安田政彦は『大鏡』に出てくる源融の逸話は宇多天皇即位時の話を光孝天皇即位時の話として作り替えた可能性を指摘している[6]。
- ^ 右京北辺三坊
出典
- ^ 奈良県立美術館編集・発行 『特別展「室町時代の肖像画」』 2000年9-10月、73頁。
- ^ 『宇多天皇』 - コトバンク
- ^ 『大鏡』 第一巻 五十九代 宇多天皇 十三段
- ^ 河添房江『光源氏が愛した王朝ブランド品』角川書店〈角川選書〉、2008年、202-203頁。
- ^ 坂上 2009, pp. 231–232. 角田文衛「尚侍藤原淑子」からの引用。
- ^ 安田政彦「皇位継承と皇親賜姓」『古代文化』第53巻第3号、2001年3月/所収:安田政彦『平安時代の親王と政治秩序-処遇と婚姻-』吉川弘文館、2024年11月 ISBN 978-4-642-04684-8 P74-86.
- ^ 中野渡俊治「古代日本における公卿上表と皇位」『古代太上天皇の研究』思文閣出版、2017年、238・247頁。
- ^ 古藤 2011, p. 359.
- ^ 古藤 2011, p. 357、363.
- ^ 古藤 2011, p. 363-365.
- ^ 古藤 2011, p. 357、363、366-367.
- ^ 古藤 2011, p. 362.
- ^ 北山 1973, pp. 332–333.
- ^ 北山 1973, p. 348.
- ^ 駒井匠 著「宇多法皇考」、根本誠二、秋吉正博; 長谷部将司 ほか 編『奈良平安時代の〈知〉の相関』岩田書院、2015年。ISBN 978-4-87294-889-9。
- ^ 『北山抄』巻三・拾遺雑抄上、内宴事
- ^ 上村 2023, pp. 387–388.
- ^ 藤原明衡撰『本朝文粋』中の紀長谷雄「亭子院賜飲記」
- ^ 上村 2023, pp. 394–397.
- ^ 北山 1973, p. 273.
- ^ 『大鏡』 第一巻 五十九代 宇多天皇 十四段
- ^ 東海林亜矢子『平安時代の后と王権』吉川弘文館、2018年、27・52頁。ISBN 978-4-642-04642-8。
参考文献
- 遠藤慶太『平安勅撰史書研究』皇學館大学出版部、2006年。ISBN 4876441316。
- 森田悌『平安時代政治史研究』吉川弘文館、1978年。ISBN 4642020888。
- 河内祥輔『古代政治史における天皇制の論理』吉川弘文館、1986年。ISBN 4642021612。
- 坂上康俊『律令国家の転換と「日本」』〈講談社学術文庫 日本の歴史05〉2009年。 ISBN 978-4062919050。
- 北山茂夫『平安京』〈中公文庫 日本の歴史4〉1973年。
- 上村正裕「平安前期太上天皇制とその行方」『日本古代王権と貴族社会』八木書店、2023年。 ISBN 978-4840622592。
- 古藤真平「<共同研究報告>『政事要略』阿衡事所引の『宇多天皇御記』 : その基礎的考察」『日本研究』第44巻、国際日本文化研究センター、2011年、doi:10.15055/00000478、 ISSN 09150900、 NAID 120005681433。
関連項目
外部リンク
- 日本の苗字7000傑 姓氏類別大観 宇多源氏【1】
- 『摂関期古記録データベース』国際日本文化研究センター(『宇多天皇御記』の読み下し文を公開)
宇多天皇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/30 06:13 UTC 版)
宇多天皇は昌泰2年(899年)に後院として洛南の亭子院(ていじのいん)を離宮とした。宇多天皇は亭子院を建築するにあたり先の不動明王像が安置された井戸を勅命によって封じた。またこの霊石に刻まれた不動明王像を「霊石不動明王」と名づけ、特別に祀ったという。室町時代の応仁の乱の兵火により亭子院は焼失するが、井底に安置された不動明王像はそのまま残ったという。現在の本堂は明和元年(1764年)の建立である。
※この「宇多天皇」の解説は、「不動堂明王院」の解説の一部です。
「宇多天皇」を含む「不動堂明王院」の記事については、「不動堂明王院」の概要を参照ください。
宇多天皇と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 宇多天皇のページへのリンク