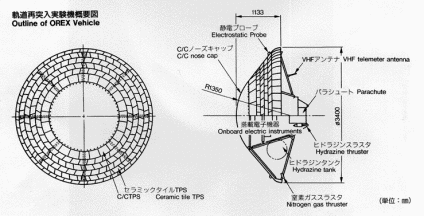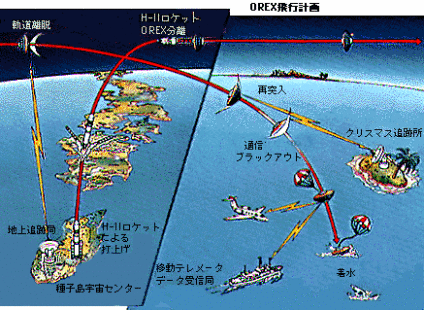りゅう‐せい〔リウ‐〕【流星】
読み方:りゅうせい
1 宇宙塵(うちゅうじん)が地球の大気中に高速で突入し、発光する現象。高度100キロ付近で衝突・発熱して輝き、多くは大気中で消滅する。特に明るいものを火球という。大きなものは地上に落下し、隕石(いんせき)という。流れ星。《季 秋》
りゅう‐せい【隆盛】
りゅうせい
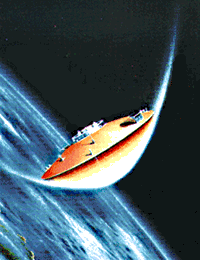
名称:軌道再突入実験丘りゅうせい」/OREX
小分類:技術開発・試験衛星
開発機関・会社:宇宙開発事業団・航空宇宙技術研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:宇宙開発事業団・航空宇宙技術研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打上げ年月日:1994年2月4日
運用停止年月日:1994年2月4日
打上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打上げロケット:H-II
打上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)
国際表記番号:1994007A解説:「りゅうせい」は、宇宙ステーションで実験した成果物の回収や、補給などをおこなった後、スペースシャトルのように、地上に帰ってくる無人の有翼回収機(宇宙往還機)、HOPEを開発するための実験機です。軌道再突入実験機(OREX=Orbital Re-entry Experiment)といわれています。1994年2月4日H-IIロケット1号機によって打ち上げられ、軌道高度約450kmの円軌道に投入された後、地球を1周したところで、大気圏に再突入しました。この再突入の際の各種データの取得、大気圏再突入に耐える飛行体の設計・製作技術の蓄積などを目的としています。
軌道再突入実験丘りゅうせい」をよく知るためのアラカルト
どんな形をして、どんな性能を持っているの?
どんな目的に使用されるの?
宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
どのように地球を回るの?
分類:人工衛星軌道再突入実験丘りゅうせい」をよく知るためのアラカルト
どんな形をして、どんな性能を持っているの?
どんな目的に使用されるの?
宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
どのように地球を回るの?1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
|
| 軌道再突入実験機概要図 |
「りゅうせい」は再突入時、空力加熱により最高で約1570℃の高熱に加熱されますが、その空力加熱を受ける機体前面には、HOPEで使用予定の耐熱、熱防護材料であるカーボン・カーボン材やセラミックタイルが使用されています。
また、再突入時は周囲の電離気体によって電波が反射、散乱、吸収されるため、地上との通信が不可能となる通信ブラックアウトという現象が起こります。このときの機体の状態を「りゅうせい」各部に取り付けられたセンサーによって計測し、データメモリに記録します。
2.どんな目的に使用されるの?
「りゅうせい」は、宇宙往還機HOPE開発の技術課題のうち、特に大気圏再突入に関する次のようなデータ取得を目的としています。
再突入時の通信途絶現象(通信ブラックアウト現象)基礎データ3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
計画通りに各種データを得た後、中部太平洋のクリスマス諸島上空で、大気圏へ再突入させることに成功しました。4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
ありません。5.どのように地球を回るの?
|
| OREX飛行計画 |
流星
りゅうせい
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/21 15:25 UTC 版)
| りゅうせい (OREX) | |
|---|---|

1/1模型(H-IIAのフェアリングに内蔵。岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の展示。)
|
|
| 所属 | NASDA(現JAXA) |
| 公式ページ | 「りゅうせい (OREX)」 |
| 国際標識番号 | 1994-007A |
| カタログ番号 | 22978 |
| 状態 | 運用終了 |
| 目的 | 再突入の技術開発 |
| 計画の期間 | 1日 |
| 運用終了日 | 1994年2月4日 |
| 物理的特長 | |
| 本体寸法 | 直径:3.40 m 高さ:1.46 m |
| 質量 | 打ち上げ時:865 kg 再突入時:761 kg |
| 軌道要素 | |
| 高度 (h) | 450 km |
| 軌道傾斜角 (i) | 30.5度 |
| 軌道周期 (P) | 93.5分 |
りゅうせい(OREX; Orbital Re-entry Experiment, 軌道突入実験機)は、航空宇宙技術研究所(NAL)と宇宙開発事業団(NASDA)[注釈 1]が共同開発した日本初の大気圏再突入実験機である。1994年(平成6年)2月4日にH-IIロケット1号機により打ち上げられ、計画通り大気圏に突入し太平洋に着水した[1]。
目的と設計
NASDAではかねてよりH-IIロケット打ち上げ型有翼回収機(HOPE)の開発が進められていたが、その完成には大気圏再突入に関するデータの蓄積が必要だった。大気圏再突入における空気力・空力加熱・耐熱構造・通信・GPS航法に関するデータを取得し、また大気圏再突入を目的とした飛行体の設計・製作技術の蓄積を目的として開発されたのが本機である。
機体設計
- OREXは直径3.4m、高さ1.46mの円盤状の人工衛星で、円盤の片面は炭素繊維強化炭素複合材料やセラミックタイルから成る耐熱シールドになっていた。材質はHOPEで使用予定のものと同様だった。
- 熱構造・外形形状[2]
- エアロシェルにはスペースシャトルなどで実績のあるC/C複合材とセラミックが使用される。C/C複合材は炭素繊維にフェノール樹脂を含侵させオートクレープ成型によって作られるCFRPである。
- 球形のノーズキャップ部は曲率半径1.35m・直径1.7mの一体成型であり、当時としては世界最大級であった。大気中の酸素との燃焼を防止するためにSiCコーティングが施される。耐熱温度1,700℃程度に対し、熱解析では1,560℃程度になると予測された。
- スカート部は進行方向から50°の角度をなす円錐形で、中心付近にC/C-TPS(Thermal Protection System)、外縁部にセラミックタイルTPSが採用された。
- マッハ30から着水前の30m/sまで、広い速度域で空気力学的に安定するよう設計された。空力過熱はマッハ20の時点で最大となる。
- 推進系[2]
- 計測通信系[2]
- 電力系[2]
- 打ち上げから着水までの8,000秒間は内蔵の銀亜鉛電池によって電力供給される。
- GPS受信機
運用
H-IIロケット1号機にはOREXとH-IIロケット性能確認用ペイロード(VEP)が相乗りする形で搭載された。OREXとVEPは軌道投入後にそれぞれ「りゅうせい」「みょうじょう」と命名された。
1994年2月4日、H-IIロケット1号機は種子島宇宙センターから打ち上げられ、OREXを高度454.5kmの円軌道[1]に、VEPを静止トランスファ軌道(GTO)の投入に成功した。
りゅうせいは1時間半かけて地球を一周して種子島上空に達し、種子島宇宙センターとの通信が可能となってから逆噴射を実施して減速する[2]。軌道離脱中は種子島宇宙センターおよび小笠原局でデータを受信し、レーダによって追跡される。クリスマス島の西方約1,000km、高度約120kmで大気圏に再突入を開始し、約10分後にクリスマス島の南方460km[1]の太平洋上に軟着水[2][4]に成功した。飛行時間は7,982秒(2時間13分)[1]。これは日本初の大気圏再突入の実験であった。
脚注
注釈
- ^ 両者は後に合併し宇宙航空研究開発機構
出典
- ^ a b c d 山本昌孝ほか (1994-09). “軌道再突入実験(OREX)概要”. 航空宇宙技術研究所特別資料 24: 61-76. ISSN 0289-260X.
- ^ a b c d e f 『三菱重工技報 = Mitsubishi Juko giho 28(6)(167)』三菱重工業、1991年11月、634-639頁。
- ^ 日産技報編集委員会 編『日産技報 = Nissan technical review (36)』日産自動車総合研究所研究企画部、1995年2月、10頁。
- ^ a b 『三菱重工技報 = Mitsubishi Juko giho 30(6)(179)』三菱重工業、1993年11月、477頁。
- ^ 東芝ビジネスエキスパート株式会社ビジネスソリューション事業部 編集・制作『東芝レビュー 53(7)(589)|人工衛星搭載用GPS受信機』東芝技術企画部、1998年7月、35-38頁。
- ^ 『Fujitsu : 技術情報誌 48(1)(278)|人工衛星の軌道決定技術』富士通、1997年1月、32頁。
関連項目
外部リンク
- JAXA - 軌道突入実験機「りゅうせい (OREX) 」
- JAXA宇宙情報センター - 「りゅうせい」 - ウェイバックマシン(2010年5月16日アーカイブ分)
- NSSDC Master Catalog Display
りゅうせい
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 09:54 UTC 版)
伊勢の教え子の青年。幼少時代の詩暢に対戦するが完封負けする。
※この「りゅうせい」の解説は、「ちはやふる」の解説の一部です。
「りゅうせい」を含む「ちはやふる」の記事については、「ちはやふる」の概要を参照ください。
りゅうせい
りゅうせいと同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- りゅうせいのページへのリンク