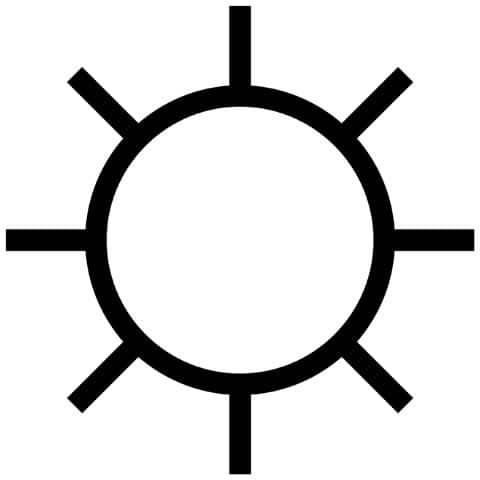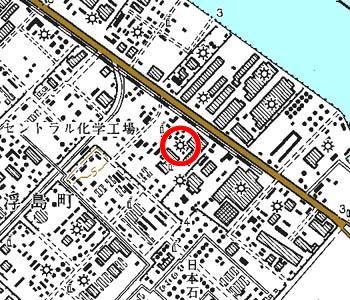工 場
工場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/08 01:31 UTC 版)
工場(こうじょう、こうば、英:factory)は、
- 生産用の機械をそなえておりそれを使用して工員が製品の製造や加工に従事する施設。製造・生産や加工するための施設や家屋。生産のための工場を生産工場、加工のための工場を加工工場と総称する。
- 既成の機械製品の整備(点検・保守も含む)を行う施設。整備のための工場を整備工場と総称する。
工場(こうじょう)は大規模な施設を指し、工場(こうば)は小規模な施設を示すことが一般的である。生産のための工場は製作所、製造所と呼ばれることもある(それが社名になっている会社もある)。そのほか企業内では事業所、事業場などと呼ばれることもある。
概要
工場で製造する製品に応じた機械設備が設置されている。
- 立地
小規模から中規模の工場は、内陸地域に設置されることが多い。特定の地域に工場が自然と集中し工業集積地(工業地域)となることも多い。また意図的に開発された工業団地内に建設されることも多くなった。

一方、石油や鉄鋼などの大規模な工場は、原料の搬入や製造した製品の搬出の便を図るために、海岸沿いの臨海部に設置されることが多い。石油コンビナート、製鉄所などはそれ自体が非常に規模が大きく、また関連工場も多くは近隣に設けられ、一大工業地区を形成する。
- 予備知識
なお、かなり小規模で一人ないし数名程度が働く施設は工房ということが多い。
種類
製造業や加工業は業種が細分化されており、工場も業種の数だけ細分化されている。
製造業の工場は製造の業種ごとに細分化されている。
金属素材を生産する工場については、製銑[注釈 1]・製鋼[注釈 2]・圧延をして鉄材や鋼材を生産する工場は製鉄所、アルミを精錬する工場はアルミ精錬工場、銅を生産する工場は銅溶錬工場などと分類する。アルミは何度でも溶かしてリサイクルされ一旦精錬されたアルミの75%は何度でも再利用され続けているので[1]、アルミ精錬工場の数は減ってきており代わりにアルミリサイクル工場が増えてきている。
鋳鉄・銅合金・アルミニウム合金・鋼などを溶かして型に流し込み鋳物を作る工場は鋳物工場という。
加工するための工場も、鉄材や鋼材を加工する工場は鉄工所、その中で切削加工に特化した工場は切削工場、研磨加工に特化した工場は研磨工場などと細かい分類も可能で、メッキ加工をするための工場はメッキ工場、塗装するための工場は塗装工場などと加工の種類だけ細分化できる。
丸太から材木を生産する工場は製材工場といい、木材の加工を行う工場は木工所(もっこうじょ)という。
化学物質を製造する工場は化学工場と言い、その中核となっている生産施設や装置を化学プラント(en:Chemical plant)という。
完成品の工場については、たとえば自動車メーカーが部品工場を運営する会社から納入された部品を集めて組み立てて自動車を製造するための工場は自動車工場、バッテリーメーカーがバッテリーを製造するための工場はバッテリー工場、半導体メーカーが半導体(集積回路類)を製造するための工場は半導体工場、楽器メーカーが楽器を製造するための工場は楽器工場、家具を製造する工場は家具工場などと分類される。
造船会社が船舶を建造する施設は造船所という。軍艦・兵器・軍需品の工場は工廠や兵器工場(アーセナル)と言う。
繊維から糸を紡ぐ工場は紡績工場、糸を織り織物を作る工場は織物工場、布を裁断しミシンで縫い合わせる工場は縫製工場、糸を機械で編んで編物(ニット)を作る工場は編物工場(ニット工場)という。
水産物を加工する工場は水産加工工場、食肉を生産するための工場は食肉工場ということもあるがと畜場や食鳥処理場ということが多く、野菜を洗浄したりカット・加熱などする工場は野菜工場や野菜加工工場、穀類から穀粉を製造する工場は製粉工場(製粉所)、食品メーカーが食品を製造するための工場は食品製造工場という。
乗り物の整備工場としては自動車整備工場、オートバイ整備工場、船舶整備工場[注釈 3]、航空機整備工場(機体整備工場)など、乗り物の種類ごとにある。(なお、自動車整備工場やオートバイ整備工場は多くの一般人が車検毎に使い、一般人も馴染みのある工場である)。 自動車のボディーのへこみを直す工場は板金工場(ばんきんこうじょう)という。
-
金属工場
-
製鉄所の圧延工程
-
鋳物工場
-
メッキ工場
-
化学工場
-
自動車工場
-
ボーイング社の航空機工場
-
スタインウェイのピアノ工場
-
食品工場
-
自動車整備工場
歴史

2世紀頃には製粉工場であるバルブガル水道と水車群跡がローマ帝国の領域内、現在の南フランスに当たる場所で建設され、4世紀頃までには一日あたり28トンの穀粉[2]、ローマ帝国の住民で言うと80,000人分に相当にする穀粉を生産できる状態になっていた[3][4][5]。
近代的な工場が出来たのは1770年頃のイギリスである。1769年にイギリスのリチャード・アークライト(Richard Arkwright)が水力を使った紡績機を発明した。この紡績機は非常に高速で強い糸を紡ぐことが出来たが、利用するには水車のある場所に設置しなければならなかった。アークライトは1770年頃、靴下製造業者であったサミュエル・ニード、ジェディダイア・ストラットらと組んで、ダービーシャー州のクロムフォードに、何台もの紡績機を集め、全ての紡績機の動力となる水車を備えた紡績工場を作った。これが近代的な工場の出発点とされ、産業革命の要因の1つともなった[6]。
日本の工場
日本において、働く人の数が300人以上の工場を「大工場」、300人未満の工場を「中小工場」と呼ぶ[7]。さらに29人以下の工場は「小工場」と呼ばれる。
大工場の例としては、自動車工場や化学工場、電化製品工場などが挙げられる[8]。ほとんどは重化学工業である。
中小工場の例としては、部品工場や食品工場、繊維工場、日用品工場などが挙げられる[9]。中小工場は、大企業の下請けが多く、大工場でつくっている製品の部品などを作っている工場が多い。部品工場のことを、最終製品を作っている工場からの視点で、関連工場ともいう。
日本にはおよそ36万もの工場がある(2017年)が、そのうち99%以上が中小工場であり、大工場はわずか1%未満である[9]。外国に比べると、日本の中小工場の割合は大きい[10]。しかし、中小工場に仕事を発注する大工場の海外移転の増加などに伴い、日本の中小工場の数は年々減少傾向にある[11]。日本の全工場で大工場と中小工場を比較した場合、従業員数は中小工場が約7割を占めるが、生産額は中小工場が全体のおよそ半分である[12]。
中小工場ではそれぞれの優れた技術を持つ職人が多く働いているが、従業員の高齢化による後継者不足が問題となっている。また、中小工場は景気の影響を受けやすいため、経営的に厳しい状況になることもある。
| 大工場 | 中小工場 | 総数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 工場数 | 3248 | 0.9% | 35万7596 | 99.1% | 36万844 |
| 従業員数 | 249万人 | 31.5% | 541万人 | 68.5% | 790万人 |
| 工業生産額 | 169兆4089億円 | 52.6% | 152兆6613億円 | 47.4% | 322兆703億円 |
工場と周辺地域の関係
特に大規模な工場や工場集積地は多くの労働者を必要とするので、労働者が使う店舗も工場の周辺に集まることもある。工場を中心として形成される生活圏を企業城下町と呼ぶこともある。
文化
工場見学と呼ばれる内部見学を行うツアーが組まれることがある[13][14]。また、工場によっては見学用の施設を設置する場合もある[15]。
工場内部を見学する番組の例
出典
注釈
- ^ 鉄鉱石、マンガン鉱、造滓溶剤。コークスを使い炭素を多く含む銑鉄を作る工程
- ^ 銑鉄を精錬して炭素含有量の少ない鋼にすること
- ^ 船舶の場合はやや特殊で、造船所が整備も兼業で行うことが多い。造船は行わず船舶整備専業の業者・施設もある。
出典
- ^ “アルミでかなえる軽やかな世界”. 株式会社UACJ. p. 6. 2025年3月3日閲覧。
- ^ Hill, Donald (2013). A History of Engineering in Classical and Medieval Times. Routledge. pp. 163–166. ISBN 9781317761570
- ^ TK Derry, (TI Williams ed) – A Short History of Technology: From the Earliest Times to A.D. 1900 Courier Dover Publications, 24 March 1993 Retrieved 12 July 2012 ISBN 0486274721
- ^ A Pacey – Technology in World Civilization: A Thousand-Year History MIT Press, 1 July 1991 Retrieved 12 July 2012 ISBN 0262660725
- ^ WM Sumner – Cultural development in the Kur River Basin, Iran: an archaeological analysis of settlement patterns University of Pennsylvania., 1972 [1] Retrieved 12 July 2012
- ^ ロジャー・ブリッジマン 著、小口高、鈴木良次、諸田昭夫 監訳『1000の発明・発見図鑑』丸善出版、2003年11月1日、107-108頁。 ISBN 4-621-07301-X。
- ^ “ちゅうしょうこうじょう【中小工場】 | ち | 辞典”. 学研キッズネット. 2021年3月23日閲覧。
- ^ “「統計から見る日本の工業」大工場と中小工場| 経済産業省”. www.meti.go.jp. 2021年3月23日閲覧。
- ^ a b “「統計から見る日本の工業」大工場と中小工場| 経済産業省”. www.meti.go.jp. 2021年3月23日閲覧。
- ^ “だいこうじょう【大工場】 | た | 辞典”. 学研キッズネット. 2021年3月23日閲覧。
- ^ NHK. “中小工場がかかえる問題”. NHK for School. 2021年3月23日閲覧。
- ^ “「統計から見る日本の工業」大工場と中小工場| 経済産業省”. www.meti.go.jp. 2021年3月23日閲覧。
- ^ 『まっぷる 工場見学 社会科見学 首都圏'26』出版社:昭文社 · 2025
- ^ 『ニッポンの工場見学【マニア聖地編】: 週刊東洋経済eビジネス新書No.111』出版社:週刊東洋経済編集部
- ^ “まるで宇宙探検!?明治初のアポロ見学施設が埼玉に誕生|ウォーカープラス”. ウォーカープラス(Walkerplus). 2025年8月8日閲覧。
- ^ “【神戸市】1/11(土)12時15分、NHK探検ファクトリーで「淡路屋」!冬のすきやき弁当食べてみた(斎信夫(いつき)) - エキスパート”. Yahoo!ニュース. 2025年8月8日閲覧。
- ^ “NHK「探検ファクトリー」オトナの工場見学で見えてくる、もの作りニッポンの真骨頂と矜持|テレビ 見るべきものは!!”. 日刊ゲンダイDIGITAL (2024年6月19日). 2025年8月8日閲覧。
関連項目
外部リンク
工場(箱崎食品工業団地)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:28 UTC 版)
「箱崎ふ頭 (福岡市)」の記事における「工場(箱崎食品工業団地)」の解説
食品工業関連の企業を集団化し、原料輸入、基幹食糧生産、加工食品生産及び製品流通の各機能が連携した食品工業団地が箱崎六丁目の一部で形成されており、多くの工場が立地している。また、団地内における施設の効率的利用を図るために共同利用施設も立地している。
※この「工場(箱崎食品工業団地)」の解説は、「箱崎ふ頭 (福岡市)」の解説の一部です。
「工場(箱崎食品工業団地)」を含む「箱崎ふ頭 (福岡市)」の記事については、「箱崎ふ頭 (福岡市)」の概要を参照ください。
工場
出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 08:38 UTC 版)
| この単語の漢字 | |
|---|---|
| 工 | 場 |
| こう 第二学年 |
じょう 第二学年 |
| 音読み | |
| この単語の漢字 | |
|---|---|
| 工 | 場 |
| こう 第二学年 |
ば 第二学年 |
| 重箱読み | |
名詞
類義語
翻訳
- アルメニア語: գործարան
- チェコ語: továrna 女性, fabrika 女性
- デンマーク語: fabrik 通性
- ドイツ語: Fabrik
- 英語: factory
- スペイン語: fábrica
- フィンランド語: tehdas
- フランス語: usine 女性
- ガリシア語: fábrica
- ハンガリー語: gyár
- イタリア語: fabbrica 女性
- ロジバン: lo fanri
- ドゥンガ語: fràveca 女性
- オランダ語: fabriek 女性
- ポーランド語: fabryka
- ロシア語: завод (zavód) 男性, фабрика (fábrika) 女性
- スコットランド語: taigh-oibre m, taigh-gnìomhachais m, taigh-ceàirde m, taigh-tionnsgain m
- スウェーデン語: fabrik 通性
- タイ語: โรงงาน
- 中国語: 工廠
「工場」の例文・使い方・用例・文例
- その工場では自動車を組み立てている
- 彼らは工場にたくさんの爆弾を投下した
- 工場は経済不況のために操業を停止した
- トラックの一団が工場を出発した
- 工場の生産量は半分に減らされた
- その工場主は労働者たちの要求を退けた
- その工場は海に廃液をたれ流している
- 工場が閉鎖されてからずっと失業中だ
- 最新の機械がすべて装備された工場
- たくさんの人がこの工場で働いている
- 自動車工場
- その工場はひどい臭いを発生させた
- 工場ではフル稼動だ
- 工場は活気づき始めた
- 彼らは工場を視察した
- 工場監督官
- 彼は工場で働くことしか知らない
- あの工場は1,000人以上の労働者を解雇した
- 私は工場の流れ作業の現場で働いていた
工場と同じ種類の言葉
- >> 「工場」を含む用語の索引
- 工場のページへのリンク