流行性角結膜炎
りゅうこうせい‐かくけつまくえん〔リウカウセイ‐〕【流行性角結膜炎】
流行性角結膜炎
|
・流行性角結膜炎(EKC,epidemic keratoconjunctivitis) 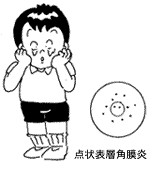 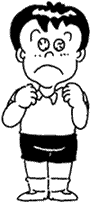
|
一般に「はやり目」といわれるもので,主としてアデノウィルス8型によるウイルス性の結膜炎です。感染力が強く,感染してから1週間前後の潜伏期間をおいて突然発病します。まず結膜が真赤に充血し,涙がよく出ます。次にまぶたが腫れ,ゴロゴロした異物感もあり,しばしば耳下腺リンパ節が腫れることもあります。片眠が先に発病することが多く,数日後にもう片方の目にも発病してきますが,比較的後の目の方が軽くすみます。おとなと子どもでは経過症状が違い,幼児では,結膜の裏に偽膜という白濁色の膜のようなものができ,まぶたの腫れは非常に強くなります。この膜ははがれるときに出血するので,目から血が出たとおどろきますが,心配しなくてよいものです。おとなでは,症状がおさまりかけた頃に角膜の表面に点状の濁りがたくさんでき(点状表層角膜炎),視力が悪くなります。この角膜の濁りはすぐには治りませんが,いずれは完全に治り,視力も元に戻ります。結膜炎は2~3週間で治りますから,それ自体はたいしたことはないのですが,その間は充血,流涙などの症状が強く,うっとおしい日が続きます。特効薬がないため,混合感染を防ぐ意味で抗生物質,点状表層角膜炎に対して副腎皮質ホルモンやビタミンB2の点眼を使用しますが,症状の軽減はそれほど期待できません(むしろ周囲への感染防止に努めることが大切になってきます。感染防止のための注意等は次項)。 |
|
流行性角結膜炎
流行性角結膜炎
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/23 01:18 UTC 版)


流行性角結膜炎(りゅうこうせいかくけつまくえん)(EKC:epidemic keratoconjunctivitis)は、ウイルスによって引き起こされる急性の結膜炎、あるいは角膜炎。別名「はやり目」ともいわれ、感染力が強い。
原因・症状

主にアデノウイルス8型、19型、37型によっても引き起こされるが、希に B群の3型、7型、11型、E群の4型によっても引き起こされる[1]。以前はプールでうつる夏の病気だったが、近頃では一年中見られるようになった。1週間から2週間程度の潜伏期の後、発症する。結膜炎と角膜炎を起こすため、角結膜炎と呼ばれる。また全例ではないが、耳前リンパ節の腫脹を伴う[1]。
結膜炎
- 充血し、眼脂(めやに)が出る(ひどいときには「めやに」で目が開かないくらいになる)。
- 片目発症後、4〜5日後に反対側の目も発症する場合が多い。
- 涙目になったり、まぶたがはれることもある。
- 視力が少し低下する場合がある。
- 症状が重くなると、耳前リンパ節が腫れて触ると痛みを伴う。
- 症状が強い人の場合は、まぶたの裏の結膜に白い膜ができ、眼球の結膜に癒着をおこす。
- 症状が治まるまで約2-3週間かかる。
角膜炎
- 透明な角膜に点状の小さな混濁[2]が生じ、眼痛を感じる。
- 眩しさやかすみを感じる。
- 視力障害を感じることもある。
- 黒目の表面がすりむける角膜びらんを伴い、目がゴロゴロしたり、眼痛がひどくなる。
- 症状が数ヶ月から丸一年に及ぶこともある。
診断・治療
結膜炎の原因はウイルス性のほか、アレルギー性、細菌性などもあり、初期の段階での判断は難しい。症状や所見から当該疾患が疑われ診断されるが、現在では迅速診断法として抗原抗体反応を利用したELISA やクロマトグラフィー法により、簡易キットを用いた早期段階での判断ができるようになってきている。しかし、検査で陰性であっても必ずしもEKCが否定できる訳ではなく、後述の治療をしつつ数日間は経過を見る必要がある。
ウイルスに対する有効な薬剤はない。充血・炎症に対しステロイドの点眼を行い、細菌の混合感染の可能性に対しては、抗菌剤の点眼を行う。特に新生児や乳幼児では、細菌の混合感染で角膜穿孔を起こす事があるので注意が必要である。
角膜炎が強度になり視力低下や場合によっては失明の危険もあるため、早期に治療を開始することが望ましい。
感染症法に基づく届出のために必要な臨床症状は、「重症な急性濾胞性結膜炎」「角膜点状上皮下混濁」「耳前リンパ節腫脹・圧痛」のうち2つ以上[1]。
注意点
主として手を介した接触感染である。ウイルスに感染した眼を手で触れると、手にウイルスが付着する。そのままいろんな物に触れると、その物にウイルスが付く。更に、他の人がそれに触れて、その手で目をこするなどした場合に感染するという経路がほとんどとなる。
- 手をよく洗い、手で目をこすったり、顔に触れたりしないこと。
- 休養をとって体力をおとさない。
- 風呂は最後に入り、その湯はすぐに捨てる。
- タオル類の共有はやめる。
- 治ったように見えても、しばらくの間は外出などは控える。
- 流行時には、院内感染による流行拡大もあるため、乳幼児は、診察を受けるとき以外は病院につれて行かない。また、入院中の患者が感染した場合、退院可能な場合は強制退院の対象となり得る[3]。
関連法規
- 感染症法 - 5類感染症定点把握疾患。眼科定点医療機関(全国約700カ所の眼科医療機関)は週単位で、翌週の月曜日に保健所に届け出なければならない。
- 学校保健法 - 学校感染症の一つで第3種(学校において流行を広げる可能性がある伝染病)。伝染の恐れがないと、医師が認めるまで出席停止。
- 児童に限らず成人が感染した場合でも原則的に出勤停止となり、特に医療従事者の感染は時に患者への二次感染を引き起こす事がある[4]。
出典
- ^ a b c “流行性角結膜炎とは”. 国立感染症研究所感染症疫学センター. 2024年7月30日閲覧。
- ^ 石田篤行、益子直子、箕輪美紗斗ほか、流行性角結膜炎後、角膜混濁を生じた症例の生体共焦点顕微鏡による観察 日本視能訓練士協会誌 Vol.41 (2012) p.201-206, doi:10.4263/jorthoptic.041F121
- ^ “大阪大学医学部附属病院感染管理マニュアル(2019年11月改訂版)”. 大阪大学医学部附属病院. 2024年7月30日閲覧。
- ^ 細田昌良、小松敏美、松下美幸、流行性角結膜炎に対する地域社会と連携した感染対策の試み 日本環境感染学会誌 Vol.23 (2008) No.2 P.140-144, doi:10.4058/jsei.23.140
関連項目
外部リンク
流行性角結膜炎(EKC)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 07:40 UTC 版)
「アデノウイルス」の記事における「流行性角結膜炎(EKC)」の解説
主として8、19、37型によるとされてきたが、近年の日本においては53、54および56型によるEKCが多発するようになった。これらはいずれもD種アデノウイルスである。B種の3、7型やE種の4型による場合もあるが、D種より軽症である。 目が充血し、目やにが出るが、咽頭結膜熱のように高い熱はなく、のどの赤みも強くはない。結膜炎経過後に点状表層角膜炎を作ることが多く、幼小児では偽膜性結膜炎になることがある。角膜混濁が発症することがあり、数か月以上も症状が残ることがあるので眼科での治療が必要である。 流行性角結膜炎は学校保健安全法上の学校感染症の一つで、伝染の恐れがなくなるまで登校禁止となる。
※この「流行性角結膜炎(EKC)」の解説は、「アデノウイルス」の解説の一部です。
「流行性角結膜炎(EKC)」を含む「アデノウイルス」の記事については、「アデノウイルス」の概要を参照ください。
流行性角結膜炎と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 流行性角結膜炎のページへのリンク



