はく‐ちょう〔‐チヤウ〕【白張/白丁】
はくちょう〔ハクテウ〕
昭和54年(1979)2月に打ち上げられた日本初のX線天文衛星CORSA-b(コルサビー)の愛称。東京大学宇宙航空研究所(後の宇宙科学研究所、現JAXA(ジャクサ))が開発。名称は強力なX線天体白鳥座X-1に由来する。超軟X線から硬X線までを観測し、すだれコリメーターによって新たに八つのX線バースターを発見。ほかの主な成果として、X線パルサーの異常な周期変化や白鳥座X-1のX線強度の時間変動が挙げられる。昭和60年(1985)4月に運用完了。
はくちょう〔ハクテウ〕
はく‐ちょう〔‐テウ〕【白鳥】
読み方:はくちょう
カモ科ハクチョウ属の鳥の総称。大形の水鳥で、くびが長く、水底などの水草を食べる。日本に冬鳥として渡来するオオハクチョウとコハクチョウは全身白色で、夏には北アメリカ・ユーラシア北部に渡り繁殖。スワン。しらとり。《季 冬》「—といふ一巨花を水に置く/草田男」
はくちょう〔ハクテウ〕【白鳥】
消防ヘリコプター
中型ヘリコプター |
大型ヘリコプター |
| 消防ヘリコプターは、中型3機(ちどり・かもめ・つばめ)、大型3機(ひばり・ゆりかもめ・はくちょう)の合計6機が就航し、空からの消火、救助、情報収集、救急患者の搬送等を行っています。 |
| 諸元性能(ちどり) 全長13.68m(主回転翼を含む) 燃料タンク容量1,158L 全幅11.94m(主回転翼を含む) 燃料消費量350L/h 全備重量4,250kg スリング能力1,600kg 最大速度315km/h ホイスト能力272kg 巡航速度260km/h、製造会社仏ユーロコプター社 航続距離715km AS365N2(ドーファンII) 航続時間2時間45分、座席数13席(かもめ・つばめは14席) |
諸元性能(ひばり) 全長18.7m(主回転翼を含む) 燃料タンク容量2,743L 全幅15.6m(主回転翼を含む) 燃料消費量650L/h 全備重量8,600kg スリング能力3,000kg 最大速度278km/h、ホイスト能力272kg 巡航速度256km/h、製造会社仏ユーロコプター社 航続距離1,012km、AS332L1型(スーパーピューマ) 航続時間3時間58分座席数23席(ゆりかもめ・はくちょうは27席) |
はくちょう
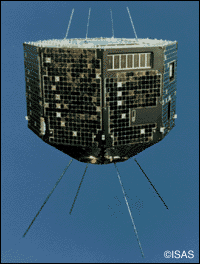
名称:第4号科学衛星「はくちょう」(CORSA-b)
小分類:科学衛星
開発機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げ年月日:1979年2月21日
運用停止年月日:1985年4月15日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:M-3C
打ち上げ場所:鹿児島宇宙空間観測所(KSC)
国際標識番号:1979014A
CORSA-bは、1976年2月4日の打ち上げで軌道投入に失敗したCORSAの代替衛星で、3年後の1979年2月21日には姿勢基準装置を改良したM-3Cロケットによって打ち上げに成功、第4号科学衛星「はくちょう」と命名されました。はくちょうは「すだれ型X線コリメーター」と呼ばれる観測機器を搭載した初の観測衛星で、X線星、X線バースト、硬軟X線星雲などの観測を行なっています。
すだれコリメーターは東大宇宙航空研究所のX線観測責任者で、後に宇宙科学研究所長となる小田稔教授の発明で、すだれ状の格子を重ねることによって星の光の入射角をより正確に検知できるようになりました。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
はくちょうの基本構造はCORSAと同様の8角柱形で、直径75.5cm、高さ65.5cm、重量96kg。ゆっくり回転しながら軌道を周回、X線コリメーターによる走査を行ないます。
2.どんな目的に使用されるの?
はくちょうは広視野X線コリメーターにより、X線星、X線バースト、硬軟X線星雲などを観測、中性子星やブラックホールの謎に挑みました。中でも、強いX線を放射しているはくちょう座のX-1と呼ばれるブラックホールと推定される天体が主要ターゲットで、「はくちょう」という名称はここに由来しています。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
強いX線を放射する天体としては、連星のガスを高速で吸い込む際にX線バーストと呼ばれる爆発的なX線放射を行なう中性子星が知られています。はくちょうは打ち上げから47日目の4月9日に、はくちょう座の大バーストを発見、その後もいくつかのX線バーストを発見しました。このほか、1981年までの観測期間中に国内およびヨーロッパ、南アメリカの天文台と同時観測をおこなって、中性子星の大きさや自転のふらつきなどの新発見に寄与しました。また、ガス吸入にともなうX線バーストが見られることからブラックホールの有力候補とされている、はくちょう座X-1の観測を行ないました。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
X線観測衛星としては、欧米のウフルーやアインシュタインがよく知られていますが、アインシュタインが1981年に機能停止して以降は日本の独壇場で、はくちょうのひのとり、てんま、ぎんが、あすかなどが相次いで打ち上げられています。
5.どのように地球を回るの?
高度545〜577km、傾斜角30度、周期96分の略円軌道です。
※参考文献:大澤弘之・監修「日本ロケット物語」三田出版会、斎藤成文「日本宇宙開発物語」三田出版会、山中龍夫・的川泰宣「宇宙開発のおはなし」日本規格協会
はくちょう 【白鳥】
ハクチョウ
(はくちょう から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/02 02:47 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2016年12月)
|
| ハクチョウ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
|||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 属と種 | |||||||||||||||||||||
ハクチョウ(白鳥、swan)とは、カモ科の7種の水鳥の総称。シベリアやオホーツク海沿岸で繁殖し、冬季は温暖な日本などへの渡りをおこない越冬する大型の渡り鳥である。
現生の空を飛ぶ鳥の中では最大級の重量を有している。
おとなしいイメージもあるが、子育て中の野生個体は警戒心が強くなっており、雛を捕まえようとした人間を追い払う例も報告されている。
日本語のハクチョウは、文字通り「白い鳥」という意味だが、名称に反してハクチョウ属には「黒い鳥」である「コクチョウ」も存在する。
寿命は野生で最長20年ほど、飼育状態では20年から30年ほどである。
日本におけるハクチョウ
現在は「白鳥」という漢名が一般的だが、「くぐい(鵠)」の古称をもち、「日本書紀」垂仁天皇の条などに記載がある。ヤマトタケルは、死後に白鳥になったという伝承があり、日本では古くから親しまれている鳥である。
「優雅に泳ぐ白鳥も水面下では激しく足を動かしている」というフレーズが、漫画『巨人の星』の作中で登場人物の台詞として語られたことから有名になっているが、これは原作者の梶原一騎による創作であり、実際にはそれほど激しく足を動かしているわけではない。実際には、尻にある尾腺から分泌される油を羽繕いで羽に塗りつけ、撥水性を持たせている。これによって羽毛の間に水が浸入せず、浮力を得られる仕組みになっている。
餌付けされていない野生の白鳥は、マコモの茎や根、稲の落穂や水中の藻等を、水と一緒にすくいながら食べる。
地域
日本にはオオハクチョウとコハクチョウが越冬のために渡ってきて、北海道や本州の湖沼、河川等で過ごす。晩秋から初冬に渡来し、春には飛去する。青森県・島根県・東京都千代田区・新潟県新潟市・阿賀野市の県鳥および区鳥・市鳥である。
北海道で主に見られるのは、オホーツク地方、函館地方、小樽周辺(余市など)である。

青森県東津軽郡平内町浅所海岸のハクチョウは、「小湊のハクチョウおよびその渡来地」として国の特別天然記念物に指定されている。
青森県南津軽郡藤崎町地内平川水域に飛来するハクチョウは、「藤崎のハクチョウ[1][2]」として青森県の天然記念物に指定されており、周辺地域は「白鳥ふれあい広場」として整備されている。
新潟県阿賀野市の瓢湖はハクチョウの飛来により2008年にラムサール条約に登録されている。新潟には他に福島潟・五十公野公園のます潟・佐潟・三条市下田などにハクチョウが多く飛来している。
埼玉県川島町は都心近郊ながら人為的撹乱の比較的少ない豊かな水場環境が残されていることから、毎年多くのコハクチョウが飛来、越冬する。都心から1時間弱で訪れることができるエリアにありながら、自然に近い河川環境のなかで、見物客が至近距離から白鳥に餌やりをしたり、写真撮影をしたりして自由に楽しめる貴重な観光スポットになっている。都市公園の池や皇居のお堀とは異なり、自然環境における野生に近い生態を観察できることから、写真愛好家などが多く訪れており、都心近郊にある「白鳥の町」として知られている。川辺だけでなく、河川敷の内外にある刈り取り後の田んぼや小麦畑で、穀物の種などを啄んでいる姿も観察できる。多い年には、50羽ほど飛来することもある。

川島町に飛来するコハクチョウの群れは、広大な河川敷と浅瀬の多い河川で、野生に近い生活を送っているが、来訪者が多いことから人間に慣れており、餌やりをしに来た見物客が持参したパンや菓子類の袋の音を聞きつけると、マガモなど他の渡り鳥といっしょに、一斉に、岸辺に向かって殺到する。見物客から餌をもらうと、我先にと、猛烈な勢いで食らいつく。“コハクチョウ”とはいえ、成鳥は巨体であり、立ち上がって岸辺に接近し、長い首を伸ばして詰め寄られると、けっこうな迫力がある。至近距離で大きな羽を広げてアピールされると、怖く感じるほどである。羽撃きの力も強いので、給餌の際には注意を要する。
各地の公園の池に周年いるハクチョウは、コブハクチョウ。元ヨーロッパを中心に生息していたものを飼育したものや、半野生化したものである。
ギャラリー
-
印西市のハクチョウ
-
二羽のハクチョウ
-
陸に上がり草を食べるハクチョウ
文化
- レダと白鳥 -ギリシア神話の主神ゼウスが白鳥に変身しレダを誘惑したというエピソードと、それを題材にした芸術作品群。
- はくちょう座 -上記のギリシア神話を由来とする。
- 白鳥の歌
- 白鳥の湖
- みにくいアヒルの子 - アンデルセンによるハクチョウを題材にした童話。
- 白鳥調べ(スワン・アッピング) - 白鳥は全てイギリス王室の管理下であったことから、個体識別用の足輪を付ける作業が行われる[3]。
脚注
- ^ “藤崎のハクチョウ”. 青森県庁ホームページ. 2025年11月2日閲覧。
- ^ 『青森県の文化財』青森県教育委員会、1997年3月28日、283頁。
- ^ “英テムズ川で「女王の白鳥」の調査始まる、伝統の年中行事”. Reuters (2018年7月17日). 2022年12月15日閲覧。
関連項目
- 列車
- 特急『白鳥』・『スーパー白鳥』 - 2016年まで運行されていた青函連絡特急。
- 特急『白鳥』 - 2001年まで大阪-青森間で運行されていた特急列車。
外部リンク
- 冬の使者ハクチョウが新潟・瓢湖に集結 - YouTube(朝日新聞社提供、2017年9月7日公開)
はくちょう
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/21 15:38 UTC 版)
「白鳥 (曖昧さ回避)」の記事における「はくちょう」の解説
カモ目カモ科ハクチョウ属に属する鳥類の総称 サギの別名。 かつて函館~新青森間(運転開始時は函館~八戸間)で運転されていたJRの特急列車→スーパー白鳥・白鳥 かつて大阪~青森間で運転されていた国鉄・JRの特急列車→白鳥 (列車) 日本人の名前の一つ。(例:正宗白鳥、三遊亭白鳥など) カミーユ・サン=サーンス作曲の組曲動物の謝肉祭中のチェロの独奏曲 X線天文衛星、はくちょう (人工衛星) 白鳥 (戯曲) - モルナール・フェレンツの戯曲。白鳥 (1930年の映画)(英語版) - 1930年のアメリカ映画。 白鳥 (1956年の映画) - 1956年のアメリカ映画。 白鳥 (1966年の映画) - 1966年の日本映画。
※この「はくちょう」の解説は、「白鳥 (曖昧さ回避)」の解説の一部です。
「はくちょう」を含む「白鳥 (曖昧さ回避)」の記事については、「白鳥 (曖昧さ回避)」の概要を参照ください。
「はくちょう」の例文・使い方・用例・文例
- はくちょうのページへのリンク









