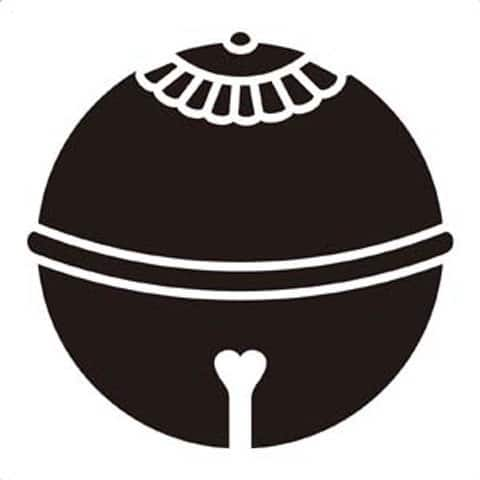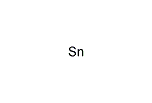鈴
「鈴」とは、金属や陶器などで作る振ると音が出る鳴り物のことを意味する表現。
「鈴」とは・「鈴」の意味
「鈴」は、金属や陶器で作られた小さな中空の外身の中に小さな石や玉を入れた音を出す道具で、乾燥したムクロジなどの木の実を振ると中で種子が動いて音を出すことに着想を得て作られたと言われている。その起源は定かではないが、縄文時代にはすでに土で作られた同じ構造の道具が作られていた。農耕文化が始まった縄文時代には、音を出す道具は合図など意思の表現に用いたり、作物を荒らす動物やクマなどの大型獣を追い払うための重要な道具であり、実際に多くの出土品も見つかっている。さらに弥生時代には鈴を大型にした銅鐸、続く古墳時代には金属製の鈴が存在していたことが考古学によって実証されている。さらに、鈴の澄んだ音色は魔除けの効果があるとされ、古くから祭礼にも広く用いられていた。日本の宗教である神道では、神々を祀る神社の拝殿に吊るされている鈴を「本坪鈴(ほんつぼすず)」と呼び、本坪鈴から下がっている綱「鈴緒(すずお)」を揺らすことで悪を祓い魔を退散させるとともに、神霊を呼び出して神様に会いに来たことを知らせるという意味を持つ。他にも仏教における仏具「リン」や、キリスト教の礼拝道具「香り香炉」など、スピリチュアルな面からも鈴と宗教とのつながりは深い。
また、鈴の音色は清らかな美しさを連想させることから、「美しく、清らかに育って欲しい」という思いを込めて「鈴」の字を子ども、特に女の子の名前に付けることが多い。ただし、ネットで「鈴 名前」と検索すると「鈴 名前 よくない」と関連キーワードが提示されるが、これは金・銀・鉱物に関する字は名前にふさわしくない、といういわれや、「中身が空洞」で縁起が悪いということが理由と思われる。しかし、実際には名前ランキングでも常に上位にランクインしている漢字であり、「美鈴」「鈴音」など人気の名前も多い。
「鈴」の語源・由来
「鈴」は「金」と「令」を組み合わせた文字で、土地の神を祀るための金の象形と、冠の下でひざまずく人の象形から成り立っている。その語源は明らかではなく、江戸時代中期の国学者・谷川士清(たにかわことすが)による国語辞典「和訓栞」の中にある「鈴とよむは音の涼(すず)しきより名づくなるべし」が起源であるという説や、音色を表現した「音の清(すず)しき意ともする」など諸説ある。「鈴」の熟語・言い回し
お守り鈴とは
お守り鈴とは、お守りに付いている小さな鈴のこと。お守り鈴には魔除けや邪気を浄化するという意味と、神様が来てくれるように願う「神の訪れ」が、鈴の音を身近に聞くことで「神の音連れ」となり、神様との縁を結ぶという意味もある。
鈴鳴りとは
鈴鳴りとはギターサウンドを形容する際によく使われる言葉で、鈴のように高音がきらびやかで美しい音のこと。シングルコイルのピックアップを持つエレキギターのハーフトーンでこの表現が用いられることが多い。
五十鈴とは
五十鈴は、奈良県吉野郡にある天河大辨財天社(てんかわだいべんざいてんしゃ)に「神宝」として祀られている鈴。3つの鈴が正三角形につながった形状で、それぞれ「いくむすび」「たるむすび」「たまめむすび」という魂の状態を表しており、この鈴の清流のような音の響きによって魂が深く清められ、本来あるべき状態に戻ると言われている。天河大辨財天社では各種の授与品が販売されている。
土鈴とは
土を焼いて作った鈴。古くから祭祀や動物除け、遠方との連絡などに使われており、縄文時代の遺跡などから数多くの出土品が見つかっている。現在でも地域にちなんだ土鈴や干支の土鈴など、魔除けや縁起物の郷土玩具で見ることができる。
すず【珠洲】
すず【×篠/×篶】
すず【鈴】
読み方:すず
1 金属・陶器などの、下部に裂け目のある空洞の球の中に小さい玉が入っていて、振り動かして音を立てるもの。神社にある大きなものや、合図用・装飾用・玩具用のほか、神楽・能楽・歌舞伎などの楽器としても用いられる。「拝殿で—を鳴らす」「猫の首に—をつける」
2 (「鐸」とも書く)釣鐘型で、舌(ぜつ)をつるし、振り動かして音をたてるもの。風鈴の類。鐸(たく)。れい。
3 西洋音楽の打楽器の一。1および2の形状のもの2種がある。ベル。
「—ばかり給はって」〈平家・五〉
すず【×錫】
すず 【鈴】
鈴
| 姓 | 読み方 |
|---|---|
| 鈴 | すず |
すず
すず
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/05/09 05:54 UTC 版)
義賊団「ねずみ党」の頭首。金髪のロングヘアーをツインテールにしている。頭頂部に、1束のアホ毛がある。
※この「すず」の解説は、「電撃ネコミミ侍」の解説の一部です。
「すず」を含む「電撃ネコミミ侍」の記事については、「電撃ネコミミ侍」の概要を参照ください。
すず
鈬
鈴
鈴
鈸
錫
鐸
鑞
鑾
「すず」の例文・使い方・用例・文例
- あの楽屋すずめは根も葉もないうわさを広める。
- 彼女は楽屋すずめで他人のうわさを広める誘惑に抗えない。
- すずりに墨を入れて筆に墨をつけて字を書きます。
- すずめが道を歩いていると、後ろから鷲が襲ってきました。
- すずめはこそこそ歩きました。
- すずめはその木の棒を大事に持って帰りました。
- そしてついにすずめは木の棒を取り返しました。
- 青銅は銅とすずから成り立っている。
- 今日は少しすずしい。
- すずめ百まで踊り忘れず。
- すずめが飛び回っていた。
- この鉄の板はすずでメッキしてある。
- 7月にしては今日はすずしい。
- 金[すず]アマルガム.
- 《諺》 「すずめ百まで踊りを忘れぬ」.
- すずめの涙ほどの給料.
- 金[すず]箔.
- この通りは通称「すずらん通り」と呼ばれている.
- 他の金属(特に鉛)を少量含んだすずの合金
- >> 「すず」を含む用語の索引
- すずのページへのリンク