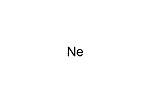neon
「neon」の意味・「neon」とは
「neon」は、化学元素の一つで、原子番号10の希ガス元素である。無色・無臭で、大気中に少量存在する。また、電気を通すと鮮やかな光を放つ特性から、看板や広告などの照明に利用される。この特性により、「neon」は「ネオンサイン」や「ネオンライト」といった形で日常的に耳にすることがある。「neon」の発音・読み方
「neon」の発音は、IPA表記では /ˈniː.ɒn/ となる。IPAのカタカナ読みでは「ニー・オン」となり、日本人が発音するカタカナ英語では「ニーオン」と読む。発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「neon」の定義を英語で解説
「neon」は、"A chemical element that is a colorless, odorless, inert monatomic gas that heads the noble gas group in the periodic table and that is used for filling fluorescent and various kinds of lamps and for some kinds of signs."と定義される。つまり、無色無臭で反応性の低い単原子のガスで、周期表の希ガス群を先頭に立つ元素であり、蛍光灯や様々な種類のランプの充填、あるいは一部の看板に使用される。「neon」の類語
「neon」の類語としては、「neon light」、「neon sign」、「neon lamp」などがある。これらはいずれも「neon」の特性を利用した製品や装置を指す言葉である。「neon」に関連する用語・表現
「neon」に関連する用語や表現としては、「neon lighting」、「neon tube」、「neon glow」などがある。「neon lighting」はネオンを使用した照明、「neon tube」はネオンガスを封入した管、「neon glow」はネオンが発する光を指す。「neon」の例文
1. Neon is a chemical element with the symbol Ne and atomic number 10.(ネオンは化学元素記号Ne、原子番号10の化学元素である。)2. Neon is a colorless, odorless, inert monatomic gas.(ネオンは無色無臭の反応性の低い単原子ガスである。)
3. Neon is used in neon lamps and fluorescent tubes.(ネオンはネオンランプや蛍光管に使用される。)
4. The neon sign lit up the dark street.(ネオンサインが暗い通りを照らした。)
5. The city was aglow with neon lights.(都市はネオンライトで光り輝いていた。)
6. Neon lighting is commonly used in commercial settings.(ネオン照明は商業施設でよく使用される。)
7. The neon tube emits a bright light when electricity is applied.(ネオン管は電気が通ると明るい光を放つ。)
8. The neon glow gave the room a surreal atmosphere.(ネオンの光が部屋に幻想的な雰囲気を与えた。)
9. The artist used neon in his installation.(その芸術家は彼のインスタレーションにネオンを使用した。)
10. The neon gas is sealed in a glass tube.(ネオンガスはガラス管に封入される。)
ネオン【neon】
ネオン
| 化合物名や化合物に関係する事項: | ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸 ニコチン酸 ネオン ノルアドレナリン バソプレッシン ヒスタミン |
ネオン
(NeoN から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/10 17:50 UTC 版)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 外見 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無色の気体に高電圧をかけると赤橙色に発光する。  ネオンのスペクトル |
|||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称, 記号, 番号 | ネオン, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 貴ガス | ||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 18, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 20.1797(6) | ||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8(画像) | ||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 相 | 気体 | ||||||||||||||||||||||||
| 密度 | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L |
||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 24.56 K, −248.59 °C, −415.46 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 27.07 K, −246.08 °C, −410.94 °F | ||||||||||||||||||||||||
| 三重点 | 24.5561 K (−249 °C), 43[1][2] kPa | ||||||||||||||||||||||||
| 臨界点 | 44.4 K, 2.76 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 0.335 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸発熱 | 1.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 熱容量 | (25 °C) 5R/2 = 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 酸化数 | 1[3], 0 | ||||||||||||||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 2080.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第2: 3952.3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 第3: 6122 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 58 pm | ||||||||||||||||||||||||
| ファンデルワールス半径 | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方格子構造 | ||||||||||||||||||||||||
| 磁性 | 反磁性[4] | ||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | (300 K) 49.1x10−3 W/(m⋅K) | ||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| 体積弾性率 | 654 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS登録番号 | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
| 主な同位体 | |||||||||||||||||||||||||
| 詳細はネオンの同位体を参照 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
ネオン(英: neon [ˈniːɒn]、仏: néon)は、原子番号10の元素である。元素記号はNe。原子量は20.180。
名称
ギリシャ語の「新しい」を意味する「νέος(neos)」に由来する[5]。
歴史

ネオンは1898年にロンドンで、イギリス人化学者ウィリアム・ラムゼー卿(1852–1916年)とモーリス・トラバース(1872–1961年)が発見した[6]。この当時、すでにヘリウムとアルゴンの存在が知られていたこと、さらに周期律が知られていたことから、その存在が確実視されていたが、この発見によって周期表の空欄が1つ埋まった。発見に至った手法は液化空気の分留である。ラムゼーが、液体状になるまで冷却した大気を暖めて気化したガスをそれぞれ分留する実験を行っているとき、大気主成分(窒素・酸素・アルゴン)を取り除いたあとに残る物質からクリプトン・キセノン・ネオンをそれぞれ見つけた[7]。
1910年12月、フランスの技術者ジョルジュ・クロードがネオンガスを封入した管に放電することで、新たな照明器具を発明した。パリの政府庁舎グラン・パレで公開後、1912年には彼は仲間たちとこの放電管をネオン管として販売し始め、理髪店で最初の広告として使用された。1915年に特許を取得し「クロードネオン社」を設立[8]。1923年、彼らがネオン管をアメリカに紹介すると、早速ロサンゼルスのパッカード自動車販売代理店に2つの大きなネオンサインが備えられた。赤々と輝き人目を惹くネオンの広告は、他社との差別化を鮮明に映し出した[9]。
1913年にジョゼフ・ジョン・トムソンが、陽極線の成分分析を行っていた際、磁界や電界を通る流れを導き出し、写真乾板上に写り込んだ軌跡から偏向を計測して、ネオン原子の基本的性質の解明が始まった。写真には2本の光軌跡が見つかり、これは異なる放物線を描くネオンの偏向があることを示していた。トムソンは、これが同じネオン元素で分子量が異なるものが2種類あるために起こった現象と結論づけた[10]。これは最初の安定的な同位体発見であり、その手法は改良され現在の質量分析法へ[11]と発展した。
性質・用途
単原子分子として存在し、単体は常温常圧で無色無臭の気体。融点−248.7 °C、沸点−246.0 °C(ただし融点沸点とも異なる実験値あり)。密度は0.900 g/L(0 °C、1 atm)、液体時は 1.21 g/mL(−246 °C)。空気中に18.2×10−6含まれ、貴ガスとしてはアルゴンに次ぐ割合で存在する。
質量磁化率−4.20×10−9 m3/kg。水に溶解する体積比は0.012[12]。
ネオンの三重点(約24.5561 K)はITS-90の定義定点になっている[13]。
ネオンはガスとしてのみならず、物質全体でももっとも反応性に乏しい元素である[14]。



ネオンは貴ガスとしては2番目に軽く、ガイスラー管に詰め放電すると橙赤色で光るため、ネオン管の封入気体として利用される[12]。実際は、アルゴンや水銀などの添加物を用いてさまざまな色を出す。標準的な電圧と電流下において、ネオンのプラズマは貴ガス中でもっとも激しい光を放つ。人間の目には一般に赤 - オレンジ色に見えるこの光は、実際には多くの波長からなっている。強い緑色の光線も含まれるが、これは分光しないと判断できない[15]。ネオン管は高電圧がかかると、管内に封入されているネオンがイオン化するために、サージ電流を素早く流す性質があり、落雷の電気をアースに流し機器類を守る避雷塔にも使われる[5]。
ネオンは窒素や酸素よりも原子番号が大きく、原子1つを比べた場合は、ネオンの方が重い。しかし、ネオンは地球の地表付近でも単原子分子として存在できるのに対し、同じ条件で窒素や酸素は二原子分子として存在する。気体は同一体積当たりの分子数がおおよそ等しいので、ネオンは地球の地表付近の空気の大部分を占める窒素分子や酸素分子よりも軽く、このため、ネオンの気球はヘリウムと比べればゆっくりであるが上昇する[16]。
液体ネオンの気化熱は1.8 kJ/mol であり、極低温環境での冷媒として非常に効率が高く、経済的である[5][17]。
同じ質量で気体・液体の体積比率差が大きいこともネオンの特徴である。通常の気体:液体比率が500–800倍なのに対し、ネオンは1400倍にもなる。そのため貯蔵性・輸送性に優れる。また、ネオンは窒素分子に近い密度があるため、酸素とネオンを混合して作った人工空気の中では、ほとんど音速が変化しない。よって、酸素とヘリウムの混合気のような声の変化は起こさない。この特徴を生かして大深度潜水のテクニカルダイビングや宇宙で使用されることもある[5]。
工業的には、空気を液化・分留して作る手段が唯一事業性を持てる[5]。半導体製造ではエキシマレーザーとフッ化クリプトンレーザーのバッファガスとして欠かせないが、工業用のネオンはロシアで生産され、ウクライナで精製されるネオンのシェアが高かった為、2014年のクリミア危機で価格が高騰したことから、利用量の削減や再利用の技術開発が行われた[18]。2016年にはアメリカのリンデが増産を発表した[18]。
このほかにも、ヘリウムとの混合ガスはレーザー光の波長を揃えることができる(ヘリウムネオンレーザー)[5]。
同位体
20Ne、21Ne、22Neの3種類の安定同位体の存在が知られている。地球では、これらのうち20Neが約9割を占めていて、22Neが1割弱、21Neはごくわずかである。
脚注
- ^ Preston-Thomas, H. (1990). “The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)”. Metrologia 27: 3–10.
- ^ “Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Melting, boiling, triple, and critical temperatures of the elements”. CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th edition ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press. (2005)
- ^ “HNe”. NIST Chemistry WebBook. National Institute of Standards and Technology. 2013年1月23日閲覧。
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds Archived 2012年1月12日, at the Wayback Machine., in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ^ a b c d e f 「【ネオン】」『元素111の新知識』(第六刷)講談社、1998年(初版1997年)、72–74頁。ISBN 4-06-257192-7。
- ^ ウィリアム・ラムゼー、モーリス・W・トラバース (1898年). “On the Companions of Argon”. Proceedings of the Royal Society of London 63: 437–440. doi:10.1098/rspl.1898.0057.
- ^ “Neon: History” (英語). Softciências. 2007年2月27日閲覧。
- ^ 小野博之. “ネオン史余話”. 社団法人全日本ネオン協会. 2010年4月17日閲覧。
- ^ Mangum, Aja (2007年12月8日). “Neon: A Brief History”. New York Magazine 2008年5月20日閲覧。
- ^ “1-3:中性子の発見”. 九州大学粒子物理学講座. 2010年4月17日閲覧。
- ^ “核燃料サイクル工学実験教育テキスト” (PDF). 財団法人エネルギー総合工学研究所. pp. 81. 2010年4月17日閲覧。
- ^ a b 「【ネオン】」『岩波理化学辞典』(第四版第九刷)岩波書店、1994年、948頁。 ISBN 4-00-080015-9。
- ^ “The Internet resource for the International Temperature Scale of 1990”. 2009年7月7日閲覧。
- ^ Lewars, Errol G. (2008年). Modelling Marvels. Springer. pp. 70-71. ISBN 1402069723
- ^ “Plasma” (英語). 2007年3月5日閲覧。
- ^ Gallagher, R.; Ingram, P. (2001年). Chemistry for Higher Tier. University Press. ISBN 9780199148172
- ^ “NASSMC: News Bulletin” (2005年12月30日). 2007年3月5日閲覧。
- ^ a b 株式会社インプレス (2022年2月28日). “【福田昭のセミコン業界最前線】 半導体不足を追い風に、2年連続で過去最大を更新する半導体市場”. PC Watch. 2022年3月15日閲覧。
参考文献
関連項目
外部リンク
- 国際化学物質安全性カード ネオン (ICSC:0627) 日本語版(国立医薬品食品衛生研究所による), 英語版
- 『ネオン』 - コトバンク
「neon」の例文・使い方・用例・文例
- NeoNのページへのリンク