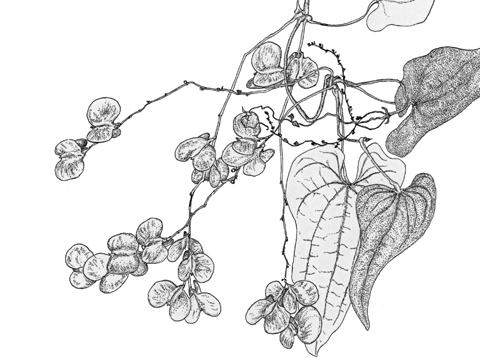やま‐の‐いも【山の芋/薯=蕷】
自然生
薯蕷
ヤマノイモ
ヤマノイモ ヤマノイモ科
山のいも
山の芋
ヤマノイモ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/23 08:44 UTC 版)
| ヤマノイモ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ヤマノイモ
|
|||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||
| Dioscorea japonica Thunb. (1784)[1] |
|||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||
| ヤマノイモ(山の芋) | |||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||
| Japanese yam glutinous yam |
ヤマノイモ(山の芋[2]・山芋[3]、学名: Dioscorea japonica)は、ヤマノイモ科ヤマノイモ属のつる性多年草。または、この植物の芋として発達した担根体のこと。地下に生じる芋は、ジネンジョウ(自然生)、ジネンジョ(自然薯)、ヤマイモ(山芋)ともよばれ、食用になり、とろろは粘性が非常に高い。また、ヤマノイモ属の食用種の総称ヤム(yam)をヤマノイモ、ヤマイモと訳すことがある。
なお、植物分類学上の「ヤマノイモ」はジネンジョ(自然薯)のみを指すが[4]、食材としての「やまのいも」はヤマノイモ科ヤマノイモ属に属する食用いも類として栽培されているものの総称をいう[4][5][注 1](ナガイモを参照)。本項では植物種としてのヤマノイモを基準に述べる。
名称
古くは中国原産のナガイモを意味する漢語の薯蕷を当ててヤマノイモと訓じた。日本特産で、英名はジャパニーズ・ヤム(Japanese yam)[7]、中国植物名(漢名)では、日本薯蕷(にほんしょよ)という[8]。日本原産の種であり、学名はディオスコレア・ジャポニカ(Dioscorea japonica)である。
別名のジネンジョ(自然薯)は、自然に生えている芋であるところからついた呼び名である[8]。日本で「芋」といえば、ヤマノイモのことを指す言葉であったが、人里で栽培される南アジア原産のサトイモが普及するにつれて、これに対してヤマイモ(山芋)とよばれるようになったものである[2]。地方により、キリイモ(霧いも)、トロロイモ、ムカゴイモなどの別名でもよばれる[9]。
畑で作られる中国原産のナガイモ(学名: Dioscorea polystachya)と一緒にして「やまいも」とよばれることもあるが、ナガイモとヤマノイモは別種の植物であり、本来「山芋」といえば日本原産のヤマノイモのほうを指した[2]。ナガイモの一品種にはヤマトイモ(大和芋)があり、日本の大和地方から栽培が広がったと考えられているが、ヤマイモ(ヤマノイモ)とヤマトイモの音が似ているので混同が生じたとも考えられている[2]。
分布と生育環境
日本原産で、北海道南西部[10]から本州・四国・九州・沖縄に分布[11]、国外では台湾および、朝鮮半島、中国に分布する[12]。平地から山地までの山野の林縁や藪などに他の木に絡みついて自生し[13][12][3]、里山の林道沿いや河川沿いの土手によく生えている。やや湿った土壌を好むが、鬱蒼とした林の中では自生しにくく少ない。高山には分布しない。発育条件が合えば公園の植え込みでも生育する。
形態・生態
雌雄異株の多年生つる植物で、茎は淡緑色で他物に絡みつき、地上部は1年で枯れる[14][13]。茎は長く伸びて、まばらに枝分かれをする[14]。葉はふつう対生するが、まれに互生し、葉身は長卵形から三角状披針形で、基部が凹んだ細長いハート形をしており、長い葉柄で茎につく[14][13][11]。葉身には先端に向って伸びる5本の葉脈が目立つ[2]。
花期は夏(7 - 9月ごろ)で[9]、葉腋から3 - 5本の細長い穂状の花序を出して、白い小さな粒のような目立たない花を付ける[14][2][12]。雌雄異株で雄株と雌株があり、雄花の花序は直立し、雌花の花序は垂れ下がる[14][13]。
果実は蒴果で平たく、円形の大きな3枚の陵(翼)があり、縦の長さより横幅が広い[14][13]。それぞれの陵が中に種子を1個含んでいて、熟すと壁が剥がれて、中から扁平な種子が出る[13][11]。種子は、周囲に紙のように薄い円形の膜質翼がついていて、果実が割れたときに散布される[14][13]。雌株では種子のほかに、葉腋に発生する球状の芽である零余子(むかご、珠芽)をつけて栄養繁殖する[13][11]。ムカゴ(球芽)は、種類によって付けるものと、つけないものがある[15]。ムカゴは直径1センチメートルほどの球状から、大きなもので長さ3センチメートルほどに達する場合がある。
地下には円柱状で多肉質の担根体(芋)が1本あり、自然薯(じねんじょ)ともよばれている[13]。トロロイモとしても知られているが、芋とされる中が白くて柔らかい部分は、植物学的には特殊な組織で担根体(たんこんたい)とよび、ヤマノイモ属に特有な根でも茎でもない器官であり[2]、茎の基部についた枝の下側部分が伸びたものである[14]。担根体は地下深くへとまっすぐに伸びて[14]、石などの障害物がなければ長さは1メートルを超えることもある[16]。毎年春に再び頂部から発芽して地上部を育てる栄養源となり、成長にしたがって担根体は縮小して夏までには元のイモはすっかりなくなって空の袋となり、秋までには再び栄養を蓄えて一回り大きな新しい担根体と置き換えられ更新される[9][3]。なお、秋にできるヤマノイモにできる芋のようなムカゴも、小型の担根体である[2]。
-
ムカゴ
-
果実
-
販売されている自然薯
採取・栽培

元来は野生の植物であり、晩秋にできる根茎を食用とするため、かつては山へ行って掘ってくるものだった。ヤマノイモと外観がよく似ている種にオニドコロがあり、収穫の際に間違うことがある[8]。オニドコロは葉が互生し、苦くて食べられない[8]。
イモ(担根体)は晩秋になって地上部が枯れるころ(11 - 1月[9])が収穫時期である。枯れ残った蔓を目当てにして山芋を探すが、地上部が枯れると場所がわからなくなるので、枯れる前に目印をつけておく[16]。芋を掘るには深い穴を掘らねばならないので、なるべく斜面の所を探す。掘る道具は、柄の長い鍬[9]、シャベルや移植ゴテのほか[16]、掘り棒・芋掘り鍬と呼ばれる大人の背丈ほどの鉄の棒で、先端が平らになったようなものを使う。蔓が地面に入り込んだところを特定し、イモを折らないように周辺の土を深く掘り下げて、石などを取り除きながら注意深く掘り出す[9]。地中深く曲がりくねって伸びるイモは、折らずに掘り出すまで難しさがあり[9]、先端まで掘り出すにはかなりの根気がいる[16]。うまく掘り出せた場合、蔓の元端に当たる芋の端を残して、穴を埋めるときに一緒に埋めておけば翌年も芋が生育し、再び収穫することができる。
むかごの採取時期は秋(9 - 11月ごろ)で、熟すと触れただけでつるから落ちるので、帽子などを受け皿にして採取する[9]。
現在ではむかごの状態から畑で栽培されており、流通しているのは栽培ものが多い。収穫しやすいように、細長い塩化ビニールパイプや波板シートを使って栽培している。なお、天然のもの(自然生・自然薯)は、掘り出す行為そのものが山の斜面の崩壊を助長すること等の理由から、山芋掘りが禁止されている場合がある。
利用法
| 100 gあたりの栄養価 | |
|---|---|
| エネルギー | 506 kJ (121 kcal) |
|
26.7 g
|
|
| 食物繊維 | 2.0 g |
|
0.7 g
|
|
| 飽和脂肪酸 | 0.11 g |
| 一価不飽和 | 0.04 g |
| 多価不飽和 | 0.11 g |
|
2.8 g
|
|
| ビタミン | |
| チアミン (B1) |
(10%)
0.11 mg |
| リボフラビン (B2) |
(3%)
0.04 mg |
| ナイアシン (B3) |
(4%)
0.6 mg |
| パントテン酸 (B5) |
(13%)
0.67 mg |
| ビタミンB6 |
(14%)
0.18 mg |
| 葉酸 (B9) |
(7%)
29 µg |
| ビタミンC |
(18%)
15 mg |
| ビタミンE |
(27%)
4.1 mg |
| ミネラル | |
| ナトリウム |
(0%)
6 mg |
| カリウム |
(12%)
550 mg |
| カルシウム |
(1%)
10 mg |
| マグネシウム |
(6%)
21 mg |
| リン |
(4%)
31 mg |
| 鉄分 |
(6%)
0.8 mg |
| 亜鉛 |
(7%)
0.7 mg |
| 銅 |
(11%)
0.21 mg |
| 他の成分 | |
| 水分 | 68.8 g |
| 水溶性食物繊維 | 0.6 g |
| 不溶性食物繊維 | 1.4 g |
| ビオチン(B7) | 2.4 µg |
| 有機酸 | 0.4 g |
|
ビタミンEはα─トコフェロールのみを示した[18]。廃棄部位: 表層及びひげ根
|
|
|
|
| %はアメリカ合衆国における 成人栄養摂取目標 (RDI) の割合。 |
|
主に地下に出来る長いイモの部分を食用にし、ムカゴも食用にする[12]。根茎(芋)とされる担根体は、昔から滋養強壮がつくとして食用・薬用に利用されており、根茎にはデンプン、粘液質のムチレージ、アミラーゼ(ジアスターゼ)、マンニット、コリン、アルギニン、アミノ酸、サポニンなどが含まれている[19]。根茎の汁が肌につくとかゆみを感じるときがあるが、根茎に含まれるサポニンによって肌が刺激されるためで、アレルギー体質の人は強く感じるときがある[19]。ムチンは、たんぱく質の吸収を促して、血糖値の上昇を抑制し、コレステロールの低下にも効果がある[7]。栄養素としてはビタミンB群、ビタミンC、カリウム、食物繊維を含む[7]。
食用
地中に長く伸びる芋(担根体)をすりつぶしてとろろにして食用にする[20]。自生するものは自然薯(じねんじょ)とよばれ、栽培種のナガイモ(長いも)よりモチモチした食感で粘りが強い[20]。すりおろしたイモを海苔で巻いて油で揚げた磯辺巻き、粗い千切りにしてサラダや天ぷらにする[16]。
むかごは、主に加熱調理して塩茹でや、少し塩味をつけて炊き込みにして食用にするが[2]、生食もできる。そのままの状態だとカリカリという食感が楽しめ、すりおろすと芋同様の強い粘りがある。むかごは、時間をかけてよく茹でたあとに塩を振ったり、フライパンで塩焼きにして食べられていて、とろろ芋同様に滋養強壮によいといわれている[14][20]。むかごを米と一緒に炊いた「むかご飯」は風味豊かで、日本料理でしばしば出る高級料理でもある[20]。油炒めや唐揚げにしても良い[16]。
生食の可能な理由はヤマノイモが多量に含む消化酵素アミラーゼがデンプンの消化を促進するためといわれている[7]。ただし近年の研究では、これを否定する研究発表もなされている[21]。
- とろろ
- すりおろしてから白醤油や出汁などを加えてのばしとろろにするのが代表的な調理法である。ナガイモのとろろと比較すると遥かに粘り気が強い。
- とろろを伸ばして麦飯ないし麦入り米飯にかけた「麦とろ」があり、東海道五十三次の鞠子宿(現、静岡県静岡市駿河区丸子)の名物とされたが、鞠子宿のとろろ汁は、自然薯を味噌でのばしたものが供される[22]。岡本かの子の随筆「東海道五十三次」にも、丸子で食したとろろ汁について「炊き立ての麦飯の香ばしい湯気に神仙の土のような匂いのする自然薯は落ち付いたおいしさがあった」とある[注 2][23][24]。この宿駅のとろろ汁の店は「丁字屋」(慶長元年(1596年創業))であるとその名が『東海道中膝栗毛』に明記されており、この店は浮世絵師の歌川広重によっても描かれている[23]。松尾芭蕉に「梅若菜、鞠子宿のとろろ汁」という俳句があり、店のそばの句碑は文化11年(1814年)に建てられたものである[23]。
- とろろ芋をすりおろしたものを「山かけ」と称し、「まぐろの山かけ」や「山かけ蕎麦」があるが[25][26]、こうした山かけの料理や、うどん等にあえて自然薯のとろろ使用をうたった飲食店もある[27][28]。また、自然薯をそば粉に練り込んで打った自然薯そばもそば処で出されている[注 3][26]。
- 伝統料理
- 芋粥は、平安時代を背景とする物語(芥川龍之介の小説『芋粥』やその原典『今昔物語集』中)に登場するが、これは皮を剥き薄切りにしたヤマノイモを、アマヅラの煮詰め汁で炊いたものであり、現代のサツマイモ入りの穀物粥であるいわゆる芋粥とは根本的に違う[29][30]。これは『群書類従』に収録された鎌倉時代の宮中料理次第事典『厨事類記』の、菓子の部類についてのうちにその調理法などが記載され、文章は以下である[31]。
薯預粥ハ ヨキイモヲ皮ムキテ ウスクヘキ切 <天> ミセン(味煎)ヲワカシテイモヲイルヘシ イタクニルへカラス 又ヨキ甘葛煎ニテニルトキハ アマツラ一合ニハ水二合ハカリイレテニル也 石ナへ(石鍋)ニテニル チヒサキ銀ノ尺子ニテモリテマイラス云々 銀ノ提ニ入テ銀ノ匙ヲク(具)シテマイラスヘシト云々—厨事類記
- ヤマノイモを利用した米粉の麺類である薯蕷麺は、『日葡辞書』(1604年)に「Ioyomen ジョヨメン」記載があり[32]、江戸時代後期に塙保己一(1821年没)が著した叢書『続群書類従』(料理物語 - 飲食部)の章にて「しよよめん(薯蕷麺)」を紹介している。内容は端的に食材と料理法を載せ、文章は以下である。
山の芋を細かにおろし、もち米の粉六分、うる米四分をこまかにはたき。山の芋にてよきころにこね。玉をちいさうして、きりむぎうち申ごとくに、うち候。茹で加減は、にまううきあがる時節。是も汁は切麥同前。—塙保己一、続群書類従
- 現在は薯蕷麺(いもめん)と呼び、『続群書類従』同じくもち米とうるち米の粉、ヤマノイモを原料とした麺を言う[33]。
- ヤマノイモは、薯蕷饅頭(じょうよまんじゅう)、かるかん、栗きんとんなど、和菓子の材料にもなる。製菓用の粉末状の製品もある。
- その他
- とろろを出汁でのばさずに海苔に包んで揚げる料理もあり、磯辺揚げと呼ばれている。
- ヤマノイモを生のまま短冊切りなどの食べやすい形に切って、他の生野菜と共にサラダにする食べ方も現代では行われている。断面に若干の粘り気があり、オクラのような食感が楽しめる。
薬用
『古事記』(712年)や『日本書紀』(720年)の時代から薬用として使われていたとみられている[7]。
皮をむいて天日乾燥した担根体(根茎)は、野山薬(のさんやく)または土山薬(どさんやく)と称され、生薬になる[8]。山薬(さんやく)は本来は中国原産で栽培されるナガイモ(通称:トロロイモ)の漢名であるが[8]、ヤマノイモまたはナガイモの担根体を生薬にしたものもこう呼ばれており[13]、栽培種も同様に用いられる[13]。これは日本薬局方に収録されており[34]、滋養強壮、止瀉、止渇作用があり、腸炎による下痢止め、夜尿症、頻尿、寝汗、咳、喘息、腰痛に効用があるといわれており[8][13]、薬効はナガイモ(山薬)も同じである[8]。漢方では滋養強壮の目的で処方され[16]、八味地黄丸(はちみじおうがん)、六味丸(ろくみがん)などの漢方方剤に使われる。生薬にする根茎は、秋にヤマノイモの葉が黄変してから冬季にかけて根茎を掘り採って、頭の部分を切り取って水洗いし、竹べらで皮を剥ぎ取って、長さ10センチメートルくらいに切り、天日で乾燥して調整される[8][13]。
民間療法では、乾燥した根茎1日量3 - 10グラムを水400 ccで4分の3になるまで煎じ、3回に分けて服用する用法が知られる[8][13]。また、生食しても同様の薬効が期待できる[8]。咳、喘息には痰が切れにくくカラ咳の人によいとされ[8]、生の根茎をすり下ろして、砂糖を加えて熱湯を注いで飲む[13]。寝汗や夜尿症に、生のイモをアルミホイルで包み焼きにし、毎日食べると効果があるといわれる[16]。乗り物酔いする人や、吐き気のある人への服用は禁忌とされている[8]。滋養強壮には根茎をそのまま生食するか、山薬酒をつくって就寝前に1日盃1杯飲用する[19]。山薬酒は、山薬を細かく砕いて200グラムあたりホワイトリカー1.8リットルに漬け込み、2 - 3か月冷暗所に保存しておいてから、漉して作られる[19]。
保存
晩秋から冬に掘り上げた生いもは、凍らせない程度に保存し、随時使用する[13]。皮をむき、せん切り、輪切りなどを使いやすい大きさに切り、酢水につけてから水気をふき取り、冷凍保存袋にいれて保存する。保存期間は2週間[35]。
類似している植物

ヤマノイモ科の植物はトコロ種など野生種が数種あり、いずれもよく似ている。むかごを作るものもあるが、食用にならないものもある。
グロリオサ
高知県では2006年(平成18年)に、静岡県では2007年(平成19年)に、ユリ科の鑑賞用植物のグロリオサの球根をヤマイモと間違えて食べ、死亡する事故が起こっている[36]。
ユリ科の鑑賞用植物のグロリオサは、地上部が葉の巻ひげや反転する花弁を持つことから識別は容易であるが、球根の形状が似ているため誤食される。球根での見分け方は、表面が滑らかでヒゲ根がなく、表皮がはがれやすい特徴が異なる[38][39]。
ナガイモ
中国原産で17世紀に日本に移入されたとされるナガイモ(D. batatas)のことをヤマイモと呼ぶことがある[40]。 栽培されるヤマノイモによく似た植物で、野生化して茎と葉柄が紫色になった個体は、ヤマノイモとの見分けは難しい[12]。
なお、植物分類学上の「ヤマノイモ」はジネンジョ(自然薯)のみを指し[4]、ナガイモとは染色体数が異なる別種であるが[41](染色体数は通常、ジネンジョが2n=40、ナガイモが2n=140[42])、先述の通り、食材としての「やまのいも」は広くヤマノイモ科ヤマノイモ属に属する栽培された食用いも類の総称をいう[4][5][41]。
トコロ種
- オニドコロ(鬼野老、学名:Dioscorea tokoro)
- ヒメドコロ(姫野老、学名:Dioscorea tenuipes)
- 本州から沖縄に分布。山野の林縁に生える。葉はハート形でオニドコロよりも細い。花期は夏で、雄花・雌花ともオニドコロによく似た淡緑色で、雄花の花序が垂れ下がる。葉の付け根にムカゴは出来ないが、根茎は食用になる。[44]
カシュウイモ
別名ニガカシュウ(苦何首烏、Dioscorea bulbifera)。名前は根塊が薬用の「何首烏」に似ていることからついた。葉はハート型で大きく、デコボコした大ぶりのむかごがつくが、日本野生種は苦く有毒で食用にならない。しかし苦味や毒のない品種もあり、ヤマイモほど大きくはならず粘りも出ないが食用できる。むかごが数百グラムにも肥大する「Air potato(空中のイモ)」と呼ばれる食用品種もあり、日本でも「宇宙イモ」という名前で一部で栽培されている。
関連項目
脚注
注釈
出典
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Dioscorea japonica Thunb. ヤマノイモ(標準)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2023年9月16日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i 吉村衞 2007, p. 120.
- ^ a b c 高野昭人監修 世界文化社編 2006, p. 110.
- ^ a b c d e 新津泰亮 (2019年10月). “やまのいもをめぐる情勢について”. 『特産種苗』 第29号. 公益財団法人日本特産農作物種苗協会. 2025年7月20日閲覧。
- ^ a b “やまのいも”. VEGETABLE BOOK. 独立行政法人農畜産業振興機構. 2025年7月20日閲覧。
- ^ “農業技術大系・野菜編 2022年版(追録第47号)”. ルーラル電子図書館. 2025年7月20日閲覧。
- ^ a b c d e 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編 2012, p. 124.
- ^ a b c d e f g h i j k l m 貝津好孝 1995, p. 73.
- ^ a b c d e f g h 篠原準八 2008, p. 108.
- ^ 北海道南西部桧山地域に生育するヤマノイモの遺伝的特性
- ^ a b c d 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 2012, p. 220.
- ^ a b c d e 近田文弘監修 亀田龍吉・有沢重雄著 2010, p. 214.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 馬場篤 1996, p. 112.
- ^ a b c d e f g h i j 田中孝治 1995, p. 211.
- ^ 板木利隆『図解やさしい野菜づくり』家の光協会、1996年10月、257頁。ISBN 978-4259533946。
- ^ a b c d e f g h i 高野昭人監修 世界文化社編 2006, p. 111.
- ^ 文部科学省 「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」
- ^ 厚生労働省 「日本人の食事摂取基準(2015年版)」
- ^ a b c d 田中孝治 1995, p. 212.
- ^ a b c d 篠原準八 2008, p. 109.
- ^ 団野源一「ヤマノイモを生で食することができる理由は生でんぷんの消化性によるものではない」『大阪青山大学紀要』第2巻、大阪青山大学『大阪青山大学紀要』編集委員会、2009年3月、29-31頁、 CRID 1050564288823221632、 ISSN 18833543、国立国会図書館書誌ID: 10905743。
- ^ 徳力富吉郎『東海道53次』保育社、1992年、37頁。
- ^ a b c 清水茂雄「静岡市とその周辺の文学」『国文学年次別論文集 国文学一般平成10(1998)年』、42–43頁2000年。
- ^ 岡本かの子『東海道五十三次』1939年
- ^ 見坊豪紀「山かけ」『三省堂国語辞典』、1152頁1982年。
- ^ a b 植原路郎『蕎麦談義』東京堂出版、1973年、61頁。
- ^ 「マグロ祭りきょうから 都留」『読売新聞』2019年3月16日。
- ^ 「自然薯の栽培を10年前に始め自然薯料理店「みや古」、玉城町に」『伊勢志摩経済新聞』2014年2月23日。
- ^ 赤井達郎『京の美術と芸能: 浄土から浮世へ』京都新聞出版センター、1985年、89頁。
- ^ 谷口歌子「′85短歌セミナ--2-古典文学にみる食物--奈良・平安期を中心として」『短歌研究』第42巻、第2号、313頁、1990年。
- ^ 『群書類従 厨事類記』国立公文書館デジタルアーカイブ
- ^ 林文子「『日葡辞書』が語る食の風景(1)」『東京女子大学紀要論集』第58巻第2号、東京女子大学、2008年3月、134頁、 CRID 1050001337659479552、 ISSN 04934350。
- ^ 歴史民俗用語辞典「薯蕷麺イモメン(imomen)」 日外アソシエーツ 2015年09月19日閲覧
- ^ “第十八改正日本薬局方”. 厚生労働省. p. 生薬-166. 2021年4月5日閲覧。
- ^ 『作りおきおかずで朝ラクチン!基本のお弁当300選』180頁。
- ^ 自然毒のリスクプロファイル:高等植物:グロリオサ 厚生労働省
- ^ 稲葉, 大地、杉本, 龍史、安武, 祐貴、上村, 吉生、芳澤, 朋大、花澤, 朋樹、吉原, 秀明「グロリオサ誤食によるコルヒチン中毒の1例」2022年12月10日、doi:10.57388/jjct.35.4_319。
- ^ a b “グロリオサによる食中毒の発生について - 高知市公式ホームページ”. www.city.kochi.kochi.jp. 2024年12月18日閲覧。
- ^ “東京都健康安全研究センター » ヤマイモとグロリオサの根”. www.tmiph.metro.tokyo.lg.jp. 2024年12月18日閲覧。
- ^ 主婦の友社編『野菜まるごと大図鑑』主婦の友社、2011年2月20日、204 - 205頁。 ISBN 978-4-07-273608-1。
- ^ a b “ながいものルーツ”. 環境研ミニ百科. 公益財団法人環境科学技術研究所. 2025年7月21日閲覧。
- ^ 鈴木健司、小原麻里、岩佐博邦 (2005年3月). “倍加ジネンジョの作出とその特性について”. 『千葉県農業総合研究センター研究報告』 第4号. 千葉県農業総合研究センター. 2025年7月21日閲覧。
- ^ 吉村衞 2007, p. 121.
- ^ a b 近田文弘監修 亀田龍吉・有沢重雄著 2010, p. 215.
- ^ 鈴木晋一 『たべもの史話』 小学館ライブラリー、1999年、195 - 201頁
参考文献
- 板木利隆『図解やさしい野菜づくり』家の光協会、1996年10月、257頁。 ISBN 978-4259533946。
- 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編『かしこく選ぶ・おいしく食べる 野菜まるごと事典』成美堂出版、2012年7月10日、124 - 125頁。 ISBN 978-4-415-30997-2。
- 貝津好孝『日本の薬草』小学館〈小学館のフィールド・ガイドシリーズ〉、1995年7月20日、73頁。 ISBN 4-09-208016-6。
- 近田文弘監修 亀田龍吉・有沢重雄著『花と葉で見わける野草』小学館、2010年4月10日、214 - 215頁。 ISBN 978-4-09-208303-5。
- 篠原準八『食べごろ 摘み草図鑑:採取時期・採取部位・調理方法がわかる』講談社、2008年10月8日、108 - 109頁。 ISBN 978-4-06-214355-4。
- 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文『草木の種子と果実』誠文堂新光社〈ネイチャーウォッチングガイドブック〉、2012年9月28日、220頁。 ISBN 978-4-416-71219-1。
- 高野昭人監修 世界文化社編『おいしく食べる 山菜・野草』世界文化社〈別冊家庭画報〉、2006年4月20日、110 - 112頁。 ISBN 4-418-06111-8。
- 田中孝治『効きめと使い方がひと目でわかる 薬草健康法』講談社〈ベストライフ〉、1995年2月15日、210 - 212頁。 ISBN 4-06-195372-9。
- 馬場篤『薬草500種-栽培から効用まで』大貫茂(写真)、誠文堂新光社、1996年9月27日、112頁。 ISBN 4-416-49618-4。
- 吉村衞『おいしく食べる山野草』主婦と生活社、2007年4月23日、120 - 121頁。 ISBN 978-4-391-13415-5。
ヤマノイモ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 17:58 UTC 版)
「日本原産の食用栽培植物」の記事における「ヤマノイモ」の解説
ヤマノイモ(山芋)は、自然薯(じねんじょ)ともいい、ヤマノイモ科ヤマノイモ属のつる性の多年草である。マレー半島が原産地と思われるサトイモや中国原産のナガイモとは異なり、日本原産であり、学名をDioscorea japonicaという。すりおろしてとろろにして生食するのが一般的であるが、ナガイモよりはるかに粘性に富み、むかごも食用可能である。かるかんなど和菓子の素材となったり、生薬の材料となることもある。
※この「ヤマノイモ」の解説は、「日本原産の食用栽培植物」の解説の一部です。
「ヤマノイモ」を含む「日本原産の食用栽培植物」の記事については、「日本原産の食用栽培植物」の概要を参照ください。
「ヤマノイモ」の例文・使い方・用例・文例
ヤマノイモと同じ種類の言葉
- ヤマノイモのページへのリンク