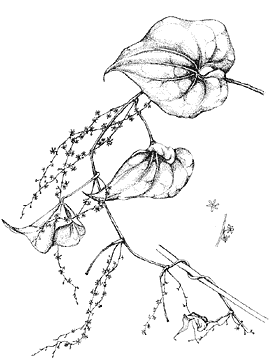ところ【所/▽処】
読み方:ところ
 [名]
[名]
㋐住んでいる場所。住所。住居。「お—とお名前を教えてください」
2 抽象的な場所。場面。範囲。多く、連体修飾語によって限定される場所や部分をいう。
㋑その人の所属している組織や集団。「知り合いの—に発注する」
㋓場面。局面。「今の—おとなしい」「今日の—は許してやろう」
㋕事柄。内容。こと。「思う—あって辞任する」「自分の信じる—を貫く」
㋖範囲。程度。「調べた—では、そんな事実はない」「歩いて30分といった—かな」
㋗(数量を表す語に格助詞「が」が付いた形を受けて)だいたいの程度を表す。「10分が—遅れた」「1万円が—借りている」
3 (「どころ」の形で)
㋐名詞に付いて、それが名産となっている地域を表す。「米—」「茶—」
㋑動詞の連用形に付いて、その動作の行われる場所や部分、またその対象となる部分をいう。「うわさの出—」「つかみ—のない人」
㋒動詞の連用形に付いて、その動作をするのによい場所や部分、そうすべき場所や部分をいう。「ごみの捨て—」「見—のある新人」「心のより—」
㋓名詞や形容詞・形容動詞の語幹に付いて、それにあてはまる人々の意を表す。「中堅—が脇を固める」「きれい—を集める」
4
㋐《漢文の、受身を表す「所」の訓読から。「…ところとなる」の形で》前に置かれた語句が示す行為の対象であることを表す。「世人の称賛する—となった」
㋑《西洋語の関係代名詞の翻訳から、格助詞「の」を介して、体言またはそれに準じるものを修飾して》連体修飾語の役割をする。多く翻訳調の文章に用いられる。「世に知られている—の画家」「かつて訪れた—の屋敷」
5 (「…したところ」の形で接続助詞的に用いて)上述した内容を条件として文を続ける。順接にも逆接にも用いる。「訪ねた—、不在だった」「依頼した—、断られた」
6 「蔵人所(くろうどどころ)」「武者所(むしゃどころ)」などの略。
1 場所や箇所などを数えるのに用いる。「傷口を三—も縫った」
[下接句] 帰する所・此処(ここ)の所・十指の指す所・十目(じゅうもく)の視(み)る所十手(じっしゅ)の指す所・早い所・日没する処(ところ)
ところ【野=老】
オニドコロ
葇檞
山萆檞
止己呂
都古侶
野老
草薢
野老
トコロ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/13 00:55 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年6月)
|
| トコロ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ウチワドコロ
|
||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||
| Dioscorea | ||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||
| トコロ |
トコロ(野老)は、ユリ目ヤマノイモ科ヤマノイモ属 (Dioscorea) の蔓性多年草の一群。「~ドコロ」と呼ばれる多くの種があるが、特にオニドコロを指すことがある。
ヤマノイモなどと同属だが、根は食用に適さない。ただし、灰汁抜きをすれば食べられる。トゲドコロは広く熱帯地域で栽培され、主食となっている地域もある。日本でも江戸時代にはオニドコロ(またはヒメドコロ)の栽培品種のエドドコロが栽培されていた。現代では、青森県や岩手県の南部地方などで食用とする文化が残っている。
なお、有毒のハシリドコロはトコロと名が付いているが、ヤマノイモ属ではなくナス目ナス科ハシリドコロ属である。また、おなじくトコロと名が付くアマドコロは根茎がオニドコロに似るためこの名があるとされるがキジカクシ目キジカクシ科アマドコロ属である。
主な種類
- ツクシタチドコロ D. asclepiadea
- トゲドコロ(トゲイモ、ハリイモ) D. esculenta
- タチドコロ D. gracillima
- ミツバドコロ D. hispida
- イズドコロ D. izuensis
- ウチワドコロ D. nipponica
- アケビドコロ(ゴヨウドコロ) D. pentaphylla
- カエデドコロ D. quinqueloba
- キクバドコロ D. septemloba
- ユワンオニドコロ D. tabatae
- ヒメドコロ D. tenuipes
- オニドコロ D. tokoro
関連項目
固有名詞の分類
- トコロのページへのリンク