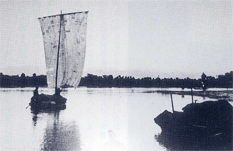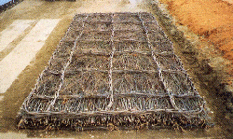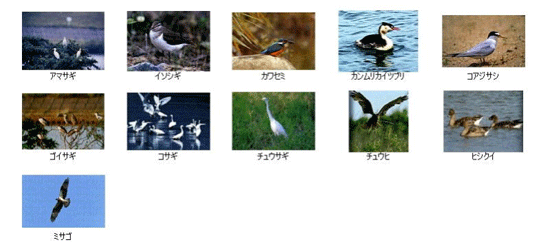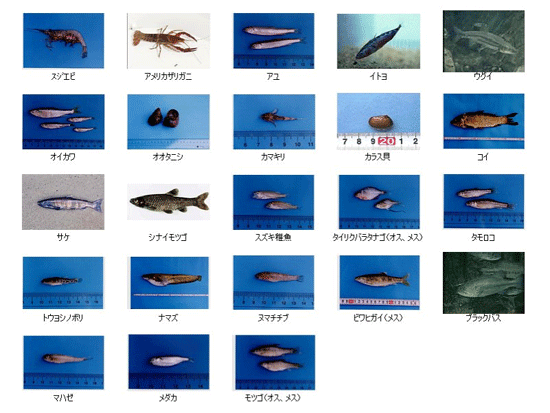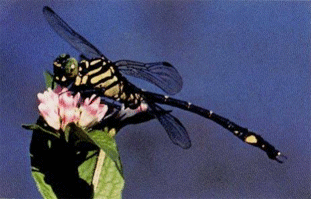信濃川下流
| 信濃川の水源は、甲武信ヶ岳にその源を発し、「千曲川」という名で長野県内を流れ、途中犀川を合流し、新潟県に入って「信濃川」と名前を変え、越後平野をうるおし日本海へと注いでいます。信濃川下流とは、大河津分水路分派点から日本海に注ぐ河口までの約60kmを指します。 |
 |
| 新潟市中心部を流れる信濃川 |
| 河川概要 |
|
 ○拡大図 |
| 1.信濃川下流の歴史 |
| "信濃川流域に住む人々は、川の流れを利用した舟運を行うなど、水運から多くのものを得ました。人々は度重なる水害に苦しみながら洪水の氾濫を防ぎ、低湿地という厳しい条件の中で日本の代表的な穀倉地帯を造りました。雑木を用いて組み立てる伝統的河川工法「粗朶沈床」は現在も広く使われています。" |
|
人と文化を運んだ信濃川と先人達のたたかい |
| 2.地域の中の信濃川下流 |
| "信濃川と中ノ口川に挟まれた白根市では川を挟んだ大凧合戦が有名です。三条市から白根市にかけての河川敷は春先にモモやナシの花に染まり、新潟市街地では緩やかな斜面をもつ堤防「やすらぎ堤」が多くの人々に親しまれています。" |
|
地域とのつながり「水辺からやすらぎを、まちへ、人へ」 伝統文化 信濃川と中ノ口川に挟まれた白根で有名なのは、なんといっても白根大凧合戦です。 毎年6月2日から5日間、中ノ口川を挟んで、対岸の味方村との間で行われる大凧の大きさは縦7.27m、横5.46m、この大凧に縦3.03m、横2.42mの六角凧が混じって、合わせて十数枚の凧が空を乱舞します。上杉謙信や桃太郎の巨大な図柄が大空に浮かぶ様は勇壮そのものです。この大凧合戦は、空中で凧を絡ませ、どちらかの綱が切れるまで引き合って勝負を決めます。だから綱は軽くて丈夫でなければならず、綱よりの名人が斎戒林浴してよりあげると言います。
白根側が中ノ口川堤防工事が完成したことを祝って大凧を揚げたところ、その凧が対岸の味方村に墜落して農作物に大きな被害を出してしまいました。怒った味方村の人々が大凧を揚げて挑んだのがこの凧合戦のそもそもの始まりと言われています。 河川敷利用 三条市大島の信濃川河川敷は、大正時代からモモが植えられています。その後野菜畑や水田となったが、十数年ほど前からモモの栽培が盛んになり、春先になると大島の河川敷はモモの花でピンク色に染まります。洪水によって悩まされ続けた土地は、肉質、風味とも抜群の「幻のモモ」を育む恵みの大地に変わりました。三条市大島から信濃川下流域の白根市大郷にかけての河川敷にはモモとナシの畑が続き、県内でも有数の果樹地帯となっています。
親水空間の創出 関屋分水と分かれて日本海へ注ぐまでの新潟市街地を流れる区間の堤防は洪水による被害を防ぐことに加え、良好な水辺環境の創出に配慮した緩やかな斜面をもつ堤防整備に全国で初めて取り組み、通称「やすらぎ堤」と名付けられ、市街地に近接した「水と緑のオープンスペース」として散策やスポーツ、花火大会等イベントの場としても利用され多くの人々に親しまれています。
総合的な学習の時間
|
| 3.信濃川下流の自然環境 |
| "信濃川の魚の主役はサケです。鳥屋野潟や佐潟に代表される湖沼には多くの魚類が生息し、多種の渡り鳥も姿をみせます。新潟市内の信濃川には県内唯一の生息地と考えられるトンボの「ナゴヤサナエ」が羽化を続けています。" |
|
信濃川下流域の豊かな自然 信濃川下流域は、「新潟」の名のとおり潟が多く、潟・湿地といった静かな水面と、信濃川という動的な水面を結ぶネットワークが形成されており、自然の状態が多く残っている河岸では、越後平野に広がる低平湿地の面影を残す水際植生や魚類、植生を住処とする野鳥を観ることができます。 信濃川下流付近で見られる鳥類 信濃川下流域は、1年を通して60種を越える様々な野鳥を見ることができ、渡り鳥の通過地や休息地としても、多種類の鳥が姿をみせます。4月には、越冬していたマガモ、ツグミなど冬鳥のグループと、渡米したツバメ、コムクドリなど夏鳥のグループが、9月には、繁殖期を終えたササゴイ、ノビタキなどが移動を始める一方で、ツバメやオオヨシキリなどはまだ川にとどまっています。冬には、ハクチョウ類や、カモメ類などの水鳥が飛び交い、厳冬期の湖沼群では、翼を広げると2mにもなるオジロワシやオオワシの姿を目にすることができます。鳥屋野潟一帯には猛禽類がエサとする生き物が住んでいるため、ハヤブサ、オオタカなど10種類ものワシタカ類が姿を見せます。
信濃川下流域で見られる魚類
信濃川下流域で見られる昆虫
|
| 4.信濃川下流の主な災害 |
|
(注:この情報は2008年2月現在のものです)
固有名詞の分類
- 信濃川下流のページへのリンク