カルマ
英語:karma
「カルマ」の意味・「カルマ」とは
「カルマ」とは、インド哲学や宗教において、個人の行為や意識が生み出す善悪の実体であり、それが次の生に影響を与えるとされる概念である。カルマは、人間の行いや心の働きが宇宙の法則によって報いられるという考え方に基づいている。具体的には、善行を積めば幸福な生活や良い転生が得られるとされ、逆に悪行を積むと苦難や悪い転生が訪れるとされている。「カルマ」の語源
「カルマ」の語源は、サンスクリット語の「कर्म」(karma)であり、「行為」や「業」を意味する。この言葉は、インドの古典語であるサンスクリット語に由来し、インド哲学や宗教において重要な概念として扱われている。また、カルマの概念は、ヒンドゥー教や仏教、ジャイナ教などのインド起源の宗教に共通して見られる。「カルマ」に関連する用語・知識
スピリチュアルな観点における「カルマ」とは
スピリチュアルな観点からの「カルマ」は、人間の魂が持つエネルギーの総体として捉えられることが多い。スピリチュアルな世界では、カルマは前世や今世、来世にわたって影響を及ぼすとされ、自分自身のカルマを浄化することで、より良い人生や魂の成長が促されると考えられている。「仏教」における「カルマ」とは
仏教においては、「カルマ」は「業」とも呼ばれ、人間の行為が次の生に影響を与えるという考え方が基本である。仏教では、カルマが蓄積されることで輪廻転生が続くとされ、悟りを開いてカルマを断ち切ることで、輪廻から解脱し、涅槃に至ることができるとされている。「業(カルマ)」とは
「業」とは、カルマの日本語訳であり、人間の行為や意識が生み出す善悪の実体を指す。業は、善業と悪業に分けられ、善業は幸福や良い転生をもたらし、悪業は苦難や悪い転生をもたらすとされている。業は、インド哲学や宗教において重要な概念であり、人間の行いや心の働きが宇宙の法則によって報いられるという考え方に基づいている。「カルマ」の梵語とは
「カルマ」の梵語は、「कर्म」(karma)であり、「行為」や「業」を意味する。梵語は、インドの古典語であり、ヒンドゥー教や仏教、ジャイナ教などの聖典が記されている言語である。カルマの概念は、インド起源の宗教に共通して見られ、人間の行いや心の働きが宇宙の法則によって報いられるという考え方に基づいている。「カルマ」を用いた例文
1. 彼女は前世で善行を積んだため、今世では幸福な人生を送っていると言われている。 2. 彼は悪行を繰り返していたため、カルマによって次の生では苦難に見舞われることになった。 3. 仏教徒は、悟りを開いてカルマを断ち切ることで、輪廻から解脱し、涅槃に至ることができると信じている。カルマ
「カルマ」とは・「カルマ」の意味
「カルマ」とは、業・業報・応報・行為・造作・所作・宿命のことを意味するサンスクリット語表現である。サンスクリット語とは別名梵字(ぼんじ)で、古代インドで使われていた言葉だ。サンスクリット語は、「神仏を一字で現す文字」といわれ、仏教の経典や哲学の書籍などで使われている。空海が遣唐使として唐(現在の中国)に渡ったときにサンスクリット語で書かれた密教を学び、後に日本に伝承した言葉でもある。「カルマ」とは、自分が行った行動・態度は自分に帰ってくるという意味である。一般的に、「カルマ」という言葉は悪い行いのみが影響を及ぼすという意味にとらえがちだが、実は善悪を問わないニュートラルな言葉である。さらに、「カルマ」は現在進行形で、常にそれぞれの人に積み上げられているものだ。つまり、善行を重ねれば明るく良い結果が生まれ、悪事を繰り返せば同様の壊滅的結果が生じるという意味がある。
ちなみに、「カルマ」は必ずしも人の行動・態度から生じるのではなく、思考や欲望、性癖も関係している。それは、行動の根幹は精神と直結し、心の内は行動に現れるためだ。
「カルマ」は、スピリチュアルの世界、いわゆる魂の世界を解釈する際にも使われる。スピリチュアルの世界でのカルマは、自分自身の行動・態度・思考が自分に帰って来るだけではなく、前世の悪事・善行も今世に影響を与えるという考えだ。
「カルマ」は神秘的な要素を持った言葉なので、占いの世界で使われることも多い。一般的には、今世のカルマ、および前世のカルマを知り、さらに自分自身を成長させる方法を指南するという占いが主流となっている。
「カルマ」は、ヒップホップミュージシャンの名前でもある。正式な名前は呂布カルマ(りょふカルマ)で、名古屋芸術大学卒、名古屋在住のラッパーだ。呂布カルマは、テレビ朝日で2015年から2020年まで放送されていた『フリースタイルダンジョン』のラップバトルで、2代目・3代目モンスターになったという経歴がある。ちなみに、モンスターとは番組内で強豪ラッパーという意味で使われていた。
「カルマ」の類義語には、因果応報、自業自得・自業自縛・善因善果・悪因悪果・勧善懲悪・天罰・煩悩 ・火宅・エゴイズムなどがある。
「カルマ」の語源・由来
「カルマ」は、サンスクリット語で業・行為という意味がある「karman」が語源である。「カルマ」の熟語・言い回し
「カルマ」の熟語・言い回しには、アルマ=カルマ、前世のカルマ、カルマを背負う、バッドカルマがある。アルマ=カルマとは
アルマ=カルマとは、アニメ『D.Gray-man』に登場するキャラクター名である。アルマ=カルマは、元々「セカンドエクソシスト」と呼ばれる人造使徒であった。しかし、ユウという人造使徒に破壊されたアルマ=カルマは、脳を別の器に移植して新たなる生命体となった。
前世のカルマとは
前世のカルマとは、前世での行動や経験、体験が今世のカルマとしてよみがえるという意味の言葉だ。具体的には、前世の悪事や善行、トラウマなどが今世の生命体に影響を与えるという意味がある。
カルマを背負うとは
カルマを背負うとは、前世、今世の善行や悪行を背負った上で自分自身が存在しているという意味がある。スピリチュアルの世界や占いで使われることが多い言葉だ。
バッドカルマとは
バッドカルマとは、悪い行動・態度に対する報いという意味がある。バッドカルマを日本語で表現すると、天罰・天誅・罰が当たる・身から出た錆などが該当する。
「カルマ」の使い方・例文
「カルマ」の使い方・例文は、「私は占い師からカルマが深いタイプといわれた」、「彼の人生は前世のカルマによって定められている」、「カルマは自分自身の行いや行動によって創り上げるものだ」、「私の母はカルマから逃れられずに苦しんでいる」、「彼女の行動や態度はカルマが深いので、いずれ破綻してしまうだろう」などがある。その他には、「私たちは誰もがカルマを背負って生きている」、「誰もが改心すれば未来のカルマを変えることができる」、「根拠もなく人を見下している彼はカルマが深い」、「バッドカルマを破壊し、新たなる自分に生まれ変わるつもりだ」、「カルマを背負う人には特徴がある」などが挙げられる。
カルマ
カルマ
「カルマ」の基本的な意味
カルマの基本的な意味は、「業(ごう)」だ。わかりやすさを重視して、「行為」や「行い」という意味で使用されることもある。良い行いをすると良い結果がもたらされ、悪い行いをすれば悪い結果が降りかかるという、インド哲学の考え方に基づいた言葉がカルマである。そして、インド哲学から発展した仏教にも、カルマの考え方は存在する。仏教におけるカルマには、前世の行いが、現世に影響しているという意味合いも含まれる。「業」は、行為を意味する言葉として、四文字熟語「自業自得」にも使用されている。そして、自業自得は、悪い行いをした報いは、自分で受けるという意味だ。そのため、業と同義のカルマも、悪行が自分に返って来る考え方であると誤解されることがある。しかし、カルマの対象となる行いには、善悪の区別はない。そして、何らかの行為に対する、当然の結果としてもたらされるのがカルマであるという解釈で、意味合いが「宿命」になることもある。
現代では、スピリチュアルな要素のひとつとして、カルマが取り入れられることも珍しくない。スピリチュアルにおけるカルマは、人に良い行いをさせたり、ポジティブな考えを持たせたりすることが目的であることが多い。また、他者に嫉妬したり、欲深かったりするなどの悪い性質が、悪い結果に繋がるという、戒めとして取り入れられることもある。
「カルマ」の語源・由来
「カルマ」は、「業」や「行為」を意味するサンスクリット語「karman」をカタカナで表記したものである。「karman」は紀元前の時代からインドに存在した考え方であり、仏教と共に日本に伝来し、カルマとして定着した。「カルマ(BUMP OF CHICKENの曲)」とは
「カルマ」は、日本のロックバンドBUMP OF CHICKENを代表する楽曲のひとつである。歌詞には、「人は生まれた時から奪い合い、何らかの業を背負う」「人が誰かと対峙した時、相手に自分の業が映し出される」といった意味合いが込められている。「カルマ(YouTuber)」とは
YouTuberの「カルマ」は、CMに出演したり、本を発売したりするなど、手広く活躍する人物である。親の離婚をきっかけに転校し、転校先の学校でいじめの被害に遭ったり、非行に走ったりするなど、壮絶な生い立ちをしている。そして、2016年から配信活動を始めた。当初は2人組で活動していたが、2018年からは1人での活動となっている。2020年からは理由を明かさないまま活動を休止していたが、現在はavexを所属事務所として活動を継続している。また、2019年に公開した動画内で、弟が俳優であることを公表した。「カルマ」を含むその他の用語の解説
カルマパーマとは
「カルマパーマ」は、前髪を分けたような見た目となるパーマである。「カルマ」は、韓国語で「分け目」を意味する。「業」や「行為」を意味する「カルマ」と読み方は同じであるが、意味は違う。そして、韓国人俳優やk-popアイドルが流行らせたパーマであるため、カルマパーマと呼ばれる。
呂布000カルマとは
「呂布000カルマ」は、ラッパーである呂布カルマの別名義である。読み方は「りょふせんかるま」であり、呂布という単位が千あるという意味となっている。名前の「カルマ」の部分は、格好良いという理由で付けられていて、「業」や「宿命」といった言葉本来の意味はない。
「カルマ」の使い方・例文
「カルマ」は、自らの業を指すために使用する。例文にすると、「最近は良いことが続くが、何かのカルマだろうか」「私は、将来の幸運のために、日ごろから良いカルマを溜めるようにしている」となる。そして、「彼には数多くの試練が訪れるが、前世からいったいどれほどのカルマを背負っているのだろうか」のように、現世より前の業を指すこともある。また、自らの行いは結果として返って来るという、考え方そのものを指すために、カルマを使用することも可能だ。その場合は、「彼女は、カルマについて熱心に説明している」「良い行いをしたにも関わらず、災難ばかりが降りかかるので、私はカルマを信じなくなった」という風に使用する。
カルマ【(梵)karman】
読み方:かるま
業(ごう)。
カルマ
カルマ
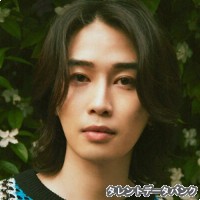 カルマの画像
カルマの画像
| 芸名 | カルマ |
| 芸名フリガナ | かるま |
| 性別 | 男性 |
| URL | https://avex-management.jp/artists/actor/KARUMA |
| プロフィール | 夢は有名人になる。16歳に福岡から俳優を目指し上京しオーディションやエキストラの下積み時代を5年経験。鳴かず飛ばずの状況が続き、自分が有名になってファンダムを抱えてから芸能参入の戦略に切り替え、当時勢いある媒体を模索し21歳でYouTubeを開始する。1年で100万人を突破し、現在180万人を超えるファンダムを保持することになる。戦略がハマり芸能事務所からもオファーが増えavexへの入所を決断。現在は様々なオファーが増え俳優として邁進している。 |
| 代表作品1年 | 2024 |
| 代表作品1 | 映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』(広川役) |
| 代表作品2年 | 2024 |
| 代表作品2 | テレビ朝日『伝説の頭 翔』(ブラッドマフィアボス 東城真役) |
| 代表作品3年 | 2023 |
| 代表作品3 | テレビ朝日『波よ聞いてくれ』(第6話) |
| 職種 | 俳優・女優・タレント |
» タレントデータバンクはこちら
カルマ
カルマ
業
(カルマ から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/20 07:09 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2021年8月)
|
業(ごう)、業報(ごうほう)、業力(ごうりき)、応報(おうほう)、[要出典]カルマ(梵: कर्मन् karman[注釈 1])に由来し、行為、所作、意志による身心の活動、意志による身心の生活を意味する語[2]。原義においては単なる行為(action)という意味であり、「良い」「悪い」といった色はなく、暗いニュアンスもない[3]。
インド哲学正統派、および異端派の一部(仏教など)の説では、善または悪の業を作ると、因果の道理によってそれ相応の楽または苦の報い(果報)が生じるとされる[2][4]。業は果報と対になる語だが、業の果報そのものを業という場合もある[4]。
業の思想はインド発祥の宗教(とりわけヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、シーク教)と道教において、輪廻と強く結びつく概念である[5] これらの多くの説では、善意と善行は良い業と幸福な転生をもたらし、悪意と悪行は悪い業と悪い再生をもたらすとされる[6](善因善果、悪因悪果)[7]。
インド哲学
| インド哲学 - インド発祥の宗教 |
| ヒンドゥー教 |
|---|
 |
業はインドにおいて、古い時代から重要視された。ヴェーダ時代からウパニシャッド時代にかけて輪廻思想と結びついて展開し、紀元前10世紀から4世紀位までの間にしだいに固定化してきた。
善をなすものは善生をうけ、悪をなすものは悪生をうくべし。浄行によって浄たるべく。汚れたる行によって、汚れをうくべし
— 『百道梵書』 (Śatapathā-brāhmana)
善人は天国に至って妙楽をうくれども、悪人は奈落に到って諸の苦患をうく。死後、霊魂は秤にかけられ、善悪の業をはかられ、それに応じて賞罰せられる
あたかも金細工人が一つの黄金の小部分を資料とし、さらに新しくかつ美しい他の形像を造るように、この我も身体と無明とを脱して、新しく美しい他の形像を造る。それは、あるいは祖先であり、あるいは乾闥婆(けんだつば)であり、あるいは諸神であり、生生であり、梵天であり、もしくは他の有情である。……人は言動するによって、いろいろの地位をうる。そのように言動によって未来の生をうる。まことに善業の人は善となり、悪業の人は悪となり、福業によって福人となり、罪業によって罪人となる。故に、世の人はいう。人は欲よりなる。欲にしたがって意志を形成し、意志の向かうところにしたがって業を実現する。その業にしたがって、その相応する結果がある
— 『ブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド』
異端派と沙門たち
正統派の説に反発する人々はから、従来のバラモン教に所属しない、様々な自由思想家たちがあらわれていた。彼らは高度な瞑想技術を育み、瞑想による体験から様々な思想哲学を生み出し、業、輪廻、宿命、解脱、認識論などの思想が体系化されていった。この中に業の思想も含まれていた。それが沙門とよばれ、釈迦と同時代の哲学者として知られた六師外道と仏教側に呼ばれる人々であった。
ある人は、霊魂と肉体とを相即するものと考え、肉体の滅びる事実から、霊魂もまた滅びるとして無因無業の主張をなし(順世派)、また他の人は霊魂と肉体とを別であるとし、しかも両者ともに永遠不滅の実在と考え、そのような立場から、造るものも、造られるものもないと、全く業を認めないと主張した(アージーヴィカ教)。
プラブリッティとニヴリッティ
インド哲学の正統派では、業は輪廻転生の思想とセットとして展開した。この輪廻と一体化した業の思想は、因果論として決定論や宿命論のような立場で理解される。インドにおいて業は、プラブリッティ(pravṛtti)という「発展するもの」と、ニヴリッティ(nivṛtti)という「止滅に向かうもの」が区別されており、倫理的見地として、プラブリッティ(「社会生活の維持に不可欠な行為肯定の立場」)とニヴリッティ(「業の束縛を形而上学的な認識によって脱し精神の自由を求める行為否定の立場」)がある[8][9]。行為否定の立場は業の克服が理想であり、業の克服においては止滅の方向が重視され、涅槃や悟りといった形での輪廻の終焉が目指される[8][9]。
『マハーバーラタ』では倫理的見地として、「行為肯定の倫理」「厭世主義」「行為否定の倫理」「調和の立場」が示されており、これらは業報の思想に基づいている[9]。『バガヴァッド・ギーター』では、プラブリッティとニヴリッティを同時に成立させる調和の立場が示される[9]。福田槙子は、「厭離(業を離れること)と平静(既に業を離れた境地)の二観念を土台とした行為の実行」が『バガヴァッド・ギーター』の調和の立場の倫理構造であると述べている[9]。本作では、万物の物質的な根源から生じる三つのグナ、トリ・グナが人間の精神を束縛し、人を善悪の行為に駆り立てる因であるとされ、ヨーガ(心統一)はグナの影響を断ち業を離れた境地に至る補助となる[9]。
仏教
| 仏教用語 業 , カルマ |
|
|---|---|
| パーリ語 | kamma |
| サンスクリット語 | karma (Dev: कर्मन्) |
| チベット語 | ལས། (Wylie: las; THL: lé;) |
| 日本語 | 業 or ごう |
| 英語 | karma |
仏教はすべての結果について「偶然による事物の発生」「(原因なく)事物が突然、生じること」「神による創造」などを否定し、その原因を説く[10][11]。業は果報(報い、果熟)を生じる因となるので、業のことを業因や因業ともいう[2][注釈 2]。釈迦は業に基づいた理論にて、バラモン教が説く生まれによるカースト制を否定した[12]。
業による報いを業果(Karmaphala)や業報という[2]。業によって報いを受けることを業感といい、業による苦である報いを業苦という[2][注釈 3]。過去世に造った業を宿業または前業といい、宿業による災いを業厄という[2]。宿業による脱れることのできない重い病気を業病という[2]。自分の造った業の報いは自分が受けなければならないことを自業自得という[2]。
- 自分のもの(sakkā)- 死によって失われるものではなく、来世についてくる所有物[14]。
- 相続する(dāyādā)- 身・口・意の三業から引き継がれる[14]。
- 生まれる(yoni)- 生命を生み出すのは、自ら行った行為からで、すべて業より生まれる[14]。
- 切り離せない(bandhu)- 生命は業との繋がりを切ることはできない[14]。
- よりどころとする(paṭisaraṇā)- 生命のよりどころである[14]。
- 優劣をつける(satte vibhajati yadidaṃ hīnappaṇītatāyāti) - 生命に優劣をつける要素の一つである[14]。
仏教学者の佐々木閑は、阿含経典(二カーヤ)、アビダルマ哲学から読み取れる初期仏教における業の基本原則を次のようにまとめている[15]。
- 人が行った善悪の行為は、すべてが漏れなく記録されていく。
- 記録された善悪の行為は、業という潜在的エネルギーとなって保存され、いつか必ず、なんらかのかたちで、当の本人にその果をもたらす。
- 業のエネルギーがその果をもたらす場合、それがどのようなかたちでもたらされるかは予測不可能であり、原因となる善悪の行為から、その結果を推測することはできない。[15]
次の2点は、上記の基本原則の補足である[15]。
- 原因となる行為を行った順番と、その結果が現れる順番は対応していない。①②③④⑤という順番で行った行為の結果が、④③①⑤②の順で現れることもあるということである。したがって結果の現れ方から、その原因となった行為を推定することはできない。
- 善い行いと悪い行いを相殺して、エネルギーをゼロにすることはできない。善い行いの業を100、悪い行いの業を100背負った者は、100回の楽と100回の苦を受けることになる。両者を足してプラスマイナスゼロにはできないということである。[15]
釈迦は当時の世俗的な幸福の概念を全否定し、生死の繰り返しは苦そのものであり、真の安楽とは輪廻から逃れることだと考え、輪廻の原動力である業を生み出さない状態になることが必要であると考えた[16]。生命の本質である生きようとする欲望・希望が人間に強い意思作用を生じさせ、それが業を生み、業が輪廻を発動するため、釈迦は生きようとする欲望・希望から生じる意思作用を継続的なトレーニングで抑制し、幸福のために行動したいという思いを捨て、心を善悪の意思を離れた中立状態に維持することで、業が生じない境地になることを得て、この教えとトレーニングの実践方法を望む人々に教え、実践し正しく伝授するための場として仏教集団、サンガ(僧伽)が形成された[16]。なお、世俗的な幸福を全否定し輪廻からの離脱を目指す仏教の世界観は一般的に見て特異なものであり、仏教は最初から「一部の、理解できる人たちだけのための特殊な教え」であり、自分たちの価値観に全ての人が受け入れるべき普遍性があるとは考えておらず、サンガという特殊な一部だけのものだという自覚を持っていた[17]。
人間は自らの行いの結果として良い境涯や苦しい境涯に生まれ変わり、五道(後に六道)を永遠に巡るという業と輪廻の世界観は、釈迦が生きた当時のインドにおいては一般的なものであり、世俗においては、良い境遇に生まれ変わるため、幸福になるための善業、一種の投資として他者への布施が積極的に行われた[18]。仏教の在家信者とは、サンガの修行者たちを崇高な目的に邁進する優れた境涯の人々と考え、彼らをすぐれた果報が期待できる最良の布施の対象とみなした人々であり、輪廻からの離脱を目指すサンガの修行者と善業の果報を期待する在家信者は、人生の目的が異なるがゆえに、生きる糧と果報を相互に与え・受け取るギブアンドテイクの関係にあった[16]。
分類
仏教における業は、様々に分類される。 ここでは主に部派仏教ないし上座部仏教の諸経典に基づいて記す。中観派、密教等の大乗諸宗派では教義における比重、意味合いが異なる可能性に注意すること。[要出典]
三業
業は一般に、身(しん)・口(く、もしくは語)・意(い)の三業(さんごう)に分けられる[2]。戒においても十悪業として、三業に分類して説かれる。
- 身業(しんごう, 梵: kāya-karman[20]、カーヤ・カルマン) - 身体に関わる行為[21]。身体的行為[20]。
- 口業(くごう, 梵: vāk-karman[20]、ヴァーク・カルマン) - 言語に関わる行為[21]。言語表現[20]。語業(ごごう, 梵: vāk-karman[25]、ヴァーク・カルマン)ともいう[26]。
- 意業(いごう, 梵: manas-karman[20]、マナス・カルマン) - 意志に関わる行為[21]。心意作用[20]。
思業と思已業
業は、意志の活動である思業(しごう, cetana kamma)と、思業が終わってからなされる思已業(しいごう, cetayitva kamma)との2つに分けられる[27][2]。
説一切有部の阿毘達磨大毘婆沙論では、第一段階を意業(思業)とし、第二段階は身業・口業のみ(思已業)とした[28][27]。
一方で阿含経では、行為が行われる場合は、第一段階:思(cetanā; 意志の発動)の心作用、第二段階:実際の行為(身業・口業・意業)があるとしている[22]。ここでは、(第二段階の意業だけでなく)、第一段階の思をも業のなかに含めて理解している[22]。そればかりでなく、第一段階こそが業の本質的なものだとして重要視している[29]。
なお、経量部や大乗仏教は、三業すべての本体を思(意志)であるとする[2][27]。
表業と無表業
説一切有部は、身業と語業には表(ひょう)と無表(むひょう; 梵: avijñapti[30]、アヴィジュニャプティ)とがあるとし、これらは表業(ひょうごう; 梵: vijñapti-karman[31]、ヴィジュニャプティ・カルマン)と無表業(むひょうごう; 梵: avijñapti-karman[30]、アヴィジュニャプティ・カルマン)ともいわれる[2]。表業は、「知らしめる行為」[32]、外に表現されて他人に示すことができるもの[2]、行為者の外面に現われ他から認知されるような行為[32]を意味する。無表業は、他人に示すことのできないもの[2]、善悪の業によって発得される悪と善を防止する功能(習性)[33]、行為者の内面に潜み他から認知されないような行為[32]を意味する。また、無表業は無表色(むひょうしき、梵: avijñapti-rūpa)[34]ともいう。
阿毘達磨倶舎論において、業を起こした時の心が善心ならそれと異なる不善あるいは無記の心を乱心といい、業を起こした時の心が不善心ならそれと異なる善あるいは無記の心を乱心という[35]。また、無想定や滅尽定に入って心の生起が全くなくなった状態を無心という[35]。この上で無表色は、 阿毘達磨倶舎論 の分別界品第一においては、これらの「乱心と無心等(この2つに不乱心および有心を含めた4つを四心という[36]。著者の世親はこれによって全ての心の状態を示し得たと考えている[37]。)の者にも随流(法が連続生起して絶えない流れをなすこと[35]。なお、随流は相続(梵: pravāha)ともいう[38]。)であって、浄や不浄にして、大種(四大種)によってあるもの」と定義されている[39]。分別界品第一の定義は四分随流ともいう[33]。なお、無表色は四大種の所造であるが極微の所成ではない[40]。また、法処、法界に属しながら色法であり[40]、五根の対象とはならず、ただ意根の対象である[40]。
無表業とは、説一切有部の伝統的解釈によれば「悪もしくは善の行為を妨げる習性」で、具体的には律儀、不律儀、非律儀不律儀の三種であり(これは阿毘達磨倶舎論の分別業品第四の所説であり、この所説が無表業全体を解明しているという考え方がある[33] 。)、いわゆる「戒体」と同じものである[33]。 また、無表色は身無表と語無表の二種に分けられ、殺生、偸盗、邪淫の三つの身業と妄語、綺語、離間語、悪口の四つの語業を合わせた七支に関わるものである[36]。明治大正期より、近代仏教学者によって経部の種子説との混同や[41]、大乗仏教の立場から有部の無表業を誤謬として規定したり[42]、「仏教元来の無表」を想定することによって、無表色を「業の結果を生ぜしめるもの」とする理解が流行したが、文献学的に論証されたものではなく、根拠に乏しい[42]。
身表と身無表、語表と語無表の四つに意業を加えて五業という[2]。
引業と満業
総体としての一生の果報を引く業を引業(牽引業、総報業、引因とも)という[2]。これは人間界とか畜生界などに生まれさせる強い力のある業のことを指す[2]。他方、人間界などに生まれたものに対して個々の区別を与えて個体を完成させる業を満業という[2]。引業と満業の2つを総別二業という[2]。
共業と不共業
山河大地(器世間)のような、多くの生物に共通する果報をひきおこす業を共業(ぐうごう)といい、個々の生物に固有な果報をひきおこす業を不共業(ふぐうごう)という[2]。無著「大乗阿毘達磨集論」においては、共業による影響は、これを結果に対する増上縁 (adhipati-pratyaya) と考え、直接的な結果、すなわち異熟 (vipāka) とは考えない[43]。
三性業
善心によって起こる善業(安穏業)と、悪心によって起こる不善業(悪業、不安穏業とも)と、善悪のいずれでもない無記心によって起こる無記業の3つがあり、この3つを三性業という[2]。
三時業
業によって果報を受ける時期に異なりがあるので、業を下記の3つに分ける[2]。この3つを三時業という[2]。三時業の各々は、この世で造った業の報いを受ける時期がそれぞれ異なる[2]。
- 順現業(順現法受業 、じゅんげんぽうじゅごう[要出典]、dṛṣṭadharma-vedanīya-karman[44]) - この世で造った業の報いを、この世で受ける[2]。
- 順生業(順次生受業 、じゅんじしょうじゅごう[要出典]、upapadya-vedanīya-karman[45]) - この世で造った業の報いを、次に生まれかわった世で受ける[2]。
- 順後業(順後次受業 、じゅんごじじゅごう[要出典]、aparaparyāya-vedanīya-karman[46]) - この世で造った業の報いを、次の来世より先の世で受ける[2]。
三時業は報いを受ける時期が定まっているので定業といい、報いを受ける時期が定まらないものを不定業(順不定業、梵: aniyata-karman[47])という[2]。三時業に不定業を加えて四業という[2]。
業因と業果との関係
善悪の業を造ると、それによって楽や苦の報い(果報、果熟)が生じることを、業因によって業果(Karmaphala)が生じるという[2][注釈 4]。この業因と業果との関係について諸説がある[2]。
説一切有部は、業そのものは三世に実在するとし、業が現在あるときにはそれが因となっていかなる未来の果を引くかが決定し、業が過去に落ちていってから果に力を与えて果を現在に引き出すとする[2]。
経量部は、業は瞬間に滅び去るとするが、その業は果を生じる種子(しゅうじ)を識の上にうえつけ、その種子が果をひきおこすことになるとする[2]。
業道
業がそこにおいてはたらくよりどころとなるもの、あるいは、有情を苦楽の果報に導く通路となるものを業道という[2][注釈 5]。業道には十善業道と十悪業道の2つがある[2]。
業識、業障
業識(ごっしき)とは、業を縁として生じた識、または無明のために動かされた識のこと[48]。業障(ごっしょう)とは、業の障りのことを指し、業識障(ごっしきしょう)ともいう。善業および悪業を含む前世からの宿業により様々に生まれつくこと[49]。また、業識性(ごっしきしょう)は、惜しい・欲しい・憎い・可愛いという煩悩妄想を指す[50]。
仏典や宗派ごとの扱い
パーリ経典
大四十経においては釈迦は八正道を説き、十事正見として、果報の否定を「邪見」と断じている。阿毘達磨発智論においても五悪見のひとつとして排している。
阿毘達磨
『総合仏教大辞典(1988)』によれば、 阿毘達磨では[どこ?]、十二支縁起の第十支の「有」は業を意味するものと解釈されている[2]。これを業有という[2]。
浄土教
一般に、念仏して阿弥陀仏の浄土に往生しようと願うことを浄業という[2]。
密教
 |
この節の加筆が望まれています。
|
ジャイナ教
西洋
西洋では、ドイツの思想家ゴットホルト・エフライム・レッシング(1729年 - 1781年)の時代から、生まれ変わって人生を繰り返すことによる学びを通し個人が段階的に完成するという、東洋よりはるかに楽観的な転生思想が唱えられてきた[51]。
心霊主義
フランス人アラン・カルデック19世紀に創始した心霊主義のキリスト教スピリティズム(カルデシズム)では、転生が信じられており、神から与えられた自由意思によって、転生する間に過ちを起こしてカルマを形成し、この負債であるカルマによって、その人に災いが起こると考えられた[52][53]。人間の苦しみの原因は自らが過去生で蓄積した負債であり、地上の生はこの負債の返済のためにある[52]。また人生の苦しみは神の恩寵でもあり、苦しみを通じて負債が軽減されることは神の期待に沿うことであり、苦しみを乗り越えることは大きな栄光であると考えられている[52]。スピリティズムにおいて、自由意思は負債の原因であると同時に救いを可能にするものであり、個人が救済されるか否かは全て個人の自由意思次第であり、救いは慈善活動、他者救済のみによって可能となる[52]。
エドガー・ケイシー(後述)と同時代には、心霊主義の霊媒モーリス・バーバネルがおり、彼に憑依した霊であるという「シルバー・バーチ」という人格によると、転生とは償いや罰が問題ではなく、進化のためにあり、「業という借金」は「教訓を学ぶための大切な手段」であるとされ、懲罰的な意味合いは中心から外されているか、完全になくなっている[54]。
神智学
19世紀に近代神智学を創始したロシア人オカルティストのヘレナ・P・ブラヴァツキーは転生説を説いたが、輪廻転生説というものの中核はカルマ論であるとし、それを「全存在を貫く不可侵の法則」であるとした[55]。身体的な進化のベースに霊的な進化があると主張し、人間は転生の繰り返しを通して神性の輝きに向かって進化するもので、連続する生はカルマの法則によって統括されていると考えた[56]。ヨーロッパにインドの輪廻説に似た転生説がなかったわけではなく、古代ギリシアのピタゴラスや中世のカタリ派、フランスの心霊主義者カルデック等が転生説を説いたと言われるが、ブラヴァツキーは、こうしたヨーロッパの転生説はカルマ論が欠けているため、「科学的真理」としては不十分であるとみなしている[55]。
インド・イラン学研究者の岡田明憲は、カルマ論は、神智学とインド思想の違いを示す好例であると述べている[57]。彼女が言うカルマの法則は、善業善果(良い事をすれば良い結果となる)、悪業悪果(悪いことをすれば悪い結果となる)の因果応報の理で、この理に従って世の不正は正され社会は進歩し、人間は神へと進化していくのだという[57]。神智学のカルマの法則は、この「神への進化」という目的論と不可分であるとされ、岡田明憲によると、止滅の方向が重視されるインドのカルマ論とは別物である[57]。インドにはそもそも進化という発想はなく、インドの業(カルマ)の理論では、根元への帰還は神智学が言うような進化・発展とは逆に、涅槃や悟りという止滅の方向が重視される[8]。インドの輪廻・業の理論では、人間は生まれ変わって虫になることもあるが、神智学ではこうした考えは否定されており、岡田明憲は、近代ヨーロッパの大きな特徴であるチャールズ・ダーウィンの進化論の影響と、伝統的なキリスト教的終末観に基づく目的論的歴史意識が見られると指摘している[8]。岡田明憲は、神智学はヨーロッパの限界を超えようとし、キリスト教を批判したが、その思想はヨーロッパ的・近代ヨーロッパ的な意識を脱し得ていないと評している[8]。
ニューエイジ
近代神智学から直接生まれ変わりの思想を受け継いだニューエイジでは、転生やカルマが信じられている[58][59]。津城寛文によると、ニューエイジを一般に広めた女優のシャーリー・マクレーンなどの「スピリチュアルな」重要人物たちは、心霊診断家のエドガー・ケイシーを最大の権威として参照しており、ケイシーは現代アメリカの転生思想に最も大きな影響がある[60]。催眠状態のケイシーが語る「リーディング」で伝えた原則的な教訓は、「蒔いたものは刈り取らねばならない」という新約聖書の言葉を標語にするもので、死後も存在が続くと意識することによって生じる内面の正義を目的とする倫理である[60]。リーディングでは、カルマという用語で説明された[60]。ヒンドゥー教から用語を借りつつも、キリスト教内部に元々あった教えであることが暗に示されている[60]。ケイシーの教えには、カルマを活用することで生まれ変わりの機会を改善するという志向がある[60]。リーディングには、割り当てられた問題を今生で解決し、もう地球に転生しないかもしれないというごく少数の事例もあり、彼らは死後より高次の惑星に移行するとされている[60]。ケイシーはアトランティス大陸滅亡を歴史的事実として語り、その時のカルマにより現代社会の滅亡が近いという終末論を唱えた[61]。
ニューエイジの「カルマの法則」は、原因と結果に関する宇宙の法則、互いに結びつき道徳的な均衡へと向かう宇宙の傾向の一部であり、しばしば道徳的な意味で宇宙の進化と同じと考えられた[58][59]。悪や苦しみは幻影であるとされ、カルマは悪や苦しみとは無関係の概念になっている[58]。今の人生の課題は前世のカルマによって決められているという考え方は、生きる指針を見失い喪失感に苦しむ現代アメリカ人たちから、広い支持を得た[62]。
脚注
注釈
出典
- ^ 宮元啓一「インドにおける唯名論の基本構造」『RINDAS ワーキングペーパー伝統思想シリーズ19』、龍谷大学現代インド研究センター、2014年、6-8頁。}
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq 総合仏教大辞典 1988, p. 363-365.
- ^ スマナサーラ 2014, 11%.
- ^ a b 広辞苑 1986, p. 789.
- ^ Parvesh Singla. The Manual of Life – Karma. Parvesh singla. pp. 5–7. GGKEY:0XFSARN29ZZ 4 June 2011閲覧。
- ^ Halbfass, Wilhelm (2000), Karma und Wiedergeburt im indischen Denken, Diederichs, München, Germany
- ^ スマナサーラ 2014, No.91/359.
- ^ a b c d e 岡田 2002, p. 121.
- ^ a b c d e f 福田 2012, p. 99.
- ^ スマナサーラ 2014, 16%.
- ^ スマナサーラ 2012, No.893/1930.
- ^ 志賀浄邦「インド仏教復興運動の軌跡とその現況」『京都産業大学世界問題研究所紀要』第25巻、2010年、23-46頁、NAID 110007523445。
- ^ 長友泰潤「原始仏典に見る人間観 : チャラカ・サンヒターの人間観との比較研究」『南九州大学研究報告. 人文社会科学編』第44巻、2014年、21-28頁、 NAID 40020099536。
- ^ a b c d e f g チャンディマ・ガンゴダウィラ『新しい生き方を切り拓く7つの実践 『小業分別経』』Sukhi Hotu、2020年、22%。ASIN B0852RN3Q3。
- ^ a b c d 佐々木 2019, pp. 155–157.
- ^ a b c 佐々木 2019, pp. 158–160.
- ^ 佐々木 2019, pp. 158–161.
- ^ 佐々木 2019, pp. 157–158.
- ^ 馬場 2018, pp. 121–122.
- ^ a b c d e f 岩波仏教辞典 1989, p. 314.
- ^ a b c 岩波仏教辞典 1989, p. 246.
- ^ a b c d e f 櫻部・上山 2006, p. 117~118.
- ^ 精選版 日本国語大辞典、小学館『邪淫・邪婬』 - コトバンク
- ^ a b c 松久保 2001, p. 77.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 索引頁「仏教基本語彙(3)」.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 117.
- ^ a b c 池田練太郎「思業と思已業」『印度學佛教學研究』第30巻第1号、1981年、298-302頁、doi:10.4259/ibk.30.298。
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 120.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 117-18.
- ^ a b 岩波仏教辞典 1989, p. 788.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 索引頁「仏教基本語彙(7)」.
- ^ a b c 櫻部・上山 2006, p. 121.
- ^ a b c d 青原 2017, p. 847.
- ^ 櫻部・上山 2006, p. 索引頁「仏教基本語彙(9)」.
- ^ a b c 櫻部 1989, p. 63.
- ^ a b 青原 2017, p. 846.
- ^ 加藤 1967, p. 120.
- ^ 工藤 1981, p. 130.
- ^ 阿部 1995, p. 35.
- ^ a b c 櫻部 1989, p. 66.
- ^ 青原 2017, p. 844-846.
- ^ a b 青原 2017, p. 844-843.
- ^ 干潟龍祥「業(ごう)の社会性-共業(ぐうごう)-について (昭和五十年二月十二日提出)]」『日本學士院紀要』第33巻第1号、1975年、1-7頁、doi:10.2183/tja1948.33.1。
- ^ 「順現法受業」 - 佛光大辭典 (慈怡法師主編)
- ^ 「順次生受業」 - 佛光大辭典 (慈怡法師主編)
- ^ 「順後次受業」 - 佛光大辭典 (慈怡法師主編)
- ^ 清水 2011, p. 17.
- ^ 精選版 日本国語大辞典『業識』 - コトバンク
- ^ 山本 1960, p. 16.
- ^ 秋月 2002, p. 33.
- ^ 教皇庁 2007, pp. 36–37.
- ^ a b c d 山田政信 「新宗教のブラジル伝道(14)キリスト教の変容 ⑪」天理大学
- ^ 山田政信 「改宗を正当化する語りの論理」 ラテンアメリカ研究年報No.19(1999年)
- ^ 津城 2005, p. 76.
- ^ a b 岡田 2002, p. 120.
- ^ Tingay, 宮坂清訳 2009, pp. 428–434.
- ^ a b c 岡田 2002, pp. 120–121.
- ^ a b c 教皇庁 2007, p. 119.
- ^ a b York, 井上監訳 2009, pp. 428–434.
- ^ a b c d e f 津城 2005, pp. 71–73.
- ^ 大田 2013. 位置No.1173/2698
- ^ 大田 2013. 位置No.1165/2698
参考文献
- 新村出(編)『広辞苑』(第三版)岩波書店、1986年10月。
- 総合仏教大辞典編集委員会(編)『総合仏教大辞典』法蔵館、1988年1月。
- 中村元他『岩波仏教辞典』(第2版)岩波書店、1989年。 ISBN 4-00-080072-8。
- 櫻部建、上山春平『存在の分析<アビダルマ>―仏教の思想〈2〉』角川書店〈角川ソフィア文庫〉、2006年。 ISBN 4-04-198502-1。(初出:『仏教の思想』第2巻 角川書店、1969年)
- 青原令知「いわゆる「無表業の誤解」について」『印度學佛教學研究』第65巻第2号、日本印度学仏教学会、2017年、848-841頁、doi:10.4259/ibk.65.2_848。
- 清水俊史「不定業と既有業 : 有部と上座部の業理論」『佛教大学大学院紀要 文学研究科篇』第39号、佛教大学大学院、2011年、17-34頁。
- 工藤道由「世親の無表業の解釈をめぐって」『印度學佛教學研究』第31巻第1号、日本印度学仏教学会、1981年、130-131頁、doi:10.4259/ibk.31.130。
- 阿部真也「倶舎論における無表について」『印度學佛教學研究』第87巻第1号、日本印度学仏教学会、1995年、35-37頁、doi:10.4259/ibk.44.35。
- 加藤純章「新薩婆多」『印度學佛教學研究』第16巻第1号、日本印度学仏教学会、1967年、120-121頁、doi:10.4259/ibk.16.120。
- 松久保秀胤『唯識初步 : 心を見つめる仏教の智恵』鈴木出版、2001年。 ISBN 978-4-7902-1103-7。
- 山本玄峰『無門関提唱』大法輪閣、1960年。 ISBN 978-4-804-61019-1。
- 秋月龍珉『無門関を読む』講談社学術文庫、2002年。
- 津城寛文『<霊>の探究 : 近代スピリチュアリズムと比較宗教学』春秋社、2005年、1-283頁。 ISBN 4-393-29194-8。
- 岡田明憲「神秘思想とヨーロッパ」『別冊環』第5巻、藤原書店、2002年、113-122頁。
- 教皇庁文化評議会/教皇庁諸宗教対話評議会『ニューエイジについてのキリスト教的考察』カトリック中央協議会司教協議会秘書室研究企画 訳、カトリック中央協議会、2007年。
- 『現代世界宗教事典—現代の新宗教、セクト、代替スピリチュアリティ』クリストファー・パートリッジ 編、井上順孝 監訳、井上順孝・井上まどか・冨澤かな・宮坂清 訳、悠書館、2009年。
- Michael York 執筆「ニューエイジの伝統」。
- Kevin Tingay 執筆「神智学協会」。
- 福田槙子「『バガヴァッド・ギーター』の行動倫理 : 行為肯定(pravrtti)と行為否定(nivrtti)との調和の構造」『宗教と倫理』第12巻、宗教倫理学会、2012年10月、99-115頁、 CRID 1520290885037651456。
- 大田俊寛『現代オカルトの根源 - 霊性進化論の光と闇』筑摩書房〈ちくま新書〉、2013年。 ISBN 978-4-480-06725-8。
- アルボムッレ・スマナサーラ『無我の見方 (「私」から自由になる生き方)』(kindle)サンガ、2012年。 ISBN 978-4905425069。
- アルボムッレ・スマナサーラ『Power up Your Life 力強く生きるためにブッダが説いたカルマの法則』(Kindle)サンガ、2014年。 ISBN 978-4904507230。
- 馬場紀寿『初期仏教――ブッダの思想をたどる』〈岩波新書〉2018年。 ISBN 978-4004317357。
- 佐々木閑「釈迦の死生観」『現代思想 2019年11月号 特集=反出生主義を考える ―「生まれてこない方が良かった」という思想―』、青土社、2019年、154-162頁。
関連項目
カルマ
「カルマ」の例文・使い方・用例・文例
固有名詞の分類
- カルマのページへのリンク







