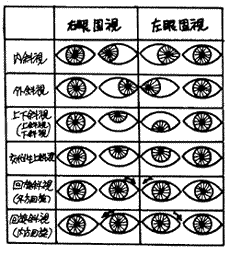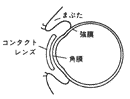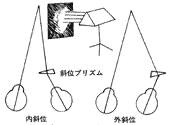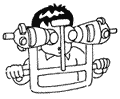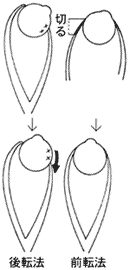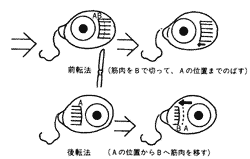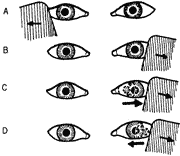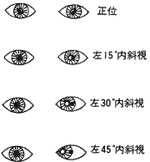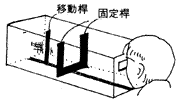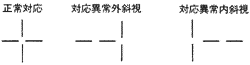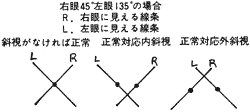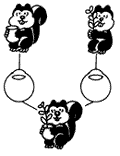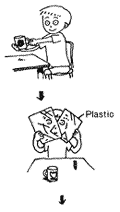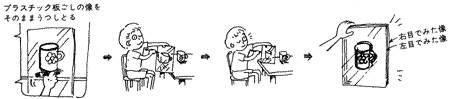しゃ‐し【斜視】
斜視
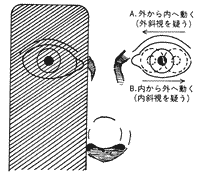
(1)カバーテスト (2)カバーアンカバーテスト (3)ヒルシュベルグテスト(Hirschberg法) (4)ステレオテスト |
斜視の検査
1)カバーテスト遠見目標(5m)を見させておき,長さ15cm,幅5cmほどの厚紙などで右目をおおいます。このとき,左目をよく見ておきます。動かなれけば正位,Aのように内から外へ動けば内斜視,Bのように外から・内へ動けば外斜視が疑われます。次に,厚紙で左目をおおい,同様に右目の動きを見ます。このようにして,斜視の有無,その斜視眼が右目か左目か交代性かを知ることができます。また,近見目標(30cm)を見させて同様に検査します。 2)カバーアンカバーテストカバーテストと同様の方法で行ないますが,こちらの方法は,一度厚紙でおおった目がおおいをとったときどのように動くかを見る方法で,斜位(潜伏斜視)の有無や斜視のずれの方向を知る検査です。たとえばA,Bのように,右目のおおいをとっても左目のおおいをとっても,それぞれ目の動きがない場合は正位ということになります。Cのように左目のおおいをとったとき,左目が内から外へ動いたら,内斜位(潜伏内斜視),Dの場合は外斜位(潜伏外斜視)が疑われます。 3)ヒルシュベルクテスト(Hirschberg法)乳幼児で斜視角の検査を正確にできない場合に使います。角膜反射の位置(両眼の角膜に光が当たるように近距離に光源をおき,その光輝を両眼で見させ,角膜に映った光の位置)で,斜視の強さ,斜視角を測定します。たとえば,光の影がどちらかの目の角膜の中心からずれて映っていたら,その目が斜視ということです。 4)ステレオテスト立体視を測定するテストです。偏光メガネを装用させて検査用の図を見せると,正常であれば立体的に見えます。また,三桿法といって検査器の中に垂直に立てた3本の棒の両端の2本が固定してあり,真ん中の1本を動かして3本が一直線に並んだときを答えさせ,ずれがないかどうかをしらべる方法もあります。 5)ワース4灯法両眼固視,抑制,複像の有無を調べる検査法です。右に赤,左に緑のついたメガネをかけて,5m先の白,赤,緑,緑の4つの光をみせて,光の数と色を答えさせます。 1)四つみえるとき・・・・正常対応 |
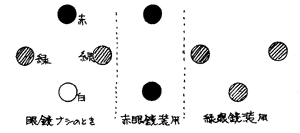
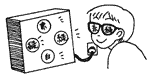 (5)ワース4灯法
(5)ワース4灯法
|
|
6)残像検査棒状の電灯を用い,右目は垂直方向,左目は水平方向にして光を見せたあと,両目の残像の位置から網膜対応の状態を検査する方法です。正常であれば十字の残像が見えますが,異常の場合はそれがずれます。 7)バコリーニ線条レンズ検査ガラスに線条のスジを入れた検査用メガネをかけ,光源を見せると,線条の光が見えます。その見え方で,網膜対応の異常を知る検査方法です。 |
|
Q.目が二つあるのになぜものはひとつに見えるのですか「両眼視機能」 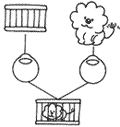
|
私たちの目は二つあるにもかかわらず,見るものは一つとして見えています。これは,大脳の中で右目と左目に映った像を重ね合わせて一つの像にする働きをしているからです。この働きにより,片目で見たときには感じられない遠近感や立体感が生まれてくるのです。このような働きを「両眼視機能」といいます。 左右の網膜にうつった像を重ね合わせて,一つの像としてみる働き 左右の網膜にうつった像の位置が違うことにより,遠近感や立体感をもった像にする働き この両眼視機能は,生後2,3カ月にものを見ることができるようになるとともに自然の訓練として発達し,5,6歳で完成します。この発達がうまくいかないと斜視になり,逆に斜視があると,両眼視機能の発達がうまくいきません。このように,斜視と両眼視機能はお互いに密接な関係があるのです。 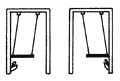 (3)立体視 (3)立体視
|
|
|
|
|
|
|
||
 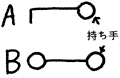
|
「わとおし」という方法があり,この方法で生活上での立体視の有無を簡単に調べることができます。足立という人が考えたもので,針金で図のようなA,B,二つのものを作ります。被検者はAを,検者がBを持ちます。検者はBの輪を被検者の正面,上下左右に見せ,その中にAの先を通させます。両目でする場合と片目でする場合とを調べ,その出来具合を観察します。立体視ができていれば,両目でするほうが片目でするよりうまくできます。この場合は,わとおし(+)とします。両目でも片目でも,出来具合が変わらない場合は,わとおし(一)です。わとおし(一)では,斜視が疑われます。 しかし,これはあくまで疑いですからくわしくは専門医に調べてもらうことが必要です。眼科では,先に述べた斜視の検査法以外にも,大型弱視鏡という器械を使って,簡単にくわしく,斜視や両眼視機能の検査をすることができます。 |
|||||
|
斜視の人は両目で見ると,視線のズレのために複視(ダブって見える)や混合視(はなれていってもひっついて見える等)が起こるはずですが,それを自覚しないように斜視の方の目が見えにくくなってくるようになります。これを抑制と呼び,同時視のないことをいいます。この両眼視での抑制は正常な人間でも起こします。たとえば,片方の目で顕微鏡をのぞきながら,もう片方の目を使ってスケッチを書く場合,両目の網膜に違った映像がうつるとどちらかの網膜が抑制され,スラスラとスケッチが書けなくなります。このようなことをいいます。 |
||||||
|
Q.斜視と斜位とはどうちがうのですか 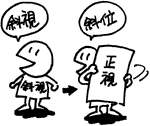
|
|
|||||
|
Q.斜視のように見えるが,異常がないといわれたのですが・・・ |
眼位ずれがないにもかかわらず,一見すると内斜視や外斜視に見える場合があります。これは,実際には斜視ではありませんから,心配はいりません。よく間違われる例としては,乳幼児で,内眼角の皮ふが鼻側の球結膜をかくしている場合に内斜視と間違われます。日本人などモンゴロイド系にはこの傾向が強くみられます。一般にこのようなものを偽斜視とよんでいます。 |
|||||
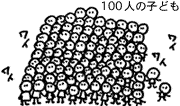
|
若年者では,全体の2%前後といわれています。100人の子どもがいれば,2人ぐらいは斜視があるわけです。また,斜視は遺伝することが少なくありません。これは,両眼視の働きは,生まれつきの素質が大いに関係していることを示しています。 |
|||||
|
眼性斜頸の一種の脳障害によるものと思われます。これは,眼球振畳や水平方向の眼球運動障害を伴います。そのため,顔を回して見れば見やすくなるためで,ただ単にクセによるものだけではありません。 |
||||||

|
両眼の屈折度の差によるものでしょう。もし右目が近視,左目が遠視の人なら,右に顔を向けてテレビを見るでしょうし,その反対なら右目が遠視,左目が近視ですので,どちら側に顔を向けているかよく見ることです。また頸の筋肉の左右差(斜頸)がないかどうかを調べることが大切です。また,横目症候群とよばれるくせもあります。これは,頸を右や左にぶって,いわゆる流し目のように横目でものを見る場合などがあります。このくせは,テレビや本などを熱中して見ているときに起こってきますから,自分で自覚するように,あまりしかりつけないでゆっくり注意して,指導してください。 |
|||||
|
Q.斜視の子どもに対して学校で特に気をつけることはどのようなことですか 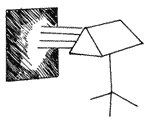
|
斜視の子どもがどのような斜視であり,どのような治療をしているかをおおよそ把握しておく必要があります。“ひんがらめ”“ヤブニラミ”“ドキンガン”“メカチン”などの悪口のために精神的な治療をしなければならなくなった例があります。特にその子どもがコンプレックスをもたないよう,まわりの子どもたちにもよく説明する必要があると思います。斜視の種類によっては,メガネをかけたり,プリズムメガネ,度の強いメガネを治療の過程で用いることも多く,そのほか,アイパッチや眼帯でおおうこともあります。 |
斜視
|
斜視(屈折異常編P87)でも間歇性斜視(斜視のときと,斜視でないときがある)や斜位(眼位ずれはあるが,それを眼筋を働かせて自ら矯正している)の人は,眼精疲労が起こってきます。視線をまっすぐにして,斜視をなくし,ものをひとつにみようと常に目の筋肉を緊張させるために疲れるわけです。プリズム眼鏡をかけたり,斜視手術をするなどの方法で治します。 |
||
斜視 (しゃし)
斜視
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/07 22:55 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2018年5月)
|
| 斜視 | |
|---|---|
 |
|
| 概要 | |
| 診療科 | 眼科学, 斜視学[*] |
| 分類および外部参照情報 | |
| ICD-10 | H49 – H50 |
| ICD-9-CM | 378 |
| OMIM | 185100 |
| DiseasesDB | 29577 |
| MedlinePlus | 001004 |
| Patient UK | 斜視 |
| MeSH | D013285 |
斜視(しゃし)とは、ヒトの眼の片方は視線が正しく目標とする方向に向いているが、もう片方の目が内側や外側、あるいは上や下に向いている状態のことをいう。教室など前に近い場所では見えづらく、個人差がある。
京都大学の研究グループはレセプトに基づいて、斜視に分類される約80の病気を合算し、加齢で眼球を支える組織が弱ることに伴う発症を含めて日本人の50人に1人程度が患っていると推計し、「国民病の一つ」と指摘している[1]。
俗に眇(すがめ)[2]、ひんがら目(ひんがらめ)、藪睨み(やぶにらみ、𥍃[3])[4]、ガチャ目、ロンパリ、寄り目と言われる。
眇は、片目が細い、あるいは潰れているさまを表すこともある[2]。ひんがら目は「僻目(ひがらめ。僻眼とも)」が変化した語である。また「ロンパリ」は、一方の目でロンドンを見つつ、もう一方の目でパリを見ているさまに喩えた語であるとされる[5]。
原因
遺伝という説もあるが、はっきりした関係性やメカニズムなどはわかっておらず、遺伝によるものとは断定できない。他には、強度の近視や遠視、失明、乳幼児期の弱視などで目の筋肉バランスが崩れてしまうことによる。また、外傷による場合もある。脳腫瘍によるものもあるので注意。
症状
左右の目がそれぞれ異なる方向を向いているため、美容的なデメリットの他、機能的には両眼視差による立体視(遠近感の獲得)が困難になる他、視ている像が二つに見える複視が生じることもある。両眼視差による立体視はおおよそ生後2ヶ月から2歳頃までで形成されるので、その期間で恒常性斜視が続くと、手術で矯正されても両眼視差による立体視を獲得するのは難しくなる。ただし、大人になってから立体視機能を獲得した例もある。
人間の目は本来、片方が左右のずれを捉え、もう片方で奥行きのずれを捉える事により立体視している。両眼視機能がない人間は「利き目」が両方の役割を担うことになる。そのため利き目に負担がかかりやすく、逆の目の映像は複視や視力差により脳内で混乱を起こすため「抑制」と呼ばれる脳機能で本来の映像が制限される。両眼視機能がある状態であれば、前視界のうち50/50程度の割合となるが、仮に右目が斜視、左目が通常の場合は70/30といったような役割分担となる。「抑制」は特に幼少期の患者に起こるが、「抑制」により使われなくなった目は視力低下などを併発する傾向があり、これによりさらに斜視の症状が進んだり、弱視となる可能性もある(「斜視弱視」も参照)。
左右どちらの眼で見ているのか自覚できる場合がある。片眼しか見えないわけではなく常に両眼が見えているのだが、「見ている」眼と「見えている」眼とに意識的に切り替えることができる。それにより遠方と近方を左右で使い分ける習慣が身についた場合、左右の視力差が大きくなることもある。
日常生活への影響
重度の斜視は外見上非常に目立つため、いじめや差別、人の目を真っすぐ見られないなどの理由による対人恐怖症や、コミュニケーション障害になる事もある。近年では心のケアを目的とした外科手術での見た目のみの修正も行われている。一般的には3歳頃までに両眼視機能を獲得できなければ、その後の獲得は非常に難しく、見た目を矯正できても両眼視機能を獲得できるわけではないため、物が二重に見えたり、左右別々の視野情報を脳が「抑制」してしまい斜視の目を使わなくなるため、数年で戻ってしまうことが多い。ただし、多感な幼少期〜青年期において人と目を見て話すことができないというデメリットを考えると、精神的に大人になるまで定期的に外科手術を受けるのは悪くない選択である。
両眼視差による立体視(遠近感)能力が無いと、物に触れたり物をつかんだり、球技等をする際に目測を定めづらいと感じたりすることがある他、坂道や階段を下る際に足を踏み外す危険性もある。
ただ、これらは物の大きさなどで距離感を補うなどすることが可能なため、実際は日常生活において不便や不都合を感じることはほとんどない。
また、立体映画や3D画像などの、左右の映像差を利用した「手前に迫ってくる」感覚は認識できない。ただし、これは必ずしもそうではなく、斜視であるが3D映像などの飛び出す感覚を感じることができる人もいる。
一般的に、片目は左右のズレを、片目は奥行きを、といった役割分担がなされるが、幼少期に斜視になり成人すると利き目がそのどちらの役割もこなすようになるため、運転などの比較的平面的な視野動作であれば問題無くこなすことができる。
幼少期の発症による影響
先天性または幼少期に斜視となった場合は、上述の通りおおよそ生後2ヶ月から2歳頃までの立体視形成段階で恒常性斜視が続くと、以降は手術をしても両眼視差による立体視(遠近感)を獲得することが難しくなる。
同じく上述の通り、幼少期は「抑制」が大人に比べて働きやすい。「抑制」により使われなくなった目は視力低下、などを併発する傾向があり、これによりさらに斜視の症状が進む可能性がある。また、人間の視力が完成する8歳頃までの視力発達段階で「抑制」により使われなくなった目の視力低下が続くと、弱視となる可能性もある。
幼少期の発症だと症状の無い逆の目が利き目となることが多く、利き腕と利き目が違うことにより字がうまく書けなかったり、まっすぐな線が引けないなどの症状が出る場合がある。
先天性の場合はこれらの症状が起こっていても「生まれたときからの普通の感覚」と捉えてしまうため本人の自覚がない場合も多く、他人が気づくまで発見が遅れる場合もある。
後天的に両眼視を獲得した例
マウント・ホリヨーク大学の神経生物学教授であるスーザン・R・バリーは48歳の時に両眼視機能を獲得した。その経験を著書「Fixing My Gaze」(邦題 視覚はよみがえる : 三次元のクオリア)にまとめている。彼女は幼少期から斜視で立体視が出来なかったが、テレサ・ルッジェーロという両眼視機能と視覚トレーニングの専門医に特別な視覚療法トレーニングを受け両眼視機能を獲得した。この著書により脳が新しい経験や学習に応じてその構造や機能を変える能力「脳の可塑性」(または神経可塑性)が大きく注目された。
スーザン・バリー博士が行った視覚療法
視覚療法は一人ひとりの状況に応じてカスタマイズされるため、これらの訓練の効果には個人差があり、誰もが後天的に両眼視機能を獲得できるわけではない事を前提に、彼女が行った代表的なトレーニングを「Fixing my gaze」から引用する。
Brock String(ブロック紐)
- 紐とビーズを使った両目の協調訓練。紐の先のビーズに焦点を合わせることで両目の協調を学ぶ。
プリズムレンズトレーニング
- 特殊なプリズムレンズを使用し、目が異なる方向に向かうようにして視覚情報の統合を促す。脳が両目からの視覚情報を調整して処理することを学ぶのを補助する。
ステレオグラム(Magic Eye Puzzle)
- ステレオグラムは、目を特定の方法で見ることによって三次元のイメージを浮かび上がらせる視覚パズルである。これを使用して、脳が両眼視を統合する能力を高める。
コンバージェンス/ダイバージェンストレーニング
- 目が同時に内側(コンバージェンス)または外側(ダイバージェンス)に向かうようにするトレーニング。これは、両眼が同時に動くように調整するためのエクササイズで目の筋肉の神経系を発達させる。
視覚追跡エクササイズ
- 動く対象物を追いかけるトレーニング。このエクササイズにより、目の筋肉を強化し、目の動きを両眼で統合する能力を高める。
目の位置による分類
 |
この節の加筆が望まれています。
|
- 内斜視
- 斜視のある側の目が内側を向くもの
- 外斜視
- 斜視のある側の目が外側を向くもの
- 上下斜視
- 斜視のある側の目が上や下を向くもの
状態による分類
- 恒常性斜視
- 常に斜視の状態であるもの
- 間歇(かんけつ)性斜視
- 普段は正常だが時々斜視の状態になるもの
斜視眼での分類
- 交代斜視
- 左右の目が交代に斜視の状態になるもの
- 片眼斜視
- 斜視になる目が、どちらか片方の目に決まっているもの
その他の分類
 |
この節の加筆が望まれています。
|
- 廃用性外斜視
- 失明した眼は外転筋の作用により外を向く傾向があるため起きるもの
- 固定内斜視
- 調節性内斜視
- 脳腫瘍によるもの
- 脳幹部(橋)部に脳腫瘍が発生したことによる内斜視と複視が認められる。小児脳幹部グリオーマ
治療
斜視の原因により、基本的には異なる。眼科専門医、視能訓練士による検査により明確にその原因についてはっきりさせ治療計画をたてる。
調節性内斜視に代表される斜視では、眼鏡やコンタクトレンズなどで屈折矯正を行うことにより、斜視を治療することができるケースもある。また物を見る力をつけさせる(視能訓練)ことにより斜視を治療できる場合がある。プリズム眼鏡等を用いる方法もある。
また、手術による治療法もある。眼を動かす外眼筋の位置をずらし、斜視を治療する方法である。小児においては全身麻酔下で行い、大人は局所麻酔で行う場合が多い。
手術の合併症・危険性
- 手術中
-
- 筋肉の処置をする際に脈が落ちたり、止まったりする人が稀にいる。
- 筋の縫合の際に眼球に穴が空くことがある。
- 手術後
-
- 術前の斜視が強い場合は、一回の手術では治らない場合がある。
脚注
関連項目
- ヒルシュベルグテスト(ヒルシュベルク法) - 斜視を確認するための角膜反射試験。
- カバーテスト ‐ 斜視を確認するための試験。カバー・アンカバーテストなどもある。
- ヘス赤緑テスト(Hess赤緑試験)
外部リンク
斜視
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 08:44 UTC 版)
学生時代の学生運動中の事故が原因である斜視(失明した事による廃用性)については周囲からそのままでも良い、トレードマークであると励まされていた旨を自著などで明らかにしていたが、『元気が出るテレビ!!』時代にテリーの下で演出を手掛けていた日本テレビの土屋敏男の勧めで斜視の矯正手術を決意し、2007年に土屋の手掛けるインターネットテレビの第2日本テレビとその関連番組である『でじたるのバカ²』でその模様にも密着した。 2007年5月10日に斜視手術で名医とされる丸尾敏夫による手術を受け、同月13日の『サンデージャポン』から本格的にテレビ復帰。術後の経過は良好で、23日には治った目を公開した。
※この「斜視」の解説は、「テリー伊藤」の解説の一部です。
「斜視」を含む「テリー伊藤」の記事については、「テリー伊藤」の概要を参照ください。
「斜視」の例文・使い方・用例・文例
- 恋は嫉妬深いもので、正常な目を斜視にさせる。
- 斜視です。(寄り目)。
- あの人は斜視だ
- ひどい斜視だ
- 斜視眼
- 内斜視眼
- 外斜視眼
- 斜視手術
- 斜視のように寄り目にする
- 収束性の斜視があるさま
- 斜視の
- 外斜視を持っている
- 斜視を修正するために目の筋肉あるいは腱を切る外科手術
- 手術行わない方法による両眼視障害(斜視と弱視など)の治療(特に目の筋肉を強くするエクササイズによって)
- 内斜視である
- 斜視になる
- 斜視の人
- 片目、あるいは両眼が、鼻に向かって内側に入る斜視
- 一方のもしくは両方の眼が外側に向いている斜視
- 異常な筋収縮が特徴の斜視、顔面痙攣、および他の神経障害を治療するために、医学的に少量使用される神経毒(商標名ボトックス)
斜視と同じ種類の言葉
品詞の分類
- >> 「斜視」を含む用語の索引
- 斜視のページへのリンク
辞書ショートカット
カテゴリ一覧
すべての辞書の索引
「斜視」の関連用語
| 斜視のお隣キーワード |
斜視のページの著作権
Weblio 辞書
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
|
(C)Shogakukan Inc. 株式会社 小学館 |
|
| Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved. | |
| Copyright (C) 医療法人社団 医新会 All Right Reserved. | |
| Copyright©2025 Mothers' and Children's Health and Welfare Association. All Rights Reserved. | |
|
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. この記事は、ウィキペディアの斜視 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。 |
|
|
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL). Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのテリー伊藤 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 |
|
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います: Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France. Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France. | |
| この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。 | |
| Copyright © 1995-2025 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved. | |
| Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved. | |
| Copyright (c) 1995-2025 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved. | |
| 日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved. WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License | |
| Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved. 「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編 | |
| This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence. |
ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問
文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典
|
ご利用にあたって
|
便利な機能
|
お問合せ・ご要望
|
会社概要
|
ウェブリオのサービス
|
©2025 GRAS Group, Inc.RSS