うめ2号
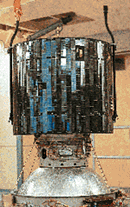
名称:電離層観測衛星「うめ2号」/Ionosphere Sounding Satellite-b(ISS-b)
小分類:地球観測衛星
開発機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:郵政省通信総合研究所
打ち上げ年月日:1978年2月16日
運用停止年月日:1983年2月23日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:N-I
打ち上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)
国際標識番号:1978018A
うめ2号は、うめの予備機で、打ち上げ1ヵ月後に不具合を起こしたうめの後継機として、改善を加えられて打ち上げられました。短波通信の効率的な運用のために電離層の観測を行なうことが目的で、1978年4月下旬から郵政省通信総合研究所によって運用され、約1年半のミッションを遂行しました。ミッション終了後も観測データの収集を続け、海外通信などに必要な電波予報の改善に重要な役割を果たしました。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
直径約94cm、高さ約82cmの円筒形で、重量は約141kgです。
観測装置は、電離層観測装置(トップサイド・サウンダ)、電波雑音観測装置、プラズマ測定器、イオン質量測定器を搭載しています。
2.どんな目的に使用されるの?
電離層臨界周波数や、電波雑音源の世界的分布の観測、電離層上部の空間におけるプラズマ特性と、正イオン密度の測定を目的に開発されました。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
軌道投入後、約2ヵ月間の初期運用を行なった後、1978年4月下旬から郵政省通信総合研究所による、運用が開始されました。約1年半のミッション期間が終了した後も観測データの収集を続け、海外通信などに必要な電波予報の改善に重要な役割を果たすとともに、超高層物理学の分野にも大きく貢献しました。1983年2月23日に発生電力の低下により運用を終了しました。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
うめがあります。
5.どのように地球を回るの?
高度981kmから1,228km、傾斜角69.4度、周期約107分の円軌道です。スピン安定方式で姿勢を制御します。
うめ2号
(Ionosphere Sounding Satellite - b から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/04 00:17 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 電離層観測衛星「うめ2号(ISS-b)」 | |
|---|---|
| 所属 | NASDA, RRL |
| 主製造業者 | 三菱電機 |
| 公式ページ | 電離層観測衛星「うめ」 |
| 国際標識番号 | 1978-018A |
| カタログ番号 | 10674 |
| 状態 | 運用終了 |
| 目的 | 電離層の観測 |
| 観測対象 | 電離層 |
| 計画の期間 | 5年 |
| 設計寿命 | 1年半 |
| 打上げ場所 | 種子島宇宙センター大崎射場大崎射点 |
| 打上げ機 | N-Iロケット4号機(N4F) |
| 打上げ日時 | 1978年2月16日13:00 (JST) |
| 運用終了日 | 1983年2月23日 |
| 物理的特長 | |
| 本体寸法 | 直径: 0.935 m 高さ: 0.82 m |
| 質量 | 141 kg |
| 発生電力 | 60 W |
| 姿勢制御方式 | スピン安定方式 |
| 軌道要素 | |
| 周回対象 | 地球 |
| 軌道 | 略円軌道 |
| 近点高度 (hp) | 972 km |
| 遠点高度 (ha) | 1,225 km |
| 軌道傾斜角 (i) | 69.4 度 |
| 軌道周期 (P) | 107 分 |
| 搭載機器 | |
| TOP | 電離層観測装置 |
| PIC | 陽イオン質量測定器 |
| RAN | 電波雑音観測装置 |
| RPT | プラズマ測定器 |
うめ2号(英語: Ionosphere Sounding Satellite - b, ISS-b)は宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた人工衛星(電離層観測衛星)である。
目的
当機は打ち上げ1ヶ月で故障した「うめ」の後継機であり、ミッションの内容もほぼ同じである。電離層を観測し、短波通信の効率的な運用に欠かせない電波予報と警報に利用することを目標とした。また、その観測能力を生かして国際磁気圏観測計画 (IMS) に参加した。IMSには他に「きょっこう」「じきけん」も参加している。
特徴
基本的な設計・構成はうめと同一であるが、バッテリーの発熱を少なくした他、バッテリーの熱放散を良くするように電源系の改修を行うなど、うめで問題となった箇所に改良が加えられている。
開発
元々うめの予備機として開発されていたものであり、1975年6月には設計が終了しており、サブシステムも1976年3月までに製作を完了していた。しかし、うめが1976年4月2日に故障したことから改良の必要性が生じ、1977年3月までにバッテリーを除くサブシステムの改修・受入試験を実施、残るバッテリーも同8月にフライト品が完成し、10月には衛星が完成した。
運用
1978年(昭和53年)2月16日にN-Iロケット4号機で種子島宇宙センターから打ち上げられ、高度約1,000km、軌道傾斜角約70度の円軌道に投入された。およそ2ヶ月間の初期運用を行ったのち、郵政省電波研究所に運用を引き継いだ。
1979年10月に当初予定していたミッションを終了したが、衛星自体はその後も観測を続け、1983年2月23日に太陽電池の劣化による発生電力低下のため運用を終了した。
成果
海外短波通信などに必要な電波予報の改善に重要な役割を果たした他、超高層物理学の分野にも大きく貢献した。
関連項目
外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「Ionosphere Sounding Satellite - b」の例文・使い方・用例・文例
- 今年からは、フィットネスセンターのNice-n-Fitチェーンと契約を結びました。
- 便利なことにNice-n-Fitの本店は隣のBlake Tower内にあり、街中にも4 つの店舗があります。
- Nice-n-Fit の会員になると、同チェーンのすべての施設に通うことができます。
- ご注文いただいた3 品のうち、引き出し2個付きのファイル棚(商品番号34-210)と、便利なデスク用掃除機(商品番号5202)は7 月15 日に発送されました。
- Bay Areaの5か所で10日間にわたり、Cream-Liteが30 グラム入った無料の箱が、200 グラム入り箱の割引券と一緒に見込み客に配られます。
- Cream-Liteが30グラム入った試供品
- Cream-Liteが200グラム入った容器
- 7 月25 日、本社で参加者にインタビューを行い、その際に効力や風味、ネーミングなどの区分について、1-10の段階で試供品を評価してもらいます。
- 詳細は、Mauer不動産のKim Yoshida、832-2938までご連絡ください。
- 許可されているものとされていないものの安全基準は、弊社のウェブサイトwww.air-qatar.comでご確認いただけます。
- 詳細は、Sophistication のウェブサイト、www.sophistication-magazine.comをご覧ください。
- 登録するには、(352) 112-3944 までお電話をいただくか、コミュニティーセンターのウェブサイトから登録用紙をダウンロードして、Addo通り948 番地、Mephisto、AZ85002 まで郵送してください。
- サケは通常2-3kgである。
- インターロイキン-6受容体
- CTLA-4遮断はがん細胞の再増殖を抑制する。
- 効率化を図る為に20-80のルールを利用した。
- 政府による現在のポリシ-ミックスは国家経済が望ましい方向へと進むのに役立っているようだ。
- サプライヤとメーカーはできるだけ早くWin-Winのパートナー関係を築くべきだ。
- 2-Dと同等の
- 私たちは注文番号F-2144、F-2146、F-2147の注文の品を発送しました。
- Ionosphere Sounding Satellite - bのページへのリンク


