きく5号
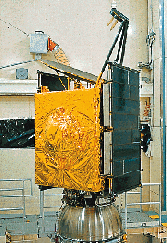
名称:技術試験衛星V型「きく5号」/Engineering Test SatelliteーV(ETS-V)
小分類:技術開発・試験衛星
開発機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))/郵政省通信総合研究所(CRL)/運輸省電子航法研究所(ENRI)
運用機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))/郵政省通信総合研究所(CRL)/運輸省電子航法研究所(ENRI)
打ち上げ年月日:1987年8月27日
運用停止年月日:1997年9月12日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:H-I
打ち上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)
国際表記番号:1987070A
きく5号は、H-Iロケットの性能確認や、「静止三軸衛星バスの基盤技術の確立」、将来の「大型静止衛星の開発」に必要な技術の習得、そして船舶の通信・航空援助・捜索救難のための「移動体通信実験」などを目的に開発されました。移動体通信実験とは船舶・航空畿自動車などの移動体へ衛星を利用して通信をおこなう、通信システムの研究開発を目的におこなわれるものです。従来の無線による移動体への通信手段は、有効範囲や品質・情報量の点で満足できるものではありませんでした。しかし衛星通信システムにより、これらの欠点の改善を目指しました。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
展開型の太陽電池パドルを持つ箱型をしています。大きさは、本体部が約1.4m×1.67m×1.74mで、翼のような太陽電池パドルとアンテナなどを広げると、南北方向約9.7m×地球方向約3.5mの大きさになります。重量は約1,096kg(打上げ時)/静止衛星軌道上初期約550kgとなっています。
姿勢制御方式は、「三軸姿勢制御方式」を採用しています。
きく5号には、宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))が郵政省通信総合研究所、運輸省電子航法研究所と協力して開発した「移動体通信実験器(AMEX)」を搭載しています。AMEXでは、衛星と海岸/航空地球局との間をCバンド(上り6GHz、下り5GHz)、衛星と移動体との間をLバンド(上り1.6GHz、下り1.5GHz)の電波を使ってやりとりします。またLバンドアンテナはふたつのビームを持ち、Nビームは「日本全土を含む北太平洋域」、Sビームは「南太平洋域」をカバーします。
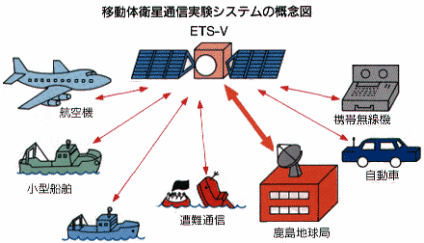
実験システム前述のように、打ち上げロケットであるH-Iロケットの性能確認や、船舶の通信・航空援助・捜索救難のための移動体通信実験のほか、航空機の太平洋域での洋上管制、初の国内開発品であるアポジモーターの性能確認などに利用されています。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
初期段階の追跡管制、衛星機能確認試験を経て、1987年11月末以降、本格運用となり、1989年3月31日、打ち上げ後、約1年半の定常段階を終了しました。しかし、きく5号の移動体通信実験機器(AMEX)は、その後も静止軌道上でCバンド、Lバンド帯回線を用いて、地上の基地局と航空畿船舶などの移動体との通信や移動体同士の通信を中継する機能を持ち、実験がおこなわれていました。1997年12月、運用を終了しました。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
きく、きく2号、きく3号、きく4号、きく6号、きく7号(おりひめ・ひこぼし)、きく8号があります。
きく5号
(ETS-V から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/22 19:49 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 技術試験衛星V型「きく5号(ETS-V)」 | |
|---|---|
| 所属 | NASDA, CRL, ENRI |
| 主製造業者 | 三菱電機 |
| 公式ページ | 技術試験衛星V型「きく5号(ETS-V)」 |
| 国際標識番号 | 1987-070A |
| カタログ番号 | 18316 |
| 状態 | 運用終了 |
| 目的 | 550kg級静止3軸衛星バス技術の確立 移動体通信実験 |
| 計画の期間 | 10年 |
| 設計寿命 | 1.5年 |
| 打上げ場所 | 種子島宇宙センター大崎射場大崎射点 |
| 打上げ機 | H-Iロケット2号機(H17F) |
| 打上げ日時 | 1987年8月27日18:20 |
| 運用終了日 | 1997年9月12日 |
| 物理的特長 | |
| 本体寸法 | 1.4 m × 1.67 m × 1.74 m |
| 最大寸法 | 9.7 m × 3.5 m (太陽電池パドル及びアンテナ展開時) |
| 質量 | 1,096 kg(打ち上げ時) 550 kg(静止軌道上初期) |
| 発生電力 | 1.09 kW |
| 主な推進器 | 固体アポジモータ 二次推進系 |
| 姿勢制御方式 | 3軸姿勢制御 (コントロールド・バイアスモーメンタム方式) |
| 軌道要素 | |
| 周回対象 | 地球 |
| 軌道 | 静止軌道 |
| 静止経度 | 東経150度 |
| 高度 (h) | 約36,000km |
| 搭載機器 | |
| AMEX | 移動体通信実験機器 |
| Lバンド中継器(1.5/1.6GHz) | |
| Cバンド中継器(5/6GHz) | |
| TEDA | 技術データ取得装置 |
きく5号(英語: Engineering Test Satellite - V、ETS-V)は宇宙開発事業団 (NASDA) が打ち上げた人工衛星(技術試験衛星)である。
目的
3段式H-Iロケットの性能確認、国産固体アポジモータの性能試験、静止3軸衛星バスの基盤技術の確立、将来の実用衛星開発に必要な新規技術の実証、船舶の通信・航空援助・捜索救難のための移動体通信実験を目的としている。
開発
1978年度から1979年度にかけて概念検討が行われた。当時は中高度3軸衛星用バス技術の確立を目的とし、ミッション機器として合成開口レーダをもつ全備質量1.3tの衛星として計画され、2段式のH-Iロケットで打ち上げられる予定であった[1]。その後、計画は変更され、1982年度に静止3軸衛星用バス技術の確立などを目的とする静止衛星として宇宙開発委員会に提案された。宇宙開発委員会では従来より郵政省及び運輸省から要望のあった移動体通信実験衛星と統合する方向性が示された。翌1983年度から開発を開始、1983年5月より基本設計を行い、1984年11月から詳細設計を実施した[2]。
運用
1987年8月27日にH-Iロケット2号機で種子島宇宙センターから打ち上げられた[3]。衛星の機能確認などの初期運用を経て、同年11月末から定常運用に入り、移動体通信実験や洋上管制実験等の実験を実施した。1989年3月31日までの1年半にわたる定常運用を終了した後も実験を続け、1997年9月12日に全ての運用を終了した[3]。
出典・脚注
- ^ 山口弘一「実利用分野における日本の衛星計画」『計測と制御』第19巻第6号、計測自動制御学会、1980年6月、 pp.564-570、 ISSN 0453-4662、2010年9月14日閲覧。[リンク切れ]
- ^ 通信総合研究所季報 第34巻 第6号3-1 ETS-Vの概要
- ^ a b “技術試験衛星V型「きく5号」(ETS-V)”. 宇宙航空研究開発機構. 2021年12月23日閲覧。
関連項目
外部リンク
- ETS-Vのページへのリンク

