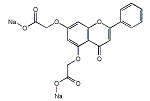ペリセル
| 分子式: | C19H12Na2O8 |
| その他の名称: | ペリセル、フラボダートジナトリウム、Intercyton、ジナトリウムフラボダート、Pericel、Disodium flavodate、Flavodate disodium、インテルシトン、2,2'-[(4-Oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-5,7-diyl)bis(oxy)]bis(acetic acid sodium) salt、[(4-Oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-5,7-diyl)bis(oxy)]diacetic acid disodium salt、FM-7 |
| 体系名: | [(2-フェニル-4-オキソ-4H-1-ベンゾピラン-5,7-ジイル)ビス(オキシ)]ビス[酢酸ナトリウム]、2,2'-[(4-オキソ-2-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-5,7-ジイル)ビス(オキシ)]ビス(酢酸ナトリウム)、[(4-オキソ-2-フェニル-4H-1-ベンゾピラン-5,7-ジイル)ビス(オキシ)]二酢酸ジナトリウム |
FM-7
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/08 03:51 UTC 版)
|
この記事で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。
|
FM-7(エフ・エム・セブン)は富士通が発売した8ビットパソコンであり、正式名称はFUJITSU MICRO 7。富士通はこのFM-7のヒットにより、シャープ、NECと共にパソコン御三家と呼ばれる様になる。
FM-7
| 開発元 | 富士通 |
|---|---|
| 種別 | パーソナルコンピュータ |
| 発売日 | 1982年11月8日[1] |
| 標準価格 | 126,000円 |
| 販売終了日 | 1984年4月[2] |
| 出荷台数 | 22万台[2] |
| OS | F-BASIC、OS-9 |
| CPU | MBL68B09 2 MHz |
| メモリ | ROM 44KB, RAM 64KB |
| グラフィック | テキスト80桁×25行、グラフィック640×200ドット8色 |
| サウンド | PSG8オクターブ3音 |
| 入力機器 | JISキーボード |
| 外部接続 | CMT、プリンター、拡張カード |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 25VA |
| サイズ | 430(W)×288(D)×100(H)mm |
| 重量 | 4.5kg |
| 前世代ハード | FM-8 |
| 次世代ハード | FM-NEW7 |
FM-7は1982年11月8日、FM-8の廉価版後継機種として発売された[3]。開発時の名称はFM-8Jr.(ジュニア)。FM-8と一定の互換性があり、アプリケーション、OS(CP/M、FLEX、UCSD Pascal[4]、OS-9)、開発言語、ツール、周辺機器の資産継承が考慮されていた。FM-8を含んで、FM-7/8シリーズと呼ばれ、CPUの高速化等、実質的にはFM-8の性能が向上した後継機にあたる。
モトローラ社のMPU 68B09をメインCPUとグラフィックを独立制御するディスプレイサブシステムへそれぞれ搭載する2CPUのアーキテクチャを採用。FM-8と同様にオプションのZ80カードが搭載可能[注 1]になっており、CP/Mや、Oh!Xで使われたS-OS"SWORD"など、Z80CPUベースのシステムを動作させることも可能[注 2]になっている。このZ80カード用スロットは後にユーザベースで63C09を搭載するハードウェアにも使われた。F-BASIC V3.0がROMに搭載されている。漢字ROMカード、フロッピーディスクドライブ[注 3]はオプション。
発売当初のイメージキャラクターはタモリ。キャッチコピーは「青少年は興奮する」[5]。
競合機種と同等のカラー表示にPSGがつき価格が安かったことから、FM-7は一定の普及をみて、富士通をパソコン御三家の地位にまで押し上げた。FM-7に端を発する低価格・高性能という路線はPCユーザ拡大に貢献し、'80年代パソコンブームの原動力となった。
FM-7が販売面で成功したのは本体価格が126,000円という低価格にもかかわらず、当時の最新機能を盛り込み1クラス上のPCに匹敵または凌駕する性能を備えていたことにある。同時期の人気機種は、NEC PC-8801(228,000円)、PC-9801(298,000円)、日立 ベーシックマスターレベル3(298,000円、後に価格改定)。学生を中心に人気があった「パピコン」ことNEC PC-6001(89,800円)やコモドールVIC-1001(69,800円)などの初心者PCのユーザー層にも大きな影響を与え、その成功からFM-7を引き継ぐ形で、後継機が完全上位互換で作られていく形になる。
FM-8から引き続き、広いメモリ領域とVRAM領域の確保と処理速度向上のためにメイン(演算部)、サブ(主にグラフィック部)に独立した6809を搭載する贅沢なアーキテクチャを採用した。FM-8を祖とするこの設計は、マルチCPUとしてではなく、ホストCPUと表示端末の関係にあり、サブCPUに処理の大きな表示周りの作業をさせることによるメインCPUの負担を軽減することに目的があった。また、このグラフィックスサブシステムの実装ではキャラクターコードをハードウェア的にフォントに展開するテキストVRAMを持たなかったため、20並びに25行のスクロール処理における転送量軽減のため、2ラインごと[注 4]のハードウェアスクロール機能を備えている。ハードウェアによるスクロールが使えない画面モードでは、当時の処理速度と比較して広大なグラフィックVRAMを再描画する必要があり、リスト表示などでのスクロールのもたつきや、カーソルを移動するとその通り道にあったグラフィックも消えてしまうという制限も引き継いでいる。また、リアルタイムゲームが流行すると両システム間の転送容量に制限や処理のタイムラグがあったこと、キーボードのスキャンを専用CPUに任せ、チャタリング除去なども行っているためにBREAK以外のキーでは押下した結果しか認識できず、ユーザの間ではリアルタイムゲーム向きではないとされ、議論になった[注 5]。前述のとおり、任意のコードの実行を想定して設計されているわけではないサブシステムではあったが、サブシステムモニタ開発時にデバッグ用に実装されたメンテナンスコマンド[注 6]の利用や、そのノウハウの蓄積、後述する内部技術資料の積極的な公開により、サブシステムで任意のプログラムを実行することで描画の高速化や、高速にデータを転送するテクニックなどが考案され、ハードウェア的なキー入力の制限を除けば競合機種と同等のゲームが発売されるようになっていった。
他社と同様、富士通も本体添付品や別売マニュアルという形でBIOS、I/Oアドレス、ファームウェア、システムコマンド等を積極的に公開した。また富士通の支援により、FMシリーズ専門誌『Oh!FM』(日本ソフトバンク、後の『Oh!FM TOWNS』)をはじめとして、技術評論社や工学社などから『活用マニュアル』などと呼ばれる良質なリファレンスマニュアルが多く出版された。またショウルームやサポートセンター経由では、内部技術資料なども必要に応じて比較的簡単に入手できた。
回路設計の問題としては、同等の音源を搭載した他機種に比較して、サウンド出力にデジタル回路からリークしたノイズも多く、音割れも見られた。
1985年、スペインのSECOINSA社という富士通に近い会社より FM-7 が販売されている[6][7][8]。
従来機種との互換性
- FM-8との主な共通点。
- FM-8との主な差異。
- MPUクロックの高速化(メイン1.2MHz→2MHz、サブ1MHz→2MHz)。
- FM-8と同じ速度にするモードもある。
- ソフトウェア制御可能なF-BASIC ROMとRAMのバンク切替機能の追加。
- サウンド機能(PSG3声)、カラーパレット機能、マルチページ機能の追加。
- キーボードのメインCPU側からのBREAKキー以外のキーコード読み取り機能、メインCPU側へのキーボード及びタイマ割り込み機能を追加。
- 拡張スロットを内蔵し、工具を使用せずにオプションカードの増設が可能。
- 拡張スロット用カードとして、漢字ROMカード(JIS第一水準のみ搭載)、FDDインタフェースカード、RS-232Cカード、Z80 CPUカード、音声合成ボードなどが発売された。
- 使用頻度の低いRS-232C、アナログ入力ポート[注 11]、バブルカセットホルダ等の機能を削除。
- キーボード専用マイコンの仕様改善[注 12]。
- 富士通から発売されたMSX規格パソコンであるFM-Xと連携動作を可能とするインタフェイスボードが発売されていた。
基本仕様
- FM-7
- CPU: メイン MBL68B09(入力外部周波数4.9/8MHz切換機能付[3])、サブ MC6809(入力外部周波数4/8MHz切換機能付)
- ROM: F-BASIC 32KB、ブートローダ 2KB、サブシステムモニタ 8KB、キャラクタ 2KB
- RAM: メイン64KB(BASICでのフリーエリアは32KB)、コンソール処理用4KB[9]、VRAM 48KB
- Text Mode: 80×20/25、40×20/25[注 13]
- Graphic Mode: 640×200モノクロ3プレーン若しくはカラー1プレーン。パレット機能付き。
- Sound: PSG(AY-3-8910あるいはAY-3-8913などの相当品); 入力クロックは 1.2288 MHz
- 電源(消費電力): AC100V 50/60Hz(最大70W)
- 使用条件: 温度 0〜35℃,湿度 20〜80%,(ただし結露しない事)
- 本体添付品
- 簡易言語 NEW VIPカセットテープ(表計算ソフト)
- 簡易言語 NEW VIP操作マニュアル
- FM-7 ユーザーズマニュアル システム解説書
- FM-7 ユーザーズマニュアル システム仕様書
- FM-7 F-BASIC 文法書
- FM-7 F-BASIC ポケットブック
- FMシリーズ F-BASIC入門
- オプション
- 本体内蔵オプション:
- 外部オプション:
- 動作する主要OS:
FM-7シリーズ
他のモデルのように実装機器による商品バリエーションは無いが、後期にリファインされた同等の機種が発売された。
- FM-7 [MB25010](1982年11月発売)126,000円。

- FM-NEW7 [MB25015](1984年5月発売)99,800円。
- FM-7の廉価モデル。ゲートアレイの利用により集積率を上げ、基板のサイズ、レイアウトは大幅に変更された他、ROM BASICなどでバグが修正されている等の違いはあるが機種としてはほぼ等価である。簡易言語 NEW VIPの添付がなくなった。初期ロットではフロッピィディスクのステップレートを変更できる新ブートROMを搭載していたが、いくつかの市販ソフトが動作しない問題があったためすぐにFM-7のブートROMに戻された。
FM-77
| 開発元 | 富士通 |
|---|---|
| 種別 | パーソナルコンピュータ |
| 前世代ハード | FM-NEW7 |
| 次世代ハード | FM77AV |
FM-77(エフ・エム・セブン・セブン)は1984年、FM-7後継機種としてFM-NEW7とともに発売された。FM-11と同様にキーボードを分離し、3.5インチフロッピーディスクドライブ、JIS第一水準漢字ROMを本体に内蔵したモデルである。ディスク版F-BASIC V3.0L2.0とFM Logoが付属した。
キーボードはパラレルインターフェースで、コードは黄色い(D1/D2のみ。L2/L4は本体同色)カールコードとなっているが太い。本体色はオフホワイト。
本体の発熱量が高く、長時間使用し続けているとフロッピードライブに入れたディスクまで熱くなるという特徴があった。
拡張性がFM-7に比べ大きく向上し、メモリ管理ユニット(MMU)であるメモリ・マネージメント・レジスタ(MMR)を搭載してメイン側のメモリアドレス空間が256KiBに広がったほか、サブシステムが改良され、サイクルスチールによりVRAMアクセスのタイミングなどが向上し、表示が高速化された。ただし、MMR使用時にはMPUクロックが2MHzから1.6MHzに低下した。
専用オプションとして、400ラインセット、1MBフロッピィコントロールカード、スーパーインポーズユニットなども用意された。
400ラインセットは99,800円と大変高価であったため、後にRAM容量と日本語ワードプロセッサが削られた廉価版の400ラインセットIIが49,800円で用意された。
1MBフロッピィコントロールカードは当初F-BASIC V3.5とOS-9 Level II(OS-9 Level IIの起動にはRAMが最低128KB必要だが、400ラインカードはなくても可能)でしかサポートされていなかったが、後に400ラインセット不要で使用できるようにF-BASIC V3.1が用意された。
スーパーインポーズユニットは200ラインでしか使用できないため、400ラインセットとは排他的に使用する必要があった。
従来機種との互換性
FM-7とはほぼ完全上位互換であるが、MPUクロックをFM-8相当に落とす機能は削除されている。
ブートモードは従来機種のディップスイッチ方式からボタン式スイッチ方式に変更され、BOOT1、BOOT2、BASICの3種類から選択できる。 BOOT1スイッチは1MBフロッピィDOSモード、BOOT2スイッチは320KBフロッピィDOSモード、BASICスイッチはF-BASICモードになっており、FM-7/NEW7と比較して1MBフロッピィDOSモードが追加された。なお、FM-NEW7と異なり全ロットでフロッピィディスクのステップレートの変更はできない。
また、グラフィックモードスイッチでサイクルスチールのON/OFFが選択でき、OFF時にはFM-7/NEW7同等の描画速度となる。
内蔵オプションは互換スロットが用意されていたため、FM-7用の各種増設カードはほぼそのまま使用可能になっているが、ミニフロッピィディスクインタフェースカード、漢字ROMカード等、すでに実装済の機能と等価の一部周辺機器については利用できない(利用する必要がない)。
外部オプションはインタフェースコネクタが変更されたため同じケーブルでは接続できなくなったが、信号線は変更されなかったため、ケーブルさえ用意できればFM-7用の各種外部オプションは使用可能。
基本仕様
- FM-77D1/D2
- CPU: メインMC6809(2MHz)、サブMBL68B09E(2MHz)
- ROM: F-BASIC 32KB、ブートローダ 4KB、サブシステムモニタ 8KB、キャラクタ 2KB、JIS第一水準漢字 128KB
- RAM: メイン64KB(最大256KB)、サブ5KB、VRAM 48KB
- FDD: 3.5"2D×2(D2),3.5"2D(D1)
- OS: F-BASIC V3.0L2.0、FM Logo
- Text Mode: 80×20/25、40×20/25
- Graphic Mode: 640×200モノクロ3プレーン若しくはカラー1プレーン。パレット機能付き。
- Sound: PSG(AY-3-8910)
- 電源(消費電力):AC100V 50/60Hz(最大100W)
- 使用条件:温度 5〜35℃、湿度 20〜80%(ただし結露しない事)
- 本体添付品
- FM Logo(作図言語)
- FM-77 77をつかおう
- FM-77 ユーザーズマニュアル F-BASIC入門
- FM-77 ユーザーズマニュアル ファームウェア解説
- FM-77 ユーザーズマニュアル ハードウェア解説
- FM-77 F-BASIC 文法書
- FM-77 ディスクユーティリティ操作手引書
- FMシリーズ FM Logo プログラミング入門
- FMシリーズ FM Logo V2.0 リファレンスマニュアル
- 追加オプション(基本はFM-7に準ずる)
- 本体内蔵オプション:
- 外部オプション:
- MB22610 スーパーインポーズユニット
- MB26002J I/O拡張ユニット(接続ケーブルがFM-7と異なる)
- MB22439J MIDIアダプタ(接続ケーブルがFM-7と異なる)
- 動作する主要OS:
FM-77シリーズ
- 初代(1984年5月発売)カールコード黄色。
- FM-77D1 [MB25240] FDD1基搭載。198,000円。
- FM-77D2 [MB25250] FDD2基搭載。228,000円。1984年度グッドデザイン賞受賞[13]
- 二代目 FDD2基搭載。カールコード白色。
FM77AV
| 開発元 | 富士通 |
|---|---|
| 種別 | パーソナルコンピュータ |
| 前世代ハード | FM-77 |
FM77AVはFM-7/FM-77シリーズの上位機種となるシリーズ。1985年に初代機が発売され、FM TOWNSシリーズの発売される直前の1988年秋までマイナーチェンジが繰り返された。初代FM77AVはメタリックダークグレーに近い色であるが、基本的に黒に近い色を基調としたデザインでシリーズは展開されている。イメージキャラは南野陽子。
FM16βSD/FM16π等と同様、FM-7の系譜では本機より、正式な機種名からは「FM」と「77」との間のハイフンは無くなった。しかし、従来機種の流れから、ソフトウェアパッケージや、雑誌記事、Webの記述などでは、ハイフンを入れて記述されることも多く見られる。
従来の640ドット×200ライン8色が2画面持てるようになったほか、320ドット×200ライン4096色という当時では画期的な色数の同時発色を可能とし、キャッチコピーではカラー化した映画などで使われた語である「総天然色」にかけて「総、天、然、ショック。」とうたった。セットの専用モニターはテレビチューナー内蔵で、単体でもテレビ放送が受信可能でビデオ入力端子も装備(スピーカーはモノラル)。
AV40シリーズでは全てのピクセルに対し26万色から任意の色を表示できるようになっているが、選択可能な色数が画素数を上回ったため広告から同時発色の記述はなくなっている。
オプションのビデオディジタイズカード(現在でいうビデオキャプチャカード)増設で専用テレビを通じてテレビ放送・ビデオ入力などからの画像取り込みもできた。
4096色モードではパレットの割り当てにより、重ね合わせ付きの64色2画面・16色3画面・8色4画面・単色12画面モードなどにすることができた。また、VRAMのオフセット指定による横8ドット/縦1ドットごとのハードウェアスクロール機能があり、オフセットは2画面別々に設定できた。このため、家庭用ゲーム機並みのゲーム画面も実現可能だった。アナログRGBディスプレイのコネクタおよびケーブルはEIAJ規格のRGB21ピンのクロスケーブルが使われた。
また、サブシステム側MPUを停止することにより、メインMPUからVRAMなどサブシステム側の資源に直接アクセスすることが可能になったほか、新サブシステムの機能としてハードウェアによる直線補間・論理演算機能付きのLINEコマンドやPAINTコマンドなどを搭載した。FM-8/7/77では1ドット単位で描画していたSYMBOLコマンドも直線補間機能を利用するようになり高速化している。キーボードは押下だけではなく開放も認識できる[注 15]ようになった。
キーボードは初代FM77AVでは電話の受話器と同じ4ピンモジュラージャックを使用した細いカールコードによる接続[14]で、初代FM77AVのキーボードは赤外線によるワイヤレス接続やnキーロールオーバーもサポートしていたが、これらの機能は後継機種ではコストダウンのため段階的に撤廃される。AV20/AV40では電話回線と同じ6ピンモジュラージャック、AV20EX/AV40EX/AV40SXはS端子と同形状の4ピンミニDINコネクタを使用している。
キーボードエンコーダには仕掛けがあり、特定の操作をするとマニュアルに無い機能があったり、隠しメッセージが表示されるようになっている。
FM77AVシリーズは、1989年3月末までに累計10万台を販売した[15]。
従来機種との互換性
FM-7/77シリーズとは高い互換性を持つ。
内蔵オプションは、Z80カード用スロットが削除されたためメインCPUの切替が不可能になりCP/MなどのOSはサポートされなくなったが、FM-7互換スロットは用意されたため各種増設カードはほぼそのまま使用可能だった。
外部オプションは、一部インタフェースが仕様変更されたためモジュール方式のI/O拡張ユニットやFM-77に用意された専用オプションなどは使用できなくなったが、プリンターなどはケーブルさえ用意すればそのまま使用可能だった。
起動時のBASICモード/DOSモードを選択するブートモードスイッチおよびサイクルスチールのON/OFFを選択するグラフィックモードスイッチなど従来機種と同等のスイッチは用意されており、FM-7/77同様BASICモード[注 16]でディスクを入れずに起動するとF-BASIC V3.0(ROMモード)が起動する。
これはブート機構に工夫がなされており、リセットがかかると先ずイニシエータROMが表に出てそこから起動。画面モード、アナログパレットなど[注 17]、新規デバイスの初期化を行い、モードスイッチを読み取ってBASIC ROMを有効化させたりRAM領域にするかなどの設定を行った後、従来のブート機構に制御を移す[注 18]という2段構えの初期化機構が採用されており、これによって新たなモードスイッチを用いない上位互換を確保している。
このため、FM77AV専用ではないアプリケーションソフトやゲームソフトにも、リアルタイムキースキャン・DMACに対応する「リバイバー」(アルシスソフトウェア)、DMACに対応する「キス・オブ・マーダー 殺意の接吻」(リバーヒルソフト)など、FM77AVで拡張されたハードウェア[注 19]の機能を使用出来るようになっているものが存在する。
基本仕様
- FM77AV-1/2
- CPU: MC6809(2MHz)×2(メイン、サブ)
- ROM: F-BASIC 32KB、イニシエータ 8KB、サブシステムモニタ 28KB、キャラクタ 4KB、JIS第一水準漢字 128KB
- RAM: メイン128KB(最大192KB)、サブ5KB、VRAM 96KB
- FDD: 3.5"2D×2(AV-2),3.5"2D(AV-1)
- OS: F-BASIC V3.3L10
- Text Mode: 80×20/25(3bit color),40×20/25(3bit color/12bit color) character
- Graphic Mode: 640×200(3bit color)×2,320×200(12bit color) pixel
- Sound: YM2203によるFM音源、SSGを各々8オクターブの音域で3音同時出力可能。
- キーボード: シリンドリカル・ステップドスカルプチャキーボード、nキーロールオーバー機能、ワイヤレス機能搭載
- ジョイスティック: アタリ規格9pin端子×2
- 追加オプション(基本はFM-7に準ずる)
- 内部オプション
- FM77MD201/FM77MD202 モデムカード-1200
- FM77-121 SCSIカード
- FM77EM64 拡張RAMカード-64(AV用)
- FM77EM64A 拡張RAMカード-64(AV20/AV20EX用)
- FM77EM256 拡張RAMカード-256(AV40/AV40EX/AV40SX用)
- FM77-211 日本語カード(AV/AV20/AV20EX用、JIS第二水準漢字ROM、辞書ROM、64KB RAMを搭載。学習RAMのバッテリーバックアップ機能付き)
- FM77-411 ビデオディジタイズカード(AV用)
- FM77-412 ビデオディジタイズカード(AV40/AV20用)
- FM77-413 ビデオディジタイズカード(AV40EX/AV20EX用)
- FM77-414 ビデオカード(AV20EX/AV40EX用。ビデオディジタイズカードにビデオコンバート機能を追加したもの)
- FM77-171 文字放送カード
- FM77-143 ハンディイメージスキャナインタフェースカード
- FM77-421 音声認識カード
- FM77-431 音声合成カード
- 外部オプション
- 動作する主要OS:
- OS-9/6809 Level 2
FM77AVシリーズ
- 初代(1985年10月発売)ワイヤレスキーボード、nキーロールオーバー対応。F-BASIC V3.3L10添付。
- FM77AV-1 FDD1基搭載。128,000円。
- FM77AV-2 FDD2基搭載。158,000円。
- 二代目(1986年発売)2DD/2D兼用FDD搭載、ワイヤレスキーボード、2キーロールオーバー。
- FM77AV20-1 FDD1基搭載。138,000円。F-BASIC V3.3L20添付。
- FM77AV20-2 FDD2基搭載。168,000円。F-BASIC V3.3L20添付。
- FM77AV40 FDD2基搭載。228,000円。日本語カード搭載。VRAM144KB(320×200×262,144色1画面・640×400×8色1画面)、DMAC追加。F-BASIC V3.4L10添付。MMUのアドレス空間が1MiBに拡張され、最大搭載メモリが、960KBとなっている。
- 三代目(1987年発売)2DD/2D兼用FDD2基搭載。MMR使用時にクロックスピードが2MHz→1.6MHzに落ちないモードを追加[注 20]。
- FM77AV20EX 128,000円。カセットインターフェースが廃止。DMAC追加。F-BASIC V3.3L30添付。
- FM77AV40EX 168,000円。VRAM192KB、640×400×8色・320×200×4096色 2画面・640×200×8色 4画面。F-BASIC V3.4L20添付。
- 最終機(1988年11月発売)本体色変更(黒色→マーブル色)
- FM77AV40SX 178,000円。F-BASIC V3.4L21添付。
- ビデオディジタイズ、スーパーインポーズ等ができる機能を標準で搭載したFM77AV40EXのマイナーチェンジモデル。RGB出力端子はそれまでのEIAJ-21ピン端子から、D-sub25ピンに変更されている。また、FM77AV40EXでは隠し機能[注 21]だったアップスキャンコンバータ(HSYNC 15kHzから24kHzへの変換)が正式な機能となった他、カセットインターフェースが廃止されている。ビデオディジタイズ・ビデオコンバート機能(FM77-414相当)を標準装備。グレー色の本体の前面とキーボードの上面に大理石のような塗装が施されており、墓石パソコンと呼ばれることもあった。FM-7シリーズの最終機となった。
- FM77AV40SX 178,000円。F-BASIC V3.4L21添付。
脚注
注釈
- ^ 回路はほぼ同じだがFM-8用と形状が異なり互換性はない。
- ^ 同時にZ80エミュレーション版も同時に掲載されており、速度は遅いものの、Z80カードなしでもSWORDは実行可能になっている。
- ^ 発売当初は5.25インチのみ。後に3.5インチも発売される。
- ^ 200ラインのグラフィック画面で10ラインと、8ライン単位のスクロールを実現するため、公約数の2ラインごとのオフセット表示が実装されている。
- ^ 多くのアクションゲームではキーの押下時にその方向へ直進し、キーを離す代わりに主にテンキーの5等、別のキーを押下させることでキーの開放の代わりとして停止するなど特徴的な実装がなされ、シューティングゲームなど同じキーに対して連続したキー入力が必要な機能にはBREAKキーを割り当てる形になっていた。
- ^ 正式名称はTESTコマンド。FM-8では、コマンド$3Fに続き、サブシステムの開発者の名前であるYAMAUCHIの8文字を渡す必要があったため、通称YAMAUCHIコマンドと呼ばれる。FM-7以降は任意の8文字を渡すことで実行できることから、その場所を8バイトのワークとして使うことも可能だった。
- ^ 同世代の他機種の様に独立したテキストVRAMという概念はなく、サブCPU側にテキスト・アトリビュート領域として用意された約4KBの「コンソールバッファ」がそれに相当する。
- ^ BREAKキーのみメインCPUに対してハードウェア割り込みを発生したり、メインCPU側の専用I/Oで押下/解放の判定が可能になっているが、キーボードはメインシステム/サブシステムに対して文字コードしか送信しないため、それ以外のキーは開放されたことを検出する手段が無い。nキーロールオーバー、キーリピートに対応している。
- ^ システムROMの裏側に隠れているため同様の仕組みは他の機種も含め「裏RAM」という俗称で呼ばれていた。
- ^ それを可能にするための改造は当時非常にポピュラーなFM-8のハードウェア改造の一つであった。
- ^ FM-8では主にジョイスティックの接続に用いられた。
- ^ たとえば「"」を入力する場合、FM-8では「2」キーよりも先にShiftキーを離すと、数字の「2」を続いて入力したとみなされ、「"2」がサブシステムへ渡されたが、FM-7ではShiftキーを先に離しても「"」のみが入力されるようになった。
- ^ グラフィックス画面にフォントを直接描画。
- ^ ただし必要となるのは拡張RAMカードであり、400ラインカードはなくても起動時に警告は出るものの動作する。
- ^ キーを押した時にMakeコード、キーを離した時にBreakコードが発行される機能が新設された。従って、基本的にはFM77AVシリーズ専用として新たに作られたソフトウェアでなければメリットは享受できない。
- ^ 初代FM77AVのみ。FM77AV20/AV40以降はDOSモードでも同様にF-BASIC V3.0が起動する。
- ^ AV20/40/20EX/40EX/40SXではメモリマッピングレジスタなども追加。
- ^ 初代FM77AVのみ。FM77AV20/AV40以降は任意のドライブから起動可能な新たなブート機構をRAMに展開し、そこに制御を移している。
- ^ VRAMのバンク切り替えやMMRやダイレクトアクセスやキーボードエンコーダの新機能など。
- ^ 実際にはMMRの有効/無効に関わらずメモリアクセスがノーウェイトで行われる。
- ^ 基板上のジャンパピンをはずすことによって有効になる。
出典
- ^ 「富士通、パソコン3機種を開発―1月から月産計3万台、半導体の社内販売急増へ」『日経産業新聞』 1982年11月9日、4面。
- ^ a b 小林紀興『富士通の大逆襲計画』講談社、1987年、95頁。ISBN 4061928074。
- ^ a b ASCII 1983年1月号, p. 82.
- ^ ASCII 1983年1月号, p. 83.
- ^ 『年鑑広告キャンペーン 1983』222-223頁。NDLJP:12022603/114
- ^ フジツウ・エスパーニャ (FESA) 同窓会
- ^ Fujitsu / Secoinsa FM-7
- ^ Fujitsu FM-7 (Fujitsu Micro 7)
- ^ a b 富士通 FM-7 ユーザーズマニュアル システム解説書
- ^ ASCII 1983年7月号, p. 158.
- ^ a b c d ASCII 1983年7月号, p. 161.
- ^ ASCII 1983年7月号, p. 160.
- ^ 受賞番号:59K1044(受賞対象:FM-77D2(MB-25250))
- ^ FM77 | クラシックPC研究会
- ^ 『コンピュートピア』1989年5月号、16頁。NDLJP:3250143/9 - 原文では「FM77シリーズ」表記だが、昭和60年に販売とある。
参考文献
- 「ASCII 1983年1月号」第7巻第1号、株式会社アスキー出版、1983年1月1日。
- 「ASCII 1983年1月号」第7巻第7号、株式会社アスキー出版、1983年7月1日。
関連書籍
- 「FM-7/8活用研究」 工学社 1983年。
- 「Oh!FM」日本ソフトバンク。
関連項目
外部リンク
FM-7
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 07:04 UTC 版)
FM-7は1982年11月8日、FM-8の廉価版後継機種として発売された。開発時の名称はFM-8Jr.(ジュニア)。FM-8と一定の互換性があり、アプリケーション、OS(CP/M、FLEX、UCSD Pascal、OS-9)、開発言語、ツール、周辺機器の資産継承が考慮されていた。FM-8を含んで、FM-7/8シリーズと呼ばれ、CPUの高速化等、実質的にはFM-8の性能が向上した後継機にあたる。 モトローラ社のMPU 68B09をメインCPUとグラフィックを独立制御するディスプレイサブシステムへそれぞれ搭載する2CPUのアーキテクチャを採用。FM-8と同様にオプションのZ80カードが搭載可能になっており、CP/Mや、Oh!Xで使われたS-OS"SWORD"など、Z80CPUベースのシステムを動作させることも可能になっている。このZ80カード用スロットは後にユーザベースで63C09を搭載するのにも使われた。F-BASIC V3.0がROMに搭載されている。漢字ROMカード、フロッピーディスクドライブはオプション。 発売当初のイメージキャラクターはタモリ。キャッチコピーは「青少年は興奮する」。 競合機種と同等のカラー表示にPSGがつき価格が安かったことから、FM-7は一定の普及をみて、富士通をパソコン御三家の地位にまで押し上げた。FM-7に端を発する低価格・高性能という路線はPCユーザ拡大に貢献し、'80年代パソコンブームの原動力となった。 FM-7が販売面で成功したのは本体価格が126,000円という低価格にも関わらず、当時の最新機能を盛り込み1クラス上のPCに匹敵または凌駕する性能を備えていたことにある。同時期の人気機種は、NEC PC-8801(228,000円)、PC-9801(298,000円)、日立 ベーシックマスターレベル3(298,000円、後に価格改定)。学生を中心に人気があった「パピコン」ことNEC PC-6001(89,800円)やコモドールVIC-1001(69,800円)などの初心者PCのユーザー層にも大きな影響を与え、その成功から、FM-7を引き継ぐ形で、後継機が完全上位互換で作られていく形になる。 FM-8から引き続き、広いメモリ領域とVRAM領域の確保と処理速度向上のためにメイン(演算部)、サブ(グラフィック部)に独立した6809を搭載する贅沢なアーキテクチャを採用した。FM-8を祖とするこの設計は、マルチCPUとしてではなく、ホストCPUとグラフィック端末(現代で言えばGPU)の関係にあり、サブCPUに処理の大きな表示周りの作業をさせることによるメインCPUの負担を軽減することに目的があった。また、このグラフィックスサブシステムの実装では、キャラクターコードをハードウェア的にフォントに展開するテキストVRAMを持たなかったため、ハードウェアによるスクロールが使えない画面モードでは、当時の処理速度と比較して広大なグラフィックVRAMを再描画する必要があり、リスト表示などでのスクロールのもたつきや、カーソルを移動するとその通り道にあったグラフィックも消えてしまうという制限も引き継いでいる。また、リアルタイムゲームが流行すると両システム間の転送容量に制限やタイムラグがあったこと、キーボードのスキャンを専用CPUに任せ、チャタリング除去なども行っているためにBREAK以外のキーでは押下した結果しか認識できず、ユーザの間ではリアルタイムゲーム向きではないとされ、議論になった。前述のとおり、任意のコードの実行を想定して設計されているわけではないサブシステムではあったが、サブシステムモニタ開発時、デバッグ用に実装されたメンテナンスコマンドの利用や、そのノウハウの蓄積、後述する内部技術資料の積極的な公開により、サブシステムで任意のプログラムを実行することで、描画の高速化や、高速にデータを転送するテクニックなどが考案され、ハードウェア的なキー入力の制限を除けば、競合機種と同等のゲームが発売されるようになっていった。 他社と同様、富士通も本体添付品や別売マニュアルという形でBIOS、I/Oアドレス、ファームウェア、システムコマンド等を積極的に公開した。また富士通の支援により、FMシリーズ専門誌『Oh!FM』(日本ソフトバンク、後の『Oh!FM TOWNS』)をはじめとして、技術評論社や工学社などから『活用マニュアル』などと呼ばれる良質なリファレンスマニュアルが多く出版された。またショウルームやサポートセンター経由では、内部技術資料なども必要に応じて比較的簡単に入手できた。 回路設計の問題としては、同等の音源を搭載した他機種に比較して、サウンド出力にデジタル回路からリークしたノイズも多く、音割れも見られた。 1985年、スペインのSECOINSA社という富士通に近い会社より FM-7 が販売されている。
※この「FM-7」の解説は、「FM-7」の解説の一部です。
「FM-7」を含む「FM-7」の記事については、「FM-7」の概要を参照ください。
- FM7のページへのリンク