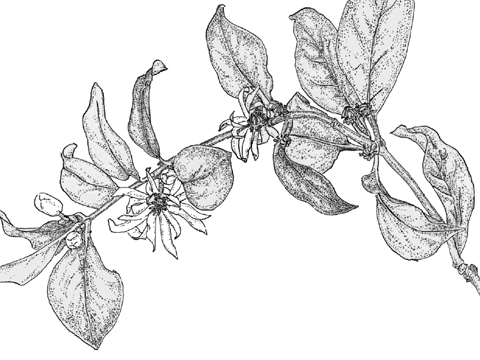シキミ
しきみ (樒)






●わが国の本州、東北地方南部以南から四国・九州それに済州島や台湾、中国に分布しています。山地の林内に生え、高さは2~5メートルになります。よく分枝して、長楕円形の葉は互生します。枝や葉には香りがあり、「抹香臭い」という言葉の語源になっています。また、全草にアニサチンなどの有毒成分が含まれるため「悪しき実」とされ、名前のいわれになっています。3月から4月ごろ、葉腋に淡黄色の花を咲かせます。果実は集合果で、秋に熟します。
●シキミ科シキミ属の常緑小高木で、学名は Illicium religiosum。英名は Japanese anise, Japanese star anise。
| シキミ: | 樒 |
シキミ
(樒 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/12 13:35 UTC 版)
| シキミ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|
||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||
| Illicium anisatum L. (1759)[1] | ||||||||||||||||||
| シノニム | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||
| シキミ (樒[3][4][5]、梻[3]、櫁木[6]、木密[3]、之伎美[7])、シキビ (櫁、嬥)[8][9][10]、コウノキ (香木)[11]、コウシバ (香柴)[12]、コウノハナ[8]、タコウボク (多香木)[13]、マッコウ[8]、マッコウギ[8]、マッコウノキ[8]、マッコー[14]、マッコーギ[14]、ヤマグサ (山草)[15]、ハバナ (葉花)[16]、ハカバナ[8]、ブツゼンソウ (仏前草)[17]、ホトケバナ (仏花)[18]、ハナシバ (花柴)[19]、ハナノキ (花木、花の木)[20][21]、ハナサカキ (花榊)[22]、ハナ (花、華、英)[23][24][25] | ||||||||||||||||||
| 英名 | ||||||||||||||||||
| Japanese star anise[26], aniseedtree[26], sacred anisetree[26] |
シキミ(樒、梻、学名: Illicium anisatum) は、マツブサ科シキミ属に分類される常緑性小高木から高木の1種である。葉は枝先に集まってつき、春に枝先に多数の黄白色の花被片をもつ花をつける(図1)。本州(宮城・石川県以西)から沖縄諸島および済州島に分布する。アニサチンなどの毒を含み、特に猛毒である果実が中華料理で多用される八角に似ているため、誤食されやすい危険な有毒植物である。ときに仏事や神事に用いられ、しばしば寺院や墓地に植栽されている。また材や抹香、線香として利用されることもある。別名は「シキビ」「ハナノキ」「ハナシバ」「ハカバナ」「ブツゼンソウ」「コウノキ」「コウシバ」「コウノハナ」「マッコウ」「マッコウギ」「マッコウノキ」など。
特徴
常緑の小高木であり、高さはふつう2~5mだが、ときに10m以上の高木になる[27][4]。日本海側では高さ3m以下であることが多い[28]。材は散孔材、道管は直径50µm以下で、単独または数個が接線方向に複合する[29]。樹皮は帯黒灰褐色でやや平滑、若枝は緑色[27]。
葉は互生するが、枝先に集まってつく[27][4]。葉柄は長さ5~24mm、葉身は倒卵状長楕円形から倒披針形、10~60cm、葉先は急鋭頭、葉脚は広いくさび形、中央脈以外の葉脈(側脈5~8対)は不明瞭[27][4][30]。葉の表面は濃緑色で光沢があり、裏面は灰緑色、表裏とも無毛、厚く革質、葉を透かすと油点が見え、傷つけると抹香に似た匂いを出す[4][27][30]。葉芽は長卵形 (下図2c)、花芽は球形 (下図2f)[4]。
花期は3月から5月、ソメイヨシノの開花よりも早い春彼岸のころに、葉腋から短い花柄を出して黄緑色を帯びた白色の花が咲き、ときに枝先にまとまってつく[4][5][27][31]。花は直径2.5~3cm、花柄は長さ5~35mm[4][27][30]。花被片はらせん状につき、12~28枚、萼片と花弁の明瞭な分化は見られないが、外側のものはやや幅広くて短い楕円形、内側のものは細長い線状長楕円形(長さ10~25mm)で多少波状によじれる[4][8][27][注 1]。雄しべは15~28個がらせん状につき、長楕円形、葯と花糸はほぼ同長[8][27]。雌しべは離生心皮からなり、7~10個が1輪につく[8][27]。
果期は9月から10月、8個ほどの袋果が側面で合着しており、8角形から星形、直径2~3cm[5][27][4]。各袋果 (心皮) は12~18×6~10×3~6mm[27]。果実は木質化し、裂開した後に乾燥によって幅が狭くなって種子をはじき飛ばし、また動物によっても散布される[32][33][34] (下記参照)。種子は光沢がある黄褐色、やや扁平な楕円形、長さ 6 - 8.5 mm[27][4]。
染色体数は 2n = 28[27]。葉緑体DNAの塩基配列が報告されている[35]。
毒性

葉や茎、根、花、果実、種子など全体が有毒である[8][4][36]。なかでも果実、種子は毒性が強く、食用にすると死亡する可能性がある[27][37][38]。実際、八角との誤認による事故が多いため、シキミの果実は植物としては唯一毒物及び劇物取締法により劇物に指定されている[39]。中毒症状は、嘔吐、腹痛、下痢、痙攣、意識障害などがあり、昏睡状態に陥り、最悪の場合死に至る可能性もある[40][41][42]。有毒成分は神経毒であるアニサチン (anisatin) やネオアニサチン (neoanisatin) である[43] (下記参照)。
同じシキミ属に属するトウシキミ(Illicium verum; 日本には自生していない)は毒成分を含まず、果実は八角、八角茴香(はっかくういきょう)、大茴香(だいういきょう)、スターアニスとよばれ、香辛料や生薬として利用される[44][45]。シキミの果実は形態的に非常によく似ているため、シキミの果実をトウシキミの果実と誤認して食用にすることで中毒を起こす事故が多発している[35][38][40][41]。そのため、シキミの果実は「毒八角」ともよばれる[46]。トウシキミの果実とくらべると、シキミの果実はやや小型で先端が鋭く尖り、また抹香の匂いがする点でも異なる[38]。第二次世界大戦以前、シキミの果実を実際に「日本産スターアニス」として出荷し海外で死亡事故などが発生した事例がある[40][47]。また、シキミの種子はシイの実にやや似ているため、誤って食用にして集団食中毒を起こした例がある[48]。
また、シキミは人間以外の動物に対しても有毒である。平成12年3月には、黒毛和種の繁殖牛を飼育する農家で、シキミが混ざった木の枝を気づかずに敷料として使用したところ、5頭の牛が痙攣などの神経症状を示し、そのうち3頭が死亡するという中毒が起きている。解剖の結果、死んだ牛の胃からシキミの葉が確認されており、敷料の残りのシキミ葉から抽出した液体をマウスに投与したところ神経症状が現れたため、シキミによる中毒と診断された[49]。また、シキミはニホンジカの食害を受けにくく、不嗜好性植物リストにも掲載されている[50]。ただし、安芸の宮島のサルは、シキミの種子を食べるという[51]。また後述のように、ヤマガラやヒメネズミはおそらくシキミの種子を食用としている[32]。
成分
アニサチン

シキミの毒成分は1881年にヨハン・エイクマンによって初めて研究されたが、その後1952年にLaneらによってセスキテルペンであるアニサチンが単離された[52]。アニサチンは神経伝達物質であるGABAに拮抗作用を示す神経毒であり、植物毒としては最強のものの1つである[43]。またアニサチン関連物質として、ネオアニサチンやプソイドアニサチン (pseudoanisatin)、2α-ヒドロキシネオアニサチンがシキミから報告されている[43]。
シキミ酸

1885年、ヨハン・エイクマンによってシキミの果実から環状ヒドロキシ酸が発見され、シキミ酸と名付けられた[53][54]。シキミの果実には乾燥重量の25%、葉には0.5%のシキミ酸が含まれるという[54]。その後の研究で、ほとんどの植物において、シキミ酸を中間産物として芳香族アミノ酸を生合成していることが判明し、この生合成経路はシキミ酸経路とよばれている[54]。シキミ酸経路は植物における重要な二次代謝経路であり、アルカロイド、フェニルプロパノイド、フラボノイド合成に関わっている[55]。シキミ酸は、シキミ属(トウシキミなど)のほか、コンフリーやイチョウにも多く含まれることが報告されている[56]。シキミ酸は、インフルエンザ薬であるオセルタミビル (商品名タミフル) の原料となる (シキミ酸自体にはその効果はない)[57]。
精油

シキミは精油を含み、葉や樹皮には芳香がある。シキミの葉から得られる精油の主成分として、1,8-シネオール、サフロール、リナロール、ミリスチシンなどが報告されている[58]。
分布・生態

本州(宮城県、石川県以西)、四国、九州、屋久島、種子島、トカラ列島、奄美大島、徳之島、沖縄島、慶良間諸島、韓国・済州島の暖温帯域に分布する[2][4][27][59][60][61][62]。石垣島、西表島、台湾には同属のヤエヤマシキミが分布している[27][60]。
果実・種子は有毒であるが、ヤマガラやヒメネズミがシキミの種子を収穫・輸送・貯蓄して種子散布に寄与していることが示唆されている[32][63]。
ときに植生を区分する標徴種となり、日本の植物群落名としてシキミ-アカガシオーダー (カクレミノ-スダジイオーダーの異名とされる) やシキミ-モミ群集(サカキ-ウラジロガシ群集の異名とされる)、オキナワシキミ-スダジイ群集がある[64]。また、次節の記述の通り仏事に関係が深く、寺社や墓地によく植栽されている[27][4]。
人間との関わり
利用
シキミは仏事に広く使われ、関西地方ではしばしば仏前や墓前に供えられる[8][65][28][44][66]。また精油を含んだ葉や樹皮は、抹香や線香の原料として利用される[8][4][59][28][67]。これらは、シキミが毒性と独特の香りを持つため、邪気を払う力があると考えられていたことに由来する[66]。
墓地に多く植えられているのは、シキミの葉が発する強い香りで死臭を消したり、害獣を忌避したのが起源とされる[68]。古くは、遺体を土葬した墓の周りにオオカミなどの害獣が嫌うシキミを植えることで、屍を守ったともされる[69][5]。また新しい墓や畑に植えて害を防ぐこともある[28]。墓に植えたシキミが成長することは、死者が冥界で幸福であるしるしと見ることもある[28]。

死者の枕元に供える花を「一本花(いっぽんばな)」というが、これにはふつうシキミが用いられる[70][注 2]。死水をとる際には、このシキミの葉に水をつけてとる[20]。また納棺では、棺にシキミの葉などが敷き詰められた[5]。熊野では、死者の霊魂が手向けられたシキミの葉を手に阿弥陀寺に参詣し鐘をつくと伝承されており、この鐘は「亡者の一つ鐘」とよばれる[71] (図6a)。阿弥陀寺がある妙法山は、樒山(しきみやま)ともよばれる[72]。他にも、散華においてシキミの花や葉が使われたり[73]、閼伽にシキミの花 (閼伽の花) を浮かべることがある[74]。また葬儀にシキミ (樒) が飾られていたことに由来して、参列者の名を書いた紙や板は、紙樒や板樒とよばれる[66]。
シキミは古くから仏事に関わってきた。『真俗仏事編』(1728年)には
| 「 | 」 |
とあり、鑑真が日本にもたらしたとしている[44]。ただしシキミはインドには自生せず、日本では『万葉集』にも詠われ、また洪積世から種子が出土することから、日本の自生種と考えられている[29][44]。また、空海が青蓮華の代用として花が似ているシキミを密教の修法に使ったともされる[75]。密教では、葉を青蓮華の形にして六器に盛り、護摩の時は房花に用い、柄香炉としても用いる[要出典]。
上記のように、現在ではシキミは仏事に広く用いられ、一方で神事にはふつうサカキ(モッコク科)が用いられている。しかし平安時代以前には、シキミは神事にも盛んに用いられていたと考えられている[5][65]。平安時代の神楽歌の中に「榊葉の香をかぐわしみ求めくれば」とあるが、サカキには強い香りがないことから、シキミも神事用に使われ、榊とよばれていたと考えられている[28][76][77]。シキミは仏事、サカキは神事と分かれたのは仏教が一般化した平安時代から中世以降であり[28][65]、明治時代に神仏分離令が出てから、庶民の間でもこの傾向が広まったとされる[5]。

現在でもシキミが神事に用いられている例があり、京都市の愛宕神社ではシキミを神木として神事に使用している[28][44]。平安時代中期には
| 「 |
愛宕山 しきみが原に 雪積り 花摘む人の 跡だにもなし
|
」 |
—曽禰好忠 |
||
と詠まれており、愛宕神社のある樒原(しきみがはら、右京区宕陰地区)は古くからシキミの名所であったと考えられている[44]。近世になると愛宕は火除けの神としての信仰を集め、これがシキミと結びついて火伏の護符とシキミの枝がセットで扱われている[66][78]。
門松にはふつうマツやタケが使われるが、愛知県北設楽郡などでは、シキミが用いられることがある[28][79]。また、事八日や節分に鬼を脅すために飾るものを「鬼威し」(おにおどし)とよび、ふつうはヒイラギ (モクセイ科) が用いられるが、シキミが使われることもある[80]。これは、三方ヶ原の戦いに破れて浜松城に逃げ込んだ徳川家康が折からの節分にヒイラギがなかったため、シキミを代用したことに由来するとの伝承がある[3]。
このようにシキミは仏事などに広く利用されているため、商用に栽培されている[81][82]。2016年では、日本全体での生産量は1,875t、そのうち上位5県は鹿児島県で537.3トン、宮崎県で340.3t、静岡県で289.4t、愛媛県で232.9t、高知県で191.4tであった[83]。
シキミは寺院や墓地に植えられることが多く、家庭の庭に植えることは嫌われることがあるが[28]、庭木として栽培されることもある[84]。枝葉が密生し、萌芽性がよいため刈り込んで生け垣として利用できる[84]。やや湿り気のある半日陰地を好む[84]。園芸品種として、'Murasaki-no-sato'、'Pink Stars'、'Variegata' などがある[85]。病虫害としては、クスアナアキゾウムシ、シキミグンバイムシ、コミカンアブラムシ、アオバハゴロモ、シキミタマバエ、ハマキガ類、フシダニ類、炭疽病、すす病などがある[84][82][86]。
シキミの材は心材が淡紅褐色で気乾比重は約0.67、サカキやツバキの材に似て緻密で粘りが強くて割れにくく、細工物 (ろくろ細工、寄木細工、象嵌細工)、傘の柄、数珠、樽などさまざまな用途で用いられる[3][8][28][29][5]。またシキミの材は、木炭や薪にも使われる[8][29]。樹皮からは繊維がとれる[28]。
シキミの果実は食べると死に至るほどの猛毒であるが、その毒性を利用してシキミを煎じた液を牛馬の皮膚寄生虫駆除のために塗布することがあり[41][5]、また殺虫剤に使われることもある[28]。いぼや眼病に、シキミを浸した水をつける民間療法もある[28]。他にも船酔い避けにシキミの葉をへそに乗せるとよい、シキミの木でできた天秤棒は肩が痛まない、病人の布団の下にシキミの枝を入れておくと治る、などの伝承もある[28]。
文化
先述の通り、シキミは古くから日本人になじみの深い植物であり、『万葉集』をはじめ、いくつかの和歌集で詠まれている。
奥山の しきみが花の 名のごとや しくしく君に 恋ひわたりなむ—『万葉集』巻20-4476
しきみおく あかのをしきの ふちはなく 何にあられの 玉と散らまし—『山家集』下
あはれなる しきみの花の契かな ほとけのためと 種やまきけん—『夫木和歌抄』
また、『枕草子』や『源氏物語』にも登場し、前者ではその香りが称賛されている。
帯うちして、拝み奉るに、「ここに、つかうさぶらふ」とて、しきみの枝を折りて持て来たるは、香などのいと尊きもをかし。—『枕草子』116段
濃き青鈍の紙にて、しきみにさしたまへる、例のことなれど、いたく過ぐしたる筆づかひ、なほ古りがたくをかしげなり。—『源氏物語』若菜下の巻
花活に 樒の花の 淋しいぞ—鬼城
シキミの花言葉は「援助」、「甘い誘惑」、「猛毒」[88]。
名称
シキミの学名はリンネが命名した Illicium anisatum であり、種小名の anisatum は香辛料となるアニスの香りに似ていることを意味する[33]。シノニム(同物異名)としてシーボルトが命名した I. japonicum や I. religiosum(religiosum は、「宗教的な」を意味するラテン語) などがある(右上分類表のシノニム欄参照)[2]。
和名の「シキミ」の語源については諸説ある。四季を通して美しいことから「四季美」[89]、または四季を通して芽をつけることから「四季芽」[90]に由来するともされる。その他に、実の形から「敷き実」とする説、多数の種子をつけることから「重く実」(しげくみ)とする説、香りが強いことから「臭しき実」(くしきみ)とする説、あるいは有毒で「悪しき実」とする説などがある[27][4][44][76][90][91]。ただし、上代では「実」が乙類の仮名で記されているのに対し、「しきみ」の「み」は甲類の仮名で表記されている[3]。
別名が多く、精油を含み枝葉を切ると香気が漂うため、コウノキやコウノハナ、コウシバ、抹香の原料となるためマッコウやマッコウギ、マッコノキともよばれる[8]。また墓や仏に供えられることが多いため、ハナノキ[注 3]、ハバナ、ハカバナ、ブツゼンソウ、ホトケバナなどともよばれる(右上分類表の和名欄参照)。単に「ハナ (花、華、英)」といった場合も、シキミを意味することがある[23][24][25]。
和歌山県伊都郡かつらぎ町花園[75][93]や滋賀県大津市の花折峠[94]の地名にある「花」は、シキミを意味している。かつらぎ町花園は古くは高野山領であり、供花である花 (シキミ) を産する場所として花園荘とよばれ、これが現在の地名に引き継がれている[93]。大津市の花折峠の名は、これより北にはシキミが生育しないため、京からの帰り道にシキミを折って故郷へ持ち帰ったとする故事に由来するとされる[33]。
山口県の一部では、シキミの果実を「おしゃり」(
中国では莽草 (拼音: mǎngcǎo)、厳密には日本莽草(拼音: rìběn mǎngcǎo)と呼ばれている。生薬としては日本でも「
保全状況評価
上記のようにシキミは比較的広く見られる植物であり、現在では広く栽培もされているが、山採りしたものが仏事用に売られていたため、絶滅した地域もある[28]。シキミは日本全体としては絶滅危惧等に指定されていないが、下記のように地域によっては絶滅危惧種等に指定されている[95]。
また鹿児島県では、変種のオキナワシキミ (下記参照) が準絶滅危惧種に指定されている[96]。
分類
沖縄諸島のものは葉が細く、変種オキナワシキミ (Illicium anisatum var. masa-ogatae (Makino) Honda, 1939) とされることがあるが、区別は難しい[27][97][98]。また八重山列島から台湾には、同属のヤエヤマシキミが分布している[27][60]。
また花被片の色が淡紅色のものは、品種ウスベニシキミ (Illicium anisatum f. roseum (Makino) Okuyama, 1955) とされることがある[27][99]。
ギャラリー
-
花
-
果実
-
植物画
脚注
注釈
出典
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003- エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “シキミ”. BG Plants 和名-学名インデックス(YList). 2021年7月15日閲覧。
- ^ a b c d e f g h “Illicium anisatum”. Plants of the World online. Kew Botanical Garden. 2021年7月23日閲覧。
- ^ a b c d e f g h 「樒・梻」『精選版 日本国語大辞典』。コトバンクより2021年7月25日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 勝山輝男 (2000). “シキミ”. 樹に咲く花 離弁花1. 山と渓谷社. p. 391. ISBN 4-635-07003-4
- ^ a b c d e f g h i j 田中潔 2011, p. 18.
- ^ 「櫁木」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「之伎美」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p 「シキミ」『日本大百科全書 (ニッポニカ)』。コトバンクより2021年7月24日閲覧。
- ^ 「嬥」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「櫁」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「香木」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「香柴」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月25日閲覧。
- ^ 「多香木」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^ a b “16350 シキミ”. 奄美群島生物資源Webデータベース. 2021年7月23日閲覧。
- ^ 「山草」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「葉花」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「仏前草」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「仏花」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「花柴」『精選版 日本国語大辞典』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ a b 「シキミ(樒)」『世界大百科事典』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「花木」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ 「花榊」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ a b 「花」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ a b 「華」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ a b 「英」『動植物名よみかた辞典 普及版』。コトバンクより2021年7月28日閲覧。
- ^ a b c GBIF Secretariat (2021年). “Illicium anisatum”. GBIF Backbone Taxonomy. 2021年7月23日閲覧。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v 大橋広好 (2015). “シキミ属”. In 大橋広好、門田裕一、邑田仁、米倉浩司、木原浩. 改訂新版 日本の野生植物 1. 平凡社. pp. 49-50. ISBN 978-4582535310
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 植田邦彦, 堀田満, 星川清親, 緒方健, 新田あや, 飯島吉晴 (1989). “シキミ属”. In 堀田満ほか. 世界有用植物事典. 平凡社. pp. 550–551. ISBN 9784582115055
- ^ a b c d 伊東隆夫「日本産広葉樹材の解剖学的記載II」『木材研究・資料』第32巻、京都大学木質科学研究所、1996年12月、66-176頁、 ISSN 02857049、 NAID 110000214340。
- ^ a b c 馬場多久男 (1999). “シキミ”. 葉でわかる樹木 625種の検索. 信濃毎日新聞社. p. 172. ISBN 978-4784098507
- ^ a b 西田尚道監修 学習研究社編 2009, p. 54.
- ^ a b c “猛毒のシキミ種子を運ぶ動物がいた”. 森林総合研究所 (2018年3月2日). 2021年7月23日閲覧。
- ^ a b c 植田邦彦 (1997). “シキミ”. 週刊朝日百科 植物の世界 9. p. 28. ISBN 9784023800106
- ^ 小林正明 (2007). 花からたねへ 種子散布を科学する. 全国農村教育協会. p. 223. ISBN 978-4881371251
- ^ a b Park, J., Kim, Y. & Xi, H. (2019). “The complete chloroplast genome of aniseed tree, Illicium anisatum L.(Schisandraceae)”. Mitochondrial DNA Part B 4 (1): 1023-1024. doi:10.1080/23802359.2019.1584062.
- ^ かざまりんぺい・えひまかみつる (2004). 完全図解冒険図鑑 大冒険術. 誠文堂新光社. p. 67. ISBN 4-416-80502-0
- ^ 中沢与四郎, 岳中典男, 酒井潔, 松永行雄, 岡武, 貞松繁明, 河野信助「シキミ有毒成分の分離,含有量並に毒性の検討」『日本薬理学雑誌』第55巻第3号、日本薬理学会、1959年、524-530頁、doi:10.1254/fpj.55.524、 ISSN 0015-5691、 NAID 130000756106。
- ^ a b c 東京都薬用植物園. “トウシキミ(八角)とシキミ(有毒)”. 東京都健康安全研究センター. 2021年7月23日閲覧。
- ^ 毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第1項第39号「しきみの実」
- ^ a b c 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 (2012年12月7日). “シキミ”. 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構. 2013年4月15日閲覧。
- ^ a b c “シキミ”. 熊本大学薬学部 薬草園 植物データベース. 2021年7月23日閲覧。
- ^ “シキミ”. 食品衛生の窓. 東京都福祉保険局. 2021年7月23日閲覧。
- ^ a b c 丹羽治樹 & 山田静之「植物神経毒アニサチンの合成」『ファルマシア』第27巻第9号、1991年、924-927頁、doi:10.14894/faruawpsj.27.9_924。
- ^ a b c d e f g h 村上守一 (2018). “表紙について”. (公社) 富山県薬剤師会広報誌 富薬 40 (4).
- ^ 「ダイウイキョウ」『日本大百科全書 (ニッポニカ)』。コトバンクより2021年7月29日閲覧。
- ^ 「毒八角」『中日辞典 第3版』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^
「 」 - ^ 岩部幸夫「シキミの実による食中毒」『食品衛生学雑誌』第32巻第5号、日本食品衛生学会、1991年、472-474頁、doi:10.3358/shokueishi.32.472、 ISSN 0015-6426、 NAID 130003693059。
- ^ 小林弘明, 久保田泰徳, 山田博道, 保本朋宏, 沖田美紀, 平田晴美, 金森久幸, 豊田安基江 (2011年6月17日). “黒毛和種繁殖牛におけるシキミ中毒”. 2025年8月6日閲覧。
- ^ 橋本佳延 & 藤木大介「日本におけるニホンジカの採食植物・不嗜好性植物リスト」『人と自然』第25巻、2014年、133-160頁、doi:10.24713/hitotoshizen.25.0_133。
- ^ 金井塚務『宮島の植物誌』東洋書店、1998年、103頁。 ISBN 4885952204。
- ^ Lane, J. F., Koch, W. T., Leeds, N. S. & Gorin, G. (1952). “On the toxin of Illicium Anisatum. I. The isolation and characterization of a convulsant principle: anisatin”. Journal of the American Chemical Society 74 (13): 3211-3215. doi:10.1021/ja01133a002.
- ^ Enrich, L. B., Scheuermann, M. L., Mohadjer, A., Matthias, K. R., Eller, C. F., Newman, M. S., ... & Poon, T. (2008). “Liquidambar styraciflua: a renewable source of shikimic acid”. Tetrahedron Letters 49 (16): 2503-2505. doi:10.1016/j.tetlet.2008.02.140.
- ^ a b c 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “シキミ酸”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 564. ISBN 978-4000803144
- ^ 後藤英司「「植物環境工学の研究展望」(第四回) 環境ストレスと二次代謝」『植物環境工学』第31巻第1号、2019年、7-20頁、doi:10.2525/shita.31.7。
- ^ Bochkov, D. V., Sysolyatin, S. V., Kalashnikov, A. I. & Surmacheva, I. A. (2012). “Shikimic acid: review of its analytical, isolation, and purification techniques from plant and microbial sources”. Journal of Chemical Biology 5 (1): 5-17. doi:10.1007/s12154-011-0064-8.
- ^ 大平浩輝, 鳥居直太, 渡邉賢, Richard Smith「熱水を用いた八角からのシキミ酸の抽出」『化学工学会 研究発表講演要旨集』2007f化学工学会第39回秋季大会、化学工学会、2007年、627-627頁、doi:10.11491/scej.2007f.0.627.0、 NAID 130005040143。
- ^ 藪内弘昭, 橋爪崇, 石原理恵, 河島眞由美, 石井光代 (2019). “未利用資源を虫よけ剤に活用するための研究 -人工知能を用いた虫よけ植物スクリーニング手法の開発-”. 平成30年度和歌山県工業技術センター研究報告 28: 25-27.
- ^ a b 林弥栄『日本の樹木』(増補改訂新版)山と溪谷社〈山溪カラー名鑑〉、2011年11月30日、200頁。 ISBN 978-4635090438。
- ^ a b c 琉球の植物研究グループ (2018 onward エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “「琉球の植物」データベース”. 国立科学博物館. 2021年8月1日閲覧。
- ^ 林将之『樹木の葉 実物スキャンで見分ける1100種類』(山溪ハンディ図鑑14)山と溪谷社〈山溪カラー名鑑〉、2014年4月15日、91頁。 ISBN 978-4635070324。
- ^ 鈴木時夫 (1962). “モミ-シキミ群集について”. 日本生態学会誌 12 (3): 120. doi:10.18960/seitai.12.3_120_3.
- ^ Yoshikawa, T., Masaki, T., Motooka, M., Hino, D., & Ueda, K. (2018). “Highly toxic seeds of the Japanese star anise Illicium anisatum are dispersed by a seed-caching bird and a rodent”. Ecological Research 33 (2): 495-504. doi:10.1007/s11284-018-1564-6.
- ^ 村上雄秀, 中村幸人 & 鈴木伸一 (2016). “日本の森林植生の群落体系の整理 ―常緑広葉樹林 (ヤブツバキクラスほか); 2016年版―”. 生態環境研究 23 (1): 9-21. doi:10.24600/ecohabitat.23.1_9.
- ^ a b c 萩原秀三郎 (1997). “シキミの民俗”. 週刊朝日百科 植物の世界 9. p. 28. ISBN 9784023800106
- ^ a b c d “葬儀で使われる樒(しきみ)について”. お葬式用語解説. いい葬儀 (2021年4月20日). 2021年7月24日閲覧。
- ^ 「抹香」『世界大百科事典 第2版』。コトバンクより2021年7月24日閲覧。
- ^ 平野隆久監修 永岡書店1997, p. 242.
- ^ 牧野富太郎 (1956). 牧野植物一家言. 北隆館. pp. 129. ASIN B000JB28TQ
- ^ 「一本花」『精選版 日本国語大辞典』。コトバンクより2021年7月25日閲覧。
- ^ 鈴木正崇 (2019). “日本人にとって山とは何か ―自然と人間、神と仏―”. ヒマラヤ学誌 20: 54-62. doi:10.14989/HSM.20.54.
- ^ “四 季 彩 々 2018”. 熊野妙法山 阿彌陀寺. 2021年7月30日閲覧。
- ^ 「散華」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^ 「閼伽」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^ a b 仁井田好古 (編)『紀伊続風土記』高野山之部 (1839)
- ^ a b 木下武司 (2017). 和漢古典植物名精解. 和泉書院. ISBN 9784757608191
- ^ 「サカキ」『百科事典マイペディア』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^ 八木透「愛宕をめぐる民俗信仰」『アジア宗教文化情報研究所報』第1号、アジア宗教文化情報研究所報、2004年3月、9頁、 NAID 120007023011。
- ^ 「門松」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^ 「鬼威し」『デジタル大辞泉』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^ “熊野の山で夫婦が栽培する「仏前草」-シキミ”. 社団法人 日本森林技術協会. 2021年7月29日閲覧。
- ^ a b “シキミの栽培技術指針 -仁淀川流域-” (PDF). 高知県 中央西林業事務所 森林技術センター. 2021年7月29日閲覧。
- ^ “木ろう、竹皮、しきみ、さかきの生産量・面積”. e-Stat. 2022年7月20日閲覧。
- ^ a b c d “シキミ”. みんなの趣味の園芸. NHK出版. 2022年7月29日閲覧。
- ^ “Illicium anisatum”. The North Carolina Extension Gardener Plant Toolbox. 2021年7月30日閲覧。
- ^ “シキミの栽培技術指針 -仁淀川流域-” (PDF). 高知県 中央西林業事務所 森林技術センター (2013年4月). 2021年7月29日閲覧。
- ^ 「樒」『デジタル大辞泉』。コトバンクより2021年7月24日閲覧。
- ^ GreenSnap編集部 (2020年8月24日). “樒(シキミ)の花言葉”. GreenSnap. 2021年7月30日閲覧。
- ^ 山田隆彦 (2021). 自然散策が楽しくなる! 葉っぱ・花・樹皮で見わける 樹木図鑑. 池田書店. pp. 85. ISBN 978-4262136349
- ^ a b “樒(シキミ)”. 補陀洛山 千手院. 2021年7月30日閲覧。
- ^ “シキミ(シキビ, ハナノキ, ハナシバ)”. 植物図鑑. 筑波実験植物園. 2021年7月24日閲覧。
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003- エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “ハナノキ”. BG Plants 和名-学名インデックス(YList). 2021年7月27日閲覧。
- ^ a b 「花園(和歌山県)」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2022年7月24日閲覧。
- ^ 「花折峠」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』。コトバンクより2021年7月30日閲覧。
- ^ “シキミ”. 日本のレッドデータ 検索システム. 2022年7月28日閲覧。
- ^ “オキナワシキミ”. 日本のレッドデータ 検索システム. 2022年7月28日閲覧。
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003- エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “オキナワシキミ”. BG Plants 和名-学名インデックス(YList). 2021年7月27日閲覧。
- ^ 新里孝和, 諸見里秀宰「与那演習林の植物 (I) : 1. 樹木目録(林学科)」『琉球大学農学部学術報告』第19号、琉球大学農学部、1972年12月、503-557頁、 ISSN 03704246、 NAID 110000220412。
- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003- エラー: 日付が正しく記入されていません。(説明)). “ウスベニシキミ”. BG Plants 和名-学名インデックス(YList). 2021年7月27日閲覧。
参考文献
- 田中潔『知っておきたい100の木:日本の暮らしを支える樹木たち』主婦の友社〈主婦の友ベストBOOKS〉、2011年7月31日、18頁。 ISBN 978-4-07-278497-6。
- 西田尚道監修 学習研究社編『日本の樹木』 5巻、学習研究社〈増補改訂 ベストフィールド図鑑〉、2009年8月4日、54頁。 ISBN 978-4-05-403844-8。
- 平野隆久監修 永岡書店編『樹木ガイドブック』永岡書店、1997年5月10日、242頁。 ISBN 4-522-21557-6。
関連項目
外部リンク
- シキミの標本 国立科学博物館標本・資料統合データベース
- “シキミ”. 三河の植物観察. 2021年7月24日閲覧。
- “シキミ(シキビ, ハナノキ, ハナシバ)”. 植物図鑑. 筑波実験植物園. 2021年7月24日閲覧。
- “シキミ”. 日光植物園. 東京大学. 2021年7月23日閲覧。
- “シキミ”. 熊本大学薬学部 薬草園 植物データベース. 2021年7月23日閲覧。
- 東京都薬用植物園. “トウシキミ(八角)とシキミ(有毒)”. 東京都健康安全研究センター. 2021年7月23日閲覧。
- “Illicium anisatum”. Plants of the World online. Kew Botanical Garden. 2021年7月23日閲覧。 (英語)
樒(しきみ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 00:08 UTC 版)
屍に効果のある数少ない毒草の一つで、対象を麻痺させることが出来る。屍に植えつけ、精気を吸い上げるよう品種改良した物も存在する。
※この「樒(しきみ)」の解説は、「屍姫」の解説の一部です。
「樒(しきみ)」を含む「屍姫」の記事については、「屍姫」の概要を参照ください。
樒
樒 |
- >> 「樒」を含む用語の索引
- 樒のページへのリンク