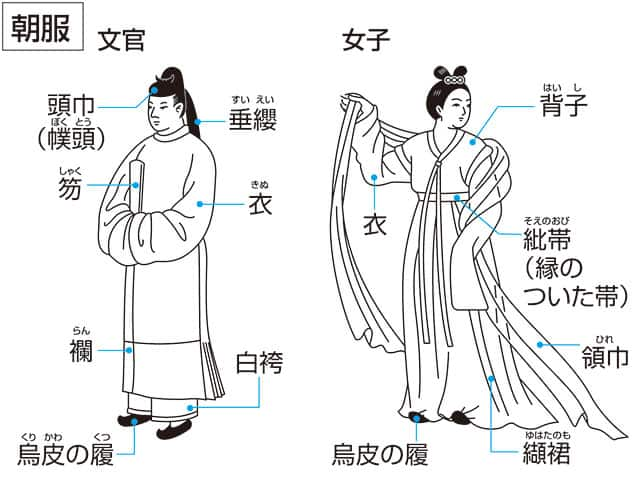ヒレ【(フランス)filet】
ひれ【領=巾/肩=巾】
ひれ【×鰭】
放れ
ひれ 【比礼・領巾・肩巾】
鰭
(ひれ から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/02 02:21 UTC 版)

ひれ(鰭)は、主に魚類などの脊椎動物が持つ、水中で動かし水をかいたり水流を制御したりすることによって、主として身体姿勢を制御することに使用する運動器である。体から薄膜状に突出する。その内部に骨や軟骨による支えがある場合が多い。
種によっては、水底の歩行、威嚇、子育てのために卵へ酸素を多く含んだ水を送るためにも使われることがあるが稀である。
ひれを持つ動物
脊索動物
-
魚類のひれ
脊索動物、細長い体の中心に脊索という支えを持ち、全身を左右にくねらせることで遊泳する方向に進化したと見られる。これに対応して、その体は左右に扁平になっている。さらにその体の縁に沿って体壁が薄膜状に伸びたものがひれである。これは体面積を広げ、推進力を増す効果があると考えられる。このようなひれは正中線に沿って発達し、体周を取り巻き、特に体の後半部に発達する。このようなひれを不対鰭といい、脊椎動物の無顎類・魚類・両生類に見られる。魚類では背びれ、尾びれ、尻びれがこれに当たる。
これに対して体の主に腹面から左右に突き出したひれが魚類にはあり、これは対鰭といわれる。原始的なものでは左右に水平に広がり、主に体の安定に寄与したと考えられるが、次第にその構造を複雑化し、多様な方法で使われるようになった。胸びれと腹びれがこれに当たる。これは無顎類にはなく、それ以降に発達したものである。また、それらは脊椎動物の陸上進出に際し、四肢に変化した。またそれに並行して、陸上での運動に寄与しない不対鰭は消失した。
哺乳類、爬虫類、鳥類のひれは、すべて二次的に形成されたものである。たとえばクジラや魚竜の胸びれや腹びれ様の鰭は脚や翼から二次的に変化したものである。ただしそれらも元は魚類のひれだった器官である。
英語では、魚のような流体制御目的のヒレをフィン(Fin)、クジラやカメやペンギンのような四肢が変化したフリッパー(英語版:Flipper)の使い分けが見られる[1]。

脊椎動物以外の脊索動物、例えばナメクジウオ(頭索動物)にも背びれや尾びれがあり、その様子は無顎類のそれに似ている。これは脊椎動物のそれらと相同である可能性がある。
その他の動物
脊索動物以外の動物群においても、明確にひれをもつ例がある。
-
オヨギヒモムシ類
- ヤムシ類(毛顎動物)の体の側面と尾にひれがあり、いずれも体に対して水平に左右相称な形を取る[2]。
- ヒモムシ類(紐形動物)のオヨギヒモムシ類は、体の左右が張り出して一面のひれとなる。
- 軟体動物の中で明確にひれをもつ例は主に頭足類であり、メンダコ、ジュウモンジダコ類、イカなどが挙げられる。これらの動物のひれは外套膜の左右に備わり、コウイカ類に至ってはひれの付け根がほぼ外套膜の全長に及ぶほどである。腹足類の中で翼足類(カメガイ、クリオネなど)は遊泳生活に適しており、腹足が左右に広げてひれのような翼足となる。
- 基盤的な節足動物と考えられる古生物ラディオドンタ類およびその近縁(オパビニア、ケリグマケラなど)は、各胴節が対になるひれをもつ。これらのひれは前後で重なった部分があり、あわせて一面の大きなひれのように機能していたと考えられる[3]。現生節足動物の中でもひれらしき付属肢(関節肢)をもつ例はあるが、鰓脚もしくは遊泳脚と呼ばれる。
水かきや扁平化

爬虫類・鳥類・哺乳類を含む群、あるいは両生類以外の四足動物では全生活に渡って完全に陸上生活が可能な形で進化し、その過程で四肢を除く全てのひれを失った。しかし、その一部は再び水中や水辺の環境に進出し、その過程で、二次的にひれのような構造を獲得した。まず足指の間に水かきを獲得するのがよく見られるが、この形は遊泳により適すると同時に足指の指としての使用が可能な形である。さらに遊泳にのみ適する形で進化したものは指骨本来の指の本数が減少したり、また足全体や尾などが扁平化し、ひれのような役割を持つ動物も存在する。これらは、収斂の結果である場合も多い。
扁平化は左右からの場合もあれば腹背方向になる場合もある。爬虫類までは体を左右にくねらせる運動が簡単であるため、尾は左右扁平になるのに対して、鳥類・哺乳類では陸上での四肢による運動への適応から上下にくねらせる運動が優勢となっており、尾部は腹背から扁平になる例が多い。
水かきを持つ動物
体が扁平化した動物
魚類のひれ
脚注
- ^ Stephenson, Deborah. “The Difference Between a Dorsal Fin & a Flipper” (英語). Pets on Mom.com. 2024年5月2日閲覧。
- ^ Park, Tae-Yoon S.; Nielsen, Morten Lunde; Parry, Luke A.; Sørensen, Martin Vinther; Lee, Mirinae; Kihm, Ji-Hoon; Ahn, Inhye; Park, Changkun et al. (2024-01-05). “A giant stem-group chaetognath” (英語). Science Advances 10 (1). doi:10.1126/sciadv.adi6678. ISSN 2375-2548.
- ^ Usami, Yoshiyuki (2006-01-07). “Theoretical study on the body form and swimming pattern of Anomalocaris based on hydrodynamic simulation”. Journal of Theoretical Biology 238 (1): 11–17. doi:10.1016/j.jtbi.2005.05.008. ISSN 0022-5193. PMID 16002096.
関連項目
ひれ(鰭)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 05:37 UTC 版)
詳細は「鰭 (魚類)」を参照 ひれ(鰭)は体から突き出した薄膜状の構造である。基部には骨格や筋肉があり、動かせる。泳いだり、海底や地上を這ったり砂に潜ったりするのに使われる。 ひれは体につく位置により次のように分類される。 胸鰭(きょうき・むなびれ) Pectoral fins - 頭の後方、体の側面に位置する一対のひれ。両生類以降の前肢に変化したとされる。 背鰭(はいき・せびれ) Dorsal fin - 背側にあるひれ。種によって数が異なり、第一背鰭・第二背鰭などと区別する。 腹鰭(ふっき・はらびれ) Pelvic fins (Ventral fins) - 腹側の肛門より頭側にある一対のひれ。両生類以降の後肢に変化したとされる。 臀鰭(でんき・しりびれ) Anal fin - 腹側の肛門より尾側にあるひれ。 尾鰭(びき・おびれ) Caudal fin (Tail fin) - 体の最も後方にあるひれ。 脂鰭(しき・あぶらびれ) Adipose fin - サケなどに見られる、背びれの後方にある1 つの小さなひれ。 小離鰭(しょうりき・はなれびれ) Finlets - サバやマグロなどの尾部に見られる、多数の小さなひれ。 頭鰭(とうき・あたまびれ) -イトマキエイ類の頭部にある1対の角のようなひれ。 胸びれと腹びれは左右1対あり、これらを対鰭(ついき)、それ以外を不対鰭(ふついき)と呼ぶ。また背びれの数は1基、2基、3基と数え、前から順に第1背鰭、第2背鰭、第3背鰭と呼ぶ。 ひれの形態は、軟骨魚類、肉鰭類、条鰭類で大きく異なる。 サメ・エイなど軟骨魚綱では、ひれは厚い皮膚で覆われ、中は輻射軟骨で支えられる。硬骨魚類のようにあまり自由に動かすことはできず、後退などの動作ができない。サメのものは鱶鰭(ふかひれ)と呼ばれ、高級食材として名高い。 シーラカンス・ハイギョなど肉鰭綱では、ひれの基部が筋肉で覆われる。一部の肉鰭類では、胸びれや腹びれが陸上を這う脚となり、四肢動物へと進化していったと考えられている。 条鰭綱ではひれは膜状の構造物であり、体の正中線、あるいはその左右に対になって張り出す。膜を支えるようにひれには多数の筋(鰭条)が入っていて、基部では骨と筋肉が接続しているのが普通である。鰭条には軟条(なんじょう)と棘条(きょくじょう)の2 種類があり、棘条には毒腺(刺毒装置 しどくそうち)を備えているものもある。 ひれが遊泳以外の目的に進化している場合もある。また進化の過程で、一部のひれが退化していることも多い。 トビウオの仲間は、体に対して非常に大きな胸びれを持ち、空中を滑空することができる。 ハゼやウバウオの仲間では腹びれが吸盤に変化して、岩や海藻などにくっつくのに都合が良い。 コバンザメでは第一背鰭が吸盤に変化し、大型の魚にくっついて移動する習性を持っている。 アンコウの仲間は、背びれが釣竿のような形状に変化(エスカ・擬餌状体)し、先端はルアーになっている。 チョウチンアンコウの仲間はルアーの部分に発光器を備える。 ミノカサゴやゴンズイなどは、棘条に毒腺を発達させて身を守っている。 ホウボウは腹びれが脚のようになっており、海底を這って歩くのに適している。 マンボウは尾びれと臀びれがつながって特殊な形態(舵鰭 かじびれ)をなしている。 遊泳力の強いマグロやカジキなどは2基の背びれを持ち、前方にある第1背鰭は溝に折りたたむことができる。それぞれのひれは極限まで水の抵抗を減らすように設計され、高速遊泳に特化している。
※この「ひれ(鰭)」の解説は、「魚類」の解説の一部です。
「ひれ(鰭)」を含む「魚類」の記事については、「魚類」の概要を参照ください。
帍
帍 |
|
裱
鰭
「ひれ」の例文・使い方・用例・文例
- 魚の尾ひれ
- …の前にひれ伏す;…に屈服する
- 魚のひれは鳥の翼に相当する
- アザラシのひれ状の前肢
- イルカのひれは我々の手と相同器官である。
- 水中眼鏡とシュノーケルと足ひれをつけて船から海に入り、サンゴ礁の中を泳ぎました。
- 「学園の廊下で、濃厚なキスシーン・・・聞いたぞ聞いたぞ」「濃厚じゃなーい!話に尾ひれ付いてるって・・・」
- 全国民は恐怖からこの独裁者の前にひれ伏した。
- 彼女は彼をひれ伏せさせ手にキスをさせた.
- その老人は祭壇の前にひれ伏した.
- 背びれは、魚と特定の海洋哺乳類の後部の垂直ひれである
- 腹部(または骨盤の)ひれは、四足獣の後ろの手足と一致する
- 足ひれとして使用される四肢を持つ
- コイ目の、ひれが柔らかい魚
- 一般的に歯のないあごと円形のうろこがある柔らかいひれのある主に淡水の魚
- 小さい柔らかいひれをした魚の大きな科
- 浅海に広く分布するサメで、インクに浸されたようなひれを持つ
- そのひれ(中国人によってスープに使われる)と肝臓(ビタミンAが豊富な)のために高く評価される太平洋のサメ
- 彼女は欲求不満でひれ伏した
- 短い尾と幅広のひれを持つアカエイ
ひれと同じ種類の言葉
「ひれ」に関係したコラム
-
FX(外国為替証拠金取引)のくりっく365とは、株式会社東京金融取引所(金融取)の運営するFX(外国為替証拠金取引)の名称です。くりっく365は、2005年7月から取引が開始されました。くりっく365...
-
個人投資家が株式投資を行う場合、証券会社を通じて株式売買を行うのが一般的です。証券会社は、株式などの有価証券の売買をはじめ、店頭デリバティブ取引や有価証券の管理を主な業務としています。日本国内の証券会...
- >> 「ひれ」を含む用語の索引
- ひれのページへのリンク