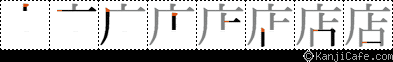店
店
店
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/02 01:00 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2020年9月)
|




店(みせ、たな、英語: store)は、商品を陳列して売る場所。商品やサービスを提供する場所。店舗(てんぽ)や商店(しょうてん)とも言う。
概要
数
経済産業省の1997年(平成9年)の統計によると、全国の小売業の商店は141万9696店であった。このうち、大規模小売店舗の外にあるのが 129万5144店で、全体の91.2%で、大規模小売店舗内にある店は12万4552店で、8.8%であった[1][2]。
種類
立地条件により分類するのが基本で、道路に面した1階にある路面店や建物の2階以上にある階上店舗(空中店舗)に分類するのが基本だが、そのほか、多層のビルディング内に置かれる「ビルイン型」や複合商業施設内(ショッピングセンターなど)に置かれる店もある。
店舗経営者が所有している物件なのか、借りている物件なのかで分類する方法もある。ショッピングセンターや地下街などにはテナントといい、場所を借りて営業している店舗が並ぶ。
売り場面積で分類する方法もある。ただし調査者や基準策定者ごとに基準は異っている。たとえば総務省統計局は、平成9年全国物価統計調査で売場面積が450平方メートル以上の店舗を大規模店舗、450平方メートル未満の店舗を小規模店舗として調査した[3]。大店法の規定では売場面積が500平方メートル以上の店舗を大規模小売店としているが、路面店を中心に大店法の下限である500平方メートルをわずかに下回る店舗が多数あり、それが地域における価格形成に大きな影響を与えていると考えられたからだという[3]。
固定された店舗のほか、移動式店舗もある。たとえば屋台や移動販売車である。古くは振売りというものがあった。
また当然ながら、鮮魚店、酒屋、薬屋、書店、生花店、クリーニング店 など、扱う商品やサービスで専門店を分類することは行われている。スーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなど商品分野を限定しない店舗もある。商品やサービスを販売している店が基本だが、品物の買取を行っている店もある。
古くから野菜の無人販売所は畑周辺にあったが、2010年代後半から野菜以外でも無人店舗が増えてきている。
店舗開発
店舗を新規に出店するために、不動産物件の調査から始まり実際に開店するまでの工程を管理する業務を店舗開発という。全国に店舗を展開する大手チェーンなどでは店舗開発に専念する人が社内にいる。
店舗と法規
店舗を開設し、商品の販売やサービスの提供を行う場合、その商品やサービスによって様々な法的規制が課せられる場合が多い。規制内容は営業を行う場所の制限、衛生設備や消防設備が必要とされる建築物の構造、客席数の制限などがある。
日本の場合、店に関係する法規には、都市計画法(用途地域)、食品衛生法、公衆衛生法、建築物衛生法、消防法、建築基準法、旅館業法、風俗営業法、労働安全衛生法などがある。
既存の建築物を改装し、以前と異なる店舗を開設しようとしたとき、既存建築物によっては営業許可が得られない場合もあり、このような場合には、事前に専門家の調査が必要とされる。
「店舗」や「みせ」や「たな」の語源
「店舗」あるいは単に「店」は、律令制度の伝来とともに中国から日本へと入ってきた漢字である。本来の意味は、都市に存在した邸店(現在で言う宿泊施設にあたる。倉庫施設を併せ持つ例が多かった)と肆舗(しほ、現在で言う商業施設にあたる)を併せて称したものであった[要出典]。当時、肆舗が集まる市場の近くに商用の客のための邸店が多く置かれていたために、これらを一括して扱う事が多かった[要出典]。
「みせ」の語源は「見世棚(みせだな)」である[4]。「見世棚」は商品を陳列する棚のことで、この言葉は鎌倉末期より存在し、台を高くして「見せる」ことから「見世」といい、室町期に「店」の字が当てられるようになった。
店に関する用語、雑学
- 店頭 - 店の入り口やその付近、あるいは陳列棚やレジスターなどがあり客に応対するところ[5]。
- 店子(たなこ) - 店の場所を借りている人、法人。テナント、賃借者。
- 店主 - 店舗経営者。
- 店員 - 店舗で働く従業員。
- 店長 - 従業員の最高責任者。
- 店商い(たなあきない) - 店を構えて商売すること[6]。
- 店を畳む - 商売をやめる。
出典
関連項目
店
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/08 13:43 UTC 版)
毎朝新聞販売店(1巻) 明日菜のバイト先。 食堂棟(13時間目) 地下から屋上まで全て飲食店で占められている。鳴滝姉妹がネギにスイーツをおごらせている。 STARBOOKS CAFE(3巻 - ) 麻帆良駅前にあるカフェ。看板に「STARBOOKS COFFEE」と描かれている。STARBUCKS COFFEEのパロディ。 売店(3巻) 停電用品を売っていた店。 MAGGY(9巻) さよが夜を過ごしている学校近くのコンビニ。サンクスのパロディ。名前の由来はアシスタントの一人の通称「まぎぃ」から。 まほらストア(9巻) 犬上小太郎が持っていたレジ袋に書かれたコンビニ名。 イグドラシル(9巻) 高畑としずなが一緒に座っていたシーンで登場したカフェ。麻帆良祭公式プログラムにも載っている。名前は北欧神話に登場する世界樹ユグドラシルに由来。 麻帆良洋品店(14巻) ネギ達が服をレンタルした洋品店。 超高級学食JoJo苑(160時間目) 名前のみ登場の焼肉屋。焼肉チェーン店叙々苑のパロディ。 まつ屋(165時間目) 名前のみ登場の牛丼店。円の大好物であり、駅前の店舗が移転してしまい彼女や美空の涙を誘った。牛丼チェーン店松屋フーズのパロディ。 麻帆ミヲン(175時間目) 映画館。
※この「店」の解説は、「麻帆良学園都市」の解説の一部です。
「店」を含む「麻帆良学園都市」の記事については、「麻帆良学園都市」の概要を参照ください。
店
店
「店」の例文・使い方・用例・文例
- その店は病院の向かいだ
- 広告代理店
- 旅行代理店
- 重役会はインドネシアに支店を開設することに合意しなかった
- この川沿いのどこかにいい店がある
- 犬は店内には入れません
- 町の商店街
- 角を曲がったところにある店
- その店ではあらゆる種類の品物を売っている
- 彼は店主と価格のことで交渉した
- 店は8時に閉まる」と「8時には閉まっている
- 彼の店が人気があるのは必ずしも味がよくてではなく,早いからだ
- この店で一番高級な自転車
- へんぴなところに店を出す
- その店は彼らの地下活動のための偽装にすぎなかった
- 教会のバザーの飲み物売店
- 道の両側にたくさんの店がある
- 彼は空き瓶を店に返した
- その銀行は大都市全部に支店がある
- 店を出す
- >> 「店」を含む用語の索引
- 店のページへのリンク
![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈
〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈みせ〉「
〈みせ〉「![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 〈たな(だな)〉「
〈たな(だな)〉「