つう‐や【通夜】
つ‐や【通夜】
【佛式】通夜・葬儀
通夜

通夜には仮通夜と本通夜があります。 逝去直後で精神的に落ち着かなかったり時間的に葬儀の段取りが出来ない場合などは、とりあえず僧侶に枕教のみの読経をお願いして、自宅で極親しい者だけが集う通夜を「仮通夜」といい、僧侶の読経の元で関係者に通知・参列いただいて、葬儀場などで一般に行う通夜のことを「本通夜」と言います。仮通夜に駆け付ける際は、余程親しかった場合を除き、玄関で挨拶程度にしておくのが遺族への礼儀です。
本来、通夜には特に故人と生前親しかった遺族・近親者・親しい知人友人に限られ、それ程でもなかった方々は告別式に参列する習しになっていましたが、現在ではいずれか都合の良い日に参列するのが一般的になってきています。また、昨今では半通夜と言って、1時間程度で終えるのが通例となっています。
※通夜と葬儀の両方に参列する場合の弔慰金品は、通夜に持参するのが一般的です。
通夜振る舞い
通夜の後に、故人への供養にあわせて通夜弔問へのお礼を兼ねて、簡単な飲食物が用意されることを通夜振る舞いと言い軽い酒食類が一般的ですが、お茶菓子程度などの場合もあり地区によって用意されるものは異なります。
会食をすすめられたら、遺族の心遣いに応えるためにも余程の事情がない限り出席して、生前の故人の在りし日を語りあうのが習わしですが、長居は返ってご迷惑になりますので頃合いを見計らって失礼するのが礼儀です。
夜伽(よとぎ)
通夜から翌日の葬儀当日の死者を葬るまでの間、近親者が祭壇に安置されている故人の柩のそばで、夜を徹して交替でローソクと線香を絶やさないようにして守ることを夜伽と言います。これは元々、家族・親族縁者・親しい知人友人などが、葬るまでに故人が蘇生することを願って夜通しそばに付き添っていたことに由来します。
葬儀・告別式
本来は、「葬儀」と「告別式」は区別して行われるもので、葬儀は文字通り故人の冥福を祈り成仏することを願って遺族や近親者のみによって故人を葬り、浄土に導く引導を渡すために営む儀式であり、「告別式」は葬儀を一旦終えた後に、友人・知人・近隣者・勤務先の関係者などが故人と最後のお別れをする儀式になっています。
現在では、土葬による埋葬から火葬に変って、参列者が墓地まで行く機会がなくなるなど葬儀の慣習が変ってきたことから、葬儀と告別式を同時に行うのが一般的になり、告別式参列者も焼香による会葬をもって故人とお別れする形式に変ってきています。
ひとくちMEMO
- 香奠返しは通夜・葬儀時にはお印程度のものを手渡し、正式には忌明け法要後に贈る。
- 宗教・宗派にかかわらず通夜・葬儀の儀式においては、町内会役員・近隣者・会社や職場や業界関係者・寺院や教会などの方々には、世話役・進行係・会計係・受付係・会場案内係・台所係・駐車及び交通整理係・霊柩車やハイヤー及びタクシーやマイクロバスの運転手・火葬場係員などの他、寺院のお手伝いさん・教会の聖歌隊やオルガニストなどとしてお世話になりますが、そうした方々への謝礼の献辞(表書き)は「御礼」とします。(注:係員が公的職員の場合は謝礼受取りを禁じています。)
- お祝い返しや香奠返しは通常1/2〜1/3返しとされていますが、基本的には「上に薄く下に厚く」返すのが一般的とされています。また、商品で返す場合は1/3返し、商品券で返す場合は1/2返し、両方の場合は各々1/3返しが最近の傾向です。
- ふく紗は慶事と弔事では、色や包み方などが異なりますのでご注意ください。
- 枕経や通夜の僧侶への謝礼は葬儀時の謝礼と一括にして手渡すのが一般的。関西の中心都市部では、葬儀時にも黄白(銀)水引の金封・のし袋・のし紙を用いる習慣がある。仏教一般では、葬儀時は「霊前」、法要時は「佛前」とするが、浄土真宗に限り霊前は用いず葬儀時も「佛前」を用いる。
御香典の目安
| 贈り先 | 年代別 | 東西別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 関東 | 関西 | |
| 全体 | 3千円 | 5千円 | 1) | 1万円 | 5千円 | 5千円 |
| 勤務先の上司 | 3千円 | 5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 5千円 |
| 勤務先の同僚 | 3千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 2) |
| 勤務先の部下 | − | * | 5千円 | 1万円 | 5千円 | 5千円 |
| 勤務先社員の家族 | 2) | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 3千円 |
| 取引先関係 | − | 5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 祖父母 | 1万円 | 1万円 | * | − | 2万円 | 1万円 |
| 両親 | * | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 兄弟・姉妹 | − | 5万円 | * | 3万円 | 5万円 | 3万円 |
| おじ・おば | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| その他の親類 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
| 友人・知人 | − | 5千円 | 1) | 5千円 | 1万円 | 5千円 |
| となり・近所 | 2) | 3千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |
| 友人・知人の家族 | 5千円 | 5千円 | 1万円 | 5千円 | 5千円 | 5千円 |
| その他 | * | 2) | * | 1) | 3千円 | 1) |
1)5千円・1万円 2)3千円・5千円
注意)−は該当するサンプルがないもの *はサンプル数が少ないためクロス集計していません
ご贈答のマナー
| 贈答様式 | 贈り元 | 献辞(表書き) | 慶弔用品 |
|---|---|---|---|
| 枕経時の僧侶への謝礼 | 遺族 | 御車料 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 通夜時の寺院・ 僧侶への謝礼 |
遺族 | 御車料 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 葬儀(告別式)時の 寺院・僧侶への謝礼 |
遺族 | 御法禮 御回向料 御経料 御供養料 御布施 御礼 |
【金封】 双銀結切り/双銀あわび結び/黄白結切り 黄白あわび結び/水引熨斗なし 【のし袋】 白無地/黄白(銀)結切り 黄白(銀)あわび結び/御布施字入 |
| 戒名・法名・法号を 付けて貰った謝礼 |
御戒名料 御法名料 御法号料 御礼 |
||
| 葬儀時の僧侶への 謝礼に付ける |
御膳料 | 【のし袋】白無地 | |
| 御車料 | |||
| 葬儀委員長・ 世話役への謝礼 |
遺族 | 御礼 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 受付係・お手伝い の方への謝礼 |
遺族 | 御礼 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 会食に参加されない 受付係・お手伝いの方 への謝礼 |
遺族 | 御膳料と御礼 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 寺院の使用料 (寺院を借りる場合) |
遺族 | 御席料 | 【金封】水引熨斗なし 【のし袋】白無地 |
| 葬儀に弔慰金を贈る | 身内 身内以外 |
御霊前(御佛前) 御香奠 御香料 御悔み 御香華料 |
【金封】 黒白結切り/黒白あわび結び/双銀結切り 双銀あわび結び/黄白結切り/黄白あわび結び 【のし袋】 藍銀結切り/藍銀あわび結び/黄白(銀)結切り 黄白(銀)あわび結び/白無地 |
| 葬儀にお供え物を贈る | 身内 身内以外 |
御供物 御供 |
【のし紙】 藍銀結切り/藍銀あわび結び/ 黄白結切り/黄白あわび結び |
| 通夜・葬儀時の志 | 遺族 | (東)志 (西)粗供養 |
使用例(のし紙/金封/のし袋の様式)
| のし紙/金封/のし袋の様式 | 使い方 |
|---|---|



 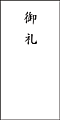
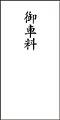

 |
通夜
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/14 07:12 UTC 版)
仏教の通夜

意義
通夜の起源は、釈迦の弟子たちが釈迦の死後の7日間、遺体を見守りながら、釈迦が生涯をかけて説いた説法を夜通し互いに聞き合ったという故事による[1]。通夜の目的は故人の成仏を祈ることではなく、大夜(たいや)に故人の現世での最後の夜を共に過ごすために集まった親しい人々が、遺体を取り囲んで故人の思い出話を語り合うことであった。
曹洞宗では釈迦の弟子にならい、『修証義』を遺族らが住職とともに読誦するのが通夜の本来の儀式である[1]。
日本
通夜はもともと故人を葬る前に親族や知人が夜通しで死者を守ることを意味した[2]。古くは葬儀に至るまでの夜を通して通夜と称した[2]。しかし、時代の変化とともに、2時間程度の半通夜が一般化してきており、僧侶を招いて読経と焼香を行うという、葬儀に準じた儀式となっている[2]。通夜の儀式化に伴い、弔問客も会葬して行われる通夜を本通夜、遺族など近親者だけで前もって行われる通夜を仮通夜と称することもある[2]。
通夜では一般的に、僧侶が読経を始め、しばらくすると親族や会葬者により順次焼香が行われる[3]。読経の終了後に僧侶が法話や説教を行う場合もある[3]。
また、故人とともに最後の食事を行うという意味で通夜ぶるまいが行われる地域もある[4]。故人の供養と参列者へのお礼の意味で食事をふるまう地域もあれば、食事は家族のみで参列者は茶菓子や飲み物を受け取るだけの地域もある[4]。
弔問客が帰ってからも親族が交代で死者を守るという習慣は見られ[2]、特に夜伽(よとぎ)と称して夜を通して故人とともに過ごす地域もある[3]。
昼間は勤務などで告別式に参列できないとなどの理由で、近親者以外は通夜のみに参列し、告別式には参列しない、若しくは通夜のみを行って告別式を行わないのが一般的な地域もある(西日本全域、特に中国地方や北海道の一部の地域など)。
逆に通夜は近親者のみ参列し、一般の参列者は葬儀にのみ参列するのが一般的な地域もある(東北地方の一部の地域など)。
通夜を行わない風習を持つ地域もある(秋田県の一部など。秋田市や青森県弘前市では一般的に火葬を行ってから、通夜(逮夜)・告別式を行うことが多い)。また、もともと通夜を行っていた地域でも単身世帯の増加や高齢化の進行とともに通夜を行わず葬式だけ行う「1日葬」が増えている[5]。
韓国
韓国語には通夜に相当する単語が存在しない[6]。葬儀に関連する礼儀作法や手順をまとめて初終凡節と称する[6]。
他宗教の儀礼
- 神式の儀礼については通夜祭と呼ぶ。
→詳細は「神葬祭」を参照
脚注
注釈・出典
- ^ a b イオンのお葬式 - 曹洞宗の葬儀・通夜についての解説
- ^ a b c d e 藤村英和『新版 葬儀・法要のあいさつ』西東社、2011年、22頁
- ^ a b c 吉川美津子『はじめての喪主 葬儀・葬儀後マニュアル』秀和システム、2014年、77頁
- ^ a b 吉川美津子『はじめての喪主 葬儀・葬儀後マニュアル』秀和システム、2014年、54頁
- ^ 通夜を行わない「1日葬」増える/青森県内 東奥日報 2018年12月13日閲覧
- ^ a b 金容権『韓国語手紙の書き方事典』三修社、2012年、65頁
- ^ かたち-諸奉神礼:日本正教会 The Orthodox Church in Japan - 日本正教会公式サイト
関連項目
通夜
「通夜」の例文・使い方・用例・文例
- その通夜は、葬式の前夜に行われた。
- そのお通夜に参列しました。
- 私は亡くなった佐々木さんのお通夜に行きました。
- 通夜をする.
- お通夜をする.
- ごく近しかったわずかの人々だけが集まって, しめやかに通夜が営まれた.
- まるでお通夜みたいなパーティーだね.
- 彼が来るまではパーティーはお通夜のようだった.
- お通夜をする
- この地方では人が死ぬと全村集まってお通夜をする
- 通夜をする
- この地方では人が死ぬと全村集まって通夜をする
- アイルランドの通夜で泣くことはできない
- 通夜の時,死者の枕元で経を読む僧
- 葬送の前夜に行う通夜
- この小説は通夜に集まったさまざまな親戚たちについて描いている。
通夜と同じ種類の言葉
- >> 「通夜」を含む用語の索引
- 通夜のページへのリンク




