貿易史
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/06 04:35 UTC 版)
中世
8世紀には、アッバース朝によって西アジア、アフリカ、ヨーロッパまでの貿易ルートがつながった[130]。13世紀には、モンゴル帝国のもとでシルクロードの東西が初めて統一されて、東アジア、アフリカ、ヨーロッパまでの貿易ルートがつながった。こうした交通網の発達は、貿易にまつわる制度や文化の交流ももたらした[131]。
西アジア
イスラーム帝国

ウマイヤ朝を滅ぼして成立したアッバース朝は、メソポタミア平原のバグダードを首都としてサーサーン朝の制度を取り入れた。広大な領土の交通がバリードという駅伝制で整備されると、流通が改善して農業や手工業の商品化が進んだ。農業ではサワードと呼ばれる平野で商品作物が作られ、穀物はエジプトなどの穀倉地帯から自給が困難な地域へと運ばれた。都市では繊維製品の特産物が増え、エジプトの亜麻布、クーファやシーラーズの絹織物、ペルシアやアルメニアの絨毯が有名となる。こうして高級品のほかに穀物や繊維製品の流通も盛んとなった。都市の商業施設が充実し、隊商の宿と倉庫を兼ねたキャラバンサライと、仕入れたものを売るスークやバザールが組み合わせて建設された。外部の人間を一時的に保護して、旅人に食料や宿を提供する互助的なジワール制度もあった。大都市には、ジワールを巡礼や学問に利用する者も多数おり、ムジャーウィルーンと呼ばれた。最盛期のバグダードは人口が100万人を超え、バスラ道とクーファ道にそって貿易用の大市場が設けられ、各国の産物が集まった[注釈 10][132]。
貿易ルートの発達

アッバース朝のもとで数々の貿易ルートがつながり、陸路と海路の結びつきも強まった。陸路ではラクダがアフリカの隊商にも導入され、海路ではダウ船が普及して、季節ごとに移動手段と方向が使い分けられた。こうして地中海ルート、紅海・インド洋・南シナ海ルート、イベリア半島からモロッコを経由するエジプトへのルート、シリアとイラク間の陸上ルート、ビザンツ帝国のコンスタンティノープルへのルート、フランク王国へのルートなどが存在した。地理学者であるイブン・フルダーズベの『諸道路と諸国の書』には、貿易ルートの商人たちの活動が記録されている[132]。交通の整備は、イスラーム教徒のマッカ巡礼と密接な関係にあり、国家の巡礼キャラバンが組織されていた。商業のキャラバンは、巡礼キャラバンと同じルートを使うことで安全保障の費用を軽減した。巡礼キャラバンの時期に合わせて年市が開かれ、巡礼者と地元の商人や遊牧民との間で取り引きや情報交換が行われた。交通が緊密になると地理学や地理書も盛んになり、イスタフリーやイドリースィーの記録や世界地図を生み出した。旅行者の記録も増え、イブン・ジュバイル、イブン・ハウカル、イブン・バットゥータらが有名である。中でもイブン・バットゥータは、北アフリカのマグリブからマッカに至って中国まで旅をしたと語っており、当時の東西交通の活発さを伝えている[133][134]。
商業の振興

貿易をする大商人はタージルと呼ばれ、イスラーム法のもとで貿易の制度も整えられた。出資者が事業家に出資する方法や共同出資が発達して、ユダヤ商人やキリスト教の商人との間でも用いられた。イスラーム経済では等価・等量交換を重視することから、ディナール金貨やディルハム銀貨の重量が保たれ、ヨーロッパでも信用の高い貨幣として扱われた[135]。遠隔地貿易の代理人としてアラビア語のワキール、ヘブライ語でバーキードと呼ばれる者がおり、イスラーム商圏で紛争処理、商品保管、仲介などを行った。ワキールにはイスラーム法の知識が求められるため、法官のカーディーが務めることも多かった[136]。アッバース朝以降には商業書も多数書かれ、中でもディマシュキーの『商業の功徳』が有名である。ディマシュキーは、取り引きや品質管理についての経営論、商人の類型なども論じた。ディマシュキーは商人について、倉庫業者で卸売をするハッザーン、運送業者で遠距離交易をするラッカード、各地に代理店を作って買い付けをするムジャッヒズに分類している。『商業の功徳』は、のちにヨーロッパの商業学にも影響を与えた[34]。
地中海、黒海
ビザンツ帝国軍とアラブ軍は8世紀から9世紀にかけて海戦を行い、シリア、エジプト、チュニジアがイスラーム王朝の統治下におかれた。アラブやシリアのイスラーム商人、ユダヤ商人、イタリア都市の商人が地中海貿易を活発に行い、イスラームのキラード制度によって、宗教が異なる者同士でも協力をして取り引きを行った。海上商人は武装商人でもあり、機会があれば他船を攻撃して略奪を行う場合もあった[注釈 11][138]。地中海の縦断には1、2週間かかり、チュニスからリヴォルノまでは11日、コンスタンティノープルからアレクサンドリアまでは寄港を含めて2週間ほどで、地中海全域の横断には2、3ヶ月かかった。トゥルン・ウント・タクシス家の郵便事業は、ローマとマドリードを1カ月ほどで結び、重大な知らせは、さらに迅速に運ばれた[139]。
シチリア
交通の重要地域で穀倉地でもあるシチリアは、イフリーキーヤのアグラブ朝の属領となる。イスラームの灌漑技術で耕地が拡大して、ヨーロッパで珍しかったレモン、メロン、綿花、パピルス、サトウキビといった作物も栽培され、イブン・ジュバイルやイドリーシーの記録では豊富な果樹園が特筆されている。養蚕も行われてパレルモを中心に絹を輸出して、中継貿易は11世紀に最盛期を迎える。12世紀にはノルマン人によってキリスト教徒の統治下となるが、シチリア王国のルッジェーロ2世はイスラームの制度を引き継ぎ、住民もイタリア人、ギリシア人、アラブ人、ノルマン人が併存した。アラブ人やギリシア人は宮廷の役人としても働き、領内のシチリア、南イタリア、チュニジアは緊密に交易を行い、ルッジェーロ2世は当時のヨーロッパで最も富裕な王とも言われた。1220年代に入るとイスラーム教徒の強制移住が行われて、灌漑技術は衰退した[140]。
東地中海、黒海
ビザンツ帝国との貿易で最も恩恵を受けたのは、ヴェネツィアだった。ヴェネツィアはアドリア海を渡るビザンツ帝国軍の輸送を担当したため、バシレイオス2世は992年にダーダネルス海峡に入るヴェネツィア船の基本税を30ソリドゥスから17ソリドゥスに減額した[141]。
インド洋や陸路を経由して運ばれる香辛料は、イタリアの都市に大きな利益をもたらした。13世紀にはモンゴル帝国による戦乱ののちにモンゴルの地方政権によって交通が安全になり、黒海から中国へ向かう陸路の貿易も増えた。ジェノヴァやヴェネツィアは、モンゴル政権のイルハン朝やジョチ・ウルスと商業協定を結んで黒海から東方へ進出する[142]。フィレンツェの商人ペゴロッティが1330年代頃に編纂したとされる商業書『商業指南』には、中国や黒海方面の貿易の記述が多く、タナから中国まで陸路で早ければ7、8カ月で到着すると書かれている。カッファやトレビゾンドはジェノヴァの拠点となり、本国と紛争にいたることもあった。黒海では穀物、塩、魚といった食料の物産に加えて、イタリア商人を中心に奴隷貿易が行われ、スラヴ系の奴隷はサカーリバと呼ばれた[40]。
15世紀にはオスマン帝国がビザンツ帝国を征服して、地中海貿易は大きく変化する。オスマン帝国は東西の中継貿易に力を入れ、イタリアの都市国家は貿易ルートの支配が低下した。このためヨーロッパでは、地中海以外のルートを開拓する試みが活発となる。サファヴィー朝が建国されるとアルメニアや商人やギリシア商人の進出が増え、イスラーム商人は地中海やインド洋での活動が縮小していった[89]。
インド洋、ペルシア湾
綿織物と香辛料貿易
インド洋は、イスラームが広まるとマッカ巡礼のルートとしても交流が活発となった[134]。インド洋の貿易ではインド産の綿織物が質がよく、綿織物を入手するためにマラバール海岸、スマトラ、ジャワではコショウやカルダモン、セイロン島ではシナモン、モルッカ諸島ではクローブなどを輸出した[143]。インド洋貿易における香辛料は綿織物と取り引きするための生産物であったが、香辛料がインド洋を横断して地中海に運ばれると珍重され、高値で取引された。そのためモルッカ諸島は香料諸島とも呼ばれた[144]。地中海からインド洋への輸出品は銀を中心とする金属、工芸品、奴隷などに限られ、ヨーロッパでは毛織物も特産物として輸出しようとしたが成功せず、逆にインドの綿織物がヨーロッパで注目されるようになる。地中海からの輸出は品目が増えなかったため、取り引きされる香辛料の量も限られ、高価な状態が続いた[145]。
銀の流通
モンゴル帝国が中国からペルシアにかけて統治するようになると、ペルシアから中国にかけての海上貿易が増加した。キーシュ島やホルムズが海上貿易の中心となり、紅海やペルシア湾からの馬が重要な輸出品となった。インドは馬を大量に輸入して、中国からの銀を支払いに用いた。イスラーム諸国は10世紀から銀不足が続いていたが、東から西へと銀が流入するにつれて13世紀に銀不足は解消された[146]。
ヨーロッパの進出

地中海を経由せずに香辛料貿易で利益を得るために、ポルトガルはアフリカを周回してインド洋に達する航路を開拓する。ヴァスコ・ダ・ガマは喜望峰を通過して東アフリカのキルワ王国に着き、1498年にインドのカリカットに到着して、その後も2回の航海でコーチンに着いてポルトガルのアジア進出の基礎を築いた。しかしヴァスコや後任者は各地の行動規範や商慣習に従わなかったため、海賊の疑いをかけられたり武力衝突を起こした。商業ではなく軍事力で貿易を拡大する方法は、のちにアジアへ進出するスペイン、オランダ、イギリスなどのヨーロッパ諸国も用いた[147]。
南アジア、東南アジア
インド
9世紀から15世紀にかけては、マニグラーラムや五百人組と呼ばれる商人ギルドが活動し、南インドのタミルの商人が中心となる。マニグラーラムはケーララの領主からの特権として、関税の免減、居住区での裁判権などを得ていた。五百人組は商人グループの連合組織であり、スリランカやスマトラで活動する一方、特定の品物だけを扱う商人や、個々の街の商人も含んでいた[148]。13世紀からは綿布の生産が増えて手工業品の輸出も増える。南インドのパーンディヤ朝は中国の元と貿易を盛んにして、元の歴史書『元史』にもその繁栄が記録されている。パーンディヤ朝は中国との貿易で得た銀で、ペルシア湾から馬を大量に輸入して、それまでのインドで伝統的であった象と歩兵の編成から騎馬兵への移行がなされた[149]。
15世紀のグジャラート・スルターン朝はインド洋貿易の統制をせず、ボーラ (イスマーイール派)やボホラと呼ばれるイスマーイール派の商人や、バニヤと呼ばれるヒンドゥー教徒やジャイナ教徒の商人たちが、グジャラートの綿織物やマラバールの香辛料を運んだ。グジャラートの港は古代から重要な中継地であり、9世紀から16世紀にかけてはカンバートが中心となった[150]。グジャラート、コロマンデル海岸、ベンガルで生産される綿織物は、染色が容易で良質であり広く流通した。やがて綿織物はヨーロッパにも輸出されるようになる[151]。
東南アジア

11世紀に中国の宋が海上貿易に進出し、東南アジアにも影響を与えた。南シナ海ではチャンパ王国で沈香の輸出が盛んになり、東インドネシア海ではフィリピンの三島、ミンドロ島の麻逸国、ブルネイの渤泥国が中継貿易を行う。クメール王朝は大陸の産物を輸出して、ジャワのコショウの流通はインド人、ジャワ人、マレー人、中国人が手がけた。モルッカ諸島の香料は、ジャワを経由してインドや中国方面へ運ばれた[24]。
マレー半島の都市であるマラッカは、季節風の交差地点であるためインド洋と東南アジアをつなぐ中継地となり、14世紀にタイのアユタヤ王国から独立してマラッカ王国が成立した。マラッカ王国はアユタヤ王国との戦いにおいてイスラームが広まり、イスラーム商人が進出して中継貿易がさらに栄える。貿易の増加にともない、外国商人にシャーバンダルという役職を定め、出身地別に4人を任命して外国商人の管理にあたらせた。のちにマラッカはポルトガルに占領されるが、ポルトガルの占領政策でイスラーム商人の多くは去り、アチェ、アユタヤ、ジョホールへ移住した[152]。
ヨーロッパ
南ヨーロッパ

イタリア半島では、ヴェネツィア共和国、ジェノヴァ共和国、フィレンツェ共和国、ピサなどの都市国家や自治都市がビザンツ帝国やイスラーム世界と貿易をして栄えた。特にヴェネツィアは海上交易が必須とされる地理にあり、早くから生活のための食料貿易や漁業、塩業を行った。ヴェネツィアは国営のガレー船が定期航海をして高価軽量の商品を運び、私立造船所で建造した帆船でかさばる商品を運んだ。ビザンツ帝国法の影響を受けた商業金融としてコレガンツァが生まれ、コレガンツァによって能力のある者が資本を調達して商人となる機会が増えた。工芸や手工業も栄え、フィレンツェではイギリスから羊毛を輸入して毛織物を輸出し、ヴェネツィアではヴェネツィアン・グラスが発達した。十字軍の費用をイタリア都市が出したことがきっかけで、イタリア商人は北西ヨーロッパにも進出した。商人たちが安価な保護費用で活動できる都市は成長し、ノルマン王国が商人に重税を課したアマルフィのような都市では貿易は衰退した。ヴェネツィアが香辛料貿易で得る利益は他国に注目され、地中海以外の航路開拓のきっかけとなる[40]。
貿易と金融を行う商業組織であるコンパーニアの支店が各地に広まるにつれて、管理が複雑化する。13世紀には財務管理のために複式簿記が導入され、14世紀には北西ヨーロッパでも使われるようになった[注釈 12][153]。
アンダルス
イスラーム帝国のウマイヤ朝の王族は、アッバース家との争いで西方へ逃れる。ウマイヤ朝は北アフリカからジブラルタル海峡をへてイベリア半島の西ゴート王国を征服して、後ウマイヤ朝が成立した。イベリア半島はアンダルスと呼ばれ、イスラームの農耕技術や貿易で繁栄した。首都のコルドバは最盛期に人口50万人を超え、ヨーロッパの大都市となった[154]。イスラーム政権下では、ズィンミーの制度でキリスト教徒とともにユダヤ教徒も保護されたため、ユダヤ商人がヨーロッパ各地から移住した。さまざまな奢侈品のほかに奴隷も貿易品となり、ヨーロッパ人の奴隷であるサカーリバも多数にのぼった。レコンキスタによってキリスト教国が成立すると、ユダヤ人はイベリア半島から各地へ移住してセファルディムとも呼ばれた[155]。
東ヨーロッパ
ビザンツ帝国では、コンスタンティノープルが陸海のルートの中心として貿易を行った。ただし、古代ローマからの伝統で、商売は自由人にはふさわしくないとされた。元老院身分をはじめとしてビザンツ帝国のエリートは土地に投資して、商業には関与しなかった。国家にとって必要物資とされた金、塩、鉄、貝紫色に染めた絹、兵器であるギリシアの火は輸出を禁じられており、絹は外交の贈与貿易に用いられた。そうした商業観がありつつも、エフェソスをはじめとして定期市は毎年開催された。7世紀にはロードス海法が定められて海事法が整備され、輸送で損害をこうむった商人は船主から補償額を受け取れるようになった。東ローマの法律は、ヴェネツィアにも影響を与えた[156]。

ルーシ北部では、8世紀のハザール王国がヴォルガ川、カスピ海、アゾフ海の貿易ルートを押さえてヴォルガ・ブルガールを支配した。9世紀には、水上交易路としてヴァリャーグからギリシアへの道が確立して北欧との交通が盛んになり、ルーシ人が建国したルーシ・カガン国にはヴァイキングも含まれていたとされる。9世紀にヴォルガ川流域の貿易が弱まるとドニエプル川が重要となり、キエフ大公国が栄える。12世紀からキエフは政治的に分裂して、その中でもノヴゴロド公国はバルト海、黒海、ルーシ、中央アジアの中継貿易を行い、民会による共和制的な運営がなされた。ノヴゴロドは蜜蝋や毛皮を輸出してイヴァン商人団が力を持ち、スウェーデン、デンマーク、ハンザ都市からの商人が琥珀、ラシャ、装飾品や塩を輸入した。ノヴゴロドでは当時の商業文書にも用いられた白樺文書も発見されている[157]。
14世紀からはモスクワ大公国が領土を拡げる。モスクワの輸出品はテンやオコジョの毛皮と森林の物産で、ノガイ・オルダから馬を輸入して、ジョチ・ウルスにも商人を送った。やがてバルト海のハンザ商人はロシアにとって障害と見なされて、1494年にロシアがノヴゴロドを併合するとハンザ商館は閉鎖され、代わってオランダとイギリスが進出する。ロマノフ朝初期の動乱の時代には、政府の許可を受けたオランダやイギリスの商人が工場建設にも乗り出し、ロシア商人は外国商人の排除をうったえる。ロシアの大商人はゴスチと呼ばれ、貿易や土地所有の特権を得るかわりに政府の代理として働いた[158]。
15世紀にはオスマン帝国がビザンツ帝国を征服する。オスマン帝国は、ヨーロッパ人にカピチュレーションという特権を与えて貿易と居留の自由を与えた。ただし、ヨーロッパ商人の活動は居留地のある港市に限定され、そこから出る際にはイスラーム法官であるカーディーの許可が必要だった。そのためヨーロッパ人は現地に詳しいアルメニア人たちに及ばず、オスマン帝国に開放政策を迫ることになる[89]。
西ヨーロッパ

西ヨーロッパではローマ時代からヴィクと呼ばれる交易地が点在して、北方ではフリースラント人が遠距離貿易を行った。フランク王国のもとで貨幣や市場の制度が定められ、教会の所領で定期市が開かれた。キリスト教が浸透するとワインの消費が増え、サン=ドニ修道院の所領ではワインなど各地の物産が取り引きされ、中世初期の国際市場としてよく知られていた[159]。ユダヤ人、ザクセン人、シリア人の商人が貿易を行い、地中海のオリーブ油や東方の香辛料、絹織物を輸入した。輸出されたのはヨーロッパ各地の毛皮や奴隷であり、ヴェルダンは奴隷を去勢してアンダルスへ送る拠点となった。カロリング朝で保護された商人は、王から委託を受けて貿易をするかわりに流通税、軍役、徴発などを免除され、私貿易も行った。修道院では荘園の産物を販売しており、修道院の使用人にあたる商人が請け負った[160]。
12世紀になると、商人や職人の相互扶助団体であるギルドが都市において発言力を強め、有力な商人や職人は都市の政治に参加した。商人の同盟だったハンザがリューベックを中心に都市同盟に成長して、200近い都市が参加した。ドイツ・ハンザや、北フランスを中心とした17都市ハンザ、ロンドンにおけるロンドン・ハンザなどがバルト海と北海を南ヨーロッパに結びつけ、コグ船で木材や穀物を運んだ。13世紀には羅針盤や羅針儀海図、航海日誌が普及して、航海術の向上は南北の海上貿易を統合した[161]。年市とも呼ばれる定期市で毛織物、ワイン、絹、香料などの貿易品が取り引きされるようになり、イングランドのスターブリッジの市、フランドルのシャンパーニュの大市などが開催された[162]。フランドル伯領では5つの都市で年市が開かれており、その一つであるブリュージュが南北の中継貿易でネーデルラントに繁栄にもたらして、イタリアから金融技術が伝わった。ブリュージュでは商工業者のためのオランダ語とフランス語の2カ国語の手引書として、1369年頃に『メティエの書』が編纂された。この手引書は19種類の毛織物、各地のワイン、食べ物、家財道具、ギルド名称、商人や職人の挨拶、数詞などが分かるようになっている[35]。
北ヨーロッパ

スカンディナヴィアでは贈与貿易が盛んであり、ヴァイキング時代に入ると、東方との交流がきっかけで銀を多用する貿易へと変化が起きる[注釈 13]。装飾品や副葬品のために銀の蓄蔵を積極的に行い、羊毛、毛皮、奴隷を輸出した。ヴァイキングは8世紀にはヴォルホフ川流域やスターラヤ・ラドガに現れ、9世紀には水上交易路であるヴァリャーグからギリシャへの道を開拓した。河川ぞいにドニエプル川から黒海やコンスタンティノープル、ヴォルガ川からカスピ海へと移動して、ビザンツ帝国のスラヴ人やイスラーム帝国の商人と取り引きを行った。遠征先で定住する者もおり、ルーシ・カガン国の住人にはヴァイキングも含まれていたとされる。河川での移動には、ロングシップよりも小型のクナールを用いた[163]。
9世紀のバルト海沿岸や、交易港であるビルカ、ヘーゼビュー、ゴットランド島では、西ヨーロッパの硬貨よりも精度が高いウマイヤ朝の分銅が普及した[164]。アイスランドでは14世紀から干しタラが名産品となって、ドイツ・ハンザ商人がヨーロッパ各地に輸出した。保存食として優れた干しタラはカトリックの食習慣にも適していたため、スペインやポルトガルの植民地となったメソアメリカや南アメリカにも輸出された。のちにはイギリスからも漁船が訪れるようになり、イギリスとハンザ商人の間で漁獲をめぐる対立が起きた[37]。
中央アジア、北アジア
シルクロードのイスラーム化
ウマイヤ朝は、シルクロードのオアシス地帯であるマー・ワラー・アンナフルを征服して、オアシス国家は唐に支援を求めた。唐は遠征軍を派遣するが、指揮官の高仙芝がオアシス国家の財宝を略奪したために不評を買って唐軍は孤立して、タラス河畔の戦いでアラブ軍に大敗する。シルクロードは次第にイスラームの貿易ルートとなり、都市もイスラーム化が進んでモスク、マドラサ、スークをそろえた街並みとなっていった。また、唐軍からの捕虜に紙漉きの職人がいたため、製紙法が伝わってサマルカンドにイスラーム世界初の製紙工場が作られた。アッバース朝と唐の対立に加えて、ウイグルや吐蕃などの遊牧民によって8世紀後半にはシルクロード貿易は不安定となる。そのためペルシア湾から中国へ至る海上貿易ルートが増加した[注釈 14]。養蚕の技術がペルシアに伝わって絹織物工業が盛んになったことも、シルクロード貿易の縮小に影響を与えた[165]。
トルコ系遊牧民
9世紀のマー・ワラー・アンナフルにはサーマーン朝が建国され、ソグディアナのブハラを首都として積極的な貿易を続けた。シルクロード以外の陸路も開拓され、カザフスタンのトルコ系遊牧民との貿易が盛んになる。家畜、毛皮、皮革、乳製品、宝石が取り引きされ、特にマムルークと呼ばれるトルコ系の白人奴隷はサーマーン朝の重要な財源とされた。マムルークはイスラーム世界で優れた軍人として重用され、マムルーク朝の成立へとつながる[165]。トルコ系遊牧民は中央アジアで増加を続け、オアシス国家の農耕民として定住して、のちにトルキスタンと呼ばれるようになる[166]。ヴォルガ川流域で貿易ルートの開拓が進むと、北方のルーシや、北ヨーロッパのヴァイキングとの交流も増加した。
シルクロード東端
10世紀の河西地方は吐蕃やウイグル諸国が馬の名産地となり、中国と絹馬貿易を行った。吐蕃の諸部族によって涼州や汾州が不安定になってからは、中国の直轄地として節度使が置かれている北方の霊州へと迂回するルートが用いられた[167]。11世紀にはチベット系民族のタングートが西夏を建国して、霊州の貿易ルートを支配する。西夏は隣国である遼に朝貢を行って中国の宋に対抗した。西域のウイグル人諸国も遼と管理貿易を行い、400人以上の大規模な隊商を3年に1度組織して翡翠、乳香、琥珀、サイの角などを送った[168]。ウイグル商人は河西、オルドス、山西から華北のルートにも進出して、遼や金では貿易品によって中国文化の流入も進んだ。12世紀以降の中国王朝は主に北京が首都とされたため、華北のルートの重要性が増した[169]。
モンゴル帝国のシルクロード統一
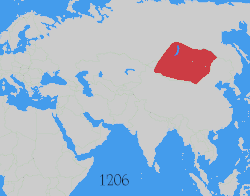
13世紀に入ると、シルクロードはモンゴル帝国の支配下に置かれる。モンゴリアを統一したモンゴル帝国は、イランのイスラーム王朝であるホラズム・シャー朝を攻める。モンゴルは当初はホラズム・シャーのもとにラクダ500頭の隊商を送るが、スパイの疑いをかけられて隊商が殺害されたため、モンゴルのホラズム・シャー朝征服が起きた。モンゴル帝国の征服は続き、東アジアから東ヨーロッパに及ぶ広大な領域を支配下に収めた。それまでのシルクロードは、東西で大きく勢力が分かれていたが、モンゴル帝国のもとで初めて統一された。モンゴル帝国はジャムチという駅伝制を定め、30キロから50キロ間隔で駅が置かれて、通行証として牌子を発行した。牌子の所持者は通行の安全が保証されるのに加えて、賦役や地方税が免除された。モンゴルの駅伝制はクビという再配分の制度から発祥しており、各地で得られた戦利品や富を輸送するためのものだった。再配分の物資を送る道は、交易路としても活用が進むようになる。クビの制度は人材の分配にも適用されて、多数の商人、使節、技術者が東西を移動した。モンゴルの整備された駅伝の様子は、ヴェネツィアからの旅行者であるマルコ・ポーロも記している[170]。
東アジア
宋の貿易と華僑
宋の時代から羅針盤が使われるようになり、航海技術が向上した。この時代の海商は、各国の権力者や大商人の代理として取り引きを行った。北宋ではジャンク船が建造され、官船は500トン、民間船は300トンが用いられた。航路が整備され、泉州を出発した船がマレー半島で積荷の3分の1を下ろしてからパレンバンへ向かうといった航程が可能となる。そのため12世紀から東南アジアで海商が活動して、1回の航海に長期間をかけて各地を巡った。南方航海から長期間帰らない者は住蕃と呼ばれ、福建からは北ベトナムに海路や陸路で移住する者も増えて、華僑の始まりとなった[171]。華僑の商人は、特に華商と呼ばれる。
中国では銅貨が伝統的に流通しており、宋に入ると大量の宋銭が作られた。宋銭は周辺諸国にも広まり、朝鮮半島の高麗以降、日本の平安時代後期以降、ベトナムの安南などでも用いられた[172]。華北が金に征服されて南宋の時代になると、貿易が国家収入で大きな割合を占めた。貴金属や宋銭の流出を防ぐために、陶磁器や絹との交換で決済したために陶磁器の輸出が急増した[173]。中国に移住したアラブ、ペルシア、トルコ系の人々は回民と呼ばれ、アラブ系の蒲寿庚のように巨富を得て活躍したイスラーム商人は、のちの元の時代でも重用された。日本では禅僧が南宋から元の時代に数百人以上が留学して、大陸との外交や貿易にも参加した。禅僧の書簡である禅林墨跡には、12世紀から14世紀の日宋貿易の記録も含まれている[174]。
元と東西貿易の統一

13世紀にモンゴル帝国が南宋を征服して、クビライによって元が成立する。クビライは貿易を盛んに行い、オルトクという制度で商人に貿易や財政を任せた。オルトクはウイグル人やイスラーム商人を中心としており、もともとは内陸の遊牧民と商人が協力をするための制度であった。沿岸都市が元の支配下になるとオルトク商人も海上貿易に進出して、漢人からも楊氏のようなオルトクが輩出された。同じモンゴル政権のイルハン朝が西アジアに成立して西方との貿易が増えると、元のオルトク商人は南シナ海を経由してインド洋へ進出し、イルハン朝のオルトク商人はインド経由で南シナ海に向かう。こうして、モンゴル帝国によってユーラシアの東西が貿易ルートでつながった。朱清や張瑄などの海賊や塩商だった者も漕運を任されて官位を得て、中央アジア出身でオルトクを管理するシハーブ・ウッディーン(沙不丁)との対立も起きる。このような新興の富豪は官豪勢要とも呼ばれた[175]。
元は交鈔と呼ばれる紙幣と、銀錠という銀貨による貨幣制度を定めた。国内では貴金属の私的な流通を禁じて交鈔を流通させ、銀錠でオルトク商人が管理貿易を行なった[176]。陶磁器は宋に続いて重要な輸出品であり、絹織物の製法も発達して、泉州(ザイトン)を由来としたサテンの名が生まれてヨーロッパに伝わった[注釈 15]。印刷や羅針盤などの技術も、この時期に西方へ伝わった[170]。元による東西交通の活発化は病原菌の伝染も容易とし、14世紀のペストの大流行をもたらした[177]。
明の海禁と朝貢

明が成立すると海禁の政策をとり、私的な貿易を取り締まった。海禁は大きな反発を呼び、倭寇と呼ばれる集団が増加した。倭寇は日本、朝鮮、中国の沿海部の出身者を中心としており、対馬、壱岐、松浦、済州島、舟山列島を根拠地とした。倭寇は密貿易や海賊を行い、売買のために奴隷を捕獲する者もあった。倭寇対策をめぐって室町幕府と李氏朝鮮のあいだで交わされた朝鮮通信使は、のちの江戸幕府では数少ない正式な外交使節にもなった[178]。密貿易の増加にともない、それまで内陸で活動をしていた徽州商人が海上貿易に参加するようになり、博多や平戸でも取り引きをする王直らの登場につながった[179]。
明は海禁の一方で、永楽帝の時代に冊封体制の拡大を計画して、鄭和の指揮のもとで西方への航海が行われた。鄭和の大航海は、『明史』によれば「西洋下り」とも呼ばれ、1405年から1433年にかけて7回に渡って行われ、大艦隊がインド洋を横断して東アフリカまで到達した。朝貢国は非関税で明と貿易ができたが、回賜の増加は明の財政を圧迫するとして批判もあった[114]。

明の朝貢において優遇されたのは、沖縄の琉球王国だった。1383年に明は琉球に大型船を提供して朝貢が頻繁になり、華人が琉球に移住して久米三十六姓と呼ばれ、朝貢は華人たちが担当した。久米三十六姓の人々が住む場所は大明街と呼ばれ、福建には滞在用の琉球館が建設された。琉球には朝貢の回数制限がなく、一国で複数の朝貢主体が認められるという特例もあった。これは倭寇の対策として琉球の貿易を活発にして、民間貿易の受け皿にするという明の政策が関わっていた[180]。琉球は小型の馬と、硫黄鳥島の硫黄を送り、そのほかにコショウや蘇芳を東南アジアのマラッカ王国などから調達して送った[181]。琉球は他の朝貢国とも貿易を行い、朝鮮とは高麗の時代に交流が始まり、日本からは博多や堺の民間商人も訪れた。琉球の朝貢は、明の時代から400年以上続いた[182]。
陶磁器貿易
宋の時代に景徳鎮、龍泉、福建などが名産地として知られるようになった。元の時代には、食器を中心に大型化して好評を呼んだ。これはモンゴル人やイスラーム教徒が大勢で取り分ける食習慣を反映したもので、イスラーム法で金銀の食器が使えない点も普及につながり、特に龍泉窯青磁は西アジアでも愛好された。新安郡で発見された沈没船(新安沈船)は1323年頃のもので、陶磁器は龍泉窯青磁、景徳鎮窯や福建の白磁と青白磁を中心に2万点以上が積まれており、大量の輸出を示している[173]。中国の陶工は輸出先の好みに合わせて工夫を加え、西アジア向けの作品には青い顔料のためにペルシアからラピスラズリを輸入した。明の時代には、ヨーロッパへの輸出も始まる[173][183]。
貿易の案内書
宋・元・明の時代には、アジア海域の案内書が多く書かれた。著者は地方官や外交使節とそのメンバーである。内容は多岐にわたり、航程と日程、位置と国情、地理、民族や信仰、婚姻習慣、貨幣と度量衡、唐貨(中国の物産)と土貨(現地の物産)、朝貢関係の有無、華僑の有無などが記されている。また、カンボジア、シャム、福建や広東では女性が交易の取り引きを行うといった商習慣も注目された。元の汪大淵が、泉州からインド洋沿岸をめぐって書いた『岛夷志略』が有名である[184]。
アフリカ
北アフリカ、東アフリカ
ウマイヤ朝の時代にはエジプトのフスタートが貿易都市として繁栄して、バグダードを首都とするアッバース朝が成立するとアラビア海近辺の貿易ルートはペルシア湾経由が増え、カイロを首都としたファーティマ朝が成立すると紅海経由が増えた[185]。紅海の出入口にあたるイエメンの商人が東アフリカに進出して、キルワ、モガディシオ、モンバサなどの都市が成長した[186]。地中海沿岸では、イスラーム商人が港湾都市のベジャイア、アルジェ、オランを建設して、代理人であるワキールは各地に商館を建てて、遠方からの依頼で取り引きを行った。15世紀には、中国の明が鄭和の指揮する艦隊を派遣して、東アフリカにも来航している[187]。西アフリカのサハラ交易で入手された金は、地中海沿岸へと運ばれた。エチオピア原産のコーヒーノキは、イエメンでも栽培されてイスラーム世界で飲まれるようになり、イランやインドへと産地が広まる。イエメンは15世紀からコーヒーの世界的な輸出港を持ち、やがてカイロの商人もコーヒー貿易に進出して、コーヒーの習慣はトルコをへてヨーロッパでも流行する。ヨーロッパ向けの船が寄港するモカは、のちにコーヒーのブランド名の由来になった[188]。
西アフリカのサハラ交易
西部のニジェール川流域では、中流の内陸デルタの都市であるジェンネが古くから栄え、サハラの銅やサバンナからの金を運ぶサハラ交易が行われていた。アラブ・イスラームの進出以前は、ベルベル人が貿易に携わっていた。7世紀から北アフリカにラクダが導入されると、イスラーム商人の隊商が盛んになる。地中海沿岸のアラブ人はサハラ砂漠の彼方をスーダン(黒人の国)と呼び、ニジェール川流域は西スーダン、チャド湖近辺は中央スーダン、ナイル川上流を東スーダンと呼んだ。サハラ砂漠からは岩塩が運ばれてニジェール川流域の金と取り引きされ、地中海へ金が運ばれた[189]。また、イスラームの影響でコーラの実も嗜好品として流通した。ベルベル人はイスラームへ改宗して、アラブ人が来たのちもサハラ交易の取り引きを主導した。北からのベルベル人のほかに、マンデ系のワンガラ族やジュラ族が活動した。コーラの実がとれる森に沿ってジュラ商人の街も建設されて、交易網を緊密にした[190]。

貿易ルート沿いの王国は商人の保護と課税によって経済的基盤を得る一方、イスラームへの改宗も進んだ。主な国としては8世紀から記録があるガーナ王国、13世紀のマンデ人のマリ王国、水運を支配した15世紀のソンガイ王国がある。ガーナ王国の首都はイスラーム教徒の居住地と王の土地に分かれており、セネガル川上流から金が産出された。以後、金の産出地は東へと移ってゆく[191]。マリの王は大規模なキャラバンでマッカ巡礼を行い、中でもマンサ・ムーサは8000人以上を率いたとも言われており、新しい交易ルートの開発も目的だったとされる。ルート上に点在する都市も繁栄して、特にトンブクトゥは有名となった[192]。
中部アフリカ
11世紀から13世紀にかけてザンビアとインド洋をつなぐ貿易ルートが確立して、コンゴ川の河口部にコンゴ王国、上流部にはルンダ王国や、ルバ族のルバ王国が成立した[193]。ルバ王国は鉄、銅、塩を輸出して、コンゴ王国ではポルトガルとの奴隷貿易を行った。アフォンソ王時代のコンゴ王国は戦争の捕虜を輸出していたが、アメリカでプランテーションの労働力が求められるにつれて奴隷の輸出は激増して、地域間の紛争とともにコンゴ王国の衰退を招いた[194]。
南部アフリカ
南部のザンベジ川とリンポポ川の流域では、10世紀からショナ人によって金の採取や採掘が盛んとなる[195]。貿易ルートはインド洋と結びつき、14世紀に最盛期を迎えたグレート・ジンバブエではイスラーム商人と取り引きをした。輸出品としては塩、金、象牙などかあり、遺跡からは中国の元や明の陶器、キルワの金貨、そのほかの輸入品が発見されている[196]。
15世紀にはグレート・ジンバブエの建築文化を引き継ぐモノモタパ王国が建国され、交易港のソファラからインド洋に向けて金や銅を輸出して、16世紀からはポルトガルと通商関係を結ぶ[197]。16世紀はトルワ王国、17世紀のチャンガミレ王国といった国々も興り、ポルトガルと貿易や戦争を行った[198]。
ヨーロッパとの海上貿易

1415年にポルトガルのアヴィス朝がジブラルタル海峡のアフリカ側に進軍して、スーダンからの金が集められていた貿易港のセウタを占領した。これがポルトガルによるインド航路開拓のきっかけであり、ヨーロッパの大航海時代の先駆けとなった。ポルトガルのエンリケ王子はセウタの防衛を任され、アフリカ西海岸の貿易独占権を得てから、アフリカの金とインド洋の香辛料を求めて航海事業に力を入れる。15世紀のポルトガルはヨーロッパの他国に比べて戦争や内乱による混乱がなく、ヴェネツィアと競争関係にあるジェノヴァからの投資も受けた。この頃、クリストファー・コロンブスは西インド航路の開拓をポルトガルに提案したが受け入れられず、スペインのカスティーリャ王国に雇われることとなる。ポルトガルのキャラベル船はアフリカ西海岸沿いに南下して航路の開拓を進め、1488年にはバルトロメウ・ディアスがアフリカ南端を通過して帰路に喜望峰を発見した。ポルトガルに続いてイギリス、フランス、オランダもアフリカを南下して、海岸沿いには各国の城砦が貿易拠点として建設された。当初はヨーロッパの金属製品とアフリカの金、象牙、胡椒などが取り引きされていたが、16世紀には大西洋の奴隷貿易が主流となる[199]。
アメリカ
プトゥン人

古典期のマヤ文明が崩壊したのちは、低地でプトゥン人が遠距離の海上貿易を行い、内陸の交易ではチチェン・イツァが8世紀から10世紀にかけて中心地となった[200]。海上ではカヌーを用いて、16世紀頃にはユカタン半島の北海岸や東海岸を通ってタバスコ州からベリーズやホンジュラスまでをつなぐ沿岸交易ルートがあった[201]。交易港にはシカランコ、コスメル島、トゥルム、ニトなどがあった。品物には、ユカタン半島の北部では蜜、塩、奴隷などを輸出し、マヤ南東部ではカカオ、翡翠、黒曜石、銅が輸出された。ほかに土器、トルコ石、金などもあった[200]。
アステカ
メキシコ高地のアステカは、テノチティトラン、テスココ、トラコパンの3都市の同盟を中心として、首都にあたるテノチティトランと姉妹都市である商業都市トラテロルコではポチテカと呼ばれる特権商人が遠距離貿易を独占した。ポチテカはすでに14世紀にはトラテロルコで活動しており、世襲制のギルドを組織して、メシコ各地へ出向いて取り引きをする他に諜報活動も行ってアステカの征服の一端を担った。ポチテカの扱った品物には、羽毛材として装身具に使うケツァールの羽、貴重な嗜好品で貨幣でもあるカカオ、宝石、貴金属、ジャガーの皮、奴隷などがある。カカオはのちにチョコレートの原料としてヨーロッパ向けの輸出品となる[202]。
南アメリカ
8世紀から14世紀にかけて、ペルーの北海岸でシカンが栄えた。シカンは灌漑農耕を行い、金属工芸品を制作して交易に用いた。金属製品に優れ、特に金製品はマスク、王冠、グローブ、イヤリングなど多岐にわたる。砒素青銅の製品は長距離交易で輸出され、斧型のものは貨幣に用いられた可能性もある。ウミギクガイ、紫水晶、エメラルドも発見されており、エメラルドはコロンビアからの輸入品とも言われる。ペルーのチンチャ地方やエクアドルには海上貿易を行った商人もいた[203]。
15世紀にアンデスを統合したインカは、アンデスで伝統だった垂直統御を引き継いで精緻にした。交通ではインカ道とも呼ばれる交通網と駅伝制を整備して、タンプと呼ぶ宿駅を一定間隔で建設して物資を保存した[204]。険しい地形のために水運や車輪ではなく人力とリャマで輸送をしたため、かさばる物品の長距離輸送は困難となった。インカは植民制度であるミトマクで住民の移住を進めつつ、インカ以前から活動していたエクアドルやチンチャの特産品を扱う商人は存続された[205][206]。
高原地帯のアルティプラーノ周辺の熱帯林には、葉に覚醒作用があるコカノキが生息しており、贈与や貢納、儀式に用いられた。コカの葉は、チチカカ湖沿岸のティワナクでは疲労回復に用いられ、インカでは貢納されたコカの葉を臣下に再分配していた。のちにコカの葉は世界的な商品となる[207]。
ヨーロッパ人の到着
ポルトガルのアフリカ周航ルートに対して、スペインでは別の航路の開拓が検討された。コロンブスは1492年に西回りのインド航路を開拓するために航海をして、大西洋を横断して現在のバハマに到達した。1500年には、ポルトガルのペドロ・アルヴァレス・カブラルがアフリカ周航ルートから外れ、現在のブラジルに漂着した[208]。
注釈
- ^ プランテーションの作物としては、サトウキビ、コーヒーノキ、綿花、タバコ、ゴムノキ、アブラヤシなどがある。
- ^ ホメーロスの叙事詩『イーリアス』と『オデュッセイア』には、フェニキア人が人さらいの海賊まがいとして描かれている[64]。
- ^ 国内のアゴラの穀物価格は公定価格が維持されていたが、紀元前4世紀にアテナイの海上支配が衰えると、エンポリウムの貿易では穀物価格が高騰して、アゴラの価格にも影響を与えた[67]。
- ^ アテナイの喜劇作家アリストパネスの戯曲『アカルナイの人々』では、ペロポネソス戦争の最中に敵国と単独和平をして貿易で儲ける人物が登場して、戦争に積極的な有力者と対照的に描かれている[69]。
- ^ ペトロニウスの小説『サテュリコン』に登場する解放奴隷のトリマルキオが、貿易で成功したのちに土地所有者に転じているのも、こうした価値観の表れとされる[73]。
- ^ 紀元前3千年紀に編纂されたギルガメシュ叙事詩には、英雄ギルガメシュがレバノンスギを手に入れるエピソードがあり、当時の事情を表しているとされる[81]。
- ^ 南インドのシャンガム文学の叙事詩にはヤヴァナの貿易活動も謳われた[98]。
- ^ 絹馬交易という語は、松田壽男によって考案された[108]。
- ^ 唐物は、『竹取物語』、『うつほ物語』、『源氏物語』などの文学にも描かれている[122]。
- ^ 中世に成立した説話集である『千夜一夜物語』には、バスラの船乗りで海上貿易を行ったシンドバードをはじめとして、8世紀から9世紀にかけての広範な貿易ルートをうかがわせる物語が収められている。
- ^ フィレンツェの作家であるボッカチオの『デカメロン』には、商人と海賊を兼業して利益を得た話が収められており、当時の生活を反映していると言われる[137]。
- ^ 中世のヴェネツィアにおける貿易を題材とした作品として、シェイクスピアの戯曲『ヴェニスの商人』が有名である。
- ^ 北欧の叙事詩を収めたサガや、北欧神話の歌謡集『エッダ』には、贈与が重要な役割を果たす逸話が多く残されている。
- ^ 地理・歴史学者であるアブー・ザイドの『シナ・インド物語』やマスウーディの『黄金の牧場』には、内陸の商人たちが海路で広州などへ向かった様子が記されている。
- ^ ボッカチオやチョーサーはこれをタタールの織物やタタールのサテンと表現している。
- ^ オランダのデルフトに住んでいた画家ヨハネス・フェルメールの作品『兵士と笑う女』には北アメリカのビーバーの毛皮帽子、『地理学者』には和服が描かれており、当時のオランダの繁栄がうかがえる[215]。
- ^ オランダ東インド会社の資本金は650万グルデンで株主は有限責任制だった。対するイギリス東インド会社の第1航海の起債は6万8000ポンド(約53万グルデン)だった。
- ^ ネイボッブには帰国後に腐敗選挙区から下院議員に当選する者も出て批判の声があがり、東インド会社の独占廃止と第1次選挙法改正 (Reform Act 1832) につながった[221]。
- ^ マデイラ諸島、カボヴェルデ、サントメに植えたサトウキビは地中海よりも育ちがよかった。
- ^ イギリスのダニエル・デフォーによる小説『ロビンソン・クルーソー』の主人公も、ブラジルに農園を持つ奴隷商人だった[229]。
- ^ オラウダー・イクイアーノやフレデリック・ダグラスは作品を通して奴隷制度の廃止を訴えた[230]。
- ^ 東南アジアやスリランカの胡椒・丁子・ナツメグ・メイス・シナモンが主な商品だった[233]。
- ^ アラビア半島の乳香・馬、東アフリカの金・象牙、ペルシアの絹織物・絨毯などが主な商品だった[233]。
- ^ サンレイとは中国語の生利(shengli)、商旅(shanglu)などを由来とする説があり、パリアンとはタガログ語で駆け引きが行われる場所を意味した[237]。
- ^ アメリカの小説家ジャック・ロンドンの短編集『南海物語』や、イギリスの小説家サマセット・モームの『作家の手帳』には、契約年季労働者やブラックバーダーの様子も描かれている。
- ^ ペート建設で得られる市場長や市場書記のワタン(vatan)が目的であった。ワタンとは17世紀以降の西インドにおける世襲の家職・家産であり、商品経済の浸透にともなって新しいワタンが作られていった[257]。
- ^ イギリスでは1700年にはキャラコ禁止法、1720年にはキャラコ輸入禁止法が成立し、イギリスの繊維業者が保護された。
- ^ 強制栽培は当時からオランダでも問題視されており、エドゥアルト・ダウエス・デッケルは、ムルタトゥーリのペンネームで小説『マックス・ハーフェラール』を発表して、強制栽培制度を告発した[266]。
- ^ のちに20世紀アメリカの作家アレックス・ヘイリーは、ガンビアからアメリカへ運ばれた祖先の体験をもとに小説『ルーツ』を書きベストセラーとなる。のちにテレビドラマ化もされた。
- ^ ジャーナリストのエドモンド・モレルの『赤いゴム』、作家ジョゼフ・コンラッドの『闇の奥』、マーク・トウェインの『レオポルド王の独白』には、自由国時代のコンゴが描かれている[299]。
- ^ フランス人はインヌ族やアルゴンキン語族を支持する一方で、イギリス人はイロコイ連邦を支持しており、フランス対イギリスの代理戦争の面もあった[309]。
- ^ ナチス・ドイツはアドルフ・ヒトラー内閣が自給自足政策を進めたが、食糧や石油をはじめ国内での自給は不可能であり、のちにアメリカが保護貿易政策をとった点も影響して行き詰まった[318]。
- ^ 世界経済を工業製品の先進国と一次産品の途上国に二分して考えると、工業製品は技術革新や新製品があるため所得が上がりやすいが、一次産品は相対的に工業製品と比べて不利となる。そこで、一次産品価格を引き上げて工業製品の価格にリンクしつつ、先進国からの援助も含めて途上国の工業化をすすめることが目標とされた[334]。
- ^ HPAEsは大きく3つに分かれ、第1は日本、第2は1960年代の香港、台湾、韓国、シンガポール、第3は1970年代と1980年代のマレーシア、タイ、インドネシア、中国となる。
- ^ 貿易面での構造調整プログラムは、輸出の促進による国際収支の改善を目的としたが、輸出品目の多様化を進めなかったため国際価格が低落し、公定価格の撤廃などが影響して農民の生活は改善されなかった。地元の民間資本や企業家が育っていない中で公共部門の民営化は、外資系企業による支配の強化や民族対立にもつながった[350]。
- ^ 日本の輸出は、1960年代の繊維や鉄鋼、1981年の自動車の輸出自主規制、1986年の工作機械の輸出自主規制などを起こした。日本の輸入に関しては、1970年代の牛肉やオレンジ、1980年代の半導体、米、スーパーコンピュータ、1990年代のフィルム・印画紙などが問題とされた。
- ^ トヨタ自動車は全世界の生産が22%減少し、ソニーは26億ドル、東芝は28億ドル、パナソニックは38億ドルの損失となった[367]。
出典
- ^ a b c 山本 2000.
- ^ キンドルバーガー 2014, 第3章、付録B.
- ^ ポランニー 2005, p. 159.
- ^ コトバンク「交易」世界大百科事典 、精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説より
- ^ グリアスン 1997.
- ^ 瀬川 2013.
- ^ 鶴見 1987, p. 114.
- ^ サーリンズ 2012.
- ^ マリノフスキ 2010.
- ^ 角谷 2006, pp. 161–164.
- ^ モース 2009, 第4章第3節.
- ^ ポランニー 2005, p. 180.
- ^ 生田 1998, p. 125.
- ^ 丸山 2010, p. 266.
- ^ 濱下 1997, pp. 60–61.
- ^ ポランニー 2005, pp. 491–493.
- ^ 角谷 2006, p. 160.
- ^ 栗本 2013, pp. 732-752/3838.
- ^ 栗本 2013, pp. 735-740/3838.
- ^ 安野 2014.
- ^ 栗本 2013, pp. 735-746/3838.
- ^ 大津, 常木, 西秋 1997, p. 109.
- ^ 長澤 1993, pp. 35–37.
- ^ a b c d 桜井 1999.
- ^ 上田 2006.
- ^ ポメランツ 2015, p. 304.
- ^ 長澤 1993, p. 22.
- ^ リード 1997, 第1章.
- ^ 永田 1999.
- ^ 青山, 猪俣 1997, p. 7.
- ^ a b ポメランツ 2015, p. 195.
- ^ 橋本 2013, p. 213.
- ^ 湯川 1984, pp. 114–117.
- ^ a b 齋藤 2004.
- ^ a b 河原 2006, 第2章.
- ^ 鶴見 1987, p. 98.
- ^ a b 松本 2010.
- ^ 四日市 2008.
- ^ 上里 2012, p. 110.
- ^ a b c マクニール 2013, 第1章.
- ^ 栗本 2013, p. 107.
- ^ 清水 1984, p. 179.
- ^ 熊野 2003, 第2章.
- ^ 薩摩 2018.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, p. 231.
- ^ 服部 2002.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 242–243, 254–255.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 277–280, 285.
- ^ 高宮 2006, 第2章第4節.
- ^ 屋形 1998.
- ^ ポランニー 2005, pp. 422–428.
- ^ 蔀 1999, pp. 252–253.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, pp. 414–416.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 703–710, 774-780/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 881–894, 912-924/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1919-1932/8297.
- ^ クレンゲル 1991, 第2章、第3章.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, p. 31.
- ^ クレンゲル 1991, 第15章.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, p. 100.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, p. 36.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, p. 169.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, p. 50.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, pp. 139–140.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, pp. 136–137.
- ^ 前沢 1999, pp. 161–165.
- ^ 前沢 1999, pp. 166–168.
- ^ 前沢 1999, p. 162.
- ^ ポランニー 2005, pp. 326–329.
- ^ ポランニー 2005, pp. 237–239.
- ^ グリーン 1999, pp. 31, 90.
- ^ グリーン 1999, pp. 367–369.
- ^ 坂口 1999, p. 38.
- ^ 坂口 1999, pp. 30–32.
- ^ 蔀 1999, pp. 258–260.
- ^ a b 村川訳註 2011.
- ^ 東野 1997, pp. 59–60.
- ^ 長澤 1993, pp. 159–160.
- ^ 栗田, 佐藤 2016, pp. 106–108.
- ^ 佐藤, 池上 1997, 第2章.
- ^ a b 小林 2007, p. 171.
- ^ 小林 2007, p. 189.
- ^ 小林 2007, p. 141.
- ^ 小林 2007, p. 183.
- ^ 大村 2004, 第3章、第4章.
- ^ 明石 2015.
- ^ 長澤 1993, pp. 90–92.
- ^ 小林 2007, p. 175.
- ^ a b c 坂本 1999.
- ^ a b 遠藤 2013.
- ^ 小林 2007.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2458-2482/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, p. 2490/8297.
- ^ 宮内, 奥野 2013.
- ^ 木村 2013.
- ^ 山崎, 小西編 2007, pp. 100–101, 178–179.
- ^ 山崎, 小西編 2007, p. 278.
- ^ 蔀 1999, pp. 283–285.
- ^ 山崎, 小西編 2007, pp. 144–145.
- ^ 山崎, 小西編 2007, pp. 169–170, 178–179.
- ^ 生田 1998, pp. 第45-46.
- ^ 石澤, 生田 1998, 第4章.
- ^ 長澤 1993, pp. 55–56.
- ^ 長澤 1993, pp. 56, 60–62.
- ^ 長澤 1993, pp. 29–31.
- ^ 荒川 2010, 第1部.
- ^ 長澤 1993, pp. 72, 79–80.
- ^ 松田壽男 (1967-06-30). “縞馬交易と「偶氏の玉」 - 最古のシルク・ロードについて”. 東洋史研究 26 (1): 30-57.
- ^ 長澤 1993, pp. 108–110.
- ^ 長澤 1993, pp. 132–133, 138–140.
- ^ 荒川 2010, p. ).
- ^ 菊池 2009, 第5章.
- ^ 山田 2000, p. 13、19.
- ^ a b 濱下 1997.
- ^ 荒川 2010, 第10章.
- ^ 長澤 1993, pp. 270–272.
- ^ 長澤 1993, pp. 291–292.
- ^ 可児 1984, p. 2.
- ^ 東野, 2007 & pp146-148.
- ^ 東野 2007, pp. 154–156.
- ^ 東野 2007, pp. 51–52.
- ^ a b 河添 2014.
- ^ 青山, 猪俣 1997, p. 85.
- ^ 中村 2007, p. 227.
- ^ 中村 2007, pp. 175, 186.
- ^ 中村 2007, pp. 230–231.
- ^ 中村 2007, 第3章-第4章、第7章.
- ^ 大貫 1979.
- ^ 関 2010.
- ^ 家島 2006.
- ^ ウェザーフォード 2014.
- ^ a b 宮崎 1994, 第3章.
- ^ バットゥータ 1996.
- ^ a b 家島 2006, 第2部第1章.
- ^ 加藤 1995, 第2章.
- ^ 清水 1984.
- ^ 清水 1984, pp. 179–180.
- ^ 清水 1984, pp. 179, 191.
- ^ ブローデル 1992, p. 25.
- ^ 高山 1999, 第7章、第8章.
- ^ ヘリン 2010, pp. 219–220.
- ^ 齊藤 2011.
- ^ 生田 1998, pp. 31–32, 37.
- ^ 生田 1998, pp. 44–45.
- ^ 生田 1998, p. 16.
- ^ 家島 2006, 第5部第4章.
- ^ 生田 1998, pp. 8–10.
- ^ 辛島編 2004, p. 178-181, 184.
- ^ 辛島編 2007, p. 144.
- ^ a b 小谷編 2007, pp. 195–197.
- ^ 辛島編 2004, 第4章.
- ^ 生田 1998, 序章.
- ^ マクニール 2013.
- ^ 前嶋 1991.
- ^ メノカル 2005.
- ^ ヘリン 2010, pp. 208–211.
- ^ ヤーニン 1998.
- ^ 和田編 2004, 第4章.
- ^ 山田 1999.
- ^ 佐藤, 池上 1997, 第4章.
- ^ 佐藤, 池上 1997, 第10章、第11章.
- ^ ウォルフォード 1984, 第4章、第5章.
- ^ 熊野 2003, 第2章、第4章.
- ^ 角谷 2006, pp. 176–178, 187–190.
- ^ a b 宮崎 1994, 第6章.
- ^ 長澤 1993, pp. 330–331.
- ^ 長澤 1993, pp. 322–323.
- ^ 長澤 1993, pp. 324–326.
- ^ 長澤 1993, pp. 327–329.
- ^ a b ウェザーフォード 2014, 第9章.
- ^ 可児 1984, p. 3.
- ^ 四日市 2008, p. 145.
- ^ a b c 森 2008.
- ^ 榎本 2008.
- ^ 四日市 2008, pp. 125–128.
- ^ 四日市 2008, pp. 131, 139.
- ^ ウェザーフォード 2014, 第10章.
- ^ 田中 1997, 第1章.
- ^ 臼井 1999.
- ^ 上里 2012, pp. 65–69.
- ^ 上里 2012, pp. 89–91.
- ^ 上里 2012, pp. 105–106, 109–110.
- ^ ブルック 2014, p. 83.
- ^ 斯波 1995, p. 37.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2519-2531/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2535-2545/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2549-2554/8297.
- ^ 臼井 1992, 第2章.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1633-1646/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1663-1670/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1603–1609, 1675-1687/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1639-1646/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 940-947/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 979–998, 1053, 1072-1078/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1268-1275/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1329-1348/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1348-1353/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1418-1430/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2945-2965/8297.
- ^ a b 青山, 猪俣 1997, pp. 157–158.
- ^ 中村 2007, p. 91.
- ^ 小林 1985.
- ^ 関 2010, p. 196.
- ^ 関 2010, pp. 241–243.
- ^ 関 2010, pp. 253–254.
- ^ ダルトロイ 2012.
- ^ 網野 2018, p. 203.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2893–2899, 2928, 2945/8297.
- ^ ホブズボーム 1993.
- ^ a b マグヌソン 2012, 第2章.
- ^ 和田編 2004, 第5章.
- ^ a b マグヌソン 2012, 第6章.
- ^ 中沢 1999.
- ^ 名城 2008.
- ^ a b ブルック 2014.
- ^ 谷澤 2010.
- ^ ウォルフォード 1984, 第5章.
- ^ a b 浅田 1989, 第1章.
- ^ 永積 2000, 第2章.
- ^ 宮本, 松田編 2018, 第10章.
- ^ a b 浅田 1989, 第9章、第10章.
- ^ ホント 2005.
- ^ 服部 2002, 第6章第4節.
- ^ エルティス, リチャードソン 2012, 第1章.
- ^ エルティス, リチャードソン 2012, p. 序章.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2985-2991/8297.
- ^ a b エルティス, リチャードソン 2012, 第4章.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3022-3028/8297.
- ^ a b ポメランツ, トピック 2013, p. 250.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3060-3067/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3162-3188/8297.
- ^ エルティス, リチャードソン 2012, 第6章.
- ^ a b c 薩摩 2018, p. 104.
- ^ 薩摩 2018, pp. 104–106.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2928-2933/8297.
- ^ 生田 1998, 第1章.
- ^ a b 菅谷 1999.
- ^ ブルック 2014, 第6章.
- ^ 斯波, 1995 & 123, 139-140.
- ^ 濱下 1997, pp. 65–66.
- ^ ポメランツ, トピック 2013, p. 265.
- ^ 山本編 2000, p. 226.
- ^ a b 秋道 2000.
- ^ ポメランツ, トピック 2013, p. 349.
- ^ ポメランツ 2015, p. 294.
- ^ マグヌソン 2012, 第4章.
- ^ マグヌソン 2012, p. 228.
- ^ a b 玉木 2012.
- ^ 服部 2002, pp. 114–115, 122–123.
- ^ マグヌソン 2012.
- ^ ホブズボーム 1993, p. 88.
- ^ a b c ホブズボーム 1993, 第3章.
- ^ ホブズボーム 1993, p. 80.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 5679–5697, 5737-5750/8297.
- ^ ホブズボーム 1993, p. 94.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3340-3347/8297.
- ^ 小谷編 2007, pp. 230–231, 251–255.
- ^ 小谷編 2007, pp. 247–255.
- ^ a b ポメランツ, トピック 2013.
- ^ 小谷編 2007.
- ^ 辛島編 2004, pp. 367–368.
- ^ 生田 1998.
- ^ 斯波 1995, 第2章.
- ^ 白石 2000, pp. 43–44.
- ^ 白石 2000, pp. 26–27.
- ^ 石坂 2013.
- ^ 白石 2000, pp. 68–71.
- ^ 鶴見 1987, p. 156.
- ^ 佐々木 1996.
- ^ 森永 2014, p. 5.
- ^ a b 森永 2014.
- ^ ウォルフォード 1984, p. 304.
- ^ 小松編 2000, p. 305.
- ^ 小松編 2000, 第6章.
- ^ 角山 1980, 第1章.
- ^ a b 角山 1980, p. 101.
- ^ 永積 2000, p. 139.
- ^ 東野 1997, pp. 176–180.
- ^ 鶴見 1987, p. 144.
- ^ ブルック 2014, 第3章.
- ^ 永積 1999.
- ^ 濱下 1997, 第9章.
- ^ ポメランツ, トピック 2013, p. 150.
- ^ 山田編 1995.
- ^ 多田井 1997, p. 下227.
- ^ 濱下 1997, pp. 25–28.
- ^ 濱下 1997, pp. 173–174.
- ^ 武田編 2000.
- ^ ナン 2018, pp. 181–183.
- ^ 栗本 2013, pp. 1124-1130/3838.
- ^ エルティス, リチャードソン 2012.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3375-3088/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3434-3447/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 2728-2753/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3558-3603/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3661-3680/8297.
- ^ 坂井 2003.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3085–3097, 3101/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3923-3941/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 3893–3904, 3947/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 1448-1462/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 4378–4387, 4402-4419/8297.
- ^ ダイアモンド 1997, p. 386.
- ^ a b 湯浅 1998.
- ^ 池本, 布留川, 下山 2003.
- ^ 臼井 1992, 第7章.
- ^ 木村 2000.
- ^ ポメランツ, トピック 2013, p. 151.
- ^ a b ブルック 2014, 第2章.
- ^ 木村 2004.
- ^ カーク 2014, p. 21.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, p. 51.
- ^ ヤーギン 1991, 第1部.
- ^ a b c 秋元 2009, 第1章.
- ^ ポメランツ 2015, p. 293.
- ^ ホブズボーム 1993, 第2章.
- ^ a b ヤーギン 1991, 第2部第10章.
- ^ トゥーズ 2019, pp. 330–334, 346–347.
- ^ 野林, 他 2003, 第3章.
- ^ ヤーギン 1991, 第2部第11章.
- ^ ヤーギン 1991, 第2部第15章.
- ^ ヤーギン 1991, 第3部第16章、第18章.
- ^ トゥーズ 2019, pp. 466–467.
- ^ 橋本 2013, p. 214.
- ^ 橋本 2013, p. 216.
- ^ 橋本 2013, p. 220.
- ^ 橋本 2013, p. 226.
- ^ 猪木 2009, 第1章、第2章.
- ^ 野林, 他 2003, 第4章.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 285–287.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 278–279.
- ^ 阿部, 遠藤 2012, pp. 308–310.
- ^ 平野 2009, p. 3.
- ^ a b 平野 2009, p. 4、p.10.
- ^ 平野 2009, p. 5.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 315–317.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 317–319.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 319–321.
- ^ 猪木 2009, 第2章.
- ^ a b 野林, 他 2003, 第5章.
- ^ 猪木 2009, 第6章.
- ^ 平野 2013, 第2章.
- ^ 篠田 2005.
- ^ 大野, 桜井 1997, p. 36.
- ^ 大野, 桜井 1997, p. 157.
- ^ 大野, 桜井 1997, p. 291.
- ^ 平野 2013.
- ^ 内藤, 中村編 2006, 第11章.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 5737–5743, 5756–5762, 5909-5913/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 6356–6367, 6773-6379/8297.
- ^ 宮本, 松田編 2018, pp. 6325–6330, 6386/8297.
- ^ 平野 2013, 第2章、第3章.
- ^ 猪木 2009, 第5章.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 289–291.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 196–197.
- ^ 阿部, 遠藤 2012, 第9章.
- ^ a b c d e 阿部, 遠藤 2012, 第10章.
- ^ a b 野林, 他 2003, 第10章.
- ^ 古屋 2011.
- ^ 渡辺 2007.
- ^ クルーグマン, オブズフェルド, メリッツ 2017, pp. 289.
- ^ 山田 2003, p. 165.
- ^ 阿部, 遠藤 2012, p. 309.
- ^ 猪木 2009, 第3章.
- ^ a b c トゥーズ 2020, pp. 183–185.
- ^ a b トゥーズ 2020, pp. 259–260.
- ^ トゥーズ 2020, p. 184.
- 貿易史のページへのリンク