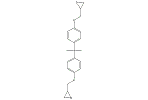badge
「badge」とは・「badge」の意味
「badge」とは、主に識別や所属を示すために使用される記章やシンボルのことである。従業員の名前や役職が記載された名札や、スポーツチームのエンブレム、警察官や消防士の階級章などがこれに該当する。また、オンラインゲームやソーシャルメディアでの実績やステータスを示すアイコンも「badge」と呼ばれることがある。「badge」の発音・読み方
「badge」の発音は、IPA表記では/bædʒ/であり、カタカナ表記では「バッジ」となる。日本人が発音するカタカナ英語では「バッジ」と読むことが一般的である。「badge」の定義を英語で解説
A badge is a small object, such as an emblem or a symbol, that is worn or displayed to show a person's membership, rank, or achievement. Badges can be found on employee name tags, sports team logos, and the insignia of police officers and firefighters. They can also represent accomplishments or status in online games and social media platforms.「badge」の類語
「badge」の類語には、emblem, insignia, symbol, logo, crest, patch, medallionなどがある。これらの単語は、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあるが、基本的には所属や地位を示す目印としての役割が共通している。「badge」に関連する用語・表現
「badge」に関連する用語や表現には、ID card(身分証明書)、lanyard(紐に付ける名札)、lapel pin(襟に付けるピンバッジ)、achievement(実績)、rank(階級)などがある。これらの用語は、「badge」が使用されるさまざまな状況や目的に関連している。「badge」の例文
1. The police officer's badge was clearly visible on his uniform.(警察官のバッジは制服にはっきりと見えた。) 2. She proudly wore her team's badge on her jacket.(彼女は誇らしげにチームのバッジをジャケットに付けていた。) 3. The conference attendees were required to wear their badges at all times.(会議参加者は常時バッジを着用することが求められた。) 4. He received a badge for his outstanding performance in the competition.(彼は競技での優れたパフォーマンスに対してバッジを受け取った。) 5. The company's logo was designed to resemble a badge of honor.(その企業のロゴは名誉のバッジに似せてデザインされた。) 6. The scout earned a badge for learning first aid skills.(スカウトは応急手当の技能を学んでバッジを獲得した。) 7. The employee's name and position were displayed on their badge.(従業員の名前と役職がバッジに表示されていた。) 8. The badge indicated that she had completed the training course.(そのバッジは彼女が研修コースを修了したことを示していた。) 9. He collected badges from various events and displayed them on his wall.(彼はさまざまなイベントのバッジを集め、壁に飾っていた。) 10. The online game awarded badges to players who achieved certain goals.(そのオンラインゲームは特定の目標を達成したプレイヤーにバッジを授与した。)バッジ【badge】
読み方:ばっじ
1 職務・地位・所属などを示すために、帽子や衣服につける小さい記章。バッチ。
2 パソコンやスマートホンの操作画面で、アプリのアイコンに重ねて表示される数字。電子メールやメッセンジャーアプリの受信件数、オペレーティングシステムによる通知件数などを表す。
バッジ【BADGE】
読み方:ばっじ
《Base Air Defense Ground Environment》航空自衛隊が採用していた自動防空警戒管制組織。コンピューターとレーダーを組み合わせた防空システム。バッジシステム。
バッチ【badge】
ビスフェノールAジグリシジルエーテル
| 分子式: | C21H24O4 |
| その他の名称: | ジアンジグリシジルエーテル、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、Diandiglycidyl ether、Bisphenol A diglycidyl ether、2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane、2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenylene)bis(oxymethylene)]bisoxirane、2,2-Bis[4-(oxiranylmethyloxy)phenyl]propane、ジオメタンジグリシジルエーテル、Diomethane diglycidyl ether、Diglycidyl bisphenol A、アラルジト、アラルダイト、Araldite、BADGE、DGEBA、ジグリシジルビスフェノールA、3,3'-[Isopropylidenebis(4,1-phenylene)bisoxy]bis(1,2-epoxypropane)、Isopropylidenebis(4,1-phenylene)bis(glycidyl ether)、2,2'-[Isopropylidenebis(4,1-phenylene)bis(oxymethylene)]bisoxirane、2,2'-[(Dimethylmethylene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、4,4'-(Isopropylidene)bis[1-(glycidyloxy)benzene]、2,2'-[Isopropylidenebis(p-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、2,2'-Isopropylidenebis[(4,1-phenylene)oxymethylene]bisoxirane、3,3'-Isopropylidenebis(4,1-phenylene)bisoxybis(1,2-epoxypropane)、2,2'-[1-Methylethylidenebis(p-phenylene)bis(oxy)bis(methylene)]bisoxirane、1,1'-(2,2-Propanediyl)bis[4-(glycidyloxy)benzene]、2,2'-[2,2-Propanediylbis(p-phenylene)bisoxybismethylene]bisoxirane、1,1'-Isopropylidenebis[4-[(oxiranyl)methoxy]benzene]、4,4'-Isopropylidenebis(glycidyloxybenzene)、2,2'-[(Isopropylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、4,4'-Isopropylidenebis[(oxiranylmethyloxy)benzene]、4,4'-Isopropylidenebis[1-(glycidyloxy)benzene]、1,1'-Isopropylidenebis[4-(glycidyloxy)benzene]、1,1'-(Isopropylidene)bis[4-(oxiranylmethoxy)benzene]、2,2'-[(Propane-2,2-diyl)bis(p-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、2,2'-(Dimethylmethylene)bis[(p-phenylene)oxymethylene]bisoxirane、1,1'-Isopropylidenebis[4-(oxiranylmethoxy)benzene]、2,2'-[Dimethylmethylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、4,4'-Isopropylidenebis[(glycidyloxy)benzene]、2,2'-[Isopropylidenebis[(p-phenylene)(oxy)(methylene)]]di(oxirane)、2,2'-[Dimethylmethylenebis[(4,1-phenyleneoxy)methylene]]bisoxirane、[Dimethylmethylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、1,1'-Dimethylmethylenebis[4-(oxiranylmethoxy)benzene]、4,4'-Bis(glycidyloxy)-(1,1'-isopropylidenebisbenzene)、ビスフェノールAエポキシ、Bisphenol-A epoxy、2,2'-Dimethylmethylenebis(1,4-phenyleneoxymethylene)bisoxirane、1,1'-Dimethylmethylenebis(4-oxiranylmethoxybenzene)、1,1'-(Propane-2,2-diyl)bis(4-glycidyloxybenzene)、Epon-828、2,2'-[2,2-Propanediylbis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、2,2'-[Isopropylidenebis[4,1-phenylene(oxymethylene)]]bisoxirane、2,2'-(Isopropylidenebis-4,1-phenylenebisoxybismethylene)bisoxirane、4,4'-Isopropylidenebis(1-glycidyloxybenzene)、2,2'-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、1,1'-(1-Methylethylidene)bis[4-(glycidyloxy)benzene]、2,2'-[Isopropylidenebis(p-phenylene)bisoxybismethylene]bisoxirane、1,1'-(1-Methylethylidene)bis[4-(oxirane-2-yl)methoxybenzene]、2,2'-[Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene)bis(oxymethylene)]bisoxirane、4,4'-(Propane-2,2-diyl)bis(glycidyloxybenzene)、2,2'-[(Isopropylidene)bis[(4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane、2,2'-[Isopropylidenebis[(4,1-phenylene)oxymethylene]]bisoxirane、2,2'-[Isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane、2,2'-[1-Methylethylidene]bis(4,1-phenylene)bis(oxymethylene)bisoxirane、2,2-Bis[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]propane、JER-828、2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane |
| 体系名: | 2,2'-[イソプロピリデンビス[4,1-フェニレン(オキシメチレン)]]ビスオキシラン、2,2'-[2,2-プロパンジイルビス(4,1-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、1,1'-(プロパン-2,2-ジイル)ビス(4-グリシジルオキシベンゼン)、1,1'-ジメチルメチレンビス(4-オキシラニルメトキシベンゼン)、2,2'-ジメチルメチレンビス(1,4-フェニレンオキシメチレン)ビスオキシラン、4,4'-ビス(グリシジルオキシ)-(1,1'-イソプロピリデンビスベンゼン)、1,1'-ジメチルメチレンビス[4-(オキシラニルメトキシ)ベンゼン]、[ジメチルメチレンビス(4,1-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、2,2'-[ジメチルメチレンビス[(4,1-フェニレンオキシ)メチレン]]ビスオキシラン、2,2'-[イソプロピリデンビス[(p-フェニレン)(オキシ)(メチレン)]]ジ(オキシラン)、4,4'-イソプロピリデンビス[(グリシジルオキシ)ベンゼン]、2,2'-[ジメチルメチレンビス(4,1-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、1,1'-イソプロピリデンビス[4-(オキシラニルメトキシ)ベンゼン]、2,2'-(ジメチルメチレン)ビス[(p-フェニレン)オキシメチレン]ビスオキシラン、2,2'-[(プロパン-2,2-ジイル)ビス(p-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、1,1'-(イソプロピリデン)ビス[4-(オキシラニルメトキシ)ベンゼン]、1,1'-イソプロピリデンビス[4-(グリシジルオキシ)ベンゼン]、4,4'-イソプロピリデンビス[1-(グリシジルオキシ)ベンゼン]、4,4'-イソプロピリデンビス[(オキシラニルメチルオキシ)ベンゼン]、2,2'-[(イソプロピリデン)ビス(4,1-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、4,4'-イソプロピリデンビス(グリシジルオキシベンゼン)、1,1'-イソプロピリデンビス[4-[(オキシラニル)メトキシ]ベンゼン]、2,2'-[2,2-プロパンジイルビス(p-フェニレン)ビスオキシビスメチレン]ビスオキシラン、1,1'-(2,2-プロパンジイル)ビス[4-(グリシジルオキシ)ベンゼン]、2,2'-[1-メチルエチリデンビス(p-フェニレン)ビス(オキシ)ビス(メチレン)]ビスオキシラン、3,3'-イソプロピリデンビス(4,1-フェニレン)ビスオキシビス(1,2-エポキシプロパン)、2,2'-イソプロピリデンビス[(4,1-フェニレン)オキシメチレン]ビスオキシラン、2,2'-[イソプロピリデンビス(p-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、4,4'-(イソプロピリデン)ビス[1-(グリシジルオキシ)ベンゼン]、2,2'-[(ジメチルメチレン)ビス(4,1-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、2,2'-[イソプロピリデンビス(4,1-フェニレン)ビス(オキシメチレン)]ビスオキシラン、イソプロピリデンビス(4,1-フェニレン)ビス(グリシジルエーテル)、3,3'-[イソプロピリデンビス(4,1-フェニレン)ビスオキシ]ビス(1,2-エポキシプロパン)、2,2-ビス(4-グリシジルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス[4-(オキシラニルメチルオキシ)フェニル]プロパン、2,2'-[(1-メチルエチリデン)ビス(4,1-フェニレン)ビス(オキシメチレン)]ビスオキシラン、2,2-ビス[4-(グリシジルオキシ)フェニル]プロパン、1,1'-(プロパン-2,2-ジイル)ビス[4-[(オキシラン-2-イル)メトキシ]ベンゼン]、2,2-ビス[4-(オキシラニルメトキシ)フェニル]プロパン、2,2'-[1-メチルエチリデン]ビス(4,1-フェニレン)ビス(オキシメチレン)ビスオキシラン、2,2'-[イソプロピリデンビス(4,1-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、2,2'-[イソプロピリデンビス[(4,1-フェニレン)オキシメチレン]]ビスオキシラン、2,2'-[(イソプロピリデン)ビス[(4,1-フェニレン)オキシメチレン]]ビスオキシラン、4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ビス(グリシジルオキシベンゼン)、2,2'-[プロパン-2,2-ジイルビス(4,1-フェニレン)ビス(オキシメチレン)]ビスオキシラン、1,1'-(1-メチルエチリデン)ビス[4-(オキシラン-2-イル)メトキシベンゼン]、2,2'-[イソプロピリデンビス(p-フェニレン)ビスオキシビスメチレン]ビスオキシラン、1,1'-(1-メチルエチリデン)ビス[4-(グリシジルオキシ)ベンゼン]、2,2'-[(1-メチルエチリデン)ビス(4,1-フェニレンオキシメチレン)]ビスオキシラン、4,4'-イソプロピリデンビス(1-グリシジルオキシベンゼン)、2,2'-(イソプロピリデンビス-4,1-フェニレンビスオキシビスメチレン)ビスオキシラン |
自動警戒管制組織
(badge から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/25 05:17 UTC 版)

自動警戒管制組織(じどうけいかいかんせいそしき、BADGE:Base Air Defense Ground Environment)は、1969年から2009年まで運用されていた航空自衛隊の防空指揮管制システム。略称はバッジ・システム。自動化された航空警戒管制システムであり、指揮命令、航空機の航跡情報等を伝達・処理する全国規模の戦術指揮通信システム(コンピュータシステム)である。
2009年7月1日に、後継の自動警戒管制システム(JADGE:Japan Aerospace Defense Ground Environment、略称:ジャッジ)に換装された。
来歴
1954年7月1日に発足した航空自衛隊は、その6年後の1960年7月より、自力での航空警戒管制組織の運用に着手した。当時の防空体制は、F-86DおよびF-86F戦闘機を要撃機としていたが、警戒管制は下記のような手動運用方式であった[1]。
- 目標発見 - 防空監視所(SS)に設置されたレーダーのスコープ上で監視係員が発見
- 航跡情報表示 - SSから音声で報告を受け、防空指令所(DC)の表示係員が手書きで大型表示板に表示
- 識別 - 大型表示板に表示された航跡情報表示をもとに識別係員が敵味方識別
- 要撃 - 管制官が音声により要撃機に指令
その後、1961年7月18日に決定された第2次防衛力整備計画では、新戦闘機(F-X)としてのF-104Jやナイキ・エイジャックスなど、新たな防空手段の導入が決定されたことから、これとあわせて、航空警戒管制組織の自動化が模索されることとなった。これに応じて導入されたのがBADGEシステムである[1]。
1962年度より採用機種の検討が進められ、ゼネラル・エレクトリック(GE)、リットン社、ヒューズ社の3社が技術提案を行った。二度に渡り調査団が派米されるなど慎重に検討が進められ、1963年7月1日、ヒューズ社が提案した戦術航空火器管制システム(Tactical Air Weapon Control System, TAWCS)の採用が決定された[2]。決定理由は「完成が遅れることがあっても、ヒューズ社の提案が要求を満たし、費用が最低である」という点であった[1]。
なお、1964年12月4日に締結された政府間合意に基づき、本システムの開発にはアメリカからの財政支援がなされている[3]。
情報漏洩事件
1960年代前半、最初のシステムの受注をめぐり、米メーカー・日本輸入商社・日本メーカーが3つのグループ、ゼネラル・エレクトリック-三井物産-東芝、リットン-日商岩井-三菱電機、ヒューズ-伊藤忠-日本電気(日本アビオトロニクス)に分かれ競い合った。1963年4月の決定直前に大幅値引きをしたヒューズが130億円で受注した(GEは207億円、リットンは170億円)。その後1966年から1967年にかけて怪文書が出回り、1968年1月に東京地検が伊藤忠を家宅捜索、3月に防衛庁警務隊が航空幕僚監部防衛課長の一佐を逮捕、3日後に上司の空将補が謎の自殺を遂げた。受注を競い合っていた時期に一佐から伊藤忠に膨大な機密情報が漏れたとされ、その後一佐は自衛隊法違反で起訴、実刑となった。最低価格で受注契約したはずのヒューズのシステムであったが、その後電子妨害防止装置などを追加したため、1968年完成時までにかかった費用は当初受注額のほぼ2倍の253億円となった。
- 瀬島龍三(陸士44期卒、伊藤忠取締役業務本部長としてバッジシステム受注競争を指揮、受注競争が始まる直前の1960年に旧陸軍技術将校出身の航空幕僚監部技術情報班長を伊藤忠にスカウト。)
- 浦茂(陸士44期卒、航空幕僚監部防衛部長・バッジシステム導入のための調査団長として、1963年アメリカ視察、最終報告を行う。後に航空幕僚長。情報漏洩事件発覚時は丸紅に天下っていた。)
BADGE
ヒューズ社がアメリカ海軍向けに開発した海軍戦術情報システム(NTDS)の改良型であるTAWCSをベースとして[4]、日本アビオトロニクス(現:日本アビオニクス)社が航空自衛隊向けにカスタマイズしたものである。1964年12月に「航空警戒管制組織の自動化」として受注、1968年3月に領収され、点検評価を経て、1969年3月26日から、まず全防衛区域で昼間8時間の運用が開始された[1]。
構成
当時府中基地に所在していた航空総隊作戦指揮所(COC)がトップとして、システム全体を統括した。当時、航空方面隊ごとに北部・中部・西部の3個防衛区域が設定されており、それぞれに防空管制所(CC)が設けられていた。実際にBADGEの警戒管制機能の中核となり、要撃機や地対空ミサイルへの指令を担当する防空指令所(DC)もこれに併設されるが、中部防衛区域のみ、笠取山分屯基地と峯岡山分屯基地に分割されていた[1]。なお、システムはアメリカ軍のシステムとも連接されていたが、政治的な理由により、この計画は西太平洋北部情報利用プログラム(WESTPACNORTH Information Utilization Program)と呼称されていた。これにより、海軍戦術情報システム(NTDS)および琉球防空システム(Ryukyu Air Defense System)、韓国防空システム(Korea Air Defense System)との連接がなされていた[3]。
主要構成器材・機能は下記のとおりであった。
- RTS-IIレーダー追尾装置(Radar Tracking Station-II)
- SSに設置され、捜索・測高レーダーからの情報を集中処理する。最初の自動捕捉で目標の位置を求め、続く自動追尾では追尾しながら真目標の速度・針路を計算する。これらの自動追尾は、電子攻撃(EA)や悪天候下においても継続的に実施できるよう措置されている。なお算出された目標情報は、下記の地対地データリンクを介してDC・CCに伝送される[1][2]。
- H-330B要撃計算機

- DCに設置される大型の汎用コンピュータで、要撃諸元の計算伝送、フライトプランの挿入による自動的な各種情報の処理を行う。なおマンマシンインタフェースとしては、監視統制・識別・指揮・兵器割当・要撃管制の各コンソールのほか、戦術状況を総合的に表示する大型カラー・データ・スクリーンや、各基地の気象状況・待機状況を表示するステータスボードが配された[1][2]。
- H-3118情報処理計算機
- CCに設置された。H-330B要撃計算機とは異なり、基本的には目標情報・兵器待機状況等の表示に特化しており、連接されるコンソールも指揮用のもののみである[1][2]。
- HC-270地対地データリンク
- SS・DC・CC間を結ぶ高速データ伝送装置。
- 地対空データリンク
- 要撃管制に必要な誘導諸元を自動的にパイロットに指示するための地上装置。UHF帯の時分割データリンク(Time Division Data Link, TDDL)を利用している。要撃機ではF-104Jより対応し[1]、機上端末としてF-4EJではARR-670が搭載された[5]。
組織構成は下記のようなものであった。
- 北部防衛区域
- 中部防衛区域
- 西部防衛区域
運用史
運用開始直後は、DCの要撃計算機が1基のみであったことから、計算機故障時に直ちに手動運用に切替えられるよう訓練が重ねられた。またSSのレーダー追尾装置も不安定で、オペレータが目標の探知感度をこまめに調整する必要があった。その後、1975年10月1日より、要撃計算機の二重化により、24時間連続の運用体制が整備された[1]。
なお本システムは、アメリカ空軍が1959年より稼働させていた半自動式防空管制組織(SAGE)に続いて、世界で2番目の警戒管制システムであった。本システムの成功を受けて、これを開発したヒューズ社は、北大西洋条約機構のNADGEシステムなど、この当時に世界中で就役しつつあった同種のシステム開発を席巻することとなった[1]。
BADGE改
初代システムは、就役当初は世界最高といわれる能力を有していたものの、1970年代後半になると、航空機の性能向上に伴う脅威の増大、および連接されている周辺システムの性能向上に追随しきれなくなってきた。このことから、防衛庁では昭和54年度より次期システムの検討に着手し、1981年8月に、日本電気など3社に対して提案要求を行った。これを受け、1982年1月には各社から提案書が提出され、評価した結果、日本電気のシステムをもとに、他2社の電子交換機と基地内通信回線を組み入れたものを採用することとされた。昭和58年度予算で所要の経費が盛り込まれ[6]、1984年3月に、「自動警戒管制組織の近代化」として、日本電気と契約が締結された[1]。
日本電気を主契約社として、1983年から改修が開始された。この改修は、下記のようなものであった。
- 総合的C4Iシステムへの発展
- 全般的な性能向上
- 戦術情報処理装置の処理能力向上
- マン・マシン・インターフェースの改良
- 地上固定回線の光ファイバー化
- 構成の拡張・効率化
- 新型機への対応
JADGE

BADGE改システムでは指揮統制機能(CCIS)と通信回線統制機能(LCCM)の統合が図られたものの、その後のC4Iシステムの拡充に伴い、CCISは航空総隊指揮システム、またLCCMは作戦用通信回線統制システム(TNCS)として、それぞれ切り離して整備されるようになっていた。このことから、航空警戒管制機能(ADGE)に絞って近代化・機能充実を図ったのが新BADGEシステムである「自動警戒管制システム(JADGE)」である[1]。研究開発は2002年より開始され、2007年3月20日に入間基地に配備されたのを皮切りに、各基地等の機器の更新が順次行われ、2009年7月1日に正式に運用を開始した[7]。
JADGEとしての主な改修点は下記のとおりである。
- 分散処理アーキテクチャの採用。
- 地上回線の強化:作戦用通信回線統制システム(TNCS)の整備。
- 他システムとの互換性強化:防衛省コンピュータ・システム共通運用基盤(Common Operating Environment:略称COE)と防衛情報通信基盤(Defense Information Infrastructure:略称DII)の採用。これにより、同級システムである海上自衛隊の海上作戦部隊指揮管制支援システム(Maritime Operation Force System:略称MOFシステム)や陸上自衛隊の師団通信システム(Division Integrated Communications System:略称DICS)との相互運用性が飛躍的に向上している。
また、JADGEは、ミサイル防衛作戦において、3自衛隊の共通指揮システムとして運用されることとなっている。管制施設の特徴として従来はプロジェクター等の使用により管制室を暗くする必要があったが、液晶ディスプレイ等の採用により通常の屋内と同程度の明るさになった。これにより管制業務を行う隊員の視覚への負担が緩和された。
登場作品
- 『ガメラ3 邪神覚醒』
- イリス・ガメラとF-15の交戦シーンでバッジシステムが運用される。
- 『機動警察パトレイバー 2 the Movie』
- バッジシステムを運用する入間基地の中部航空方面隊作戦指揮所(SOC)が描写されている。
参考文献
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 宮脇俊幸「将来のネットワーク型戦闘に向け能力向上「自動警戒管制システム(JADGE)」 - 中国戦闘機大接近!空自指揮統制の要」『軍事研究』第49巻第7号、ジャパン・ミリタリー・レビュー、2014年7月、71-83頁、NAID 40020120001。
- ^ a b c d 日本科学史学会 編「資料11-9 自動警戒管制組織TAWCS (BADGE)」『日本科学技術史大系 (電気技術)』 19巻、第一法規出版、1969年3月。 NCID BN01591768。
- ^ a b Commander-in-Chief U.S. Pacific Command (1967年6月3日). “CINCPAC Command History 1966 (Volume I) promulgation of (U)” (PDF) (英語). 2014年11月15日閲覧。
- ^ 「Industry International」『Flight International』、Melanie Robson、1963年8月8日、222頁。
- ^ J.P. Gillen「Japanese data link」『RCA Engineer』第20巻第3号、RCA Research and Engineering、1974年11月、55-59頁。
- ^ a b 菊池征男『航空自衛隊の戦力』学研パブリッシング、2007年。 ISBN 9784059117087。
- ^ 自動警戒管制システム(JADGE)の運用開始について 航空自衛隊 2009年7月1日
関連項目
外部リンク
- 平成13年度政策評価書(事前の事業評価) 別紙1:バッジ・システムの航空警戒管制機能の概要、防衛庁(当時)防衛局計画課
BADGE
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 06:35 UTC 版)
ヒューズ社がアメリカ海軍向けに開発した海軍戦術情報システム(NTDS)の改良型であるTAWCSをベースとして、日本アビオトロニクス(現:日本アビオニクス)社が航空自衛隊向けにカスタマイズしたものである。1964年12月に「航空警戒管制組織の自動化」として受注、1968年3月に領収され、点検評価を経て、1969年3月26日から、まず全防衛区域で昼間8時間の運用が開始された。
※この「BADGE」の解説は、「自動警戒管制組織」の解説の一部です。
「BADGE」を含む「自動警戒管制組織」の記事については、「自動警戒管制組織」の概要を参照ください。
badgeと同じ種類の言葉
- badgeのページへのリンク