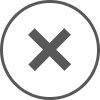国語辞典
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/24 04:17 UTC 版)

現在は、約50万語を収める最大規模の『日本国語大辞典』(小学館)をはじめ、中型辞典(10万語 - 20万語規模)や、小型辞典(6万語 - 10万語規模)が編纂され、特色を競っている。電子辞書やウェブ辞書、モバイルアプリケーションによる辞書も利用されている。これらデジタル版の内容は大多数が書籍版に基づいており、書籍版のように全体を一目で見渡せる一覧性には乏しいものの、コンピュータによる多様な検索を可能とし、携帯性に優れるなどの利点がある[3]。
構成
国語辞典に限ったことではないが、辞書は「誰が、どのような時に、どのような目的で使用するか」によって性格が異なる[4]。例えば使用者の職業や年齢、日本語が母語か否かなどによって要請は様々であり、図書館で調べるときや、学校や家庭で学習するときなど、使用する場面も多様である。
以下においては一般的な国語辞典の条件について述べることにする。
見出し
一般的に国語辞典の見出しは「こくご【国語】」「ディクショナリー【dictionary】」のように「仮名見出し【表記欄】」の形で書かれる。それぞれの詳細は以下の通り。
- 仮名見出し
-
- 活字はアンチック体やゴシック体といった太めのものが用いられる[5]。
- 仮名遣いは「現代仮名遣い」が用いられる[6]。敗戦前は歴史的仮名遣いが用いられたが、「表音式」と呼ばれる表記法を採用したものが現れ、1946年の現代かなづかい実施後も多く見られた[7]。表音式による仮名見出しは、発音が同じ語でも書き分ける場合が多い歴史的仮名遣いの難しさに対処する方式であり、仮名遣いを調べるための手段でもあったが、統一されたものではない[7]。現代かなづかい以前の1943年に刊行された『明解国語辞典』初版では、長音を表すのに「あ」「い」「う」「え」「お」を用い(例・てえ-こお【抵抗】テイカウ)、「ぢ」「づ」は「じ」「づ」に統一した。『広辞苑』第4版が仮名見出しを全面的に現代仮名遣いとしたことで、以降新たに刊行された主要な辞典から表音式見出しは姿を消した。『新明解国語辞典』は2020年の第8版でも「てい こ
う 【抵抗】」「こんにちは 」などの見出しに「表音式表記」としてカタカナ小字を添える[8]。 - 和語や漢語には平仮名を用いる(例・ごい【語彙】)。和語を平仮名、漢語を片仮名にするものもある(『新潮国語辞典』『新潮現代国語辞典』)。外来語には片仮名を用い、外来語の長音には長音符「ー」を用いる(例・ボキャブラリー【vocabulary】)。活用のある語は原則として終止形を見出し語とする。
- ハイフンや中黒といった約物(記号)で語構成や語幹・活用語尾の区切りを示すものが多い。
- 表記欄
- すみ付き括弧(【 】)または角括弧([ ])でくくるものが多い[9]。現代の辞書に使用される漢字は常用漢字または人名用漢字による字体整理に従い、新字体を基本とする。送り仮名は「送り仮名の付け方」を基準として[10]、「許容」により増減が認められる仮名を丸括弧でくくって示すことがある(例・浮(か)ぶ〈本則は「浮かぶ」〉、行(な)う〈本則は「行う」〉)。多くの国語辞典では、漢字が常用漢字表にある字種(表内字)かそうでない字種(表外字)か、表内字の読みが常用漢字表に採用されたもの(表内音訓)かそうでない(表外音訓)か、熟字訓である場合に常用漢字表の付表に示されているかどうかを約物で示す。教育漢字または常用漢字に含まれる漢字の場合、書体を変えて教科書体で示すものもある。
- 外来語の原語・原綴
- 表記欄に外来語の原語・原綴を掲げる国語辞典もある。その場合、英語以外の語については言語名が注記されることも多い。現代中国語などの場合には、そのまま原語の漢字表記を置くこともある。ラテン文字・漢字以外で表記される語は、通例ラテン文字に翻字されたものが原語として示される。なお原語から著しく乖離している場合や和製語の場合には別の括弧で注記することが多い。
- 歴史的仮名遣い
- 歴史的仮名遣いは利用者の目的の範囲内で記載される[注 1]。歴史的仮名遣いが仮名見出しと異なる場合、「仮名見出しと表記欄の間に示すもの」と「表記欄の後に示すもの」とがあり、多くは割注で示す[11]。漢語の字音仮名遣いを示すものと示さないものとがある。表音式見出しを採用した辞典では、歴史的仮名遣いと同様に現代かなづかいもこうした方法で示した。
語義がほぼ同じである場合は、見出しの表記が少々異なる語も一つの項にまとめられる。語義が異なる場合には別項とする(例・じてん【字典】、じてん【辞典】、じてん【事典】)。この処理は辞典や語によって異なることがある。『岩波国語辞典』は「じてん①【辞典】……②【字典】……③【事典】……」と「じてん」の項目の語義区分で分ける処理をする。『日本国語大辞典』の「だい-じてん【大辞典・大字典】」の項目は両表記をまとめ、一般名詞、栄田猛猪による漢和辞典『大字典』、平凡社の国語辞典『大辞典』を併せて扱う。
排列
近現代の多くの国語辞典は、項目を五十音順に排列する[12]。明治より前の字引の類いはいろは順であり、近代にもいろは順のものがあるほか、ローマ字排列のものもある[13]。個々の辞典によって細部は異なるが基本的なルールはだいたい同じである。他の事典類では長音記号を無視したような順で並べるものが多いが、国語辞典では長音記号の発音に該当する母音があるものとするものが多い、といった違いがある。
- 清音、濁音、半濁音については、そのまま清音、濁音、半濁音の順となる(例・はり【玻璃】、ばり【罵詈】、パリ【Paris】)。
- 直音、促音、拗音については国語辞典により異なる。
- 長音についても国語辞典により異なる。
- 複合語についても国語辞典により異なる。
- 同音の場合の配列についても国語辞典により異なる。
歴史
近代以前
「日本書紀」によれば、日本人が手掛けた最初の辞書は682年(天武天皇11年)に完成した『新字』といわれる[注 4]。その内容は伝わっていないため真偽は不明であるが、現存する木簡に字書らしき記載が確認できることから[15]、少なくとも天武朝において辞書編纂が行われた可能性はある[16]。
日本で作られた現存最古の辞書は、空海の編纂になる『篆隷万象名義』(承和2年・835年以前成立)である[17][18]。これは漢字に簡潔な漢文注を付しており、高山寺に唯一の古写本が伝わっている[19]。和語(和訓)が載ったものとしては、『新撰字鏡』(寛平4年 - 昌泰3年・892年 - 900年)、『和名類聚抄』(承平4年・934年)、『類聚名義抄』(11世紀末 - 12世紀頃)、『色葉字類抄』[注 5]といった辞書が編まれた[21]。ただし、これらは厳密には漢籍を読むための漢和辞典もしくは漢字・漢語を知るための “和漢辞典” であると考えるべきで、現在の国語辞典の概念からは遠い。
15世紀になると、日常で接する単語をいろは順に並べた書物「節用集」が広まった。漢字熟語を多数掲出して、それに読み仮名をつけただけのもので、もとより意味などの記述はないが、日常の文章を書くためには十分であった[22]。「節用集」の写本は多く現存し、文明本(文明6年・1474年頃成立)、黒本本、饅頭屋本、前田本、易林本などが知られる[22]。「節用集」は江戸時代にますます広く利用され、明治以降も継続して刊行されたが、次第に役割を近代国語辞典に譲った[23]。
近世には、貝原好古が1688年に中国の『爾雅』に倣った『和爾雅』を出版した。18世紀には石川雅望『雅言集覧』、太田全斎『俚言集覧』、谷川士清『和訓栞』といった辞書が出た[注 6]。『雅言集覧』は和歌や擬古文の作成において規範となる「雅語」を集めたもので、いわば古語辞典であるが、用例の出典および流布本の丁数を記しているので、古語研究に欠かすことのできないものとなっている[27]。『俚言集覧』は当時の俗語に焦点を当てたもので、今日の国語辞典の概念により近く、語をアカサタナ順に並べ、たまに出典や説明を付している[注 7]。『和訓栞』は、見出し語の下に語釈・用例をかなり細かく示している[注 8]。
「言海」から第二次世界大戦まで
「近代国語辞典の始まり」は『言海』であると一般に認められている[31][32][33][34][35]。もっとも、その前段があった。
文部省編輯寮では『語彙』という辞書の編集が進められた[36]。ところが、1871年に「あ」の部[37]が成立した後、1884年に「え」の部[38]まで出たところで頓挫した[注 9]。こうした『語彙』の失敗に鑑みて、文部省の命により大槻文彦のほぼ独力によって編集が進められた[40][41]。
大槻は『ウェブスター辞典』の簡易版を参照しながら[注 10]、辞書編纂の理念と方法として「発音」「語別」「語源」「語釈」「出典」の5種を絶対条件とした[40][41][45]。約3万9000語が収録されている。
『言海』は成稿の後、資金不足のため、しばらく文部省内に保管されたままだったが[注 11]、やがて1889年から1891年に私費で刊行された[41]。その最中、幼い娘、そして妻を相次いで病気で亡くしている[注 12]。当初は全4冊であったが、後に吉川弘文館などから1冊本として刊行されるようになり、その後も印刷を重ね、1949年に第1000刷を迎えた[41]。
『言海』以降の主な辞書
- 辞林
- 三省堂(1907年)金沢庄三郎
- 広辞林
- 三省堂(1925年、1983年第6版)金沢庄三郎
- 小辞林
- 三省堂(1928年)金沢庄三郎
- 大言海
- 冨山房(1932年 - 1935年)大槻文彦
- 大辞典
- 平凡社(1934年 - 1936年)石川貞吉ほか
『明解国語辞典』以降
- 言林
- 全国書房(1949年)新村出
- 敗戦後の新しい社会に対応すべく編纂されたもの[70]。1961年に小学館から新版。
- 辞海
- 三省堂(1952年)金田一京助
- 編者の「純粋の国語辞典を作りたい」という意図のもとに編纂された[71]。研究者、国語教師などから高く評価されたが、実際の販売は好調とは言えず、改訂されることなく品切れとなった。1974年新装。
- 例解国語辞典
- 中教出版(1956年)時枝誠記、小型
- 三省堂国語辞典
- 三省堂(1960年〔初版〕、2022年第8版)見坊豪紀・市川孝・飛田良文・山崎誠・飯間浩明・塩田雄大、小型
- 見坊は、この辞書の編纂のために生涯に約140万語に及ぶ現代語の採集カードを作った。語釈は平易な言葉を使い簡潔。第7版にはプロ野球3球団仕様がある。第8版では仮名見出しにアクセントを加えるなど全面改訂を行った。第7版以降にはモバイルアプリケーションがある。
- 旺文社国語辞典
- 旺文社(1960年〔初版〕、2023年第12版)山口明穂・和田利政・池田和臣ほか、小型
- 日常生活に必要な語をはじめ、科学技術・情報・医学などの最新語、和歌(百人一首・現代短歌)・現代俳句や、人名・地名・作品名などの固有名詞、故事ことわざ・慣用句を豊富に収録。常用漢字・人名用漢字はすべて見出しとして収載。
- 日本国語大辞典
- 小学館(1972年 - 1976年〔第1版〕、2000年 - 2002年第2版)、大型
- 角川国語中辞典
- 角川書店(1973年)時枝誠記・吉田精一、中型
- 現代語を先に記述する方式を採った最初の辞書。見出し語数は約15万語。1982年に見出し語数5000語程度の増加をもって『角川国語大辞典』を出版する。
- 新潮現代国語辞典
- 新潮社(1985年〔初版〕、2000年第2版)山田俊雄・築島裕・白藤禮幸・奥田勲、小型
- 漢語に強い。字音語に対する仮名見出しを片仮名にする。近現代の文学作品から用例を多く採り、実例を示す[84]。
- 現代国語例解辞典
- 小学館(1985年〔第1版〕、2016年第5版)林巨樹〔監修〕、小型
- 「日本国語大辞典」の成果を踏まえて編まれた小型国語辞典。類語の違いを他の言葉との組み合わせによる適否で示す類語対比表、可能な表記より一般的な表記を重視することに特徴がある。
- 国語大辞典 言泉
- 小学館(1986年)林大〔監修〕、中型
- 「日本国語大辞典」をベースとしていることが特徴。他の『言泉』との関連はない。
- 大辞林
- 三省堂(1988年〔初版〕、2019年第4版)松村明、中型
- 「広辞林」の改訂では『広辞苑』に対抗できないと認識した三省堂が、倒産をはさんだ28年間をかけて編纂した。語釈を「現代広く使われているものから順に記す」など、現代語主義を採る[85]。インターネット上で第2版、第3版が提供された。第3版・第4版にはモバイルアプリケーションがある。
- 日本語大辞典
- 講談社(1989年〔初版〕、1995年第2版)梅棹忠夫・金田一春彦〔監修〕、中型
- 国語辞典と百科事典の特徴を併せ持つ[86]。同辞典の冒頭の「序」によると、国際化が進む中での日本語の現状を、情報処理の能率も鑑みながら、日本語の歴史的な背景も視野に入れ、将来を含めて考察するための材料を提供することを目的とする。
- 集英社国語辞典
- 集英社(1993年〔初版〕、2012年第3版)森岡健二・徳川宗賢・川端善明・中村明・星野晃一、中型に近い小型
- 語数は約9万4000語。この規模の辞書では初めて横組み版も発売された(第2版まで)[87]。文法項目の用例に分かりやすい唱歌などを用いている。一般語にNHKのアクセントを示す。
- 辞林21
- 三省堂(1993年)松村明・佐和隆光・養老孟司〔監修〕、中型
- 横組み。語数は約15万語。百科事典、カタカナ語辞典、人名事典、地名辞典、アルファベット略語辞典、ワープロ漢字字典としての機能を併せもつ。1998年の『新辞林』は本書の改題改訂版に当たる。
- 角川必携国語辞典
- 角川書店(1995年)大野晋・田中章夫、小型
- 大辞泉
- 小学館(1995年〔初版〕、2012年第2版)松村明〔監修〕、中型
- 現代語を重視し、新聞や放送、インターネットからも広く語彙を集める[90]。第2版は横組みで刊行された。ジャパンナレッジ、コトバンクといったウェブサイトやモバイルアプリケーションを通じて提供される『デジタル大辞泉』はかつては年3回、2022年3月時点では年2回の更新を継続し、新語・時事用語などを収録する。固有名詞の収録に特色がある。
- 三省堂現代新国語辞典
- 三省堂(1998年〔初版〕、2024年第7版)小野正弘〔編集主幹〕・市川孝ほか、小型
- 「三省堂現代国語辞典」(1988年初版)の改題改訂。高校教科書密着型を謳い、評論文のキーワードなどを重視する。第6版では「ググる」「スクショ」などの俗語や「沼」「ギガ」などの新用法を収録し「バズる」(これも新たに立項)[91]。
- 小学館日本語新辞典
- 小学館(2005年)松井栄一、小型
- 類語の使い分けが詳しい。意味などがよく問題になる語について、コラムで詳述する。顔文字のような記号によって、日常語にこもる感情がプラス(称賛)かマイナス(非難)かを示す。
- 精選版 日本国語大辞典
- 小学館(2005年 - 2006年)、大型
- 「日本国語大辞典」第2版の「エッセンスを凝縮し精選」した30万項目全3巻の縮約版であると同時に、約1500語・用例約5000例の増補が施されている。モバイルアプリケーションで提供されるほかコトバンクで引くこともできる。
注釈
- ^ 例えば和歌などの創作に際して古典的な表記を用いる場合、川は「かわ」なのか「かは」なのかを知りたい時など[11]。
- ^ a b 集文館『新選国語辞典』など。
- ^ a b 岩波書店『広辞苑』など。
- ^ 巻第29(天武天皇11年3月13日条)に「三月の(略)丙午に、境部連石積等に命じて、更に肇(はじ)めて新字一部四十四巻を造らしむ」とある[14]。
- ^ 12世紀、鎌倉初期に増補して十巻本としたのは『伊呂波字類抄』と呼ばれる[20]。
- ^ これらは「三大辞書」といわれる[23][24][25][26]。
- ^ ただし『俚言集覧』が一般に広まるのは、明治になって、1899年に『増補俚言集覧』として刊行されて以降である[28][29]。
- ^ 前編は古語・雅語、中編は雅語、後編は方言・俗語を収める[30]。なお、刊行は前編が1777年に出たにもかかわらず、後編の完結は1887年のことである。
- ^ 大槻文彦は、その原因を「議論にのみ日を費やしたせいだ」とする[39]。
- ^ この他にもヘボンの『和英語林集成』や[42]、谷川士清『和訓栞』などの近世辞書からの影響も指摘されている[43][44]。
- ^ この間の1885年には近藤真琴編『ことばのその』、1888年〜1889年には高橋五郎編『和漢雅俗いろは辞典』、1888年には物集高見編『ことばのはやし』と高橋五郎編『漢英対照いろは辞典』が刊行されている[46]。
- ^ その悲嘆のうちに本書を刊行したことが『言海』末尾の「ことばのうみ の おくがき」で述べられている[41]。
- ^ ほぼ松井簡治の独力によって成り、上田万年は名目上の共著者であったと考えられている。『世界大百科事典』「大日本国語辞典」項(林大執筆)は「上田万年・松井簡治共著(実際は松井著)」と注記する[要出典]。松井は修訂版の序「修訂版及び增補卷の刊行に就いて」で、上田が多忙であったため「殆ど一回の閱覽をも請ふことが出來なかつた」と書き、上田は版元との交渉の斡旋に当たったと続ける[52][53][54]。松井の没後、長男・驥(き)は修訂新装版の「あとがき」に「故上田萬年博士との共著といふことで、やうやく兩出版社の引受けを得たものであつたらしい」と記す。
- ^ 膨大になったのは固有名詞や動植物名を多く採録したからである[65]。
- ^ 初版は金田一編、改訂版は金田一監修。実際は見坊豪紀のほぼ独力による[68]。
- ^ 『日本辞書辞典』は「現代語本位の本格的な国語辞典の創始というべきもの」と評する[69]。
- ^ 増井元によると、岩淵悦太郎が「解説文がすぐれ、例文が適切である」と高く評価していたという[73]。
- ^ 判型は少し大きめ。
- ^ 例えば「右」の語釈に「この辞典を開いて読む時、偶数ページのある側を言う」とあるのは秀逸とされる[77]。
- ^ たとえば助詞「が」の説明だけで1ページ以上ある。
出典
- ^ a b 沖森卓也 (2023), p. 9(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 沖森卓也 (2021b), p. 145.
- ^ 田鍋桂子 (2021), p. 165.
- ^ 沖森卓也 (2023), p. 6(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 佐藤宏 (2021), p. 7.
- ^ 中川秀太 (2021), p. 32.
- ^ a b 佐藤宏 (2021), pp. 8–9.
- ^ 中川秀太 (2021), p. 33.
- ^ 中川秀太 (2021), p. 28.
- ^ 中川秀太 (2021), p. 35.
- ^ a b 橋村勝明 (2021), p. 19.
- ^ 沖森卓也 (2000), pp. 41–43.
- ^ 佐藤宏 (2021), pp. 4–5.
- ^ 沖森卓也 (2015), pp. 29–30.
- ^ 沖森卓也 (2023), p. 12(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 犬飼隆 (2000), p. 16.
- ^ 沖森卓也 (2021a), p. 147.
- ^ 沖森卓也 (2023), p. 13(原著:沖森卓也 2008)
- ^ “世界遺産 栂尾山 高山寺 公式ホームページ”. 高山寺. 2018年10月19日閲覧。
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 32–33(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 13–15(原著:沖森卓也 2008)
- ^ a b 沖森卓也 (2023), pp. 74–75(原著:沖森卓也 2017)
- ^ a b 木村一 (2021c), p. 154.
- ^ 湯浅茂雄 (1995), pp. 238–240.
- ^ 湯浅茂雄 (2000), p. 64.
- ^ 木村義之 (2015), p. 103.
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 72–73(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 木村義之 (2015), p. 111.
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 66–67(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 70–71(原著:沖森卓也 2008)
- ^ “げんかい【言海】”. goo辞書(出典:デジタル大辞泉(小学館)). 2020年8月19日閲覧。:「最初の近代的国語辞典」
- ^ "言海". 日本国語大辞典 (第2版 ed.). 小学館.:「体裁、内容の整った国語辞典として最初のもの」
- ^ "言海". 精選版 日本国語大辞典(小学館). コトバンクより2020年8月19日閲覧。:「体裁、内容の整った国語辞典として最初のもの」
- ^ "言海". 大辞林 (第4版 ed.). 三省堂.:「漢字表記・品詞・語釈などを完備した最初の近代的国語辞典」
- ^ 古田, 啓. "言海". 日本大百科全書(小学館). コトバンクより2020年8月19日閲覧。:「わが国で最初の近代的な組織の普通語辞書」
- ^ “国語施策年表 (『国語施策百年史』2006年より)” (pdf). 文化庁. 2020年7月17日閲覧。
- ^ 文部省編輯寮 編『語彙 あの部』文部省編集寮、1871年。NDLJP:862768/2。
- ^ 文部省編集局 編『語彙 えの部』文部省編集局、1884年。NDLJP:862780/2。
- ^ 大槻文彦 編「ことばのうみ の おくがき」『言海』大槻文彦(自費出版)、1891年。NDLJP:992954/634。 (巻末「ことばのうみ の おくがき」の著者:大槻文彦)
- ^ a b 犬飼守薫 (2000), p. 75.
- ^ a b c d e 沖森卓也 (2023), pp. 214–215(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 犬飼守薫 (2000), pp. 75–76.
- ^ 湯浅茂雄 (1995), pp. 252–254.
- ^ 湯浅茂雄 (1997), pp. 10–11.
- ^ 田鍋桂子 (2021), p. 158.
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 204–205(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 216–217(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 辞書解題辞典 (1977), p. 418.
- ^ 齋藤精輔 (1991), pp. 94–95.
- ^ a b c d 沖森卓也 (2023), pp. 220–221(原著:沖森卓也 2017)
- ^ a b c d 沖森卓也 (2023), pp. 224–225(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 倉島長正 (1997a), pp. 192–196.
- ^ 倉島長正 (2003), pp. 90–91.
- ^ 倉島長正 (2010), pp. 58–59.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), pp. 183–184.
- ^ a b 沖森卓也 (2023), pp. 218–219(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 倉島長正 (1997a), pp. 189–191.
- ^ 倉島長正 (2003), pp. 88–89.
- ^ 倉島長正 (2010), pp. 57–58.
- ^ “商品説明:辞書:『広辞林 第六版』”. 三省堂. 2020年8月19日閲覧。
- ^ a b 沖森卓也 (2023), pp. 226–227(原著:沖森卓也 2017)
- ^ a b 沖森卓也 (2023), pp. 228–229(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 230–231(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 石山茂利夫 (2004), pp. 262–263.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 182.
- ^ 大辭典 縮刷 - 平凡社
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 206–207(原著:沖森卓也 2017)
- ^ a b 沖森卓也 (2023), pp. 232–233(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 252.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 85.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 116.
- ^ a b 沖森卓也 (2023), pp. 234–235(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 増井元 (2013), p. 187.
- ^ 石山茂利夫 (2004), p. 135.
- ^ a b 辞書解題辞典 (1977), p. 189.
- ^ 辞書解題辞典 (1977), p. 274.
- ^ 飯間浩明 (2013), pp. 201–202.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 12.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 158.
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 238–239(原著:沖森卓也 2008)
- ^ a b c 沖森卓也 (2023), pp. 236–237(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 倉島長正 (1997b), pp. 47–49.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 59.
- ^ サンキュータツオ (2013), p. 158.
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 240–241(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 209.
- ^ サンキュータツオ (2013), pp. 156–157.
- ^ サンキュータツオ (2013), p. 170.
- ^ サンキュータツオ (2013), pp. 169–170.
- ^ 日本辞書辞典 (1996), p. 181.
- ^ ながさわ (2018年12月5日). “バズった『三省堂現代新国語辞典』第6版。「キメる」「刺さる」…さらに「攻めてる」点を紹介”. Zing!. 2018年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月18日閲覧。
- ^ 編, 石黒修 (1961). 三省堂小学国語辞典. 東京: 三省堂
- ^ 編, 時枝誠記 (1969). 文英堂学習国語辞典. 東京: 文英堂
- 1 国語辞典とは
- 2 国語辞典の概要
- 3 小学国語辞典
- 4 主題として扱った作品
国語辞典と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 国語辞典のページへのリンク