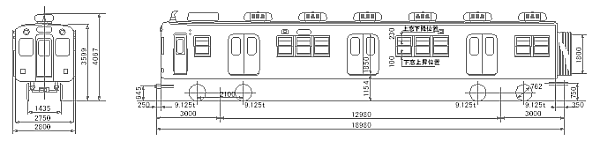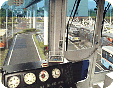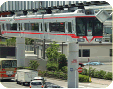5000系
5000系 普通用
5000系
5000系
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000系

| 形式 | 5000形 | 5100形 | 5600形 | 5500形 |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | 電動車 M1 |
電動車 | 付随車 T |
制御車 Tc |
| 車体 | アルミ合金製 | アルミ合金製 | アルミ合金製 | アルミ合金製 |
| 旅客定員 (座席) |
152人 (座席54人) |
152人 (座席54人) |
152人 (座席54人) |
141人 (座席50人) |
| 最大寸法 長さ |
20,725 ミリメートル |
20,725 ミリメートル |
20,725 ミリメートル |
20,825 ミリメートル |
| 最大寸法 幅 |
2.830 ミリメートル |
2.830 ミリメートル |
2.830 ミリメートル |
2.744 ミリメートル |
| 最大寸法 高さ |
4,160 ミリメートル |
4,050 ミリメートル |
4,050 ミリメートル |
4,050 ミリメートル |
| 自重 | 33.0トン | 33.0トン | 24.0トン | 29.0トン |
| 台車 | SU型ミンデン・ボルスタレス空気バネ台車 | SU型ミンデン・ボルスタレス空気バネ台車 | SU型ミンデン・ボルスタレス空気バネ台車 | SU型ミンデン・ボルスタレス空気バネ台車 |
| 主電動機 | 三相交流かご形誘導電動機 170kW |
三相交流かご形誘導電動機 170kW |
- | - |
| 駆動装置 | 歯車式平行可とう駆動式 | 歯車式平行可とう駆動式 | - | - |
| 制御装置 | VVVFインバータ制御 | VVVFインバータ制御 | - | - |
| ブレーキ 装置 |
電気指令式空気ブレーキ・回生ブレーキ併用 | 電気指令式空気ブレーキ・回生ブレーキ併用 | 電気指令式空気ブレーキ・回生ブレーキ併用 | 電気指令式空気ブレーキ・回生ブレーキ併用 |
| 製造年度 | 平成2~7年度 | 平成2~7年度 | 平成2~7年度 | 平成2~7年度 |
5000系
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/24 01:26 UTC 版)
5000系(5000けい)とは、5000の数値を使用するないしは4桁の数値の内上1桁目が「5」を使用する体系を持つものを指す。
鉄道車両
5000系または5000形と呼ばれる鉄道車両
日本
国鉄・JR
国鉄・JR以外
- 伊豆箱根鉄道5000系電車
- 一畑電気鉄道5000系電車
- 伊予鉄道モハ5000形電車
- 上田交通5000系電車
- 営団5000系電車
- 大阪市交通局5000形電車
- 大阪府都市開発5000系電車
- 小田急5000形電車 (初代)
- 小田急5000形電車 (2代)
- 小田急キハ5000形気動車
- 関東鉄道キハ5000形気動車
- 近鉄5000系電車
- 熊本市交通局5000形電車
- 熊本電気鉄道5000形電車
- 京王5000系電車 (初代)
- 京王5000系電車 (2代)
- 京阪5000系電車
- 京福電気鉄道モハ5001形電車
- 神戸市交通局5000形電車
- 神戸電鉄5000系電車
- 札幌市交通局5000形電車
- 三岐鉄道5000系電車
- 山陽電気鉄道5000系電車
- 湘南モノレール5000系電車
- 西武5000系電車
- 相鉄5000系電車
- 秩父鉄道5000系電車
- 東急5000系電車 (初代)
- 東急5000系電車 (2代)
- 東京都交通局5000形電車 (軌道)〈都電〉
- 東京都交通局5000形電車 (鉄道)〈都営地下鉄〉
- 東京都交通局E5000形電気機関車
- 東武5000系電車
- 長崎電気軌道5000形電車
- 名古屋市交通局5000形電車
- 西鉄5000形電車
- 阪急5000系電車
- 広島電鉄5000形電車
- 富士急行5000形電車
- 松本電気鉄道5000形電車
- 名鉄5000系電車 (初代)
- 名鉄5000系電車 (2代)
- 名鉄ワム5000形貨車
- 流鉄5000形電車
大韓民国
その他
- Ryzen#Zen 3アーキテクチャ - 型番に5000番台を使用した世代。世代と数字にズレが生じたため5000シリーズと呼ばれている。
関連項目
5000系
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 23:57 UTC 版)
1979年(昭和54年)5月から同年8月にかけて4両編成・2両編成各2本の計12両が登場した。更新施工は西新井工場内にある津覇車輌で行われた。 4両編成は浅草方から順にモハ5100形-サハ5200形-モハ5300形-クハ5400形、2両編成はモハ5500形-クハ5600形の順にそれぞれ編成されており、4両編成の編成形態は種車である78系のそれを踏襲したものであるが、2両編成・4両編成ともに78系とは編成の向きが逆となり、8000系等新性能車各系列と同一の向きとされた。MGはクハ5400形・クハ5600形に1基、CPは4両編成ではサハ5200形およびクハ5400形に1基ずつ分散して搭載し、2両編成ではクハ5600形に1基搭載した。 前述のように車体外観および車内設備は8000系と同一であり、運転席もマスコン・ブレーキ弁を除き共通のレイアウトである。本系列はいずれも非冷房車として落成しており、ベンチレーターとパンタグラフ(PT-42J)は8000系の冷房化改造に伴い余剰となったものが流用された。なお、パンタグラフは各電動車の連結面寄りに1基搭載されている。前面方向幕上のおでこ上辺が平面となっており、3000系と共に津覇車両製の車体の特徴となっている。 竣工当初は伊勢崎・日光線系統と東上線系統に分散配置されたが、5050系が登場すると本系列はそれらとの併結が不可能であったことから、後に全車東上線系統へ集約され、主に6 - 8連で朝ラッシュ時などの限定運用に就いていた。
※この「5000系」の解説は、「東武5000系電車」の解説の一部です。
「5000系」を含む「東武5000系電車」の記事については、「東武5000系電車」の概要を参照ください。
固有名詞の分類
- 5000系のページへのリンク