framing
「framing」の意味・「framing」とは
「framing」は英語の単語で、主に「枠組み」「構築」「設定」などの意味を持つ。特に、情報や事象を特定の視点や観点で解釈・提示することを指すことが多い。例えば、ニュース報道においては、同じ事象でもその提示の仕方(フレーミング)によって受け手の理解や感じ方が大きく変わる。「framing」の発音・読み方
「framing」の発音は、IPA表記では /ˈfreɪmɪŋ/ となる。IPAのカタカナ読みでは「フレイミング」となる。日本人が発音するカタカナ英語では、「フレーミング」と読む。「framing」の定義を英語で解説
「Framing」 is a term used in communication studies, sociology, and psychology, referring to the social construction of a social phenomenon by mass media sources or specific political or social movements or organizations. It is an inevitable process of selective influence over the individual's perception of the meanings attributed to words or phrases.「framing」の類語
「framing」の類語としては、「structuring」、「shaping」、「formulating」などが挙げられる。これらの単語も「枠組みを作る」「形成する」「構築する」などの意味を持つが、それぞれ微妙にニュアンスが異なる。「framing」に関連する用語・表現
「framing」に関連する用語としては、「frame of reference」、「media framing」、「cognitive framing」などがある。「frame of reference」は参照枠という意味で、特定の視点や基準を示す。「media framing」はメディアが情報を提示する際の枠組みを指し、「cognitive framing」は個々の認知や思考の枠組みを指す。「framing」の例文
以下に「framing」を用いた例文を10個示す。 1. English: The framing of the issue was crucial to the debate.日本語訳:問題の枠組み設定は、討論にとって重要であった。 2. English: The media's framing of the event influenced public opinion.
日本語訳:メディアの事件に対するフレーミングは、公衆の意見に影響を与えた。 3. English: The framing of the argument was biased.
日本語訳:議論のフレーミングは偏っていた。 4. English: The framing of the story made it more interesting.
日本語訳:物語の枠組み設定はそれをより興味深くした。 5. English: The framing of the policy was done carefully.
日本語訳:政策の枠組み設定は慎重に行われた。 6. English: The framing of the research question guided the study.
日本語訳:研究問題のフレーミングが研究を導いた。 7. English: The framing of the interview questions was important.
日本語訳:インタビューの質問の枠組み設定は重要であった。 8. English: The framing of the discussion helped to clarify the issues.
日本語訳:議論のフレーミングは問題を明確にするのに役立った。 9. English: The framing of the project determined its success.
日本語訳:プロジェクトの枠組み設定はその成功を決定した。 10. English: The framing of the proposal was strategic.
日本語訳:提案のフレーミングは戦略的であった。
フレーミング【flaming】
フレーミング【framing】
フレーミング
フレーミングとは、インターネット上で悪意を持って相手を貶めるために書かれる文章、またその文章に端を発する論争や喧嘩のことである。
フレーミングは、掲示板の書き込みやチャットの際などに起こりやすい。この理由として、非対面型のコミュニケーションであるために感情的な表現が目立ってしまうという点が挙げれれる。
フレーミングは、掲示板の書き込みやチャットの際などに起こりやすい。この理由として、非対面型のコミュニケーションであるために感情的な表現が目立ってしまうという点が挙げれれる。
フレーミングを防止するためには、書きこむ内容が相手にとって不快なものでないか慎重に吟味するのが必要となる。また、フレーミングを収拾するための書き込みは、より論争を加速させる結果となってしまうことが多いため、基本的には無視することが最善の対策という意見もある。
フレーミング
フレーミング
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/19 03:01 UTC 版)
フレーミングとは、
- 写真や絵画の制作において、フレームの位置、大きさなどを検討、決定すること(frame)。
- 野球において、捕手がストライクゾーンぎりぎりのボール球を、球審にストライクとコールさせる技術のこと。フレーミング (野球)を参照(framing)。
- 認知心理学や社会心理学において、枠付けをすることでものの見方を特定の方向に誘導すること(framing)。
- 火災などにおいて、炎が炎上すること(flame)。
- 転じて、電子掲示板などでの論争のこと。電子掲示板#炎上を参照(flame)。
- 悪意ある書き込みのこと。フレーミング (ネット用語)(flaming)。
- 転じて、電子掲示板などでの論争のこと。電子掲示板#炎上を参照(flame)。
- ドイツ、ブランデンブルク州とザクセン=アンハルト州にまたがる丘陵地、また文化的景観。フレーミング (ドイツ)。(Fläming)
関連項目
フレーミング
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 10:20 UTC 版)
フレーミング(Catcher Framing)とは、ストライクゾーンギリギリの投球、いわゆる「際どいボール」を捕球動作や捕球体勢などを工夫することによって審判に「ストライク」と判定させる捕球技術である。 規則上明確に定義付けられているものではないが、メジャーリーグベースボール(MLB)の公式サイトでは「Catcher framing is the art of a catcher receiving a pitch in a way that makes it more likely for an umpire to call it a strike -- whether that's turning a borderline ball into a strike, or not losing a strike to a ball due to poor framing.(フレーミングとは、ボーダーラインのボールをストライクにしたり、ストライクをボールにさせないようにしたりと、球審がストライクと判定する可能性を高める捕球技術)」と説明されている。 また、メディア上では「捕球時にミットをわずかに動かす」ことで「ボールゾーンの投球をストライクに見せる技術」と説明する向きもあるが、谷繁元信はあくまで「投球が来たところで止めて捕る」ことで「ストライクをボールと言われないようにする」ための技術であると説明しているなど、その解釈は様々である。 この技術が劣っていると捕球の瞬間にミットが流れてしまい、本来ストライクゾーンを通過しているはずの投球を「ボール」と判定されてしまう場合もある。捕手のフレーミング能力の優劣の差によっては、1シーズンあたりのチームの総失点の差が30から40ほどにまで及ぶことが判明している。MLBでは、PITCHf/xなどのトラッキングシステムを用いて「機械的に判別した投球コース」と「実際の試合での判定」との比較によってデータ化したストライクの増減値を、捕手のフレーミング能力の評価指標として用いることが一般的となっている。 野口寿浩はフレーミングについて「絶対にやらなければならないものでもないし、フレーミングありきというのはどうかなと個人的には思っている」「ここぞの時にやるから意味がある」とし、フレーミングと称してミットを動かすことに対しては「アンパイアを欺く行為でもある」「ミットを動かすキャッチャーは、アンパイアから評判が良くない」「ピッチャーに対して失礼になる」と述べている。 捕球時の捕手の姿勢・動作が球審の判定に影響を与えるということについては「フレーミング」という言葉が定着する以前から議論されており、特に捕球後にミットを動かして有利な判定を引き出そうとすることが高度なテクニックと見なされてきた。しかし2000年代頃より国際試合において「マナー違反」であるとして問題視されるようになり、北京オリンピックで決定的に表面化。これをきっかけに、露骨な「ミットずらし」は忌避される行為と見なされるに至り、特にアマチュア野球界においては「捕手はミットを動かすな」という指導方針が定められたという経緯も存在する。 ただし、2010年代後半から米独立リーグやマイナーリーグなどでの試験運用が始まっている「自動ストライクボール判定システム(Automated Ball-Strike System、ABS)」が本格的に普及すれば、捕手のフレーミング技術は不要になるとされている。
※この「フレーミング」の解説は、「捕手」の解説の一部です。
「フレーミング」を含む「捕手」の記事については、「捕手」の概要を参照ください。
「フレーミング」の例文・使い方・用例・文例
- フレーミングのページへのリンク

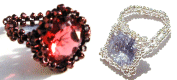 【
【


