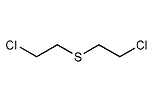マスタード‐ガス【mustard gas】
読み方:ますたーどがす
【マスタードガス】(ますたーどがす)
硫化ジクロジエチルを主成分とする毒ガス。
1886年、ドイツ人科学者マイヤーによって農薬を作る過程で偶然合成された。
皮膚をただれさせ、粘膜を破壊するびらん剤の一種。
純粋なマスタードガスは無色、無臭で粘液質だが、不純物によって黄色くマスタードのような匂いがしたため、マスタードガスと呼ばれるようになった。
気体では1500mg-分/m^3で致死率50%、液体では1滴でも触れると水疱が生じる強い毒性を持ち、解毒剤はない。
特に目、肺が敏感に作用し、少量でも重い障害が残り大量に浴びた場合は数時間で痙攣から昏睡に陥り死に至る。
作り方が比較的簡単で高度な設備や技術が必要ないため毒ガス兵器として広まり、第一次世界大戦時にイペルン戦線においてドイツ軍が初めて実戦で使用した。これにちなみ「イペリット」とも呼ばれる。
また最近ではイラン・イラク戦争でイラクがマスタードガスの入った砲弾を使用し、これにより当時のイラク大統領サダム・フセインが非難を浴びた。
その後、これが大量破壊兵器とされアメリカによるイラク攻撃の口実となった。
マスタードガス
| 分子式: | C4H8Cl2S |
| その他の名称: | イペリット、マスタードガス、硫化ビス(2-クロロエチル)、β,β'-ジクロロジエチルスルフィド、Yperite、Mustard gas、Bis(2-chloroethyl)sulfide、β,β'-Dichlorodiethyl sulfide、1-Chloro-2-(2-chloroethylthio)ethane、Bis(2-chloroethyl) sulfide、S-マスタード、S-mustard、硫黄マスタード、化学兵器ロスト、ロスト、HD、Agent HD、S-Lost、Iprit、S-ロスト、イプリット、Lost、Sulfur mustard、Kampfstoff Lost、薬剤HD、スルファマスタード、1,1'-Thiobis(2-chloroethane)、1,5-Dichloro-3-thiapentane、2,2'-Thiobis(1-chloroethane)、Chemical weapon Lost |
| 体系名: | 1,5-ジクロロ-3-チアペンタン、1,1'-チオビス(2-クロロエタン)、2-クロロエチル(2-クロロエチル)スルフィド、2,2'-チオビス(1-クロロエタン)、1-クロロ-2-(2-クロロエチルチオ)エタン、ビス(2-クロロエチル)スルフィド |
イペリット
マスタードガス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/13 14:41 UTC 版)

|
|

|
|

|
|
| 物質名 | |
|---|---|
|
1-Chloro-2-[(2-chloroethyl)sulfanyl]ethane
|
|
|
別名
Bis(2-chloroethyl) sulfide |
|
| 識別情報 | |
|
3D model (JSmol)
|
|
| バイルシュタイン | 1733595 |
| ChEBI | |
| ChEMBL | |
| ChemSpider | |
| ECHA InfoCard | 100.209.973 |
| EC番号 |
|
| Gmelin参照 | 324535 |
| KEGG | |
|
PubChem CID
|
|
| UNII | |
|
CompTox Dashboard (EPA)
|
|
|
|
|
|
| 性質 | |
| C4H8Cl2S | |
| モル質量 | 159.07 g·mol−1 |
| 外観 | 粘性の液体 純粋なものは無色透明 通常は薄い黄色~暗褐色 |
| 匂い | ニンニクもしくはホースラディッシュ様の微かな臭気[1] |
| 密度 | 1.27 g/mL, 液体 |
| 融点 | 14.45 °C (58.01 °F; 287.60 K) |
| 沸点 | 217 °C (423 °F; 490 K) 217 °Cで分解し始め、218 °C で沸騰 |
| 7.6 mg/L at 20°C[2] | |
| 溶解度 | エーテル、ベンゼン、脂肪、アルコール、テトラヒドロフランに溶ける |
| 危険性 | |
| 労働安全衛生 (OHS/OSH): | |
|
主な危険性
|
可燃性、有毒、皮膚腐食性、発がん性、変異原性 |
| GHS表示:[3] | |
 |
|
| Danger | |
| H300, H310, H315, H319, H330, H335 | |
| P260, P261, P262, P264, P270, P271, P280, P284, P301+P310, P302+P350, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P312, P320, P321, P322, P330, P332+P313, P337+P313, P361, P362, P363, P403+P233, P405, P501 | |
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |
| 引火点 | 105 °C (221 °F; 378 K) |
| 安全データシート (SDS) | External MSDS |
| 関連する物質 | |
| 関連物質 | ナイトロジェンマスタード、ビス(クロロエチル)エーテル |
|
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
|
|
マスタードガス(Mustard gas)は、化学兵器のひとつでびらん剤である2,2'-硫化ジクロロジエチル(2,2'-Dichloro Diethyl Sulfide)という化合物を主成分とする。びらん剤(皮膚をただれさせる薬品)に分類される。硫黄を含むことから、サルファマスタード(Sulfur mustard gas)とも呼ばれる。毒ガス史上1番多くの命を奪ったことから化学兵器の王様とも呼ばれている。
概要
主にチオジグリコールを塩素化することによって製造される。また、二塩化硫黄とエチレンの反応によっても生成される。
純粋なマスタードガスは、常温で無色・無臭であり、粘着性の液体である。不純物を含むマスタードガスは、マスタード(洋からし)、ニンニクもしくはホースラディッシュ(セイヨウワサビ)に似た臭気を持ち、これが名前の由来である。他にも、皮膚につくと傷口にマスタードをすりこまれるぐらいの痛さという説もある[要出典]。第一次世界大戦のイープル戦線で初めて使われたため、イペリット(Yperite)とも呼ばれる。また、不純物が多いときに呈する黄色や黄土色がマスタードに似ていたという説もある。
実戦での特徴的な点として、残留性および浸透性が高いことが挙げられる。特にゴムを浸透することが特徴的で、ゴム引き布を用いた防護衣では十分な防御が不可能である[4]。またマスクも対応品が必要である。気化したものは空気よりもかなり重く、低所に停滞する。
マスタードガスは遅効性であり、被害を受けても気づくのが遅れる。皮膚以外にも消化管や、造血器に障害を起こすことが知られていた。この造血器に対する作用を応用し、マスタードガスの誘導体であるナイトロジェンマスタードは抗がん剤(悪性リンパ腫に対して)として使用される。
ナイトロジェンマスタードの抗がん剤としての研究は、第二次世界大戦中にアメリカ合衆国で行われていた。しかし、化学兵器の研究自体が軍事機密であったことから、戦争終結後の1946年まで公表されなかった。 一説には、この研究は試作品のナイトロジェンマスタードを用いた人体実験の際、白血病改善の著効があったためという。[要出典]
マスタードガスの使用は、ジュネーヴ議定書および化学兵器禁止条約(CWC)により、国際法で明確に禁止されている。
人体への作用
マスタードガスは人体を構成する蛋白質やDNAに対して強く作用することが知られており、蛋白質やDNAの窒素と反応し(アルキル化反応)、その構造を変性させたり、DNAのアルキル化により遺伝子を傷つけたりすることで毒性を発揮する。このため、皮膚や粘膜などを冒すほか、細胞分裂の阻害を引き起こし、さらに発ガンに関連する遺伝子を傷つければガンを発症する恐れがあり、発癌性を持つ。また、抗がん剤と同様の作用機序であるため、造血器や腸粘膜にも影響が出やすい。
人体への影響は非常に長く続く。イラン・イラク戦争でマスタード・ガスの被害に遭った民間人は、30年以上経過してもなお後遺症に悩まされている[5]。
歴史
- 1859年、ドイツの化学者アルベルト・ニーマンにより初めて合成。彼は皮膚への毒性を報告するが、2年後に中毒が原因と思われる肺疾患により死去。翌1860年にはイギリスのフレデリック・ガスリーも合成して毒性を報告している。
- 1886年、ドイツの研究者ヴィクトル・マイヤーが農薬開発の過程で合成法を完成。彼はその毒性に手こずり、実験を放棄。
- 1917年7月12日、第一次世界大戦中にドイツ軍がカナダ軍に対して実戦で初めて使用し、約3500人の中毒者のうち89人が死亡。その後、同盟国・連合国の両陣営が実戦使用した。大戦中のドイツ・フランス・イギリス・アメリカの4ヶ国での生産量は計1万1千tに及んだ。
- 1943年12月、イタリア南部のバーリ港にて、アメリカの貨物船「ジョン・ハーヴェイ号」がドイツ空軍の爆撃を受け、大量のマスタードガスが流出し、アメリカ軍兵士と一般市民617名が負傷、83名が死亡した(ジョン・ハーヴェイ号事件)。
- 旧日本陸軍は「きい剤」の名称で、マスタード-ルイサイトを保有し、主に日中戦争で使用していたと見られている[6]。
- 1990年、東京の製薬会社研究所に勤める男がマスタードガスを密造し、交際相手のマンションや実家の門扉の取っ手、郵便受けなどに塗りつけて家族に火傷を負わせるという事件が発生[7]。これは日本国内での化学兵器の初使用例であり、この際の教訓から警視庁の科学捜査研究所は化学兵器を自動識別できるガスクロマトグラフ質量分析装置を導入、1995年の地下鉄サリン事件の際の原因物質の特定に活用された[7]。
- 2002年9月25日、神奈川県寒川町の旧相模海軍工廠跡地の工事現場でマスタードガスが入ったガラス瓶が発見される[8]。
- 2008年4月、浦添市内の建設現場で沖縄戦当時のアメリカ軍の不発弾76発が見つかった。そのうち、22発は1943年製のM57迫撃砲弾で、マスタードガスが入った化学弾だと見られている[9]。
- イラン・イラク戦争当時、イラク軍はイラン軍および自国のクルド人に対し、マスタードガス、サリン、タブンを使用したと言われる(ただし異説あり)。このうちクルド人に対して行なわれたものを、事件の起こった町の名を取って「ハラブジャ事件」と呼ぶ。詳細は同ハラブジャ事件の項を参照。
その他
フラットウッズ・モンスターの目撃者の症状がこのマスタードガスを浴びた際の症状に似ているという[要出典]。
関連項目
出典
- ^ FM 3–8 Chemical Reference handbook, US Army, 1967
- ^ Mustard agents: description, physical and chemical properties, mechanism of action, symptoms, antidotes and methods of treatment. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Accessed June 8, 2010.
- ^ “Sulfur Mustard”. PubChem, US National Library of Medicine (2025年9月27日). 2025年10月13日閲覧。
- ^ 生物・化学兵器への公衆衛生対策(世界保健機関)2004年
- ^ “イラン・イラク戦争開戦から40年、生存者が語る毒ガス攻撃の恐怖”. AFP (2020年9月23日). 2020年9月27日閲覧。
- ^ 内閣府大臣官房遺棄化学兵器処理担当室
- ^ a b 服藤恵三『警視庁科学捜査官』文藝春秋、2021年。ISBN 978-4163913445。
- ^ “事故発生より現在までの経緯”. 国土交通省 (2002年). 2025年5月31日閲覧。
- ^ 不発弾、化学兵器の可能性 琉球朝日放送報道制作局 2008年4月24日
「マスタードガス」の例文・使い方・用例・文例
マスタードガスと同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- マスタードガスのページへのリンク