みどり
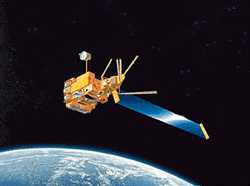
名称:地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」/AdvancedEarthObservingSatellite(ADEOS)
小分類:地球観測衛星
開発機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))/環境庁(EA)/通商産業省(MITI)/アメリカ航空宇宙局(NASA)/フランス国立宇宙研究センター(CNES)
運用機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げ年月日:1996年8月17日
運用停止年月日:1997年6月30日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:H-II
打ち上げ場所:種子島宇宙センター (TNSC)
国際標識番号:1996046A
みどりは8つのセンサを搭載した地球観測衛星です。
海色海温走査放射計(OCTS=Ocean Color and Temperature Scanner)は、海洋の水色と水温データを取る光学センサで、海洋の基礎生産量や炭酸ガスの循環の把握、漁海況情報の把握、環境モニタなどに利用されます。
高性能可視近赤外放射計(AVNIR=Advanced Visible and Near-Infrared Radiometer)は、陸域や沿岸域から反射される、可視から近赤外域の太陽光を観測する高分解能の光学センサで、そのデータは熱帯林破壊、砂漠化、水質汚染などの把握・監視や、土地利用・資源探査などに利用されます。
改良型大気周縁赤外分光計(ILAS=Improved Limb Atmospheric Spectrometer)は、南北両半球の高緯度地方の、成層圏オゾンを監視・研究するための大気センサです。
地上・衛星間レーザー長光路吸収測定用リトロリフレクター(RIS=Retroreflector in Space)は、地上から発射されるレーザー光を地上に反射し、往復の光路の大気吸収スペクトルを測定して、地上局上空のオゾン、フロン12、メタンなどを測定します。
温室効果気体センサ(IMG=Interferometric Monitor for Greenhouse Gases)は、温室効果気体(二酸化炭素、水蒸気、メタン、一酸化炭素、オゾンなど)の濃度分布の観測などを行ないます。
NASA散乱計(NSCAT=NASA Scatterometer)は、氷におおわれていない全海域(90%)の風速と風向を天候に左右されることなく、2日ごとに観測します。
オゾン全量分光計(TOMS=Total Ozone Mapping Spectrometer)は、オゾン層の総量の分布を計測し、二酸化イオウの検出により、火山の爆発を知ることができます。
地表反射光観測装置(POLDER=Polarization and Directionality of the Earth's Reflectances)は、地球表面、エアロゾル、雲、海で反射される太陽光の偏光、方向性、分光特性を測定し、温室効果ガス増加による地球輻射の潜在的な影響、対流圏におけるエアロゾルの循環、全球的な炭素循環の解明を行ないます。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
一翼式の太陽電池パドルを持つモジュール方式です。本体は約4m×4m×5m、太陽電池パドルは約3m×24mの大きさです。
重量は約3.56t(打ち上げ時)。姿勢制御方式は、3軸姿勢制御方式(ゼロモーメンタム)を採用しています。
みどりは宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))が開発した2つのセンサーのほかに、NASA、CNESなどにより開発された6つのセンサーを搭載しています。
2.どんな目的に使用されるの?
みどりの通信システム地球の温暖化や、オゾン層の破壊、熱帯雨林の減少、異常気象の発生などの環境変化が年々進んでいますが、みどりは、こうした全地球規模の環境に関する観測データを取り、地球環境監視に役立てることを目的としています。また、それとともに、将来型衛星の開発に必要な技術(プラットフォーム技術)と、地球観測などの衛星間データ技術の開発などを目的としています。
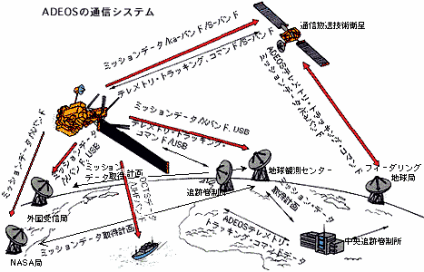
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
打ち上げ後、太陽電池パドルやNACATアンテナなどを広げ、定常姿勢制御モードへ移り、その後、初期軌道制御を実施。また、OCTS、AVNIRの初画像を正常に受信することに成功するなど、初期段階において各機器が正常に作動するか、機能確認試験を実施しました。順調に地球観測データを送り続けていたものの、太陽電池パドルに異常が発生して1997年6月に同衛星は機能を停止したため、以来運用停止になっています。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
みどりIIがあります。
5.どのように地球を回るの?
高度約800km。公転周期約101分(地球を約101分で1周します)、軌道傾斜約98.6度の太陽同期準回帰軌道です。太陽同期準回帰軌道とは、いつもほぼ同じ時刻に同一地点の上空を通過するため、観測衛星に向いている軌道です。また、地球の自転によって経路が少しずつずれていきますが、41日後には再び同じ時刻に同じ位置に戻っています(回帰周期)。
- AdvancedEarthObservingSatelliteのページへのリンク
