こん‐やく【婚約】
婚約(こんやく)
婚約
婚約の形
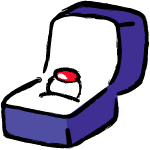 昔は婚約といえば結納でしたが、最近は結納を行わない人も増えてきています。結納以外で婚約の形として、『食事会を行う』『婚約指輪を贈る』『婚約式を行う』『婚約通知を送る』『婚約披露パーティーを開く』などがあります。
昔は婚約といえば結納でしたが、最近は結納を行わない人も増えてきています。結納以外で婚約の形として、『食事会を行う』『婚約指輪を贈る』『婚約式を行う』『婚約通知を送る』『婚約披露パーティーを開く』などがあります。
贈答習慣
婚約記念品は、両家の食事会などの際に、お互いが交換し合ったり、しきたりにこだわらない結納での席で、正式な結納品の代わりに送ったりします。必ずしも必要なものではありませんが、婚約の証として用意することがあります。男性から女性へ贈るものとしては『指輪』『アクセサリー』『着物』など、女性から男性へ贈るものとして『腕時計』『スーツ』などがあります。
記念品を贈る
婚約の印として男性から女性に贈られる『エンゲージリング』。そのほとんどはダイヤモンドの指輪ですが、誕生石の指輪を贈ってもいいでしょう。かつては給料の3ヵ月分が目安といわれていましたが、値段に関係なく気に入った物を選ぶとよいでしょう。
お返し側
婚約指輪のお返しとして女性から婚約記念品を贈ります。腕時計やスーツ、礼服などが一般的ですが、値段は男性から指輪を贈られている場合、金額は指輪の3分の1程度が多くなっています。
誕生石一覧
| 月 | 誕生石 | 意味 |
|---|---|---|
| 1月 | ガーネット | 貞節、忠実、友愛 |
| 2月 | アメジスト | 誠実、純真、平和 |
| 3月 | アクアマリン・サンゴ | 聡明、沈着、知恵 |
| 4月 | ダイヤモンド | 純潔、清浄、貞潔 |
| 5月 | エメラルド | 愛、幸福 |
| 6月 | パール | 富、健康、長寿 |
| 7月 | ルビー | 情熱、自由、率直 |
| 8月 | サードニックス・ペリドット | 友愛、夫婦和合 |
| 9月 | サファイア | 心理、慈愛 |
| 10月 | オパール | 忍耐、克己、希望 |
| 11月 | トパーズ | 友情、友愛、忠誠 |
| 12月 | トルコ石 | 成功、不屈 |
婚約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/18 13:47 UTC 版)



婚約(こんやく、フランス語:fiançailles, 英語:engagement, betrothal)とは、結婚の約束をすること[1]。 婚約した相手をフランス語では「fiancé(e) フィアンセ」と言い、日本語では「婚約者」と言う。
概説
婚約の発表の形態や方法には様々な様式があり、その文化的、法的な位置づけも様々である。 結婚式が宗教的になされることが多いので、婚約もまた宗教的な面が見られることが多い。キリスト教圏とイスラム教圏と仏教圏では、結婚や婚約の仕方は大きく異なることが多い。ただし近年では各国とも、生活の欧米化にともなって、キリスト教圏の影響が大きい。 欧米の伝統的な理解では、婚約は契約であり、婚約後に履行を拒むことは契約違反と見做される。しかし、離婚の増加や婚姻に関する考え方や慣習が変化する中で、婚約破棄を契約違反とは見做さない法理や判例も現れており、アメリカでは婚約違反訴訟を廃止している州も多い[2]。
婚約から結婚までの間の期間を婚約期間といい、かつては居住環境の構築や、必要となる知識やスキルを習得するなど、結婚後の生活を立ち上げるための準備期間と考えられていたが、結婚への準備が簡素化した現代では、その婚姻を本当に自分は欲しているかどうかを再検討するための猶予期間と捉えられる場合も多い[2]。
世界における婚約
ローマ・カトリック
ローマ・カトリックにおいては、歴史的にはbetrothal婚約は、結婚と同程度に拘束力の強い、形式を伴った契約だと見なされていたもので、それを解除するには正式に離縁の手続きを経る必要があった[3]。婚約をした男女は、たとえ結婚式をまだ挙げていなくても、また肉体的関係を持っていなくても、夫と妻であると法的にも認められた。人々に公にする形での「婚約期間」という概念は、1215年の第4ラテラン公会議(インノケンティウス3世が指揮したもの)によって導入された。「結婚することになる者たちは、教会で司祭によって人々の前で公に名を告げられるべきである。そうすることによって正統性のある障害[4]がある場合は、それがやがて明らかになるからである Medieval Sourcebook: Twelfth Ecumenical Council: Lateran IV 1215」。このような、教会による公の告示は、banns of marriageとして知られている。地区(教区)によっては、このようなbannsを声にして読みあげることが、結婚式の一部になっている場合もある。
正教会
正教会では、婚約は伝統的に、教会堂の拝廊で行われ、男女が結婚の第一段階に入ったことを示す。神品(聖職者)が婚約者たちにキスをし、蝋燭に火をともし、彼らにそれを持たせる。連祷および参加者全員による祈祷の後、「花嫁の指輪」を花婿の右手の指にはめ、「花婿の指輪」を花嫁の指にはめる。聖職者または花婿付き添いの男がそれを3回繰り返し、それを終えた後、最後の祈りをささげる。もともとは、婚約の式は、婚約の発表と同時に行われていたが、近年では結婚式の直前に行われる傾向がある。正教会では指輪の交換は結婚式では行われず、あえて言えば婚約式の中でだけ行われる。伝統的には「花婿の指輪」は金で、「花嫁の指輪」は銀である。
欧米圏
多くの欧米圏(オーストラリアや南アメリカを含む)では、婚約パーティーを開くことも多い。婚約パーティーは くだけた雰囲気で行われることが大半で、ゲストからの贈り物も求められない(ただし自主的に持参する人もいる)。またしばしば婚約指輪を交換する。
ただし、これらの慣習は、国・民族ごとに差異があるので、一律に述べることはできない。
アフリカ圏
アフリカ圏では、婚約指輪を交換するという伝統的な慣習は特にない。
アジア
近代になって、生活が欧米化するにつれて、風習もだんだん欧米化していくようだが、昔ながらの伝統的な慣習に従うことも多い。
中国は地方によりいろいろな習慣があり、1978年の改革開放以来、経済発展が早い中国南方では西洋文化が導入され、婚約、結婚式なども欧米化していく傾向がある。一方で内地においては伝統習慣が強く、伝統的な式が執り行われる場合が多い。
アジア圏では、婚約指輪を交換するという伝統的な慣習は特にない。ただし、この点は日本も同様である。
日本における婚約
日本文化における婚約
 |
この節の加筆が望まれています。
|
婚約の法的効力
婚約の意義
日本では講学上において、婚約は男女間の将来的な婚姻についての契約と位置づけられている。ただし、日本の民法には婚約について全く規定が設けられていない(婚約の法的効果については判例による)[5]。
婚約は内縁とは異なる[6]。一般に婚約は「婚姻の予約」として理解されるが、判例には内縁について婚姻予約と位置づけて保護したものもあり、注意を要する[7]。
婚約の要件
不要式行為
婚約は何ら方式を必要としない不要式行為である(最判昭38・9・5民集17巻8号942頁)[8]。学説には確実な合意で足りるとする学説と公然性を要求する学説があり、対立点となっている[9]。
ただし、結納や婚約指輪の交換は婚約成立の証明となり[10]、後に当事者間で婚約の不履行が問題となった場合においても婚約の存在を証明するものとして重要な意味を持つ[11]。外形的事実のない場合における婚約成立の認定には特に慎重さが求められるとされる[8]。
婚姻障害事由との関係
婚姻時に婚姻障害事由が存在しなければ、婚約時に婚姻障害事由が存在してもその効力は否定されない[12](婚姻適齢に達していない場合や未成年で父母の同意がない場合にも婚約については有効に成立する)。近親婚の禁止に違反する婚約は無効となる[12]。
法律上の配偶者のある者との婚約の有効性については、大正期にこれを否定した判例があるが(大判大9・5・28民録26輯773頁)、事実上の離婚状態にあればこれを有効と解する学説がある[12]。
婚約の効力
婚約は婚姻についての合意(契約)ではあるが、その本質上、婚姻は両性の合意のみによって成立させるべきものであることから(日本国憲法第24条1項参照)、婚約の強制履行は認められない(通説・判例。判例として大連判大4・1・26民録21輯49頁)[13][12][8][11]。
しかし、正当な理由なく婚約を破棄した場合には相手方に対して債務不履行あるいは不法行為として損害賠償責任を負わねばならない(通説・判例。判例として最判昭38・9・5民集17巻8号942頁)[13][12][8][11]。
相手方に帰すべき事由によって、やむなく婚約を破棄する場合にも、その相手方に対して損害賠償を請求しうる(最判昭27・10・21民集6巻9号849頁)[12]。また、他者の婚約関係を不当に妨害した者は共同不法行為者として不法行為責任を負う(通説・判例。判例として最判昭38・2・1民集17巻1号160頁)[13][14][8][11]。
なお、結納が交わされていた場合には、その返還について別途問題となる。
他

婚約時に交換される指輪は婚約指輪と呼ばれ、男女とも左手の薬指につける。男性の払う着手金のような意味合いがある[要出典][15]。
一方、結婚指輪は比較的安価なものが選ばれる。
婚約をしてから婚約指輪を交換するのではなく、男性が婚約指輪を贈ることでプロポーズ(求婚)することもある。
日本の婚約破棄率
婚約破棄には書面などが必要ないことから、日本での婚約破棄に関する公式な統計データは存在しない。
しかし、日本の婚約破棄について調べたデータ[16](結婚の約束をしたことのある男女200名を対象にインターネット経由でアンケート 調査時期:2020年5月)によると、婚約破棄率は45%という結果がでている。
この調査結果は、別れて破談になっただけではなく『結婚前の死別・別れてはないが、結婚の話がなくなった』なども含まれる。
脚注
- ^ 広辞苑第六版「婚約」
- ^ a b 國府剛「アメリカにおける婚約違反訴訟廃止の現況」『關西大學法學論集』39(4 - 5) 関西大学法学会 NAID 120007097747 1990-02-20 pp.713 - 744.
- ^ ASK
- ^ 本当は男女のどちらかに、すでに正式に結婚している相手がいるのに、それを相手に隠している場合などのこと。
- ^ 青山・有地、1989年、279-280頁
- ^ 我妻 他、1999年、55頁
- ^ 我妻 他、1999年、55-56頁
- ^ a b c d e 青山・有地、1989年、280頁
- ^ 川井、2007年、8頁
- ^ 二宮、1999年、98-99頁
- ^ a b c d 我妻 他、1999年、56頁
- ^ a b c d e f 二宮、1999年、99頁
- ^ a b c 川井、2007年、9頁
- ^ 二宮、1999年、99-100頁
- ^ 景気の影響もあり日本では婚約指輪そのものを交わさないという婚約も一般的になってきている。ダイヤモンドのような高価な宝石の指輪にすることが多い[要出典]。この時「男性の月給3か月分」などと言われることもあるが、この月給3か月分という数字そのものには全く根拠がなく、もともと1950年代に米国でデ・ビアス社(宝石会社)が宝石(ダイヤモンド)を販売することを目的として "Diamond is forever" (ダイヤモンドは永遠の輝き)というキャッチフレーズとともに「婚約指輪は給料の2か月分」という宣伝キャンペーンを行って大成功し、それがそのまま日本に渡って1970年代頃から日本においても同「ダイヤモンドは」のキャッチフレーズとともに「婚約指輪は給料の3か月分」として定着した。よってこの金額にしないといけない、という具体的な根拠はない。(リンク切れ)婚約リング物語 ゆえに(上記の広告キャンペーンが行われていなかった)日本や米国以外の国々でこのような高価な金額の婚約指輪を日常一般的に贈ることは稀である。
- ^ “【悲報】婚約破棄率の統計データを取ったら約半分のカップルがプロポーズ後破局している結果に!”. 復縁占い当たるのはココ! (2020年5月11日). 2020年5月13日閲覧。
参考文献
- 青山道夫・有地亨編著『新版 注釈民法〈21〉親族 1』有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月
- 我妻榮・有泉亨・遠藤浩・川井健『民法3 親族法・相続法 第2版』勁草書房、1999年7月
- 川井健『民法概論5親族・相続』有斐閣、2007年4月
- 二宮周平『家族法 第2版』新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月
関連項目
婚約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 02:35 UTC 版)
「アンヌ・ド・ブルターニュ」の記事における「婚約」の解説
娘の結婚問題で、フランソワ2世はフランス王に対して自らの地位を強めていった。自分の領土にブルターニュ公国を加えようとするヨーロッパ各国の王子たちの目論見は、同時に相手国との同盟関係を築くことになるため、常に効果的であった。 1481年、イングランド王エドワード4世の息子であるプリンス・オブ・ウェールズ、エドワード王子と公式に婚約。王子は父親の死後自動的にエドワード5世となるが、その後すぐに失踪している(薔薇戦争中の1483年に死んだとされている)。 ヘンリー7世との結婚はブルターニュ側が持ち出したが、ヘンリー自身がこの結婚に興味を示さなかった。 ローマ王のマクシミリアン(のちの神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世)は、当時ブルゴーニュ女公マリーと死別して寡夫となっていた。 アラン・ダルブレ - カトリーヌ・ド・ロアンの息子で、ブロワ=パンティエーヴル家のフランソワーズの夫。フランソワ2世のいとこにして同盟者。 オルレアン公ルイ(のちのルイ12世) - シャルル8世のいとこ。しかし既にフランス王女ジャンヌと結婚していた ジャン・ド・シャロン - オランジュ公。リシャール・デタンプの娘カトリーヌを母とする。フランソワ2世の甥。アンヌとイザボー姉妹に次ぐブルターニュ公位継承権者 レオン子爵ジャン2世・ド・ロアンは、彼自身もブルターニュ公位継承権者であり、自分の息子フランソワおよびジャンを、アンヌとイザボー姉妹と二重結婚させる案を出したが、フランソワ2世に拒否された。
※この「婚約」の解説は、「アンヌ・ド・ブルターニュ」の解説の一部です。
「婚約」を含む「アンヌ・ド・ブルターニュ」の記事については、「アンヌ・ド・ブルターニュ」の概要を参照ください。
婚約
「婚約」の例文・使い方・用例・文例
- 彼女は突然婚約を破棄した
- 破約,婚約不履行
- 彼はパーティーに婚約者を伴って来た
- 彼らの婚約は私たちにはまさしく寝耳に水だった
- 婚約
- 婚約中の2人
- ジムは私の姉と婚約している
- 彼は以前の教え子と婚約した
- 彼はジェーンとの婚約を発表した
- 婚約を破棄する,破談にする
- 彼らは婚約を解消した
- 婚約指輪,エンゲージリング
- 彼女は父親ほどの年の男と婚約していた。
- 私は婚約していて彼に捨てられた。
- 彼女の父親の健康状態の関係で、彼女と彼女の婚約者の家族の間だけの小さな集まりになる予定です。
- 婚約しています。
- 私の婚約者がこの週末私の家に来る。
- 彼女は今の夫と出会った時、既に婚約者がいました。
- 彼女は彼との婚約を破棄した。
- 私たちは婚約しました。
品詞の分類
- >> 「婚約」を含む用語の索引
- 婚約のページへのリンク





