ウイスキーの製造工程(図)
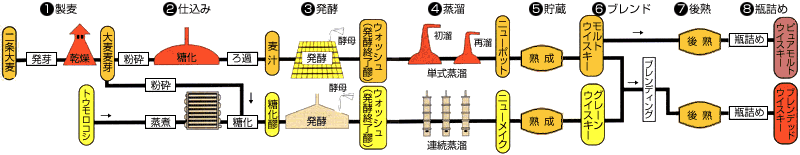 |
ウイスキーの製造工程(酵母)
| 糖化した麦汁に酵母を加えると、酵母は麦汁中の糖分を分解し、アルコールと炭酸ガスに変えるとともに、ウイスキー独特の味わいや香気成分をつくります。上面発酵酵母、液中分散酵母などがあり、サントリーでは約3000種類の酵母を保有しています。そのうちウイスキー用として好ましいものは、約200種類。それらの中から求める香味に合わせて複数の酵母を使い分けます。 |
ウイスキーの製造工程(仕込み)
| 酵母は、穀物のデンプンをそのままアルコールに変えることはできません。そこで、まず発芽した大麦を乾燥させて大麦麦芽(モルト)をつくります。これを細かく砕いて温水を加え、約65℃にし、麦芽中の糖化酵素でデンプンを糖類に変え、これを濾過して甘い麦汁(ばくじゅう)をつくります。これを発酵、蒸溜したものが、モルトウイスキーです。グレーンウイスキーの場合は、蒸煮した穀物に大麦麦芽を加えて、同様に糖類に変えていきます。これらの変化過程を糖化といいますが、仕込みともいいます。麦汁の味わいは仕込みの水質に大きく左右されるため、蒸溜所は良い水の湧く土地に立地しています。 |
ウイスキーの製造工程(熟成)
| ニューポットをホワイトオークでつくった樽の中で寝かせると、やがて荒々しかった香味は芳香とまろやかさをもち、無色透明の液体は、深い琥珀色に生まれかわります。これを樽熟成といいます。樽の中では、樽材を通して不要な成分が空気中に蒸散していったり、徐々に樽に入ってきた空気によって原酒の成分が酸化したり、またエステル化が進んだり、樽材からリグニン、糖類、オークラクトンなどの成分が溶け出し微妙に影響し合うことによってウイスキー独特の香味成分が生成されてゆきます。熟成期間は一概に長ければ長いほどよいということではなく、ニューポットの個性、樽の種類、熟成の仕方で熟成年数は変わってきます。それぞれに最も適した熟成年数を見極めることが大切なのです。熟成が「時の技」と神秘的に表現されるのはそのためです。熟成年数の違いによってさまざまな個性を持ったモルト原酒が生み出されますが、20年〜30年の長期熟成に耐えうるウイスキーはまれで、良質なモルトのあかしといえます。 |
ウイスキーの製造工程(蒸溜)
| 蒸溜とは、液体を加熱し、沸騰点のちがう揮発成分を分離・濃縮することです。ウイスキーの場合、穀物を発酵させたアルコール含有液 ウォッシュ(醪=もろみ)を蒸溜機にかけてアルコール濃度の高い酒を取り出すことです。ジャパニーズウイスキーやスコッチウイスキーは、大麦麦芽の発酵液を単式蒸溜器で2回蒸溜して、アルコール度数70度前後のモルトウイスキーをつくります。また、穀物の発酵液を連続式蒸溜機で蒸溜して、93度前後のグレーンウイスキーをつくります。アイリッシュウイスキーは穀物の発酵液を単式蒸溜器で3回蒸溜して、原酒とします。アメリカやカナダのウイスキーは一部の例外を除いて、連続式蒸溜機で蒸溜します。 |
ウイスキーの製造工程(製麦)
| ウイスキーへの第一歩は麦芽(モルト)づくり。精製した二条大麦を水に浸して発芽させ、デンプンを糖分にかえる酵素(アミラーゼ)がほどよく生まれたところで乾燥させ成長を止めます。これを製麦といいます。麦を乾燥させる時に、燃料の一部としてピートを焚きます。その煙から独得の香り(スモーキーフレーバー)が麦の中にたきこめられます。 |
ウイスキーの製造工程(貯蔵)
| 蒸溜を終えたニューポットは、オークの樽に詰め、貯蔵庫でじっくり寝かせます。貯蔵中のウイスキーは樽材を通してゆっくりと外気を呼吸し、樽材から溶け出してくる微量成分と溶けあいながら、やがて琥珀色に色づき、まろやかな香味を備えていきます。樽は、揺り籠。ウイスキーは、樽貯蔵なしには生まれません。 |
ウイスキーの製造工程(発酵)
| 麦汁に酵母を加えると、はじめは細かい泡がたち、やがて激しくなり、槽は一面純白の泡に包まれます。発酵が終わりに近づくと、液面はおだやかになります。発酵は25℃〜35℃の間で3日間おこなわれ、発酵終了後のアルコール度数6〜7%のこの液をもろみと呼びます。発酵により生成されるもろみ成分のほとんどは、エチルアルコールですが、それ以外にきわめて微量ではありますが、ウイスキーにとって重要な高級アルコール類、エステル類、脂肪酸類など数百種類に及ぶ香気成分が生成され、これらのバランスがウイスキー独特の香味の特徴を生みます。酵母以外にもミクロフローラと呼ばれる微生物群(主として乳酸菌)によっても香気成分が生成されます。またウイスキーの発酵槽には、木製と金属製の2種類があり、これによっても香気成分は微妙に異なってきます。 |
ウイスキーの製造工程(瓶詰め)
- ウイスキーの製造工程のページへのリンク
