サーベイヤー【Surveyor】
サーベイヤー
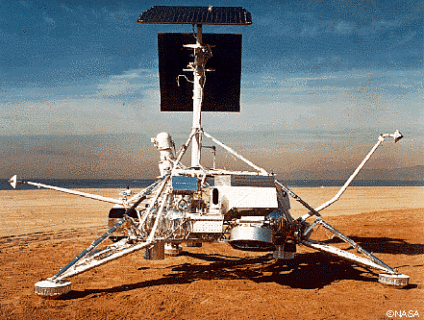
名称:サーベイヤー1〜7号
小分類:月探査
開発機関・会社:アメリカ航空宇宙局(NASA)
運用機関・会社:アメリカ航空宇宙局(NASA)
打ち上げ年月日:サーベイヤー1号(1966年5月30日)/サーベイヤー2号(1966年9月20日)/サーベイヤー3号(1967年4月17日)/サーベイヤー4号(1967年7月14日)/サーベイヤー5号(1967年9月8日)/サーベイヤー6号(1967年11月7日)/サーベイヤー7号(1968年1月7日)
運用停止年月日:サーベイヤー1号(1966年6月2日)/サーベイヤー2号(1966年9月23日)/サーベイヤー3号(1967年4月20日)/サーベイヤー4号(1967年7月17日)/サーベイヤー5号(1967年9月11日)/サーベイヤー6号(1967年11月10日)/サーベイヤー7号(1968年1月10日)
打ち上げ国名:アメリカ
打ち上げロケット:アトラス・セントール
打ち上げ場所:ケープカナベラル空軍基地
国際標識番号:サーベイヤー1号:1966045A/サーベイヤー2号:1966084A/サーベイヤー3号:1967035A/サーベイヤー4号:1967068A/サーベイヤー5号:1967084A/サーベイヤー6号:1967112A/サーベイヤー7号:1968001A
サーベイヤーのシリーズは、ルナー・オービターと並んで、アポロ有人月着陸計画の下準備となる計画でした。月の周回軌道から表面全体の写真を撮るルナー・オービターに対して、サーベイヤーは月の表面に着陸して月の地形をテレビで送信してくることになっていました。サーベイヤー1号は本来テスト用でしたが、1966年6月2日に月の嵐の大洋の南にふんわりと着陸するのに成功しました。心配されたように着陸脚が表面にめりこむこともなく、回りの地形の画像を11,237枚も送信して来ました。サーベイヤー2号以下も、2号と4号が着陸に失敗しましたが、残りの4機は着陸に成功、画像を送信しています。サーベイヤーの事前調査のおかげで、アポロは安心して月に降りることができたのです。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
サーベイヤー1号:上から見て三角形にパイプを組み、機器を取り付けた形をしています。三角の各頂点に着陸脚、上部には太陽電池板と平面アンテナが取り付けられています。高さ3m、幅4.3m、打ち上げ時の重量は995kg、月着陸時の重量は294kg。
2.どんな目的に使用されたの?
月表面のテレビ画像撮影、土壌の分析です。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
月の表面がアポロ宇宙船の着陸に耐えられることを証明しました。そして、月の地形のパノラマ画像撮影や、月の岩石が玄武岩質であることを分析しました。
4.打ち上げ・飛行の順序はどうなっているの?
サーベイヤー1号:1966年5月30日打ち上げ、直行軌道で月へ。月からの高度96kmで固体ロケットにより減速開始、降下速度は9,600km/hから400km/hへ。液体ロケットでさらに減速を続け、高度4.3mでエンジン・カットオフ。接地速度は11km/hでした。
サーベイヤー
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/25 18:09 UTC 版)
サーベイヤー(surveyor)とは、イギリスにある建物や土地造成設計などの都市建設事業と不動産事業にかかわる職能。資格名としてもこの名称が使用されている。
サーベイヤーは、王室建設局および植民地の最高技監の歴史的な職名 (surveyor general) でもあった。
日本における用例
日本で一般にイギリスのサーベイヤーをさす場合、英国王立勅許鑑定士協会で認定されるチャータード・サーベイヤーを指すか、コストマネジメント専門家・積算技術者であるクオンティティ・サーベイヤー (Quantity_surveyor) を指している。
サーベイヤーは建設に関してかなり広範囲な業務を担う職種であり、現代の解釈でこの職種については「日本の国家資格では、建築士、土地家屋調査士、測量士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者等の業務範囲を行なう。歴史的には積算、建物検査、コンストラクション・マネジメント、プロジェクトマネジメントをする業として広がってきた。他に、商業不動産の評価、ファシリティマネジメント、プランニングと開発、環境評価、マネジメント・コンサルトなどを行う。」[1]との解説がある。
イギリス独自の職能名であるが、主に不動産における各種の「調査」「鑑定」を行うことから、日本語に訳すときは調査士、鑑定士などと訳される。それぞれ日本では土地家屋調査士、不動産鑑定士の略称として使用されているが、どちらも公益を重視した資格であり、職務内容的にも歴史的なサーベイヤーの位置付けに合致している。
その他、行政機関においては、法務省による日本法令外国語訳データベースシステムで建築主事を「Surveyor」と訳している例がある。
歴史的背景
ヨーロッパ諸国に出現したアーキテクトの形成にも歴史的段階があり、サーベイヤーはアーキテクトに先行する職能としてイギリスに以前からみられた職名で、一部がのちにアーキテクト(建築家)へと分離発展する。
16世紀から18世紀まで長らくアーキテクトなどと同義に使われたサーベイヤーは、歴史的にみるとクラフトマンとは違った系譜の下で発展してきている。
サーベイヤーの前身は12世紀に設置されたビュアー(Vewer「監査官」)という会計検査的な側面と現場監督的側面をもつ職務の官職にさかのぼる。当時イギリスは国家形成期で王室建設局は直轄監理できるほど発達していなく、技術職人・技能士からの人足集めや手配から資材の購入と納品管理、運搬から建設資金の運用など建設工事の責任主体は各地方州長官が担った。
このとき州政府の建設工事について監督し、工費の正当性を財務裁判所で証言する役目がビュアーである。ビュアーには主に医者や牧師など、ほかの職業をもち王室に信頼を得ている人が就任しており、一般に建築技術等については素人であったとされている。
その後、国家体制の集権化の中で増大する工事量をさばくために、工事管理者の位置づけのキーパー(keeper)という職が出現する。さらには、現場監督という位置づけである建設局所属のクラーク(clerk of the work)が現われる。とくに、それまでの証言方式から書類方式とする1236年の会計制度の改革に伴い、王室建設局はクラークを軸に展開する。
1378年にはイギリス全土の王室建築工事をすべて統轄するクラークが確立し集権化が達成されるとともに、ここから14世紀に「クラークがサーベイする」という言い方が生まれる。集権国家体制の中で建設工事全般の管理という任務が強く出されたことに由来したのである。
14世紀には王室建設局でもクラークにあたる任務者に、一時期サーベイヤーという官職名をもちいている。こうしてビュアーが徐々にサーベイヤーと発展していくようになり、その任務もすべての大工や石工その他の職人手配や、未熟な職人は腕のある職人に入れ替えるなどや仕事をやり直しを含め、しかるべく遂行するよう、彼らが王室の城郭や館その他国内の領地で行われる仕事全般を担当し、職務に属する諸々の事項が確立していくことになる。
15世紀から16世紀にかけて、名実ともにサーベイヤーが王室建設局の最高技監の職名になっていく。他方、18世紀の修道院領没収という政策によって、その払い下げを受けた新興地主の土地・財産(イギリスでいうところのエステート)の管理が急増し、民間においてこの仕事を引き受ける職能が大量に出現し、これらがエステート・サーベイヤーとして発展する。
こうしてイギリスに発生したサーベイヤーは14、5世紀の建設工事管理的職務に、さらに測量・物件鑑定・見積り積算など、今日のサーベイヤー的な職務がだんだんと加わって、民間の建設コンサルタント的職能の確立をみていった。
脚注
- ^ 齋藤・中城(2009,pp. 302―303)
関連項目
参考文献
- 秀逸建築家シリーズ 10選 アラップ・アソシエイツ 、シグマユニオン、1995年
- 近代世界システムと植民都市、布野 修司、京都大学学術出版会、2005年
- 建築積算資格者試験問題と解説 積算技術研究会
- 齋藤広子・中城康彦(2009):英国における中古住宅売買の取引制度と専門家の役割.日本建築学会技術報告集,15(29),pp. 301―304.
サーベイヤー (Surveyor)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 09:24 UTC 版)
「Trainz」の記事における「サーベイヤー (Surveyor)」の解説
Trainzにおける路線作成ツール。地面テクスチャの塗装、地形の造成、線路・駅・建物等の構造物といったオブジェクトを設置することで、オリジナルの路線データを作成することができる。
※この「サーベイヤー (Surveyor)」の解説は、「Trainz」の解説の一部です。
「サーベイヤー (Surveyor)」を含む「Trainz」の記事については、「Trainz」の概要を参照ください。
「サーベイヤー」の例文・使い方・用例・文例
- サーベイヤーという月探査機
- サーベイヤーのページへのリンク




