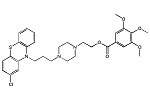【T-5】(てぃーふぁいぶ)
富士 T-5.
海上自衛隊が採用している、サイドバイサイド型のターボプロップ初等練習機。
メーカーは富士重工。
海上自衛隊では、練習機として長らくT-34「メンター」や、それを日本独自に4座化したKM-2を使っていた。
しかし、実用機がレシプロのP2VからターボプロップのP-2JやP-3Cへ代わって久しいため、エンジン特性の習熟や燃料の共用化といった観点から、ターボプロップの練習機が開発されることとなった。
機体構造はKM-2を踏襲しているが、機首が延長されトルクも強くなっているので、バランスを取るため垂直尾翼に後退角が設けられた。
またスピンからの回復訓練も考慮された結果、4座のプロペラ機としては珍しくキャノピーを備え、曲技機として使用することも可能である。
エンジンは420馬力のアリソン250を、350馬力に減格したものを使用している。
また、ターボプロップ化の副次効果として、騒音の低減も果たしている。
本機は山口県・小月基地の第201教育飛行隊(教育航空集団隷下)で運用されている。
関連:ブランエール T-7
スペックデータ
メトフェナザート
| 分子式: | C31H36ClN3O5S |
| その他の名称: | メトフェナジン、メトフェナザート、Metofenazate、Methophenazine、T-5、2-[4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazinyl]ethyl=3,4,5-trimethoxybenzoate、3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-[4-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazinyl]ethyl ester、3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-[4-[3-(2-chloro-10H-phenothiazine-10-yl)propyl]piperazino]ethyl ester、3,4,5-トリメトキシベンゾイルペルフェナジン、3,4,5-Trimethoxybenzoylperphenazine |
| 体系名: | 2-クロロ-10-[3-[4-[2-[(3,4,5-トリメトキシベンゾイル)オキシ]エチル]-1-ピペラジニル]プロピル]-10H-フェノチアジン、2-[4-[3-(2-クロロ-10H-フェノチアジン-10-イル)プロピル]-1-ピペラジニル]エチル3,4,5-トリメトキシベンゾアート、2-[4-[3-(2-クロロ-10H-フェノチアジン-10-イル)プロピル]-1-ピペラジニル]エチル=3,4,5-トリメトキシベンゾアート、3,4,5-トリメトキシ安息香酸2-[4-[3-(2-クロロ-10H-フェノチアジン-10-イル)プロピル]-1-ピペラジニル]エチル、3,4,5-トリメトキシ安息香酸2-[4-[3-(2-クロロ-10H-フェノチアジン-10-イル)プロピル]ピペラジノ]エチル |
T5
T-5
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/10 02:32 UTC 版)
ソ連が独自の核爆弾の設計に成功した1950年代初期から効果的な輸送手段が求められていた。T-5魚雷は5キロトンの爆発力を有するRDS-9核弾頭を搭載していた。1954年10月10日にカザフスタンのセミパラチンスクで行われた最初のT-5テストは失敗した。1年後、さらなる開発の末、1955年9月21日にノヴァヤゼムリャでのテストが成功した。1957年10月10日、ノヴァヤゼムリャでの別のテストでウイスキー型潜水艦S-144がT-5を打ち上げた。「Korall」と名付けられた試作兵器は湾の水面下20メートルで4.8キロトンの威力で爆発し、高放射能の巨大な水柱が上空に打ち上がった。10.4kmの距離にある退役した潜水艦三隻がターゲットとして使用された。S-20とS-34は完全に沈没し、S-19は重大な損傷を受けた。 1958年、T-5は53-58型魚雷として完全に運用されるようになった:28。ほとんどのソ連潜水艦に配備可能なこの兵器は核または高爆発物のどちらの弾頭にも交換可能であった。これにより、配備に関する迅速な戦術的決定が可能になった。アメリカのMark 45魚雷のようにT-5は直撃させるのではなく水中の爆破範囲を最大化するように設計されており、爆発により潜水艦の船体を破壊するのに十分な衝撃波を発生させる。ただし、Mark 45のようにT-5は深海潜航用に最適化されておらず、誘導機能が制限されていた。またT-5の熱的動作範囲は+5°Cから+ 25°Cであったため、北大西洋と北極圏海域での有効性が低下した。 1962年10月、 キューバのミサイル危機が始まる少し前にソ連の潜水艦B-59がアメリカ海軍によって大西洋で追跡された。ソ連の潜水艦が浮上しなかったとき、アメリカ海軍の駆逐艦は訓練用爆雷の投下を開始した。第三次世界大戦が始まったかもしれないと考えたB-59の艦長は搭載されたT-5核魚雷の発射を望んだが、偶然にもB-59を指揮艦として使用していた彼の小艦隊司令官で副艦長のヴァシーリィ・アルヒーポプは、命令の承認を拒否した。議論の末、海上へと浮上しモスクワからの命令を待つことで合意した。ソビエト連邦の崩壊後、この潜水艦がT-5で武装していたことが明らかになった。1965年の冷戦映画『駆逐艦ベッドフォード作戦』では架空のソビエトの核魚雷が配備された。
※この「T-5」の解説は、「核魚雷」の解説の一部です。
「T-5」を含む「核魚雷」の記事については、「核魚雷」の概要を参照ください。
- T-5のページへのリンク