尻屋埼灯台

- 所在地:
- 青森県下北郡東通村
- 点灯年月日:
- 明治9年10月20日
- 塗色:
- 白色
- 構造:
- 円形・レンガ造
- 光り方:
- 単閃白光 毎10秒に1閃光
- 光りの強さ:
- 530,000cd
- 光りが届く距離:
- 18.5海里
- 構造物の高さ:
- 32.82m
- 海面から光りまでの高さ:
- 45.7m
- レンズ:
- 第2等レンズ
水銀槽式回転機械 - 電源:
- 商用電源
灯塔は,レンガ造である。設計者は,R・H・ブラントンである。
尻屋埼灯台は,霧信号発祥の地であり,明治10年11月,灯ろう外縁に吊るされた霧鐘が我が国最初の霧信号となっている。
また,電気灯台発祥の地でもあり,明治34年12月,本灯台でアーク灯を点じたのが灯台電化の始まりとなっている。この光学装置は,フランスのエクミール灯台をモデルとしたもので,アラード式電気弧光灯といった。この改良により光度は3万6千燭光から一躍千3百万燭光となり,その明るさは「海の太陽」と航海者から讃えられるほどであった。
しかしながら,設備費が嵩み,取り扱いがわずらわしいところから,神島灯台(三重県)の副灯に国産品が用いられただけでアーク灯は姿を消した。
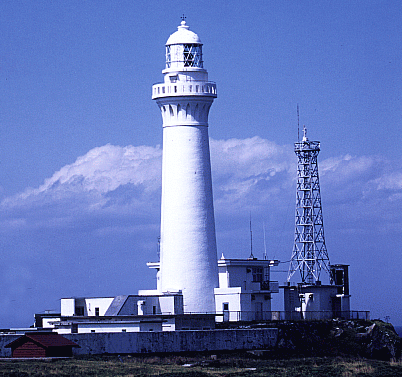
尻屋埼灯台
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/29 07:26 UTC 版)
| 尻屋埼灯台 | |
|---|---|

尻屋埼灯台
|
|
| 航路標識番号 [国際標識番号] |
1601 [M6630] |
| 位置 | 北緯41度25分49.27秒 東経141度27分43.9秒 / 北緯41.4303528度 東経141.462194度座標: 北緯41度25分49.27秒 東経141度27分43.9秒 / 北緯41.4303528度 東経141.462194度 |
| 所在地 | 青森県下北郡東通村尻屋字尻屋崎1-1 |
| 塗色・構造 | 白色 塔形 レンガ造 |
| レンズ | 第2等フレネル式 |
| 灯質 | 単閃白光 毎10秒に1閃光 |
| 実効光度 | 530,000 cd |
| 光達距離 | 18.5海里(約 34 km) |
| 明弧 | 52度から3度まで |
| 塔高 | 32.82 m (地上 - 塔頂) |
| 灯火標高 | 45.70 m (平均海面 - 灯火) |
| 初点灯 | 1876年(明治9年)10月20日 |
| 管轄 | 海上保安庁 第二管区海上保安本部 |
| 区分 | 重要文化財(建造物) |
| 指定日 | 2022年12月12日 |
| 指定コード | 02747 |

尻屋埼灯台(しりやさきとうだい)は、青森県下北郡東通村の尻屋崎の突端に立つ白亜の灯台。国の重要文化財に指定され、日本の灯台50選に選ばれている。
「日本の灯台の父」と称されるブラントンによって設計された、二重のレンガ壁による複層構造の灯台となっている[1]。周辺には寒立馬(かんだちめ)と呼ばれる馬が放牧されており、一帯は景勝地となっている。
歴史
- 1876年(明治9年)10月20日:東北最初の灯台として初点灯[2][3]。なお、参考文献での表記は「尻矢崎」となっている。
- 1877年(明治10年)11月20日:日本で初めて霧鐘が設置される[2][4]。
- 1879年(明治12年)12月20日:日本で初めて霧笛が設置される[5]。これを記念して12月20日が霧笛記念日となっている。
- 1883年(明治16年)10月24日:隕石が落下しガラス損傷[6]。
- 1889年(明治22年)4月12日:灯明変更[7][8]。
- 1901年(明治34年):日本初の自家発電の電気式灯台になる[9]。
- 1908年(明治41年)1月1日:船舶通報事務取扱開始[13]。
- 1923年(大正12年)6月30日:燭光数変更[14]。
- 1932年(昭和7年)2月11日:無線方位信号所業務開始(無線標識・無線羅針)[15]。
- 1945年(昭和20年):米軍の攻撃により破壊。運用不能になる。
- 1946年(昭和21年)
- 1947年(昭和22年)
- 1949年(昭和24年)
- 1976年(昭和51年):点灯100周年。
- 2006年(平成18年):土木学会選奨土木遺産に選出[24]。
- 2007年(平成19年)4月10日:無線方位信号所(レーマークビーコン)廃止[25]。
- 2016年(平成28年)9月:気象通報業務の廃止[26]。
- 2017年(平成29年)6月28日:国の登録有形文化財に登録[27]。
- 2018年(平成30年)6月1日:一般公開が始まり、参観灯台の一つとなる[28]。
- 2019年(平成31年)3月:ディファレンシャルGPS局を廃止[29]。
- 2022年(令和4年)12月12日:国の重要文化財に指定[30]。
付属施設
- 無線方位信号所
- ディファレンシャルGPS局(2019年廃止)
- GPS補正・テキストメッセージ方式の気象通報を実施していた。
- 船舶気象通報施設(灯台放送)
- 1670.5kHz(H3E)で龍飛埼灯台、尻屋埼灯台、松前ディファレンシャルGPS局、大間埼灯台、恵山岬灯台の気象通報業務を行っていた。
一般公開
4月下旬から11月上旬までの期間に限り一般公開され、上まで登ることができる(寄付金として、中学生以上の参観者から300円を原則徴収している)[31]。
まぼろしの灯台
第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)に米軍機の機銃掃射を受けて、当時勤務していた村尾常人標識技手が殉職した。翌1946年(昭和21年)、攻撃を受け破壊しつくされたはずの灯台が光を放ち、その目撃が相次いだ。謎の光のおかげで付近を航行中の漁船が遭難を免れたということもあった。人々は米軍の攻撃時に殉職した村尾標識技手の霊なのではないかと噂した。当時の灯台長が公文書「灯台の怪火について」を灯台局に報告した[32]。同年8月に霧信号舎屋上に仮の灯りを点灯すると同時にこの現象は消えた[33]。なお、灯台には銃撃の跡が今でも残る。
アクセス
- 旧むつバスターミナルよりデマンドタクシーで75分[34]、1日3 - 6往復、1270円(11月 - 4月は見学施設閉鎖により徒歩で約30分手前の「尻屋」まで)
- むつ市中心部より青森県道6号むつ尻屋崎線から東通村道尻屋灯台線に入る。
その他
ギャラリー
-
西側より
-
灯台と看板(2012年10月)
-
説明看板(2012年10月)
-
改修工事で発生した外壁部分で使われていたレンガの展示(2012年10月)
脚注
- ^ 灯台敷地内にあるレンガの展示(写真)にあった説明の看板による
- ^ a b 『青森県史 第7巻』青森県、1926年、pp.420-428.
- ^ 明治9年10月2日工部省布達第17号(『法令全書 明治9年』内閣官報局、pp.1343-1345.)
- ^ “法令全書. 明治10年”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “法令全書. 明治12年”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “火球状ノモノ灯台ニ衝突ノ儀ニ付灯台局ヨリ気象台ヘ質問回答. 官報. 1883年11月21日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月25日閲覧。
- ^ “逓信省告示第55号. 官報. 1889年03月15日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “逓信省告示第90号. 官報. 1889年04月18日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “尻矢崎灯台電気灯器装置. 官報. 1902年01月04日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “逓信省告示第373号. 官報. 1901年09月21日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “逓信省告示第433号. 官報. 1901年10月30日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “逓信省告示第505号. 官報. 1901年12月09日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “逓信省告示第868号. 官報. 1907年12月24日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “逓信省告示第1146号. 官報. 1923年07月05日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “逓信省告示第273/274号. 官報. 1932年02月16日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “運輸省告示第246号. 官報. 1946年09月21日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月18日閲覧。
- ^ “運輸省告示第14号. 官報. 1947年01月25日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月25日閲覧。
- ^ “水路告示第4号. 官報. 1947年02月01日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月27日閲覧。
- ^ “水路告示第8号. 官報. 1947年03月01日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月27日閲覧。
- ^ “水路告示第12号. 官報. 1947年03月29日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月27日閲覧。
- ^ “水路告示第18号. 官報. 1947年05月10日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月27日閲覧。
- ^ “水路告示第26号. 官報. 1949年07月02日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月25日閲覧。
- ^ “海上保安庁告示(航)第10号. 官報. 1949年10月08日”. dl.ndl.go.jp. 国立国会図書館. 2021年11月27日閲覧。
- ^ “土木学会 平成18年度選奨土木遺産 尻屋埼灯台”. www.jsce.or.jp. 2022年6月8日閲覧。
- ^ “無線方位信号所(レーマークビーコン)廃止計画 (PDF) ”(海上保安庁)2021年11月20日閲覧。
- ^ 海上保安庁が実施する情報提供業務の一部終了について(PDF) Archived 2016年8月17日, at the Wayback Machine. - 海上保安庁交通部 (2016年5月) ※茨城県水産試験場漁業無線局ホームページでの掲載(2016年7月12日閲覧)
- ^ 尻屋埼灯台 - 国指定文化財等データベース(文化庁)、2021年1月7日閲覧。
- ^ “青森の「尻屋崎灯台」が全国16カ所目の参観灯台に”. 海上保安新聞. (2018年6月6日) 2021年1月7日閲覧。
- ^ “ディファレンシャルGPSの廃止について” (PDF). 海上保安庁 (2017年6月30日). 2019年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月7日閲覧。
- ^ 令和4年12月12日文部科学省告示第155号。
- ^ “尻屋埼灯台(しりやさき)”. 公益社団法人燈光会. 2021年1月7日閲覧。
- ^ 尻屋埼灯台日本の近代遺産50選、2016年10月9日閲覧。
- ^ 第2管区海上保安本部、2016年10月9日閲覧。
- ^ 予約型タクシーを実証運行します東通村2023年3月8日付
関連項目
外部リンク
尻屋埼灯台
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 05:04 UTC 版)
尻屋崎には国内最大級の光度、53万カンデラを誇る尻屋埼灯台がある。 詳細は「尻屋埼灯台」を参照
※この「尻屋埼灯台」の解説は、「尻屋崎」の解説の一部です。
「尻屋埼灯台」を含む「尻屋崎」の記事については、「尻屋崎」の概要を参照ください。
固有名詞の分類
- 尻屋埼灯台のページへのリンク






