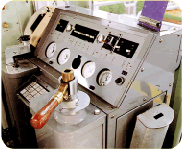500形
500形
|
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500系
(500形 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/30 06:36 UTC 版)
500系(500けい)とは、500の数値を使用するないしは3桁の数値の内上1桁目が「5」を使用する体系を持つものを指す。
鉄道車両
500系または500形と呼ばれる鉄道車両
日本
国鉄・JR
- 国鉄500形蒸気機関車
- 新幹線500系電車
- JR貨物EF500形電気機関車
- JR貨物ED500形電気機関車
- JR貨物EH500形電気機関車
- JR北海道オハテフ500形客車
- 国鉄ウ500形貨車
- 国鉄ケ500形蒸気機関車
- 国鉄タム500形貨車
- 国鉄チ500形貨車
国鉄・JR以外
- 会津鉄道AT-500形気動車
- 五日市鉄道→南武鉄道→国鉄キハ500形気動車
- 営団500形電車
- 江ノ島鎌倉観光500形電車 (1956 - 2003)
- 江ノ島電鉄500形電車 (2006 -)
- 近江鉄道500系電車
- 青梅電気鉄道→日本国有鉄道モハ500形、クハ500形電車
- 大井川鉄道スハフ500形客車
- 大分交通500形電車
- 大阪市交通局500形電車
- 大阪鉄道デニ500形電車
- 大阪窯業セメントいぶき500形電気機関車→大井川鉄道ED500形電気機関車
- 小田急500形電車
- 鹿児島市交通局500形電車
- 鹿島鉄道KR-500形気動車
- 京都市交通局500形電車
- 京急500形電車
- 京阪500型電車 (初代)(1929 - 1976)
- 京阪500形電車 (2代)(1979 - 1993)
- 京福電気鉄道デナ500形電車
- 神戸市交通局500形電車
- 札幌市交通局500形電車
- 三陸鉄道36-500形気動車
- 定山渓鉄道ED500形電気機関車
- 上信電鉄500形電車
- 湘南モノレール500形電車
- 秩父鉄道500系電車
- 秩父鉄道デキ500形電気機関車
- 秩父鉄道トキ500形貨車
- 樽見鉄道オハフ500形客車
- 筑波鉄道キハ500形気動車
- 鶴見臨港鉄道モハ500形電車
- 帝都電鉄クハ500形電車
- 東武500系電車
- 東武トク500形客車
- 東京モノレール500形電車
- 土佐電気鉄道500形電車
- 長崎電気軌道500形電車
- 名古屋市交通局500形電車
- 名古屋電気鉄道500形電車
- 南武鉄道→日本国有鉄道モハ500形電車
- 西鉄500形電車 (鉄道)
- 西鉄500形電車 (軌道)
- 函館市交通局500形電車
- 阪急500形電車 (初代)
- 阪急500形電車 (2代)
- 阪和電気鉄道→南海鉄道→日本国有鉄道クヨ500形電車
- 広島電鉄500形電車 (初代)(1938 - 1950)
- 広島電鉄500形電車 (2代)(1954 - 2003)
- 平成筑豊鉄道500形気動車
- 松浦鉄道MR-500形気動車
- 美濃電気軌道BD500形電車
- 名岐鉄道デシ500形電車
- 名鉄500系電車
- 名鉄デキ500形電気機関車
- 名鉄トム500形貨車
- 名鉄モ500形電車
- 名鉄ワム500形貨車
- 目黒蒲田電鉄モハ500形電車
- 横浜高速鉄道Y500系電車
台湾
自動車
関連項目
500形
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 14:08 UTC 版)
川崎市電初の新造車として1949年12月8日に日本鉄道自動車製の501、502号車の2両が導入されたもので、標識灯が正面上部左右に設置されている以外は都電6000形初期車とほぼ同形であった。全線廃止まで使用されている。
※この「500形」の解説は、「川崎市電」の解説の一部です。
「500形」を含む「川崎市電」の記事については、「川崎市電」の概要を参照ください。
- 500形のページへのリンク