ひまわり5号
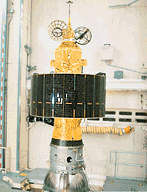
名称:静止気象衛星5号「ひまわり5号」/Geostationary Meteorological Satellite-5(GMS-5)
小分類:地球観測衛星
開発機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))/気象庁
運用機関・会社:宇宙航空研究開発機構(JAXA)/気象庁
打ち上げ年月日:1995年3月18日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:H-II
打ち上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)
国際標識番号:1995011B
ひまわり5号は、ひまわり4号を引き継ぎ、日本の気象業務の改善と、静止気象衛星に関する技術の向上を目的に打ち上げられました。ひまわり5号は、世界気象機関(WMO)が進める世界気象監視(WWW)計画では、世界の気象を観測する5個の静止気象衛星のひとつを担います。
天気予報などでおなじみの「ひまわり」の写真は、北極から南極までを赤道と並行に帯状に撮影したものを並べたものです。この帯状の写真を2,500枚並べると、静止軌道上から見た地球の写真が1枚できます。ただし、すべてを撮影するのに約25分かかるため、この写真は北極と南極で約25分の時差のある写真になります。天気予報でよく見かける日本付近の写真もこうして撮影されたもので、厳密には南北で時差がありますが、ほとんど無視してよい範囲のものです。この撮影は可視光線像と赤外線像の両方を同時に行なうことができます。
ちなみに、このひまわり5号を打ち上げたH-IIロケット3号機は、H-IIロケット1号機、H-IIロケット2号機に無かった固体ブースタを2本追加して、推力を増大したものです。しかもひまわり5号とフリーフライヤ(SFU)を同時に打ち上げ、別々の軌道に投入するというデュアルロンチの方法を成功させました。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
直径約215cm、高さ約354cm(アポジモータ分離後)の円筒形で、重量は約345kg(静止軌道上初期)です。
地球を撮影する可視赤外線走査放射計(VISSR)は、可視1バンド(距離分解能1.25km)と赤外1バンド(距離分解能5km)を持っています。また、ひまわり5号では赤外波長の分割と水蒸気バンドの検出器の追加を行なっています。
デスンアンテナ(パラボラおよびヘリカル)、オムニ(無指向性)アンテナを装備し、Sバンドテレメトリ送信帰Sバンド広帯域送信機(VISSRデータの送信および処理済みデータの配信と、測距信号の中継・コマンド信号の受信を行ないます)、Sバンド/UHF中継器(通報局データの収集や地震・津波情報の配信を行ないます)、UHF/Sバンド中継器(捜索救助実験信号の中継を行ないます。また軌道・姿勢制御運用などの宇宙航空研究開発機構(JAXA)との通信にはUSB通信系を使用します)を搭載しています。
ひまわり5号はスピン安定方式で姿勢を制御し、5年の設計寿命を持っています。
2.どんな目的に使用されるの?
可視赤外線走査放射計(VISSR)による地球の大気、地面・海面の状態を観測し、台風・低気圧の発生や動き、雲頂の高さ、雲量、上層・低層の風向風速、海面温度のデータを得るために使用されます。
そして、VISSR観測データの利用者への配信や、ブイ・船舶・離島観測所など(通報局)からの気象観測データの収集、船舶の非常用位置指示無線標識(EPIRB)が発する遭難信号を中継し、捜索救難活動に利用する実験なども目的としています。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
初期段階における運用・試験を経て、1995年6月21日から気象庁によって運用されています。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
ひまわり、ひまわり2号、ひまわり3号、ひまわり4号があります。
5.どのように地球を回るの?
高度3万6,000km、傾斜角±1度、周期約24時間、東経140度の静止衛星軌道です。
※参考文献:齋藤成文「宇宙開発秘話」三田出版会
- 静止気象衛星5号「ひまわり5号」のページへのリンク
