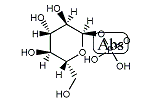グルコース‐1‐りん酸
| 分子式: | C6H13O9P |
| その他の名称: | グルコース1-りん酸、Glucose 1-phosphate、Cori ester、コリエステル、α-D-Glucopyranose 1-phosphoric acid、D-グルコース1-りん酸、α-D-グルコース1-りん酸、α-D-Glucose 1-phosphate、グルコース-1-りん酸、Glucose-1-phosphate、α-D-Glucopyranose-1-phosphoric acid、G1P、α-グルコース◇1-ホスファート、α-Glucose 1-phosphate、α-グルコース1-ホスファート、α-D-Glucopyranose 1-phosphate、α-グルコース1-りん酸、α-D-gluco-Hexopyranose-1-phosphoric acid、Phosphoric acid α-D-glucopyranosyl ester、α-D-Glucopyranose-1-phosphate |
| 体系名: | α-D-gluco-ヘキソピラノース1-りん酸、α-D-グルコピラノース1-りん酸、α-D-グルコピラノース-1-りん酸、α-D-グルコピラノース1-ホスファート、α-D-gluco-ヘキソピラノース-1-りん酸、りん酸α-D-グルコピラノシル、α-D-グルコピラノース-1-ホスファート |
G1P
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 15:52 UTC 版)
SEAMによって推し進められた G1Pは設計者のPoniatowskiの頭文字をとって命名された。SEAMは1935年の時点で最初の仕様についてすでに知っていた優位もあり、1936年12月3日にヴィンセンヌの自動車試験委員会(Commission de Vincennes)にむけた試作車両を未完成であったとはいえ実際に製造するのに十分なだけ進捗していた唯一の企業であった。予定通りのエンジンも武装も搭載していない(ターレットリングの上に大型のガラス窓がついた球形のダミー砲塔を設置)にもかかわらず20トンの重量があり、現状の仕様要求では28トン以下にさえ押さえるのは不可能だろうというARLの提言が裏付けられた。想定されていた280馬力エンジンではなくイスパノの120馬力エンジンが搭載された。理論上はより効率よく出力を発揮できるガス・エレクトリック方式を採用していたにも関わらず仮置きのエンジンそのもの馬力の低さにより12月3日から10日の試験では整地で14 km/h 、不整地では10 km/hという失望的な結果に終わった。しかもトランスミッションだけで2.4トンあり、従来の機械式トランスミッションより1.5トンの重量増大を招いた。しかしステアリングは単純で他の多くの電気式とは異なり信頼性の問題はなかった。滑らかにカーブした鋳造の傾斜装甲を多用した設計を採用していた。車体右側には主武装として75mm砲が搭載されている。乗員は車長が機関銃砲塔の操作を兼任し、運転手、砲手、通信手の4人乗りだった。全長は577 cmだった。 未完成の状態という結果を受けて委員会は最終決定を下すことはできないと判断。より車体長を延長し、より柔軟なサスペンションを装備し、防火壁を95 mm 後退させ戦闘室を広くし75mm砲の運用がしやすくした新たな試作車両を作ることをSEAMへ勧告した。 1937年6月6日にはこの計画は最高司令部である陸軍高等会議(Conseil Supérieurde la Guerre)にとって歩兵科の戦車師団(Divisions Cuirassées)が将来装備する戦車となりうると考えていた。 1937年から1938年にかけて、同社はARLと協力して再設計しサスペンションを変更、280馬力のイスパノスイザ製エンジンへと換装した。この再設計された車両は片側6つづつの転輪を装備していたことがわかる写真が残されている。1938年5月24日に委員会は砲塔を47 mm SA35戦車砲を備えたAPX 4砲塔をその無線機とともに換装し車体の主砲以外の武装も装備することを命じた。試作車両の寸法も変わり幅は2.94 m から2.92 m へ減少、車高も2.76 m から 2.73 m となった。より大型の砲塔となったことを補うため車体の高さも183 cmから147 cmとなっている。1939年初頭の段階になっても委員会はまだ約250輌を発注すべきかどうか検討していた。しかし、この間にSEAMは深刻な財政難となっていた。1938年7月に主砲の75 mm 砲を砲塔に搭載するという新たな仕様が定められたときにこの企業はもはや完全な再設計に必要な費用を捻出できない状態で、既存の試作車両もすでに重量過多であり容易には適合させられそうにはなかった。同社はARLに支援を求め兵器諮問委員会も1月19日にARLへこれに応じるよう命じ。SEAMは試作車両を引き渡しARLが大型砲塔のARL 3砲塔を搭載させることとなった。1939年9月10日に戦争が勃発するとこの開発は中断されてしまう。1939年12月22日に再開されましたが単に技術実証としてのものであった。フランスが降伏した時、車両は未完成のまま砲塔なしの状態でしかなかったが、G1計画の設計案で唯一の走行試験までこぎつけた案だった。
※この「G1P」の解説は、「G1 (戦車)」の解説の一部です。
「G1P」を含む「G1 (戦車)」の記事については、「G1 (戦車)」の概要を参照ください。
- G1Pのページへのリンク